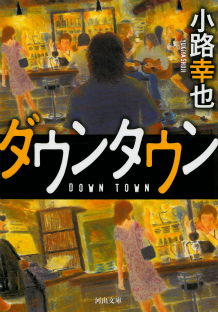花歌は、うたう
『花歌は、うたう』
小路幸也(しょうじ ゆきや)
2016.05.19

Prologue
「大きくなったねぇ。高校生? 十七歳? そうかぁ、もうそんなになるんだねぇ。そうだよ、スタジオで何回もね。僕は君を抱っこもしたんだよ。君はもうニコニコ笑ってて本当に可愛くてね。皆の人気者だったよ。いや、泣いたりはしなかったんだそれが。レコーディングだから、いくら防音ってもね、赤ん坊の泣き声が響いたりしたら困るって思ってたけど、まーったく泣かなかった。本当に人懐っこい赤ん坊だったよ。僕らが弾いたり叩いたりするのを機嫌良く見てると思ってたらいつの間にか寝ててね。天使だったなぁ」
「そうだな。うん、捨てたんだろうな。少なくとも俺はそう思ってるし世間的にもそうでしょ? でもそれはさ、いや、そんな簡単に言葉にできないな。俺たちは所詮は他人だし。でも、俺が君に言えることはただひとつ。ハルオは君のことが大好きだったよ。それは、絶対に間違いない。断言する」
「才能っていうのは、二種類あると思うんだ。私たちみたいにこうやって誰かの後ろで弾いたり叩いたりして食べていけるのも確かに才能。ハルオたちみたいにステージの真ん中に立って、そこで輝けるっていうのは、もうワンランクどころじゃなくて私たちから見ても手の届かないところに立ち続けられる才能。ハルオは、確かにそれを持ってた。そう思うからこそ、今のハルオを見たら私は怒っちゃうな。いいかげんにしろって。でもね、そういう人だからこそ、輝くものを持てたのかもしれない。そこはもう、神様の領分なんで、私にもわからない」
「怒っていいと思うよ。花歌(はなか)ちゃんはハルオの子供なんだし、自分を捨てて何をやってるんだって。でも、怒ったところであいつはどうにもならないよ。そういう男なんだ。だらしがないとか、ろくでなしとか、いろいろ言葉はあるだろうけど、そういう男なんだよ。それを全部ひっくるめて〈宮谷ハルオ〉という男なんだからさ」
「今でも思ってますよ。帰ってきてほしいって。表舞台にね。それができるミュージシャンだと信じてますし、思ってます。それは、彼のファンはもちろん、一緒にアルバムを作った、ライブをやった人間なら誰もが思ってるはずです。ステージに立って歌えば、観客は彼のことをまるで知らない若者だったとしても熱狂の渦に巻き込むことができる、希有なミュージシャンだって」
「生きてることは間違いないよ。この間は沖縄にいたって聞いたし。何をやってるのかなぁ。わかんないけど、ほら、こんだけ皆がツイッターとかやってるのにさ、そしてあいつのファンだってたくさんいるのに、まったく噂が上がってないだろ? どっかでライブやったとかさ、飲んでるのを見かけたとかさ。だから、オレが思うには、どっか人里離れたところで畑でも耕してんじゃないかって。まぁあいつにはまったく似合わないけどね」
宮谷花歌 十七歳
「トラちゃん」
むっちゃんが呼んだからトラはにゃあん、って鳴いてゆっくり歩いて、縁側の端っこを、わたしたちの前を通り過ぎて行く。
「トラちゃん」
にゃあん。
「トラちゃん」
にゃあん。
トラはもう十四歳のおばあちゃん猫で、ぜんぜん遊んでくれないしかまってくれないネコなんだけど、名前を呼ぶとゼッタイに返事してくれるからカワイイ。そして呼ばれる度にちらっとこっちを見るのもカワイイ。猫は何でもカワイイけどうちの子だからもっとカワイイ。
「三毛なのにトラ。何でトラちゃんになったんだっけ」
むっちゃんが訊いた。
「お祖母ちゃんが、トラの顔を見た瞬間に『この子の顔は虎だ』って言ったんだよ。だからトラちゃん」
トラはむっちゃんの家で保護された子猫だった。うちにいるおきゃんもオードリーも全部そう。獣医さんのむっちゃんのお祖父ちゃんが、うちのお祖母ちゃんに引き取ってくれないかって頼んで、お祖母ちゃんが顔を見て名前を決めた。
「いつもすみません、うちの祖父がお願いばかりで」
「いえいえぇ、どういたします」
むっちゃん家のお祖父ちゃんとうちのお祖母ちゃんは小さい頃からの知り合い。幼馴染みみたいなものらしい。そしてうちのお祖母ちゃんは顔が広いから、むっちゃん家が子猫や子犬を保護する度に、あちこちに声を掛けて里親を探しているんだ。
わたしは犬も好きなんだけど、犬を飼うと散歩が大変だからって猫だけにしてる。そして、家で飼うのも三匹まで。その辺は、お母さんもわたしもお祖母ちゃんの言う通りにしてるんだ。
自転車のブレーキの音がすごく大きく聞こえて、ちょっとわたしもむっちゃんも驚いて顔を上げたけど、その後に何にも音がしなかったから、そのまま作業続行。
お陽様がぽっかぽっかで気持ち良いし、何もしてなかったらゼッタイそのまま眠っちゃう。
むっちゃんが、ふぅんん、ってヘンな息を吐いた。
「ここの縁側本当にいいよね。気持ちいい。ここでずっと座ってたい。寝たい。住みたい」
お祖母ちゃんの家の、わたしん家の縁側。黒い板の塀に囲まれていて小さな庭があって、お祖母ちゃんがいつもきれいにしてる縁側。
「でも夏はここにいたら死ぬるよ」
今は六月に入ったばかりだからちょうどいいけど。
「夏は逃げるかな」
お祖母ちゃんが毎日毎日雑巾でお掃除をしている縁側。わたしも休みの日には掃除するけど、雑巾掛けってめっちゃ体力を奪うんだ。昔の人は全部これだったっていうのが信じられない。
「毎日やってるお祖母ちゃんを尊敬するよ」
「する。格好良いと思う」
むっちゃんが言った。
そう。うちのお祖母ちゃんは、カッコいい。
世の中にカッコいいお祖母ちゃんはたくさんいるんだろうし、ドラマに出てるお祖母ちゃんと同じような歳の女優さんは確かにカッコいいけど、ああいう人は、いろんな意味でカッコよくないと女優なんかできないんだし。
普通の、いっぱんピープルで、あんだけカッコいいお祖母ちゃんはなかなかいないと思うんだ。
そう言ったら、むっちゃんもまんまるの眼をさらに丸く大きくして頷いてくれた。
「思う。本当にそう思う。うたお祖母ちゃんは理想のお祖母ちゃんだよね」
「ねー。人生の最終目標はうた祖母ちゃんにしたっていいよね」
「いいと思う。こういうきれいな小さな一軒家で、老後も静かに悠々自適の生活って憧れる」
ゆうゆうじてき。
「って、どういう意味だっけ」
「ググってください」
「教えてん」
「のんびりと、自分の思うままに、静かに残りの人生を過ごすことを〈悠々自適の生活〉って言うのよ」
「なるほど」
本読みのむっちゃんは本当にいろんな言葉を知ってる。
「花歌が知らなさ過ぎなんだよ」
「知ってるよゆうゆうじてきぐらい。正確にはどんな意味だったかなって思って訊いただけ。あー、風がぱしゃぱしゃ叩く」
「ヘンな言葉を使うしね」
「ヘンな言葉なんか使ってないじゃん」
「風は、ぱしゃぱしゃ顔を叩いたりしないの。ぱしゃぱしゃは、たとえば水面を叩いたりしたときにする音なの」
そうか。さっきからずっと風が髪の毛を揺らしてぱしゃぱしゃ叩いていると思ってるんだけどな。ダメか。
「あたしのことを噂してたかい。名前を呼んだだろ」
音もなくお祖母ちゃんは背後から現れる。本当にお祖母ちゃんはいつもいつも音を立てずに歩き回るんだ。あの摺り足っていうのをいつか会得したい。会得? 会得でいいんだよね。
「噂じゃないよ。褒めてたんだよ」
「褒めるのも噂のひとつだよ。ほら、おやつだよ。ひと休みしてお食べ」
「わーい。ありがと」
「ありがとうございます!」
お祖母ちゃんの作った林檎ジャムと、お祖母ちゃんが焼いたスコーン。これがまたホントに美味しいんだ。林檎ジャムは毎日食べてるけどわたしはまったく飽きる気がしない。
「どれ、見せてごらん。どれだけできた」
お祖母ちゃんが、わたしとむっちゃんが縁側に座ってひたすら縫っていた鍋つかみとティーコゼーを手にして、見た。
「あら、上手く縫えてるじゃないか。こっちの鍋つかみは睦美(むつみ)ちゃんかい」
むっちゃんがスコーンを食べて口をムグムグさせながら慌てたように頷いた。
「ほうです! わたひです!」
「わたひだって」
ちゃんと飲み込んでから喋りなさい。
「大したもんだね。それに比べて花歌、お前のティーコゼーはひどいね」
「ひどくないよ。縫えてるよ」
お祖母ちゃんがじろりとわたしを見た。
「何度も教えたのにね。お前は手先は器用なはずだから、集中力の問題かね」
そうなのかな。
「まぁいいさ。こういうもんは上手い下手じゃなくて心だからね。鍋つかみはしっかり縫えてないと心許(こころもと)ないけど、ティーコゼーはただ被せとくだけのものだから、多少不細工でもいいだろうさ」
「良くはないけどさ。心は込めてるよ」
わたしとむっちゃんの大事な友達の、えっちゃんへの誕生日プレゼント。むっちゃんと二人で手作りのものを贈るって決めて縫い物にしたんだ。お祖母ちゃんはもう一度じっくり見て言った。
「もう一頑張りすりゃあ、今日中に完成するだろう。むっちゃんは家で晩ご飯食べていったらどうだい。遅くなったら泊まりゃあいい」
「いいんですか? いつも悪いです」
「若いもんが遠慮するものじゃないよ。今日は私が晩ご飯を全部作るから、お前はそれを一生懸命縫ってなさい。花子にもメールしておきなさい。むっちゃんが泊まるって」
「おいっす!」
お祖母ちゃんが、ぽん、とわたしの頭を叩きながら、すいっ、って立ち上がった。
「お返事は『はい』と、きちんとする。お嫁の貰い手がなくなるよ」
そして音を立てずに歩いていく。いつも思うけどどうやったら着物であんなにキレイに立ち上がれるのか不思議。
「じゃ、ワタシもママンにLINEしとくね」
「おっす。うちの母もLINEにしてくれればラクなのになー」
「メールでもそんなに手間はかかんないじゃん」
「LINEの方がラクだーよ」
お母さんにメール。でも、仕事中だから返事は返ってこない。仕事が終ってからチェックして、返事をしてくる。まぁだからLINEやっててもメールでも同じでどっちでもいいんだけどさ。
どうやったらラクになるかを考えるのはいい。でも、どうやったらラクできるかを考えるのはよくない。お祖母ちゃんの口癖だ。
人間は手間暇をかけることをきちんと覚えてからじゃないと、ラクできることを考えちゃいけないって。
「よしっ、晩ご飯までガンバルか」
「うん」
むっちゃんも頷いて、鍋つかみを取った。針を持つ。集中する。わたしは集中さえすれば大抵のことはできる子だって、お母さんもお祖母ちゃんも言ってる。上手くできるかどうかはともかくも、最後までやり通せるって。
集中。
お料理大好きなえっちゃんが、これを使って美味しい料理を作ったりお茶を淹れられるように。わたしたちに食べさせたり飲ませたりしてくれるように。いや、人を当てにしないで料理は自分で作れってか。でもお茶ぐらいは淹れてくれたら嬉しいなってね。
集中。
むっちゃんが、笑うのが聞こえた。
「なに笑ってんの」
「ヘンな歌を作らないで。歌わないで」
「歌ってた?」
むっちゃんが笑いながら三回頷いた。
「いつもながらすっごく良い曲だと思うんだけどね。変な歌詞はやめてほしい。笑いが止まらない」
「そうか。でもウケるってのはいいことだよ」
わたしのクセだ。
集中すると、鼻歌を歌ってる。テストの真っ最中でも歌って怒られたことが何度もある。自分でもわかんないんだ。言われたら確かに歌ってたって思うけど、言われるまでわかんない。
しかもオリジナルらしい。どっかの誰かの歌じゃなくて、聞いたこともない曲ばっかし。それも自分ではわからない。
「それ、前にも訊いたけど思い出せないの? ホントにいっつも良い曲なんだけどなぁ」
「さっぱり全然まるっきり」
思い出せない。ときどき歌詞もついているらしいけど、その歌詞もわからない。
「今はね、〈ちょっと待ってあなたはまわってたもーれわたしはあまくてアモーレ〉って歌ってたよ」
「何だそりゃ」
二人で笑っちゃった。笑うと針を指に刺しちゃうからダメだ。むっちゃんが、あーあ、とか言いながらまた縫い物に集中しようとしてから、ちょっと手を止めた。
「あのね、花歌」
「うん」
「気を悪くしたらゴメンなんだけどね」
「なになに」
「花歌って、音楽の才能があると思う」
「そう?」
むっちゃんは、吹奏楽部だ。
中学に入ったときからずっとアルトサックスを吹いてるからもう五年も吹いてて、すっごく上手。獣医さんのお父さんも、そしてお母さんも音楽がすごい好きで、特にジャズなんか昔のLPが棚一面にあって、遊びに行く度にすごい数だなぁって思うんだ。
だから、むっちゃんは音楽にむちゃくちゃ詳しい。街を歩いていてどっかから流れてきた曲を立ち止まって聴いてるからどうした? って訊いたら「このピアノの人好きなんだ」とか言っちゃう。どうやったらあの音の洪水みたいな音楽の中からピアノの音だけを聞き分けられるっていうのか。
「でも楽器なんか全然弾けないよ」
「ギター上手いでしょ」
「ギターはね」
それだけは、得意だ。亡き父の遺産と自分で言ってる。や、お父さんはまだ死んでないけど。
死んでないと思うけど。
「花歌の鼻歌はさ、スゴイと思う。本当にきれいな良いメロディなの。そして全然聴いたことのないメロディばかり。もう一度聴かせてって言ってもいっつも花歌は覚えてないって」
「だって覚えてないんだもん」
本当だもん。
「で、それが何で気を悪くするの。褒められたのに」
「あのね」
「うん」
「覚えるように、作ってみない?」
むっちゃんが、真面目な顔をしてる。これはマジな顔だ。ふざけたらパン! って頭を叩かれる顔だ。
「覚えるようにって?」
「作曲をするの」
「誰が」
「花歌が」
作曲。
「歌を作るの?」
「そう。花歌が作曲して、花歌が作詞して、歌を作るの。そして、それを歌うの」
歌う。わたしが。
考えたこともない。
「歌って、どうするの?」
歌うのは別にいいけど。そして作曲なんかしたことないけど、できるもんならやってみてもいいけど。
むっちゃんの眉間にシワが寄った。
「たとえばよ?」
「うん」
「作曲して、作詞して、歌になるでしょう」
「なるね」
「それを練習して録音とか録画したら、ユーチューブとかで流せるよね」
「なるほど」
それは、できるね。やってる人いるみたいだし。ユーチューバーになりたいとか言ってる子もいるし。
「もしそれが、みんなに、たくさんの人に聴かれるような歌になったら、お父さんに届くと思わない?」
お父さんに。
「ワタシは、花歌にはそういう才能があると思う。確信してるんだけどな」
かくしんって。
どういう意味だっけ。
「才能があるの? ゼッタイに?」
「ゼッタイに。その前に」
「なに?」
「気を悪くしてない? お父さんに届くかもしれないなんて言って」
「全然?」
そんなことはまったく思わない。
むっちゃんがもうずっと長い間わたしのお父さんの話をしないようにしてるのはわかっていたから、わたしもしないようにはしていたけど。それが習慣になっていたけど、したって全然かまわない。
九年間も行方不明のお父さん。
宮谷春男。芸名は宮谷ハルオ。
皆に〈ハルオ〉って呼ばれる人。
ミュージシャン。
わたしとお母さんを放って、どっかへ行方をくらませてしまった人。
「そもそもさ、いなくなる前からお父さんは全然まるっきり家にいない人だったんだよ。ツアーだアルバムの録音だ何だかんだってさ。わたし、学校から帰ってきてお父さんが家にいたらびっくりしてたんだからね。どうして今日はいるの! って」
「そうだよね」
「そうだよ」
お母さんと結婚したときにはまだ売れないミュージシャンで住むところもないみたいな感じで、このお祖母ちゃんの家にマスオさん状態だったお父さん。だから、ここはお父さんとお母さんとわたしの家じゃなくて、最初からお祖母ちゃんの家。
ここでわたしは育った。
京王神泉駅の脇の坂道をちょっと上ってすぐの、古い平屋の日本家屋。神泉町のお祖母ちゃんの家がわたしの家。
滅多に家にいなかったお父さんがいなくなったって聞かされても、九歳だったわたしはまるっきりピンと来なくて。
「いないのが、普通なんじゃないのって思ったよ。それがお父さんってもんじゃないのかって」
大変だったんだなって理解したのは中学生になってからだ。
お父さんが、人気のミュージシャンだった〈宮谷ハルオ〉がツアーの途中で失踪したってことがどれだけ大きなニュースだったのかって。
でも、そもそも、いや失踪っていうのも大変なことなんだけど、その前からお父さんは大変なことをやらかしてしまっていた人だったんだから。
「だから、そのことに関してはまったく気にしなくていいから」
「少しは気にした方がいいとは思うんだけど」
うん。まぁたまには考えてる。お父さんは今頃どこでどうしているのかって。でも、妻であるお母さんが何にも言わないしね。
「わたしが歌をうたうのかー」
「いや、そうしなさいって言うんじゃなくて。花歌がその気になるんだったらって話しなんだけど」
「うん」
でもその前に。
「縫おう」
「そうだね」
歌よりも今は縫い物だ。えっちゃんへのプレゼントだ。うん。
お父さんか。
ハルオさんか。
むっちゃんやえっちゃんが気にしているほど、わたしはお父さんのことを気にしていない。ずっと家にいなくてそのままいなくなっちゃった人。どうして気にしていないかって言うと。
お母さんは結婚前から区役所の職員として働いていた人で、つまり公務員。結婚してもずっと働いてお給料を貰ってわたしを育ててくれていたから、お父さんがいなくなっても生活には全然困らなくて。
そうなんだ。わたしもお母さんもお父さんがいなくなったって全然困っていなかった。お母さんはいろいろあったんだろうけど、わたしの毎日は学校に行ってみんなと楽しく過ごして、欲しいモノを買ってもらえたし、お祖母ちゃんのこの家でなに不自由なく生活できた。
だから、わたしたちを捨てたと思われるお父さんのことを別に恨んでもいない。っていうか恨む必要もなかった。
困ってないんだもん。
岩崎うた 六十七歳
聞こうとしなくても、若い女の子たちの張りのある高い声の会話は聞こえてくる。この狭い小さな家ならなおさらのこと。特に縁側の辺りはどうしてなのか、音が反響するからね。
会話が台所にまで聞こえてしまう。風が縁側から入り込んでこっちに流れてくるせいもあるんだろう。
口元に、笑みが知らずに浮かぶ。苦笑いだね。
あの子の父親も、ハルオもそう言って、ここは声が響くなどと、縁側でよくギターをつま弾いて歌を聴かせていた。
まだ赤ん坊のあの子に。花歌に。
「血だね」
血は争えない。
今、睦美ちゃんが言っていたことは、あたしも常々思っていたことだよ。
花歌の鼻歌はおもしろいって。
花歌とは、よく名付けたものだよ。感心する。単純にあたしの名前と花子の名前をくっつけただけじゃない。そうしたんだってハルオは言っていたけど、こうやって大きくなった花歌の歌を聴くと、ハルオはわかっていたんじゃないかと思うぐらいさ。
あの子の歌には、声には、華がある。
ただの鼻歌を聴いただけでそう思えるんだから、真剣に歌いたいと思ってそうしたら、どれほどのものになるか。
いつか周りの誰かが言い出すか、自分で気づくかと思っていたけれども、睦美ちゃんが言い出したかい。あの子も吹奏楽でサックスを吹いているし、何よりお父さんの幸一くんは、生粋のジャズファンだからね。そういう素養を多く持ってる。
類は友を呼ぶ。
不思議とそういうものなのさ。
「歌をうたう、かね」
それならそれでいい。自由にするといい。それで本当にあのろくでなしのところに届いたのなら、驚きだ。奴が改心でもしたのなら多少は溜飲が下がるってものだね。
それで帰ってきたとしても、この家の敷居は跨がせないけれどね。
「花歌」
「はーい?」
「ちょっと買い物に行ってくるからね。留守番頼むよ」
はーい、と、ユニゾンで、屈託のない明るい声が響く。
私は買い物袋をひとつ持ち、下駄箱から履き慣れた草履を三和土に置いて、突っかけるようにして履いて外に出る。
六月頭は梅雨の入り前。陽射しは柔らかくて強くもなく、まるで春先のような心地よさ。こういう日が続いてくれれば、どんなにか東京も過ごしやすい街になるかと思うんだけどね。
駅の北口にあるスーパーまでのんびりと歩く。買い置きってのがどうも性に合わなくてね。その日食べるものをその日に買う。冷蔵庫は一杯にしない。その方がなにかと気楽でいい。
坂道しかないようなこの辺りに住むご老体たちは、さぞや足腰が強くなっていると思うけれどもどうなんだろうね。坂道を歩く程度じゃあ健康にいいとは言えないかい。
今はまだいいとしても、この先七十代八十代になると、歩き回るのも辛くはなってくるもんだろうか。そうなると、花子や花歌に世話を頼むような日々がやってくるものか。
「やれやれ」
そんなことを考えるようになったこと自体が、歳を取ったってことなのか。あと三年もしたら七十。
「古稀だってさ」
七十年生きる人は古くから稀であるから古稀ってねぇ。そりゃあもう大昔の話だろう。今じゃ七十生きるのは当たり前なんだから言い方を変えたらどうだいって思うよ。
その昔は、木造のちんけな旅館に囲まれた鼻の穴みたいなトンネルとホームしかなかった駅の脇を通り抜けて、スーパーへ向かう。もうどこに昔は八百屋があって、肉屋があったかも忘れちまったね。お米屋さんは昔っからあそこにあるけれど、いつも配達だから買いに行くことはないしねぇ。
スーパーは味気ないなんて思ったことはないね。何でもひとつどころで賄えるし便利この上ない。
「あら、うたさん」
「おや」
こういうもんだね。薄桃色の上着を着て、財布ひとつ持った頼子さんにバッタリ会う。睦美ちゃんのお母さん。
「すみません、また睦美が泊まってくるとかLINEが来て」
「いつものことだよ。気にしないでおくれ」
子供同士が仲良くして毎日過ごしてくれるのは、親にとってはありがたいもんさ。それを邪魔する必要なんかまるでない。
頼子さんが、ふいになにかを思いついたように頭を動かした。
「うたさん、お買い物急いでます?」
「いいや? あんたこそ急いでいるんじゃないかい? 白衣のままで」
「私は大丈夫なんですけど」
そこで、ちょっと声を潜めた。
「ちょっと、お茶しませんか。隣で」
「いいよ」
なにか話があるんだろう。また進の奴が年甲斐もなくホステスにでも入れ込んだかね。スーパーの隣にある〈喫茶サンスーン〉もこれまたあたしみたいに古い店。ここで四十年ぐらいになるんじゃないかね。
からん、と、鐘がなる古いペンキの剥げた扉を開けて、中に入る。煙草の匂いとコーヒーの香りが入り交じった古臭い店の香り。店主の増岡が何にも言わないでただにこりと笑う。
「いらっしゃいぐらい言ったってバチは当たらないよ」
「いらっしゃい」
頼子さんと二人で笑う。窓際のテーブルが空いているので、そこに座る。開店の頃からまるで変わっていない褐色の椅子とテーブルが、小さい軋む音を立てる。
「コーヒーね」
「二つください」
頼子さんが、小さく頷く。
「どうぞ、一服してください」
「ついでに一本くださいって言うんだろう」
えへへ、と、笑う。
この人は四十を越えても少女のような愛らしさを失わない人だね。動物好きに悪い人はいないって言うけれど、そんなはずはないんだけど、頼子さんを見ているとそう思えてくるよ。喫煙癖は、自分のことはさておいて止めた方がいいと思うけどね。犬猫はこの匂いを嫌がるだろうに。
煙草に火を点ける。ふぅ、と、煙を吐く。
娘と孫にいい顔をされないので自分の部屋でも極力控えてはいるけれども、止める気はさらさらない。ここまで来れば寿命が多少縮んだところでどうってことないのさ。そもそも長生きする気もさらさらなかった人生だ。
「それで? また進がおいたでもしたのかい」
「いいえ」
頼子さんが首を横に振る。
「そうじゃなくて」
ちらりと店内を見回した。他に客は奥のテーブルに一組しかいない。狭い店内とは言っても、普通に話せば会話が聞こえる距離じゃあない。
「ハルオさんのことなんです」
「ハルオ?」
あらまぁ。今日はそういう日なのかね。その名前を一切聞かない日が何年も続くと思えば、今日は二度目だよ。
「ハルオがどうしたい」
「旦那の知り合いが博多でジャズ喫茶をやっているんです。〈犬狼都市〉っていう名前なんですけど」
「澁澤龍彦(しぶさわたつひこ)かね」
「何ですか?」
知らないよね。
「〈犬狼都市〉って名前さ。そういう本がある」
そうなんですか、って続ける。どうでもいいことだよね。
「さしずめ、そこのマスターが、ハルオを目撃したってかい」
「そういうことなんです。一昨日の話ですよ。その人はハルオさんのアルバムも全部持ってるファンだそうで、見間違えではないと」
生きてるかい。
「前の目撃情報は一年ぐらい前だったから、これでまた確かめられたね」
頼子さんが、苦笑いして煙草を吹かした。増岡がコーヒーを持ってきたので、話を止めて、一口飲む。旨くも不味くもないコーヒーだけど、ちょうどいい味だよね。
「それで? その他には? 一人だったとか女連れだったとかの話はないのかい」
「一人だったそうです。服装もごく普通で、汚れているとか悲惨だったとかでもなく、ごく普通の中年男。髪が長いので普通の職業ではないなとは思うだろうけど、態度もこれといって特徴もなく普通で」
「つまらない男になってるのかね」
言い換えれば、オーラも何もないってことだ。まぁいいさ。
「花子には聞かせないでおくれね」
「わかってます。それで、うちの人は、もしあれだったら、また店に来るようだったら、何とかして居場所を摑むように、その店の人に頼むからって言ってましたけど、どうします?」
居場所か。そうだね。
「無理する必要はないけれども、気にかけておいてくれると助かると言っておいてくれないかい」
捜す必要はない。そんな気もない。
ただ、花歌の父親であることは間違いないからね。
あの子が幸せな人生を歩もうとするときに、もしも父親の存在が必要であるならば、そんなときが来るのであれば、生きているか死んでいるかぐらいは知っておいた方がいいのは確かだね。
(つづく)