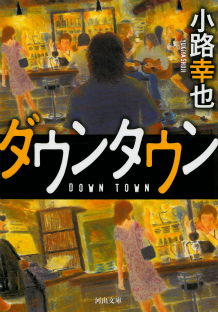花歌は、うたう
『花歌は、うたう』 最終話
小路幸也(しょうじ ゆきや)
2017.04.17

宮谷ハルオ 四十五歳
大きな画面で観たかった。
音は、まぁスマホもパソコンも大差ないだろうけど、YouTubeを、大きな画面で、ハッキリと花歌の歌う姿を観たかった。
歌を、聴きたかった。
けれども、この街で知り合いは誰もいない。この家にはパソコンもiPadもない。どうするか悩んで、結局〈犬狼都市〉に来てしまった。
ロウさんに頼み込んだ。
パソコンでも、タブレットでもいいから、YouTubeを観られるものを貸してくれないかって。
ロウさんは、少し首を傾げた。
「音楽をやりたくなった?」
そう言って、ニヤリと笑った。
「いや、そうじゃないんだ」
この間、恭一と話すためにこの店を貸してもらってから、何度か来ている。最初は迷惑を掛けたお礼のつもりだったが、ロウさんとは音楽の趣味が合った。いや、初めて店に入ったときからそう感じていたし、だからあいつを連れて何度か来ていたんだが。
どうして、この街にいるのかも、ある程度は話した。
ある程度ってのは、曲を書けなくなって失踪して今は女の厄介になっているっていう、お決まりのパターンみたいな話だけってこと。全部真実だしな。
それも、そういう話もしたのも、ロウさんがかつては同じ釜の飯を食った仲間だったってわかったからだ。いや、その表現はおかしいか。
ロウさんも若い頃はミュージシャンだった。そして、俺のアルバムを出してくれた会社で、ディレクターをやっていた人だった。もうとうの昔に退職して、故郷の街でこういう店をやっている。そういう人だった。
ロウさんは、いい人だ。きっと昔は有能なディレクターで自分が手掛けてヒットしたアルバムも何枚もあるんだろうけど、そういう話は一切しない。
ただの音楽好きのじいさんとして生きている。
「娘が、歌うんだよ」
「娘?」
ロウさんの眼が細くなった。
「娘さんがいたのかい」
それは、恭一は話さなかったのか。
「もう高校生なんだ。名前は花歌」
「その子が、歌うの?」
そうらしい。
「仲間が、あの子のサイトを作ってくれている。そこで、公開するらしいんだ。この間、恭一が教えてくれた」
花歌の歌を。
ロウさんが、頷いた。
「私も一緒に聴いてもいいかな?」
「もちろん」
歌は、誰かがうたった瞬間に、聴いているすべての人のものだ。誰のものでもない。作った本人のものですらない。
その歌を聴いて、何かを感じたその人のものなんだ。
「向こうにあるよ」
奥にある倉庫だ。ライブのための道具を置いてあって、ソファも机もある。金のないミュージシャンのための仮眠室にもなっている。
俺は、ドサ廻りはしたことないんだ。小さなライブハウスで歌ったことはあるけれど、全部東京だった。全国を廻るときにはもうメジャーデビューしていて、そこそこ大きなライブハウスでちゃんとホテルも取ってもらってスタッフがいて、っていうパターン。だから、こういうところに寝泊まりする苦労なんかまるで知らない。
まぁ今がいちばん苦労してるっちゃあ、してるか。
「今は、いいよね」
iMacを立ち上げながらロウさんが言った。
「YouTubeで流せる。才能があれば、そこから一気に広がる」
「そうだね」
「私たちの時代じゃ考えられなかった」
俺の若い頃もそうだ。まだインターネットはなかった。いや、ギリギリあるにはあったけど、誰もが動画を観られるなんていう環境はなかった。
それに、俺が失踪したこのたった八年間でも随分変わった。本当に、こういうものは日進月歩だ。
「〈花歌〉で検索してみてくれないかな」
「了解」
いろいろ出てきたけど、すぐに、わかった。
「あぁ、これだよ」
ロウさんがクリックする。花歌のサイトが出てきた。iPhoneでも観ていたけれど。
「いいね」
ロウさんがすぐに言った。
「きれいな、そしてカッコいいサイトじゃないか。ひょっとしてあの恭一くんが作ったのかい?」
「いや、たぶん凌一だ」
「凌一?」
「恭一の弟なんだ。そして、花歌の同級生なんだよ。デザインで恭一が協力してるかもしれないけど」
俺の知ってる凌一はまだほんの子供だった。そもそも花歌にだって、八年間も会っていない。まだ十歳ぐらいの頃の、小学生の可愛い花歌しか俺は知らない。
その子供たちが、こうやって自分で世界中の人間へ向けて、音楽を発信できる。その知識も技術も持っている。
サイトのトップページには、女の子がいた。
知っているのに、知らない女の子。
花歌だ。
美人とは言えないが、愛嬌のある、そして、独特の雰囲気のある少女が、女の子が、いや、女性がそこにいた。
「これが、花歌ちゃん。娘さんかい」
「そうだよ」
ロウさんが、小さく頷いた。
「いい雰囲気を持ってる」
動画が何本もアップされていた。〈ごあいさつ〉というタイトルのついた動画をクリックする。
そこに、花歌がいた。隣にサックスを持った女の子。
「むっちゃんか!」
思わず声が出た。花歌の幼馴染み。そして、花歌の後ろの連中は。
「なんてこったい」
皆が、いた。
「ひょっとして、ハルオくんの仲間かい? 見た顔もいるね」
ロウさんが言うので、頷いた。
「そうです」
ページ、ケンタ、マイカ、慎二、ルーリー。
胸の奥から、何かが湧き上がってくる。込み上げてくる。忘れようとは思っていなかったけれど、感じようとも思っていなかったものが。
その動画は、本当に挨拶だけで終わった。拍子抜けするぐらいに、あっさりと。
「〈ハルオ〉の娘だと、最初に挨拶したわけだ」
「そうですね」
ロウさんが、感心したように首を少し横に振った。
「すごいね。若いんだから、今のネットがどういうものかよくわかってるはずなのに、あえて自分は〈ハルオの娘〉だと宣言したんだ」
驚いた。本当に驚いた。
そんなことを言えば、親の七光りなんていうのが付いてまわる。つまらないものをうたえば、余計に批判される。
そんなことは全部わかっていて、やったわけだ。
「これは、気合い入れて聴かなきゃならないな」
ロウさんが言って、次の動画をクリックした。
さっきの場面から始まった。これは、〈アリス〉のスタジオだ。俺も、いや俺だけじゃなくたくさんのミュージシャンが使うスタジオ。最高の環境が整っていて、リハーサルもできるスタジオ。
金が掛かることを、高校生のガキのために、これだけのメンバーが集まっている。
それだけで、花歌は、俺の娘は、特別だと言うことが伝わってくる。
〈そこへ届くのは僕たちの声〉
タイトルの字幕が流れる。ページのカウントでマイカのピアノと慎二のギターが弾ける。
花歌の声が、響く。
明日の橋なんかそこに架からないってことをわかってる
でもそこに向かって走って走って走って踏み切る
甘くない。
声が、女の子の甘い声じゃない。
少しフラットする、少しかすれる、伸びやかに伸びて、シャウトするように声が飛ぶ。
ボーカリストだ。
アマチュアミュージシャンじゃない。
凄いボーカリストだ。この子にこの曲をうたわせてみたいと誰もが思うほどの、個性も実力もあるボーカリスト。
どうして、こんな歌声を身に付けたんだ。
俺の、花歌が。
ギターを抱えた花歌の身体からリズムが弾け飛んでいる。
佇まいが、堂に入っている。
バックを、従えている。
自分が王様に、いや、女王になっている。
目を瞠ってしまった。
なんだこのサックスは。
むっちゃんは、睦美ちゃんは、こんなにも素晴らしいミュージシャンだったのか。ミュージシャンになっていたのか。
花歌とむっちゃんが、絡む。
音が、入っている。二人の間の動きに何の歪みもない。その笑顔が、腕の振りが、身体の動きと絡みと音が完璧に一体化している。
まるで、何年も何年も一緒にやってきたミュージシャン同士だ。
いや、そうなのか。この二人は生まれたときからずっと一緒だったんだ。毎日毎日二人で遊んで笑って楽しんできたんだ。きっと、悲しいことも淋しさも何もかも二人で分けあってきた。
そういう二人が、音楽で繋がっている。
動画が終わっても、動けなかった。ロウさんもしばらく何も言わなかった。
「ハルオくん」
「はい」
「私たちは、いや、この動画を見た人は」
ロウさんがディスプレイを指差した。この動画を上げたのは昨日のはず。ただのアマチュアの高校生の女の子の動画だ。どこにも何にも宣伝なんかしていないはず。せいぜいが友達にメールやLINEで回したぐらいだろう。
それなのに、もう一万回ものアクセスが、再生回数が付いている。
「凄いミュージシャンを見つけたと、思ってるよ」
ロウさんが言う。
「〈ハルオ〉は、どう思う?」
父親じゃなく、〈ハルオ〉はどう思う? と、ロウさんは訊いた。
そんなの、決まってる。
決まってるじゃないか。
「スゲェ! って笑ってます」
笑ってるんだ。
俺。
ロウさんの前じゃなかったら、スゲェスゲェって手を叩いて足を踏みならして大声で叫んでいる。
凄い奴が出てきたって。
ロウさんは、大きく頷いた。
「ハルオくん」
「はい」
少し首を傾げてから、ロウさんは微笑んだ。
「今まで何も言わなかったのは、同じ男として、そしてミュージシャンというものを理解する男としての武士の情けだったんだ」
頷いた。
「だけど、今度は人生の先輩としてお節介を言わせてもらう」
「何でしょう」
「東京に戻るなら、後のことは任せてもらってもいいよ。今厄介になっている人たちのことを、見守るよ。私が」
それは。
「迷惑を掛けるだなんて言葉は、いちばん似合わないよ。君には」
「似合いませんか」
うん、と、笑った。
「音楽が、全てだよ。君の音楽が、愛憎も、過去も、我儘も、未来も全部だ」
宮谷花子 四十二歳
花歌の歌が、終わった。まだ動画は三本あるけれど、お母さんが何か感じ入ってるみたいだから、しばらく待った。
「似てないね。お父さんに」
そう言ったら、お母さんが唇を歪めた。
「そりゃあそうだろう。別々の人間なんだし、男と女の違いもある」
「そうね」
私は、ミュージシャンの妻ではあるし、あの人の影響もあって普通の人よりかはいろんな音楽を聴いてきたけれども、才能があるわけじゃない。
音楽を聴くのも、ちゃんと聴けるのも、才能のひとつなんだと思うけど、そういう意味であんまりよくわからない。
それでも、花歌の歌がいい歌だって思った。
「どう? お母さん」
「いいんじゃないかね」
「いいわよね」
「たぶん、玄人受けするような音楽なんじゃないのかね。若い、花歌と同じような年頃の普通の子たちよりは、もう少し年齢が上だったり、音楽がわかっている人たちにウケるような」
そうかもしれないなって思った。
「むっちゃんも凄いわぁ」
「あの子は凄いね。花歌よりもずっと目を引いていたよ」
「そもそもむっちゃん、花歌よりもスタイルいいし」
「顔立ちも派手だしね。ステージ向きなんだよ」
サックスもたぶんすごく上手なんだと思う。
お母さんが、溜息をついた。
「さ、覚悟を決めなきゃね」
「何を?」
「あんたは自分の娘が、あたしは孫が有名になる覚悟だよ」
身内びいきじゃなくて、本当にそう思う。もうとんでもない数の再生回数になっている。
「それと、あいつが帰ってくるのもね。覚悟しておきなさい」
あいつ。
あの人。
「帰ってくるかしら」
お母さんが、大きく頷いた。
「来るね。これを見て帰ってこなかったら、もしくはミュージシャンとして復帰しなかったら、本気であいつはもう駄目さ。腐っているんだろうけど、そんなことはないね」
きっとこれを観て、腰を抜かしてるさってお母さんは言う。
「本気で嫉妬するはずだよ。何たって、自分の娘なんだよ。自分の血を引く子供がこんな凄い音楽をやっていたら、黙っていられるはずがない」
確信しているように、お母さんは頷いた。
岩崎うた 六十七歳
予想を超えていたね。
花歌の歌はきっと心に届く歌になるはずだっていうのは思っていたけれども、こんなにもちゃんとした、ちゃんとしたっていうのは変だね。
はっきり、ミュージシャンだって思えるとは、想像していなかった。
うたっている花歌は、いつもこの家でにこにこしているあたしの孫の花歌じゃなかった。
アーティストってやつだね。
そういう、立ち姿をしていた。
何でもそうだよ。どんな仕事でも、そうさ。ちゃんとした仕事をする人間ってのは、その佇まいがちゃんとしているんだ。
だから、仕事ができるやつってのは見栄えが良くなるのさ。美醜じゃなくて、本質の部分でだよ。
うたっている花歌は、格好良いよ。
素直にそう思えた。
あいつもそうさ。〈ハルオ〉も格好良かったんだよ。
「お母さん」
花子が、ちょっとだけ背筋を伸ばしながら言った。
「何だい」
「あの人が帰ってきたら、どうしようか。黙って無視しようか」
「無視じゃおもしろくないだろう。どうせやるなら、何事もなかったかのように『あら、お帰りなさい』って言ってやりゃいいんじゃないかい」
宮谷花歌 十七歳
花歌です。えーと、宮谷花歌です。
こんにちは。今は、日曜日の午後四時です。
隣にいるのは、サックスのむっちゃんです。
わたしの、幼馴染みなんです。わたしの作る歌のアレンジはほとんどむっちゃんがやってくれてます。スゴイんです。わたしは、ただ作って歌うだけで、でも、むっちゃんはスゴイんです。大事なことなので二回言いました。
わたしたちは、二人で歌います。
あ、むっちゃんはサックスですけどコーラスもします。二人で一人だけど、〈花歌〉ってわたしの名前で、活動します。
そして、これから紹介する人たちもスゴイ人たちばかりなんです。
わたしの後ろ、ドラムはページさんです。
ベースは中村ケンタさんです。
キーボードはマイカさんです。
ギターは鳥海慎二さんです。
もう一人のギターはルーリーさんです。
もう、わかってしまった人もいちゃいますよね。
このスゴイミュージシャンの人たちは、みんな〈ハルオ〉と一緒にステージをやってきた人たちです。
一流のスタジオミュージシャンの人たちです。
そして〈ハルオ〉は、ミュージシャンの宮谷ハルオは、わたしのお父さんです。
そうなんです。
わたしは、〈ハルオ〉の娘の〈花歌〉です。
歌をうたおうと決めて、歌を作り始めて、そして、こんなにたくさんの人がわたしの歌のために集まってくれました。
びっくりしました。
〈歌〉って、スゴイなって、今、思ってます。
知っている人もいると思いますけど、お父さんの〈ハルオ〉は今はうたっていません。一緒に暮らしてもいません。
わたしの歌は、全部わたしが一人で作っています。
そして、わたしの歌が誰かに届いたら、うれしいなって、思います。
(了)