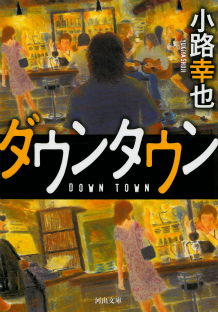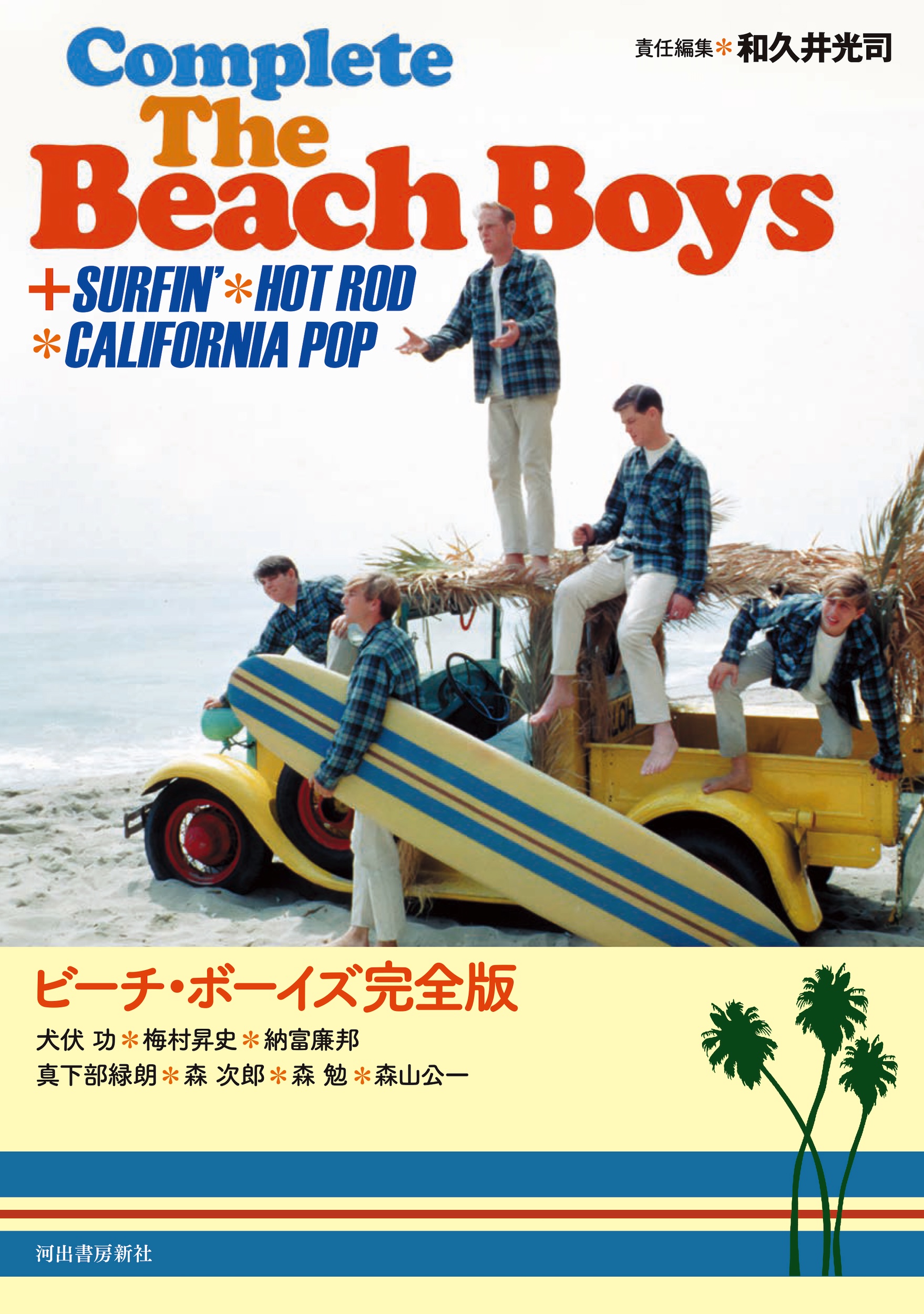花歌は、うたう
『花歌は、うたう』 11
小路幸也(しょうじ ゆきや)
2017.03.16

岩崎うた 六十七歳
「そうかい」
〈廉清〉で、また若い男と二人きりの内緒の夕食。
恭一くんから、戻ったと連絡があった。そして、あいつを、ハルオを見つけたとのこと。すぐにでも報告をしたいのだけれども、捜している間に仕事が詰まっていてそれをまずは片づけなければならない。少し待ってくれますかと。
もちろん、と、答えたよ。何よりも仕事が一番さ。お疲れ様だったね、と。自分の仕事を詰まらせてまでいろいろやってくれたのだから、こちらからどうこう言える立場じゃない。
それに、ある程度はわかったからね。見つかったのに、報告するまでしばらく時間を置いても大丈夫ってことは、急いで報告しなきゃならないようなことは一切ないってことだろうからね。
生きていることはわかってはいたけれど、自分の知っている人間がちゃんと確かめてきてくれたってことで、何だかね、あれだね。怒っていたとはいえ、家族になった男のことを気に掛けてもいたんだねあたしも。
少しだけ、ほっとしたよ。
ハルオが死んじまえば、花子は泣くだろう。花歌も泣くだろう。あたしはたぶん涙を流したりはしないけれど、自分の娘と孫が悲しむのは想像したくもない。
とりあえず、今のところはそんなことにはならないようだってのが、はっきりとわかっただけでも、良かったよ。
「生きて、元気でいたかい」
「はい」
恭一くんが戻ってきてから四日後。また〈廉清〉で特別に頼んだ夕食を食べながら、話していた。
「思っていたより、元気でした」
「様子はどうだったい。太ったり痩せたりしていなかったのかい」
「ほとんど変わっていなかったですね。多少は何というか、あの頃より全体的に身体は緩んでいたようですけど」
だろうね。
「年も取ったし、人前に出るようなことを何もしていないんだろう?」
「そうです。完全に無職でした」
「なら、そうなるだろうさ」
はい、って恭一くんは頷いた。
「何よりもまず、あたしがお礼をしなきゃならないような人はいないかい」
「お礼、ですか?」
「恭一くんが捜したとしても、そもそもハルオは家の人間だよ。そいつを見つけるために他人様に力を貸してもらったのなら、そういう人たちにはお礼をしないと」
あぁ、と、恭一くんは頷く。頷いて少し考えた。
「いえ、そういう意味では大丈夫です。そもそも僕は博多にいる友人の家に泊まりましたし、そこには僕の方から」
「何か、贈らせておくれ」
「贈る、ですか」
「恭一くんの名前でいいからね。こっちの美味しいものでも贈らなきゃあ気が済まないよ」
それが礼儀ってものだよ。そもそも恭一くんの旅費だってこっちが出さなきゃならないようなものなんだ。
それにしても、って言うと自然に溜息が出ちまった。
「その気になって、確かな情報を元に捜せば、あっさり見つかるもんなんだね」
「あ、それは僕も本当に驚きました。まさかな、って」
まぁそうでもなきゃ、興信所だったかい、そういうような商売も成り立たないんだろうけどね。
「それで」
今、どこでどういう生活をしているか。
何故失踪したのか。
これからどうするのか。
ハルオに聞いた話を、あれこれと問い詰めた結果を、そっくりそのまま恭一くんが話してくれた。
あれだね、私もいろんな人に会うような仕事をしてきたけれど、この恭一くんは仕事のできる子だね。今でこそ、一人でやるデザイナーなんてことをしているけれど、大きな会社に入って大きな仕事で、たくさんの部下を動かしていける器量を持っているんじゃないかね。まぁそういうことを好む性分じゃないのかもしれないけれども。
そして、ハルオは。
「なるほどね」
ふぅ、と、溜息が出てしまう。
「おおよそ、想像の域は出ていなかったね」
逃げた。
自分の暮らしから。
自分の周りにできた、作ってしまった柵から。
そして逃げ回った先でまた違う柵に囚われてしまった。
「女と、女の子、かい」
「はい」
「馬鹿だね、やっぱり」
馬鹿だとはわかってはいたけれど、馬鹿だったね。
「結局、自分の作った柵から逃げ切れていないんじゃないかね」
今、守っているのが女の子だなんて。
その向こうにいるのは自分の娘である花歌だって、わかっていないのかね。
「僕も、そう思いました」
「そう感じたかい」
「はい」
また、溜息が出る。そんなこったろうとは何度か考えたけれど、やっぱりそんなことだったんだね。少なくとも花子や花歌のことを嫌いになったんじゃないのだけは、あの子たちにとっては良かったのかもしれないけれど。
「情けない男だと思っただろう」
訊くと、恭一くんは苦笑いした。
「まぁ、そんなふうに言ってしまったし」
「傷をつけないとこいつは動かないと思ったんだね?」
心に、魂に、何かが残らないと動けない。そう思って、恭一くんはわざとキツイ言葉をハルオに投げ掛けた。
それも、まぁ正解だろうねぇ。
いいね、男同士っていうのは。そういうのを感じ取って、素直にぶつけられる。ハルオもきっと今頃何かを思っているだろうさ。
「本当に、ありがとうね」
改めて頭を下げる。
真っ直ぐにあたしを見る眼。
今の時代を生きる若者は何を考えているかわからないとか年寄りは言うけど、そんなこと言う奴は大抵馬鹿者でしかないんだよ。
人が考えることなんか、人の心なんか、百年千年経ったって変わるはずないじゃないか。
時代で変わるものなんか、技術しかないだろう。そうじゃなきゃ、どうして千年昔の芸術が今も人の心を打つって言うのさ。
いったい学校で何を勉強して社会で何を見てきているんだろうね。どうしてそんなこともわからない人間が大手を振って我が物顔で大声を上げるんだろうね。それだけは本当にわからないよ。
「あたしはねぇ、恭一くん」
「はい」
「お妾さんだったのさ」
お、という形に口が開いたけど、それを引っ込めた。
「意味はわかるかい?」
「わかります」
にやっ、と笑ってやると、恭一くんも苦笑した。
「こんな婆さんがお妾さんだったって聞いても、恥ずかしがる年でもないだろう。困るかもしれないけど」
「まぁ、そうですね」
首を一度振って、お茶を飲んだ。
「花歌ちゃんのおじいちゃん、うたさんのご主人がいないっていうのは、随分前から聞いていましたけど」
そうそう。
「いないどころか、あたしは結婚をしたことがないよ。今でいうシングルマザーってやつだね。恭一くんは、読書なんかするかい」
「それなりには」
「あたしたちが若い時代の小説なんかで、お妾さんが世間的にどういう扱いを受けたか、理解はできるかい」
少し、首を捻った。捻って、考えた。
「そんなに深く考えたことはないんですけど、そもそも〈お妾さん〉というのはもっともっと古い時代の言葉ですよね。うたさんの生まれる前の。うたさんの若い頃っていうのは、昭和の三十年代から四十年代ですよね」
「まぁそうなるかね」
「でしたら、その時代のお妾さんというのは、何かが許されていた時代から許されない時代へと変わっていった頃じゃないでしょうか。そもそも日陰の存在だったお妾さんですけど、それでもその昔は〈日陰〉という存在場所があった。でも、そういう時代から、その場所すら失われていった時代なのでは?」
驚いた。
「随分と詳しいねぇ」
「いえ、単純に好きなんですよ。昭和の時代って」
失われていったものが好きなのかもしれないって続けた。
「いろいろ観たり読んだりしてるのかい」
「主に映画とかドラマですけど」
そうだったかい。
「それなら言うまでもないだろうけど、あたしも随分と世間様から後ろ指を指されたもんだよ。あたしの旦那ってのはね、もうとっくの昔に死んじまったけど、貿易で随分と財をなした男でね」
「貿易ですか」
「そうなんだよ。だからしょっちゅう海外を跳び回っていた。実のところ花子なんかはあの人に二、三度しか会ったことないよ」
驚いた顔をする。
「おばさんは、その、文句というか」
「恨み辛みかい? あたしが妾だってことの」
「はい」
そりゃあ、まるっきりないはずがない。
あの子は、誰に似たのか大人しくて真面目な女の子だったからね。父親がいないことで学校に通っていた頃には、いろいろとあったさ。
「中学校の頃だったよ。男と女のそういうものをようやく理解できるようになったときに、訊いてきたよ」
「何て、ですか」
「自分に父親がいなくても平気だって思ったのかってね」
声を荒げることもなく、静かに訊いたよあの子は。
「泣き叫んでくれた方が楽だったと思うぐらいにね。花子もね、あんなに普通のおばさんみたいな感じだけど、実はかなり個性の強い子なんだよ」
「どう、答えたんですか。うたさんは」
いつかそういうことを訊かれるだろうと思っていたからね。答えは用意してあったよ。
「あたしは、あたししかあんたに与えられるものがない、とね。初めっからそういう人生しかなかったんだってね」
それでいい、じゃない。
それしかなかったんだ、と。
「その代わりに、あたしの人生は全部あんたのためにあるんだよって答えたよ。大人のこ狡い知恵じゃなくて、本心でね」
あたしは、自分の娘である花子を、愛していた。花子のためになら何でもできた。何があろうと守るつもりでいた。
親とはそういうものだ、なんて言うつもりはないよ。いろんな考え方があるだろうし、親にだって自分の人生があって然るべきだろうさ。自分の産んだ子供をきちんと自分の足で立てるまで育て上げるのは最低限の義務だけど、それ以外では親だって自分の好きなように生きる権利はあるだろうさ。
でも、あたしは、この身体で産んだ花子には、自分の人生を全部捧げるつもりで育てていた。それがあたしの人生だってね。
「納得はしたんですか。おばさんは」
「まぁ、どう思ったかは本人しかわからないけど、一応は納得してくれたみたいだよ。それからは自分の父親のことは一切言わなかったからね」
恭一くんは、少し下を向いて何かを考えるようにしていた。
「ハルオさんも、人の親ですよね」
「そうだね。一応は」
「そういうことを、考えなかったんですかね」
それも、誰にもわからないね。
「まるっきり考えなかった、ってことはないだろうさ。少なくとも失踪して、一度も連絡したり、帰ってこなかったことはその証拠だろう。親としての自分を何もかも捨てたことが恥ずかしくて戻ってこられないんだろう? 少なくとも、何もかも忘れて楽しくやっていたってわけじゃないんだろう? ハルオは」
そうでした、って恭一くんは頷く。
「悔やみとか、どういう言葉で自分の胸の内を表現しているかはわからないけど、そんな思いを抱いているんだろうさ。でもね、恭一くん」
「はい」
「あたしは、自分の人生に対して一度だって顔を下に向けたことなんかないんだよ」
自分の立場を悔やんだことなんか、ない。
いつも、いつでも、前を向いてお天道さんに顔を向けて歩いてきた。
「どうしてか、わかるかい?」
恭一くんは、考えてから答えた。
「自分に正直に生きてきたから、ですか」
いい答えだね。
「その通りさ。誰に恥じるものでもない。あたしはあたしの心の赴くままに、自分の気持ちに正直に生きてきた」
だから、花子にも正直に言ってきた。花子もそれを理解してくれた。
本当は、父親と母親がいる普通の家庭が欲しかったと思っていたかもしれないけど、ないものねだりをしたってしょうがない。
人は、自分に与えられたものの中で育って、そして自分にないものを求めて外に出たり、そのままでいいと思ったりする。
「正直に生きるっていうのはね。それは、何も特別なことじゃない。恭一くんだって、そうじゃないかい? 自分の気持ちに正直に生きようとして、今の立場を選んでいるんじゃないのかい」
「そうですね」
素直に頷いた。
会社に入ったけど、自分はそこでは動けないと思ったから、辞めてフリーになった。そしてきちんと自分の立ち位置を確保している。
「花子だってそうさ。市役所に勤めるお堅い公務員だからって不自由に生きてきたわけじゃない。あの子こそ、自分の気持ちに正直に好きなように自分の人生を歩いてきた。あんな変な男と結婚して、それでいて世間様に胸張れる真っ当な仕事をしているんだから、大したものだよ。あたしなんかよりずっと出来がいいじゃないか」
二人で笑った。
「そう考えると、おばさんは確かに凄い人ですね」
「そうさ。言っちゃあ悪いが花歌だって世間様の常識から見たら、相当におかしな子だろう?」
あぁ、と、恭一くんも笑う。
「いい意味でですけど、確かに花歌ちゃんは個性的ですよね」
「そうだろう? おかしな夫とおかしな子に囲まれて、花子はちゃあんと自分の人生を生きてきたんだ」
我が子ながら、大したものさ。
お妾さんとして生きてきたあたしと比べちゃあ申し訳ないぐらいにね。
「だからさ」
息を吐く。
「あたしは、ハルオを心の底から怒れないんだよ。あの子はむしろあたしに近しい人間だからね」
世間様の常識なんかに束縛されたくない。縛られると自分が腐っていく気がする。心のままに生きていかないと自分が駄目になる。
そういう性質に生まれついてしまった人間。
逃げたからって、花子と花歌から離れていったって、心底憎いなんて思えない。
あの子もまた、自分の心に正直にしか生きられないような男だよ。そういう男を家族に迎え入れてしまったんだ。
「うたさんも」
恭一くんが言った。
「おばさんも、花歌ちゃんも、ハルオさんのことをわかっているんですね」
わかっている、と、言ってしまうと何だかおこがましいね。
「同じなのさ」
ハルオも、あたしも。花子も、花歌も。同じような心を持った人間なんだろう。
どうしますか、と、恭一くんが訊いた。
「連絡先は、手に入れました。ハルオさん、スマホを持っていました。今一緒に済んでいる人に借りているそうです」
「借りている?」
「その女性の、亡くなったお母さんのスマホをそのまま使っているそうです」
なるほど。
「うたさんには、家の住所も全部何もかも伝えると言うと、頷いていました。そのスマホの番号も教えると言うと、いいよって」
「あたしが連絡なんかしないことをわかっているからだろうさ」
それぐらい、ハルオもわかっている。
「家族に、うたさんやおばさん、花歌ちゃん、誰にでもいいから連絡する気はないんですか、と訊いたら、僕に見つかってしまったんだから、一度は必ず連絡すると」
まぁ、そう言うだろうね。
「そう言いながら、本当に何かがないと連絡なんかしてこないだろうさ」
「それが」
恭一くんが言う。
「してくると思います」
「どうしてだい?」
「花歌ちゃんです」
「花歌?」
そうです、と、大きく頷く。
「花歌ちゃんが歌をうたう、と、伝えてきました。まだ完成していないけど、弟の凌一が撮った練習風景も見せました。聴かせました。未完成だけど、娘である花歌ちゃんの歌を」
あの子の歌を。
「どうだったい」
「一瞬ですけど、ハルオさんではなく、間違いなく〈ハルオ〉の顔になりました」
今藤恭一 二十九歳
空気が変わるんだ。
それは本当にそう感じる。ハルオさんみたいな天才じゃなくたって、ある種の天分を持った人が本気になったときには、一瞬にして違う空気を纏う。周りの空気が変わる。
そのときも、そうだった。
花歌ちゃんの歌を撮った動画をiPhoneで見せたときに、確かにハルオさんは〈ハルオ〉になった。
「ほんの一瞬でしたけど、昔にスタジオで見たミュージシャンの〈ハルオ〉そのままになっていました。
そうかい、ってうたさんは微笑んだ。
「たぶんそうなるだろうとは思っていたけど、やっぱりかい」
「はい」
俺もそうだ。
誰か他人の作ったすごい制作物を、ポスターやそういうものを見たときに、身体が震える。大げさに言うと、魂が震える。何だこれは、って思う。賞賛の気持ちと同時に、悔しさを覚える。
何で、俺が作っていないんだって。
「ハルオさんも、そう思ったはずです」
「花歌の歌が完成したら、それを聴いたら帰ってくるかね」
「来るはずです」
いや、断言はできない。
でも。
「すぐに家に帰ってこないとしても、ミュージシャンの〈ハルオ〉は必ず戻ってきます」
自分の娘が、こんな凄い歌を作っている。
うたっている。
魂が震えないはずがない。悔しくないはずがない。
iPhoneで開いた。
まだ、何もできあがっていない花歌ちゃんのサイト。
〈花歌〉
うたさんにそれを見せた。
「まだ観ていなかったでしょう? これ」
「初めてだね。花歌の名前しかないけれど」
「これからです。今、花歌ちゃんと睦美ちゃんと凌一、そして〈ハルオ〉の復活を待っているミュージシャンが集まって、作っています」
このサイトの存在を、ハルオさんにも伝えておいた。
「きっと、毎日観ているはずです。ここで花歌ちゃんの歌が聴けるのを」
宮谷花子 四十二歳
驚いた。
「恭一くんが?」
「そうだよ。幸一がね、頼んだらしい」
「佐々岡さんが」
びっくりした。本当にびっくりした。
「そんな簡単に見つかるなんて」
「あたしもそう思ったよ」
お母さんが、ゆっくり頷いた。
「繋がるものなんだろうね」
「繋がる?」
そうだよ、ってお母さんは言う。
「ハルオを知ってる人に見つけられたのは偶然だろうけど、そこから先は、花歌がうたうことで繋がったんだろう」
「花歌」
もうお風呂を済ませて、自分の部屋でギターをつま弾いている。花歌はもう毎日音楽のことばかり考えている。
自分の言葉で、自分の歌をうたうことばかり。曲だけならもう十曲ぐらいはできあがったって言っていた。毎日、睦美ちゃんと一緒に佐々岡さんの家にお邪魔して、曲を仕上げているって。
頼子さんとは、花歌と睦美ちゃんがお互いの家を行き来することに関しては、お互いに何も気を遣わずに放っておきましょうってことになっている。そもそもうちと佐々岡さんは、お母さんの時代から親戚みたいなもの。花歌と睦美ちゃんも、いとこ同士みたいな関係。姉妹と言ってもいいぐらい、ずっと一緒にいる。
だから、こんなふうに今まで以上に一緒に過ごしても特に気にせず、好きなようにやらせているけれど。
「どうしていたの? あの人」
お母さんは、一度唇を真っ直ぐに引き結んだ。
「教えない」
「どうして」
「今のあんたと花歌には必要ないものだからね」
必要ない。
「ということは、私にとっては最悪の状態だったってことかな」
「そうでもないさ」
「そうでもないの?」
お母さんが、少し笑みを浮かべた。
「むしろ、そんなものかい、って拍子抜けするぐらいのものだね」
そうなんだ。
「じゃあ、どうして教えてくれないの」
「花歌がうたっているかさ」
全然わからない。お母さんは、ときどきこういうわけのわからない表現や理屈を言う。花歌が本当にわけのわからない言葉遣いをするのは、お母さんの遺伝じゃないのかしらって思うわ。
「そこでも、花歌がうたうことが関係してくるのね」
「そういうことさ。あいつが戻ってきたときに、あいつの口から聞けばいい」
「戻ってくるの?」
もう何年も失踪したままで、半ばこのまま離婚することも考えていたのに。
「恭一くんは確信していたね」
「恭一くんが?」
「あの子は、ミュージシャンとしてのハルオのいちばん近くにいた子だよ。あたしたちよりずっとね。その子がそう言うんだから、間違いないんじゃないかね」
「じゃあ、それも」
花歌がうたえばってことに。
「そういうこと?」
「そういうことなんだろうね」
花歌がうたうと、あの人が帰ってくる。
(つづく)