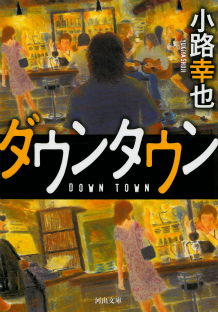花歌は、うたう
『花歌は、うたう』 2
小路幸也(しょうじ ゆきや)
2016.06.20

宮谷花子 四十二歳
「博多?」
「そうだよ」
お母さんがそう言って、揚げしんじょを一口パクリと口に入れてから頷いた。口にものが入っている間は口を開かないから、こっちもほうれん草のおひたしを食べて、ご飯を口に入れて、食べながら待った。
花歌も睦美ちゃんもそうしている。お母さんの次の言葉を待っている。
「幸一くんの知人が見たそうだよ」
「今日会ったの?」
幸一さん。睦美ちゃんのお父さん。
「買い物に出て頼子さんにばったり会ったのさ。そこで教えてくれた。その人は博多でジャズ喫茶をやっていて店にハルオが現れたとね」
思わず花歌を見たら、花歌も私を見た。お味噌汁を飲みながらちょっと眼を丸くしてからパチパチと瞬きする。花歌も今聞いたのね。
「博多に何か縁があったかねあいつは」
全然わからない。
「少なくとも私と行ったことはない。ツアーでは、たぶん何度か行ってるだろうけど」
お母さんが、うん、と頷いた。
「そのあたりかね。知り合いでもいたんだろう。まぁとりあえず一年ぶりに生きてることはわかったわけだよ」
博多は、遠いなぁ。
「間違いないって言ってたの? 幸一さん。というか、そのお店のご主人」
お母さんがまたこくり、と、頷く。
「そうらしいね。そのジャズ喫茶の店主もハルオのファンとかでね。絶対に間違いないってことらしいよ」
「どんなふうだったの? お父さん」
花歌がたくわんを口に入れて、ポリポリと嚙みながら訊いた。相変わらずこの子は、失踪中の父親の話になっても動揺も何もしない。滅多に会わない親戚の話でもするみたいに、淡々としてる。
むしろ、お父さんお母さんからその話題がやってきたと今聞かされた睦美ちゃんの方が、どんな顔をして聞いていればいいんだろうって顔をしてる。
「普通だそうだ」
「普通?」
お母さんが、返事をした花歌じゃなくて、睦美ちゃんを見て少し微笑んだ。別にこういう話になっても何も気にしてないから慌てなさんな、っていう合図ね。そうそう、大丈夫。落ち着いて美味しくご飯を食べていてちょうだい。
「薄汚れていたり、悲惨な様子もなしでごく普通の中年男に見えたそうだよ。そう聞かされる何かカチンと来るけど、生活はきちんとしてるということだろうさ。心配することもない」
「そうなんだ」
うん、って花歌も頷く。
「じゃあ、大丈夫だね」
「大丈夫でしょう」
私も、睦美ちゃんと花歌と両方に微笑んでそう言う。
「あの人はあれで意外と生活力はあるから。若い頃は力仕事でも何でも、稼ぐためにはやっていたからね」
「そうなの?」
「そうだよ。話してなかった?」
聞いてない、って花歌が言う。
「高校の頃なんか、学校にも来ないで道路工事や建設現場で荷物運んだり穴掘ったりしてたのよ」
「穴掘り?」
「たとえよ。工事現場の」
本当に何でもやっていた。
「高校の頃って、そんなに生活苦しかったの?」
「生活のためじゃないわ。ギターとか、楽器を買うために」
あぁ、って花歌も睦美ちゃんもこくこくと頷いた。
「そういうことは」
お母さんが一度箸を置いて、麦茶をボトルからコップに注いで、一口飲んだ。
「芸は身を助けるじゃないけれども、若いうちに苦労したのはあいつの財産になっただろうさ。今こうしているときにはまさにね」
「そうかもしれないね」
高校時代のあの人は、宮谷春男先輩は、学校ではいつも眠っていたそうだ。私はひとつ下の後輩だったから話を聞いただけだけど。でも、実際に見かけたときにはいつも眠そうだった。一度だけ、花壇を囲んだブロックの上に座ったまま寝ているのを見たことがある。具合悪いのかと思って心配になったけど、それもただ寝ていただけだった。
「高校のときのお父さんってさ」
花歌が、箸を置いた。麦茶をお母さんから貰ってコップに注いで、睦美ちゃんにもあげた。
「なに」
「スターだったんでしょ?」
「スターだった」
「スター?」
睦美ちゃんがちょっと眼を大きくさせて、私と花歌の顔を両方見る。
「その頃からあの人は、有名人だったのよ」
夫で、失踪中の宮谷ハルオの話をするのを、お母さんは嫌がらない。家族を捨てて、仲間やファンを裏切って、ミュージシャンであることをも放棄して失踪した男を情けないと、どうしようもない男だと怒ってはいるんだけれど、こうして私や花歌が話をすることは、怒らない。
怒ってはいても、お母さんも、あの人のことを家族の一員だとは思ってくれているからだと思う。この家に一緒にいた頃には、お母さんはあの人のことをすごく認めてくれていたんだから。
「ライブハウスをいっぱいにしてたんだもんね」
「そうそう」
こと音楽に関しては希有な才能を持っていた。私も付き合い始めてから知ったことだけど、それは小学校の頃から芽生え始めていたそうだ。
「ちょうどいい機会だからね」
お母さんが言う。
「昔話をしてあげなさいな。睦美ちゃんが気を遣わなくていいように」
「睦美ちゃん?」
見たら、そうそう、って花歌が頷いた。
「お父さんの話をしたらわたしが悲しむとか思ってるみたい」
「いや、そんな」
少し笑った。そうだね。そんなふうに思うよね普通は。
「あんなろくでなしの話をしたところで、あたし達は屁でもないってことをね。周りにも教えてあげないと」
「いや、そうやってねお母さん。娘や孫の前でろくでなしってはっきり言うのは何だと思うけど」
「人様はともかくも、あたし個人はそう思ってるってことさ。隠す必要はないね。そしてあいつの妻であるあんたや娘である花歌がどう思うかは、それぞれ勝手さね。それを否定したりしないよ」
気が強くて、けっこう毒舌で、よく江戸っ子気質みたいだって周りから言われるお母さん。母と娘と孫の女三代。同じ家で育ってきたのに、どうしてこうも性格が違ってくるのかって本当に思う。
「高校のときに、プロポーズされたんだもんね。お母さん」
「そうなんですか?!」
花歌が言うと、睦美ちゃんがびっくりして口に手を当てた。
「そうなのよ。びっくりでしょ」
私は、子供の頃から地味な女の子だった。この母親なのに、いや、こういう母親だったから余計になのか、口数も少なくて大人しくて、おさげに眼鏡がトレードマークになるような、漫画家さんが絵に描いたような文系の地味目な女の子。
そんな女の子で、音楽にだって興味がなかったとは言わないけれど、ごく普通だった。KinKi Kidsがカワイイとか、GLAYがカッコいいとか、その程度。本当に普通。
それなのに、ミュージシャンになろうとしていたあの人、宮谷春男の彼女なってしまった。プロポーズされてしまった。
「どこで、どんなことで」
睦美ちゃん食いついたわね。それはそうよね。
「学校の、屋上で」
「おくじょう?!」
睦美ちゃんは、花歌より感情表現が豊かな女の子。思いっきり笑うし、思いっきり泣くし。小さな頃からそうだった。ジャズが大好きなお父さんの影響で音楽を始めて、自分でサックスを選んで吹奏楽部に入って。
たぶん、楽器を演奏することを人生の一部に選んだ人って、感情を表に出すことが普通の人より上手なんじゃないかな。
そんな気がする。まるで音楽的な素養がないくせに、周りに音楽をやる人ばかりに囲まれて思春期を過ごした女としては。
「そう、屋上でね」
ちょうど今頃だったと思う。
六月に入った頃。あの当時の私たちの高校はまだ古い校舎で、屋上があってそこに上がることができたのよ。
もちろん、扉には鍵が掛かっていて普通は生徒が勝手に上がることはできなかったんだけど、何故かあの人は鍵を持っていた。
ハルオさん。
あの当時、皆がそう呼んでいた。
先輩や同級生の男の子は〈ハルオ〉、女の子は〈ハルオくん〉、私たち後輩は〈ハルオさん〉。
天然パーマの髪の毛は校則破りで長くて、風が吹くとくるくるふわふわ揺れていた。
男の子にはして可愛らしい感じのする顔は、ステージに立つと一変した。
そんなに高くはなかった身長を気にしていて、毎日牛乳を紙パック一本飲んでいた。
「突然、呼び出されたのよ。放課後の屋上に」
「どうしてですか?」
「全然わからなかった。どうしてあの〈ハルオさん〉が私のことを知っていたのかもわからなかったし」
びくびくしていた。
〈ハルオさん〉は人気者だったけど、同時にちょっとワルい男の子だった。
ライブハウスに入り浸っていて、お酒も飲んでいるって話もあった。乱暴者で、しょっちゅうケンカしているっていう噂もあった。煙草を吸っているところも見たことあるし、何よりも家庭に問題があった。
「お父さんがいなくてね。母一人子一人だったんだけど、そのお母さんも夜の商売をしている人で、とにかくいい噂のひとつもなかったのよ」
「ドラマみたいでしょー」
花歌が言うと、睦美ちゃんが頷いた。
「本当なのよ。住んでいたアパートもすっごく古くてね。ほとんど一人暮らしみたいなものだったのよ」
最悪の家庭環境。
付き合い出した頃に何度か部屋に行ったことがあったけれど、入るのを躊躇ってしまったぐらい。ゴミ屋敷とまではいかなかったけれど、片付けるのにとても一日では終わらなくて、結局一週間ぐらい通ってきれいにしたな。
「一回だけね。同級生と一緒に、ライブを観に行ったのよ。その頃の私は髪の毛をぴったり半分にわけておさげを作って黒縁の眼鏡をかけてね。真面目ひとすじ! って感じの女の子だったのよ」
「お前は本当に融通が利かないというか、堅苦しい女の子だったよねぇ。どうしてそんなふうに育ったのか本当にわからなかったね」
「反面教師じゃないの? お母さんの」
「あたしはちゃんとした女だと自分では思っていたけどね」
睦美ちゃんが、ちょっと唇をもごもご動かして、私とお母さんを見た。
「おじいちゃんが言ってました。うたおばあちゃんは、いなせで小股が切れ上がった女だったって」
お母さんと二人で顔を見合わせて笑ってしまった。
「それは、女子高生の孫に言う褒め言葉じゃないねぇ。進は何を言い出すんだか。睦美ちゃん、意味がわからなかっただろうに」
「ググって調べました」
「どういう意味? こまたって、この股?」
「何で股を叩くの女の子が!」
てへ、じゃないでしょ本当に。天真爛漫で誤魔化せるのは小学生までよこの子はもう。睦美ちゃんが、花歌に向かって、こう、って言いながら脚のスネのあたりを手で払った。
「着物を着てるとこの辺がちらりと見えるでしょ?」
「うん」
「で、その辺がカッコいいのが、小股の切れ上がったって言うんだって。だからこの辺を小股って言うんだって」
「へー、小股」
「大昔の言葉だよ。あたしたちの時代じゃあ、それはちょいと色っぽい艶めかしいお姉さんを褒める意味だったよね。夜の商売とかのね」
「そうだね」
私の時代でも、そんな言葉はもう死語になっていた。時代劇にしか出てこないような言葉。
「言葉って、ムズカシイねぇ。で、お母さん続きは?」
「続き?」
「ライブを観に行ったんでしょう? お父さんの」
「あぁ」
そうね。その話ね。
そのライブで、どういうわけかあの人は私のことをステージから見つけたらしい。
「周りにいなかったタイプだったんだって。だから不思議だったみたいよ」
それで、話をしてみたかったらしい。
「どうして話したかったんでしょうね」
睦美ちゃんが訊いた。
「そのときのあの人の言葉を借りると、まずは、歌詞を書くためにだって」
「歌詞?」
作詞作曲をして、自分でうたっていた。あの人のうたう歌は、今も昔も良い意味で変わっていない。女の子や男の子の素直な気持ちを、独特の言葉遣いと単語を組み合わせてリズミカルな歌詞にして、それをあの人にしか生み出せないメロディラインに乗せてうたっていた。そして、うたいながら踊っていた。
「歌詞を書くためには、いろんな経験をしなきゃならない。でも、そんなにたくさんの経験を自分一人でできるわけがない。ましてや女の子の気持ちなんか自分にはわからないし、経験もできない。だから、女の子の話なら何でも聞きたいって言ってたわ」
「だから、お前の話を聞きたかったんだよね。今まで交わったことのないタイプの女の子」
「そうそう」
そう言っていた。
『あんたと話したいんだ。あんたの話を聞きたいんだ。何でもいいから話してくれよ。オレ、ずっと聞いてるから』
ニコニコしながら、女の子みたいな顔をした巻き毛のカッコいい男の子だったあの人に言われて、私はもう何かふわふわしてしまって、屋上に二人で座り込んでずっと話していた。
「そこでもうプロポーズですか!」
「そうなの」
将来の話をしていたのよ。
あの人は、ミュージシャンになるって言っていた。すぐにでもメジャーデビューして金を稼ぐんだって。
自分の暮らしを変えるんだって。
音楽は、あの人にとって大好きなものであると同時に、どん底にいるような自分の人生を変えるための武器だった。手段だった。
それしか、あの人にはなかったんだ。
「『花子ちゃんは何になりたいんだ』って訊くから、私は公務員になりたいって答えたのよ」
「あ、じゃあ」
睦美ちゃんは、パン! って手を叩いた。
「おばさんは、自分の目標をしっかり叶えたってことなんですね?! その頃からの」
「そうなのよ」
私は、サラリーマンに憧れていた。ちょっと変だったかもしれないけど会社勤めをする人たちを憧れの眼で見ていた。それはきっとそういう人が家族にいなかったせいかもしれない。
毎日朝になるときちんとした格好をして、出勤していく人たちと同じように、あの波に乗って会社へ行く仕事をしたいって小さい頃から思っていた。それで、高校生になる頃には、どうせなら公務員になりたいって思うようになった。
公務員なら、倒産はない。きちんと仕事をしていればきちんとお給料を貰える。それでいて、皆さんのお役に立てる仕事なんだから立派な仕事だって。
「そういう話をしたの」
「屋上で二人で並んでね」
「そう。そうしたら、あの人が突然言ったのよ。『オレと結婚してくれ』って」
「そこでですか!」
睦美ちゃんぐいぐい来るわね。案外この子は早く結婚するかもね。高校生になってまだ子供みたいにふわふわしてる花歌とはちょっと違う。
「びっくりしましたよね?!」
「それがね」
驚かなかった。
いや、驚かなかったっていうより、ただ疑問に思っただけだった。どうしていきなり結婚したいなんて思ったんだろうってすぐに考えて、訊いた。
「何で? って。どうして私と結婚したいって思ったの? って訊いたのよ。もう本当に自分でも可愛げがないなぁと思うけど、すっごく冷静にね」
「そしたら、ハルオさん、何て言ったんですか!」
「『オレにはそういう女が必要なんだ』って」
ミュージシャンになるって思っていた。自分はけっこうイケるって思っていた。でも、あの世界はそんなに甘いもんじゃないっていうのも、考えていた。
「意外とそういう人なの。才能に溺れてるだけの世間知らずじゃなかったのね。自分は絶対に金を稼げるミュージシャンに、スーパーなスターになれるって思っていたけど、そこに至るまでには相当苦労もするかもしれない。そんなときに、自分を支えてくれる女が必要だって」
「え、それじゃあ」
睦美ちゃんがちょっと天井を見上げて考えてから言った。
「それって、打算ってことですか。おばさんが公務員を目指しているからってことだけで、自分のことを支えてくれそうだから、いきなり結婚してくれって言ったんですか」
「私もそう思ってさらに訊いたんだけど、それもあるんだけど、もっと違うところに本質はあるって」
ライブハウスのステージから客席なんてほとんど見えない。ステージ照明の跳ね返りが当たる前の方の人たちはそれなりに見えるけど、後ろにいるお客さんは暗がりの中で、まず見えない。
それなのに、あの人は私を見つけた。
後ろの方で、飛び跳ねもしないでただ黙って歌を聴いていた私を、あの人は見つけた。見えたんだって。
見えたときに、これはきっと運命だって感じた。
あの子は、オレに特別なものを与えてくれる女の子だって。
「そう言ったのよ。真剣な顔をして」
「すごい」
「すごいでしょー」
花歌が睦美ちゃんの肩をバシバシ叩いた。
「わたしもこの話を前に聞いたときに、お父さんスゲェ! って思ったもん。運命だ! なんて初対面で言っちゃうんだよ。しかも高校生のときに。いったいどんな男なんだって笑っちゃった」
私も、笑ってしまった。はっきり覚えているけれど、この人は絶対に頭おかしいって思ったものよ。
「でも、それで連れてきたのさ。花子は、ハルオをこの家へね」
「すぐにですか?!」
「すぐにだよ」
「どうしてですか!」
「だって、お母さんに会わせれば、この人が本気かどうかわかるって思ったから」
そう思っていた。
お母さんには、何もかも見通せるはずだって。
岩崎うた 六十七歳
懐かしいね。
「今でも思い出せるよ。鮮明にね」
あの日のこと。初めてハルオが家にやってきた日のこと。
「日曜日にね、来たんだよ。駅まで花子が迎えに行って、連れてきた」
その当時はまだ、私はこの家でお習字を近所の子たちに教えていた。
確か、八人ばかり生徒がいたよね。小学生ばかりさ。終わる頃に着くように言っておいたんだけど、少しばかり時間が延びてしまって、ハルオがやってきたときにはまだ子供たちが全員残っていた。
淳子ちゃんに、美恵ちゃん、雄介に、ひかるちゃん、藤江ちゃん、あとは誰だっけね。嫌だね、そういうものをどんどん忘れていっちまう。
とにかく、八人の子供がいたことは間違いない。いちばん大きかったのは藤江ちゃんだね。五年生だったはず。それ以外は三年生と二年生。皆、まだまだ本当に子供だったのさ。じっと座って字を書くことも二十分も続いたらいい方のね。
そして、後片づけをしているところに入ってきたハルオを見て、子供たちがすぐに反応したのさ。
「反応ですか?」
「そうだよ」
睦美ちゃんなら経験があるんじゃないかね。
「吹奏楽部で、小さな子供たちの前で演奏したことはないかい」
「あります!」
「楽器を持ってその場に入っていくと、それだけで子供たちの瞳が輝かないかい。キラキラとさ」
「輝きます!」
そうだろう。楽器にはそういう力があるものさ。そして、純粋な感性を持つ子供たちはそういうものにすぐに反応する。
「感じたんだろうね子供たちは」
「何をですか」
「楽器ではなく、ハルオの持つ音楽的な特別な〈何か〉をね。すぐに寄っていったよ。このお兄さんは誰だろう? 何だろう? ってね」
「ハルオさんは、どうしたんですか」
「うたったんだよ」
「うたったんですか」
別に、ハルオが特別に子供好きってわけじゃなかっただろう。嫌いじゃあなかったろうけど、あいつは単純に自分のことを見てくれるその瞳に反応したのさ。
注目してくれるものに、即座に反応できる。
「それは、重要な資質だね。舞台に立てる人間の」
「舞台、ですか」
「ステージだね」
何も音楽に限った話じゃない。
演劇でも、テレビドラマでも、歌舞伎でも、日本舞踊でも、人前でやるものは何でもそうさ。
「人前で輝くことのできる人間ってのは、そういう才を持って生まれた人間は、注目してくれるその瞳に反応するのさ。自然にね」
ハルオは、歌をうたい出した。
「そのときに流行っていたアニメの歌だったかね」
子供たちもよく知っている歌を、筆を持ってうたいだした。
「筆?」
「マイク代わりだったんだろうね。ひょいと手に取って、全身でリズムを取りながら、ステップを踏んで踊りながら、八人の子供たちの前でうたい出したんだ。そりゃあもう大盛り上がりだったよ」
人を熱狂させることができる人間。
「子供たちは、あそこの狭い和室を歩きながら踊るハルオの後について、一緒に飛び跳ねながらうたっていたよ。何曲うたったかね」
「三曲か、四曲ぐらい」
「幼稚園みたいですね」
睦美ちゃんは笑って言うけどね。
「違ったんだよ」
幼稚園のお遊戯とか、小学校の学芸会とか、そんなものじゃない。
「そういうレベルじゃなかったからね」
あたしも、思わず見入ってしまった。聞き惚れてしまった。楽器の伴奏もカラオケも何もない、ただのアカペラ。
高校生のガキがうたい踊るその姿に、見惚れてしまった。
「この子は何者か、と、心底思ったね」
汗をかくほどに熱唱して、踊って、最後にはごろんと座敷に横たわって笑うハルオを、子供たちが取り囲むようにしていた。
皆が心の底から楽しそうにしていた。
そういう男だったんだよ。宮谷春男という希有な才能を持った男は。
「もう紹介どころじゃなかったもんね」
「そうだね」
ろくでなしで、破天荒ではあるけれど、乱暴者じゃなかった。人を気持ち良くさせるものを自然と身に付けている男だった。
だから、その日にもう泊まっていった。泊まらせた。
「禄なものを食べてないってのは見てわかったからね」
痩せた身体、若いだけで体力はあるものの、それに任せただけの子供だってのはすぐに理解した。
話を聞いて、家庭環境も最悪なのもわかった。
「とはいえ、他人様の家の問題に口を突っ込むのも何かと思ったからね」
これがもしも、ハルオが女の子だったらあたしも家に乗り込んで、母親を叱咤したろう。人生に苦労しているのなら激励したろう。この子の将来を考えるならもう少し何とかしなさいと。自分にできることは何でもしてあげただろう。
でも、ハルオにはそれは必要なかった。
「生きる力を、あの子は自分で持っていたのさ」
学校の勉強なんかどうでもいい。義務教育は終わっていたんだし、何よりも素人であるあたしでさえ感じる音楽の才能。
「学校をサボってバイトして生活費を稼ぐことも本人は楽しんでいた。それでいて、友人と遊ぶことのできる学校生活を楽しんでいた。サボリも自分で出席日数を計算していた。だったら、あたしのすることは、せめて人並みに小奇麗でまともな暮らしができるように助けてあげることだけさ」
いつでもご飯を食べにおいでと言った。泊まっていくのならそれもいいと言った。ただし、一宿一飯の恩義をきちんと果たすために、自分のことは自分でしな、とね。
「食べたら茶碗を洗う。お風呂に入るなら風呂は洗う。寝るなら布団は自分で敷く。着ている服は洗濯する」
「まるでここが寮みたいだったね」
「そうだね」
ハルオが生まれながらに得ることができなかった〈安心して帰ってこられる家〉を、ここにしてやればいいと考えた。
もちろん、結婚するしないは、別の問題。
「そのときは、どう思ったんですか?」
「好き合った仲なら、あたしは結婚に反対なんかしないよ。ただし、娘を不幸にするのがわかっていたなら別だけどね」
何よりも。
「ハルオが、この家を好いてくれたからね」
「そうだね」
花子のことを好きになったのも本当だろう。運命的なものを感じたってのは大げさだけど、あの子の感性がそう感じたのも事実なんだろう。
それよりも何よりも、ハルオはこの家を、あたしが親から受け継いだこの家を大好きになった。
「ずっとここに居たいって、言ったね」
それはつまり、あの男がそれを求めていたってことさね。
小さくても、笑顔がある、その薫りが漂う家を。
宮谷花歌 十七歳
お父さんの話は、お母さんとお父さんの出会いや、お祖母ちゃんとの暮らしの話はときどき聞いていた。
その話をすることを、お母さんもお祖母ちゃんも嫌がらなかったから。
「つまり、あれなんですよね」
むっちゃんが言った。
「おばさんも、うたお祖母ちゃんも、花歌のお父さんを、ハルオさんのことを怒ってないってことなんですか」
おずおずだ! こういう態度のことをおずおずって言うんだよね。そんな感じで訊いたら、お母さんとお祖母ちゃんは顔を見合わせて、苦笑いした。
「怒ってるんだよ睦美ちゃん。あたしはね」
「あ、やっぱりですか」
「そりゃあ、そうさ」
お祖母ちゃんが、麦茶の入ったコップを手にして、ゆっくりと一口飲んだ。お祖母ちゃんのそういう仕草、違う、所作? 動き?
美しいんだよ。キレイなんだよ。
どうやったらあんなふうな動きを身に付けられるのかって日々けんきゅーしてるんだけどね。なかなかこれがムズカシイんだ。
そう言って少し笑って、お母さんは息を小さく吐いた。
「大事な娘と孫を、つまり自分の妻と娘をおいてどこかでフラフラしている男だよ。怒っていないはずがないじゃないか」
お祖母ちゃんがそう言って、お母さんを見た。
「もっとも、妻である花子はそんなに怒っていないんだけどね。それがまた腹立つところなんだけど」
「私だって怒ってますよ」
そう言って少し笑って、お母さんは息を小さく吐いた。
「でもそれは、結婚する前からわかっていたことだしね」
「わかっていたっていうのは」
むっちゃんを見て、お母さんが優しい感じで笑った。
「妻や子供のことをいちばんに考えて生きていけない男っていうのはいるのよ睦美ちゃん。これはね、覚えておいて損のないことよ」
むっちゃんが大きく頷いた。
「結局あの人は、花歌のお父さんは、そういう人なのよ。娘のことは可愛いし、私のことももちろん大事には思っていたとしても、自分のことがいちばん可愛くて大事なの」
「でもさ」
ちょっと言っておく。
「それはあれだよむっちゃん。テロとかは別だからね?」
「テロ?」
「そう」
「テロ?」
「そう」
「何それ」
お祖母ちゃんとお母さんが笑った。
「花子は国語の成績は良かったんだけどねぇ」
「あの人も言葉の感覚は良かったのにね」
「どうしてお前は言葉が足りないのかねぇ」
「二人で責めないで。つまりだね、むっちゃん」
言おうとしたら、むっちゃんが手の平をわたしに向けて、大きく頷いた。
「皆まで言うな。わかった。命にかかわる重大なことが起こったとしたら、そのときには、お父さんは家族を放って逃げるような奴じゃないってことを言いたいんだね?」
「そのとおり!」
皆で笑った。
「卑怯者や、人でなしではないさ」
お祖母ちゃんが言う。
「もしそんな男だったらかえってあきらめがついていいようなものだけどね。これでもしも花子がぽっくり逝ったら、あいつは帰ってきて号泣するだろうよ。済まなかったってね」
「その言葉をそっくり返すわよお母さん。ぽっくり逝くのは順番からしてまずはお母さんでしょ。あのね、睦美ちゃん」
「はい」
お母さんが、悪戯っぽく笑ってむっちゃんに言った。
「あの人がね、〈宮谷ハルオ〉が本当に大好きなのはね、このお祖母ちゃん、岩崎うたなのよ。大好きで、でも同時にいちばんコワイの。だからね」
「お父さんが帰ってこられないのは、お祖母ちゃんに怒られるのがコワイからなんだよね」
「そうそう」
お祖母ちゃんは、ただ苦笑いした。
わたしにはぜんぜんまったくそういう記憶っていうか、何も思ったことはないんだけど、お父さんはお祖母ちゃんに本当に感謝していたそうだ。
さっきの話。
ここに来て歌をうたって子供たちを喜ばせて、それから落ち着いて話をしてから、お祖母ちゃんは言ったそうだ。
〈あんたが花子を大事にするのなら、それと同じぐらいにあたしはあんたを大切にしてやろう。守ってあげるよ。だから、あんたも花子と、自分が大事にしているものをしっかり守りなさい〉
普通は、言えないよね。そんなセリフ。
突然やってきた高校生の男の子に。
お父さんが何年も家に帰ってこないのは、たぶんそのお祖母ちゃんとの約束を破ってしまったからだと思うんだ。
自分が大事にしていたお母さんとわたしを、放っておいてしまったから。
この家に、帰ってこられなくなってしまった。
まぁホントのところは、本人にしかわからないんだろうけど。
(つづく)