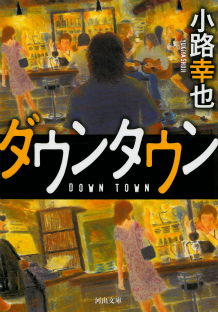花歌は、うたう
『花歌は、うたう』 5
小路幸也(しょうじ ゆきや)
2016.09.20

佐々岡睦美 十七歳
花歌がギターを持った。
実は、それだけで花歌の雰囲気が変わることをきっと花歌も知らない。自分ではわかっていないと思うんだ。
オーラなんていう簡単な言葉を使うのはちょっとあれかな、って思うんだけど、そんなふうに言うしかないものがグン! って増えるのがわかるんだ。
よくアニメで超能力みたいなものを使う寸前で主人公の服がふわりと揺れたりするけど、本当にあんな感じ。
花歌が、変わる。
椅子に座って、ギターを抱えて、軽くつま弾くだけで溢れ出す期待感にワクワクしてしまうんだ。
「でへへ」
「何で笑うの」
「いや、何かこんな部屋でギター持ってうたうなんてこっぱずかしくって」
壁にはレコードがずらりと並んで、大きなスピーカーが眼の前にあって、いかにも、って感じのお父さんのオーディオルーム。
「まぁね」
お父さんのオーディオルーム。一曲できたかもしれないって花歌が言うから、じゃあ一回試しにここでゴロゴロしながら合わせてみようって思ったんだけど。
「とにかく、聴かせてよ」
「うん」
花歌がもう一度弦を弾く。ハルオさんが残していったアコースティック・ギター。ものすごく古いマーチンD35。お父さんの話ではかなり使い込んでいるからあれだけど、マニアだったら百万出しても欲しいギターかもしれないって。音も、すごく良いって。チューニングは合ってる。
「じゃ、聴いてね」
花歌が、うたいだす。
信じてる明日を
わらえない とどかない まもらない
みかけない ありえない わらわない
でも 信じてる明日を
ららるうるうらら
らーらりるらら すっとこどっこい
「ちょ、ストップ!」
思わず、ガッ! って花歌のギターのネックを掴んじゃった。
「何ぃ。ここからサビ」
「何よ『すっとこどっこい』って歌詞は。スゴイめっちゃ良い曲! ってうっとりして聞いていたら」
「えー、まだ歌詞できてなくて」
すっとこどっこいはオマエだ。
「ららるうるうらら~は? 歌詞? ただのスキャット?」
「そこも歌詞できてなくて」
「じゃあ歌詞ないところは最後までスキャットで通してよ。すっとこどっこいはないでしょ」
むー、って花歌が唇を尖らせた。子供か。
「じゃあ、ずっとるーるるるーって歌えばいいか」
「そうしてください」
今度は、歌詞のないところはずっとスキャットした。その軽い感じのスキャットもぞくぞくするほど良い。
十七歳の女子高生が歌詞にすっとこどっこいって。
でも、そんな言葉が出てくるってこと自体がスゴイんだよね花歌は。誰もそんな言葉を使おうとしないよ。
花歌は、『すっとこどっこい』って言葉の意味を使ったんじゃないんだ。単純にその言葉の音の響きがふっとメロディラインの中で浮かんできて口ずさんだだけなんだ。
その感覚が、スゴイと思う。
そして、こうやって花歌が本気で歌うと、もっとスゴイ。喋っているときの声音と変わって、少しハスキー。スモーキーって言ってもいい。そして高音部ではウィスパーボイスも自然に使いこなす。
計算しているんじゃないんだ。自然に出てくるんだ。
一曲の中で自分の歌い方を、発声法をコロコロ変える。それが全然ヘンじゃないし、耳障りでもないし、何ていうか、自然。
本当に自然に聴こえる。
マジに天才だと思うんだ。
「どう?」
最後にピン! ってハーモニクスで終らせて、ニッコリ笑って花歌が言う。
「良い曲」
「ホント?」
「ウソついてどうすんの。歌詞がついていたらもっと良い」
「歌詞なー」
「ムズカシイか」
「ムズカシイねー」
そうだね。ムズカシイね。
メロディは、浮かんでくる。私だってずっと音楽やってるんだ。サックス吹いているんだ。アドリブでなんかやってみろって言われたら、少しは吹ける。オリジナルなメロディやってみろって言われたら、ほんの少しは。
でも、歌詞はムズカシイ。
「むっちゃん書かない?」
「書かない」
「あんなに本を読んでるのに。ムズカシイ言葉も知ってるのに」
「それとこれとは別だよ」
いくら読書が趣味でも、歌詞を書けるはずがない。いや、書ける人もいるんだろうけど私は書けない。
「曲は良い。ホントにすっごく良い」
ちゃんと録音はしておいた。柔らかな、温かい感じのするバラードっぽい感じ。でも歌詞によってミディアムテンポにしてもいいかもしれない。あ、思い切ってボサノバ風にしてもカッコいいかもしれない。
「でも、歌詞ができあがってからじゃないとアレンジもくそもないからね」
「女の子がくそなんて言っちゃいけません」
「ごめんなさいねー」
花歌が、むぅ、って唇を尖らせた。
「お父さんの歌ってさ」
「うん」
「歌詞が、ぶっ飛んでるじゃない?」
「ぶっ飛んでるかな」
「だって、『流星をカッターで切って虹をかけろ~』だよ?」
花歌が歌った。
〈ハルオ〉の『レインボーソウル』。
声はもちろん違うけど、おじさんの、〈ハルオ〉の歌い方にそっくり。物真似も上手いんだよね花歌。
「どこの世界に流星をカッターで切るバカがいるんだよ! って思わない?」
「思うけど、スゴイよね」
「スゴイよねー。本当に流星から虹が出てくる気になっちゃうもんね」
そう思う。
歌詞にルールなんかないんだ。日本語としておかしくたって、良い曲ならそれでオッケーになっちゃう。そもそも日本語として正しくある必要なんかどこにもない。
「なんだったら全部スワヒリ語でもいいんだからね」
「スワヒリ語ってなに」
「アフリカの言葉」
「知らなーいよ」
「たとえばの話だよ」
私のお父さんに聞いたことがあるんだ。昔、日本にロックが芽生えた頃に日本語でロックを歌うことでめっちゃ激しい議論があったんだって。
「ギロン?」
「議論」
「何で歌詞でムズカシイ話になるの?」
「メロディに日本語の歌詞を乗せるのにはどうしたら良いのかって話だよ」
花歌の眉間にシワが寄った。柔らかそうなカーキ色のカーゴパンツのサイドポケットに手を突っ込んで何かアメを取り出した。そんなとこにアメを入れてたのか。
「作曲した曲に歌詞をあてるのに、何でムズカシイ議論をしなきゃならなかったの?」
「そもそも、今、花歌が作曲したメロディーも〈西洋音階〉でできたものだからさ」
「何それ」
花歌が眼を丸くした。
「簡単に言うと、ドレミファソラシド」
「あたりまえじゃん」
「違うの。私たちは日本人でしょ? 日本人にとってそういう音楽は海外から入ってきたものなの。もともと日本にはなかったものなの」
あ、そうか、って花歌が頷いた。
「それでね、英語ってすっごくメロディに乗せやすいって思わない? 私はフランス語もスゴイって思うんだけど、とにかく日本語ってメロディに乗せにくいでしょ。英語で〈I Love You〉って言うところも、日本語で〈愛してるー〉じゃあ、乗らないでしょ? そういうところだよ。果たして日本語でロックをやることにどんな意義や意味があるのかどうしたらいいのかって話を、昔は大真面目にやったんだって」
あーん、ってアメを嘗めながら花歌が頷いた。
「アメ食べる?」
「いらない」
「でもさ」
「うん」
「わたしたちは、生まれたときからドレミファソラシドで日本語で歌ってるんだからさ、関係ないよ」
そう言ってにっこり笑って、うん、って花歌が頷いた。
「そうだね」
関係ないよね。花歌にはきっとそんなことは関係ない。
「わたしもね、むっちゃん」
ギターでCコードをじゃらーんって弾いて、それから適当に流す感じで軽くEmからFに行って。
「考えたんだよ」
「何を?」
「うたう人は、何のためにうたうのかなって」
何のために。
「つまり、お父さんは何のために〈うたう人〉になったのかなって」
〈ハルオ〉さん。
「むっちゃんのお父さんはさ、獣医さんになろうと思ってなったんでしょ?」
「そうだね」
動物が好きだったし、お医者さんにもなりたかったって言ってた。
「じゃあ、獣医になろうって」
「それはさ」
花歌の眼が、ちょっと真剣っぽくなっていた。これは、本当に真面目に話をしようとしているんだ。
「職業でしょ? お金を貰うために、自分の仕事として獣医さんを選んで、そうして獣医さんになってそれで大人になったんだよ。むっちゃんのパンティもそのお金で買ってるんだよ」
「何でパンティ」
「ぐへへへへ」
「やめなさいゲスぃの」
ぽん、ってツッコミのチョップを花歌の頭に入れる。
「でもね、うちのお父さんは、お金を貰うために、仕事として歌手を選んだんじゃないんだよねきっと」
「あぁ」
そういう話か。
「お父さんは、ハルオさんは、ただうたいたかったんだよね。それだけだったんだよねきっと」
「そう!」
バン! ってギターを叩いて花歌は言う。
「職業にしようとか、それでわたしを育てようとか、お母さんを食わせていこうなんてこれっぽっちも思っていなかったんだよあの人は」
「それって、おばさんに聞いたんでしょ」
「あ、わかった?」
わからいでか。
「子供の花歌がそんなことを考えるはずないしょ。訊くはずないでしょ」
「まぁね」
でもさ、って続けた。
「子供だったわたしでも、お父さんはただうたいたかった人なんだなっていうのは、感じていたんだよ。だから」
「何のために〈うたう人〉になったか、じゃなくて、ただそうなってしまったんだって言いたいのね」
うん、って花歌が頷いた。
「それがさ」
言いたいことはわかったよ。
「失踪したっていう原因は、そこにあるのじゃないかって、花歌は思っているんだね」
「そんなとこさぁね」
私も花歌もまだ高校生で、アルバイトはちょっとだけしたことあるけれど、お金を稼いだことなんかほとんどない。
でも、大人になったら働いて自分の仕事をしなきゃならない。それでお金を稼いで生活しなきゃならない。
うたう人は、本当は、そんなことを考えていちゃうたえないのかもしれない。
それは、〈ハルオ〉さんのことを考えたら、私も感じたことがあるんだ。
「花歌がうたうのは?」
「うん?」
「花歌が、自分で歌を作ってうたおうって思ってくれたのは、将来はそれで暮らしていこうってところまで思った?」
「そんなの、考えてないよ」
全然考えてないって、花歌が笑った。
「でもさ」
「うん」
「わたしがうたったら、むっちゃんは嬉しいでしょ?」
「嬉しい。すっごく」
「リョーチも喜ぶよね」
「喜ぶね」
だから、うたうんだよ。花歌はそう言った。
「じゃあね、花歌」
「うん」
「もう少し、歌詞のことを考えようか」
どうしたら、自分の世界をちゃんと作ることができるのか。それは、ちゃんと考えないとダメなことなんだ。
「むっちゃんさ」
「なに」
花歌が、買ってきたペットボトルのお茶の蓋を開けて、くいっ、と飲んだ。
「恋をしたことあるでしょうか」
「いきなりなんでしょうか」
「恋だよ恋! LOVEだねぇだよ!」
花歌の真ん丸の眼がくりん、って動いて私を見る。
「つまり、恋の歌ってこと? そういう歌詞は恋をしなきゃって話?」
「そうなんだよー」
花歌が溜息をついて言った。
「やっぱりね、こう、心ってもんがですね、ぐぐっ! と動かないと歌詞って書けないと思うんですよね」
それは、まぁわかるような気がする。
「恋は人を詩人にするって言うからね」
「そう、ポエマー」
「そう、ポエム」
本当かどうかは私は詩人じゃないからわからないけど。
「歌詞の全部が実体験である必要はないし、そんなこといったら作詞家はみんな波乱万丈な人生を送んなきゃならないし、花歌もこれからとんでもない人生を歩まなきゃならないけど」
「それはいやん」
「でも、実際に何かを経験して、それこそ心が動いたことを表現するっていうのは、言葉にしていくっていうのは確かに必要だよね」
そうなんだよねぇ、って花歌がまた溜息をついた。
「恋をしたいって?」
世の中の歌は、全部ラブソングだって言い切った人がいるけど。
「や、したいかどうかはわかんないけど、少なくともした! って感じたことないからなぁ」
「そうだねぇ」
私は、知ってるんだ。
花歌は男の子に恋したことがない。
別にレズビアンってわけじゃないんだけど、男の子を好きになってその人のことが頭から離れなくていつでも眼で追っちゃって、寝ても覚めてもその人のことが気になってしょうがない。
そういう恋を、したことないんだ。ずっと一緒にいるんだから、わかる。
好きな男の子は、みんな友達。仲良しになって、一緒に遊んで騒いでいられればそれで満足。
子供か、って感じ。
まだ小学生みたいな女子高生。
それこそ、レズビアンじゃないけど、花歌が抱きしめたくなるほどカワイイ! って感じるのは女の子の方だ。みゆちゃんなんかいっつも廊下でばったり会ったら花歌にぎゅーっ! て、抱きしめられてる。苦しい離せ! って騒いでいる。
「想像はできるよ? でも想像で言葉を並べてもさー」
「うたうときに、上っ面だけひっかいてる感じなんでしょ」
「そうそう」
でも、恋は無理矢理するもんじゃないし。できるものでもないし。
「新しいラブソングをうたえばいいんだよ」
「新しい?」
花歌がきょとん、って感じで眼を丸くした。
「わかんないけど、花歌が好きだって思ったものが、恋なんだよ。別に恋とかそういうものにとらわれないで、花歌が嬉しかったり悲しかったりしたものを、そのまま歌詞にするといいんだよ」
たぶん。
今藤凌一 十七歳
「あれ」
珍しい。兄貴からのLINE。
【最近の花歌ちゃんの話何かないか】
花歌の話?
【ネタになるような話ってこと?】
【そんなようなこと】
花歌は、ネタの宝庫だ。
昨日も朝、学校に来て教室に入って机についた途端にカバンから食パンを取り出した。コンビニで売ってる袋のままの食パン。それを一枚取り出してもぐもぐもぐもぐ食べ出した。食べながら皆と朝の挨拶やら楽しそうに話をしていた。
まぁそんなようなのはいつものことだから、誰も驚かないしツッコミもしないんだけどさ。
自由人だ。本人はまったく意識していないんだけど。
でも、やりたい放題っていう自由人じゃない。何ていうか、心が自由なんだ。あいつは何ものにも染まらない。
ただの〈宮谷花歌〉がずっとそこにいるんだ。
【いろいろあるけど、そもそも花歌のネタを何に使うの。ただ聞きたいだけ?】
【内緒なんだが】
内緒?
【お前は男と男の約束を守れるよな弟】
何だいきなり。
【守るよ兄】
【絶対に誰にも言うなよ。もちろん花歌ちゃんにも睦美ちゃんにも誰にもだ】
【わかってる】
オレは、そんなにお喋りじゃない。
ちょっと間が空いた。
【俺は、〈ハルオ〉を捜しに行ってくる】
思わずのぞけった。
マジか。
【何で!】
【いろいろあって、だ】
【いろいろって】
【それは長くなる】
【聞かせて。電話して】
すぐにiPhoneが鳴った。
「もしもし」
(部屋だよな?)
「部屋だよ」
(簡単に言うと、ハルオさんが九州の博多で目撃されたんだ)
「博多」
もちろん、行ったことないけど知ってはいる。
(確実な目撃情報で、しかも状況からしてそこに住んでいる節がある。それで、佐々岡先生に頼まれて俺がいろいろ確認しに行くことになった)
佐々岡先生が?
「いや、それで何で兄貴なの」
(大人で独身で自由に動けて、しかもハルオさんのことをよく知ってるからだ。つまりだ、これは花歌ちゃんはもちろん、宮谷家には秘密にして、内緒で行くんだ)
「内緒」
(でも、おばあちゃん、うたさんには一応行くことは伝えてある)
うたさんか。あのおばあちゃんには何を言っても平気なんだ。最強のおばあちゃんなんだ。
「けっこうヤバい状況だってことなんだね?」
(さすが俺の弟だ。察しがいいな。その通りだ。かなりヤバい。だから、くどいけど本当に誰にも言うなよ)
「わかった。で、花歌のネタがほしいっていうのは、つまり、ハルオさんに会ったときのためにってこと?」
(そういうことだ)
そういうことか。
(本人がどう思うかはわからないけど、少なくとも俺はハルオさんに戻ってきてほしい。きっとハルオさんは花歌ちゃんのことを考えないようにして暮らしているはずだ。思い出させるための武器はいろいろほしいからな)
了解した。
花歌が初めて自分で作った曲を兄貴に送ってやった。まだ歌詞もついていない、ただ録りっ放しのものだけど。
それでも、花歌が凄いシンガーになるっていうのが、はっきりわかる。兄貴も驚いてた。歌が上手いのは知ってはいたけど、こんなにも個性的で、そしていい曲を作るなんて知らなかったって。
きっと、ハルオさんも驚く。ハルオさんは、まだ八歳のときの花歌しか知らないんだから。
花歌がうたうって聞いたときには、めっちゃ嬉しかった。
花歌の歌がすごいのを、本当に才能があるのを知ってるのはゼッタイにオレと睦美だけだ。今のところだけど。
どうしてかって言うと、オレも睦美も才能があるから。
自慢するわけじゃないし、誰にもそんなことは言ってないけど、そう思ってるんだ。
オレは、ゼッタイにスゴイ映像を作る才能がある。
睦美は、音楽的な才能がある。
睦美はオレと違って控え目な性格だからそんなふうには思っていないだろうけど、この間まで吹奏楽部にいたけどあいつの耳はスゴイんだ。顧問の柏原より睦美に任せた方がきっといい演奏ができるはずって思っていた。
アレンジの才能がある。
きっとお父さんの、ジャズ好きの佐々岡先生の血を引いたんだよな。佐々岡先生には出てこなかったけど、演奏して音楽を頭の中で構成していくっていう才能があいつに吹き出したんだ。
メロディを聴いた瞬間に、睦美の頭の中には大きな部屋ができるんだ。その部屋にはこの世にある全部の楽器が置いてある。
その楽器を、睦美は全部演奏できる。
音が流れてくる。
オーケストラを操る人の頭の中は、本当に常人とは違うんだ。
兄貴も言っていた。
同じグラフィックデザイナーでも、大きなポスターを作れる人と、パンフレットしか作れない人がいるって。
それは、その人の頭の中にどれだけスペースがあるかっていうことなんだ。つまり、才能なんだ。
ポスターが作れる人の頭の中には広大なスペースがある。
音楽も同じなんだ。
もちろん、映像もそうさ。
オレの頭の中には無限に広がるスペースがある。そのスペースにはやっぱり無限のグリッドがある。
そのグリッドは自由自在に動いて映像を動かすことができるんだ。
それは、兄貴にはない才能。兄貴は、映像を頭の中で動かすことができない。グラフィックしかできないデザイナーなんだ。
別にそれはオレの方がスゴイってわけじゃなくて、平面のグラフィックをやらせたらやっぱり兄貴の方がスゴイ。
でも、映像は、オレだ。
花歌が自分で作った歌を、睦美がアレンジして完成した〈曲〉にするんだ。そうしたらオレは、その曲と花歌でMVを作る。
それを、流す。
ゼッタイに、いろんな人に届くんだ。きっと。
ハルオさんに届くかどうかは、わからない。ネットを使っていないと、少なくともスマホを持っていないとそこには届かない。
でも、もしも、兄貴が直接ハルオさんに会って、あの録音した花歌が作っている最中の歌を聴いたら、ぶっとぶはずだ。
今藤恭一 二十九歳
凌一からいろんなものを貰った。
全部、花歌ちゃんだ。
花歌ちゃんの歌はもちろんだけど、その他にも花歌ちゃんを撮った動画が山ほどあった。
「こんなに撮ってたんだな」
あいつが小学校の頃からとにかくビデオが大好きで、自分でもカメラ片手に動画を撮ってるのは知ってたし、そっちの才能があるのもわかってはいたけど。
「感心するなぁ」
これは、凄い。
ただの女の子の成長記録としても完璧だし、女子高生になった花歌ちゃんのビデオクリップとして商品にしてもいいぐらいのものだ。
別に花歌ちゃんをずっと追っかけて撮っていたわけじゃない。あいつのビデオ好きは有名だったから、小学校の頃から何か行事があると記録係を任されていたんだ。だからあいつはずっとビデオカメラを手にしていた。
ずっと同じ学校だったし、近所だったら自然と花歌ちゃんと睦美ちゃんを撮ったものが増えていく。
それを、編集している。
「これで別に恋してるわけじゃないんだからな」
でも、これはもう、恋だ。愛だ。
あいつは、花歌ちゃんというそこにいる存在に恋をしてずっと撮っているんだ。それなのに好きな子はちゃんと別にいるんだっていうから、そこは、わからん。
「その辺はやっぱり俺より才能があるんだなぁ」
今までの経験によると、突出した才能のある人間はやっぱりどこかが変だ。一般常識に照らし合わせてそぐわないところを持っている。そう言う意味では俺は本当に常識人でたまにイヤになるときはある。
動画を観る。
何でもない花歌ちゃんの登校の風景がある。睦美ちゃんも一緒に写っている。ただそれだけの映像なのに、そこに詩情がある。どうやったらこんなふうに撮れるのか、凌一に訊いてもわかんないだろう。
引いて撮っていて、ズームになった瞬間に花歌ちゃんが笑う。そして風が花歌ちゃんの髪の毛を揺らす。
完璧な映像だ。何でこんなタイミングでアップを捉えられるんだ。
「何か、ヤバいな」
これ、ずっと観ていたら花歌ちゃんに恋をしてしまいそうだ。
美人ってわけじゃない。もちろんブスじゃない。可愛い女の子だ。愛嬌があるって言った方がしっくり来ると思う。
もしも、アイドルになりたいって言ったとしても周りはちょっと「うーん」って考えた後に「まぁそっちの方向もあるかな」って少し苦笑いをするぐらいの感じだ。飛び抜けてはいないけれど、好かれる感じの女の子。
でも、もしも花歌ちゃんがその気になったらもっと美しくなる。
そういう可能性も秘めた女の子だ。
どうせ向こうでも仕事をするから、MacBook Proを持っていくことにして、映像も全部入れておいた。iPadでも見れる。
これを観たハルオさんはどんな顔をするだろうか。
可愛らしく成長した自分の娘を、八年間も何の音沙汰もなく、会っていない自分の娘。
しかも、ひょっとしたら自分を越えるほどの才能を持った女の子になっている。
感激するか、悔いるか、無視するか、泣くか。
「わかんないな」
ハルオさんも、天才だ。
一緒に仕事をしてそれはイヤって程にわかっている。普通に考えたら、優しい奥さんと可愛い娘がいる幸せな家族を捨てて八年間も音沙汰無しだなんて、とんでもない話だ。
でも、ハルオさんだから、それもありなのかって思っている自分もいる。
「何にしても」
明日だ。
明日、博多に行く。
(つづく)