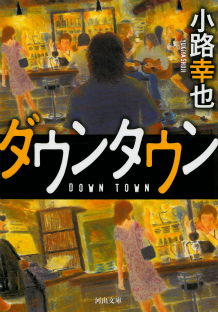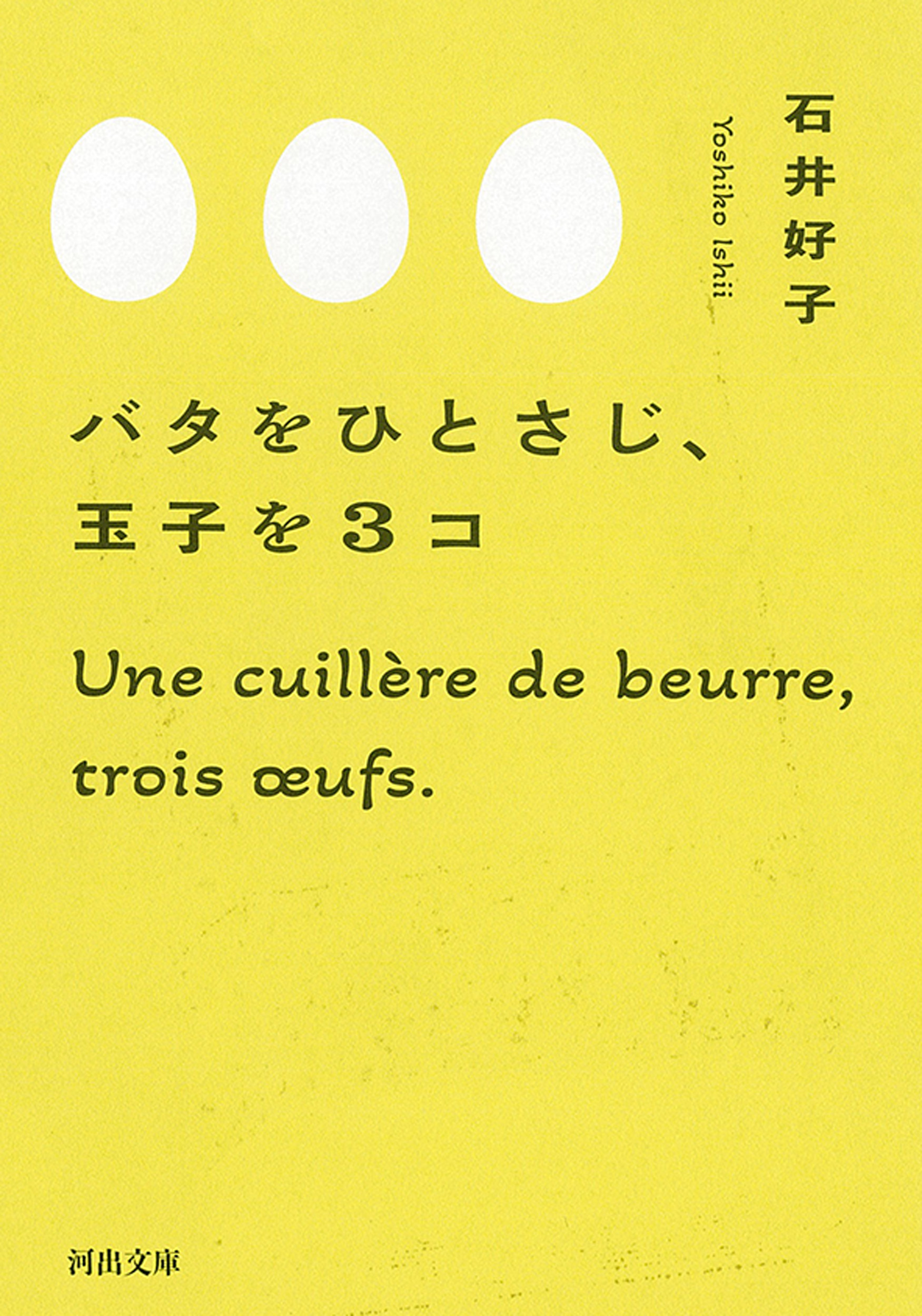花歌は、うたう
『花歌は、うたう』 8
小路幸也(しょうじ ゆきや)
2016.12.16

岩崎うた 六十七歳
トンカツを作って晩ご飯を食べたその後に三人揃って家族会議だなんて、一体何を言い出すのかと思えば。
「そんなことかい」
「そんなことってー」
花歌が口を尖らせた。この子は本当にいくつになっても仕草や表情が子供みたいで、まぁ実際に子供なんだけれども、高校生にもなれば少しは女の色気ってものが出てきて然るべきなのに。
そんなのが微塵もないっていうのは、ちょいとどうかって思うね。そういうのを好む男も世の中にはいるだろうけど、あたしに言わせればそれはもう変態だね。男の性癖ってのは千差万別でひとくくりにはできないだろうけど、赤ん坊みたいな風情を残す女に魅かれる男ってのは間違いなく変態だと思うよ。
「確かにそんなことじゃないわよお母さん」
花子が、麦茶をコップに淹れながら言う。
「家族のことは、まるっきり表に出ていないんだから、もう忘れられたミュージシャンとは言ってもけっこうな騒ぎになると思うわよ」
「そうかねぇ?」
「お祖母ちゃん、ネットの怖さを知らないね?」
「馬鹿におしでないよ。それぐらいは知ってるよ」
そんな話があたりまえのように表に出てくるこの時代に、知らないで済ませられるかい。
「悪いことをしたってのが騒がれるのならともかく、あいつの娘が歌ってるってことだけでそんなに大騒ぎになりゃしないよ」
花歌が歌をうたって、それをネットにアップする。
わかるよそれぐらい。ネットったって、テレビがこの世に出てきたときの凄さを考えたらそれほどでもないさ。
「馬が自動車になったってぐらいさ。やってることは乗って動くってことには変わりないんだから」
「まぁ」
花子が少し考える。
「そんなふうに言われちゃ、確かにそうだけど」
「携帯電話だってね、あぁスマホかい? あれだって昔から考えたらとんでもない未来だって言う人もいるけれどね、たかが電話が一人一台持つ時代になったってことだろう」
「電話だけじゃないよー」
「音楽も聴ける映画も観られる地図で案内もしてくれる、パーソナルアシスタントだって言うんだろ? そんなの電話にラジカセがついて地図もついて道案内を自動でしてくれるってだけじゃないか。今までにもあったもんが小さくなってひとつになったっていうだけじゃないか」
騒ぐようなもんじゃないんだよ。
「電話が初めてできたときの衝撃を想像して考えてごらんな。それまで、遠くにいる人と話せるなんてのは神様しかできなかったんだよ。神様がいるかどうかは知らないけど、人間業じゃないかったんだよ」
まるで神様の仕業のような技術の進歩なんて、そうそう起こるもんじゃない。
「あたしが生まれたときにはもう世界は飛行機が飛んで無線で話してドンパチやって爆弾落としてたんだよ。そこから先、この世界なんざぁ何にも進歩なんかしてやしない。ましてや人間なんて千年経っても何にも変わっていない」
悪意を持ってる奴に、善意で動く奴。勘違いする男に、勘違いする女。頭のいい奴に、頭の悪い奴。そんなもんだよ。
「何を言いたいかって言うとね、花歌がやりたいようにやればいいってことさ。あんたの家族はあたしと花子の二人っきりだ」
「二人ってことはないでしょう。親戚はいるのに」
「ほとんど何の付き合いもない親戚なんて他人より遠いよ。ほぼ二人っきりだよ。どっかにいるあいつを除いてはね。だから、どんな騒ぎになったってあたしと花子、あんたの祖母と母がどっしりしてりゃあ何の問題もないってことだろう」
「むー。まぁそうなんだけどさ。でもお母さん、学校から何か言われたらどうする?」
「それは」
花子が少し考えて、頷いた。
「この子の意思を尊重していますので、何も問題ありませんって言うわね」
「ほらご覧。そうだろ?」
「じゃあ、わたしがストーカーとかに狙われたら」
「ストーカーかい」
まぁ確かにそれはちょいと問題があるね。
「そうなったら、いやそうなる前に素直に警察にお世話になるさ。警察が守ってくれないなら、二十四時間花歌を守ってくれる警備員でも雇うさ」
そういうことだよ。
「それでいいのかー」
「いいんだよ」
「じゃあさ」
花歌が言う。
「これで、わたしは未成年だけど、ネットに顔出ししてアーティスト活動していいって保護者の承諾を得たって考えていいの?」
花子は私の顔を見た。
「あたしは祖母だよ。保護者はあんただよ」
「そうだけど」
少し首を捻る。
「そうね。悩んでもしょうがないことだし、花歌が好きでやることなんだから、いいわよ」
「ありがと!」
「ただし」
頷きながら、花子が真面目な顔をした。あれだね、あたしが言うこっちゃないだろうけど、花子も年取ったのかあたしに似てきたんじゃないのかい。そういう顔をしたときの雰囲気がさ。
「一緒に睦美ちゃんや凌一くんもやるんでしょう? いろいろと手伝ってくれるんでしょう?」
「そう!」
「二人に迷惑だけは掛けないように。二人の厚意に甘えるのはいいけれど、自分の我儘で振り回さないようにね」
「わかった」
花歌が笑顔で頷く。
我が孫ながら、この子の笑顔はいいよね。愛嬌と同時に華がある。それはきっと、あの男から受け継いだものだね。
ハルオも、笑顔が良かったんだよ。
「お母さん」
「うん」
来るかな、と思っていたら、来たね。襖がすっ、と開いて、パジャマ姿の花子が入ってきた。
「起きてた?」
「見りゃわかるだろう」
布団は敷いてあるけれども、本を読んでいたんだよ。花子が頷いて、私の横に来て布団の上に座った。
「何だい」
「この間の話」
「ハルオの話かい」
そう、と、頷いた。
「花歌がうたうんなら、きっとあの人に届くわ。間違いなく」
「だろうね」
そう思うよ。
「身内の贔屓目でなく、あの子には才能があるからね」
花子も頷いた。
「それで、もしもあの人から連絡があったなら、離婚してもらいます」
真っ直ぐにあたしを見て、言った。
「そうかい」
本気だね。
「今更って気がしないでもないけどね」
言うと、首を横に振った。
「花歌のためよ」
「離婚が花歌のためになるのかい」
「あの子が本気で音楽をやるのなら、父親と対等の立場にならなきゃ駄目だと思うの。素人考えだけど。そのためには、もう家族ではないってことをあの人に示した方が、あの子のためにもいいと思うんだけど」
「けど?」
花子は、ちょっと首を傾げた。
「そんなふうに考えたけど、どう思う?」
「あたしがどう思おうが関係ないよ。夫婦の問題なんだからね」
「花歌は、どう思うかな」
「それは、花歌に訊いた方がいいね。ただし」
「ただし?」
「連絡が来てからの話だね」
父親が失踪するのと、両親が離婚するのにどれだけの違いがあるのかなんて、その子じゃないとわからないだろう。
「花歌は父親がいなくなったってああいうふうにいい子に育ったけれど、離婚となるとまた話は別だろう。あの子のことを考えるのなら、花歌が本気でうたった歌が世に出て、自分が父親と同じミュージシャンだってことを自覚してからの話じゃないかい」
そう思うよ。
今藤恭一 二十九歳
水野のお母さんの元カレだっていう興信所の所長さんが教えてくれたのは、駅からもそんなに極端には遠くない住所。すぐ近くに小学校と中学校がある住宅街の、ただ広いだけの公園があるところ。
所長さんが言うには、〈ハルオ〉と思われる男はこの公園で子供を遊ばせていたって。女の子は一輪車に乗って楽しそうにくるくる回っていた。近くには友達らしい子もいた。それを、〈ハルオ〉らしき男はただじっと座って見つめていたそうだ。もちろん、ときどき女の子は近寄ってきてニコニコ笑って話していた。
残念ながら時間がなくて家の特定まではできなかったけど、この公園のすぐ近くにいることは間違いない。どうしてかっていうと、〈ハルオ〉らしき男はサンダル履きだったからってことだった。それは確かにそうかも。
所長さん、藤代さんは言っていた。たぶん、その女の子は〈ハルオ〉らしき男の実の子供ではないんじゃないか、と。
ただの勘でしかないから保証はしないけど、何十年も探偵をやってきたからその辺の見る眼は肥えているつもりだって。
女の子はハルオさんに懐いていたし本当のお父さんのようにしていたけれど、ハルオさんの方にどこか違和感があったって。
(違和感か)
子供を持ったことも結婚したこともないからその辺はわからないけど、たとえば、街を歩いている男女が、仲良さそうに話していても恋人かただの友達同士かっていうのは、何となくわかる場合がある。そんな感じだろうか。
公園の中に入って、見回してみた。
今日は平日でしかも午前中。人影はない。あ、おばあさんが公園の中の遊歩道を歩いているな。
子供の遊具は、少ししかないけどきれいな公園だ。だだっ広いし小学校も中学校もあるんだからきっと学校が終った頃から子供たちで賑やかになるんじゃないのか。
あまりじっとしていて、不審者に思われても困るから、ぶらぶらとあてもなく歩くことにする。歩いていれば、同じところをぐるぐる回らなければ問題ないだろう。
普通の住宅街だ。
古い普通のアパートもあれば、新築の家もある。工事中でシートで囲まれたマンションらしきところもある。こういうところはどこの街を歩いてもきっと同じなんだろうって思う。
どうしてその家に眼が留まったのかわからない。
古いブロック塀。そのブロック塀からはみだすようにして松の木や名前のわからない木がある。やっぱり古い平屋の日本家屋があって、その隣にあまり似合わないプレハブのような離れっぽい建物。狭い敷地にぎゅうぎゅう詰めで、たぶん庭だったところにそのプレハブを建てたんじゃないかって思う家。
道路から少しカーブするように五段ぐらいの階段があって家の敷地に入っていく。
その階段にしゃがみ込んで、草を抜いている男がいた。片手に箒を持っているから掃いていて雑草に気づいて抜きはじめたって感じ。
その男の背中に、見覚えがあった。
普通の、ジーンズ。普通の、白いシャツ。そしてサンダル。
「あの」
少し声が上ずってしまった。その男は少し驚いたみたいに振り返った。
ハルオさん。
僕を見て、一瞬誰だ? っていう表情をした後に、笑った。
「恭一ぃ?!」
その声は最後に会ったときの、〈ミュージシャンのハルオ〉のままで、少し痩せて皺が増えたような顔も、笑顔もそのときのままで。
「ええっ?! マジかおい! 恭一か!?」
「あ、ご無沙汰してます」
バカみたいな挨拶をしてしまった。ハルオさんは立ち上がって箒を放り出して階段を下りてきて、僕の両肩に手を置いてバンバンと叩いて。
「老けたなお前! すっかりオッサンだな!」
そう言って笑いながら僕を思いっきりハグする。そのまま背中を叩く。あのときのままのハルオさん。
でも、身体を離して、半歩下がって僕を見たときには、笑顔が消えていた。薄く、困惑したような表情を見せた。
「ひょっとして、オレを捜しに来たのか? 見つけたのか?」
「えーと」
正直に頷いた。
「そういうことです」
「そういうことか」
ハルオさんは一度下を向いて、大きく息を吐いて、頭を巡らせて家の方を見た。
「よくわかったな、なんて話は後にするか。ご覧の通り、ここがオレの家だ」
「ハルオさんの家」
「といっても、居候だ」
居候?
「そこのプレハブみたいなところが、オレの部屋だ。まぁ寄ってけ」
プレハブよりは少しマシなのかなって感じの部屋だった。どういう目的で建てられたのかまったくわからないけど、二間分の広さがある。
そこには、まったく生活感がなかった。あるのはシングルベッドと、テーブルと、小さな台所に小さな冷蔵庫。薄汚れているわけでも散らかし放題ってわけでもなく、何だろう、そうだ工事現場にある休憩所ってこんな感じなんじゃないか。簡単な食事ぐらいは摂れて、仮眠できるような部屋。
テレビもラジオもパソコンもない。
ギターもキーボードも、楽譜もない。
それなのに、本だけはたくさん積んであった。百や二百じゃきかない数の単行本から文庫本までが。パッと見は、時代小説からSFからとにかく何でも雑多に積み上げてあった。
「いくつになった」
冷蔵庫から出してくれたのは、麦茶だった。それを一口飲む。
「二十八ですよ」
「二十八かぁ」
テーブルを挟んで床に座ったハルオさんは、確かに年相応の中年男になっていた。ロウさんの言う通り、オーラも何もない。知らない人が見たらどこにでもいそうな、おっさんにしては愛嬌のある顔立ちの、ただの中年男。
何の仕事をしてるのか、まったく判断がつかない感じの、普通の男だ。
ハルオさんも麦茶を飲んで、テーブルに置いてあった煙草を取って、火を点けた。
「それで? まだデザインやってるのか?」
「やってます」
言ってから気がついて、財布を出した。何かのときに入れてある名刺を出して、ハルオさんに渡した。
「グラフィックデザイン、ね。カッコいい名刺だ。やっぱりお前はセンスがいいよ。一人でやってるのか?」
「一度会社に入ってやったんですけど、今は独立して」
そうか、って微笑んで頷いた。
「結婚は」
「まだです」
「お前さぁ」
急に砕けて、笑った。
「あの頃ちょっとゲイなんじゃないかって思ったけど、そうなの?」
「いやどうしてですか。違いますよ」
「アレ違ったか? オレの勘も当てにならないな」
そうか、って頷きながら僕を見る。
「その様子なら、なんとか食っていけてるんだな」
「お陰様で」
「才能ある奴ってのは、何とかなるもんだよ」
気づいた。
ハルオさんは、何も言おうとしない。訊こうとしない。
「あの」
「いや」
手を振った。ちょっと待てって感じなんだと思って、待った。ハルオさんが煙草を吹かしてから、言う。
「誰かが死んだとかじゃないよな?」
「え?」
「お前がオレを捜したのは、誰かが死んだとかじゃないんだろ? そんな感じには見えないから」
そういうことか。
「大丈夫です。うたさんも、花子さんも、花歌ちゃんも元気です」
そうか、って言いながら下を向いた。
「ハルオさん」
「あー、待ってくれって」
また手をヒラヒラさせた。
「ほら、まだ日が高いしさ。酒も飲めないしさ」
酒って。
「居候だからさ。いろいろとしなきゃならないことがあるんだよ」
「何ですか?」
「子供の相手とかさ。いろいろあってさ、あーそれも訊くな。誰の子供ですかとかさ、とにかく訊くな。後からにしてくれ。コントロールできないからさ」
コントロールできないって久しぶりに聞いた。ハルオさんの口癖だ。
何か迷ったり考えられなくなったり、自分でどうしていいかわからなくなったときに必ず言う。リハのときなんかステージ上でよくそう言って演奏を止めて、しばらく考え込んでいた。
「泊まるところはあるのか? ホテルか?」
「あります。友人のところです」
「こっちに友達いるのか」
「偶然ですけど、いたんです」
そっか、って頷いた。
「わざわざ来てくれたお前を追い返すなんてできないからさ。まったくなぁ、どうしてお前が来たんだよ」
「僕じゃなかったらどうしたんですか。たとえば奥さんが来たら」
「逃げるよ」
「逃げるんですか」
「そりゃそうだろ。最初に逃げたんだからそのまま逃げるよ」
まぁそうか。
「花歌ちゃんが来ても、逃げたんですか」
訊いたら、僕を見た。
困ったように、笑った。
「あいつ、美人になったか」
美人とは断言できないけど。
「いい子ですよ。愛嬌があって優しくて」
そこで、思いついた。この言葉を投げ掛けると、ハルオさんはどう反応するんだろう。
「そして、才能豊かです」
「才能?」
ハルオさんが、首を傾げた」
「ミュージシャンとしての、才能です。彼女は、花歌ちゃんは、うたいますよ」
(つづく)