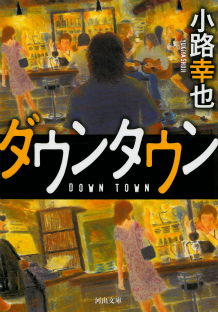花歌は、うたう
『花歌は、うたう』 9
小路幸也(しょうじ ゆきや)
2017.01.24

今藤凌一 十七歳
ガキだよなってつくづく思う。
十七歳なんて、ガキだ。高校生だ。子供だ。誰かを殺したって世間に名前は出ない。何かをしようと思ったって、学生がすることは勉強だって言われる。そんなことはわかってるけど、勉強以外にしたいことはたくさんある。
スポーツはいいよなって思うんだ。
ガキでも、プロになれる。高校生で、もうJリーグに入っているのがいるじゃん。卓球で世界に行ってるのがいる。水泳でオリンピックに行っちゃう子がいる。
そういうのが、羨ましい。
そんなこと言ったら、将棋や囲碁でも未成年でプロになれるだろ、って言われた。俳優として実力も人気もある未成年もいるだろう。
つまり、才能がある奴は何歳だろうとその方向へ突き進んで、大人の世界で勝負できるんだって。それができないで普通に学校に通っている奴は、才能があったとしても今のところそれが発揮されていないんだから、大人しく勉強しとけって。
「だよな」
そうなんだ。
俺には、才能を発揮する舞台がない。
いや、あるにはあるんだ。
ネットって舞台がある。
そこでオレの撮る、創る映像の素晴らしさを世界中に見せつけてもいいんだけど、なんか違うような気がしてるんだ。
そんなんじゃ、フツーだ。
もっとスゴイことが出来そうな気がするんだ。
花歌と一緒なら。
「ね」
花歌が急にカメラ目線になってオレを呼んだ。
「なに」
「ぴぃぶういってさ」
「ぴぃぶうい?」
なに?
「あるじゃん、ぴぃぶうい」
「PVか?」
「そうそれ」
お前は江戸時代の人間か。
「プロモーションビデオだ。昔はMV、ミュージックビデオなんても言った」
「それそれ」
「それがどうした」
花歌がカメラに向かってVサインをする。
「やめろ」
「そのPVも作るんだよね?」
「曲ができあがってからな」
曲が、アレンジされてちゃんと録音されてからじゃないと、どんなイメージで作るかなんて決められない。
「まぁ、これでいこうってなった段階である程度は考えるけどな」
睦美の家のオーディオルーム。すっかりここがオレたちの〈放課後クラブ〉になってしまった。
「そのな?」
「うん」
「どうやって作るのかって、どうやって思いつくの?」
真面目な顔して訊くから、真面目な顔で答えた。
「花歌は、どうやって曲を思いつくか説明できるか?」
言ったら、睦美が笑った。
「そうだよねー」
「そうだよ」
「何がそうだよ」
花歌が唇をとんがらせた。
「説明できないだろ?」
「できるよ」
「じゃあ、どうやって曲を思いつくんだ」
こうね、って花歌はギターの上に肘をついて、何かを考えるように上を向いた。
「どんな曲がいいかなー、って考えると、思いつくんだよ」
「説明になってねぇ」
「なってねぇ」
「えー」
ブーたれる。
「無理なんだよ。思いつくものはしょうがないんだ。最初っから速く走れる奴にどうやったら速く走れるの? って訊くのと同じだ。速く走れるからしょうがないんだよ」
「えー、でも練習したら少しは速く走れるじゃん」
話が違う方向へ行ってる。でもいいか。
「それはあたりまえだ。訓練をすれば何でも磨かれる」
「わたしは訓練なんかしてないよ。曲作るのに」
「してるんだよ」
「してない」
何でそこで強硬に否定するんだ。
「オレはしてるよ」
「何を」
「映画をたくさん観ている。PVもたくさん、アニメもドラマも何でも映像を毎日毎日浴びるように観ている。その他にも、散歩もしてる」
「散歩?」
お、睦美も反応したね。
「散歩が何の訓練になるの?」
「風景を観るんだよ」
風景、って二人が揃って繰り返した。
「お前たちは、ビデオってのはただ撮っているって思ってるかもしれないけど、違うんだぞ」
「何が違うの」
「そこのフレームに何が入っているか、をちゃんとわかっていないとダメなんだ」
「何が入っているか?」
そうだ。
「映画でもPVでもドラマでも何でもいいけど、お前たちはそれを観ているときには映っている俳優とか歌手とかしか見てないだろうけど、違う。そこにはいろんなものが映っている。才能ある映像屋っていうのは、その画面に入るものをちゃんと捉えて計算して入れられる人間なんだ」
「なるほ、ど」
花歌が頷いたけど、全然わかってないと思うぞお前。
「つまり、映画やドラマならセットだ。そのセットにどんなものが映るかってのを、考えなきゃならない。どうしたら、その場面がいちばん美しくなるか、を常にワンカットワンカットで感覚的に捉えられる人間が、素晴らしい映像を作るんだ」
そのためには。
「風景を、切り取れるようにならなきゃならない」
「風景を、切り取る?」
「何でもない、その辺の風景をどういうふうにフレームで切り取れば意図通りの映像になるかってね。たとえば、今このカメラを睦美に渡して、ちょっとこの家の玄関を出たところの風景を撮ってこいって、撮った映像と、オレが撮った映像は、同じ場所を映していても、全然違うように観えるはずだ」
「それが、切り取るってことなんだね」
花歌が言った。
「その通り」
「それって!」
手を上げた。はい、花歌さん。
「おんなじじゃね?」
「なにが」
「作詞と」
「あぁ」
睦美が頷いた。
「そうかもね」
そうか。
同じかもしれないな。
「同じ風景を見ても、それを見た花歌が作る歌詞と、睦美が作る歌詞は違う。そういうことだよ」
「そういうことか」
だから、散歩をするんだ。
「何でもない風景をちゃんと見るん
だ。撮影するんじゃなくて、自分の眼でさ。毎日見る風景だって、切り取り方で全然違って見える。そういうことに気づかないと、いい映像なんて撮れないんだ」
そうかー、って花歌がにっこり笑う。
「リョーチも考えているんだねぇ。さすがだねぇ」
「何だそりゃ」
とにかく。
「オレが作るお前のPVは、お前の歌がすべてなんだ。だからとっととすげぇ歌を作れ、ってもそんな簡単にできたら苦労しないってのはわかってるから」
まぁ、のんびり作れ。
でもな、花歌。
さっさと作らないと、兄貴がハルオさんを見つけちゃうかもしれないぞ。
もしも見つけて、とんでもないことになっていたら、お前の今の世界が壊れちゃうかもしれないぞ。
まぁ、そうなったらそうなったで、また新しいお前の世界が生まれると思うけどさ。
お前は強いから、ゼッタイに何があっても大丈夫だと思うけどさ。
今藤恭一 二十九歳
「うたう?」
ハルオさんは、一瞬無表情になった。じっと俺を見て、たっぷり十秒ぐらい動かなかった。
「うたう、ってのは」
「はい」
「あれか、カラオケとかじゃなくてか」
「違います」
カラオケにはあんまり行かないって聞いてる。
「彼女は、自分の歌を、うたいます。うたおうとしていますよ」
自分の歌、って呟いた。それから、大きく溜息をついて、立ち上がって、部屋をうろうろし始めた。あんまり急に落ち着かなくなったから、立ち上がっていつでも押さえつけれるようにしようかと思ったけど。
以前は、よくあることだってスタッフの人に聞かされた。思い出した。
ハルオさんがうろうろし始めると、その辺にあるものはまったく眼に入らなくなって、テーブルでも椅子でもゴミ箱でも何にでもぶちあたって倒したり自分が転んだりするって。それで大怪我をしたこともあるので、そうなった誰かがすぐに傍にいって付き従うんだって。
そうなったのかと思ったけど、すぐにピタリ、と動きを止めて、また座り込んであぐらをかいた。
少し、様子が変わっていた。
いや、変ったように感じた。
それまでの何のオーラも感じない、ただのその辺のおっさんの雰囲気から何かが変化したように思ったけど、それが何かはわからなかった。
「もう言うな」
「はい?」
ハルオさんが、僕を見た。少し情けない顔をしていた。
「とりあえず、もう言わないでくれ。何もさ。もうすぐ昼だしさ」
昼だけど。
「お前、お昼ご飯は?」
お昼ご飯って。
「まぁ、適当に食べますけど」
そうか、って、ニカッと笑った。
「じゃあ、まずは昼ご飯を一緒に食べよう。その後、オレは買い物に出る」
「買い物」
そうだ、って頷いた。
「醤油が切れそうなんでそれを買いに行く。あと、ヨーグルトとピザ用のチーズな。そして今晩のご飯はオムライスとスープにする予定だから」
オムライスとスープ。
晩ご飯をハルオさんが作っているのか。
誰のために?
「昼ご飯は、何にするんですか?」
「それはもう作ってある」
「作ってある?」
笑って、頷いた。
「朝、お弁当を作るからな。一緒に自分の分も作るんだ。心配するな。いつも多めに作って晩ご飯のおかずにもするからお前の分もある。確か、お前すっげぇ小食だったよな?」
よく覚えてるなそんなこと。
いや、それよりもお弁当を作ってるって。
「誰のお弁当ですか?」
訊いたら、それには素直に頷いた。
「美紀と、茜のだ」
みき、と、あかね。
隣の家には庭を歩いて縁側から入った。
古い家だ。でも、きちんと手入れがされてるって感じだ。外観から日本家屋だと思ったんだけど中はけっこう洋風だった。
これは、ミッドセンチュリーの意匠だ。直線と幾何学模様で構成された部屋。その中にアールが特徴のデザイン家具。木製とプラスチックのバランス、ポップな色使いと落ち着いた木の味わい深い色。
外は完全に日本家屋なのに、中身はアメリカン。でも、うまく調和している。よほどセンスのある建築家じゃないとこういうのは造れないと思う。
ずっと部屋の中を見回していたら、ハルオさんが言った。
「さすがデザイナーだな。興味深いんだろ」
「本当に」
「オレも最初に来たときには、何だこりゃって思ったよ。スゴイだろ?」
「中々です。建てたのはいつぐらいかってわかりますか?」
「何でも築四十年ぐらいって話だぞ」
四十年。すると一九七十年代。それぐらいのときにこんな個人住宅を建てるって。
「お金持ちだったんですか? ここを建てた人は」
ハルオさんがちょっと首を捻った。
「詳しくは聞いていない。でも、そうだったみたいだな」
そういう視点で見始めると、この家はどこもかしこもちゃんとしている。木造建築だろうけど、きっと良い木を、良い材料を使って一流の職人と素晴らしい設計士と感性の豊かなデザイナーらが組んで建てたものだ。そうじゃなきゃこんなふうにはできあがらない。
「三人で、住んでいるんですか。そのみきさん、と、あかねさん」
ハルオさんは指で空に字を書いた。
「美紀は美しい紀元前の紀。茜は茜色。茜はまだ小学校の二年生だ」
二年生か。
「その辺は訊いていいんですか」
肩を竦めて見せた。
「おいおい、話す。まぁ座って休んでいろ。ご飯の支度をするから。テレビでもステレオでも聴いていろ。スゴイだろそのステレオ。そんなのがまだ残ってるなんてな」
「現役ですか」
海外メーカーのものだってことはわかるけど、一体どこの何というものかわからない、ステレオセット。プレーヤーとアンプとスピーカーだけのシンプルな構成。
「もちろん。オレが来てから針だけは替えた。残念ながらオレのLPはないぞ。しかもクラシックがほとんどだ」
「ハルオさん、アナログなんか一枚しか出してないじゃないですか」
「その通りだ。今思えばもう少し出しておくべきだった」
クラシックを聴くことはほとんどない。それでもここに揃っているLPは大事に取ってあることはよくわかる。それに、二百枚はあるだろうか。
ということは、ここの主は何かクラシックに関係した音楽関係者だろうか。それなら、このミッドセンチュリーの意匠もわかる気がする。
居間と続いたキッチンを覗いた。
「手伝わなくていいぞ」
「いえ、ここもちゃんとしてるなって」
「すごいクラシックな調理器具がいっぱいあるんだぞ。残念ながら使えないのでそこの棚にしまいっ放しになってるんだけどな。見てみろ」
木製の棚の扉を開けた。
「わお」
写真に撮って帰りたい。アメリカンなトースターにジューサー、これは何だ、ワッフルメーカーか?
「どんな趣味だったんですかね。ここの主は」
うん、ってハルオさんが苦笑する。
「余程の趣味人だよな」
ハルオさんは、お弁当に作ったというおかずを温め直したりしている。使っているのは現代の電子レンジとかだ。でも、型はかなり古い。
「さぁいいぞ。座れ」
小さなハンバーグや、野菜の細切り炒め、きんぴらごぼうに、マカロニサラダ、それにシュウマイに味噌汁にご飯。その他に冷蔵庫にあったんだろう、漬物に、冷やっこ。
なるほど、お弁当のおかずだ。
「ハルオさんの手作りですか」
「全部だ。冷凍物じゃないぞ」
それは、スゴイ。
「食うぞ」
「いただきます」
手を付けた。ハンバーグは一口で食べられるサイズ。
「あ、美味しいです」
「だろ?」
お世辞抜きで美味しい。子供が喜びそうな味だ。
でも、ハルオさんが料理って。あの、何もしなかった人が。料理どころか寝るときに全裸になって脱いだものはそのままで、朝起きたら奥さんに全部服を用意してもらって着せてもらっていたような男が。
料理なんかまるっきりできなくて、おにぎりを作ったら指の形をつけたような人が。
「こっちで覚えたんですか」
訊いたら、首を横に振った。
「ここに来る前だな」
「来る前」
ということは、失踪してずっとここにいたわけじゃないのか。
「ここには、何年ぐらいですか」
ハルオさんはきんぴらごぼうを食べて、少し考えた。
「二年ぐらいかな」
二年。じゃあ、茜ちゃんという女の子は、ハルオさんの子じゃないのか。いやその前から一緒で皆でここに来たというのも考えられるか。
違うな。
この家は明らかにその美紀さんという女性の家なんだろう。長く住んでいる人の匂いというものはその家に立ちこめるもんだと思う。実際の匂いじゃなくて、感じる何か。それからするとここにずっと住んでいるのは女の人だ。男の人じゃない。
そして、ここに、ハルオさんの匂いはない。
何よりもあのプレハブがハルオさんの部屋なら、ハルオさんはここに来て二年ってことだ。茜ちゃんという子は、ハルオさんの子じゃない。
あぁでも隠し子だったってことも考えられるのか。
訊けないのがもどかしい。ハルオさんがコントロールを失っても困る。ハルオさんが自分で言い出すのを待つしかないんだ。
「恭一、お前仕事は?」
「やってますよ?」
「いや、こっちに来たのも大変だろう。今、ヒマなのか?」
「ヒマじゃないです。区切りがいいところで来ただけで」
ハルオさんは眼をちょっと大きくさせた。
「じゃあ、こっちで仕事するのか」
「できるものは。MacBook Pro持ってきてますから、それでできることはやります」
唇を尖らせた。
「それでも、ずっといるわけじゃないだろ」
もちろんだ。
でも、何て言おうか一瞬迷った。
「納得できたら、帰ります」
そう言うと、ハルオさんは口にご飯を放り込んで、嚙みながらしばらく考えるようにしてから、頷いた。
「そうか」
何かに納得しているみたいだった。
それから、ハルオさんにくっついて歩いた。
買い物に行って、じゃあついでだから重いものを買おうって言って、ハルオさんは米を買ってそれを僕に運ばせた。こんなところに来て力仕事をさせられるとは思ってもみなかった。
このまま美紀さんという女性が帰ってくるまで、あるいは茜ちゃんが学校から戻るまで、この家にいるかどうしようか、それをハルオさんが許してくれるかどうか、どう言おうか悩んだんだけど、一息ついたときに、ハルオさんが言った。
「どっかで、会うか」
「どっか?」
こくん、って頷いた。
「ここじゃなくてどっか、人目につかないところで、二人きりで話せるところで。ついでに酒を飲めるところで」
地元民じゃない僕は、そんなところは一つしか思いつかなかった。
☆
〈犬狼都市〉のロウさんは快くお店を貸してくれたんだ。
どうせそんなに流行っている店でもないし今夜はライブもない。ハルオさんの身体が空くのが九時過ぎだというから、十時から貸し切りにしてくれた。しかも、ロウさんもそれで帰るから好きにしてくれって。
感謝して、何がどうなったかはきちんと後でお知らせしますって約束した。もちろん、ハルオさんのプライベートに関しては話せることと話せないことが出てくるだろうけど、少なくとも、ハルオさんがこのまま博多にいるのか、それとも東京に帰るのか、どんな気持ちでいるのかは教えられると思う。
十時過ぎ。
店に入ってきたハルオさんには、少し〈ハルオ〉の空気が感じられたような気がした。それはどうしてなのかわからないけど。
ドアを開けて入ってきて、ひとつ、頷いた。
「カウンターにします?」
訊いたら、ちょっと見回した。
「いや、テーブルにしよう。ここのマスターは?」
「貸し切りにしてくれました。終わったら、電話してくれって」
そうか、って呟いた。
「ここの名前を言ったときにさ、あぁ、って思ったんだよな。ここのマスターがオレに気づいたなって思っていたから」
そうなのか。
「何を飲みますか? もちろん、店のおごりじゃないんですけど、何を飲んでもいいって言われてます」
「そっか。じゃあ、メーカーズマークをロックで」
「了解です」
カウンターに置いてあったそれを取って、グラスに氷を入れてメーカーズマークを注いだ。
「なんか、お前カウンターが似合ってるな」
「よく言われます。バイトしたせいですかね」
「バイトしてたのか」
「一時期、大学の先輩がやっていたバーで」
なるほど、って笑った。
「似合うよ。似合ってるってことは、適性があるってことだ。今のうちに将来はバーをやることを考えてもいいんじゃないのか」
「嫌いじゃないですしね」
酒はそんなに飲まないんだけど、雰囲気は嫌いじゃない。むしろ、好きだ。グラスを二つ持って、ハルオさんが座ったテーブルに持っていった。
「はい、どうぞ」
「うん」
グラスを掲げるので、合わせた。
「再会に乾杯」
「乾杯」
カチン、と鳴る。一口飲む。
「あ、旨い」
「初めてか? メーカーズマーク」
「初めてです。これ、いいですね」
「そういやぁ、サシで飲むなんて初めてだな」
「そうですね」
あの頃はよく打ち上げに参加させてもらったけど、二人きりで飲んだことなんかなかった。そもそも二人きりになることも滅多になかった。
また一口飲む。
話そうと思えば話題はいろいろあったけど、ハルオさんから話し出すのを待つしかない。だから、静かに待っていた。ハルオさんも、嘗めるようにメーカーズマーク飲みながら、静かにしていた。
「美紀はな」
美紀さん。
「オレを介抱してくれた人だ」
「かいほう? って、看病する方の介抱ですか」
「それだ」
「ってことは、病気にでもなったんですか」
いいや、って恥ずかしそうに笑った。
「食中毒」
食中毒って。
「何食べたんですか」
「いやー、わかんないんだ。確かにここに来てちょっとの間、ホームレスみたいな暮らししていたんだけどな」
「ホームレスですか」
いやいや、って手を振った。
「一応、金はあったよ。あったんだけど、まぁそんな感じになってあそこの家の前で吐きそうになるわ下からも出そうになるわ一歩も動けない状態になっていたら、ちょうど美紀が出てきてさ。トイレを貸してくれてさ」
そんなことが。
どんな美しいもしくは人生の悲哀を感じさせるような出会いがあったのかと思えば。まぁでも見知らぬ中年男に家のトイレを貸せるっていうのは、その美紀さんもかなり親切で度胸のある人だ。
「それから、あの家で寝込んじゃったっていうのが始まりですか」
「そういうことだな。結局三日間ぐらい熱が下がんなくてさ。ずっとあのプレハブで寝てた」
「あのプレハブみたいなところって何なんですか? すごく不釣り合いなんですけど」
「その辺は」
ハルオさんが悲しげな顔をする。
「簡単には言えない。あの家の事情だ」
何かがあったんだろう。あの素晴らしいデザインの家の庭にプレハブみたいなものを建てなきゃならない事情が。
「それから二年ぐらい、ずっとあそこにいるっていうのも、ひょっとしたらあの家の事情みたいなものが絡んでいるんですか」
「察しがいいねお前」
ハルオさんが笑った。
「その通りだ。まぁいちばんの理由は茜がオレに懐いちゃったっていうのもあるんだけど」
ハルオさんは、子供好きな人だ。それは知ってる。それであそこに二年もいるっていうのはいいとして。
「その前は、どこにいたって訊いていいですか。失踪して九年経つんですけど」
七年間はどこで何をやっていたのか。
そもそも。
「どうして、失踪したのかも」
ハルオさんは、俺を見た。
それから、溜息をついた。
「お前は、才能がある。グラフィック・デザインの、デザイナーとしての才能が」
スゴイ才能ではないっていうのは自分でもわかってるけど、多少は持ってるっていう自負はある。
「オレと同じ、モノを作る喜びを知ってる人間だよな」
「そういう表現もできますね」
ハルオさんの瞳が揺れているような気がする。
「だから、話す」
「はい」
「ある日突然、自分の中から何にも出てこなくなったのを想像してくれ」
何にも。
「歌をつくることが、それをうたうことがすべてだった、それしかなかった男が、何にも作れなくなったんだ。メロディが何にも出てこなくなったんだ。スランプとか、悩んでいるとか、そんなレベルじゃない」
睨むように、俺の眼を見つめた。
「一切、消えたんだ。包丁がなきゃ野菜が切れないよな? フライパンがなきゃ炒められないよな? 野菜がなきゃキッチンがなきゃ料理が作れないよな? オレの中にあったはずのキッチンが、道具が、材料が、全部消えた。突然に。そこにあるのはただの空白だった。何にもない、無の世界」
泣きそうになっていた。ハルオさんが。
「どこにも、ないんだ。何も見えないんだ。ギターを弾いても、ピアノを叩いても、その音が入ってこない。暴れ出さない。何にも連れて来ない。感情さえも浮かんでこない。きれいな音、楽しい声、熱いリズム。何にもだ。全てがその何もかも消えた無の世界に吸い込まれていくだけ」
言葉を切って、グラスを呷った。
「想像してくれ。どうなる? お前が、カッコいいポスターを作ろうと思っても、自分のここに」
胸を叩いた。
「ここに」
頭を叩いた。
「真っ白な空間しかなかったら、どうなる?」
想像してみた。
簡単だ。
怖い。叫びたくなる。死にたくなる。
(つづく)