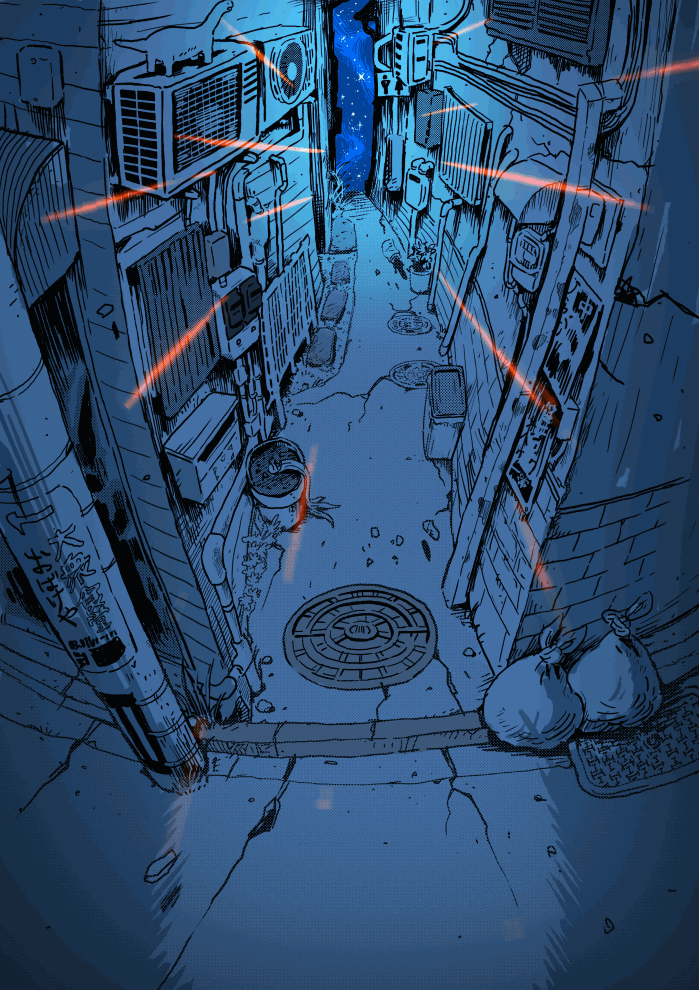単行本 - 日本文学
文芸季評 山本貴光「文態百版」:2018年12月~2019年3月 女の地獄巡り・言語・技術的無意識
山本貴光
2019.04.17
1 評する者が評される
文章を読み始める。書き手の言葉の調子と、読み手の意識の状態とは大きさと回転速度の違う二つの歯車のようだ。はじめはどこで接し合えばよいか分からず、それでも読み進めるうちにやがて眼や意識が文章に慣れて歯車がかみ合いぐんぐん先へ運ばれていくこともあれば、どこまで行ってもちぐはぐでガタガタと軋んだり、空転して滑り続けたりすることもある。同じ人でも、今日は古い本格ミステリにどっぷり没入したい日もあれば、万葉仮名や異言語をゆっくり声に出して読み上げたい日もあるし、はたまた束論や神経科学の教科書を無心に眺めたい日だってある。空腹の度合いや虫の居所もあれば、低気圧の影響や温かい一杯のお茶がもたらす寛いだ気分もある。当然同じものを読んでも感じるところが変わる道理である。
そんなふうに関わる変数が多く、不安定なコンディションで、いったいどうしたら批評などできるのだろうか。とは、この頃、仕事として文芸作品を大量に、オーヴァードース気味に読みながら感じるところである。今日ではなく、昨日あるいは明日この原稿を書いていたら、以下の文章は違うものになっていたかもしれない。日々こちらも変われば世界も変わる。ただ、物質に印刷されたテキストだけは、そのまま固定されている。なんのことはない、昔から賢人が言うように、試されるのは評する側である。
2 観察範囲と方針の変更
さて、本論に入る前に観察範囲について述べよう。この季評を書くにあたって目を通した文芸誌は以下の通り。
・「群像」「新潮」「すばる」「文學界」二〇一九年一月号から四月号
・「三田文學」二〇一九年冬号
以上の都合二〇冊。この間、「たべるのがおそい」(次の第七号で終刊とのこと)と「早稲田文学」は刊行されていないので入っていない。季節ごとに三カ月分のところ、一月号から四月号を対象とするのは編集部から調整のリクエストがあったため。いつもよりさらにたくさんギリギリまで読んでいる。そして紙幅は変わらない。助けて欲しい。
数え方にもよるが、この二〇冊におよそ六三六の文章が掲載されており、そのうち主にここで対象とする詩と小説は一八五作品である。これは連載の各回を一と数えたもので、同一作品の連載をまとめて一とする場合、いくらか少なくなる。観察対象をさらに増やしたいと念じながらそうできていないのは、ただただ時間が足りないためでありこれは遺憾である。特に目下対象としているいわゆる日本の文芸誌と、それ以外の雑誌、あるいは日本以外の文芸誌その他を比べれば、もう少し現代日本の文芸の特徴も見て取りやすくなると睨んでいる。
もう一点、方針の変更について。今回はじめて読む人には関係ないことだが、前回までは対象雑誌に掲載された詩と小説をリストにしてお目にかけていた。どんな作家がどんな作品を発表したかを一覧できれば便利だと考えてのこと。今回からは作品リストを掲載しない。編集部から「リストはなくてもいいのではないか」との提案があり、言われてみればたしかに「このリスト、とっても便利です!」といった声を耳にしたことはついぞない。提案を容れることにした。とはいえ自分のために引き続きデータは記録し続けているので、ご要望があれば別の形でご提供しようと思う。
「文芸的事象クロニクル」(雑誌内・P500)はご覧のように引き続き編纂する所存。これは、この三カ月の間に生じた文芸に関連する出来事を年表として編んでコメントしたものだ。手元でつくっている年表から紙幅にあわせていくつかを選んでお目にかけている。
3 女の地獄巡り
今回読んだ中で群を抜いて圧巻だったのは川上未映子「夏物語」前後編計千枚(「文學界」三月号、四月号)である。現代日本において女性が置かれた状況とその不如意を総ざらいする地獄巡りの書として読んだ。
はじめは作家志望者として現れ、後には作家となる夏目夏子の物語だ。子供のころ父親が行方知れずになり、祖母の家で母と姉とともに育つ。祖母、母は早くに亡くなり二人だけになった姉妹は働く他にない。娘をもうけてやはりシングルマザーとなってスナックで働く姉は豊胸手術に夢を託す。かつて男性の恋人がいたものの、セックスを苦痛に感じることが原因で別れ、以後独りで生きる夏子。家庭、貧困、仕事、美容(誰のための?)、結婚(誰のための?)、セックス(誰のための?)、身体と生理、妊娠と出産、男性、社会のジェンダーバイアスと無理解。すべてが夏子一人の身に起きるわけではないものの、こうした諸々が絡み合って生じる度しがたい状況は、地獄などと言えばかえって事態を見えなくするかもしれない。普段これらの事柄について困難を感じない人間には、ひょっとしたら意識にさえのぼらないかもしれない課題の数々を、この小説のように具体的に書いてこそようやく目に入るようになる。
このように記せばネガティヴで気の重い小説のような印象を持つかもしれないがそうではない。中心にあるのは夏子がそうした状況で、考え、行動し、前に進んでゆく様子だ。彼女は少しずつ、男性とつきあうことなしに子供を産む可能性について試行錯誤してゆく。精子提供の仕組みによる妊娠と出産は、夏子自身に関わることであるのはもちろん、同時にそのような条件で生まれてくる子供自身に関わる。
かつて生殖医療をめぐっては生命倫理の領域で、生まれてくる子供の権利が議論されたのをご記憶の読者もあるだろう。あるいは最近では、デイヴィッド・ベネターの『生まれてこない方が良かった――存在してしまうことの害悪』(小島和男+田村宜義訳、すずさわ書店、二〇一七〔原書は二〇〇六〕)に象徴される反出生主義や、それに関連してインドの男性が自分の同意なしに産んだことで両親を訴えたというニュースも報じられている。この課題の延長線上には二〇一八年に中国の研究者によってゲノム編集を施された赤ちゃんが生まれたという事件も起きている。「夏物語」は半面で女性の置かれた状況を描くと同時に、生殖医療技術がもたらす可能性とそこにある課題を描いた小説でもある。果たして夏子は子供を産み育てるのか、断念するのか、どうするのかは、ぜひ読者自身が確認されたい。
桐野夏生の新連載「燕は戻ってこない」(「すばる」三月号から)は、「男なんか要らない、独りがいい、と思うけど、今の世の中は単身では生活できないほど給料が低い」というリキが、友達のテルとエッグドナー(卵子の提供)のアルバイトに乗り出す話であり、こちらはどうなるのかと続きを待っているところ。
この二つの小説では、いずれも男性がいかに身勝手で粗雑で利己的かを難じるくだりがあり痛快だ。両者を引用してお目にかけたいのだが、ここではTwitterにcdb氏(@ C4Dbeginner)が投稿した一枚の図で代表させたい(これもまた文芸である)。ある夫婦の妻が頭痛で先に休むという状況。それがなにを意味しているのかを、ロックバンド、オアシスのノエル・ギャラガーの文体で翻訳してみせた二コマ漫画だ。もちろん戯画的なパロディではあるが、これがただの冗談でないのは、それこそTwitterやネットのそこかしこで見られる女性蔑視の酷い発言の数々を見ても推察されるだろう。
ママ語翻訳アプリ ノエル・ギャラガーエディション pic.twitter.com/V2SPg6KLvE
— cdb (@C4Dbeginner) February 21, 2019
幸い日本でも好評を博しているチョ・ナムジュ『82年生まれ、キム・ジヨン』(斎藤真理子訳、筑摩書房、二〇一八〔原書は二〇一六〕)とも響き合う、こうした偏った状況を変えることなくしてよりよい未来はない。そしてこれは、文芸の力がものをいう課題でもあるはずだ。
また、こうした文脈に関連して、しばしば脳の性差に関する誤解が流布していることにも触れておこう。かつて極めて少ないサンプルに基づいて言われた「女性の脳のほうが左右の脳をつなぐ脳梁が太い」といった研究が一人歩きして、「だから女性はおしゃべりで感情的なのだ」といった意味づけをされた「神経神話」がいまだにあちこちで目に入る。こうした神話は、科学の装いをとっているだけに厄介だ。ジーナ・リッポンの『ジェンダー化された脳―女性の脳にかんする神話を粉砕する新しい神経科学』(Gina Rippon, The Gendered Brain: The new neuroscience that shatters the myth of the female brain, The Bodley Head, 2019)は、女性を劣った存在と見なし、その延長線上で行われた性差別を助長する脳研究(神経性差別)の歴史を批判的に検討している。社会における女性の地位を公平な状態にいたらせるためにも、無用で有害でさえある神経神話の憑き物落としが必要である。同書が日本語にも訳されて広く読まれることを期待したい。
4 日本語の冒険家・橋本治
橋本治さんが亡くなった。女のモノローグで書かれた一九七七年の小説「桃尻娘」(第二九回小説現代新人賞佳作、一九七八年講談社から刊行)、一九七九年の少女漫画論『花咲く乙女たちのキンピラゴボウ』(北宋社)を皮切りに、四十余年の文業は単著だけを数えても二〇〇冊を超える。いったいなにをどうしたら一人の人間がそれほど多様な人物や出来事を創造し、天地左右を問わぬ対象に関心を持ち、これだけの仕事をこなせるのか(ご本人が語っているように借金返済というご事情はあったにせよ)。著作リストをつくりながら驚くばかりである。
その全てを読んだわけではない。それでも分かることがある。橋本さんは日本語でなにができるか、なにを考えられ、なにを表せるかを多様に試してみせてくれた作家だった。それこそティーンエイジャーの自意識がエネルギーを持てあましてはじけたようなおしゃべりの文体から、無駄をそぎ落として情景を淡々と描き出す端正な語りまで、レーモン・クノーの『文体練習』(朝比奈弘治訳、朝日出版社、一九九六〔原書は一九四七〕)のごとく硬軟を自在に使い分け、一度読んだら忘れがたい「春って曙よ!」から始まる『桃尻語訳 枕草子』(上中下巻、河出書房新社、一九八七―九五)に始まり、本誌で連載が続いていた飄々とした語り口の『落語世界文学全集』(河出書房新社、二〇一八)へと至る翻訳を通じて日本語について探究し、その富を増やし、惜しみなく共有してくれた作家だった。エッセイで発揮された、変である(と見られる)ことを恐れずむしろ楽しみ、「分からない」ことをごまかさずむしろものを観察したり考えたりするための積極的な方法として使ってゆくスタイルに励まされた読者も多いだろう。
私も「この世界には、まだ橋本治さんがいるじゃないか」と心の拠り所にしていた一人である。ご本人はいなくなってしまったが、「橋本さんならこう言うね」と(は、ご託宣としてありがたがるためではなく、彼が常日頃そうしてみせたように、物事を簡単に分かってしまう代わりにああでもないこうでもないと考える視点を増やすために)脳内でシミュレーションできるだけの材料を残していってくださったのは、残された者にとっては幸いなことであった。文芸各誌に追悼文が寄せられており、近く『ユリイカ』(青土社)では追悼特集号を出す予定もある。現代には稀有な日本語による思考と創造の冒険家のご冥福をお祈りしたい。
5 日本語の中で日本語の外に出る
そんなこともあってか、いつも以上に言語や言葉のあり方、その可能性や限界に目を向けさせてくれる作品に惹かれた。これに関して四作を取り上げる。
「新潮」一月号掲載の円城塔「歌束」は、第四三回川端康成文学賞、第三九回日本SF大賞を受賞した『文字渦』(新潮社)に続く文字の遊びである。ここで「遊び」とは、ふざけるという意味もあるが、同時に「こうしてみたらどうかな」と物事の潜在性を試すことでもある。歌を湯に通す遊びの様子を記述する今回の短篇では、『文字渦』に収録されたいくつかの短篇のように技術こそ全面に出てこないものの、ここに描かれている歌の蒐集や分解や重ね合わせや組みたてといった操作は、江戸期以来盛んになった日本語文法の分析や現在のコンピュータにおける自然言語処理に通じていながら、そうしたしかつめらしさを感じさせない飄然としたおかしさの滲む文章で綴られている。後で述べる古川日出男の「焚書都市譚」と続けて読めば、相互の面白さがいっそう際立つだろう。
台湾から日本へやってきた孟月柔(モンユエーロー/もうげつじゅう)と瀬藤絵舞という二人の女性の恋を描く、李琴峰の「セイナイト」(「群像」四月号)では、中国語を母語とする孟月柔が日本語という異言語に抱く感触が捉えられている。「もし人間は言葉というフィルターを通して世界を見ているのなら、知らない言葉がそのまま世界に対する眼差しの死角になるのではないだろうか」という彼女の考えは、母語のなかだけで用が済む場合には、それこそ死角になりやすい発想であろう。当然のことながら、人は普段、自分が知っている言葉しか知らない。母語か異言語かを問わず、自分が知らない言葉を意識できるのは、他人の発言や他人のつくった文章に接するときだ。子供が新たに言葉を学ぶように「これ」や「それ」といった世界のなにかを指し示す指示代名詞から始まって、「ゼロすら存在しない混沌の中からゆっくり世界を作り上げていく」という感覚は、本来であれば母語であっても多種多様な他人たちとそのつど話し合うために必要なものだと思う。
この点で、日本語とドイツ語で創作する多和田葉子と台湾に生まれて日本語で創作する温又柔の対話「「移民」は日本語文学をどう変えるか?」(「文學界」一月号)は興味あるものだった。そこでも指摘されているように、日本語はその歴史を見てもさまざまな時代の中国語やヨーロッパ諸語を中心に文字や語彙を借り受けてできた複合言語である。「現在普及しているいかにも小説的な日本語も、いろんな翻訳の過程を通じてできてきた」ものであり、それだけに「日本語以外の言語に通じている人は、可能性の日本語をつくる上で有利だと思います」(多和田)という指摘は、以前彼女が『エクソフォニー――母語の外へ出る旅』(岩波書店、二〇〇三/岩波現代文庫、二〇一二)で描いてみせた複数の異言語が響き合う状況とともに何度でも確認してよい。詳しくは論じないが円城塔「わたしたちのてばなしたもの」(「群像」二月号)は言語の変容とヴァリエーションを主題にして面白い。
ここまでを読んで、文芸誌全体に眼を通している人なら、次に取り上げる作品の目星がつくかもしれない。「かれ」は高山病に悩まされながら、西の蔵、チベットを目指す。ガイドブックに現れる読めないチベット語を、英訳を頼りに日本語にして理解する。読者はそうした文字を「かれ」とともに眺め、中国語に混ざって蔵語、つまりチベット語が飛び交うなかを戸惑いながら進んでゆく経験を楽しめる。というのはリービ英雄「西の蔵の声」(「群像」二月号)である。
「新潮」三月号と「文學界」二月号に掲載された黒田夏子の四掌編を音読することでも、かたときとはいえ母語が揺さぶられて、異言語のように感じられるに違いない。
考えてみれば、現在私たちが使っている日本語にしても、先に触れたように古くは中国語の語彙を、後にはヨーロッパ諸語からの語彙をそのまま、あるいは翻訳して取り入れて成り立っている。幕末から明治にかけて、二葉亭四迷(ロシア語)、森鷗外(ドイツ語)、夏目漱石(英語)という具合に異言語からの翻訳を通じて日本語の姿が模索され、当初はけったいな日本語に見えたはずのものが、やがて当たり前に感じられるようになっていまに至る。また、しばしば指摘されるように、異言語を学んでこそ、母語の性質もよりよく見えるようになることもある。私たちが使う母語は、異言語と混ざり合い、重なりあい、つながりあっている。そうした機微について翻訳を通じて考えるマシュー・レイノルズの『翻訳――訳すことのストラテジー』(秋草俊一郎訳、白水社、二〇一九〔原書は二〇一六〕)は、文学と言語について考える上でも大いなるヒントをもたらしてくれる。
6 言語と意識の変化
古川日出男の「焚書都市譚」(「すばる」四月号)は、一種の言語SFの様相を呈した実験作だ。そこに描かれる日本では、カタカナが排除されている。東京オリンピック招致を契機に、日本人の英語での意思疎通を促進するための策として、インターネット上からカタカナを排除する「換字システム」が稼働している。ネットを介してやりとりされる日本語にカタカナの文字列が含まれていると、programによって元の原語か対応する英語に自動変換される、いわゆるfilteringの仕組みだ。だから例えば「スマホ」という日本語でのみ有効な語は、smartphoneと変換されるわけである。また、alphabetを流し込みづらい縦書きも廃止され、横書きが基本となっている。この仕組みが実装された後に物心ついた子供たちは、はじめからカタカナなど存在していなかったように育つだろう。そうしたことの成り行きを、断筆した元作家の「私」が公にしない文書に記録として綴ったのが、この「焚書都市譚」である。
ここに書かれている状況は、現在でも技術的に十分実現可能だ。それぞれのカタカナ語に対応する英語のdataさえあれば、ごく簡単に試すこともできる。仮に現在のWorld Wide Webにこのweb filtering softwareが施されたらどうなるか。いまの日本語がどれほど英語由来の語彙を使っているかが浮かび上がり、英語と日本語をごちゃ混ぜにするトニー谷のTony’s Englishやルー大柴のルー語ではないけれど(これはさらに進んで日本語の一部を英語化するわけだが)、pidgin(混合言語状態)あるいはそれを母語とする話者が生まれてやがてcreolized languageと化してゆくかもしれない。古川日出男は、日本語が置かれている状況を悪い冗談のように、律儀に「私は私を紹介しなければならない」と、どこか英語を日本語に直訳した調子で語る「私」を通じて浮かび上がらせてみせる。
時折するする読むことを阻むノイズのような、同じフレーズが別様に反復するようなスクラッチプレイを連想させる文体は、日本語の不如意を語ろうとする状況と相まって効果的だ。「私は、チョークの二人に、意識は、と言うのだった」という具合に、句点が主語、間接目的語、直接目的語、術語の区切り目を英文法のように示すとともに、読み手の意識に強制的にポーズを割り込ませる。「想像する、本が棄てられるところを想像する、だから完全なる廃棄だ」という具合に、一旦「想像する」と短く言いおいてから、補足するように言い直す言葉のリズムは、英語の関係代名詞節を語順に読む経験に近い。語り手が自覚してかしないでか、彼もまたすでにカタカナが廃棄され、英語を原語表記するフィルターの影響で、文法のレヴェルでも英語化しつつある日本語を使っているようなのだ。
こうした状況に身に覚えのある読者もいるだろう。私は、スマートスピーカーに向かって、日本語を、話す、スマートスピーカーの、音声入力アルゴリズムにとって、理解しやすいように、私の日本語を、滑舌よく、語をはっきり区切って、発音する。私は、「Google翻訳」によって、私の日本語を、英語に翻訳する。その場合、私は、英語の文法を、考えながら、日本語の文章を「Google翻訳」に入力する。もう少し身近なところでも、検索エンジンにどんな語を与えれば、目的のサイトにアクセスしやすいかを考えるとき、人はすでに機械に合わせて言葉遣いを変えている。同様に、LINEでのチャットやTwitterでのツイート、Instagramでのタグづけをはじめ、技術環境はそれを日常的に使う人びとの意識状態や言語の使い方にさまざまな影響を及ぼし続けている。言語にかかわる環境とその変化は、文芸にとってまったく他人事ではない。
こんなときの常として、人工知能搭載の文字入力装置(ワーカム)が、入力できる言葉を制限するために、文章を自由につくれない世界で七転八倒する人物を描いた神林長平の『言壺』を思い出す。現に例えばATOK(仮名漢字変換ソフト)の初期設定のままでは「tosatu」が「屠殺」に変換されないように、私たちは使用するソフトウェアによって知らず識らずのうちに語彙を制限されている。
こうしたデジタル技術とそれを動かすアルゴリズム(コンピュータに課題解決手順を示す命令語の組みたて)は、いまや広く社会にも、日常生活にも浸透している。人がウェブでなにを検索し、どのサイトを訪れたかを追跡してデータを蓄積し、それに基づいて表示する広告を決め、場合によってはその広告をきっかけに人が買い物をする、といったように、利用者が意識しづらい形で私たちの意識状態や欲求や行動に影響を与える仕組みも多数稼働している。
デジタル技術の厄介な点は、裏側で動いているアルゴリズムが(プログラムを解析しない限り)直には目に見えないことだ。小説でこうした技術を扱う際、単なる説明セリフで処理する以外に、どのように記述・描写すればよいか、工夫が問われるところである。この点で巧みな日本の作家として藤井太洋と円城塔がいる。藤井は今回の観測範囲に作品こそ見られないが、『ハロー・ワールド』(講談社、二〇一八)のように技術環境と人間の間で生じうる出来事を活写する小説がある。読んで楽しめるのはもちろんのこと、GAFA(Google、Apple、Facebook、Amazon)と呼ばれる巨大企業の動きや日本政府による拙速なネットの海賊版対策(サイトブロッキングの法制化の試み)といった現実の見方にも手がかりを与えてくれるだろう。
7 技術的無意識という課題
このような現在のデジタルメディア環境において、人間とコンピュータのあいだで、あるいはネットワークを介した人間同士、人間と機械のあいだでなにが生じつつあるかという点については、石田英敬が東浩紀を聴き手として行った講義を本にした『新記号論――脳とメディアが出会うとき』(ゲンロン、二〇一九)が示唆に富む。石田の来たるべき「一般文字学」の構想に即して、たくさんの要素が盛り込まれた本だ。
なかでも「技術的無意識」というレジス・ドブレに由来する概念を踏まえた人間観は注目に値する。つまり、映像や録音された音、あるいはコンピュータの画面などの各種技術による表現は、人間が意識で捉えきれない画像や音を知覚にもたらす仕組みである。例えばスマートフォンの画面は一秒に六〇回から一二〇回ほど書き換えられているが、私たちはその書き換えを知覚していない。また、画面に映るものをくまなく意識できているわけでもない。こうしたメディアに関わる技術によって人間の無意識がつくられる状況にあるという見立てである。では、人間とメディア装置のあいだでなにが起きつつあるのか。これを探究するのが『新記号論』という講義の眼目である。
映画がDVDやデジタル装置で観られるようになったとき、いち早くフィルムで観る体験との違いを指摘していた蓮實重彥は「「ポスト」をめぐって」(「新潮」二月号/講演は二〇一八年七月)という講演の冒頭で、プレゼンテーション用アプリケーションソフト「PowerPoint」について「きわめて懐疑的」であると述べ、「あれは、その瞬間に聴衆をふとわかったような気持ちにさせはするものの、じつは見るはしから忘れさせてしまいもする邪悪な装置」と指摘している。これもまた普段人があまり気にせずにいる技術的無意識に関わる観察と直観である。
現代の日本や諸地域における通信技術環境は、いまや生活や社会に不可欠の基盤であり、日々それに接し、使う人間の意識や言語のあり方に影響を与えている。もし現代を描くなら、登場人物が連絡をとりあう小道具という範囲を超えて、これをどう捉えるか、どう距離を取るかについて、それぞれの作家の見識と手腕の見せ所にもなるだろう。もちろん、それが全てではないにしても。
8 放射性物質と生活のあいだで
最後にこれは狭義の文芸作品ではないが、ぜひ触れておきたい本がある。安東量子『海を撃つ―福島・広島・ベラルーシにて』(みすず書房、二〇一九)だ。広島に生まれ、二〇〇二年から福島県東白川郡に、二〇〇四年からいわき市に住む著者が、二〇一一年に起きた東日本大震災と東京電力福島第一原子力発電所(以下、原発)の事故後、今日までの経験を記した本である。
避難を余儀なくされる人びと。拡散された放射性物質がもたらす不安と怒りと困惑。ときとして感情をむき出しにして戦わされる終わりのない論争。被災地の惨状をよそに行われる政治ゲーム。報道の本義を忘れて責任追及に汲々とするメディア。一体誰が被災者たちの声に耳を傾け、その将来を考えているのか。
そうした中で著者はICRP(国際放射線防護委員会)が発行する報告書を読む。そこには、被曝した地域での生活状態の復興について、人びとの望みを知り、放射線量を減らしてゆくための指針が示されている。著者は、一人の市民として、どのように現状を把握し、生活のために人心と土地を回復できるのかという問題に向き合い、有志と活動を始める。放射性物質は目に見えないが、その量は計測すれば認識できる。それは単なる数値ではない。一方では現在の科学的研究によって、人体への影響を心配しなくてよいとされる数値が見積もられている。他方ではそれとは別に人びとが不安を退けて暮らすために望む数値がある。同じ放射線量でも、この二つの数値は意味がちがっているのだ。その計測は物理的・医学的な意味だけでなく、人の暮らしと安心に関わり、それを評価するという意味も帯びるのである。
放射性物質と生活、現在と未来をめぐって、人びとのあいだで感情の波がさまざまに生じ続けている。事故から八年を経た現在、果たしてどこに心の拠り所を見いだせるのか。無理解と忘却に抗ってどのように記憶を残してゆけるのか。本書は、福島の各地、チェルノブイリの原発事故の影響を受けたノルウェーやベラルーシの住人や専門家たちとのさまざまな対話の場を通じて、著者が自ら見て、感じ、考え、行ったことをあくまでも身の丈で綴った稀有な記録である。読者はその軌跡を辿るうちに自分の中にもあるかもしれない困惑と向きあい、考えるべき課題に気づかされるだろう。
そのような分類にいかほどの意味があるかは別として、『海を撃つ』は放射性物質と人間の関係を描いた第一級の文芸作品である。諸言語に訳されて、広く世界で読まれることを希望したい。