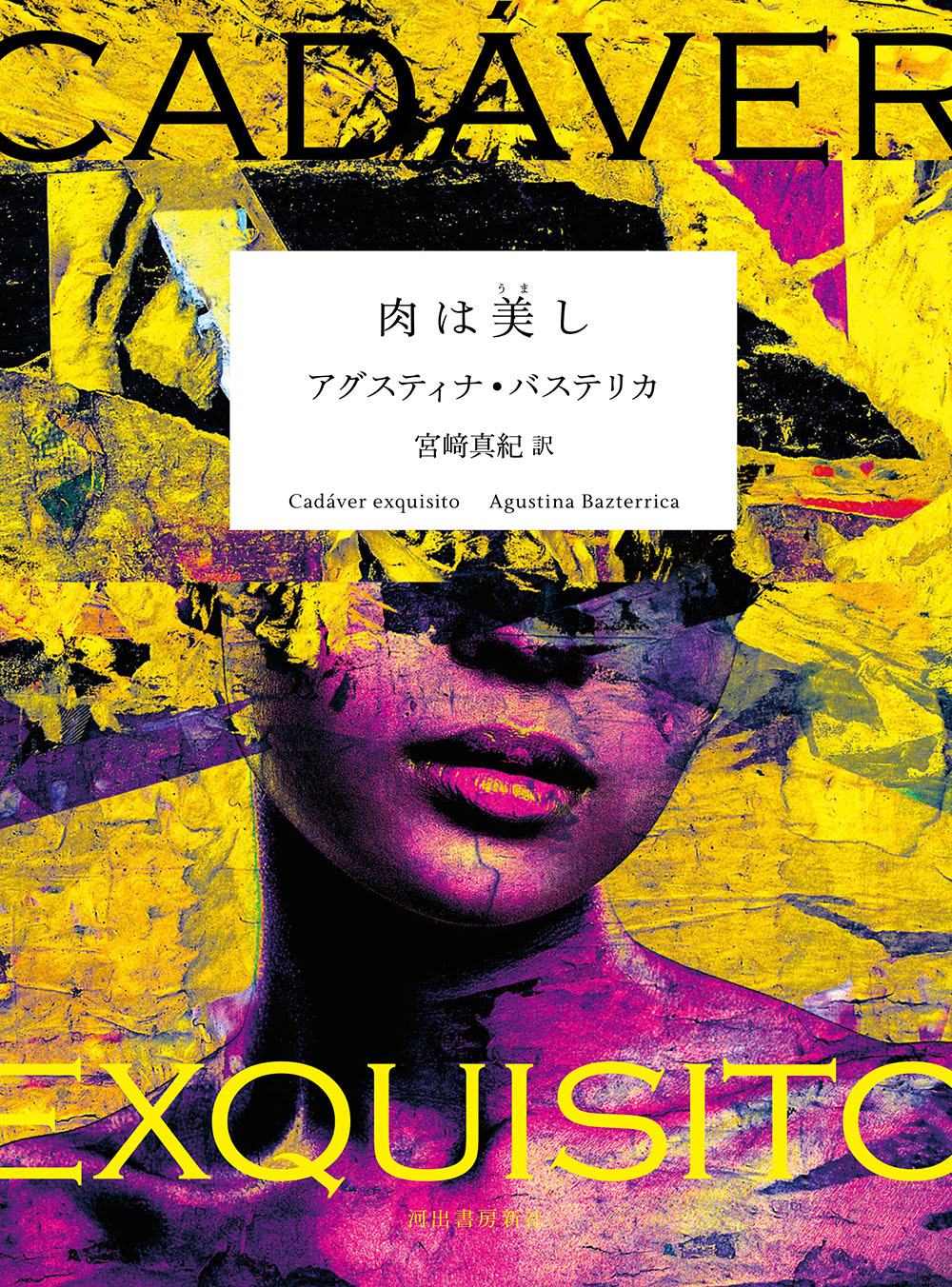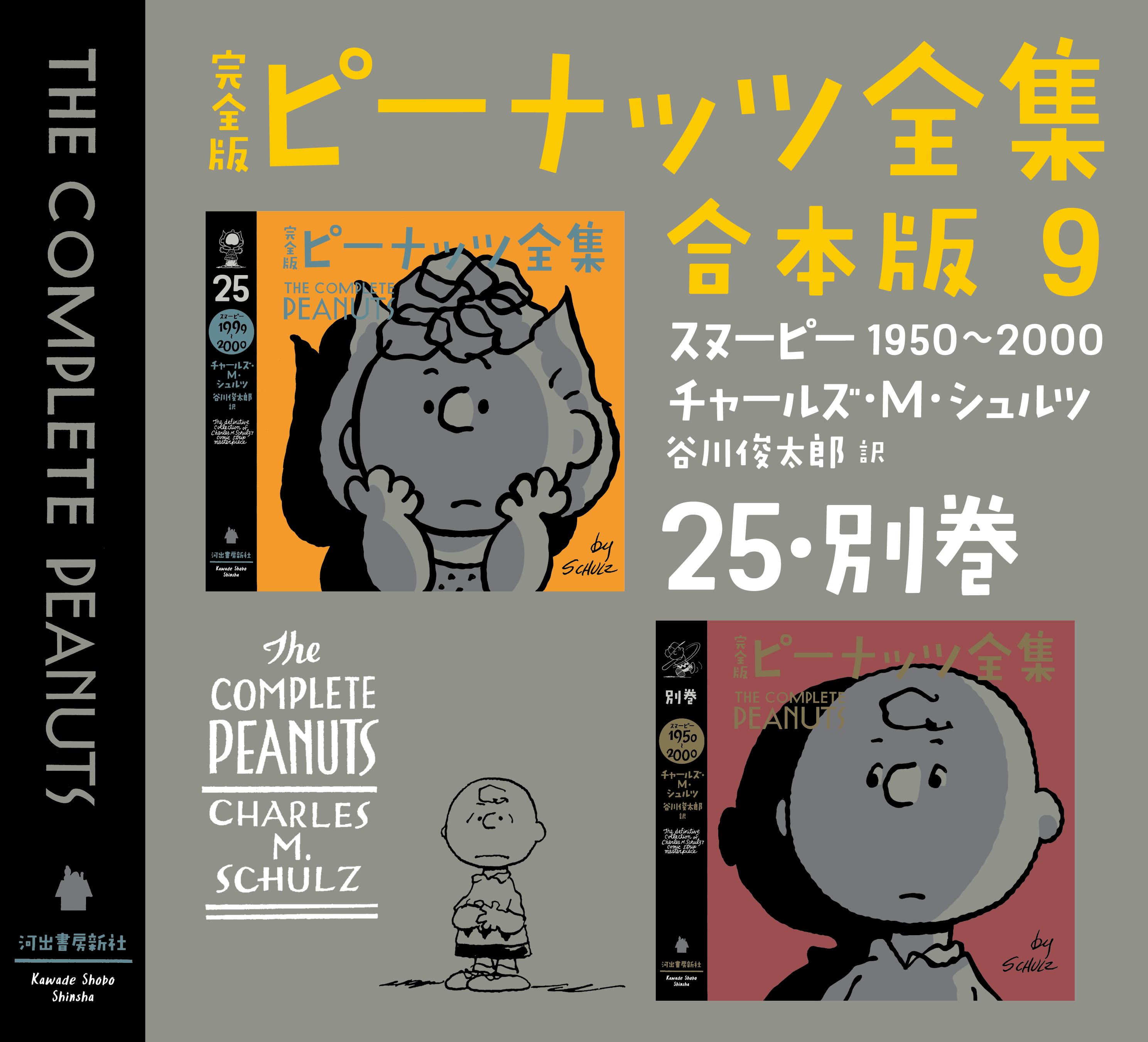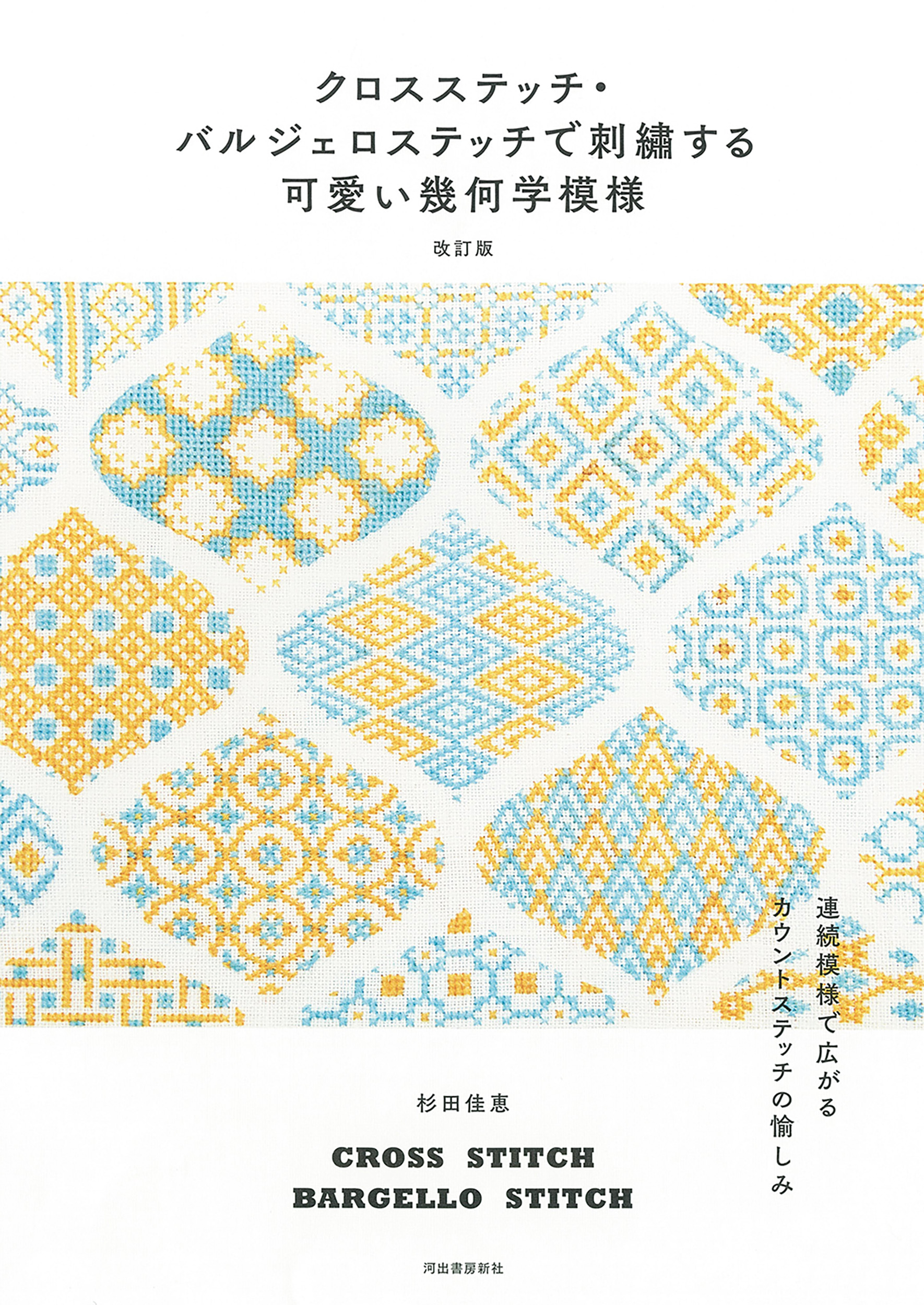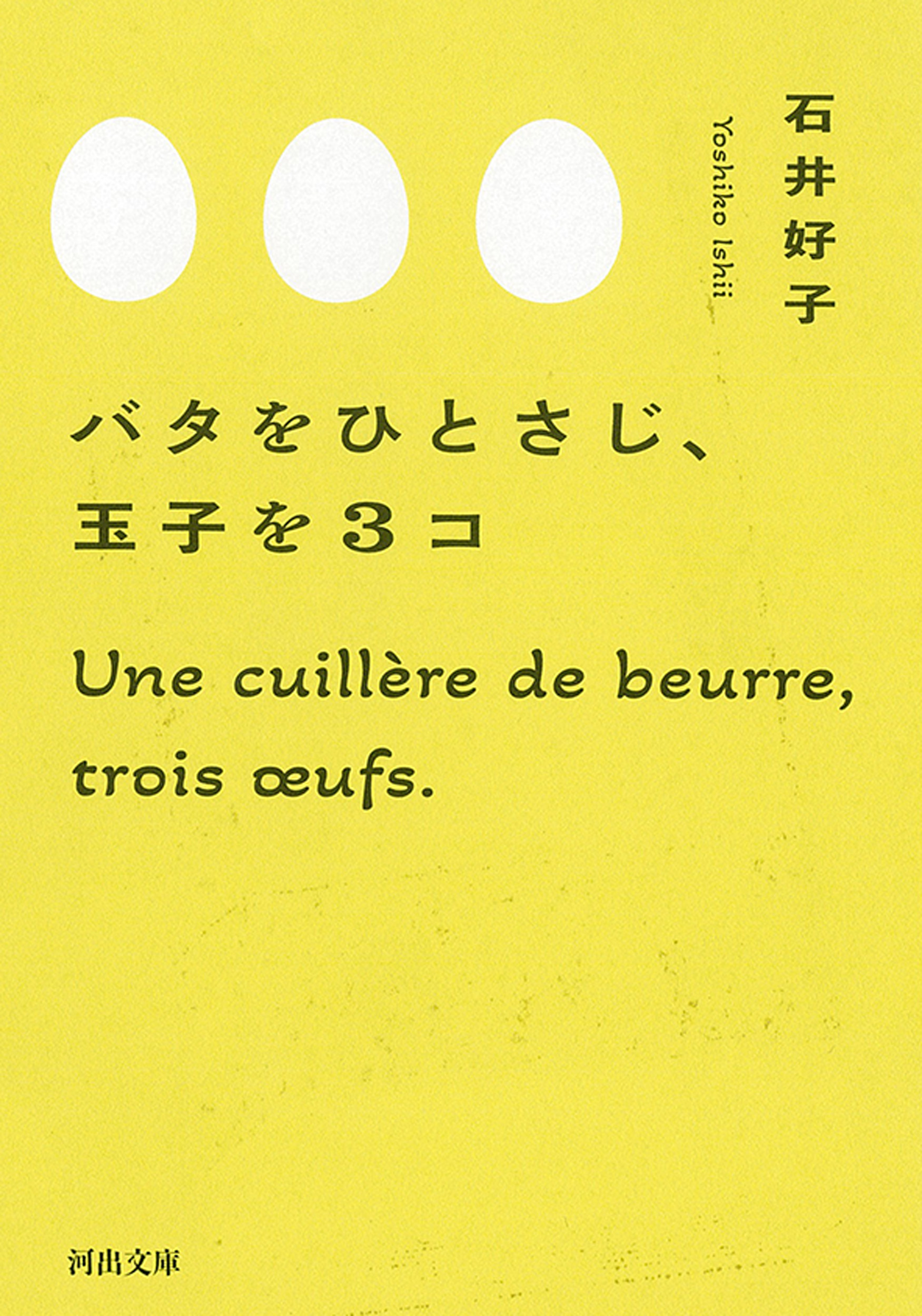単行本 - 外国文学
国際交流基金アジアセンター主催『プラータナー:憑依のポートレート』東京公演 公募書評、選出作決定!
評者・吉田雅史
2019.11.26
この6月に原作小説刊行・また東京芸術劇場で上演され好評を博した『プラータナー:憑依のポートレート』。このたび、AWRDコラボレーション企画ではこの作品がどのような点で「“私たちの物語”であるか?」あるいは「ありえないか?」という問いについて、批評的に応答する劇評・書評の募集が行われました。
結果、美術史、舞台芸術史、社会史、政治史、などの論点から展開される、公演の劇評および原作小説の書評を10名の方にご応募いただきました。文章の独創性、構成力、作品の分析力、批評性を考慮した審査の結果、以下3名の方々のレビューを選出いたしました。
【選出者】(50音順、敬称略)
永谷聡基
朴 建雄
吉田雅史
なお、以下にて学習院女子大学教授である内野儀氏より総評いただきました。
【総評】
今回の長文レビューについては、「『“私たちの物語”であるか?』あるいは『ありえないか?』」という問いに応答するという「お題」がありました。投稿された方々は、それぞれの切り口で、また、それぞれの文体で、真摯にこの「問い」に応答する文章を書かれていました。ただ、「私たちの物語」という文言があったために、どうしても私的な領域へと『プラータナー』体験(小説であれ舞台であれ)を接続させることが必要とされ、その接続の作法といったようなものが、「選考」ないしは「選出」するという困難な作業における、「優劣をつける」というより「差異化をする」という作業へと私たちを導いたという感じでした。その結果として三名の方のレビューが「選出」されました。主として小説について、自己言及(「私」)と批評的分析を手際よくかつシャープに織り込んで記述した吉田さん、学術論文と感想文のあいだにあるはずの、その両者の美点を取り込みつつ、「批評の領野」へと自己の言説を導いた朴さん、リアルタイムでの『プラータナー』体験、つまり、単に、観劇体験だけではなく、「あなたのポストトーク」で起きたことまでを含む複数的な現象を、個性的な文体で活写した永谷さん。この三名の方々のレビューは、優劣がつけがたいというより、異なるタイプの、そしてそれぞれが重要なタイプであるところの、つまり、独自の方法・スタイル・感触を持つレビューだということで、選ばせていただいたと、私は思っています。
内野儀(学習院女子大学教授)
他選出された2作についてはこちらに掲載されています。
国際交流基金アジアセンターの特集記事
ASIA HUNDREDS(アジア・ハンドレッズ)
https://jfac.jp/culture/projects/asia100/
朴 建雄
永谷聡基
◎AWRD(アワード)とは
ロフトワークが運営するコンペティションやハッカソン等を実施するためのオンライン審査プラットフォームです。
https://awrd.com/
◎長文レビュー公募についてはこちら。
https://awrd.com/award/pratthana_review_2
ウティット・ヘーマムーン
『プラータナー:憑依のポートレート』書評
吉田雅史
ぶつかり合う身体と身体。抱き合う身体と身体。交じり合う身体と身体。『プラータナー』はそのような身体の輪郭を描くことに余念がない。この小説を読みながら思わずしてしまったことを白状しよう。何度か、確認した。だが一体、何を?鏡に映る自分の顔、直接目視できる、そして触れることのできる腕や腹、足、そして性器の形は、色は、質感はどのようなものなのかを、確認した。まるでそれが他者のものであるかのように、時間をかけてゆっくり確かめた。そのように自身の身体を他者のそれとして捉え直すことは、おそらく自己の属する社会や政治状況についてそれまでとは別の距離感を持つことにつながる、と考えた。そしてそう考えたそばから、既に何かしらの変化が始まっているような感覚を覚えた。月並みな言い方だが、ウティットの小説はそのようにして、ミクロからマクロにわたる事物へ向ける私たちのまなざしに、ズレをもたらしてくれる。
物語のいたるところで、生身の身体は、動物のように互いに交わり、あるいはひとりで悶々としながら、あらゆる想像力を駆使して快楽へ近づこうとする。ウティットが文字数を尽くして精緻に描くエロティシズムは、小説を読んでいる自分のことを誰かが背後から覗き込んでいないか、思わず振り返ってしまうほどに、官能的で、直接的だ。性と性が交わる。しかしそこで交わるのは、生身の身体だけではない。しばしば身体のメタファーで表象される、タイの国家という身体もまた、性と性の狭間に影を落とす。あるいはその巨大な体躯を割り込ませてくる。ミクロの身体と、マクロの身体。そしてその巨体は、動乱に満ちている。小説の舞台となる一九九二年から二〇一六年までを取っても、数度にわたる大規模デモによる流血事件やクーデターが発生し、人々は不可避的に暴力につながる権力争いに翻弄される。翻弄されつつも、国家の身体を血流のように絶え間なく巡りゆく権力/暴力の波は、いつの間にか人々の日常の風景となる。いつの間にか、それなしではいられなくなる。物語の終盤、ウティットはそのような人々が突き当たっている隘路を言語化する。「すべての人間が、支配と庇護を欲望している」のだと(P.260)。もちろんこれは、人ごとではない。
そのような社会を背景に、主人公のカオシンは、ひとりの若者として歩み始め、美術を学び、それと格闘し、やがて恋愛関係を結ぶ人間たちとの経験から人生の裏側――ダークサイド――を理解するようになる。そこには二十五年間という歳月が横たわっているのだが、ウティットは巧みに語りの時制を転換しながら、過去の記憶と現在進行形の出来事を混交させ、カオシンというひとりの人間の意識の成り立ちと変遷を表現する。一九九二年、十五歳のときにプールサイドで美術教師に「見られる」身体を意識することを契機に、それは始まる。やがてそれは、二人の女性――ラックチャオとファー――、そして二人の男性――ナームとワーリー――と互いに「見る/見られる」「触る/触られる」を繰り返す性愛と恋愛を巡る果てしない葛藤と苦悩となる。そしてめくるめく快楽の曼陀羅が具体的なディティールを伴って、ウティットの精緻な筆致で描きこまれる。それはときに目を背けたくなるほどに直截的だ。なぜ目を背けたくなるのか。その描写が、恐ろしくリアルだからだ。彼らの抱いている欲望の強さと、その淫らさや切実さに、誰しも思い当たる節があるからだ。だから断罪されているような気になる読者もいるだろう。もっと言えば、私たちはウティットが描くような欲望を想像の中だけに保っていたいと願っているのだ。もしその想像の中の欲望が現実に手に入りうるものだと一旦認めてしまえば、私たちはそれを欲することによる苦しみに苛まされるだろう。しかしウティットの描写は、それを実際に見たり触れたりできるほどに肉感的に迫ってくる。その想像が実際に手の届くものとして錯覚してしまいそうだからこそ、私たちはそこから目を背けたくなってしまう。
そしてそのような生身の身体が交差する場所は、もっと巨大な身体の落とす影の下にある。ウティットは、倒れたデモ隊の一員が頭から血を流しながらやがて動かなくなる様子と、アダルトビデオの乱交プレイで性器が勃起しなくなる脇役の様子を、巧みに接続する。両方の描写は、場面転換も改行すらなく、連続して置かれる。読者が気づかない間に、両者はシームレスに混ざり合う。その接続がシームレスなのは、書き方によるというだけではない。ふたつの間をとりなしているものがある。それは、液体だ。血液から、精液へ。『プラータナー』は、液体/体液の物語でもある。カオシンとワーリーの出会いの話のタネとなるビール。常に身体にまとわりつく汗。自殺未遂を起こすファーの手首を流れる血液と混ざり合うシャワーの水流。そしてなによりも、牛乳やココナッツミルクのような、白濁した精液。日本のAVのぶっかけシーンの描写。カオシンとワーリーが意気投合するのは、「自分の精液を嫌う人間には魅力がない」という哲学だ(P.135)。ふたつの身体は、体液を交換し合う。体液を媒介として、ひとつになろうとする。カオシンとラックチャオは、「ひとつの身体」を目指して溶けあおうとする」(P.108)。一方でそれに対置される血液は、「塩辛く生臭く、鉄とトタンの味に満ちて」いる(P.253)。前述の銃撃されたデモ隊員の頭から音もなく広がっていくのも、カオシンの目の前で、ナームの奇妙に歪んだ身体からとめどなく流れ出るのも、血液だ。そう、ウティットは血液に嫌悪のまなざしを向け、精液を賛美するのだ。だが彼らを突き動かしているのは、また別種の体液かもしれない。
そう、彼らを突き動かすメラコリックな欲望には、確かにある体液の痕跡が見え隠れしている。そのような欲望を呼び起こす人の気質と体液の関係については、古代ギリシャの時代から様々な説が唱えられてきた。カオシンや我々の生きる現代にいたるまで、欲望の問題は普遍性を失したことがないのだ。その証拠に、現代の哲学者であるジョルジュ・アガンベンも著書『スタンツェ』の中で、気質と体液の関係性の議論を整理しつつ、さらに考察を進めている。まずアガンベンは、『サレルノ養生集』を引いて、人間の身体には四種類の体液があることを指摘する。血液、胆汁、粘液、そして黒胆汁。このうち、黒胆汁が多い人間は、メランコリー気質であるとされる。メランコリー気質者は、ときに天才的な狂気を宿しているクリエイターとなりうる反面、陰鬱で怠惰なる病に取り憑かれている。そしてその病の中でも最も力をもって宿主を苦しめるのが、肉欲=エロスなのだ。カオシンと関係を持つ四人の男女は、皆一様に、メランコリックな何かに取り憑かれている――憑依されている――ように見える。カオシンはまず口を使って「水分を交換」するが、そのことで粘液と粘液の触れ合いが開始されるや否や、本能=意識の裏側に火が灯る。彼らが身体を使って互いに交換するものこそが、メランコリックな病そのものではないか。フロイトは、たとえばかつて十七世紀に「悪魔憑き=憑依」と呼ばれた現象は、フロイトの時代においては神経症に相当していることを指摘した(注1)。であるならば、「憑依のポートレート」と日本語版のサブタイトルを冠されたこの作品でウティットが蘇らせているのは、神経症にも似た、かつての人類の意識の裏側の営みなのかもしれない。
アガンベンは続いて、同じイタリア出身のルネサンス期の人文学者マルシリオ・フィチーノがメランコリックなエロスについて指摘したことを引用する。そのエロスは「愛をむさぼったために、瞑想の対象としてあるものを抱擁の欲望に変えてしまおうとする者」に見られるというのだ(注2)。ウティットもこのことを痛いほど理解しているようにみえる。年齢を重ねたカオシンは、ワーリーとの間の画家と単なるモデルという関係を崩そうとせず、こう言うからだ。「触れることは、終わりのはじまりだ(中略)ぼくたちは元のような視線で互いを見れなくなってしまう」のだと(P.216)。アガンベンが指摘する通り、想像の中に留めておくべき対象に、触れたい、所有したいという欲望がエロスとなり、メランコリーの源泉となるのだ。
カオシンはローションを使い、ワーリーは自らの口=唾液で自らの性器を愛撫することで、スマホの画面の向こう側の相手とつながろうとする。ひとつに交じり合おうとする。しかしスマホのタッチパネル越しに見つめられる自身の身体は、スマホというデバイスを用いるからこそ余計に、想像によって補填される。それは半分想像の身体だからこそ、手に入れたいという欲望を掻き立てられる。その欲望が際限なく高まっていく様を、ウティットは切り取っているのだ。カオシンはワーリーの若い身体に、十五歳だったかつての自身の身体を幻視する。そして二十五年の歳月は、否応なしに彼の身体に堆積している。かつて見られる側だった彼は、今は見る側に立っている。しかしそれでも、年齢を重ねた彼の身体もまた、スマホのパネル越しに見られている。かつてメルロ=ポンティが指摘したように、「見るもの」は同時に「見られるもの」であり、「触るもの」は同時に「触られるもの」なのだ(注3)。ウティットは肉欲の現象学を駆使して、身体の曖昧な輪郭を描写する。小説の翻訳版の表紙に記されている、ウティット自ら身体をモデルにデザインしたフォント、「プラータナー」のように。
身体は、「見られ」なければならない。ウティットは、自身の身体を、まるで、他人のものであるかのように、「見る」視線を忘れない。あるいは他者の目を通して「見る」ことを忘れない。それは同時に「見られる」ことだからだ。岡田利規による舞台化の手法を見れば、ウティットのこの意識が作品において重要な意味を帯びていることが、より一層明らかになる。彼らは劇中劇を導入し、俳優たちの間にも「見る/見られる」の関係を二重化する。それを「見る」経験を観客にもたらすことで、読書体験における想像上の「見る/見られる」の関係は、より実践的に示される。
国家という身体もまた、「触れる」ことで終わりが始まるのだろうか。一旦実際に触れることができると錯覚してしまうことが。その身体が描く流線形はあくまでも、想像の中に留めておくべきなのか。人類が十九世紀までに目指してきたユートピアや、共産主義の盛衰を見てみれば、確かにそのようにも思える。決して捕まえることのできないユートピア的な国家=理想的な身体を人々が欲望すること自体が、矛盾を孕んでいるのではないか。刻一刻と変化し続ける社会体制は、決して落ち着くことがない。生身の身体が齢を重ねるように。生物の身体は劣化せざるをえないのだろうか。それは老成に向かうのか。若い身体は、果たして健康だといえるのか。ウティットはそのような問いを投げかけるために、生身と国家の身体を混交させているかのようだ。
身体も体液も、少なからず音をたてる。舞台でもそうだったように、それらの音は小説中に満ち溢れている。それから、それらの音の背後でたゆたうサウンドトラックたる楽曲群。たとえば、物語の中盤でカオシンが美術教師を訪ねると、彼がピンク・フロイドの『狂気』を聞いている場面が描かれている。教師はめくるめく音の響きに酔いしれている。なぜならそれは、カセットテープからCDへの音楽メディアの移行によって、16bit 44.1kHzが可能にする、よりリアルな「音の位相、重厚感、音質」を伴った音楽の聴取体験だからだ(P.45)。しかしなぜ『狂気』なのか。このアルバムの原題は『The Dark Side of the Moon』だ。月の裏側。ダークサイド。それは、人間の狂気が眠っている、無意識の領域でもある。同じくCD発明の恩恵を受けたアルバムとしてウティットが触れているエリック・クラプトンの『アンプラグド』は、この物語中リアルタイムの一九九二年にリリースされている。しかし『狂気』は一九七三年のリリースだ。この年には、学生によるクーデターが起こり、軍隊が出動した。なかでも一〇月一四日は「血の日曜日事件」として記憶されている。狂気に彩られたこの事件は結果的にタイの民主化を進展させたが、その代償に多数のデモ学生の犠牲者を出した。『狂気』の発売後、約半年後の出来事だった。
カオシンが美術教師を訪ねるのは、ちょうど曲がアルバム三曲目の「走り回って」から四曲目の「タイム」に変わる場面だ。「走り回って」では歩き回る足音が、「タイム」では時間を刻む秒針の音が、音の聴取空間を自由に動き回る。全てがアナログの時代、それらは手作業のテープ編集による試みだ。「タイム」で歌われるのは、時間が教えてくれる経験と、老いへの恐怖だ。二〇一六年にスマホ越しに相手を/相手から「見る/見られる」カオシンとワーリーの身体の描写の対比が時間の残酷さを伝える。平べったく清潔なワーリーの腹と、カオシンの腹回りを包む脂肪の塊、そしてそこに刻まれる皺。それは時間とともに刻まれる。このアルバムは、全体がテンポ六〇かあるいは一二〇という、心音に速度に近い拍子が刻まれている。それは小説の中で何度か現れる、「ドン」という音に向けて、刻まれていく。それは命が失われる際の、最も切実で、重たい響きだ。彼らがたてるこの音から、私たちは目を背けることができない。パスカル・キニャールが言ったように、鼓膜には、まぶたがない(注4)。
ロックの歴史の中で史上三番目のセールスを記録し、全世界で五千万枚以上売れた『狂気』のラストを飾る「狂気日食」は、次のような歌詞で締め括られる。「あらゆるものが太陽の下で調和している/しかし太陽は月に侵食されていくのだ」(注5)。これは、冒頭で触れたウティットの「すべての人間が支配と庇護を欲望している」というフレーズと相似形を成しているようだ(P.260)。
ここでの太陽と月の関係は、タイという国家とクーデターの関係に似ていることは、言うまでもない。であるならば、マクロの身体とミクロの身体をつなぐ体液が、権力/暴力なのだろうか。体液は、擬似的に別々の身体と身体をひとつに混ざり合わせてくれた。しかしそれは錯覚だ。性交後の身体は、必ずひとりに戻っていく。デモの集団から帰ってひとりで部屋に座る。
しかしある階級を共にする集団や共同体から本当に解放される瞬間のひとつこそが、性愛に没頭する時間なのだ。巨大な身体から切り離されて、ひとつになることを欲しつつも、同時に、体液を介して別の身体とひとつになろうとすること。ウティットはこの物語で、そのようなアンビバレントな欲望を描くことに成功している。「ひとり」で読む小説というメディアと、岡田による「みな」で見る/見られる舞台が同時多発的に、読者/観客にそのような欲望を感染させたことこそが、その証左に他ならない。
(注1)ジークムント・フロイト『フロイト全集<18>』岩波書店、2007年より「十七世紀のある悪魔神経症」
(注2)ジョルジュ・アガンベン『スタンツェ』筑摩書房、2008年
(注3)モーリス・メルロ=ポンティ『眼と精神』みすず書房、1966年
(注4)パルカル・キニャール『音楽の憎しみ』水声社、2019年
(注5)円堂都司昭『意味も知らずにプログレを語るなかれ』リットーミュージック、2019年