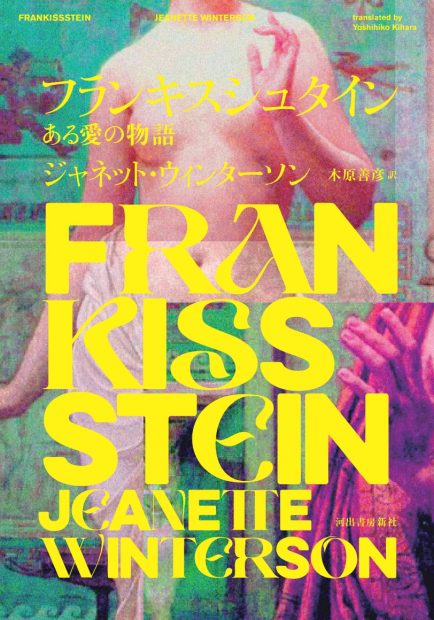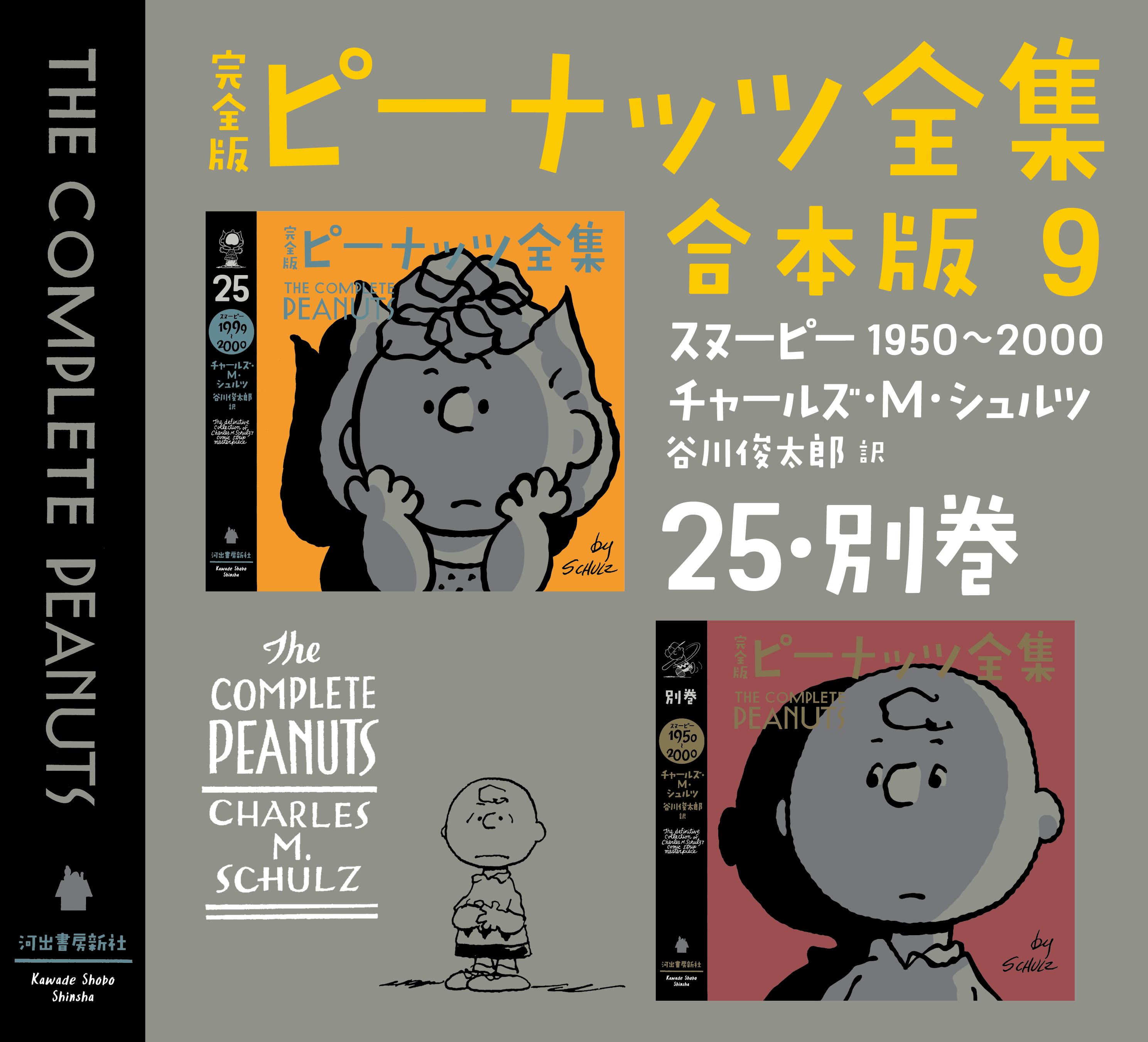単行本 - 外国文学
ジャネット・ウィンターソン待望の最新作がついに刊行!──「訳者あとがき」公開
木原善彦
2022.08.05
『オレンジだけが果物じゃない』で彗星のごとくデビューし、話題作を発表し続けているイギリス文学の代表的作家のひとり、ジャネット・ウィンターソン。本書は、フランケンシュタインの怪物や、人体冷凍保存施設、セックス・ボット、トランス・ヒューマニズム、人工知能、人工生命をめぐる「ある愛の話」を描いた、人類へのラブレターのような最新作です。本書の刊行にあわせ、訳者の木原善彦さんの「訳者あとがき」を公開します。
訳者あとがき
近年、人工知能とそこから派生する問題をめぐる優れた小説が次々に刊行されて、いずれも大きな話題になった。日本の平野啓一郎は、亡き母のヴァーチャル・フィギュア(VF)を作って生前のその本心を知ろうとする小説『本心』を2019年から新聞に連載した(単行本刊行は2021年)。英国文壇の大御所イアン・マキューアンは2019年に発表した『恋するアダム』(日本語訳は2021年刊)でアンドロイドをまじえた三角関係のようなものを描き、カズオ・イシグロはノーベル文学賞受賞後の第一作として2021年に刊行した『クララとお日さま』で人工親友(AF)と少女との友情を描いた。
そうした中2019年、イギリスの書評でマキューアンの『恋するアダム』と並んでしばしば論じられ、高く評価されていたのが、他でもない本書、ジャネット・ウィンターソンの『フランキスシュタイン』(Jeanette Winterson, Frankissstein [Vintage, 2019])である。この野心的な作品は同年のブッカー賞の候補にもなった。作品が取り上げているテーマは超人類(トランス・ヒューマン)、トランスジェンダー、AI、人工生命、セックスボットなど多岐にわたり、書き方も超越(トランス)文学的(たとえばデイヴィッド・ミッチェル『クラウド・アトラス』やハリ・クンズル『民のいない神』のように複数の場所や時間を往還する構成のことをいう)に時空を超えるスタイルになっている。先ほど挙げた人工知能関連作品はそれぞれに作家の個性が反映された興味深い内容だが、本書の濃厚な素材の中には笑いの要素も盛り込まれ、そこにもウィンターソンらしさが感じられる。
タイトルの『フランキスシュタイン』(以下の数段落では『フランキス』と略す)はもちろん、1818年に出版された『フランケンシュタイン』(同様に『フランケン』と略す)をもじっている。カタカナばかりが続くのでやや見にくい(読みにくい)が、途中に「キス」が入っているのがポイントだ。英語の原題でも見にくいのは同様なので、原著表紙ではFRAN/KISS/STEIN と改行を入れたり、KISS の部分だけ文字の色を変えたりする工夫が施されている。
『フランケン』はよく知られているように、一人の研究者が死体のパーツを材料にして超人的な生命を創造する話だ。『フランキス』内には『フランケン』からの抜粋が多く埋め込まれていて、その構成自体も「死体のパーツを材料にして超人的な生命を創造する」モチーフの反復になっている。パッチワークにも似た本書の構造は時に非常に手が込んでいる。本書69頁冒頭の「人類は過剰な現実に耐えられない」という言葉などは20世紀のT・S・エリオットの詩に出てくるのとほぼ同じ言い回しを19世紀の人物が口に出しているわけで、作者はところどころにこうした時代錯誤的なお遊びを紛れ込ませている。
なお、『フランケン』を下敷きにしながら『フランキス』を読む際に頭の隅に置いておいていただきたいことが三点ある。一つは、ヴィクター・フランケンシュタインというのは科学者の名前であって、『フランケン』中で怪物には名前が与えられていないということだ(以下、『フランキス』で重要になる人物名は初出で太字にする)。これは〝名付け〟を一つのテーマとする本書との関係で重要になってくる。第二に、『フランケン』において問題の生命体が「怪物(モンスター)」と呼ばれるのは発話者の感情が極端に高ぶった場面が大半で、それ以外の場面ではより中立的に「存在(ビーイング)」「被造物(クリーチャー)」と呼ばれていることも重要だ。それに関連して、本書に出てくる存在(ビーイング)の一人称は「私」と訳した。『フランケン』の既訳はほとんどがそれを「俺」と訳しているが、『2001年宇宙の旅』に登場する人工知能の一人称が「私」なら、やはりこの存在(ビーイング)も自らを「俺」ではなく「私」と呼ぶ可能性が高い(無論、今までそれが「俺」と訳されてきたさまざまな理由も理解できるけれども)。そして三つ目は、『フランケン』という小説の実質的な語り手は怪物を作ったフランケンシュタイン博士ではなく、彼から話を聞いた海洋冒険家ウォルトンだということ。つまり『フランキス』の語りがやや入り組んでいるのは、『フランケン』の語りの変奏でもあるということだ。
さて、『フランケン』という作品が誕生した経緯については本書の中でも詳しく語られているが、ここで大事な歴史的事実を整理しておこう。『フランケン』を書いたのはメアリー・シェリー(1797 – 1851)という女性だ。彼女の父は無政府主義者のウィリアム・ゴドウィン、母は先駆的な女権論者のメアリー・ウルストンクラフト。母は娘を産んだ直後に亡くなり、父は別の女性と再婚し、その連れ子がクレア・クレアモント(1798 – 1879)である。したがってクレアはメアリー・シェリーの継妹だが、二人の間に血縁はない。メアリー・シェリーは1814年に16歳で、(妻子のある)詩人パーシー・ビッシュ・シェリー(1792 – 1822)と駆け落ちをし、ヨーロッパ大陸に渡る。その際、クレアも付いてくる。そして1816年、スキャンダルを逃れてスイスのレマン湖畔に暮らしていたロマン派の大詩人バイロン (1788 – 1824)とその主治医ジョン・ポリドリ(1795 – 1821)に先の三人が合流し、バイロンの提案で五人のそれぞれが怪奇譚を創作し、互いに披露することになる。これが俗に言う「ディオダティ荘の怪奇談義」だ。そこでの話をきっかけとして後に、ポリドリが吸血鬼小説の元祖となる『吸血鬼』を書き、メアリー・シェリーが『フランケン』を書くことになる。
『フランキス』は200年前にディオダティ荘で交わされたであろう会話を再現するところから始まる。そしていきなり現代の世界に場面が変わると、そこには200年前の世界と共鳴するような五人の人物がいる。本書は大雑把に言うと、先に述べた19世紀のメアリー・シェリーをめぐる伝記的物語と、それを反復・変奏するかのような現代の物語を交互に語り進めるものとなっている。現代の方の物語に登場するのは、謎めいた面を持つ人気AI研究者のヴィクター・スタイン、医師のライ・シェリー、セックスボットを販売するロン・ロード、雑誌記者のポリー・D、敬虔なクリスチャンのクレア。誰が誰に対応しているか、ざっとお分かりいただけるだろうか。
こうして並べてみると、現代においてパーシー・ビッシュ・シェリーに対応する人物がいない。その代わりに、元の小説の登場人物(ヴィクター・フランケンシュタイン)に似た名前の男(ヴィクター・スタイン)がいる。つまりここでは、現実と虚構の間にあるはずの壁が故意に破られている。そして19世紀の物語の方でも、話が展開するにつれて虚構の人物が現実のレベルに侵入し始める……。現代の物語の方は、この小説の副題にある通りに「ある愛の物語」へと収束していくのだが、それは誰と誰の愛の物語なのか……。この小説は多面的で多様な解釈を許すので、これ以上、読者を誘導するような仕方であらすじを書くのは控えるが、読者を不要に宙吊りにするのも望ましくないので、アルコー延命財団のCEOであるマックス・モア、数学者のエイダ・ラブレース、同じく数学者のI・J・グッドなどが実在人物であることだけはここに記しておきたい。
ジャネット・ウィンターソンは日本でも人気の高い作家なのでご存じの読者も多いと思うが、最後に彼女の小説が日本語に訳されてからかなり時間があいているので、ここで簡単に経歴や作風をおさらいしておこう。
ウィンターソンは1959年にイギリスのマンチェスターに生まれ、熱烈な福音伝道主義のクリスチャンの家庭に養女として迎えられ、伝道師となるべく育てられたが、10代で同じ教会に通う女性と恋に落ち、それが周囲の猛反対に遭ったことで信仰を失って家を出た。そしてアイスクリームの移動販売員、葬儀屋の遺体化粧係、精神科の病院の雑用係などの職を経た後、オクスフォード大学で英文学を学んだ。1985年に発表した半自伝的な小説『オレンジだけが果物じゃない』(邦訳は岸本佐知子訳、白水Uブックス)がデビュー作部門でウィットブレッド賞(現在のコスタ賞)を受賞し、彼女は鮮烈なインパクトとともに文壇に登場した。以後も話題作を次々に発表し続けている。日本語に翻訳されたもの(絵本や子供向けの本もあるがここでは省き、版元が移ったものは新しい方のみを記す)を原著刊行順に並べると、1987年刊の『ヴェネツィア幻視行』(藤井かよ訳、早川書房)、1989年の『さくらんぼの性は』(岸本佐知子訳、白水Uブックス)、1992年の『恋をする躰』(野中柊訳、講談社)、2000年の『パワー・ブック』(平林美都子訳、英宝社)、2004年の『灯台守の話』(岸本佐知子訳、白水Uブックス)、2005年の『永遠を背負う男』(小川高義訳、角川書店)などがある。ご覧の通り『フランキスシュタイン』は彼女の小説としては久しぶりの翻訳となる。
『恋をする躰』邦訳あとがきにある野中柊さんの言葉を借りるなら、ウィンターソンは「過去と未来、現実と幻想、歴史と寓話、神話を自由に駆使し、筋書きのない物語を想像力によって導くという小説作法」を使う作家だ。とはいえ、一冊ごとに新しいことに挑戦するのでスタイルにもバリエーションがあり、読み心地もかなり違う。思弁的小説(スペキュレイティブ・フィクション)と評されることも多い『フランキスシュタイン』もこれまでの作品とは異なった道具立てが用いられているが、いわく言いがたいウィンターソンらしさ(一言で言うなら〝愉快〟)は健在で、さらにまた新たな切れ味も加わっているので、きっとこれまでの作品の愛読者にも楽しんでいただけるのではないかと思う。