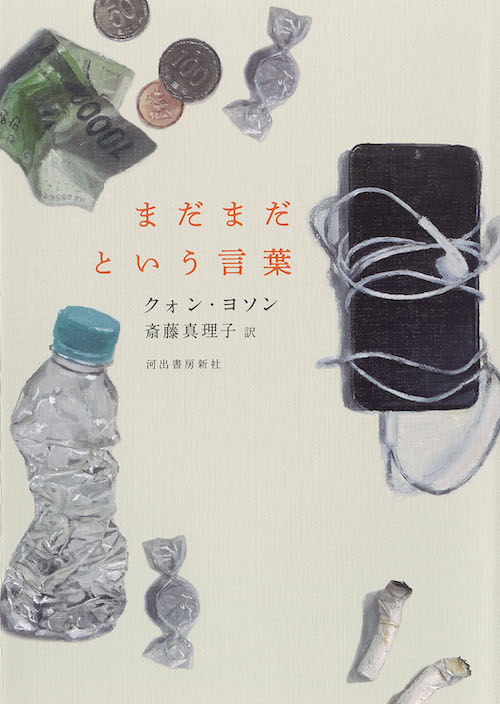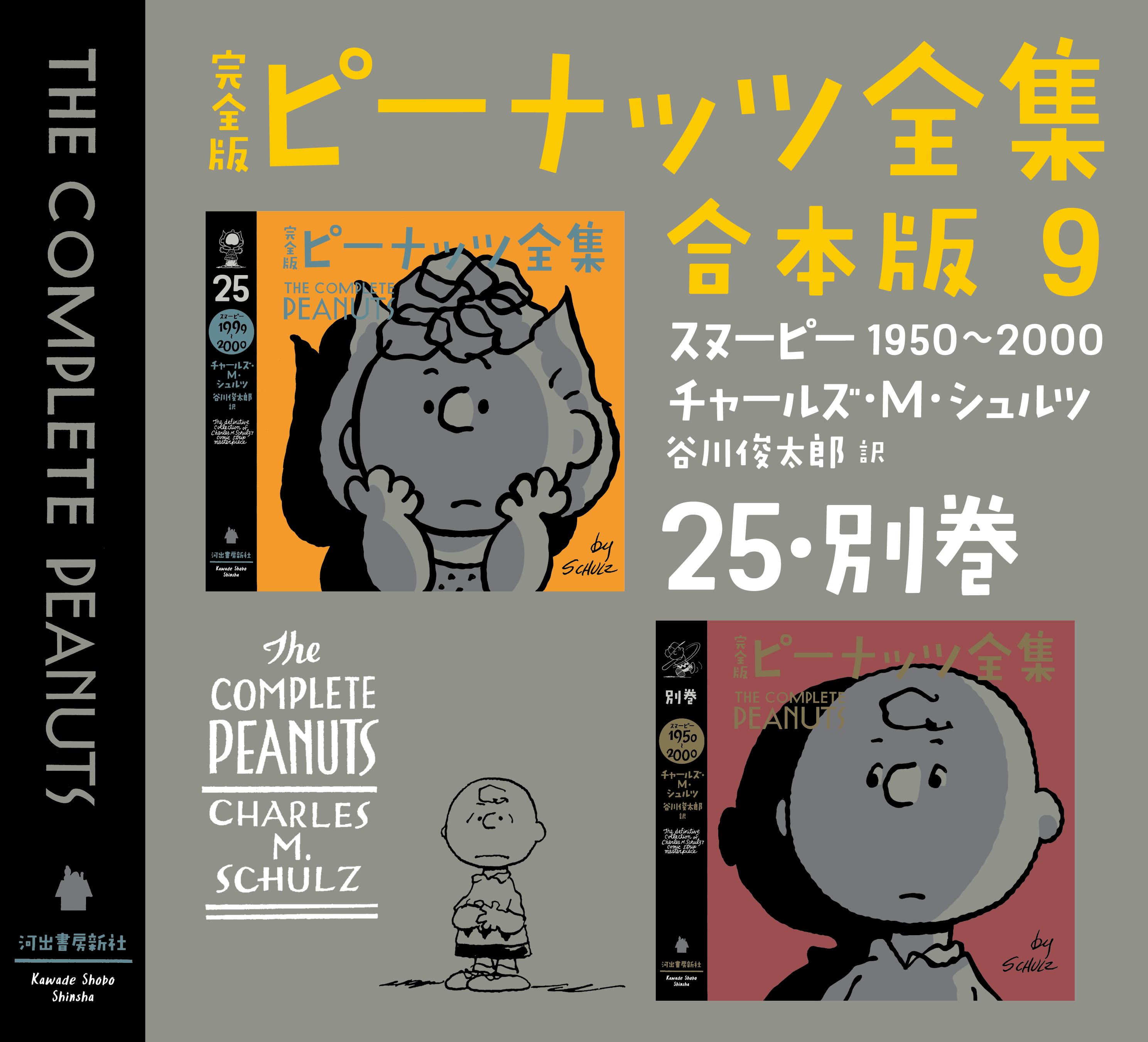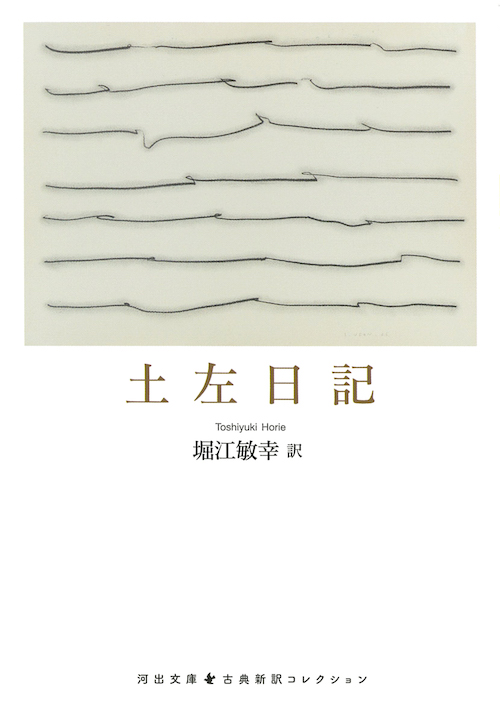単行本 - 外国文学
心の地下の扉が、その衝撃で開いてしまいそうだ──クォン・ヨソン『まだまだという言葉』書評│評・頭木弘樹
頭木弘樹
2021.12.02
ここにいない人たちの大きさ
車にはねられて入院している人が「すごく痛かった」と体験を語ったとき、お見舞いの人がどんなに無神経だったとしても、「私もむこうずねをテーブルにぶつけて痛かったことがあるから、わかる」などと返事することはまずない。痛みの度合がはるかにちがうだろうくらいは誰でもわかる。
しかし、心のことになると、人間関係で悩んで自殺未遂をして入院している人に、「私もよく人間関係で悩むから、わかる」などと返事をする人は、じつはけっこういる。
他人の身体の痛みも本当には理解できないが、心の痛みとなると、なおさらだ。理解できていないことすら、理解できていない。
そのことを、このクォン・ヨソンの『まだまだという言葉』という短編集の「爪」という作品を読んだとき、あらためて痛感した。
この短編には、経済的に追い詰められた二十歳の女性が出てくる。事情にちがいもあるが、日本でも若者の貧困化がよく話題になる。そういう記事を何度も目にしたことがある。読んで、ある程度、わかった気になっていた。私も二十歳で難病になって、ずっと働けず無職で、お金にも苦労した。病気ではなく、若くて元気なのだから、お金の苦労だけなら、まだましではないかなどと思っていた。
しかし、「爪」を読み始めて、どんどん引き込まれていった。はじめてそういう若者の内面にふれた気がした。若者の貧困化の記事でも、当事者がかなり詳しく語っているものがあった。しかし、やはり口にできない思いがある。また、日々それを体験し続けないとわからないことがある。小説は、そういう口にできない思いも描いてくれる。短編であっても、その中で長い日々を登場人物と共有できる。それによって、ようやく少しだけ実感できることがある。何もわかっていなかったことがわかった。
二〇一九年に『絶望書店──夢をあきらめた9人が出会った物語』(河出書房新社)というアンソロジーを編んだとき、翻訳家の斎藤真理子さんにも相談して、いくつか推薦していただいた中に、クォン・ヨソンの「アジの味」があった。当時は未訳で、クォン・ヨソンという作家自体、私は初めてだったのだが、「アジの味」にすっかり魅了された。
そのアンソロジーがきっかけとなって、「アジの味」を含む短編集『まだまだという言葉』が出版されたのは、とても嬉しい。アンソロジーの役目のひとつを果たせた思いだ。
他の七つの短編は今回はじめて読んだが、どれも素晴らしい。ずんずんと重く心に響いてくる。心の地下の扉が、その衝撃で開いてしまいそうだ。
「灰」という短編には、カフカの『変身』とゼーバルトの『土星の環』が出てくる。前者は虫になってしまう話だし、後者は入院するところから始まる。しかし、それらの作品を読むことが、病んでいる主人公を支える。この『まだまだという言葉』も、きっと多くの人を支えるだろう。つらい日々に、この本を読むことで、耐えられるかもしれない。
そして、この短編集に入っているすべての作品を通じて感じたのは、ここにはいない人の存在が、じつはとても大きいということだ。もう亡くなった人、去って行った人、逃げ出した人、この場にいない人……。私たちは、自分だけ、身のまわりにいる人たちとだけ生きているわけではない。いない人たちの存在は、ときには、いる人たちより大きい。そのことにも、あらためて、はっとさせられた。