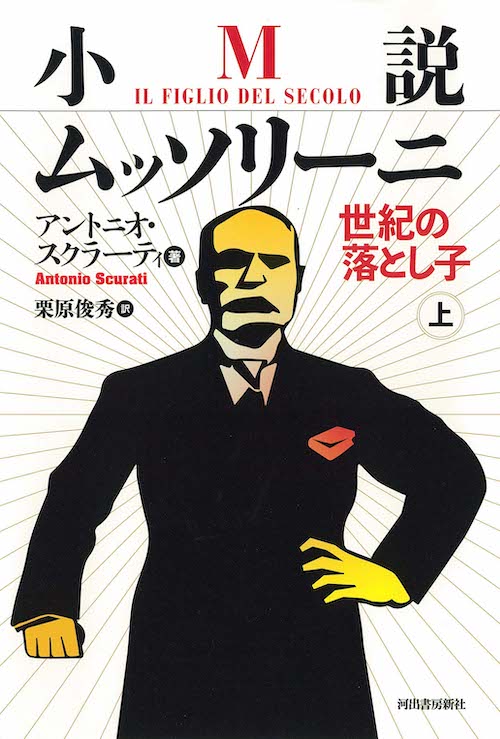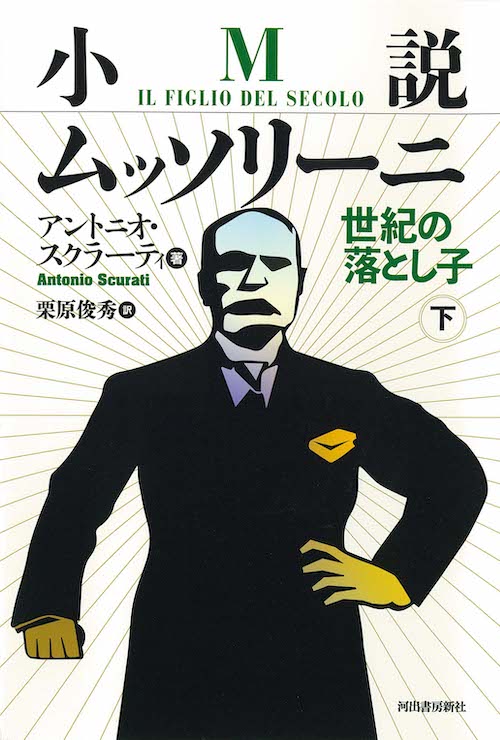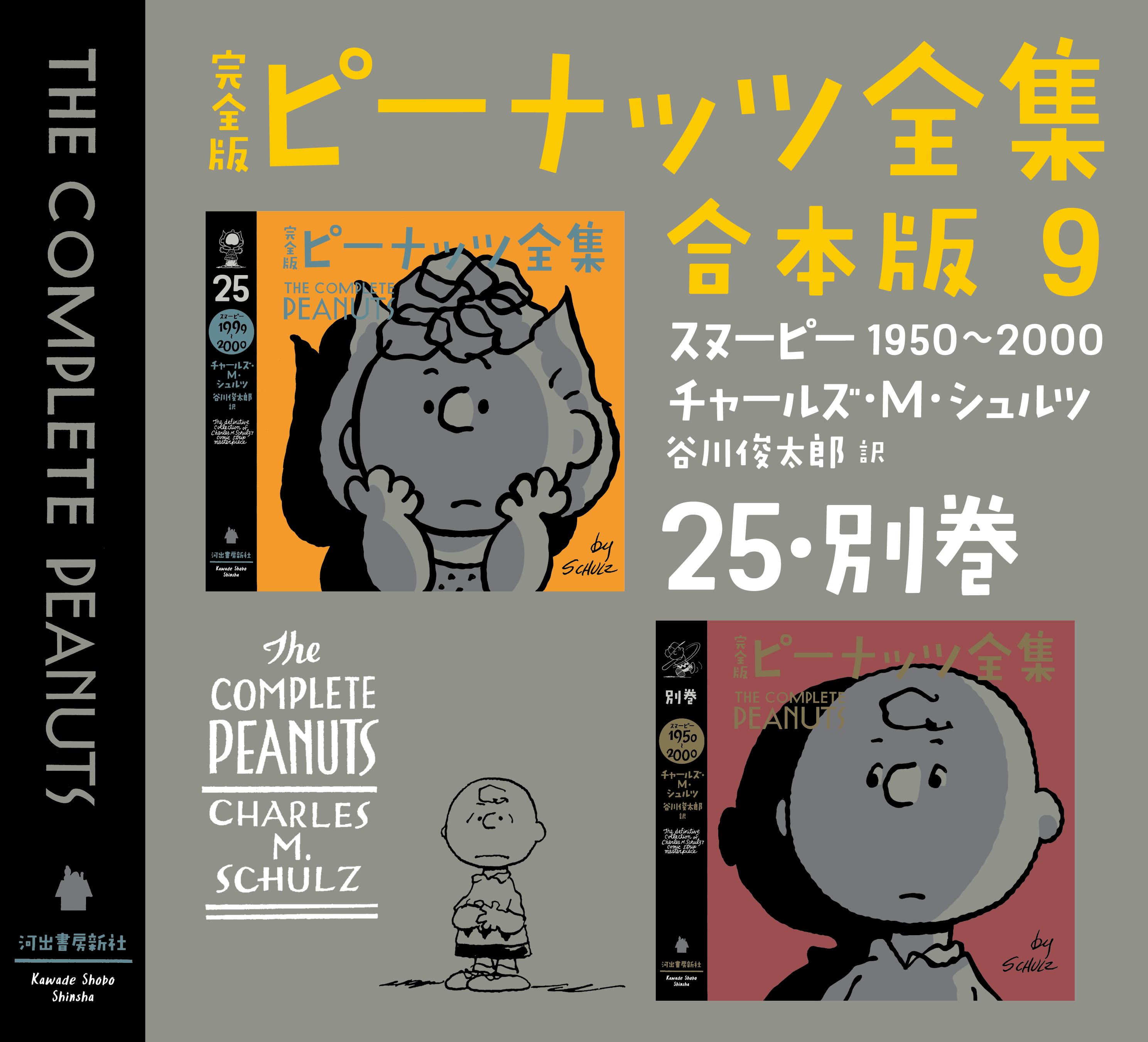単行本 - 外国文学
ファシズムの歴史を、ムッソリーニの視点から描いた挑戦的作品『小説ムッソリーニ』。訳者あとがきを公開。
アントニオ・スクラーティ 栗原俊秀訳
2021.09.27

『小説ムッソリーニ 世紀の落とし子』
刊行と同時にイタリアに一大センセーションを巻き起こした小説。ムッソリーニが「戦闘ファッショ」を結成した1919年から、クーデターのローマ進軍を経て、ファシズム独裁が始まる1925までを描く。
訳者あとがき
ファシズムの歴史を、ムッソリーニの視点から描くこと。ファシズムと闘った人びとや、その横暴の犠牲になった人びとの視点ではなく、暴力を行使した側、支配した側の視点から物語ること。第二次世界大戦後のイタリア文学の歴史において、いままで誰ひとり果たしえなかった試みに挑戦した本書『小説ムッソリーニ 世紀の落とし子』(Antonio Scurati, M. Il figlio del secolo.原題の直訳は「M.世紀の息子」)は、二〇一八年の刊行と同時に、イタリアに一大センセーションを巻き起こした一冊である。
全四部作の第一作に位置づけられる本書では、ムッソリーニが「戦闘ファッショ」を結成した一九一九年三月から、ファシズム独裁が始まる一九二五年一月までの、およそ六年間の歴史が描かれている。イタリア本国ではすでに、一九二五年から一九三二年までを取り扱った、第二作「M.神意の男(M. L’uomo della provvidenza)」が刊行済みである。
では、小説の形式でムッソリーニについて書くことが困難なのはなぜなのか。イタリアの作家たちはこれまで、ムッソリーニという、考えようによってはこのうえなく「物語向き」な素材に、なぜ手をつけてこなかったのか。
それはやはり、ムッソリーニの小説を書くことが、ファシズムの再評価、それも、肯定的な意味での再評価に結びつきかねないという危惧があったためであろう。ムッソリーニを物語の主人公に据えるのであれば、どうあっても、「人間ムッソリーニの素顔」を描写せざるをえなくなる。それにより浮かびあがるのは、常人離れした悪魔的な独裁者というよりも、ひとりひとりの読者が自分の似姿を見いだしうる、非凡ではあるが典型的なイタリア人の姿となるだろう。小説の読者たちが、ムッソリーニのパーソナリティに魅了されたり、ファシズム統治期への郷愁をかきたてられたりすることは、「反ファシズム」を揺るがぬ前提とする戦後イタリアの文芸業界において、あってはならぬことだった。
『小説ムッソリーニ 世紀の落とし子』の刊行にあたっても、当然ながらそうした懸念が取りざたされた。たしかに、「鍛冶屋の息子」ムッソリーニによる政権奪取を描いた今作には、ファシストたちの「国盗り物語」として読める面白さがある。また、ファシスト政権が直面した最大の危機「マッテオッティ事件」をめぐる箇所は、さながら一種の犯罪小説のようでもあり、ファシズムの「指導者(ドゥーチェ)」がはたしてこの難局をどう切り抜けるのか、読者は手に汗を握りながら展開を見守ることになる。原書では八〇〇頁におよぶ長大なこの作品を読み終えたとき、ファシズムの歴史には物語としての荒々しい(そして禍々しい)までの魅力が備わっていることを、読者は痛感せずにいられないだろう。
それでも、著者スクラーティは本書を指して、「かつて自分が書いたなかで、反ファシズムにもっとも多大な貢献をする一冊」と評している。スクラーティの指摘によれば、イタリア文学は過去七〇年にわたって、もっぱら犠牲者の視点からファシズムの歴史を描いてきた(ファシズム統治下のイタリアを舞台にした文学作品というと、日本語に翻訳されたもののなかでは、イタロ・カルヴィーノ『くもの巣の小道』、カルロ・レーヴィ『キリストはエボリで止まった』、ナタリア・ギンズブルグ『ある家族の会話』、はたまたカルロ・エミーリオ・ガッダ『メルラーナ街の混沌たる殺人事件』などがただちに思い浮かぶが、たしかにこれらは、「ファシストの視点から描かれた物語」ではけっしてない)。しかし、あらゆる言説、あらゆる議論の所与の条件として、反ファシズムが広く共有されていた時代が終わりを告げたように思えるいま、二十世紀の文芸を特徴づけてきた「犠牲者の視点に立った反ファシズム」が、かつての有効性を失いつつあるとスクラーティの目には映っていた。新しい世代のために、これまでの反ファシズムを炉に放り、あらためて鍛えなおすことが求められている。そこで、周縁的な事柄に焦点を当てるという昨今の流行にあえて背を向け、歴史の表舞台で主役を演じた人びとを相手にすべく書かれたのが、本書『小説ムッソリーニ 世紀の落とし子』だった。
物語の叙述に価値判断を持ちこむことなく、無慈悲なまでに率直に、事実をそのままに提示すること。ファシズムにたいし、根本的かつ決定的な「否」を突きつけるには、それが最良の方法だとスクラーティは確信していた。本書の冒頭には、「このノンフィクション・ノヴェルに記された出来事や人物は、著者の想像力の産物ではない」という注記が置かれている。スクラーティは作品の執筆にあたって、想像力の介入を可能なかぎり排除しようと努めている。自身のそうした創作態度を念頭に、スクラーティは本書を「ドキュメンタリー小説(romanzo documentario)」と形容している。
『小説ムッソリーニ 世紀の落とし子』は二〇二一年時点で、イタリア国内で五〇万部を売りあげ、世界四〇か国以上で翻訳権が取得されている。二〇一九年、「戦闘ファッショ」の結成から一〇〇周年にあたる年には、商業的な面と権威の面の双方でイタリア最高峰に位置する文学賞、ストレーガ賞を受賞している(なお、スクラーティはこの賞について、著書『私たちの生涯の最良の時』のなかで、「権謀術数や裏取引、イタリア文学界の諸党派間の票のやりとりなどをへて決定する」賞であると評している)。ファシズムとの歴史的な関係の深さもあってか、ヨーロッパの近隣諸国においては、本書にたいする注目の度合いがきわめて高い。各言語への翻訳にともなって、『ル・モンド』、『ディー・ツァイト』、『エル・パイス』などの有力紙の数々に、熱のこもった書評が寄せられている。フランスでは、刊行から時を措かずに複数回にわたって版を重ねたほか、週刊誌『ル・ポワン』が、本書の仏訳を外国小説の「年間ベスト5」に選出している。スペイン語訳は二〇二〇年半ばまでに五刷に達し、『エル・パイス』が発表した「(国内小説も含めた)二〇二〇年のベスト五〇」のリストには、本書が第一七位でランクインしている。
著者のアントニオ・スクラーティは、一九六九年にナポリで生まれ、現在はミラノの私立大学でクリエイティブ・ライティングのコースを教えている。「こうしたプロの文章表現講師が活躍するのがイタリア文壇の近年の傾向」だと、イタリア文学研究者の土肥秀行は指摘している(『文藝年鑑2020』より)。スクラーティは二〇〇二年、デビュー作となる長篇小説「闘争のくぐもった音(Il rumore sordo della battaglia)」を、「M」シリーズの版元でもある大手出版社ボンピアーニから刊行する。これは、騎士道精神が衰退し銃火器が台頭しつつあった時代、ルネサンス期のイタリアを舞台とする歴史小説である。二〇〇五年には、コロンバイン高校の銃乱射事件から着想を得た第二作「生き残り(Il sopravvissuto)」で、ストレーガ賞と並ぶ著名文学賞「カンピエッロ賞」を獲得する。その後もコンスタントに小説の発表を続け、二〇一五年には『私たちの生涯の最良の時』(望月紀子訳、青土社、二〇二〇年)により、一世紀近くの歴史を持つ由緒ある文学賞「ヴィアレッジョ賞」を受賞している。二〇〇九年には「世界の終わりを夢見た子ども(Il bambino che sognava la fine del mondo)」が、二〇一四年には「不実な父(Il padre infedele)」が、先述のストレーガ賞の最終候補にノミネートされており、本書『小説ムッソリーニ 世紀の落とし子』での受賞は、著者にとって「三度目の正直」の快挙となった。
歴史書のような風貌をたたえた本作を、著者はあくまで「小説(romanzo)」と呼び、原書の表紙にも、「M」の大きな文字のわきに、「小説」という親切な但し書きが印字されている。しかし、多くのイタリア人がこの作品を、小説を偽装した「警告の書」と受けとめたことは、インターネット上に見られる一般読者の反応からも明らかである。「ファシズムの足音が聞こえる」という、いまや狼少年の叫びと化した感のある良識的左派の呼び声が、これほどの切迫感をもって響いた時代はかつてなかった。とりわけ、本書が刊行された当時のイタリア政界の状況を鑑みるなら、一〇〇年前との類似はいっそう際だって見えたことだろう。二〇一八年三月に実施された総選挙の後、イタリアでは紆余曲折の末に、左派ポピュリズムの「五つ星運動」と、右派ポピュリズムの「同盟」が相乗りする奇妙な連立政権が誕生した。著名なコメディアンで、いわゆる「アルファブロガー」でもあるベッペ・グリッロが創設した「五つ星運動」は、既存の政治秩序にたいする異議申し立てを旨とする団体であり、反−党、反−政治階級、反−エスタブリッシュメントなどを旗印とする。「五つ星」のこうした態度は、ファシストとは「反党の集団」であり「反政治」であるとするムッソリーニの考えとぴたりと重なる(上巻86ページ)。「議会を懲らしめてやるために、議会の輪に入ろう」(上巻438ページ)というムッソリーニの呼びかけは、議会の外からの変革こそ運動の使命であると信じる、「五つ星」の構成員に向けられたメッセージのようにも聞こえる。しかし、ファシズム(ないしムッソリーニ)の記憶をより鮮明に喚起させるのはむしろ、「同盟」を率いるマッテオ・サルヴィーニの方であったろう。「イタリア人第一主義(Prima gli italiani)」を合い言葉に、反−移民、反−E Uを金科玉条とするサルヴィーニは、もとはダンヌンツィオのモットーであり、後にファシストが掠めとった「どうでもいいさ(メ・ネ・フレーゴ)!」を好んで口にし、メディアに向けては「ヨーロッパなんざどうでもいいさ」、「ブリュッセルなんざどうでもいいさ」と、挑発的な言辞を繰り返してきた人物である。加えてサルヴィーニは、暑苦しいまでの男性性のアピールという面でも、ムッソリーニを手本としているかのような政治家である。本書にはムッソリーニが、上半身を露わにした水着姿を、みずから進んで海水浴客の視線にさらす場面がある(下巻271ページ)。こうした振る舞いはサルヴィーニが得意とするところでもあり、インターネットの検索エンジンで「Salvini a torso nudo(上半身裸のサルヴィーニ)」と打ちこめば、水着姿のにこやかなサルヴィーニのイメージが数多くヒットする。
もっとも、ほんとうの意味で不気味なのは、為政者の身振りに認められる表面的な類似よりも、当時と現在の市民が共有する気分の方にある。国家への失望、裏切られたという感覚、今日より明日が良くなることはもうないのだという苦い確信……かつてムッソリーニ(およびその追随者)が利用した、民衆のあいだに渦巻く負の感情は、いまふたたび、世界のいたるところでマグマ溜まりを形づくっている。排外主義を標榜するサルヴィーニのような政治家を支えているのは、中間層が抱く出口のない不安、「じゅうぶんに所有したことなど一度もないのに、すべてを失うのではあるまいか」という切実な恐怖である(上巻459ページ)。
では、われわれ日本の読者にとって、『小説ムッソリーニ 世紀の落とし子』は「警告の書」たりうるだろうか? 「歴史に学べ」というのであれば、同じ独裁者でも、ムッソリーニよりヒトラーについて読みたいという日本の読者は多いだろう。ムッソリーニの評伝を日本語で物したロマノ・ヴルピッタは、「なぜか、ムッソリーニは戦後日本で人気のない人物である。[……]悪玉にされても、ヒトラーは一流の人物としての評価を受けているが、ムッソリーニは二流と見なされている」と書き、ニコラス・ファレルによるムッソリーニ伝を訳した柴野均は、日本語で読めるムッソリーニとヒトラーにかんする本は「一対十、あるいは一対二十ぐらい」分量の差があると見積もっている。日本の出版業界における統帥(ドゥーチェ)の重みは、総統(フューラー)とは比ぶべくもない。数年前には、ティムール・ヴェルメシュのベストセラー小説『帰ってきたヒトラー』を原作とするフィルムが日本でも大ヒットを記録したが、そのリメイクである『帰ってきたムッソリーニ』はさしたる反響も呼ばずに終わった。両作の関係は、「本家」と「パロディ」としてのふたりの独裁者のイメージを象徴しているかのようでもある(もちろん、実際の歴史に即して考えるなら、「本家」はムッソリーニの方であって、ヒトラーはその手法の模倣者なのだが)。
しかし、両者を生みの親とする思想、運動、体制である、ファシズムとナチズムに視線を移せば、目に映る景色はやや変わってくる。たしかに、書店の棚をひととおり眺めても、ムッソリーニにかんする書籍は少ない。他方で、表紙に「ファシズム」の語が記された本であれば、たいした苦労もなしにいくらでも見つけてこられる。「ナチズム」にかんする書籍は、基本的には両大戦間のドイツ史とイコールであり、第三帝国と不可分の関係にある。ところが、「ファシズム」をテーマとする書籍の多くは、イタリアの歴史には特段の関心を払うことなく、「いまそこにある危機」としてこの用語を使っている。つまり、日本の読者にとって「ナチズム」は歴史であり、「ファシズム」は今日の問題なのだ。これはなにも、ファシズムがナチズムより歴史的に先行し、前者が後者を包摂する概念であるからと指摘するだけで片づけられる話ではない。
それにしても、ファシズムとはなんなのだろう? 本書の冒頭でムッソリーニが創始する政治運動「戦闘ファッショ」が「ファシズム」の語の由来となっているわけだが、それでは「ファッショ」とはなんなのか? イタリア語の「ファッショ(fascio)」は「束」とか「まとまり」とかいった意味を持つ名詞だが、じつは、政治団体に「ファッショ」の名をつけるのは、ムッソリーニの専売特許というわけではない。古くは一九世紀末のシチリアにて、「労働者ファッショ(またはシチリア・ファッショ)」と呼ばれる、社会主義思想に触発された過激な組合運動が展開されている。第一次世界大戦の勃発直後には、ムッソリーニ自身も深いかかわりを持った「革命行動ファッショ」というグループが、イタリアの参戦を目的に活発な運動を繰り広げている。要するに、「ファッショ」とは「集団」、「団体」の意であり、議会外の(戦闘的な)運動によって政治に変革をもたらそうとする勢力を指す言葉だった。もとは普通名詞のこの言葉が、一九一九年の「戦闘ファッショ」の創設をもって、固有名詞として新たな生命を獲得していくのである(なお、日本史の専門家によるファシズムの概説書に、単数形の「ファッショ」は「杖、細い木」といった意味で、複数形の「ファッシ」はそれらを束ねたものであると解説しているものがあるが、これは誤解である。単数形であれ複数形であれ、イタリア語のファッショは「結束」や「集団」の意であって、そこに「細い木」のような含意はない)。
しかし、用語の起源をおさらいしたところで、ファシズムの輪郭が鮮明になるわけではない。ならば、原書にして八〇〇ページ、日本語訳では上下巻を合わせて一〇〇〇ページ近くになる『小説ムッソリーニ 世紀の落とし子』を読みとおせば、読者はファシズムの本質を正しくとらえることができるのだろうか。訳者としては、自信をもって「イエス」と答えたいところだが、じつをいえばそれもまた怪しいのである。「ファシズムとはなにか」を知ろうとして本書を手にとった読者は、場合によっては、読了後になおさら疑問を深めることにもなりかねない。けっきょく、ファシズムとは「右」なのか、「左」なのか。保守反動なのか、革命なのか。伝統崇拝なのか、未来へ向けて躍動するダイナミズムなのか。知的に誠実であろうとするなら、これらいずれの問いにたいしても、「どちらでもあり、どちらでもない」と答えざるを得なくなる。ウンベルト・エーコは「永遠のファシズム」と題された小文のなかで、イタリア・ファシズムを「〈ファジー〉な全体主義」と呼び、そこにはいかなる「本質」もないと評していたが、本書を読めばその言わんとするところがよくわかる。「ファシストとは誰だ? ファシストとはなんだ? ファシストの発明者ベニート・ムッソリーニは、こうした問いに意味はないと考えている。[……]アイデンティティの探求をこれより先に進めてはいけない。重要なのは、一貫性という障害物、原理原則というお荷物から、慎重に距離を置いておくことだ」(上巻86ページ)。ファシズムのなんたるかを規定して、運動に足かせをはめる結果になることをムッソリーニは警戒していた。ファシズムとは、伸縮自在の布でできた、中身がからっぽの袋のようなものである。それは定まった形を持たず、どんな思想も、運動も、無節操に呑みこんでしまう。ファシズムの語がイタリアの国境を越え、二十世紀前半という時代の枠組みを越え、今日もなお世界のいたるところを浮遊しているのは、かかる融通無碍な性格があるからこそであろう。
もちろん、猫も杓子もファシズムとする、この用語の際限のない拡大適用に異を唱える歴史家は少なくない。たとえば、一九六〇年代から九〇年代にかけて、全八巻、合計で七〇〇〇ページ以上にもなる浩瀚なムッソリーニ伝(こちらは「M」のような小説ではなく、学術的な性格を有する評伝)を著したレンツォ・デ・フェリーチェは、ファシズムをあくまで両大戦間のヨーロッパに特有の現象と捉え、それ以外の地域・時代にファシズムの語を適用することには明確に否定的な立場をとっていた。したがって、デ・フェリーチェの主張を容れるのなら、「現代に生きるファシズム」だの、「日本型ファシズム」だのというものは、そもそものはじめから存在するわけがないということになる。だが、本書にも記されてあるとおり、私たち人間は、存在しないものにも恐れを抱くことができる生き物である(「この世に悪霊が存在するかはわからない。だが、悪霊への恐怖は確かに存在する」下巻147ページ)。二十一世紀の世界にファシズムが存在するかどうかは定かでなくとも、ファシズムという「悪霊」にたいする恐怖は目に見える形で存在している。ならば、かかる恐怖を飼いならす意味でも、ファシズムの創始者ムッソリーニの歩みを、ムッソリーニの視点から再体験しておくことは、抗体獲得のための有益な作業となるだろう。敵味方の分断をあおる身振り(「われわれの側に立たない者は、すべて敵だ」下巻319ページ)、民衆のあいだにする負のエネルギーの活用(「政治的闘争のために怨恨を利用できることに、最初に気がついたのは彼だった。社会から爪はじきにされ、不平不満を募らせている落伍者に、最初に声をかけたのは彼だった」上巻216ページ)など、ムッソリーニが用いた政治手法の多くは、いまもって有効性を保っている。「極右」や「反動」といったラベリングにより理解したつもりになるのではなく、ファシズムがじっさいになにをしたのかを知ることで、為政者がムッソリーニの「手口」を(自覚のあるなしとは関係なしに)模倣しようとした際に、私たち市民はその危険性を察知できるようになる。先に名前を引いたデ・フェリーチェは、公平、冷静、客観的な記述に努めたというムッソリーニ伝を著したことにより、本書の著者スクラーティと同じように、ファシズムの名誉回復につながる仕事をしたとして激しい批判にさらされた。そうした声にたいし、この歴史家は次のように反駁している。「事実というものは、政治集会向けの反ファシズムに依拠してファシズムを糾弾するよりも、また、すでに難破しかかった数多くの図式に依拠してファシズムを糾弾するよりも、はるかに雄弁で説得力をもつものなのです」(『ファシズムを語る』より)。ひとつひとつの事実の積み重ねには、声高な政治的アピールを凌ぐ力がある。ムッソリーニは雄弁の政治家として知られるが、聴く者に事実への敬意さえあれば、事実が雄弁によって打ち負かされることはけっしてない。『小説ムッソリーニ 世紀の落とし子』に収められた、ムッソリーニとファシズムをめぐるしい量の「事実」は、私たちの時代を徘徊する悪霊を祓うための、このうえなく強力な武器となるはずである。
アントニオ・スクラーティの著書は、すでに言及した『私たちの生涯の最良の時』が、望月紀子の訳により青土社から刊行されている。本作は、傑出したロシア文学者で反ファシズムの闘士、そして、草創期のエイナウディ社(トリノの名門出版社)の主要な協力者でもある、レオーネ・ギンズブルグの生涯を扱った歴史小説である。一九四四年、ローマのレジーナ・チェーリ刑務所で拷問を受けた後、レオーネは三十四歳で生涯を閉じている。「犠牲者の視点に立った反ファシズム」を、「M」の著者がどのように書いたのか、興味を持たれた読者はぜひ手にとってみてほしい。
本書『小説ムッソリーニ 世紀の落とし子』が、ファシストの「国盗り物語」であるとするなら、シリーズ第二作「M.神意の男」は、ファシストによる「国づくり」の物語である。国政選挙の事実上の廃止(ファシスト党による一党独裁の確立)、自国通貨の威信を守るための「リラ戦争(英国のポンドにたいするリラ高を誘導する政策)」、秘密警察「オヴラ」の創立と監視社会の始まりなど、ムッソリーニが指向する国の在り方が徐々に具体化していく巻といえる。また、ほんの数回ではあるが、第二作には国家社会主義ドイツ労働者党の党首、アドルフ・ヒトラーの名前も登場する。作中に挿入された史料(『デイリー・メール』のインタビュー記事)のなかで、未来の総統は次のように語っている。「もしドイツに、ドイツ人のムッソリーニが現れたなら……ドイツの民衆は彼の足もとにひれ伏して、本家のムッソリーニにたいしてイタリア人がした以上に、激しい賞讃を捧げるでしょう」。時代を見通す力を持ったふたりの男は、この先いかなる関係を築き、いかなる運命をヨーロッパにもたらすのか。まだ道のりは長いが、日本の読者とともに、「M」の物語を最後まで見届けられたらと願っている。
二〇二一年六月十五日、佐倉にて
訳者識