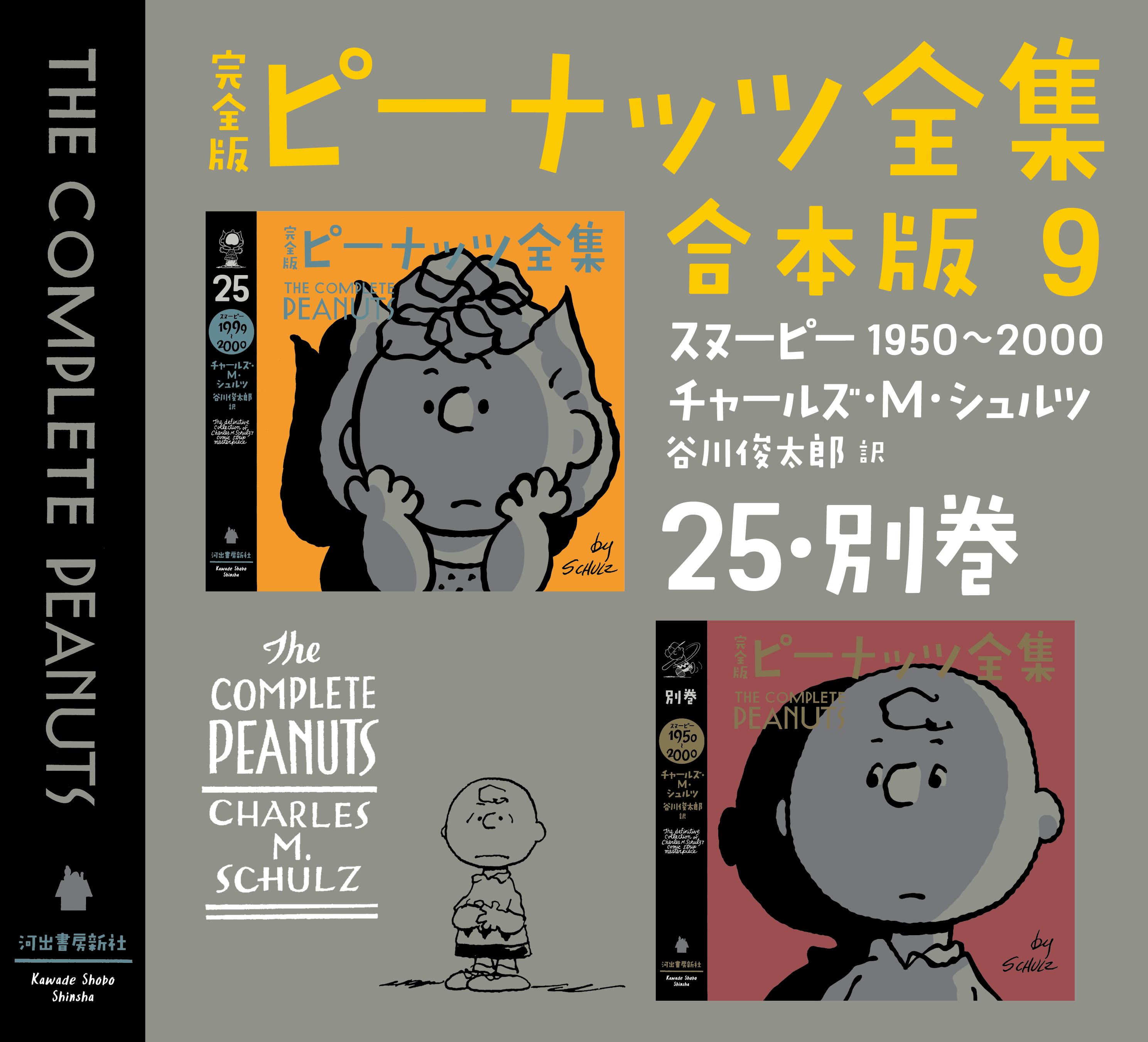単行本 - 外国文学
『黄色い雨』の著者フリオ・リャマサーレスの短篇を無料公開!クリスマスには決して読めない、クリスマス・イブの物語。
フリオ・リャマサーレス
2022.05.23
『黄色い雨』『狼たちの月』『無声映画のシーン』(いずれも木村榮一訳)等の作品で知られるスペイン語圏文学の巨匠フリオ・リャマサーレス。
滅びゆくものたちの詩情と、世界の片隅への愛と共感が読み手の魂を震わせるリャマサーレスの、「集大成」となる短篇集『リャマサーレス短篇集』(木村榮一訳)を、5月27日(金)に刊行します。刊行に先立ち、収録作となる短篇「冷蔵庫の中の七面鳥の死体」を全文無料公開します。
クリスマスには決して読めない、残酷なユーモアに満ちたクリスマス・イブの物語。ぜひお楽しみください。
冷蔵庫の中の七面鳥の死体
一九七一年のクリスマス・イブに、例年のように主人夫妻の間で口論が持ち上がった。
クリスマス・イブの口論は毎年の恒例行事になっていたが、喧嘩はその日一日だけで、残りの三百六十四日間は口をきかなかった。ご主人のほうは昼夜の別なく自分の部屋に閉じ籠もってハバネラを聴いたり、新聞を読んだりしていて、女主人は朝から晩まで家中を歩きまわって、使用人たちにあれこれうるさく用事を言いつけていた。
ご主人は一風変わった人だった。当時の若者と同じように、十七歳のときに移民としてキューバに渡り、四十歳までそこにとどまった。あきれるほど多くの仕事を転々としたものの、ついに金はたまらず、自身の冒険の夢が潰えたのか、(心の病とも言える)郷愁に駆られたのかはわからないが、ほとんど思い出すことのなかった祖国に引き上げることにした。実を言うと、ご主人は自分の決断は間違いだったとずっと考え続けていた。大西洋のこちら側で自分の帰りを待つ者などいなかったし、フィデル・カストロがキューバで権力の座に就いたときでさえ失うものなど何ひとつなかった——つねづね彼はそう言っていた。けれども、ほかの人たちと同じように祖国に戻ってきた。新大陸で一旗揚げたらしいと噂されていたが、実は財産といってもスペインを発つときに残していったものだけ。つまり、夢想家で冒険心に富んだ若者という昔のイメージ、それに両親が遺してくれた三、四カ所の地所しかなかった。
それから長い年月が経ち、ぼくはたまたまキューバを旅する機会に恵まれたが、そのときにアデラ農場(ぼくがアストゥリアス地方を飛び出す前の十五歳から二十歳まで働いていた屋敷)のご主人のアメリカ大航海に関する真実を知ることができた。ホテルの年取った給仕がまだ彼のことを覚えていたのだ。
「ベルエータ? 丸っこい眼鏡をかけた、毛の薄い小太りの男かね?……だとすると、グセンド・ベルエータだな」給仕は頭のてっぺんからつま先までぼくをじろじろ見たあとこう言った。「覚えているも何も、あの若い男のことは忘れられんよ」
そのあとダイキリを前に置き、カウンターに肘をついて給仕の話を聞いたぼくは、凍りついたようになった。ピアノの前に座った黒人がいかにも弾き慣れた感じで物憂くけだるそうにハバネラを次から次に演奏していたが、それらの曲はまさにご主人の部屋でしょっちゅう耳にしていたものだった。そうした曲に耳を傾けながら、(怪しげな仕事に手を出したり、マレコン監獄で服役したり、大金を手に入れてはそれを失ったりということを繰り返していた)誰も知らないご主人の秘められた過去を知ることができた。
「もしこのホテルの部屋が口をきいて、グセンドはスペインにいると告げ口したら、草の根を分けても捜しだしてやると言って、船に乗り込む奴が何人も出てくるだろうな」給仕は最後にそう言って話を締めくくった。
先ほども言ったように、そのことを知ったのは何年ものちのことで、ぼくがあの農場で働いていた頃には温厚な好々爺になっていた。孫をかわいがり、毎日農場を散歩するのが楽しみで、とげとげしくて我慢ならない性格の奥さんを相手にしても、平静さを失うことなく辛抱強く耐えていた。麦わら帽をかぶり、白いショートブーツをはいて(少なくとも結婚式の写真を見る限りは、そういう服装をしていた)キューバから戻ってくるとすぐにあの女性と結婚したが、式は五月のある日曜日にリャネスの教会で行われた。そうと知って近くに住む適齢期の女たちはひとり残らず肩を落としたし、彼女の父親は年齢がちがいすぎる上に(ご主人の方が二十歳年上だった)、ひとり娘が目をつけた相手はどうやら自分の財産が目あてらしいと睨んでいたが、それは必ずしも見当はずれとは言えなかった。事実、彼女の父親はあのあたりで一番の資産家だったのだ。