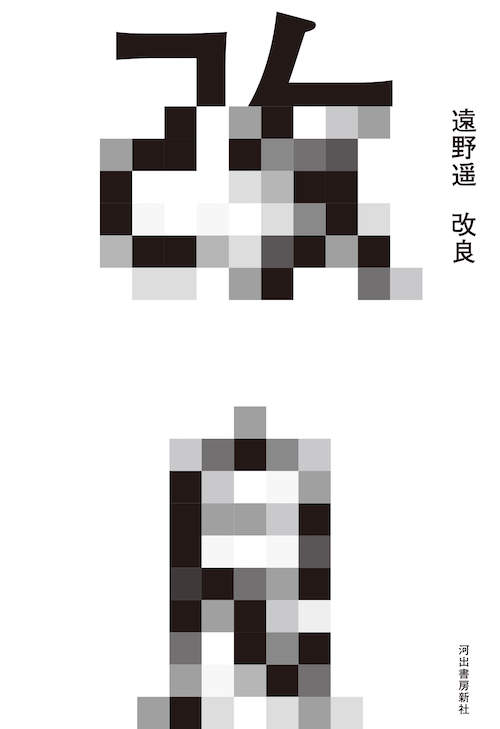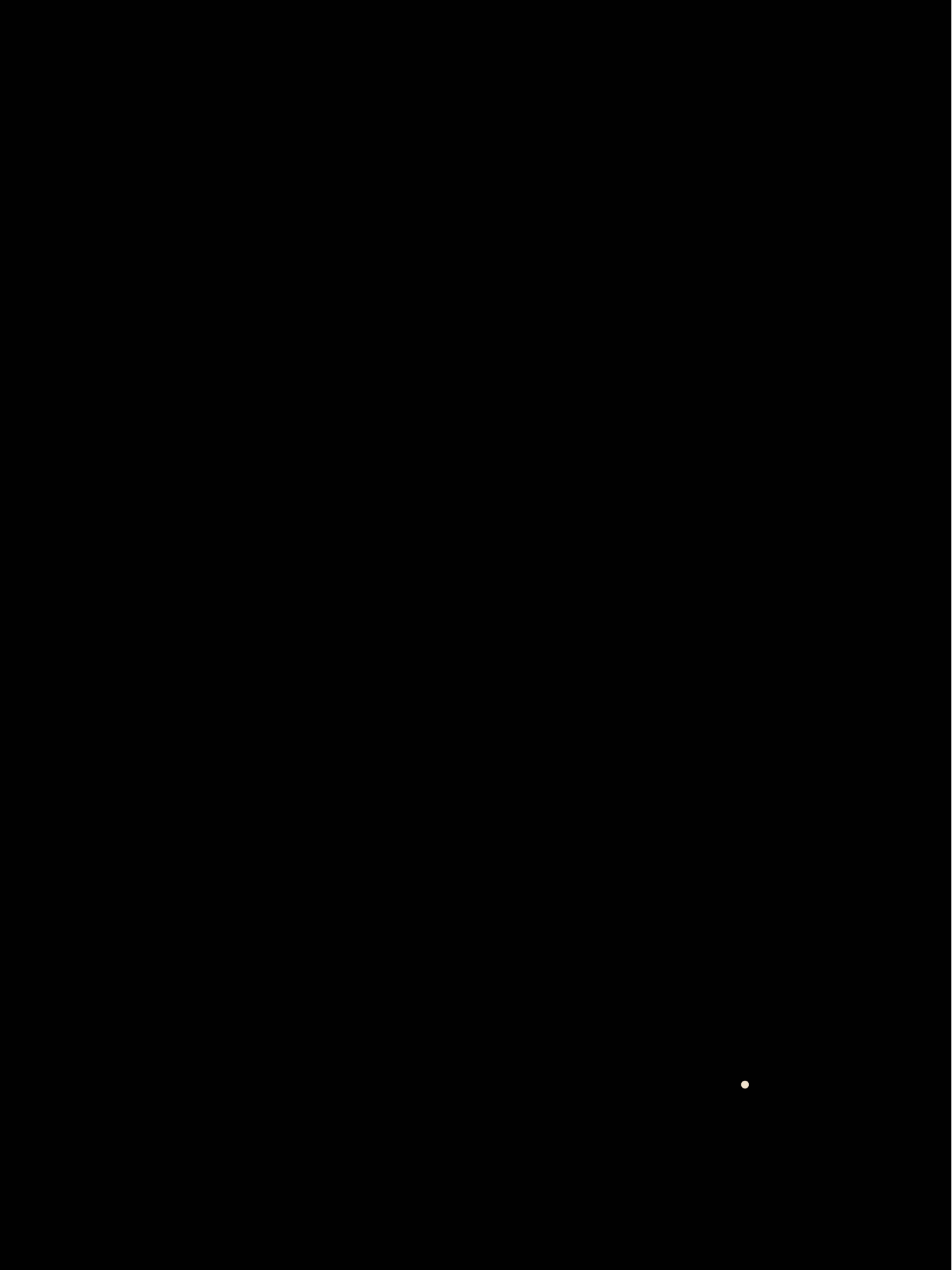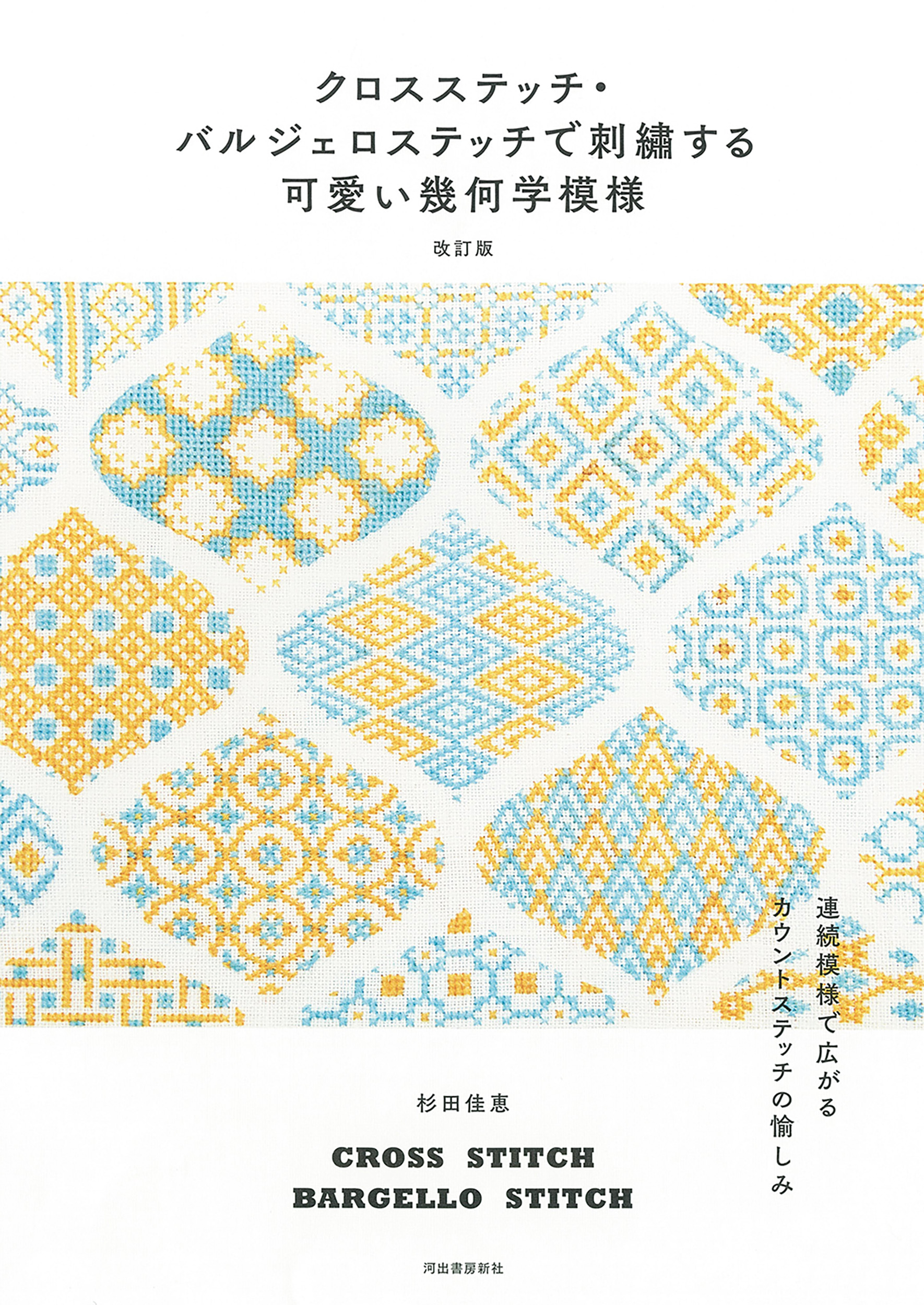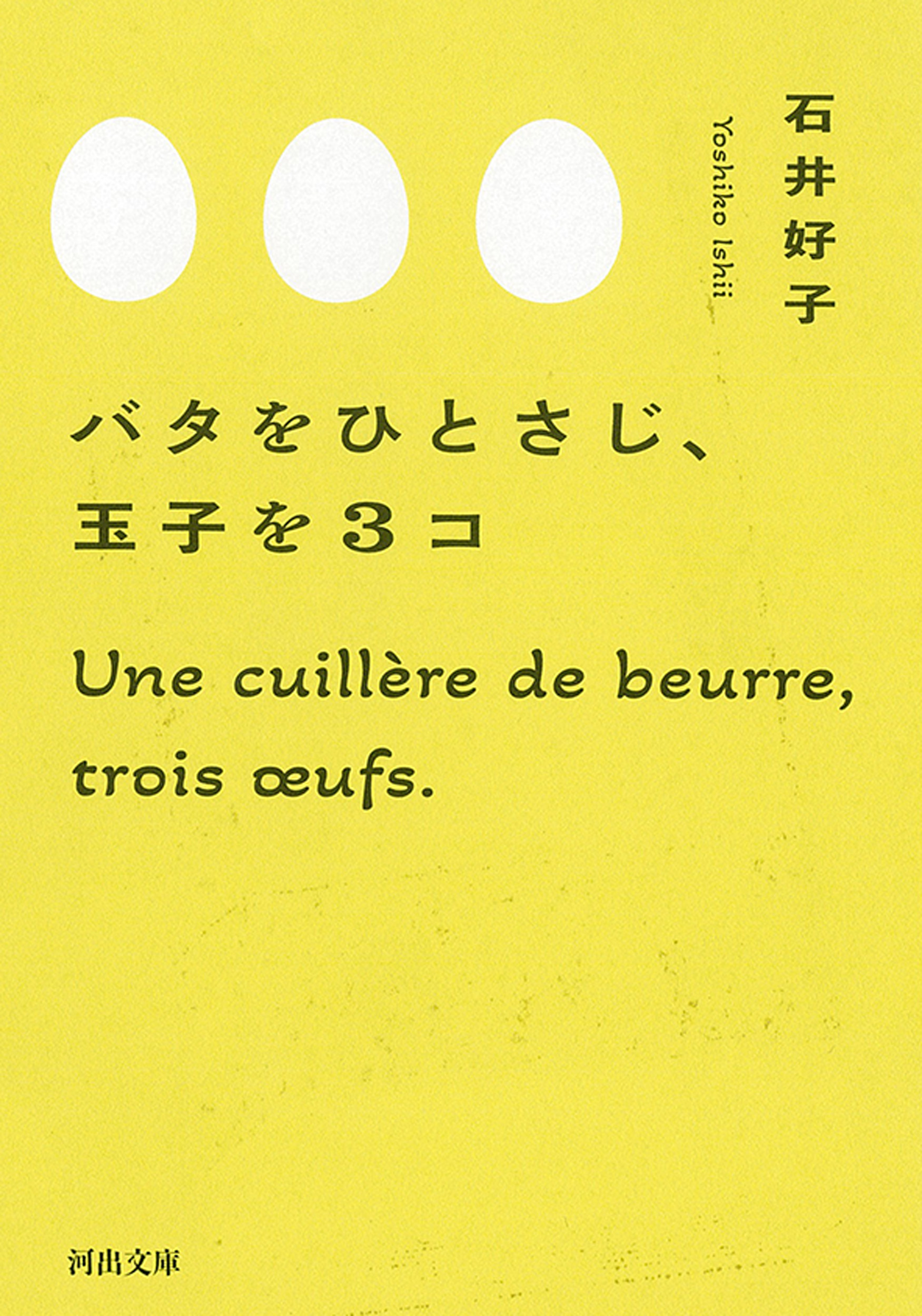単行本 - 日本文学
祝!芥川賞受賞! 遠野遥『破局』冒頭一挙20ページ無料大公開! 元高校ラグビー部員の充実&どこか奇妙なキャンパスライフ
遠野遥
2020.07.15

遠野遥さんが『破局』で第163回芥川賞を受賞しました。
2019年、美に執着し女装する大学生を描いた『改良』で第56回文藝賞を受賞しデビュー。受賞後第一作「破局」で、早々に芥川賞に初ノミネート。そのままこのたびの受賞となりました。
「破局」は元高校ラグビー部員の大学生のストイックでリア充、だけどどこか奇妙なキャンパスライフを描いた傑作。リア充の青春小説かと思いきや、思わぬ場所に連れていかれる、著者の真骨頂です。
受賞を記念し、冒頭から一挙大量20ページを無料で大公開いたします。どうぞ新芥川賞作家・遠野遥の世界をお楽しみください。
破局
遠野遥
目と目が合って、彼が恐怖を感じているのがわかった。私がこの位置までカバーに来るとは思わなかったのだろう。筋肉の付き方は悪くない。背も私よりいくらか高い。どうしてもっと自信を持って戦わないのか。私に勝ちたいと思わないのか。憤(いきどお)りを覚え、確実に潰すと決めた。
私をかわそうとして切った彼のステップは、単にスピードを落としただけで、まったく効果的ではなかった。私は彼の体の芯(しん)を正確に捉(とら)えた。衝撃で球が彼の手から零(こぼ)れる。構わずドライブして仰向けに倒す。笛が鳴ってプレーが止まり、これで球は我々のものだ。誰だっていつかは倒れるが、球だけは絶対に守らないといけない。後で厳しく言ってやる必要があった。
プレーが再開し、何度目かのアタックでセンターの選手がディフェンスラインを突破した。カバーにやってきた敵に捕まったが、まだ倒れてはいなかった。私は後方から駆け寄り、彼の腕ごともぎとる勢いで球を奪った。このプレーだけで、何人かの敵を置き去りにした。私の前には敵がひとり残っているだけだった。
彼は小回りが利(き)きそうに見えたから、余計なステップは踏まなかった。向きだけを少し変え、スピードに乗ったまま突っ込んだ。彼は体をあててきたが、姿勢が高く、あまり力が伝わって来なかった。私を止めたいなら、もっと低い位置に刺(さ)さる必要がある。彼を弾き飛ばし、ほとんど勢いを殺されることなく走り抜けた。斜(なな)め後方から、今度は別の敵が追ってきた。足だけなら現役を退(しりぞ)いた今の私よりはずっと速い。でも体がまだできていない。胸のあたりを手で突いてやると、簡単にバランスを崩した。あまりにも簡単だったから、何かいけないことをした気分だ。どうして私がこんな思いをしないといけないのだろう。きっと今はこういうプレーをする人間がチームにおらず、慣れていないのだ。強いチームほど腕をうまく使うから、対応できるようになってもらわないといけない。
走りながら、味方に向かって怒鳴(どな)った。追ってくるのは敵ばかりで、球を預けられる味方が近くに誰もいなかったからだ。少し減速して待ってみても、やはり敵のほうが近かった。適当に捕まり、ファイトせず自分から倒れた。誰かが抜け出したとき、ほかの選手がサポートに走るのは当然で、そういう状況を想定したメニューもやってきたはずだ。ひとつひとつの練習の意味を理解しないまま、ただ機械的にこなしているだけなのだろうか。この点についても、後で厳しく指導する必要があった。
練習が終わり、佐々木の車に乗った。いつものように、佐々木の家で肉を食わせてもらうためだ。
佐々木の家へ行くには、国道に乗る必要があった。しかし考えてみれば、いつか佐々木から国道と聞かされただけで、本当に国道かどうか確かめたことはなかった。車が止まり、左を見ると服を着た白いチワワが歩いていた。私が知らないだけで、チワワはみんな白いのかもしれない。
チワワは四本の短い足をせわしなく動かしながら、前方の確認を怠(おこた)り、私の顔をじっと見ていた。車の窓ガラスが、私たちを隔(へだ)てている。私が見るからチワワのほうも私を見るのだろうと考え、前を向いた。前の車は四角く、大きな鼠(ねずみ)のぬいぐるみがやはり私を見ていて、ナンバープレートに「ち」と書かれていた。左を見ると、チワワはまだ私を見ていた。先程よりいくらか前のほうにいて、首を不自然なほど捻ってまでこちらを見ている。そのうちに車が動いたので、チワワはすぐに見えなくなり、私はもうチワワの心配をしなくて済んだ。
佐々木の家に着くと、肉の前にシャワーを借りた。プレイヤーだった頃はそこまで気にならなかったが、今は何よりも先にシャワーを浴びないと、気持ち悪くて仕方なかった。当時は汗拭きシートで体を拭いただけで塾に行っていた。今では考えられない。体が臭うと、周囲の人間にも迷惑がかかる。
「もう食えるぞ」
髪を乾かしてリビングに戻ると、鉄板の上で肉が焼けていた。佐々木の妻が慌(あわ)ただしく手を動かし、佐々木はどっしりと座ってビールを飲んでいた。テレビではニュースをやっていて、強制わいせつの疑いで、巡査部長の男が逮捕されていた。走行中の東海道線の車内で、女性の下着の中に手を入れるなどしたという。犯罪者が捕まるのはいいことだ。報(むく)いは受けさせないといけない。いただきますと言って肉を食った。いつものように、旨(うま)い肉だった。
佐々木の妻が私に笑顔を向け、佐々木が旨いかと聞いた。このふたりが、ちょうど私の親くらいの年齢であることを思った。
「今年はどんな新入生が入ってくるか楽しみですね」
グラスを持ち、佐々木の妻にビールを注いでもらいながら私は言った。こうして肉や酒を振る舞ってもらっている以上、こちらから何か話題を提供するのがマナーであるはずだった。
佐々木はビールを飲み、大きくうなずいた。
「三年が抜けて、体のでかい子があんまりいなくなっちゃっただろ。そういう子が入って欲しいよな。陽介は身長は決して高くないけど、筋肉は最初からすごくてな。俺もこの部活を受け持って丸六年になるけど、やっぱり陽介は少し違ったよ。体だけじゃなくて、相手に突っ込んでいく躊躇みたいなのも最初から全然なくてな。
今でも覚えてるよ、陽介が仮入部に来たときのこと。途中から大雨になってグラウンドはぐちゃぐちゃで、今日は引き上げようって言ってるのに全然やめようとしなくてな。全身泥だらけになりながら、脇目も振らずに何回もタックルバッグに突っ込んでて。
生まれたばかりの鳥が、最初に目に入ったものを親だと思い込んでついていくって話を聞いたことがあるけど、しつこくタックルバッグに向かっていくお前を見て、俺はなんだかその話を思い出したよ。鳥は親にタックルしないと思うけどな。あのとき俺はまだ顧問(こ もん)になったばかりで知識とかも全然なかったから、申し訳ないけどちょっと頭がおかしい子なんじゃないかって思ったな。申し訳ないけど。ほかの一年生もちょっと引いてたよな。
うちは公立だし、はっきり言ってスポーツエリートが集まってくるような学校ではないよ。中学からこの競技をやってた子なんてほとんどいない。けど、それでも陽介みたいな逸材も毎年いないわけじゃないんだよ。でもそういう子は野球部に取られちゃってな。今年はそういう子を獲得したいよな。チームはやっぱり強いほうがいいな。ほかの部活とか、他校の顧問にもでかい顔されなくて済むしな」
佐々木が歯を見せて笑った。あまり白くはない歯だった。佐々木の妻も笑っていた。佐々木の妻の歯は、佐々木よりもう少し黄ばんでいた。彼らくらいの歳になると、人間の歯は自然と黄ばみゆくのだろうか。そうだとしたら憂鬱なことだ。夕食のとき、子供を持たないこのふたりはどんな話をするのだろう。私は肉を食べ、もやしも口に入れた。それから米も食った。肉だけ食っていられたら幸せだが、肉だけで腹を満たすのはマナーに反する気がした。
「見ようや」
佐々木が私の左肩を叩き、リモコンを触った。試合の映像がテレビに流れた。私の引退試合だった。佐々木は、何かにつけてこの映像を見せたがる。部の歴史に残るいいゲームだったという。この試合でチームがベストを尽(つ)くしたのは確かだ。我々は最後まで気持ちを強く持ったまま戦い抜いた。しかし相手は後に全国へ行くチームで、準々決勝で当たった我々は今思えばくじ運が悪かった。
敵は主力を温存し、私は試合が始まる前から頭に来ていた。自分たちの出る幕ではないと偉そうに構えている奴らを、嫌でも引きずり出し、出てきたことを後悔するようなタックルを食らわせてやりたかった。
しかし我々は最後まで相手のスター選手たちを引っ張り出せず、終わってみれば決して小さくない点差がついていた。これが果たしていいゲームだろうか。
「確かに相手はスターを温存してた。でも向こうのスタメンは誰も俺たちを舐(な)めてはいなかったよ。特に陽介のことは嫌な選手として意識してたと思う。ほら、見てろよ。今からやるぞ」
密集から球が出る。敵のスタンドオフがパスを受ける。この選手は正レギュラーではないが、率直に言ってとても優秀なプレイヤーだった。判断は的確で速く、競技IQの高さがうかがえた。身長は百八十以上あっただろうか。司令塔でありながら体の強さも申し分なかった。周囲をよく活かしながら、チャンスと見れば自分でも突破を図る。正確なキックを蹴(け)り、ディフェンスも手を抜かなかった。
彼がパスダミーでこちらのスタンドオフの内側を抜く。私は事前に他校との試合映像を何遍も見て、敵をよく研究していた。この選手は、一試合に何度かパスダミーをして自分で走る。きっと我々との試合でもこれをやるだろうと思い、そのときは絶対に後悔させてやると決めていた。映像の中の私が、一気に加速して死角から襲いかかる。このときの私は、我ながら速かった。おそらく彼は、タックルを受ける直前まで私に気づいていなかったはずだ。私は首尾(しゆ び)よく彼を倒し、我々は球を奪い返した。何人かのチームメイトが駆け寄って私の体を力強く叩いた。意味のない行為だが、そのときは悪くない気分だった。
しかし、このプレーが我々のピークだった。私はこのワンプレーで敵のスタンドオフを潰すつもりだった。が、筋肉の鎧を身にまとった彼はすぐに立ち上がり、平然とプレーを続けた。
流れは変わらず、一方的に押し込まれる展開がその後も続いた。確かに我々は最後まで粘り強くタックルに入り続けた。佐々木はおそらくその点を評価していいゲームだと言っている。でも我々は相手を脅(おびや)かすようなアタックをほとんどできなかった。
「この試合、俺は好きなんだよ。みんな身を挺して守ってて。どうせもう追いつけないから手を抜こうなんてやつ、一人もいないだろ。大人になるとさ、いかに手を抜くかとか、そういうことばかり考えるようになるんだ。だから眩しくてな」
佐々木は、いつの間にか涙ぐんでいた。私はそれを見て白(しら)けた気分になり、しばらく肉を食うことに集中した。肉は旨く、やはり佐々木には感謝するべきだろう。我々のチームは佐々木が顧問になってから強くなった。それまで我々の高校は準々決勝まで勝ち上がったことはなかった。
自らは競技経験がないにもかかわらず我々を追い込む佐々木に、当時は怒りを覚えることもあった。自分でやってみろと言いたくなることもあった。今では、あれくらいやってもらってよかったと思っている。やはりスポーツは勝てたほうが面白く、本気でやったほうが得るものも大きい。
私は私をコーチ役に任じてくれた佐々木の期待に応えたかった。今年こそはチームを創部以来初の準決勝進出に導き、かなうことならその先の景色も見せてやりたかった。
*
ベッドから抜け出し、目覚まし時計を止めた。いつものことながら、ぐっすりとよく眠った。心配事があって眠れないという話を時々聞くが、理解できない。考えなくてもいいことを考え、自分で自分の首を絞めているだけではないか。
テレビの電源を入れると、元交際相手の暮らすアパートに侵入して下着を盗んだとして、巡査部長の男が逮捕されていた。私は突然、他人のために祈りたくなった。こんな気持ちは、今までに経験がない。この機会を逃したら、もう二度とこんなふうには思わないかもしれない。
急いでもう一度ベッドに戻った。仰向けになり、胸の上で両手の指をしっかりと組み合わせ、交通事故で死ぬ人間がいなくなればいいと思った。働きすぎで精神や体を壊す人間がいなくなればいいと思った。誰も認知症で子供の顔や名前を忘れたりしなくなればいいと思った。すべての受験生がこの春から望んだ学校に通えていればいいと思った。何かの夢に向けて努力している人間がいるなら、その夢が今日にでもまとめて叶(かな)えばいい。しかし祈った後で気づいたが、私は神を信じていない。私の願いなど、誰も聞いてはくれないだろう。
携帯電話を確認すると、深夜に膝(ひざ)からメッセージが届いていた。自分がずっとツバメだと思っていた鳥が、実はスズメだったことに気づいたという。膝からは今朝になってもう一通、今日が何の日か知っているかというメッセージも届いていた。
頭の片隅で、今日が何の日だったかを考えつつ、裸のまま日課である腕立て伏せやスクワット、腹筋などのメニューを一通りこなした。裸で腕立て伏せをすると、性器が都度(つ ど)床に触れて面白い。でも、衛生面を考えれば下着を穿いたほうがいい。本当はジムに通ってベンチプレスなども行い、限界まで自分を追い込みたい。腕立て伏せでは自分の体重未満の負荷しかかけられないが、ベンチプレスなら100キロ以上の重さで大胸筋、三角筋などを広く一度に追い詰めることができる。しかし公務員試験が近づいていたから、それまでは休むことにしていた。
室内でのトレーニングが済むと、適当なウェアを着ていつものコースを走った。家から近く、信号に邪魔されず、水辺を見ながら走ることができるいいコースだった。人が少ないのもいい。走る距離は短いけれど、ダッシュやステップ、ジャンプなどを組み合わせるから、終わる頃には体が心地よい疲労に満たされている。帰り道の途中で外国人の男に道を聞かれ、申し訳ないが私もこのあたりをよく知らない、あなたを助けることができなくて残念だと答えた。男は日本語で礼を言い、私のもとを去った。私は男の左腕に触れながら喋っていたが、汗をかいていたから、控えたほうがよかった。私の体が熱くなっていたせいか、男の腕は冷たく感じられた。
部屋に帰り、膝にはわからないとだけ送った。今日がいったい何の日なのか、私には見当がつかなかった。シャワーを浴び、汗を流した。浴室から戻ると、今日の夜はライブがあるから、来て欲しいのだと返信があった。私は今日も大学の図書館に一日中こもって試験の勉強をするつもりだったから、行けないと返した。すると、すぐに膝から電話が来た。
「お前は知ってたのかよ。そのへんでよくチュンチュンやってる、木みたいな色の、ふっくらしたちっちゃい鳥。たぶん、俺たちが一番よく見る鳥だよ。あれ、ツバメじゃなくてスズメなんだよ。
俺とお前は同じ言語こそ喋るし、同じ大学に同じタイミングで入って、そのへんの他人、たとえば今俺にベランダから頭頂部を見下ろされてる、禿(は)げたスーツの男なんかに比べたら、たぶん共通点も多いだろうし、絆みたいなのも、お前はどう思ってるかわからんけど、俺は感じてたりする。
だけど、やっぱり俺とお前は違う人間で、もしかしたら同じ景色を見て、同じことを考えてた時間もあったかもしれないけど、でもやっぱり違うものを見て、違うことを考えてた時間のほうが、圧倒的に長いんだと思う。
だから、俺が一番よく見る鳥はスズメだけど、お前が一番よく見る鳥は、スズメじゃないかもしれない。カラスとかも、けっこう見る気がするし、お前が一番よく見る鳥は、スズメじゃなくてカラスかもしれない。というか、俺もスズメよりカラスのほうがよく見るかもしれない。でもそれは、スズメよりカラスのほうが、パンチがあるからだろうか。カラスを見ると人はどうしてもギョッとするから、それで実際の回数以上に、よく見てる気がするだけなんだろうか。本当のところは、わからんけど。
それから俺は、スズメの色を木みたいだって言ったけど、お前は俺の意図とは違って木の葉っぱのほうを思い浮かべて、もしかしたら緑色の鳥を──」
膝と知り合って、もう四年目になる。膝がこういった意味のない話をするのは、本当に言いたいことが別にあって、それを言い出す踏ん切りがつかないときだと知っていた。空いているほうの手で鞄の中身を整理し、カーペットに生えた陰毛をつまみながら相槌を打った。陰毛はなぜ縮(ちぢ)れているのだろう。縮れているせいで、すぐに陰毛とわかってしまうから、何かの拍子で人に見られたとき、恥ずかしい思いをしなくてはいけない。本の間に、まるで栞のように挟まっているときもあって、気を抜くことができない。
意味のない話を散々続けた後に、今日で最後にしようと思うんだと膝が言った。
「今日のライブはな、別に卒業ライブとかそういうのじゃなくて、新入生向けの新歓ライブなんだよ。この時期だからな。でも俺は他人が決めたタイミングで終わりにするのは嫌だから、今日で最後にする。桜も散り始めたことだし、四年生の卒業よりも少し遅くて、一年生が入ってくるよりも少し早い、この何とも言えない俺だけのタイミングで終わりにしてやるんだよ。
サークルの奴らも、俺が今日で引退するなんて知らない。そもそも、俺に対してそんなに興味がない。あいつらは、俺のネタはどう考えても新歓向けじゃないからできれば出ないで欲しいとか、新入生が引いて入部希望者が減るんじゃないかとか、逆に変な奴が入ってくるんじゃないかとか、そういうことしか頭にない。一度でもR─1の一回戦を突破すれば、みんな俺のことを認めざるを得ないだろうし、俺も自信がついたんだけど、結局最後までダメだったな。それだけは少し心残りだ……。
俺は他人と違うことをやりたいと思いながら、一方で他人に認められたいって思いもあって、それが苦しい。たぶんありふれた苦しさだと思うんだけど、それがまた余計に苦しい。俺にしか味わえない俺だけの苦しさみたいなのは、どこかにあるんだろうか?
お前が忙しいのは、俺もわかってるよ。試験、たしか来月の頭だろ? もうあんまり時間ないよな。でもな、最後だから、来て欲しいんだ。詳細送るから、もし来れたら来てくれよ。俺以外の奴なんて見なくていい。ほかの奴なんてどうだっていいから、俺だけ見て、すぐに帰ればいい。そうすれば、そんなに時間も取られないだろ?」
あらかじめ送信ボタンを押すだけの状態にしてあったのか、電話が切れるとすぐにライブの詳細が送られてきた。会場は日吉キャンパスの、普段は講義で使われている教室だった。日吉には一年前まで住んでいた。三年に上がるとキャンパスが日吉から三田に変わるので、それで三田に引っ越した。単位を取り損ねた人間は三年になっても日吉に通うけれど、私は単位を落とさないから用がなかった。
ツナやハム、チーズなどを乗せたトーストを何枚か食べた。牛乳で割ったプロテインを飲んだ。ベッドの上で仰向けになり、目を瞑って朝の自慰を始めた。自慰には常に左手を使う。利き手ではない手を用いることによって他人に性器を触られている錯覚に陥り、射精に至るまでの時間を短縮することができるのだ。
滞りなく射精し、準備しておいたティッシュで精液を拭き取った。性器からは、射精した後もしばらくは少量の精液が出ている。止まるまで待っていられたらいいが、勉強をしないといけないから、いつも性器が完全に乾く前に下着を穿く。すると下着が汚れる。だからシャワーを浴びる前に自慰をしたほうがいい。しかしそうするとシャワーから出る頃にはまた自慰をしたくなっていて、実際にしてしまう。だから最近はもっぱらこの順序だった。
服を着て家を出た。いつもより時間が遅いのを不思議に思い、膝と電話をしていたからだと気づいた。遅れを取り戻すため、私は普段より早足で歩き、横断歩道の前で小さな子供に会った。子供は黒いスカートを穿き、男と手を繋いでいた。ふたりは親子のように見えたが、本当のところは他人である私にはわからない。男は三十代後半くらいで、体格がよかった。子供の体が小さいので、男はより巨大に感じられた。
子供は男から遠いほうの手で絵本を開き、泣きながら「本が、本が」と叫んでいた。絵本のページに、くっきりとした折れ目がついていた。貸してごらん、と甘ったるい声で男が言った。男は絵本を閉じ、両手を使って胸の前でプレスした。絵本がなければ、祈っているようにも見えた。余程力を入れているのか、体が笑いをこらえるように震えていた。男は長いことそうしていたが、その間も子供はずっと「本が、本が」と繰り返していた。
やがて男が、折れていたページを子供の前で開いてみせた。ほら、元通り、と男は言った。絵本と子供の顔が、やけに近かった。絵本のページには、やはり折れ目がついている。子供は泣き止まず、「本が、本が」と叫び続けた。子供はなぜか、最初からずっと私の目を見ていた。信号が変わっていたから、私はそれ以上彼らを見なくてよかった。

続きは大好評発売中 遠野遥『破局』(河出書房新社)でお楽しみください。