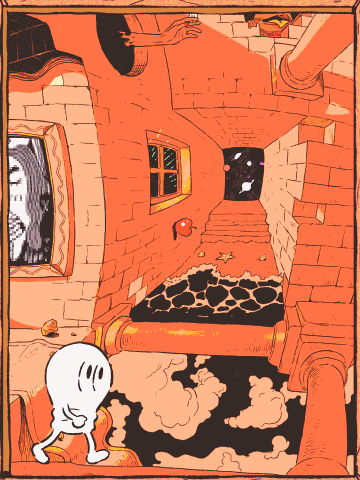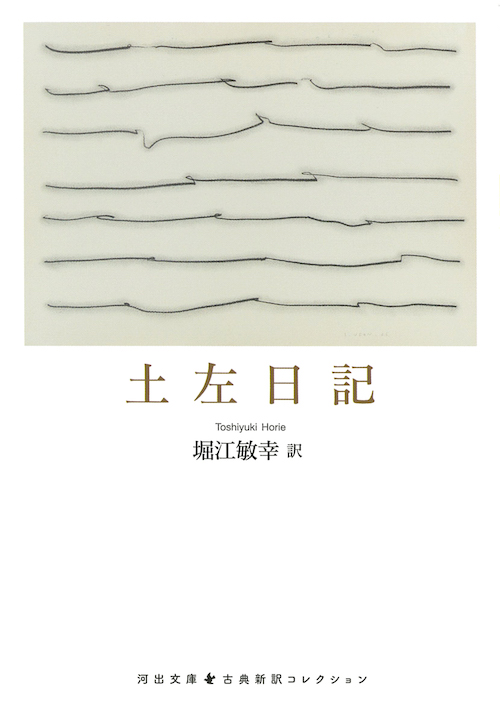単行本 - 日本文学
宇佐見りん『推し、燃ゆ』論 成熟と喪失、あるいは背骨と綿棒について
水上文
2021.02.18
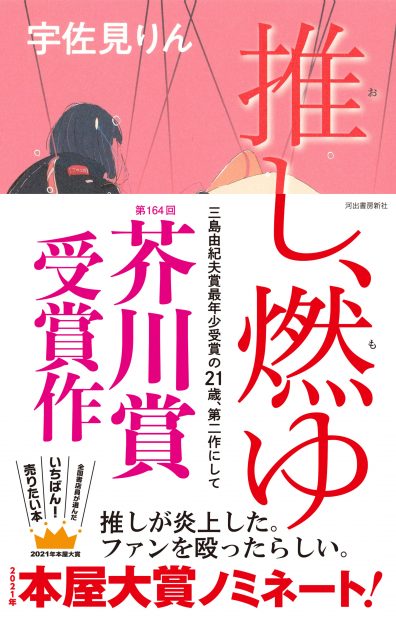
宇佐見りん『推し、燃ゆ』論
成熟と喪失、あるいは背骨と綿棒について
水上文
かつて中島梓は『コミュニケーション不全症候群』の中でオタクに向けて言っていた。
ネバーランドから出るべきだと。私たちはピーターパンではないのだと。
もちろん、私たちはピーターパンではない。
そんなことは知っている。言われるまでもない。ピーターパンではないと言われるまでもなく知っているのになおもその幻想を拭い去れないとしたら、たとえばピーターパンを演じる「推し」に魅せられてやまないとしたら、それなくしては生きていかれないように思えるとしたら、一体どうしたらいいのか?
オタクと「成熟」の問題――中島梓について
中島梓が『コミュニケーション不全症候群』を出版した1991年、「オタク」は今とはまるで違った形で社会に取り扱われていた。「推し」は受け入られた愛情の形態でもなければ生きるために必要な手段としてみなされることもなかった。『消滅世界』は文字通り消滅していて影も形も見えず、『推し、燃ゆ』は燃えるも何も火を囲む人々自体から人々が遠ざかっていた。オタクは大人になってもなお子どものようにアニメや漫画に夢中になる奇妙な人々で、コミュニケーションは不得手で、自分の世界に閉じこもる「未成熟」の別名だった。
中島梓はそんな風に「オタク」を不審げに、遠巻きに、侮蔑とからかいと好奇心を差し向ける社会に向けていかにも雄弁で精力的でJUNEジャンルの第一人者かつ批評家らしくオタクを「コミュニケーション不全症候群」という語彙を発明しながら分析してみせ、最もらしく解説し、よく言われるそのネガティブな側面をそれとして認めながらなおも擁護し、結局のところは「成熟」するべきなのだと教科書めいた教訓を垂れ、にもかかわらず「オタク」であることそのものは否定されるべきではないと強弁するという、幾重にも曲がりくねった理路を用いて新たな存在様式――たとえば妻になる、母になる、仕事をする、に付け加えられた別種の存在様式「オタクになる」――を切り開くことを模索していた。
そして彼女の言う「成熟」とは自分自身を理解すること、自分の苦しみを直視すること、自身の苦しみから逃れるようとすることでどんなに他人を犠牲にしているか知ることだった。彼女からすればそれは是非とも必要なことだった。そしてこの「成熟」なくしては投げかけられる様々な誹謗中傷を否定しきれず、オタクであること、この新たな可能性を擁護しきることはできないのだった。その言葉がたとえどれほど道徳の教科書めいていて、いささか押し付けがましく、いかにも正し過ぎたとしても、いずれにせよこの「成熟」なるものの価値は彼女の信念において譲ることはできない核心に他ならなかった。
オタクのままで、なおかつ「成熟」すること。
端的に言って、中島梓が曲がりくねった理路の先に出した結論はそれだったのだ。
非-性化された「成熟」
ところで、ここで中島梓が「成熟」をそうとは言わずにさりげなく、ひどく抽象的で道徳的な論理にのみ限定していることは重要である。
彼女の言葉のいささか道徳的に過ぎる含意はそれとして、そのように語ることで彼女が「成熟」という言葉から身体的な側面の含意を抜き去り、純粋に抽象的な問題、たとえば自分自身の苦しみに対する自覚、他者という存在への気づきと出会いとして語り直していることを改めて重視すること。ここで私が促したいのはそのような事実である。実際、同じ『コミュニケーション不全症候群』の中で彼女はこんな風に言っていた。
少女、という語そのものにすでにあらかじめ、未通女、処女、というニュアンス、汚れなき童女のイメージが歴然と混入している以上、少女たちは処女でなくてはならぬ。またいつまでも若くなくてはならぬ。犯された少女は処女ではなくなり、従って聖なる少女ではいられなくなる。少女としての自己はまず初潮によって、ついで性を知ることによって、決定的に汚され、失われる。少年は成熟によって男性となる。だが少女は喪失によって女性となるのだ。 [i]
ここで使われている「成熟」という言葉は、生物としての物理的状態を指す言葉、すなわち生殖能力の獲得や生殖それ自体のことである。
けれども彼女はその生物としての物理的状態を表す言葉を一方の性にのみ当てはめ、他方の性に割り振らないことによって、その物理的状態に張り付いたイデオロギーがどんな風に経験されるのかの違いについて語っていた。それは何かを得ることというよりは喪うことのように経験されるのだと。
少なくとも彼女にとっては決して看過できない差異に他ならなかった。そして『コミュニケーション不全症候群』で主に取り上げられる「JUNE少女」も「過食症の少女」も彼女は同じ枠組で分析していたのだった。すなわち喪失が運命付けられているかのようである社会の軋轢の結果として。喪失のように経験される「成熟」の拒否として。「少女」に居場所を与えなかった世界でさらなる「喪失」を経験してそのような世界で「女性」になることの拒絶として。
この前提を踏まえれば、要するに彼女が純粋に道徳的な問題として「成熟」を語った時に意図していたことのもう一つの側面が明らかになる――もちろん「成熟」から身体的な含意、生殖能力の獲得をもって「成熟」とみなす生物の諸状態にまつわる多分に性差別的な生殖中心主義のイデオロギーをカットすることである。
カットの事実と論理をいささか誇張的に突き詰めれば、彼女が狙っていた方途を単なる教訓的なものとは別の仕方で、非-性化された「成熟」として、理解することができる。
性差別的な生殖中心主義に塗れた形ではなく「成熟」することの模索――たとえば純粋に道徳的な問題としてのみ「成熟」を捉えなおすこと、ある種の否認としてのオタクをそれはそれとして肯定すること――という部分がそこにはあったのだと。
私たちはピーターパンではない。それはその通り。けれども、ピーターパンではないと理解することは性役割を、生殖中心主義を受け入れることではない。切り分けるのである。そして問いは戻る。切り分けた上で、どんな風に「成熟」は可能なのか?
別の仕方での「成熟」――『推し、燃ゆ』の方法
さて『コミュニケーション不全症候群』からおよそ三十年後、まさしくオタクがネバーランドから出て行く様を描いた小説があった。まるで中島梓の議論をそのままなぞるかのように、そこではままならない現実を生き、ネバーランドの幻想を見る「オタク」が描かれていた。宇佐見りんの小説『推し、燃ゆ』である。
『推し、燃ゆ』は簡単に言ってしまえば、ままならない現実を生きる女性がアイドルに夢中になり、けれどもそのアイドルが暴行事件を起こして引退を決めてしまい、心の拠り所の喪失に直面する様を描く物語である。
応援している、好きな――という言葉では十分ではないが、便宜上――アイドルやキャラクターを、多くのオタクは「推し」と言う。主人公には「推し」がいる。「推し」は彼女の生活の支え、彼女の言葉で言えば「背骨」である。主人公・あかりは言っている。
あたしには、みんなが難なくこなせる何気ない生活もままならなくて、その皺寄せにぐちゃぐちゃ苦しんでばかりいる。だけど推しを推すことがあたしの生活の中心で絶対で、それだけは何をおいても明確だった。中心っていうか、背骨かな。 勉強や部活やバイト、そのお金で友達と映画観たりご飯行ったり洋服買ってみたり、普通はそうやって人生を彩り、肉付けることで、より豊かになっていくのだろう。あたしは逆行していた。何かしらの苦行、みたいに自分自身が背骨に集約されていく。余計なものが削ぎ落とされて、背骨だけになってく。[ii]
あかりはオタク活動に邁進する自分を、様々な仕方で人生を彩り豊かにしていく「普通」の人々と対比して、「何かしらの苦行、みたいに自分自身が背骨に集約されていく」と言う。けれども同時に「その簡素さがたしかに、あたしの幸せなのだという気がする」とも言っている[iii]。苦行と幸せ、矛盾してはいるけれど確かに実感を持って感じられるその感情が、「背骨」という比喩とともに息を呑む見事さでシームレスに繋がっていく。彼女の現実の生活は喜ばしいものではない。けれども彼女は「背骨」を見つけることができたのだ。たとえそれが一種の幻想だったとして、一体誰が祝福せずにいられるだろう?
だが『推し、燃ゆ』が興味深いのは、そこに「成熟」の問題が、それも中島梓が言った意味での「成熟」――自分自身の苦痛を直視すること――が、含みこまれていることにある。
実際、『推し、燃ゆ』はこんな風にSNSやオタクのコミュニティ、「推す」という行為について描かれた小説はかつてなかったと驚嘆するほどの紛れもない新しさ、現代性がありながら、極めて正統なビルドゥングス・ロマン――主人公が困難を乗り越え、「成熟」を遂げるあの昔ながらの物語形式――の体裁を取っているのだった。
たとえば、主人公のあかりが「推し」と初めて出会うのは四歳の時だが、それが「背骨」と言わしめるほどの重要さを持って迫ってくるのは高校生、十六歳の時の話である。十六歳の彼女は、幼い頃に観た舞台でピーターパンを演じていた「推し」を発見する。彼女は「推し」が舞台で発している言葉を、「自分の一番深い場所で」聞く。
大人になんかなりたくないよ。ネバーランドに行こうよ。鼻の先に熱が集まった。あたしのための言葉だと思った。(中略)重さを背負って大人になることを、つらいと思ってもいいのだと、誰かに強く言われている気がする。同じものを抱える誰かの人影が、彼の小さな体を介して立ちのぼる。あたしは彼と繋がり、彼の向こうにいる、少なくない数の人間と繋がっていた。[iv]
十六歳――まだ子どもだけれど、二次性徴は過ぎていて「思春期」と名指されるまさしくいかにも微妙な年齢で、彼女は「推し」を見出す。
その発見はいわば大人になることの拒絶、成熟への拒絶を介する一種の「連帯」――「あたしは彼と繋がり、彼の向こうにいる、少なくない数の人間と繋がっていた」――としてなされる。そもそも彼女の心を打つ「推し」の言葉は、ピーターパンという役のセリフであった。もちろん、ピーターパンとは成熟を拒否する永遠の少年の象徴である。
要するに、彼女はその時「ネバーランド」の夢を見たのだ。
端的に言って、この小説において「推し」を見つけることとは、ある意味では成熟を拒絶する夢を見ることだったのだ。小説はピーターパンというほとんど直接的に過ぎる象徴を使って、「推し」の虚構性を、「推し」と成熟の拒絶という問題との関連性を強調している。
そして正統過ぎるほど正統に、成熟は暴力によってなされる。
彼女の「推し」はファンに暴力を振るう。彼女が暴力を振るった訳でも、振るわれた訳でもない。けれどもこの暴力行為は結果として「推し」の引退を、彼女のピーターパンの唐突かつ決定的な消滅をもたらす。幻想は暴力によって打ち破られてしまうのだ。生活の「背骨」であった「推し」の最後のライブで、彼女は気がつく。
推しが語るように歌い始めたとき、あの男の子が、成長して大人になったのだと思った。もうずっと前から大人になっていたのにようやく理解が追いついた。大人になんかなりたくない、と叫び散らしていた彼が、何かを愛おしむように、柔らかく指を使い、それは次第に、激しくなる。[v]
彼女は「推し」が大人になったこと、大人になっていたことを、もう自身の幻想を仮託できるピーターパンがいなくなったことを悟る。
物語のラストは、幻想の仮託を貫くことで外側から破壊された幻想を内側から破ろうとする試みである。彼女は「推し」のように自分も破壊したいと思う。ままならない現実が凝縮された自分の部屋を見る。破壊行為に至ろうとして彼女は綿棒のケースを選ぶ。後始末が楽そうだから。それを選んだ理由に気がつき、あかりは笑いがこみ上げる。
要するに、炎上した「推し」の暴力に自身を重ね合わせたけれど、彼女が成し得た暴力は綿棒のケースを叩きつけることだったのだ。破壊したかったけれど、彼女はちゃんとその後の現実を考えていたのだ。笑いが消える。「推し」とは暴力の度合いが違った。
彼女と「推し」は別の人間だった。幻想が終わる。あかりはかつての「背骨」の代替としての綿棒を拾う。背骨の残骸を拾う。這いつくばり、それを「これがあたしの生きる姿勢」だとあかりは言う。ここでの彼女の言葉は中島梓の言った意味での「成熟」そのものである。背骨は失ったかもしれない。けれどもかつて背骨があったからこそ、這いつくばることもまた可能になった。
彼女の破壊、綿棒という暴力の些細さ、それによって気づかされる自分自身の輪郭、生きる姿勢――すべてが「推し」に対する幻想の仮託を貫き通すことで可能になったのだ。
それは中島が、新しい存在様式としてのオタクを論じながら探し求めていたものに極めて近しいものだった。これまで強要されたのとは別の仕方でネバーランドから出ること、性差別的な生殖中心主義をキャンセルした仕方ので「成熟」の可能性――たとえば推しによって。成熟と喪失というよりは、背骨と綿棒で。
*ⅰ 中島梓(1991)『コミュニケーション不全症候群』,筑摩書房.
*ⅱ~*ⅴ 宇佐見りん(2020)『推し、燃ゆ』,河出書房新社,傍点引用者.
(本稿は「文藝」2021年春季号 に掲載の「成熟と喪失、あるいは背骨と綿棒について」に加筆修正したものです)