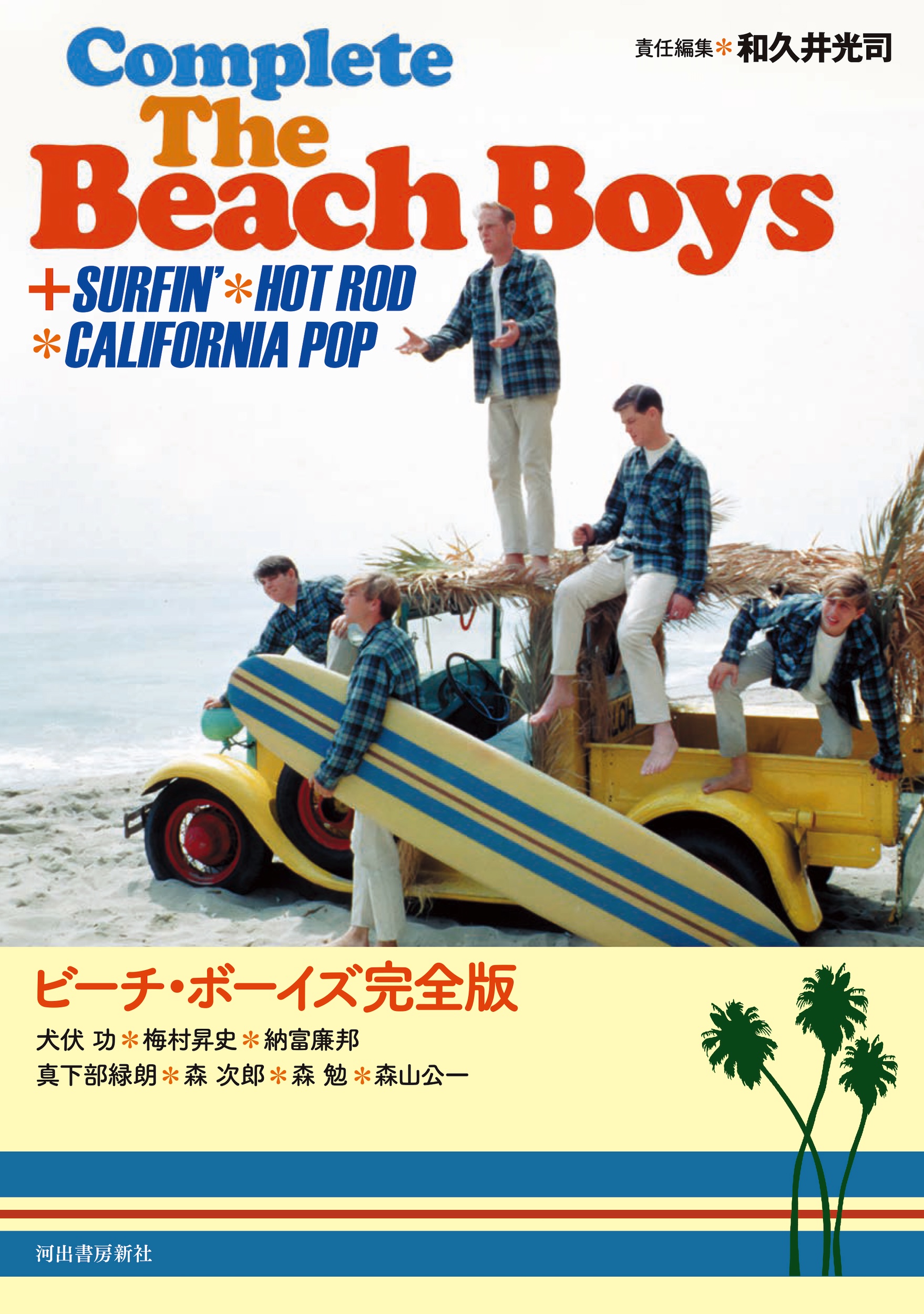単行本 - 日本文学
平田駒『スガリさんの感想文はいつだって斜め上』よりプロローグ~第一話を特別公開
平田駒
2021.03.10
感想文の天才・スガリさんと気弱な家庭科教諭・直山先生のコンビが、感想文をヒントに巻き起こる事件を解決する学園ミステリー「スガリさんの感想文」シリーズ。大好評につき、シリーズ第一巻のプロローグと、夏目漱石『こころ』をテーマとした第一話をまるごと公開します。
プロローグ
蟬の幼虫が一匹、顔を出す時間を間違えていた。成虫たちの声につられて外に出てきてしまったのだろう。
暑い日差しから逃れようと、飴色のベンチの側面をのそのそと進む。ベンチの脇に植えられた木の根元を住処としていたに違いない。
長野県の中央に位置する塩尻駅のホームには、そこかしこに葡萄の木が植えてある。実ももう十分収穫できるほどに大きくなっており、いたずらにつつけば落ちてしまいそうだ。
蟬に気づき、その進路を阻んだのは、ベンチに座っていた女の子だった。動きが遅いとはいえ、虫は虫だ。細い足は不規則に蠢く。悲鳴の一つくらいあげてもいいところだが、女の子は無言で迷子の幼虫を摘み上げた。そのまま葡萄の木の根元に戻してやる。
女の子は何事もなかったように姿勢を戻し、隣に座る祖母に背を向けて髪をいじられている。
「次の高校にもしていけるような髪形にしてあげる」
祖母は皺やシミが目立つ手を大雑把に動かしながら、ご機嫌な様子で女の子に言った。
女の子は鼻の頭に滲む汗すら気にならないのか、ひたすら手の上にあるものを見つめている。
鏡ではない。本だった。ジョン・チンダルの『アルプス紀行』。
「……おばあちゃん」
「なあに? 綴ちゃん」
「この髪形はちょっと嫌だな」
「あら、そう?」
「引っ張られる感じがするし、自分でうまくできる自信もないよ」
「もったいない。綴ちゃんは頭の形が綺麗だから、ポニーテールは似合うわよ。きっと」
綴と呼ばれた女の子は「そうなんだ」と軽く受け答える。興味がないことだけは伝わってくる返事だ。
祖母は「誰に似たんだか」と横を見ながら苦笑した。孫の隣には同じようにベンチに背を預け、本を読みふける野良着姿の夫がいる。
「お父さん、やっぱり待合室に上がりましょうよ。ここじゃ日射病になっちゃうわ」
「今いいところなんだ」
「じゃあ、綴ちゃんと上がってますからね」
「私も今いいところ」
「んもう」
祖母は綴の髪を手で直し始めた。柔らかい猫っ毛はするすると指の間を抜けていく。人の気分を害すことなくさらりと我を通す、捉えどころのない孫の気質をそのまま表しているようだ。
「ほーら、綴ちゃん。これはどう? 三つ編み」
「うん。好き。楽だから」
気に入ってくれるのは嬉しいが、正直「可愛いから」という答えを期待していた。祖母は笑顔とともにため息をついた。
「綴ちゃんはほんと、本の虫ね。やーだ、ダジャレになっちゃった」
自分で言ったことだが、おかしいものはおかしい。祖母はけらけらと笑う。
「あら? もしかして、雲間さん?」
とそこで声をかけてきたのは祖母の地元の友人である佐々木だ。病院の帰りらしく、処方薬の袋を提げていた。
「佐々木さん。あらやだ偶然ねぇ!」
祖母の声が一段と大きくなる。
「茅野から出てきてたのね。お洒落しているから気づかなかったわ。名古屋にお出かけ?」「孫だけよ。あたしたちは見送りに」と世間話に花を咲かせる。
祖母の関心が完全に己から離れたと悟った綴はしおり代わりに指を本にはさみ、もう片方の手でできたばかりの三つ編みを触ってみた。きつめに編んでもらったはずなのに、もう解けはじめている。編み目からぴょこんと飛び出した毛先がなんとも間抜けだ。
綴の口元には自然と笑みが浮かんだ。
「気に入ったんだな」
祖父の声はしわがれている。一度くしゃと丸めて伸ばした紙を思わせる。
「うん」
「写真を撮りたいんだが、時間がないな。電車が来ちまう」
祖父はゆっくりと本を閉じると時計を確認している。名古屋行きの特急〝しなの〟はもうじきホームにやってくる。
綴は「時間があっても嫌だな」とつぶやいたあと、大きなリュックを背負った。中には参考書とノートが入っている。服や下着は先に送ることができたが、出発ぎりぎりまで使うものはこうやって持ち運ぶよりなかった。
リュックにつられてずり上がったスカートの裾を引っ張り、サンダルを履き直す。綴は線路をじっと見つめた。
日の光を受け、目が痛くなるほどに輝くそれは己を慣れない土地へと連れていく。
「……おじいちゃん」
もっとちゃんと言うつもりだったが、綴の口から零れた声は信号機のメロディにも負けそうなほどか細かった。
「誰かの気持ちが分かるようになるには、……どうすればいいかな?」
祖父はしばし黙った。その間に電車の到着を告げるアナウンスが流れる。二階の待合室から一人、また一人と客が降りてきていた。
「綴は本を読むのが好きだね?」
「うん」
「だったらそのままでいい。本を読み続けなさい」
祖父は、まだ『アルプス紀行』を持ったままの綴の手に己の手を重ねた。
「おじいちゃんも綴も、もちろんおばあちゃんだって、百年くらいしか生きられない。実際に訪れることができる場所も、一緒に過ごせる人にも限りがある。だけど本は、昔からずっと時間と空間を超えてきた。そこには他の世界があって、他の誰かの生き方があるもんだ」
「でも……」
「間違っていない。綴は、何も間違っていないよ。お前はもう十分というくらいに、たくさんの人とページの上で出会ってきた。多くの考え方に触れてきたはずだ」
綴の唇はわずかに戦慄いたが、言葉は何も出てこなかった。しなのはもう扉を開けて綴が乗り込むのを待っている。
「綴ちゃん、達者でね」
友人とのおしゃべりを切り上げて祖母が言いながら手を振った。
「おじさんたちにもよろしく伝えてくれ」
「うん」
来週、荷物を整理しにまた茅野に戻ることが決まっているからか、別れは存外あっさりしていた。
ドアの窓越しにひとしきり手を振ったあと、綴は動き出した電車の揺れに体を取られながら自由席の車両に足を踏み入れた。中途半端な時間のためか、貸切だ。松本始発のしなのとはいえ珍しい。
「うわ、ガラガラだ」
思わず口に出し、綴は進行方向の最前列に進んだ。荷物棚にリュックを押し込んで、窓側の席に座る。しなのはすでに塩尻の街を抜け、田んぼの中を走っている。レールの切り替え部分を越える度に、綴のできたばかりの三つ編みが大きく揺れた。
中山道、それから木曾川と共に進む旅だ。視界には絶えず山が現れては消えていく。
「ふふ」
綴は目を輝かせて車窓ごしの風景を楽しんでいたが、長くは続かなかった。慣れ親しんだ景色はあっという間に暗闇に切り替わる。山があるということは、それだけトンネルもあるということだ。
「やれやれ」
水を差された綴は、大人しく『アルプス紀行』を開き直した。窓に映る己と見つめ合う趣味はない。
しなのがトンネルを出る度に耳に張り付くような低い音が消えて、日の光が差し込んでくる。とはいえ、ほっと息をつく間は貰えない。頭をあげる頃にはまた次のトンネルに入ってしまう。その繰り返しだ。
ページをめくる。どうにも集中できない。
(一つ……、また一つトンネルを越える度に)
綴は今になって気づいたのだ。
(私は故郷から遠ざかる。もう帰ってこられない)
電車に乗れば半日かからずたどり着く場所だから。来週また戻るから。そういう次元の話ではない。
別れ際の祖父の言葉が蘇る。人が生きているうちに行ける場所には限りがあると。望むままに全ての人と一緒に過ごせるわけではないのだと。そのとおりだ。だからこそ、こんなにも心が震える。
(帰れない。私は、もう帰れない。もう……資格がない)
『アルプス紀行』を慌てて閉じる。刹那、白い手の甲に大粒の涙が落ちる。喉の痛みや鼻の奥の痺れを、どうすることもできない。嚙み締めた歯の隙間から情けない声が漏れた。
綴は列車の中で一人、息を殺して泣いていた。

第一話 夏目漱石『こゝろ』
1
鶴羽学園の家庭科担当教師、直山杏介は困っていた。困り果てた顔で沈黙を保っていた。
「直山先生、聞いてますか?」
「はい……」
おずおずと返事をする杏介の視線は、若干下を向いている。気まずくて床を見ているわけではない。相手と目を合わせるときは、大体そうしなくてはいけないのだ。
杏介は長身だ。どれくらいかというと、調理実習で男子の班の中に立っても頭一つ抜けるほどである。肉付きはそこそこで、長い手足を文字どおり持て余している。ワインの化粧箱にすっぽり入りそうだよね、と不思議な表現で体形を称されたこともあった。
確かに身長は高い。では、モデルになれそうな顔をしているかと問われれば、かすりもしない。実際、今まで好意を寄せてくれた女性はこぞって杏介のすらりとした後ろ姿を褒めたが、正面から褒めてくれた人は木星に到達した者ほどしかいない。つまり今のところ一人もいない。
もう一つ言えば、服装もいけなかった。
学園の近くにある山崎川の桜は今朝方、薄い色の花びらを空に盛大に舞いあげていた。それは春という季節のフィナーレだと言わんばかりの盛況さで、見ているだけで自然と体温が上がってくる。だというのに、杏介は年明けから服装をほとんど変えていない。
男子生徒は学ラン、女子生徒はブレザー。そしてこれが僕の制服です。
そう主張するかのごとく毎日毎日杏介が着ているのは、カジュアルな柄のシャツと手編みのセーターだ。採寸の際、自分の好みに合わせた結果、袖が手の甲にかかる、もっさりとした着丈のものに仕上がっている。この上からさらに厚手のモッズコートをまとう。
ランチ仲間の先輩たちから、「来世は布団にでもなりたいのか」と呆れられている厚着具合だ。
外は眩しい光で溢れている。だが、杏介は登下校中まだマフラーをつけている。寒がりな杏介にとって春は、もう少し先だ。
自席があるこの家庭科準備室の環境も、杏介の厚着に拍車をかけていた。もともとは図書分室で、強い光で本が傷まないように配慮されている。薄暗い部屋の窓辺には、紅葉の木が意図して植えられている。おかげで日差しはほとんど入らない。着込んでいないとやっていられなかった。
杏介の顔色ははっきり言って悪い。持病の胃痛もじわじわ来ている。
だがそれは──寒さのせいだけではなかった。
「まったく、困ったもんですよ」
歯切れの悪い杏介の返事を聞いて、対峙する男はわざとらしくため息をついた。教頭の野間垣だ。
くたびれたスーツの上には嫌味ったらしい顔がのっかっている。鼻の穴がやけに目立つ。それは杏介が昔から抱く教頭先生のイメージとぴったり一致した。
杏介に向ける視線は、信頼する部下に向けるそれとは程遠い。どちらかといえば教育実習にやってきた鈍臭い大学生を見るようなものだ。
野間垣は嫌味を再開する。
「あなたは高等部の中で最年少の教員なんですから。もっと積極的に部活動に参加してもらわないと困るんです」
棘を隠そうともしない言いようだ。
「あのねぇ。黙ってちゃ何も進まないでしょう」
あばらの下がギリギリ痛むのを感じる。杏介はしどろもどろに「あの、ええっと……」と言葉を繫いだ。
途端に野間垣は渋い顔をする。
杏介にも自覚がある。自分の口から発せられる声は、とにかく頼りない。君と話していると、優しくしなきゃ、という使命感に駆られると苦笑いされたこともあった。部下に厳しいことで有名な教頭も例外ではない。
「直山先生。そのおどおどした感じ、なんとかなりませんかね?」
「すみません……」
「嫌ですよ。あなたが生徒に虐められてるのを助けるなんて。せっかく立派なタッパしてるんですから。ほらもっとしゃんとして、体から自信を発して!」
それができたら苦労はしない、と杏介は内心つぶやく。自分の性根は身長の半分──ちょうど四歳児くらいか──の者よりもはるかに打たれ弱いのだ。
とはいえ、野間垣の言うとおりである。黙っていては事態は何も進まない。
杏介は意を決して口を開いた。
「ですので……」
野間垣はゆったりとした語調で繰り返す。
「ですので?」
「ええっと……、その……」
杏介は右手の指で左の手のひらを叩く。意味のないモールス信号だ。そいつを自分自身に送り、思考をまとめる癖がある。
考えたわりに、自信のない、むしろ詫びるような答えが口から漏れた。
「手芸部の顧問を……しています」
野間垣はにっこりと目尻を下げる。薄っぺらいタウン誌の表紙を飾れそうな笑顔だったが、胡散臭くもあった。
「さすが直山先生。我が校初の男性家庭科担当だけあって熱心ですねぇ」
「ありがとうございます」
杏介は素直に礼を述べた。野間垣の言葉を素直に受け止め、褒められたと思ったからだ。
おかげで妙な間が空いた。野間垣は空咳をして仕切り直した。
「直山先生。あなた、自分が何者か分かっていないんですよ。あなたは我が校どころか名古屋初、いや、愛知初の男の家庭科の先生なんです。さすがに全国初ではなかったですけど……」
流行りのパンケーキ屋のような評価を貰っても、まるでピンとこない。「もっと授業以外でも生き生きしましょうよ」という野間垣の言葉に、杏介は困ったように眉尻をますます下げた。
(二十三年間、僕を見てきた母さんは「あなた、裁縫をしているときは本当、別人みたいに生き生きしてるわよねぇ」って言うけれど……)
自分が手芸部の顧問をする。一体何がまずいのだろうか。杏介の胸に素直な疑問が過ぎる。
野間垣の考えは違うらしい。わざとらしく拳を作って杏介に迫る。
その目は熱意に燃えている。学校という蛸壺空間に、改革の風を吹き込むのだと息巻く管理職の熱意だ。ますます胡散臭かった。
「直山先生は家庭科の先生。だもんで家庭科の延長の部活顧問をやっている。こういう今までの事例に引っ張られて顧問をするのも癪じゃありゃせんか? ねぇ?」
野間垣との会話は油断できない。特に地の喋り方が出ているときは危険だ。
「いいえ! 全然! 好きですから!!」
自分の主張を明確に言わないと、野間垣に勝手に決めつけられてしまう。曖昧に返事をしたら最後だぞ、と杏介は先輩教師たちから教わっていた。
「へえ、そうですか」
ひとまずこの場は切り抜けられた。
鼻の付け根に皺を作ったあと、野間垣はいったん話題を変えた。
「あのぬいぐるみも部活で?」
杏介の頭よりも高いところに置かれた熊のぬいぐるみを指す。野生のツキノワグマが木の上から獲物を狙うように、杏介の自慢のぬいぐるみは家庭科準備室のロフトの上から野間垣を見下ろしていた。
家庭科準備室のロフト。それは図書分室時代に取り付けられたものだった。かつて真下には移動書架が並び、使用頻度の低い文学全集や図鑑の類が収められていたらしい。高さは杏介が背伸びしてやっと出し入れできるほどで、登り降りには梯子を使う。
上にあがると、目と鼻の先に天井が迫る。大人の寝泊まりは絶対にできない。デッドスペースになりそうな空間だ。かつては図書委員会の雑品置き場として使われていた。
現在、学園の蔵書は全て中央図書館に集約されてしまっている。一方、家庭科準備室となった部屋のロフトは手芸部員の作品の保管場所に姿を変えていた。
得意分野の話題を振られ、杏介は「はい、一応……」と頰を赤くする。野間垣は苦虫を嚙み潰したような顔をした。
「これは去年の手芸部の合作なんです」
杏介は腕を上げてぬいぐるみを引っ張り出し、野間垣に差し出したが、手のひらで断られた。
見れば見るほど大きい熊だ。高校生でも両手を使わないと持てない。こんなサイズの熊と山で出くわしたらひとたまりもないだろう。
「直山先生が持つと不思議と様になりますね」
「よく言われます。あんまり……嬉しくはないんですが」
「あ、他意はないんですよ。本当、本当ですって」
野間垣は繰り返し主張した。杏介はしょげた顔を隠しながら、そっと綿の熊を定位置に戻す。
(セオドアって名前つけてることは黙っておこう。呆れられそうだし)
熊のセオドアは、ロフトの上からじっと杏介を見つめている。何だか「負けるな」と応援されているような気がしてきて、杏介はもう一度「ですので」と口火を切った。
「教頭先生のご期待には添えていないかもしれませんが、僕は手芸部の顧問を頑張っています。授業では立体的な縫い物をやりません。ですが、部活では生徒が『作りたい』と思うものを形にできるようサポートしています。特にあれは去年一年かけて部員全員で作りました。デザインをコンペして、パーツの担当を決めて……」
主戦力になってくれたのは今年卒業した三年生たちだ。裁縫は初心者だと言っていた二年生たちもよく手伝ってくれた。
家庭科実習室は調理部が使うため、手芸部の部室はここ──家庭科準備室だった。みんなでわいわいお喋りをしながら、針を動かしたものだった。
(ああ、でも……)
そんな楽しい思い出も、今は昔だ。勢いよく話し出した杏介の顔が歪む。
野間垣は鼻の穴を膨らませて、ふたたび本題に踏み込んできた。
「残った二年生、つまり今の三年生は三人全員が受験を理由に手芸部を退部しましたね?」
杏介はますます顔を曇らせた。
「……はい」
「もともと一年生部員がいなかったので、現二年生の部員はゼロ人、あっていますか?」
「そのとおりです」
逃げ場がどんどんなくなっていく。
「先週までがクラブ活動の勧誘期間だったわけですが……手芸部には結局何人入部したんですか?」
「え、えーっと……」
杏介は右へ左へ視線を泳がせる。フォローを求めようにも、同じ家庭科担当の大江は席を外している。
観念して、正直に答えた。
「…………ゼロです」
野間垣は大きく頷く。そして判決を言い渡す裁判長のように告げた。
「つまり手芸部の廃部が決まった、ということです」
覚悟はしていたが改めて言われると堪えるものがある。杏介は目をきつく閉じた。
「直山先生には来週からサッカー部の手伝いをお願いしますね」
「そんな!」
堪えるどころではない。杏介は目を見開いた。冗談じゃないですよと喚きたかったが、勇気がなかった。
「いや! あの! それはちょっと!! ……厳しいです」
野間垣の睨め付ける顔もなんとか耐えて、杏介は自分の正直な気持ちを伝える。変温動物にでもなったような心地だ。ただでさえ低い体温がどんどん下がっていく。口の代わりに胃袋が悲鳴をあげていた。
「ずいぶん必死なんですね。スポーツ苦手なんでしたっけ?」
「はい。初めて会う人には必ず伝えるほどに……」
恵まれた身長とは裏腹に、杏介にとって体育系の部活は鬼門中の鬼門だ。得意な種目なんて一つも思い浮かばない。赴任したときに、そのことは野間垣にも伝えたはずだ。
にもかかわらず、杏介の告白に野間垣は一歩も引かなかった。
「いい機会なんじゃないですか? 体育は苦手だったけど、大人になって運動が楽しくなるって人多いらしいですよ。そうでなくとも、部活顧問はどこも人手不足なんです」
それを言われてしまうとぐうの音も出ない。実際、顧問を掛け持ちでやっている先生だっている。
野間垣は杏介に念押しした。
「とにかく、サッカー部以外でも構いませんから、絶対に何か部活顧問をやること。いいですね?」
柿渋エキスが入った歯磨き粉の独特な匂いが鼻に届く。杏介はいったん首を横に振ろうとして、泣き出したい気持ちを隠して頷いた。
家庭科準備室に残された杏介は大きなため息をつく。誰にも聞かれていないのをいいことに、情けない声で自問した。
「手芸部以外の……部活?」
すぐに浮かんだのは調理部だが、こちらはもう一人の高等部家庭科担当である大江だけで事足りると野間垣に釘を刺されている。先手を打たれたのだ。
先月発行された学校紹介誌を広げる。パラパラめくると鶴羽学園の文化部のリストが出てきた。
「囲碁部、合唱部、プログラミング部……」
まるでピンと来ない。
「うーん……」
どこかの窓が開いているのか、吹き込む風は生暖かい。ミシンの部位名をまとめたプリントの束がふわと舞う。杏介はそれを人差し指一本で押さえた。視線は依然、部活の様子を伝えるコラムに釘付けになっている。赤煉瓦造りの校舎を背景にしていた。
「相撲部でちゃんこ番の募集とか……してるわけないか」
しかし、できるだけ早く、どこかの部活の顧問の座に収まらねば。
このままでは学校一厳しいと有名なサッカー部の練習に付き合う羽目になる。
「無理無理、絶対無理」
杏介は大きな手で自分の顔を覆った。右手の薬指には指ぬきがついたままになっている。
「僕、学生の頃、体の大きさだけでキーパーやらされて、〝顔面セーブの直山〟ってあだ名まで貰ってたんだよ? ベンチで刺繡してたら絶対怒られるし……。ああ、困った……」
何度目になるか分からない気重なため息をついたときだった。
「それはちょうどよかったです」
背中に声がかかった。
「直山先生」
名前を呼ばれたので、振り向く。
「失礼しています」
家庭科準備室の扉と掃除用のロッカーの間に女子生徒が挟まっていた。
杏介は細長い体を強張らせ、椅子ごと倒れた。悲鳴はない。人間驚くと悲鳴すら失ってしまうようだ。
「やれやれ。何もそこまで驚かなくても」
ひどく落ち着いた口調で話しかけられるが、杏介の心臓は依然、激しく脈打っている。幽霊のように現れるのがいけない。驚くなというのは無茶だ。
一体いつからそこにいたというのか。いきなり皿の中に掬い出された縁日の金魚のごとく、杏介は口をぱくつかせた。
「ス、スガ……」
うっかり、有名なあだ名が零れそうになる。
陰口にも捉えることができるそいつをなんとか飲み込んで、杏介は目の前の生徒の苗字を口にした。
「須賀田さん?」
「はい」
二年生の須賀田綴だった。去年の二学期に長野から転入してきた。
どこを見ても山だらけなだけあって、長野は標高が高い。そのため全国で一番紫外線量が多いのは長野県なのだそうだ。しかし、綴の肌は年中初雪のように白い。
綴は柔らかそうな猫っ毛を三つ編みにし、程よく崩している。愛くるしい髪形だ。綴の落ち着いた雰囲気ともよく合っている。「直毛化を含むパーマ、毛染めを禁止する」という鶴羽学園の校則を一ミリたりとも乱していない。ついでに言えば制服の着こなしも全て校則許容範囲内だ。それでいてここまでの魅力を振りまく少女も珍しい。
野間垣がその日の夜には捨てられるタウン誌の表紙なら、こちらは全国雑誌の表紙を飾れる。
(……なんだけどなぁ)
抜けた腰をどうすることもできず、倒れたままの姿勢で杏介は内心困った声をあげた。
「大丈夫ですか?」
綴はすっと杏介の脇に立膝で座した。王子然とした振る舞いに杏介は目を白黒させる。
「だ、大丈夫だから。そんな腰に手を添えてくれなくていいよ! と言うか、よろけたときに危ないから離れてくれないかな」
「私の心配はいいのです」
言葉こそしっかりしているが、綴の浮かべている表情はぼうっとしている。相手が目の前にいるにもかかわらず、そのさらに奥へ視点を置いている。何を話しても暖簾に腕押しという雰囲気をまとっていた。
「それに『腰を抜かした人にはとびきり優しくしろ』っておじいちゃんが言ってました」
「おじいちゃんが言うんじゃ……しょうがないかな」
須賀田さん、おじいちゃん子なんだ。綴の妙な説得力に、杏介はあっさり折れた。
なるべく綴に体重を預けないよう心がけて立ち上がる。
綴は杏介がまっすぐ立てたのを見届けると、満足げに一度頷いた。会心の出来で花を生けることができたとでも言うように。
その笑顔に、杏介は教師の立場でありながらドキッとしてしまう。
「直山先生、先生は今何かの部活顧問にならないといけない状況に置かれているんですね?」
杏介は目を見開く。
「え? 教頭先生と僕の話、ずっと隙間から聞いていたの?」
疑問を隠すことなく口にすれば、「まさか。そんなの、すぐ見つかっちゃうじゃないですか」という返事。
ではどこで盗み聞きをしていたのか。尋ねるのは少し恐ろしかったが、綴は結局真相を明かすことなく、本題に切り込んだ。その目は静かな光を放っている。
「直山先生、私にいいアイデアがあります」
「う、うん。な、何かな?」
杏介の困った笑顔にも同調しない。瞬きすらしない。人形めいていると言っていい。
綴は杏介の目を覗き込むようにして告げた。
「読書感想部を立ち上げようと思いますので顧問になってください」
綴の声は独特だ。単語一音一音の発音ははっきりしているのに、語尾にはどこか掠れた余韻を残す。
「もちろん、私が部長です」
摑みどころがなくて不思議だが、妙な魅力に満ちている。
(うーん……もったいない)
杏介は綴の容姿と不可解な発言のギャップに混乱した結果、心の中で一言つぶやいた。
2
高等部二年二組、出席番号十七番。須賀田綴は鶴羽学園の有名人だ。
本名を知らずとも、顔を見れば誰もが「ああ、あの子か」と合点のいった声をあげるし、校舎が離れている中等部一年生ですら、初対面で「スガリ先輩」と声をかける。
それほどにインパクトのある事件を、昨年度起こしたからだった。
事件が起きたのは二学期が始まって間もなくの月曜だった。週末なんとかもっていた天気がとうとう崩れ、しとしとと雨が降っていた。
綴はいつもどおり柔らかい髪を三つ編みにし、登校した。普段との差異を強いて挙げるのであれば、手に黄色い花柄の傘と弁当袋を持っていた。
昼休みに綴が弁当袋を取り出すと、気づいた男子生徒が我先にと席を囲う。口々に「須賀田ちゃん」と声をかける。
学生の本分が学業だろうが、興味はいつだって恋愛ということだ。
「やった、本当に人数分持ってきてくれたんだ」
山育ちでスマートフォンも持っていない、テレビもまるで見ない、都会らしい都会に行ったことすらない。転校してきたばかりのミステリアスな美少女から、盛り上がる話題を引き出すのは、名古屋の男子高校生たちにとってはちょっとした試練だった。
しかし彼らはやっと人類共通の話題、食事から綴の興味を惹くことに成功する。しかも綴のほうから「週明けお弁当持ってくるので、ぜひみんなにも食べてみてほしい」と言うではないか。
このチャンスは逃せない。誰もがずいと顔を近づけ名乗りを上げた。それが先週末のことだった。
「うん。こんなに興味を持ってもらえると思わなくて嬉しかった。すごく頑張ったよ」
目は開いているけど寝ている。そんな印象を持たせるほど日頃表情を変えないのに、綴がはっきりと笑みを作った。
教室の一部は東山動植物園のサル舎のように盛り上がった。
「へぇ、須賀田ちゃんの好物持ってきてくれたんだ。作るの大変だった?」
期待に胸膨らんでいるのだろう。綴が「作ったというか、採ってきたかな? 週末、実家に帰ったときに」と謎めいた補足をするのも聞こえちゃいない。
「味はピークより落ちているけれど美味しいはずだよ」
「う、うん?」
「よく分かんないけど、まあいいや」
珍しく綴は自分の機嫌を表情に出していた。みんなに食べてもらえるのが嬉しいというよりは、純粋に好物を食べることができる喜びが顔に滲んでいた。
「ちょっと刺激が強いかもだけど」
そう一言添えてから生粋の長野県人、それも八ヶ岳の麓で育った少女はお重の中の〝ご馳走〟を見せた。
「うぎゃああああ!!?」
「なああああああ!!?」
「はいいいいいい!!?」
殺人現場でも見たような野太い悲鳴の三重奏が教室に響く。
「何これ!? 虫やんか!!?」
「しかも生きてる!!!」
中には廊下まで走って逃げ出す者まで出る始末だ。
「何って、スガリ?」
小首を傾げて、綴は答えた。
女子相手ならともかく、男子になぜここまで嫌がられるのか。これは男の仕事だ。地元だったら、これだけの量を女手一つで準備できたら数年は自慢していい。養殖でなく野生とくればなおさらなのに。そう、滔々と説明するが誰も聞いちゃいない。
「スガリって!?」
「地蜂の幼虫だよ」
うねうねと蠢くそれらの正体を知って、絶叫がそこら中から湧き上がる。綴は大きな目をますます大きくさせた。
「え、そんなに驚くことかな?」
長野県は四方を山に囲われた土地柄、ありとあらゆるものからタンパク質を確保する歴史がある。特に昆虫食のレパートリーは全国でも群を抜いている。
長野県人の名誉のために補足すると、物流の発達した現代において、昆虫は山暮らしの人々の日常食ではない。珍味として土産物屋に佃煮が置いてある程度だ。
無論、弁当には誰も持ってこない。生食は自己責任である。安易に真似をしてはいけない。
「噓やろ!? 食うのそれ!?」
もしかして俺たちがしつこく須賀田ちゃんに付き纏ったせいで、わざと嫌われるために虫なんかを持ってきたのではないか。
そんな一縷の望みを断ち切るように、綴はクリーム色の幼虫を摘みあげる。絹を裂くような叫び声が起きた。
「素揚げもいいけど、採れたてが一番美味しいよ?」
白魚や海老を指すのであればどれだけの男子生徒が救われたか。綴はCMのような文句のあとに、大好物をぽいっと口の中に入れた。虫を模したグミでも食べるような躊躇いのなさだったが、口に入れたのは本物の虫だ。
「マジでやめて! 俺らの須賀田ちゃんのイメージが! イメージが!」
こうして美少女転入生と称されていた綴はただの奇人に格下げとなり、「スガリ」という愛称が爆誕したのであった。
3
(っていう学園唯一無二な女の子の部活動かぁ……)
五限開始のチャイムをバックに、杏介は食堂の席についた。学食に残っている生徒はもちろんいない。皆授業に出ている。この時間、食事を取るのは授業のない教員だけだ。
(読書感想部ねぇ)
裏調理部とか言われなかっただけマシだと思うべきか。相手はお弁当に生の虫を持ってくる女子高生だ。
(いや、何するか全然分からないんだけど)
綴の話をまとめると、こうだ。
同じ本を読み、その読書感想文を書き、互いの感想を共有する活動がしたい。前の高校でも部活立ち上げのために奔走したが、人数不足で実現できなかった。
幸い、鶴羽学園では部員が一名でも顧問さえつけば部活動を認めてもらえる。互いの利害が一致するのだ。
ぜひ、直山先生に我が読書感想部の顧問になってほしい。
(宿題でもサボる人がいるのに?)
読書感想文。親、下手をすれば祖父母の代から綿々と続く夏休みの宿題の鉄板だ。宿題、つまり提出を義務付けられることでやっと成立している苦行と断言してもいい。
わざわざ部活動でやるものだろうか。
「珍しいものが好きな子もいるもんだよね」
「何言ってんだ。お前だって十分物好きだろうが」
独り言を拾う声が頭上から降ってくる。杏介は顔を上げた。
「森田先生、それに堤先生も。お疲れ様です」
「どうも」
遠巻きに「あ、三兄弟が揃った」という声があがる。その言葉には誇張と事実が入り混じっている。ランチトリオは、体格も顔も性格も三者三様。だが、パーツが似ている。
「あの、名前は分からないんですが、おたくの学校の先生で……確か見た目は坊ちゃん刈りで……眼鏡かけてて……ちょっと服装がカジュアルな……」と続けても、まだそれが家庭科の直山なのか、保健室の森田なのか、はたまた倫理の堤なのか判断がつかない。
仕方がないので、問い合わせをもらった学校事務の小田松が「背が高くておどおどしているのですか? 中くらいでヘラヘラしているのですか? それともちっちゃくてジメジメしているのですか?」と失礼な確認を取っているくらいだ。
「あ、直山。またお前半盛りにしたな」
白衣をぞんざいに椅子にかけた森田が眉をつり上げる。
「お前くらいの図体だったら、もうちょっと食べないとダメだ。貧血になるぞ。ほら、食え食え」
杏介が返事をする前に、自分の皿にあるレバニラの小鉢を押し付ける。生まれ持った性格か、この場では最年長だからなのか、森田は兄貴風をびゅうびゅうと吹かせる。
杏介は弱々しい笑顔で辞退した。
「大丈夫です。僕運動してないんで。ただ存在してるだけならこれくらいのカロリーで事足りるんですよ」
そう言って、自分の昼食を広げる。おくらののった豆腐に拳ほどの大きさのあんかけ卵、なめことネギの味噌汁。森田が指摘するように、ご飯は茶碗の半分しかない。一汁二菜のつましい食事だ。
「ヒヒ、直山くん。それ授業で言ってごらんよ。休み時間にスナック菓子を一袋空ける女子たちが悲鳴をあげるぜ」
引き笑いをあげたのは杏介の隣に座った堤だ。丸メガネの奥には腫れぼったい目が埋まっている。出っ歯のせいか、どこか可愛げのないマスコットめいた雰囲気を醸し出していた。
「いいんですよ。みんな、成長期ですから」
「そうやって調子乗らせるから、三十代になってどいつもこいつも太りだすんだよ。ちゃんと指導しろ」
森田に腹を小突かれ、杏介は「すいません」とつぶやく。堤だけが冷静に「いや君も指導する立場だろ、養護教諭」と指摘した。
病院食のような昼食を一人完了させた杏介は、お手製の校内バッグを広げた。グレーのフェルト生地で作ったカバンには、貴重品や授業で使うプリント、文房具といった諸々が入っている。学校にいる間の持ち歩きには専らこれを使っていた。
ちらっとカバンの隅から覗く紙片を一瞥する。原稿用紙。もちろん綴から押し付けられた読書感想文だ。
「あいにく手持ちがこれしかないので」と申し訳なさそうに渡されたのだ。いつもは複数部携帯しているのだろうか。
さすがにここで読み始めるのも憚られる。杏介は別のものを取り出した。
「あ、また始めるのか」
「すぐ終わりますから」
森田の呆れた顔を流して、杏介はぽん、ぽんと毛糸の束を置く。
「学食のカウンターに行ったら、食器洗いのスポンジがぼろぼろになってたんですよね」
厨房のおばちゃんに話を聞くと、ストックも切れているらしい。最後の一個のスポンジなので月末まで頑張って使っているとのことだった。
「なのでこの時間でちょっとアクリルたわしを作ります」
文字どおり、アクリル毛糸で編んだたわしのことだ。デザインも様々あり、慣れていれば十分、二十分で作ることができる。
鶴羽学園のモチーフである翼の形に作ろうか。杏介はくさり編みを始めた。
「好きだね、お前も」
「はい。手芸部顧問ですから」
話しながらも、杏介の手は止まらない。かぎ編み棒を巧みに操る。少し背を丸めてくるくると毛糸を編み込む顔には、自然と笑みが浮かんでいる。
「もう廃部でしょ?」
「ううっ」
無意識に呻いていた。堤は悪びれもせず、自分のきつねうどんを啜る。
「やっぱり、一人も入んなかったんだ」
「そうなんですよねぇ。しかも教頭先生からはサッカー部の手伝いをしろって言われちゃってて……」
「やるの? っていうか、やれるの?」
「できません」
「だよねぇ」
堤は相槌を打ったあとに「ごちそうさまでした」と小さくつぶやいた。麵類とはいえ、手品のような早食いだ。
「なので、他のところの手伝いを探して断ろうと思うんですけど……」
杏介のその一言に、森田のスクエアフレームと堤の丸フレームが怪しく光った。
「よし、直山。男子ハンド部来い」
「直山くん。うちのインド哲学及びエスペラント語研にするべきだ。文化系だろう?」
始まった、と杏介は内心悲鳴をあげる。鶴羽学園はとにかく部活が多い。綴が目をつけた「顧問さえつけば部員一名からでも部活立ち上げ許可」という校則の賜物である。おかげで教壇に立たない森田も顧問を務めるし、果ては堤のように弱小部をまとめ上げて顧問を担当する者さえいる。
「安心しろ。お前に運動は絶対させない。体育館の隅っこに座って裁縫してていい。時々ドリンク作ってくれるだけでいい。最近女子マネに逃げられたんだよ」
「刺繡していいんですか!?」
魅力的な言葉に杏介は目を輝かせる。
「おいおい冷静になれ、直山くん。男子ハンド部の部員は二十人超えてるんだぞ? 一体何キロの水筒を体育館に運び続けなくちゃいけないか分かるだろう」
堤の指摘に森田は顔を歪めた。
「気づいたか。これだから察しのいい奴は嫌いなんだ」
「それに引きかえうちは楽だよ。お茶も出る。ディベートゲームの議事録書いてもらうくらいの雑用だから」
「やめとけ、やめとけ。インエペ研に行った奴の半分は元の人格を失うんだぞ?」
そこからは当事者置いてきぼりの攻防だ。
杏介は完成したアクリルたわしの出来を確認した。うん、悪くない。持ち手までつけたそれを持って学食カウンターへと避難する。
(やっぱりどこも人手不足なんだなぁ……)
部活だけではない。登下校の見守りに見学者対応、生徒の生活相談、組合のアンケート集計だってやる。一年目は大目に見てもらえていた先生のお仕事は、ホテルビュッフェのようにずらりと杏介の前に並んでいる。
この期に及んで「部の新設」だなんて言える空気ではない。
「やっぱり断ったほうがいいかなぁ」
「えぇ? なんの話?」
三角巾を頭につけた学食のおばちゃんが声を張る。厨房はいつも騒がしい。
「いえ! なんでもないです!」
「そうお!? じゃあいいわ! これ。ありがとうね、先生! 助かったわ!!」
破顔という言葉が似合う表情につられて、杏介も目尻を下げる。
振り返ると森田と堤が机の下に潜っていた。側を通った野間垣の視界に入らないようにしている。いつものことだった。
4
放課後。杏介は一人、家庭科準備室の自席に座っていた。
目の前には綴の感想文がある。
杏介はまだクラス担任を持っていない。家庭科の実習記録ならまだしも、人の作文を読むことなど、家庭教師のバイト以来の経験だ。
「夏目漱石の……『こゝろ』かぁ」
今どき、本の感想などSNSで簡単に発信できるだろうに。というか読書感想文自体、インターネットに転がっている文章を転記して済ませる猛者がごろごろいる。
わざわざ原稿用紙に鉛筆書きしてきた労力を思うと、杏介の口元は自然と緩む。
(須賀田さん、字が綺麗なんだなぁ)
止めハネがしっかりしている。筆圧の濃さも見ていて心地よい。悪筆揃いのレポートに日々苦労している杏介は原稿用紙を拝んだ。
「失くしちゃうといけないし、家で読むのはやめたほうがいいかな……」
掃除はできるだけ頑張っているが、同棲している恋人の持ち物が異様なほどに多い。うっかり紛れたら最後、ジョーンズ博士がペトラ遺跡へ聖杯を探しに行ったときくらいの冒険を覚悟しなくてはならなくなる。
「よーし」
杏介は小さな声で意気込む。
その気合を切り崩すように、夕陽差し込む家庭科準備室のドアが開いた。
「直山ぁ〜!」
さっさと帰っておけばよかったと後悔しても遅い。カレンダーを確認する。なんということだろう。今日は金曜日だ。
「森田先生? どうされたんですか?」
一応、白々しい問いを入れてみる。森田は目を細めた。ちょっと強引だが、人のいい笑顔が覗いた。
「お前こそどうされたんですかだよ。週末だぞ、放課後だぞ。週報は書いたな? じゃあ行こう」
杏介に返事をする間を与えない。こう見えて水球でインハイ経験あるからね俺、と日頃嘯いているだけあって、森田は一回り大きな杏介をものともせずに引っ張っていこうとする。
杏介は慌ててリュックに原稿用紙を突っ込んだ。
「絶対連れていくって約束した連中がいるんだ。お前、きっとびっくりして腰抜かすぞ」
「えぇ……」
「なんだ? 付き合っている彼女に義理立てか?」
「そんなのじゃないですけど……」
腰を抜かすと言われてわくわくするほど驚きを求めているわけではない。飲み会は苦手だ。森田のように酒が強いわけでもないし、日常の食事に気を遣うほど胃は弱い。伏見や栄の飲み屋をハシゴする元気もない。ないない尽くしで申し訳がなくなるくらいだ。
「僕の知っている人なんですか?」
「たぶんな」
「たぶんって」
一応、同棲中の彼女がいる身なのに、一方的に「絶対連れていく」と約束するほどの相手とは、一体誰なのだろうか?
(僕、就職するまでこの土地に縁なんてほとんどなかったんだけどな)
森田に急かされ、小走りに日泰寺参道を駆け下りる。杏介が通った拍子にソバ屋の暖簾がぱたとはためいた。
「なんだよ、そのしょげた顔は」
「見てのとおりですよ……なんで連れてきたんですか」
口を開けば恨み言しか出ない。杏介は胃を押さえた。
名古屋城の脇を抜けて伊勢湾まで続いている堀川は、このあたりでは街明かりを受けて蛍火のような光を放っている。錦橋の角には、すでに酔っ払いたちの濁った歓声が飛び交っていた。
「別にライオンの檻にお前を放り込むわけじゃないだろ。とって食われるとでも思ってるのか? クラスメイトだぞ? お前、クラスメイトに食われたことあるか? ないだろ」
森田は不思議な説得を挟みつつ、酒の匂いだけで胃痛を発症している杏介を奮い立たせようとする。白衣を脱いだ森田の派手めのスーツは夜の街によく似合っていた。
錦橋の上を、名古屋駅まで歩くサラリーマンが絶えることなく流れていく。この流れになんとか乗って帰れないか、いやいっそ橋の下をマットレスの敷かれた船が通ってくれたら、絶対飛び込むのに。
杏介が不毛な妄想を繰り返しているうちに、待ち合わせの場所に到着した。
「え、噓、本当に直山くんだ。あの身長、間違いないよ」
「うわー。直山、久しぶりだなぁ」
橋の向こうからはしゃいだ声を上げる男女。その後ろからついてくる男の姿がある。彼らが待ち合わせていた人たちらしい。あっちもちょうど着いたところのようだ。その顔を見て杏介は記憶が蘇った。
「えーっと、北倉くんと静寺さん、それから……えっと」
杏介は一年以上同じ高校にいたことはない。転勤族の親に物心ついた頃から引っ張り回されたせいだ。
高校生にもなれば下宿か何かに入れてくれればいいものを、数奇な運命か、親の行く先行く先でうまい具合に転校の手続きが取れた。だから高校時代、杏介は何度も転校の挨拶をする羽目になったし、身にまとう制服はコロコロと変わった。
友達百人どころか千人だって夢ではない境遇だ。だが、千人も友を作れるほど杏介は社交的な性格ではない。顔と名前を一致させるのでいっぱいいっぱいだった。
そんな杏介の境遇を理解してか、名前を忘れられた男は静かに名乗った。
「隣のクラスだった梶冬彦だ。すまないな。急に来てもらって」
冬彦の名前はすっかり忘れていたが、三人がサッカー部に所属していたことだけは杏介もちゃんと覚えていた。副部長が北倉慎吾で、静寺唯はマネージャーだ。
「お、お久しぶりです……」
スクールカーストの頂点、学生生活の花形たちにいきなり引き合わされても、盛り上がる話題など何一つない。三人とも高校時代に培った自信と実力に磨きをかけ、杏介と同い年とは思えぬほど泰然自若としている。
まさか東京の高校で一緒だったメンバーと、名古屋の地で再会するとは。森田が毎日のように飲み歩いていなければ実現しなかった会だった。
「名駅のバーで隣に座った北倉くんに、たまたま出身高校聞いてびっくりしたんだぜ。お前が前に指折り数えながら言ってた高校のうちの一つだったんだから。年もお前と一緒だって言うだろ、まさかと思ったんだ」
森田は可笑しそうに髪を搔く。ジョッキ一杯で出来上がっていた。酒が入るといつも以上にオーバーアクションになる。
杏介はため息を押し殺した。この先輩の厄介なところは、すぐ酔うくせに、店中の酒瓶を空にする勢いで飲んでも決して倒れることなく、浮かれた状態をキープできることだった。
「そうですか……」
場を繫ぐように白湯を飲む。アルコールを入れないと正直やっていられないが、あとが怖い。
「直山。俺、丸の内で働いてるんだ。桜通線の」
「そうなんだ。北倉くん。こっちで就職したんだね」
「正確には東京で採用されて、こっちの支社に配属になったんだけどさ」
北倉慎吾は喉を鳴らしてビールを飲み干した。がっしりした体には薄くストライプの入ったスーツがよく合っている。
ストレートに社名は教えてくれなかったが、話の端々から全国規模のメーカーで働いているということが窺えた。
「梶は違うんだけどな」
慎吾の言葉に冬彦は頷いた。
黒のポロシャツにパーカー、ワークパンツという格好は、なんだか慎吾とは正反対だ。髪の手入れもを通した程度で、写真であれば高校生だと押し通せそうな容姿をしている。垢抜けない感じだけ見れば、中学生といってもいい。
ただ、冬彦は沈黙を心細いとも思わない、重厚で澄んだ気配を発している。隣に座った杏介は自然と背筋が伸びる心地がした。
(そうだ、梶くんは確かこんな感じだった)
杏介は誰にも見えないところでこくこく頷いた。高校時代、クラスの違う冬彦と話す機会などまったくなかったが、冬彦のほうが杏介のクラスによく出入りしていたので思い出すことができる。
当時人気だったサッカー選手の髪形をみんながこぞって真似する中、冬彦は硬そうな黒髪を短くするだけで済ませていた。頓着しない性格なのだろう。切れ長の目は昔と変わらず、浮ついた空気を断ち切るような喋り方とも似合っていた。
それは今も変わらない。いかにも高校時代の延長線上にいるといった感じがする。短かった前髪は少しうるさくなっていたが、帽子のつばのような役割をしている。髪の奥から澄んだ目が覗くと、同性の杏介でも視線を奪われる。
杏介の惚けた顔を面白がるように、慎吾が唐突に尋ねた。
「こいつさ、今何やってると思う?」
「ええ……」
突然のクイズに杏介は情けない声を上げる。こういう質問は苦手だ。当てないまでも、失礼にならないような返事を考えるが、自分でも情けなくなるくらいにまったく閃いてこない。
ひとしきり手のひらを指で打ったあと、自信なげに「……小説家?」と聞く。
一瞬、場の時が止まった。
「小説家!!」
「直山くん、天才だよ!!」
慎吾と唯の笑い声が爆ぜる。冬彦とは初めて会うはずの森田もテーブルを叩いて笑っている。
酒は一滴も飲んでいないのに、杏介は耳まで赤くなった。
「俺が小説家か」
冬彦はまんざらでもなさそうな──それでもやっぱりニコリともしなかったが──顔で杏介の珍回答を繰り返した。
恥ずかしさでどうにかなりそうだ。先ほど食べたサザエの壺焼きの穴に入れるものなら入りたい。そんな図体じゃないが。
「うん。梶くん似合うんじゃないかな、小説家」
ビールのグラスを両手で持った唯が力強く頷いた。慎吾と冬彦の間に座っていると、小柄な唯は埋もれてしまいそうだ。
唯は学生時代は真っ黒に日焼けしていたが、今は抜けるような白い肌をしている。それは綴といい勝負だ。流行りに乗った服を着て、髪を器用に結い上げていた。
「花言葉とかいっぱい使う物語がいいよ。女性受けすると思う」
「花言葉?」
いきなり具体的な指定が飛び、森田は不思議がる。唯の代わりに冬彦が答えた。
「俺は今、知多で花卉栽培をやってる。花農家だ」
花農家、と杏介は復唱する。これまた自分とは縁もゆかりもない世界だった。
「今は何作ってるの?」と、店員が運んできた肉じゃがの大皿を受けながら唯が訊く。
「カーネーション。母の日向けの」
冬彦はぶっきらぼうに答えた。
こんな寡黙な男が、あの愛らしい赤い花の世話をしているとは。つばの大きな帽子を被り、ビニールハウスでせっせと花を摘む冬彦の姿を思い浮かべる。想像の中でもやっぱり目付きは険しかった。
「こいつのすげえところはさ、跡を継いだ花農家が別に実家なわけじゃないってとこなんだよ」
「え?」
「院推薦も出てたんだ。普通に就職活動したってそれなりの会社に行けたと思う。なのに、『頼まれたから』って理由だけで傾きかけてた農家を一人で継いだんだよ。大学はスポーツ科学だったから、当然花のことなんか何も知らない。勉強も一からやり直しだ」
「すごい」
心からの感想だった。
「愛知に行くって言ったときにはびっくりしたけどさ、こうしてまた三人近くで住めるなら結果オーライだよな」
慎吾は冷酒に手を伸ばした。
「三人?」
「俺は滅多にこっちに来ない。市内は車が多いし、運転が荒い」と冬彦は口を挟むが、杏介が気になったのはそっちではない。
杏介は慎吾の言葉をそのまま疑問にした。
「もしかして静寺さんも名古屋で就職したの?」
杏介の視線から逃れるように、唯は右にいる慎吾と目配せしあう。
「ええっとね……」
なんだかとっておきの秘密を打ち明けるような顔だった。
「……私と慎吾、明後日結婚するの」
烏龍茶が入った冬彦のグラスの中で、氷が小さく悲鳴をあげた。同じタイミングで、唯は慎吾のいる席と反対側に視線を送ったように見えた。
(あれ……?)
糾弾を逃れたいと願うような唯の眼差しが、杏介に高校時代の噂話を蘇らせる。
(この三人って確か……──三角関係だったんじゃなかったっけ?)
先ほどまで不鮮明だった高校時代の慎吾たちの姿がはっきりと像を結んだ。同じような背丈の慎吾と冬彦。喋りっぱなしの慎吾に、時折冬彦が頷いている。セーラー服姿の唯が困ったように微笑んで、二人の後を追いかける。
(──それこそ夏目漱石の『こゝろ』のように)
杏介は一人、生唾を飲み込んだ。
不要かもしれないが、『こゝろ』のあらすじを少しだけ紹介しよう。作者はもちろん、元・千円札の人だ。
主人公の「私」は訪れた鎌倉で、かつて友人を亡くした「先生」と出会い親交を深める。
「先生」は時折、人の性根、つまり心について思わせぶりなことを発言するが、具体的なエピソード、要は己の過去について決して語ろうとはしなかった。
そんな中、「私」は父親の危篤を知り、国へ帰ることになる。そこで「先生」からの長い手紙を受け取るのだ。「先生」の遺書である。
遺書には「先生」と「先生」の妻となる女性、そして「K」という友人の間で起きた三角関係が、当時の会話や動作を細かく再現しながら記されていた。そして、最後には「先生」の結婚を機に自殺した「K」への懺悔が綴られていたのである……。
(なんでこんなタイミングで……)
『こゝろ』の読書感想文を押し付けてきた綴が悪いのか、修羅場再びとなっている飲み会に連れてきた森田が悪いのか。どちらを責めることもできず、杏介は蛸飯を口に入れる。味わう余裕はなかった。
「いやぁ〜、しかしおめでとう。まさかまさかの話でびっくりしたけどな」
森田はいつのまにかピッチャーでビールを頼んでいる。明後日、結婚式で倒れるほどに酒を飲まされるはずの新郎のグラスに、溢れんばかりの黄金色のアルコールを注いだ。
杏介も遠慮がちに祝福の言葉を口にする。結婚の話は森田同様、今聞いたのが初めてだったし、もちろん式にも披露宴にも呼ばれていない。こっちにいることすらお互い今日確認したのだ。
別に悲しむことではないのだが、ちょっと胃が痛む。杏介の視線はいつだって事実の中に転がっている気まずさのほうにだけ行ってしまう。
「直山がこんなに近くに住んでるって、もっと早くに知ってればなぁ」
慎吾は唯に軽くぶつかって話しかける。体格差のある二人だ。唯が怪我をしそうでひやひやする。
「結婚式場の名前言って、ああ、あそこなんだねって反応した奴はお前が初めてだよ」
「職場からは徒歩圏内だから……。すごく綺麗だよね、アンゲルス教会。夜にはライトアップされるし」
同意しつつ、杏介は冬彦の顔を確認する。結婚の話を聞く前と変わっていないことが逆に怖かった。
「な、唯。式場いろいろ迷ったけど、やっぱりあそこでよかったんだよ」
「そうだね。こっち来てから三人で遊んだところとかもいいかなって思ったんだけど」
「どこだ、そこ?」
未来の夫はどうにも頼りない返事をする。唯はちょっと頰を膨らませた。
「ほら、慎吾も気に入ってた、あそこ。外のお花畑も綺麗だし、これならちょうどいいよねって話してた……」
その言葉に合点がいったらしい。慎吾は「プランナーがしきりに勧めてたあそこか」と大きく頷いた。
「確かあれだろ? なんとかフォーができるってお前はしゃいでいたもんな。でも冬彦がアクセスも悪いからやめておいたほうがいいんじゃないかって言って、今の式場に決めたんだっけ……そういえば、結局やるのか? なんとかフォー」
「サムシングフォー。やるよ! もうハンカチとか用意してるもの。慎吾のお母さんにも時計の件、一緒にお願いに行ったじゃない!」
「そうだっけ?」という惚けた返事に「そうなんです!」と眉をつり上げる。新婚らしい可愛い喧嘩だが、ここではよしてほしい。冬彦の顔を直視できない。
唯は杏介に向き直る。顔は元の穏やかな表情に戻っていた。
「ね。もし直山くんさえよければ、二次会だけでもどうかな?」
「いやいやいやいや! 悪いよ!」
誰に何がどう悪いのか、さっとは思い浮かばなかったが、反射的に杏介は首を振った。数ヶ月しか一緒にいなかったクラスメイトたちとテーブルをともに過ごす図。どんなに楽観的に想像しても、良いものにならなかった。
「会場に連絡するか? 立食だから一人増えたところで何も言われないだろう」
冬彦は携帯電話を取り出していた。今どきの若者らしからぬ、折り畳み式の古いものを使っている。唯は酒で赤くなった頰をグラスで冷やしながら、「梶くんが二次会の幹事をしてくれてるの」と杏介に話を補った。
「ビンゴの景品が安く仕入れられたから予算も余り気味だ。飛び入りだからロハで……」
これはまずい。杏介は慌てて手のひらを見せる。
「ご、ごめん……日曜日は、その、用事が」
我ながら何とも下手な言い訳だと思った。森田も声なき声で「ないわ」と呆れている。
「そうか」
冬彦の返事は竹を割ったようだった。非難めいたトーンは一切ない。
しかし森田は遠慮なくつっこんでくる。
「直山。お前な、人のめでたい席を断るほどの用事ってなんだよ」
素直に「今年度のベア作りのための素材探しです」と言ってはいけない。そんな失言をしたら最後、この出来上がった先輩は杏介の腑抜けた根性を叩き直すために一晩中酒を飲ませてくるだろう。会がおひらきになったあと、木挽町通りの飲み屋という飲み屋を曳き回されるに違いない。杏介は必死で自分の手に意味のないモールス信号を打ち込んだ。
その慌てふためいた様に、意外な人物が小さく吹き出した。
冬彦だった。
「慎吾、直山にあっちに来てもらったらどうだ」
その言葉に慎吾は目を輝かせて頷いた。
「ああ、いいなそれ。直山。俺たち明日も飲むんだよ。独身最後の馬鹿騒ぎだな」
「絶対楽しいやつだ!」
慎吾と唯の結婚に、この場で最も縁もゆかりもない森田がなぜか食いついた。
「行く行く! 絶対行く。直山は首に紐つけて引っ張ってでも連れていく!」と勢いづく。いや、杏介は実際に襟首を引っ張られていた。
「無理しなくてもいい」
タチの悪い酔っ払いが跋扈する席で、冬彦は唯一の良心だ。一分間隔で助け舟を発進させてくれる。
さすがにここまで譲歩された誘いを断るほど無粋ではない。杏介は視線を右へ左へやりながら了解した。
「決まりだな。明日、覚王山駅に集合。三次会の下見も兼ねてあそこらへんで飲もうかってことになってるんだ。開始は三時」
「は、早いね」
酒よりもお茶とケーキという感じがする開始時間だ。まさに昼酒、まさに自堕落。酒好きの森田は喜びで両手を挙げたが、慎吾は「だよなぁ」と眉を下げる。
「もっと遅くでいいって俺は言ったんだぜ? なのに結婚式本番に寝坊したら洒落にならないって冬彦が譲らなくてさ」
「当然だろう」
冬彦の言葉に迷いはない。慎吾は唯越しに親友の頭を突いた。
「お前は昔から何でもかんでもきちっとしすぎなんだよ。覚えてるぞ、インハイ予戦の試合、十分前に集合って監督に言われてたのに、一人だけ一時間前に来てただろ。当然一番乗りだと思ってた唯が度肝抜かれたって」
「迷うかもしれないから早く行っただけだ」
冬彦らしい素っ気ない返事に慎吾は肩を揺らす。唯も目尻を下げて頷いた。
「あのときは大変だったよね。試合は晴れたけど、待ってる間に雨降ってきちゃって」
「……そうだな」
杏介は冷や汗が止まらない。冬彦に愛想がないのは重々承知の上だが、その短い言葉の端々に、何か触れてはいけないものが混ざっている気がする。
五月雨の中、慎吾のいない崩れた三角形の中、二人は一体何を話していたのだろう。冬彦は今よりももっと口数が少なかったし、唯もやはりお喋りなほうではなかった。絶え間ない雨音を、冬彦と唯はずっと黙って聞いていたのだろうか。
(ダメだ、ダメだ)
杏介は自分の中に浮かんだ想像を必死で搔き消した。人の恋愛を娯楽ドラマのように扱ってはいけない。
「失礼」
少し時代遅れな着信音に冬彦が反応した。一滴も酒を入れていない体はきびきびと動く。酔っ払いがごった返す店からあっという間に外に出ていった。
「……きっと二次会の会場の人だね」
冬彦の背中を見送りながら唯がつぶやいた。
「梶には頭が上がらない」
「うん。本当に」
聞けば、冬彦は慎吾と唯の結婚を、まるで自分のことのように陰日向なく手伝ってくれているのだという。式場選びから付き合い、二次会の幹事も嫌な顔一つせず引き受けたし、披露宴の飾り付けに使うのは冬彦の育てた花なのだそうだ。
業者を使うと高くなる。種類は限られてしまうがうちのでよければ、と申し出てくれたらしい。
「梶くん、飾るお花にもアドバイスをくれたりしたの。例えば……あ、いけない。もう名前忘れちゃった……」
ええと、ええと、と唯は視線をあちこちにやるが、アルコールで鈍った頭はどうにも単語を拾い上げられない。
結局、笑顔でごまかした。
「……あるお花をね」
「おい」
「だってぇ。じゃあ、慎吾覚えてるの?」
「俺に花のこと聞くなよ」
くつくつと慎吾は肩を揺らす。「唯も知ってるだろ? 花なんてバラとひまわりくらいしか分からないってことくらい」と付け足した。
「俺も最初はそんなもんだった」と森田も神妙な顔で頷く。どうして詳しくなったのかを聞くと長そうなので、杏介は話の先を唯に促した。
「あるお花をね、テーブルフラワーにしようかって言ってたの。最初に候補に挙がってた会場にも咲いてるし、話題になるかなって。そしたら花言葉を知ってる人からするとあまりいい印象にならないからやめたほうがいいって」
「へえ」
杏介は感心した声をあげた。
「花言葉って、意外にネガティブな意味のものもあるんだよ。昔は手紙に花を添えることで『ああ、この人は本当はこう思っているんだ』って伝えたんだって。私が選ぼうとしてた花の花言葉は〝私を無視しないで〟だったらしいの」
と付け足す。
「そ、そうなんだ」
表情にこそ出さなかったが、杏介は宿命めいたものを感じて嫌な汗をかいてしまう。それを、冬彦が断ち切ったという事実に敬意すら覚えた。
「それで梶くんが監修してくれた明後日のテーブルフラワーがこれ」
「え、うわ、すごい」
華やかとは言い難い。だが、緑と白でまとめられた花々は、唯のたおやかな見た目とよく合っている。
「これなんかね、〝感謝〟って意味があるんだって。ごめん、やっぱり名前は忘れちゃったんだけど……」
スマートフォンの画面を拡大し、唯は小さな花の連なりを見せる。森田は意味深なことを言っていたくせに、興味がないのか、さっと一瞥するに終わったが、杏介は食いついた。
「静寺さん……この写真、貰えたりしないかな?」
「いいけど。お花好きなの?」
「花だからってわけじゃないんだけど……。刺繡のパターンにそのまま使えるやつだ、これ。蔦の感じとかすごくいい」
「さすが家庭科の先生だね。やっぱり手芸が好きなんだ。そういえば直山くん、昔も休み時間によく編み物してたもんね」
冬彦が空けた席越しに、お互いスマートフォンを通信させ合う。唯と杏介の二人がそつなく画像を送り、受け取る様を見て慎吾はしみじみつぶやいた。
「やっぱそんなもんだよなぁ」
「何が?」
「梶だよ。あいつ一向に機械に明るくなる気配がなくてさ。携帯も全然変えようとしないんだ。おかげであいつにだけいちいちメールしなくちゃいけない」
森田が意外そうな声をあげる。
「へえ、彼、そういうの得意そうな顔してるけどな」
「畑仕事のほうが性に合ってるってことかもしれないですね」
慎吾が深く相槌を打ったところで、話題の人が戻ってきた。
「トラブルか?」
一瞬仕事の顔を覗かせた慎吾に、冬彦は首を横に振った。
「問題ない。タイムテーブルを向こうが勘違いしてたから、頭から打ち合わせただけ」
「はー。やっぱりお前のその性格、花相手に使うべきじゃないぜ。俺の横にいてほしい。今相手してる客、話聞かないんだよ」
ぼすん、と乾いた音がする。今度は唯から慎吾にぶつかりにいったのだ。
「あのね。これから慎吾は一人でもしっかりしないとダメなんだよ。本当、なんでもかんでも適当なんだから」
「うるへー」
そこにデザートプレートがやってくる。チョコレートで書かれた「結婚おめでとう」という文字に、わあと唯は声を漏らした。
「いつの間に?」
「さっきトイレ行くついでに」
そう森田は片目を瞑る。芸能人でもない大人がやる仕草ではないが、妙に様になっていた。
「実行犯は俺だけど、首謀者は彼だぜ? 本当は予約が必要らしいんだけどな。ゴリ押しした」
森田は回ってきた烏龍茶を冬彦に差し出した。ペコと礼をして冬彦はそれを受け取る。
「梶くん、ありがとう」
「おいおい、ケーキは明後日もたらふく食べるだろ」
「もう、プランナーさんの話聞いてなかったの? 主役の二人って意外とご飯食べられないんだよ。慎吾もご馳走は明日済ませておいてね」
反論の余地もないのか、慎吾は黙って頭を搔いた。森田は杏介に「なんか北倉くん、結婚したら尻に敷かれそうだよな。唯ちゃん大人しそうなのに」と耳打ちする。実際そのとおりだろうと、杏介も頷いた。
向かいのテーブルも盛り上がっている。輪の中心にいるワンピース姿の少女が誕生日らしい。店中から手拍子を貰い、照れた顔でそこら中に礼をする。
和やかな雰囲気の中、婚約者たちは居ずまいを正した。
「何から何までありがとうな。梶」
「梶くんのおかげで結婚式、大成功だね」
無愛想な知多の花農家は首を小さく横に振った。
「大したことじゃない。大事な二人の式なんだ──」
親友とかつて恋心を寄せた相手に告げる。
その言葉は、冬彦らしく短かった。
「心から嬉しく思う。結婚おめでとう」
5
デザートプレートを空にしたあと、幸いにも会はお開きになった。飲み足りない森田は次の店に行こうとそわそわしていたが、「朝は仕事だ」という冬彦の鶴の一声で解散の流れになったのだ。どうせまた明日会って飲むのだ。誰も反対しなかった。
「ただいまぁ」
アパートのドアを開けると、こてんと倒れたハイヒールに出迎えられた。
杏介は狭い廊下の奥の暗がりを見つめる。学生街である八事日赤には珍しい、1DKのアパートだ。人の気配はない。
「と、いうことは……」
シンプルなキャンバス地のスニーカーに、カットの浅いポインテッドトゥパンプス、モカシン、スリッポン、バレエシューズ風。色とりどりの靴のほとんどは朝、杏介が並べ直した姿のままだ。最近お気に入りだと言っていたストラップシューズだけがない。
「出かけたままだね」
今日は迷うことなく靴を決めて出ていったらしい。
「ああ〜、またぐちゃぐちゃだ」
杏介はさして広くもない部屋の中を、くぐったり乗り越えたりして進んだ。地雷原を行くかの如く、慎重に歩く。油断すれば共用スペースにはみ出た恋人のワンピースやアクセサリーを踏みつけ、そのまますっ転ぶことになるからだ。
片付けという言葉を知らない、というか知らないふりをする恋人は、目を離すと家をガラクタで埋めてしまう。
見れば、ドアのそばにあるはずの大型スーツケースがなくなっている。日帰り出張用の小丸号でも、通常サイズの中丸号でもなく、十日ほどの旅にも耐える大丸号がいない。これは長くなるぞ、と杏介は顔を引き締めた。
別に喧嘩したわけではない。恋人の絵馬は仕事柄、突然家を空けることが多かった。
気を取り直し、杏介はキッチンに向かう。口の中には、慎吾に「ちょっとだけ」と飲まされた冷酒の味が残っている。ハンドミキサーとすり鉢の間に置かれた本を取り出した。
「じゃー、これっ」
読み込みすぎてクタクタになったレシピ集だ。掛け声とともに開いたページには、香り豊かな飲み物が写真とともに紹介されていた。
「ロシアンティ。いいね」
絵馬の買ってきた紅茶缶を開ける。湿っぽい匂いが鼻に届いた。
お湯を沸かす間に散らかったテーブルを片付ける。広げられた地図や置いていった小物の類から見るに、どうやら行き先はシドニーらしい。
「またお土産が増えるなぁ」
杏介は気重なため息をついた。絵馬はすぐに物を持ち帰る。部屋のキャパシティなど配慮しない。
実際、机の上には薬局で見かけるカエルまで混ざっていた。一体どこから拾ってきたのか。
「これは……見なかったことに」
杏介は自分で縁の飾り付けをしたテーブルクロスの皺を直した。
冷蔵庫からジャムを取り出す。そういえばどこかで聞いた話だが、夏目漱石は大の甘党だったそうだ。羊羹やアイスといったお菓子を愛し、ジャムも大好物だったとか。紅茶に入れたかは定かではないが、なんだか親近感を覚える。
温かい飲み物をお供に文字をたどる作業は、杏介の体を包んでいた変な緊張を和らげてくれる。
「さて、今度こそ」
厚手のマグカップから上がる湯気を顔に受けながら、杏介はリュックから綴に渡された原稿用紙を取り出した。
「やりますか」
やっぱり綺麗な字だな、と杏介は感心する。
「偉いなぁ、本が好きなんだなぁ。確かに須賀田さんの雰囲気って図書館が似合いそうな感じがするけ……ど……?」
消しゴムを何度も当てた跡を愛おしそうに見つめていた杏介は、並ぶ文字を読み取って固まった。苦手だった英文問題を読むような、渋い顔になった。
ゆっくり飲もうと決めていたロシアンティについ、手が伸びる。
「えーっと?」
手で口元を押さえ、考えられる可能性を思案してみたが表情は一向に晴れない。とうとう一人、眉間の皺に手を寄せる。
「うーん……」
唸るのも仕方がない。鶴羽学園の有名人・スガリさんが書いた読書感想文は、出だしからぶっ飛んでいたのだ。
「〝死の直前、『K』はなぜ、開いた襖を閉めなかったのでしょうか?〟……何それ?」
「K」とは『こゝろ』の中の登場人物の名前である。主人公の「私」とは面識がない。「先生」の遺書の中で初めて語られる男の名前だ。
寺の息子であった「K」は「先生」の友であり、また恋敵でもある。二人ともお嬢さんに恋していたが、「先生」が先にお嬢さんに結婚を申し込んだため、「K」の恋は破れた。そしてある朝、「K」は自ら命を絶つ……。
『こゝろ』は読書感想文でも定番の一冊だ。学校指定の課題本でもよく挙がっている。読まずともタイトルくらいは誰もが一度は聞いたことがあるだろう。
だというのに。杏介は一人、困惑の声を漏らした。
「ふ、襖……?」
読書感想文を書くのであれば登場人物、ここでは「私」や「先生」の行動や発言に着目したほうがいい。それが読書感想文のセオリーだろう。
そのほうが読んでいる己の感情とリンクさせやすいし、書きやすいのだ。
杏介は、柔らかい髪が印象的な女子高生の、奇抜な着目点に盛大に戸惑った。狐につままれるような心地で鉛筆書きの文字を追う。
「〝下宿の描写が気になって仕方がないので情報を集約し、間取り図を作成しました〟……って、本当に描いてある……」
二枚目の原稿用紙だ。ご丁寧に方位まで添えてあった。確かに「先生」と「K」の部屋の間には襖がある。
杏介は肩の力が抜けるような心地がした。
「読書感想文じゃないよ、これ……」
杏介だって学生の頃、読書感想文くらい書いた。どの本にしたかはすっかり忘れてしまったが、少なくとも全部文字で書いたことだけは覚えている。
「じ、自由すぎる」
心中をそのまま吐露し、杏介はぽそぽそと小さな声を出しながら先を読み進める。一瞬、玄関チェーンをかけ損なったんではないかと気になったが、後回しにした。
「〝『先生』の遺書の中で『K』が自殺をする夜の描写は、情景を散らすように記されています。例えば『先生』の枕の位置。東枕を習慣としていた『先生』はその夜、何の因果か西枕にしてしまったと己の行動を後悔しています。あえて声に出して言いたい──だからどうした〟いやスガリさんの感想文が〝だからどうした〟だよ!」
思わず原稿用紙に向かって叫んでしまう。マグカップの中のスプーンが小さく跳ねた。
「あわわ……」
杏介は慌てて、半分ほどしか飲めていないロシアンティを流し台に戻した。
これは飲み物同伴で読んではいけない代物だ。大惨事になる。直感ではない。経験をもって断言できることだった。
なんとか落ち着きを取り戻す。杏介は綴の指示に従って、「K」が自殺した夜に「先生」がどういう姿勢で寝たのかを間取り図で確認した。ちなみに参照図番号は①だった。
「襖に向かって寝たってことが直接書かれていないってことは分かったけど……それってそんなに気になることかな?」
杏介は綴が書いた人間のシルエットを見つめる。なんと顔が描いてある。漱石風の髭まで付け足されていた。何度目になるか分からない「読書感想文って……こんなんだっけ?」という疑念が頭を過ぎる。
「なんというか……」
杏介は一生懸命似合う言葉を探す。
とにかく独特な着目点なのだ。万人受けするかは微妙だが、惹かれるものがある。
もっと簡単な表現を使えば「くだらないけど気になる」だった。
「〝そして、件の襖は『いつも立て切ってあるKと私の室との仕切りの襖』という『先生』の記述から、普段は閉めていたことが分かります〟……もっと引用すべきところがあるんじゃないかなぁ……」
よく読んでいると褒めるべきか、いや、そういう問題ではないと突っ込むべきか。杏介は頭を右へ左へ傾けた。
「〝『先生』は夜半に目を覚ましました。寝る前に閉めたはずの襖が『この前の晩と同じくらい開いて』いたからです。幅は二尺(約六十センチ)ほど。人が通るにはやや狭く、季節は火鉢が必要なほど寒い時期です。そんな不可解な行動をしたのが誰なのかは、推測するまでもないでしょう〟……」
杏介はもう一度綴が描いた間取り図を見る。「先生」の部屋の襖は一室にしか繫がっていない。「K」の四畳間だ。
夜中、下宿部屋の襖を触るのは、当然、部屋を借りている書生たち二人だろう。「先生」はいつの間にか襖が開いていたことに気づいて起きたのだ。
「つまり……」
杏介は答えを口に出した。
「襖を開けたのはもう一人の書生……自殺した『K』」
襖をわずかに開け、眠る親友の姿を見つめる男の姿が思い浮かぶ。浮かべている表情は陰鬱で、不気味だ。
なんだかミステリー小説の後半を読んでいるような気分になった。
杏介は手元に『こゝろ』の本が欲しくなった。綴のいうとおり、「K」が襖を開けたことを難解な文章から読み取ってみたくなったのだ。
「『こゝろ』って、そんな話だっけ……?」
杏介の考える『こゝろ』の感想文は、もっと「先生」の視点に寄っている。友人である「K」の気持ちを知りながらも、抜け駆けをしてしまった後悔、そして「K」の死を目の当たりにしたときの絶望。そういったものに、目が行くのだと思っていた。
「スガリさんは……違うんだ」
頭の中で綴の姿を呼び起こす。膝丈のスカートから細い足を覗かせる少女は、いつもどこかぼうっとしている。昼行灯といってもいい。
学園中をパニックに陥れた「スガリ事件」だって、クラスの女子に泣かれなかったら、涼しい顔で生蜂のこを完食していただろう。
肝の太い、摑みどころのない生徒だと思っていた。まさかこんな探偵のような思考回路を持っているなんて。
「〝ですが、問題は襖を開けたことではありません〟」
綴は原稿用紙の上にはっきりと自分の考えを刻んでいた。
「〝閉めなかったことです〟」
冒頭の問いかけだ。
「〝部屋が隣同士なので朝、襖が開いていたら嫌でも『先生』は『K』の死体を拝むことになります。なかなかイカした目覚ましです。というか、一生安眠できないでしょう(実際、『先生』は『K』の骸を前に強いショックを受けています。『黒い光』という表現は、中二っぽくてすごくいい)〟……スガリさん、これ、文豪・夏目漱石作だからね?」
綴の文章は淡々としているが、妙に滑稽だ。ロシアンティを退避させてよかった。杏介は笑わないように口元に力を込める。
だんだん独り言が激しくなっているが、気にしてなどいられなかった。
「〝『K』は明らかに『先生』にトラウマを植え付けにかかっています。証拠は『先生』の遺書にこっそり書いてあります。『K』の部屋から去る際、『襖に逬ばしっている血潮を始めて見た』と〟……どういうこと?」
杏介は訝しむような顔で原稿用紙をめくった。
「〝思い出してください。その夜『先生』は襖に向かって眠っていたことを〟」
視界に飛び込んできた文字に、心臓をじかに摑まれた。
そんな気がした。
杏介は口元を手で覆う。逡巡するように瞼を瞬かせたあと、先を読んだ。熱っぽい声が出た。
「〝『K』は襖を閉めなかった〟」
──想い人と結婚する親友は、白い顔を晒して眠っている。
──男は黙ってそれを見つめている。
「〝静かに自分に刃を向ける。そうして、死んだ〟」
──生命活動を停止させるには十分な激痛。
だが、杏介の想像する「K」は、鋭い目を細め、口の端を上げている。愛想のない男だったが、そうかこんな顔をして笑うのか、と思わせるほどの、表情。
今までそんな情景を考えたことは一度もなかった。
タイミングだ、タイミングが悪いんだと自分を納得させるように繰り返す。
「〝襖を染め上げるほどの血しぶきが立つ〟」
綴の結論に寒気を覚える。深く息をすることができない。
「〝きっと見届けたのでしょう。『先生』の顔に、文字のない遺書が届いたことを〟……」
杏介は無言で立ち上がった。昔、保育園で教わったお化け退治の歌を叫ぶように歌いながらアパートの電気という電気をつけて回る。途中、電気コードに足を引っ掛けて悲鳴をあげた。
「本当は怖い夏目漱石の『こゝろ』……」
茶化さないとやっていられなかった。
スガリさんこと、須賀田綴の感想文は続く。
杏介は退避させていたお茶を流しの上で飲み干した。ジャムはだいぶ下に溜まってしまったらしく、クラクラするほど甘い。やっと心が落ち着いてくる。
杏介は最後の原稿用紙に手を伸ばした。
「〝遅くなりましたが、私の読後の所感を述べます〟」
杏介は目を丸くした。丸くしただけで済めばよかった。
「〝この作者、やりよる〟──いや相手、夏目漱石だからね!?」
隣近所に聞こえそうなほどの大声が出た。因果関係はないと信じたいが、同居人のこさえた漫画の山が音を立てて崩れる。
近代文学の父といってもいい相手になんて偉そうな口をきくのだ、この高校生は。怖がらせたいのか笑わせたいのか。もう滅茶苦茶だ。
「もー……」
杏介は牛のような声をあげながら先を読み進める。個性的な読書感想文は、綴の落ち着き払った声で脳内に再生された。
「〝冒頭申し上げたとおり、この作品は部屋の間取りや、『K』自殺の夜の出来事が非常に読み取りづらく書かれています。私はこれを作者が意図して行ったことなのだと確信しています〟……。どういうこと?」
眉を下げた情けない顔が少しだけ元に戻った。杏介の目は、角のはっきりした文字の並びをなぞっていく。
「〝本作では人の本性が些細な行動や痕跡に反映され、描写として世界にちりばめられています。『K』が自殺した夜の記述のように。落ち着いて目を凝らした者にだけ、相手の本当の『こゝろ』が見える。──そう、夏目漱石は教えたいのではないでしょうか?〟」
なかなか読ませる文章だ。杏介はようやく感心した。
(部活にしたいってだけのことはあるのかな?)
やっと周囲に意識を払えるようになってくる。
換気扇からは隣人の吸うタバコの匂いが漏れてきている。そこら中灯けた電気が今はうるさく感じられた。
「〝『先生』は『K』を義理堅く、侍のような男と思っていましたが、実際はそうではないのです〟はは、なるほどね」
そういう考え方もあるのか。
杏介は顔を綻ばせようとする。そして──やめた。
頭からどうしても離れてくれないのだ。綴の感想文を読んで浮かんだ情景が。死んだように布団の中で眠る北倉慎吾と、その姿を襖越しに見つめている梶冬彦の姿が。
「梶くん……」
「心から嬉しく思う」という冬彦の手短な台詞。あれは、本当は胸の内にある渦巻く嵐のような感情を封じて、やっと絞り出せた言葉だったのではないだろうか。
確証はない。裏付けるような証拠もない。
あくまで杏介の胸を過ぎった嫌な予感にすぎなかった──。
6
「じゃあ、えーっと。めでたい」
森田のしまりのない乾杯の音頭を皮切りに、バチェラーパーティは始まった。
「覚王山で飲むなら絶対にここ」と森田が一行を引き連れてきたのは、雑居ビルの三階にあるこぢんまりとしたパブだ。名前は〝フィッツ・ロイ〟。
床もテーブルも磨き上げられたオーク材でできており、オレンジ色がかった照明の光を受けてつやつやと輝いている。
「見てのとおり狭いし、酒の一つ一つの量は少ないし、フィッシュ&チップスは脂っこいけど、……まあ、トータルで見ると良い所だろ」
「ちょっと。良い所だろ、だけでよかったんじゃない?」
森田と同い年くらいの店主がバーカウンター越しに嚙み付く。髪を結い上げ、澄んだ目をした女性だった。胸には「薫」という金縁の名札をつけている。服装は無地のシャツに黒のスキニーパンツ、腰巻のエプロンとユニセックスなチョイスだった。
「俺のレビューは正直だから」
「はいはい。森田先生にはいつも助けてもらってるから、これ以上は言いませんよ」
常連と店主らしいやりとりだ。置いてきぼりを食らった同い年三人衆に、薫は顔をくしゃくしゃにして笑いかける。近所の世話焼きなお姉さん、という印象を抱かせる表情だった。
「こんにちは。自分の家だと思ってゆっくりしていってね。酔っ払われる前に言っておくと、うちのトイレは一階まで降りないとないから。男女共用で、扉開けると個室三つもあるけど他のテナントと共有なの。だから、使うときはちゃんとノックしてマナーよくお願いね。もし満室で出てくる気配がなかったら、店を出て通りを右に行った一つ目の角に、もう一つ兄弟テナントビルがあるわ。窪地に立ってるビルだから入り口に迷うかもしれないけど、行けばだいたい分かるわよ。外付け階段が派手な色してるから、それが目印。オッケー?」
まさかトイレ一つでここまでの説明を受けるとは思わなかった。杏介はやや面食らう。他の店舗の客を気にしているし、昔何かトラブルでもあったのかもしれない。
「オ、オッケーです」
正直に言えばあまり分かっていなかった。職場からは目と鼻の先の距離だというのに、全然イメージが浮かばない。
覚王山は名古屋の一等地に籍を置く住宅街だ。どこを見ても家とマンションが並び、時折思い出したように寺院や神社が顔を出す。
スイカ割りの要領で目隠しをしてぐるぐる回れば、自分が一体どこにいるのか、慣れた人間でも分からなくなるような地域だ。外に出たら十中八九迷っちゃうだろうなぁと杏介は嘆息した。
パスタ麵をそのまま丸揚げにしたチップスをかじりながら、ちまちまとビールに口を付ける。
話題はもっぱら、明日冬彦が幹事を務める二次会のことだった。
「え? 梶、お前、司会進行の原稿まで二次会会場に渡してあんの?」
「もちろん」
冬彦は森田に勧められるがままに頼んだカブトビールを口に含み、答える。慎吾はタバコで焦げたような茶色い天井を仰いだ。演技じみた仕草だった。
「心配性ここに極まれりだな」
「そんなこと言うな。俺は何があっても明日は二次会までちゃんとやりきってほしいって思ってるんだ」
「へいへい、プランナー様。そうだよ、梶、お前ブライダルでも絶対出世するぞ」
しばらくして、早々に出来上がった慎吾は、冬彦の両肩を摑んでゆすり出す。頭をガクガク揺らされたまま、冬彦は尋ねた。
「俺が花を育てるのはそんなに変か?」
「変じゃないけど……それって楽しいのか?」
「楽しい。時間が流れているって感じがする。死ぬなら土の上がいい」
冬彦の返事は即答に近かった。視線は誰とも合っていない。杏介には気がかりでたまらない反応だった。
「ふうん。そんなもんかね」
理解はしているが、納得はしていないという顔だ。気を取り直して、慎吾は杏介に話題を振る。
「直山は? 仕事楽しいか?」
「えっ?」
答えに迷った。杏介が鶴羽学園の先生になったのは、教壇に憧れたからというよりも、昼間からミシンを動かしたり編み物をすることが保証されているからだ。そのまま言うのは躊躇う理由である。
ただし、入ってみて分かったことだが、教職は授業だけが仕事ではない。事務作業も多いし、会議も多い。針を動かすことが好き、という根拠だけではその一つ一つの業務に喜びを見出すことなど到底無理だ。
愛知初の男性家庭科担当と囃し立てられても、正直プレッシャーしか感じない。
「……直山?」
「あ、えーっと」
杏介はとんとんとんと自分に信号を打って返事を探していたが、いつの間にかまったく関係ないことを考えていることに気づいた。
つい最近頼まれた仕事を思い出したのだ。読書感想部の顧問である。
(こんなときに思い出すものじゃないんだけど)
綴の感想文の中にあった〝この作者、やりよる〟というフレーズが何度も何度も頭を巡る。自分の声ではなく、綴の落ち着き払った声で再生されてしまう。連想ゲームのように西枕のくだりの追撃を受け、杏介は思わず手にしたグラスをテーブルに置いた。
やはり毒気を抜かれる。
「高校の先生でしょ? 楽しいよ」
杏介の微妙な表情を見て、誰もそれ以上つっこもうとはしなかった。
「あれ?」
トイレから戻ってくると、人が減っている。
「梶くんは?」
赤ら顔の森田が答える。手にはレーズンバターがあった。
「お前のちょっとあとに便所に立ったぞ。すれ違わなかったのか?」
はて、と杏介は首を傾げた。
薫の説明どおり、数分前にトイレに行こうと席を立った杏介は、テナントビル一階の奥まったところにトイレを見つけた。自分が入ったことで確かに個室は満室になったが、自分が一番に用を足し終えて個室を出た。そして〝フィッツ・ロイ〟までの帰り道に冬彦の気配はなかった。
「だったら、兄弟テナントビルっていうのに歩いていったんだろ」
慎吾のその言葉に、グラスを磨いていた薫が頷く。
「うん。酔いざましにはちょうどいい距離だと思うわ」
「梶くん、そんなに酔ってるようには見えなかったけど……」
明日は朝から結婚式だ。さすがに今夜は知多の家に帰ることはせず、近鉄名古屋駅裏のホテルに泊まると言っていた。昨日飲んでいない分、森田と慎吾に積極的に酒を勧められていたが、酒の回ったそぶりは見せていなかった。
「あいつも一見しっかりしていそうで、意外とポンコツだからなぁ」
この違和感は何だろう。杏介はむかむかしはじめた胃を押さえる。
「あ、これ冬彦だ」
メールの着信を告げる短いバイブ音。慎吾は割れた画面をそのままにしているスマートフォンのロックを外した。
「なになに……〝迷った〟?」
冬彦らしい短いメッセージだ。
しょうがないなと慎吾は携帯を耳に当てる。
「おーい。今どこに……ああ、それが分からないから迷子っていうんだよな。こっからどう出たか分かるのか? 駄目かよ。地図アプリ開いてって、お前まだガラケーだったな……」
折り畳み式の携帯を片手に、覚王山の住宅街をさまよっている冬彦の姿が頭に浮かぶ。杏介の頭の中の冬彦の表情は、迷子のくせに不思議とどっしりしていた。
「え? 何だ? 悪い、なんか聞こえない。よく一緒に行った場所まで出るから迎えにきてくれ? 珍しく気弱だな。どこだそれ? あ、駄目だこれ。この音、電池切れるやつ」
慎吾の携帯のバッテリーが切れかけているらしい。それでも慎吾は慌てることなく「直山、お前の電話番号を梶に言え」と自分の携帯を突き出す。杏介は時限爆弾でも預かったような面持ちでそれを受け取った。
「もしもし、梶くん。番号言うからかけ直すか、梶くんの番号教えてくれるかな?」
『不要だ』
冬彦の返事は相変わらず短い。電池切れのアラームに急かされている感じもあった。
「うん?」
短すぎて不安になる。
「不要って……」
『慎吾に、これだけ伝えてくれないか』
冬彦は杏介の声を押さえ込むように告げた。
『すまない。でも、もう決めたことだ』
受話器の向こうからは風を切る音が聞こえる。相当、足早に歩いていることが伝わってくる。杏介は上ずった声をあげた。
「え、待って。梶くん」
無情にもそこで音は途切れた。バッテリーが切れたのだ。
しかし杏介には同じタイミングで冬彦が通話を切ったとしか思えなかった。ジリジリと浅く胸を焼かれるような感覚が襲ってくる。杏介は青い顔で暗くなった画面を見つめた。
「梶、何だって?」
鼻に酒の匂いが届くのが不快だ。少し左手を打ってから、杏介はありのままを答えた。
「いや……なんか、決めたことだって伝えてくれって。あと、北倉くんに謝ってたよ」
「俺に?」
慎吾は腕を組んで数秒考えたが、「なんのこっちゃ」と疑問を露わにする。
「俺、あいつに謝られるようなことされたかな?」
「ははあ、これはあれだ」
森田が口を挟む。グラスをテーブルに置き、白い歯を見せる。目は愉快そうに細まっていた。
「これから唯ちゃんを攫いに行くってことだな」
縁起でもないことを言わないでほしい。杏介は無言で抗議した。
「え、今どき花嫁泥棒?」
薫も三流恋愛映画のクライマックスを見るような顔をしたが、一蹴する乾いた声があがった。慎吾だ。
「まさか。あいつほど義理堅い男もいないですよ。あれだけ結婚式の準備も手伝ってくれてるんだし」
「なるほど。見た目のとおりってわけか。じゃあ、直山の聞き間違いかな?」
ガキじゃないんだから戻ってこられるだろう。おつまみを追加してのんびり待つか。場を包む緊張感を過去のものにするようなやりとりが繰り広げられる。
(そんな声じゃなかったけど……)
耳にはまだ冬彦の短く刺すような声が残っている。ついさっきついた傷のように、杏介に痛みを主張していた。
なんだか冬彦のことがかわいそうになってくる。しっかり者で、みんなに信頼されている男。酔って放った言葉かもしれないが、迎えにきてほしいという願いさえ、なかったことにされようとしている。
慎吾はまったく席を立つ気配がない。冬彦を心底信頼しているからあえて何もしない、ということなのかもしれない。でも杏介は受容できなかった。
「直山、どうした? お前、酒そんなに飲んでないよな?」
杏介は青い顔で手のひらを突く。
「……本当に?」
掠れた声で問いかける。
グラス一杯のビールと不安が、ぐちゃぐちゃと頭の中を搔き回す。時折顔を出すのは、昨日読んだ読書感想文の文句だ。
取り憑かれたように、杏介は綴の言葉を諳んじた。
「〝落ち着いて目を凝らした者にだけ、相手の本当の『こゝろ』が見える〟」
「え?」
酔っ払い二人の反応は鈍い。唯一、薫だけが目を見開いた。聞き返してきた顔を正面から見てしまったが、かまわない。杏介は立ち上がる。制止の声がかかる前に〝フィッツ・ロイ〟を飛び出した。
気づいたのだ。冬彦はトイレに入りすらしなかった。杏介がトイレにいる間、廊下に続くドアを開け、個室が空いているかを確認する音はなかった。
杏介は自分の考えを声に出した。
「梶くんは、どこかに向かおうとしている」
兄弟テナントビルなんかではない。ちゃんと別の目的地を持っている。冬彦の言葉を借りれば、「もう決めて」いるのだ。
「それに、もしかしたら……」
口にするのも恐ろしい可能性だ。
立派な門構えの家々が続く道を駆け抜ける。滅茶苦茶に走ったが、見慣れた日泰寺参道に飛び出すことができた。そこで立ち止まった。
「でも……どこに?」
冬彦の行き先などさっぱりだ。見当すらつかない。体力もあっという間に底をつき、歳弘法堂の前で息を切らす。
「どうしよう……、どうしよう……」
もし自分の直感が正しければ、冬彦はこれからとんでもないことをやろうとしている。人の恋に何かを言えるほどの人生経験はないが、冬彦の決意を思うと、いてもたってもいられない。
杏介は表現ではなく、実際に両手で頭を抱えた。
「なんとかして静寺さんと連絡を……? いや、戻って北倉くんのスマホを充電したほうがいい……?」
弘法大師ののぼり旗の前をぐるぐる歩く。何度、自分の右手を木にしてキツツキしても、アイデアは全然降ってこない。
「あぁもーう、この役立たず!」
天を仰いで自分の鈍い頭を嘆く始末だ。
一人道端で奇声を上げている事実はこの際無視だった。止まっていると不安に体を乗っ取られそうになる。
「こんなことしている間に、梶くんに何かあったらどうすればいいんだよ!」
自分自身に向けた罵声を発したところで、名前を呼ばれた。
「直山先生」
まさかこんなタイミングで知り合いに見つかるとは思わなかった。杏介は情けない声とともにずっこける。尻餅をついたあたりで、一体誰に呼ばれたのかを理解した。
発音ははっきりしているのに、どこか摑みにくい特徴的な声。間違いない。
杏介は恐る恐る振り返った。
「す、須賀田さん?」
そこに立っていたのは、鶴羽学園高等部二年二組出席番号十七番、須賀田綴だった。
7
「こんばんは。せっかくの土曜日にこんなところで何されてるんですか?」
道に座り込んでいる杏介を気にもせず、綴が尋ねる。
「えっと、そっくりそのまま聞き返していい? ……と言うか、そんな格好で何してるのかな?」
そんな格好、と杏介が言うのも無理はない。綴の装いはいつもと全然違う。
綴はにこりともせずにスカートの裾を摘んだ。
「ああ、これですか」
レース襟のワンピースに腰丈のフリルエプロン。日常お目にかかることは滅多にない組み合わせだというのに、コスプレ感は全然ない。
「曾祖母のワンピースなんです、これ」
時代錯誤な格好を誇るようだ。
「エプロンとポシェットは祖母ので。二人に無理言って借りました」
「……ひいおばあさんもご健在なんだね」
なるほど、道理で浮いた感じがしない。これは本物の制服なのだ。笑顔とフワフワとした発言を振りまくことが仕事のメイドではなく、雇い主の身の回りの世話を生業にした正真正銘のメイドのいでたちなのである。
「それで何をしてるの?」
「〝べんがら〟でバイトです」
「〝べんがら〟って……揚輝荘の?」
「はい」
綴は水飲み鳥のように頷いた。
覚王山にはかつて超弩級の別荘が存在していた。松坂屋初代社長・伊藤祐民が造らせた豪邸群、揚輝荘である。そのうちの一つである洋館がまだ残っているのだ。
今は市の有形文化財として管理されている。綴の言う〝べんがら〟とは揚輝荘の一角にある喫茶店を指していた。
(うち、バイトは原則禁止のはずだけど……)
バイト許可の特例を受けるため、手間のかかる申請を綴がしているとはあまり思えない。
胃痛のタネを増やされた杏介は、ひそかに息を飲む。ところが、そんな杏介の心中など意に介さず、綴が杏介に近づいた。
「先生」
日本人なら思わず後退したくなる間合いだ。それからじいっと杏介の顔を覗き込む。
「何かトラブルらしいですね。事情を聞かせてください。私にも、手伝えることがあるはずです」
杏介は綴の遠慮ない視線から逃れるように目を泳がせた。もしかしたら全て杞憂で終わる話だ。それに、きっかけは君の読書感想文だなんて言えるはずもない。
「直山先生」
黙り込んだ杏介に綴は少し語調を強める。それだけではない。空気は夜になっても暖かいままの日々が続いているというのに、冷え切った杏介の手を包むように握ったのだ。
「須賀田さん! ダダダダメだってこんなこと!!」
ショックのあまりまともに話せなくなる。こんなところを誰かに見られたら杏介の教師人生は二年で終了する。恋人とも破局間違いなしだ。
「お願い」「後生だから」「やめて」そんな言葉を口走るが、綴は眉一つ動かさない。杏介の視界いっぱいに整った顔を晒した。
「先日申し上げたとおり、腰を抜かした人にはとびきり優しくしろとおじいちゃんが言っていました。落ち着いて、私に今何が起きているのかを教えてください」
うっかり全てを委ねてしまいそうになる、どんと構えた口調だ。年下、それも学校の教え子のものとは思えない。
「は、はい……」
杏介は上の空な声で返事をした。
アンゲルス教会に併設された事務所の中で、杏介と綴は待たされていた。ひととおりの事情を聞いた綴が、とりあえず式場に行ってみようと提案したのだ。
しかし、参加者リストに名の載っていない男と時代錯誤な給仕が何を言ってもすぐに話は通らない。新郎新婦のフルネーム、出身高校あたりまでを告げることでやっと、担当する二人の女性プランナーと話をすることができた。
揚輝荘の中ならしっくりくる格好も、街中に出ればただの仮装だ。しかし、綴は「着替えのための時間をください」などと言わなかった。
「お待たせいたしました。北倉様、静寺様のご友人様の件でいらっしゃいますね」
「はい。その、梶くんは、今日ここに来たりしませんでしたか?」
「それは……」
教えていいものかと若い女性プランナーが目配せをする。白髪染め跡がキラキラ光っている年上の上司は、なんてことないように答えた。
「はい、午前中にいらっしゃいましたよ」
「一体、何をしに……?」
「明日使うテーブルフラワーを持ってこられたんです。花農家をされているとか」
そうです、今の時期はカーネーションを作っているんです。なんて話を脱線させるわけにもいかない。杏介は短く同意する。
「売り物じゃないとおっしゃってましたけど、すごく立派なんですよ。今は傷まないようにバックヤードの冷蔵室に入れてます」
これにも杏介は頷いた。
「でもあれ、本当にいいのかしらね?」
ぽつりと、年上のほうが漏らした。度の過ぎた子どもの悪戯を見るような、悩ましい顔つきをしている。
「川辺チーフ、何か気になることでも?」
川辺と呼ばれた上司は「いいえ……知らぬが仏ってやつよ」と口走る。すかさず綴が口を挟んだ。
「どちらかというと〝言わぬが花〟では?」
部下と比較すると協力的な姿勢を見せてくれていた川辺から、笑みが消える。一言余計だったのだ。
手遅れな空気が流れていく。杏介は胃を押さえた。
「そのお花、見せていただくことってできますか?」
「いたしかねます」
望み薄な反応である。しばらく綴は川辺に食らいついたが、結局、冬彦についての情報を得ることはできなかった。
「今、式を挙げているカップルが来てしまうので」と教会前の交差点に放り出されてしまう始末である。
「うーん、あれ。絶対何か隠してますね」
懲りない綴は「よし先生、バックヤードに忍び込みましょう」と踵を返す。迷うそぶりは一切ない。潔すぎる教え子に杏介は悲鳴をあげた。
「やめとこう。お願いだから」
これ以上騒ぎを大きくして、もし学校にクレームが入ったら。週明けの全教員会議で野間垣が何を言い出すか分かったものではない。杏介は慌てて自分のスマートフォンを出した。
「ほら、これが問題のテーブルフラワーだよ。静寺……花嫁さんに写真を貰ってたんだ」
「なんと!」
綴は野球審判がストライクを下すようなポーズをした。
「ナイスプレーです、先生」
綴はたどたどしい手つきで写真を拡大する。綺麗に飾り付けられた花の山を凝視した。テレビCM一本分ほどの間が空く。
「……花嫁さんはこれ、何も言わなかったんですか?」
「うん。最初選ぼうとしていた花の花言葉が〝私を無視しないで〟っていうちょっと印象の良くないものだったから、〝感謝〟の意味のあるものに取り替えてもらったんだって」
「取り替えて?」
綴は訝しむように杏介の言葉を繰り返した。
「取り替えきれてないですよ。これ」
「え?」
「見てください。このクリームがかった白色の花。カリンカです。花言葉は〝感謝〟じゃない。〝私を無視しないで〟ですよ」
「なんだって!?」
予告なしで頭に冷水をぶっかけられたような心地だ。まさか、あの冬彦が親友に意地悪をするだなんて。
花農家で、花言葉に詳しい冬彦が自ら選び直した花の花言葉を間違えるはずがない。
信じられない。そう言いかけて、止まる。
「梶くんの……本当の心」
思えば他にも思い当たることはあった。梶が二人の結婚を本当は祝福できていないという仮説を持ったからこそ、浮き上がってくる事象だ。
例えば二次会の司会。冬彦は会場の係に自分の話す司会進行の原稿まで渡していた。あれは、ただの心配性ではなく、もし式の日に自分が不在になっても会自体はちゃんとやりきれるようにと考えてのことだったのではないか。
渡した読書感想文を読んだからこそ出てくる節回しに、綴は一瞬目を丸くした。
「心。……そうですね」
そして顔をうっすらと綻ばせる。
「梶さんはちょっと調べれば露見してしまうことをやっている。私、重要なのはそこなんじゃないかなって思うんです」
テーブルフラワーの件も、毎日花と接するプランナーの川辺はあっさり見抜いていた。いい加減な慎吾や、冬彦の言葉を鵜吞みにする唯でなければ、もっと早くに発覚していただろう。
綴は駅へと足を向ける。
「梶さんはきっと、怒ってもらいたいんですよ。喧嘩を売っている、って言ってもいいかもしれません」
よく一緒に行った場所に来てほしい。冬彦が慎吾に向けた言葉が蘇る。それは、生きているからこそできる所業だ。
綴は瞳の色を深くする。頭上の空のような、移ろう世界を切り取った色だ。
「先生。もう少し詳しく話を聞かせてください。梶さんが電話でなんて言っていたのかを具体的に。伝えたかったことが分かるかもしれません」
きっとこんな目で読書感想文を書いているんだ。杏介は確信を抱いた。
冬彦は明かりの落ちた庭園に一人佇んでいた。
今年の春は暖かい日が多い。だからだろう、来月が旬であるはずの花は、もう一様に夜空に向かって咲き誇っている。花弁の色はそのまま海に続くようだ。
スーツ姿だ。オフィス街に溶け込む格好は、シートレインランドの観覧車が見えるレジャースポットでは、間違いなく異物となる。手に冷え冷えとした色のナイフを握っているならなおさらだ。
あたりに人はいない。閉園時間はとうに過ぎている。冬彦自身、監視カメラの死角をついて忍び込んだのだ。
ところが、冬彦の耳は音を捉えている。気のせいではない。遠くから人の叫び声が聞こえる。
それはだんだん大きくなり、やがて冬彦は自分の名を呼んでいるのだと気がついた。
まさか、と身を強張らせる。ヒントなどほとんど与えていない。あの短い伝言で生来の楽天家が気づくとは到底思えない。
では、唯のほうが花言葉に気づいたか。そのほうがあり得る話だった。
しかし冬彦の前に姿を現したのは、予想すらしていなかった人物だった。
「直山?」
「梶くん! 待ってくれ!」
長い手脚をうまく使えていないといった走り方だ。一生懸命こちらに向かってくる。
しかも、その後ろを悠々と付いてくる者がいる。お下げ髪が愛くるしい、時代錯誤なメイドだ。スニーカーの杏介とは違い、ローファー履きだというのに綺麗な走行フォームだった。
開口一番、杏介は吠えた。
「駄目だよ! 自殺なんて!!」
息のあがった情けない顔とは裏腹に、まっすぐな眼差しは冬彦に誤魔化す隙を与えない。
「……どうして」
冬彦は硬い表情のままに尋ねた。
「どうして、ここが分かったんだ? 聞いたのか? なら、慎吾たちは……?」
「いません。皆さんの会話からほぼ自力で絞り込みました」
杏介は息が上がってしまって使い物にならない。代わりに三つ編みの少女が答えた。「スガリと言います」と奇妙な苗字を名乗り、冬彦につむじを見せるように頭を下げる。
「いや、それ……」
何かを正すように杏介は口を開いたが、メイドは無視して続ける。まだ杏介はまともに喋ることはできないが、これだけは言わないといけないとばかりに、「僕の……学校の……。二年生の、須賀田綴さん」と切れ切れに補足した。
なるほど、と冬彦は頷く。そして綴に先を促した。
メイド姿の綴は口を開いた。自分で解いた数式を説明するような語調だった。
「梶さん、あなたはまず親友の結婚式の前に死ぬことを決意した。そして、死に場所を決めた。ここは三人でよく訪れた思い出の場所だそうですね」
名古屋港ワイルドフラワーガーデン。メーカーの工場や倉庫が並ぶ埋立地に作られた庭園だ。周りの物々しい建物のほうが噓のように、欧米の古き良き造園が再現されている。
「確かにここは良い所です。風もあるし土の匂いもする。山がないのが残念ですが、花に看取られるというのも乙でしょう」
少し強い海風が、綴の前髪を揺らす。はためくエプロンとは対照的に、すとんとしたラインのスカートは微動だにしない。生地が厚いのか、だとしたらどれくらいの太さの糸を使っているんだろう。杏介はこんなときでも気になった。
一方の冬彦は無表情のまま佇んでいる。否定の言葉もない。綴は続けた。
「ですが、花畑に沈む自分の骸を、万が一にも見てほしくない相手がいた。想い人の静寺さんです。だからあなたはあれこれ言って、静寺さんをここから遠ざけようとした」
無意識に杏介は口を開けていた。綴は昨日の飲み会も、今日のバチェラーパーティも、もちろん六年前の教室にもいない。杏介の話という限られた情報から、冬彦の心情を見抜いている。鋭い洞察力──いや、読解力だった。
「で、でも」
杏介は生徒の推理を遮る。
「どうして梶くんは静寺さんがここに来てしまうと思ったんだい?」
「自殺場所と結婚式場の第一候補が被ってしまったからです。どっちが先だったのかは分かりかねますが」
綴は答えた。明日の天気を告げるみたいにあっさりとしていた。
「先ほど申したとおり、ここは良い場所ですからね。お天気にさえ恵まれれば、屋外の挙式は写真映えもするでしょう。私は写真が苦手なので、そこにはあまりコメントできないですが……。テーブルフラワーにもちょうどいい、青い花もありますし」
ちょうどいい。それは唯の言葉だ。綴はつやつやとした花弁を撫でる。
「ブルーボネット。サムシングブルーにちょうどいい登り藤。花言葉は、……〝感謝〟」
「それ……」
取り憑かれたように杏介は指さした。結婚式にふさわしい短い花言葉。それは冬彦が唯に教えたテーブルフラワーの花言葉だ。
「そうです。もともとテーブルフラワーに予定していたブルーボネットのほうこそ〝感謝〟という花言葉なんです。梶さんはカリンカとブルーボネットの花言葉を入れ替えて静寺さんに教えたんです。聞かれてとっさに答えたことだったのかもしれませんけどね」
冬彦はまだ何も言わない。代わりに遠く県道をゆく車の音が聞こえた。
「逆に最期に話をしたい人もいた。静寺さんを奪った、親友の北倉さんです。可能性は本当に低いと分かっていながらも、あなたは北倉さんにこの場所のヒントを与えた」
よく一緒に行った場所で待つ。親友に告げた文句は、あまりにも短くて簡単すぎる。死ぬ気だなんて、どうして汲み取れようか。
まるで「K」の名言、「覚悟ならない事もない」だ。ここから友人の死を防いでくれと言われても、簡単にできる話ではない。
「知多にお住まいだそうですが、あまりこちらには来られないそうですね。名古屋駅からそう遠くなく、サムシングフォーに使える青い花が咲いていて、結婚式も挙げられる、カップルじゃなくても普通に遊びにいくこともできる、とくればここかなぁと。私の知識ではなく、教会の隣のお店で聞いた話なので、偉そうには言えないですが。来たのはやっぱり式場の下見で……ですか?」
「違う」
ようやく、冬彦が口を開いた。
「去年、慎吾たちの引っ越しが終わったあとで、遊びにきた。季節は、今くらいだった」
冬彦は手のナイフを持ち直す。くるりと刃を向けた瞬間、杏介は短く悲鳴をあげたが、冬彦は柄を杏介に差し出しただけだった。
慌てて杏介は手を伸ばして受け取った。二度と返さないとばかりに、刃物と冬彦の距離を取る。
「やって来たのがお前だとは」
「うん。それは……僕自身もびっくりだったんだけど……」
剣吞な物を持て余していると、横から綴がガーゼハンカチを貸してくれる。「ありがとう」と礼を述べ、杏介はナイフを隠した。
「慎吾は?」
「……たぶん、まだ飲んでる」
「これは俺の一人相撲か?」
杏介は少し躊躇ったが、噓はつかなかった。
「そうだね」
大きなため息が一つ、吐き出された。
「直山、お前だったらどうする? 好きな相手が、大切な相手と結婚する。式の準備を手伝ってくれと頼まれる。二人とも今の俺の気持ちを、探ろうともしない」
「辛いと……思う」
もっといい表現が浮かべばいいのに、と杏介は唇を嚙んだ。
冬彦の胸の内は、そんな簡単な言葉に落とせるものではない。確信を持って言えるが、でも、ちょうどいい言葉はすぐには出てこなかった。
冬彦の鋭い瞳を凝視できない。杏介は視線を地面に落とした。
「式は成功してほしい。胸を張って言えることだが、あの二人はいい奴らなんだ。祝福されて当然だ。だが、俺はどうしてもその式に出られない」
胸の中の一番奥に隠していたものを取り出すような間が空く。冬彦は軋む音が立つほどに歯を嚙み締めてから、自分にしか聞こえないような声量でつぶやいた。
「二人が結婚するという未来を──受け入れられない」
〝私を無視しないで〟。明日、祝いの席の上でカリンカの骸が声もなく横たわっている。そんなビジョンが杏介には見える。
主張が薄いと思っていたテーブルフラワーは慎ましやかな新婦のためのものではない。残された男への献花になるのだ。
たまらず杏介は口火を切った。考えて発言したというよりは、口が勝手に言葉を紡いでいた。
「……明日、地震がくればいいのにね」
一瞬、冬彦は何を言われたのか分からなかったらしい。虚をつかれたような顔をした。
洗いざらしの黒髪が風に揺れる。瞼を閉じると、冬彦の顔はぎょっとするほど優しく見えた。
「子どもがよくやる妄想だな。今のご時世じゃ、冗談でも許されない」
杏介はチラと自分の携帯を見た。森田からのメッセージは入っていない。帰ってこない杏介と冬彦の心配など、毛ほどもしていないのではないか。悲しい仮説が、頭を掠める。
時間は戻ることなく進んでいく。結婚式は──もう明日だ。
「それです」
小さいのにはっきりと聞こえる。不思議な声が杏介と冬彦の顔を上げさせた。
「それですよ」
綴だった。
「行かなければいいんですよ、結婚式」
大きな目には遠くの遊園地の明かりが映っている。降ってきた妙案を披露したくてたまらない。幼い興奮に胸を膨らませているのがよく分かった。
綴は冬彦の顔を正面から捉えて告げた。
「梶さん、明日の日曜日、私と揚輝荘でデートしましょう」
「へ!?」
杏介は素っ頓狂な声をあげた。自校の生徒が自分と同い年の男をナンパしているこの光景、黙っていろと言うほうが無理である。
「安心してください。直山先生も同伴です」
「なんで!?」
ますます意味が分からない。
こんなときでも冬彦の律儀さは発揮されるのか、「直山は明日予定があると言っていた」と制する。
「空けてもらいます」
綴はガキ大将のように断言した。清々しいほどのしたり顔だ。得意満面という四字熟語がよく似合う。杏介に拒否する余地はないらしい。
もちろん、かつてのクラスメイトの命が杏介の休日、その先にある熊のぬいぐるみ一体で購えるのであれば安いものだ。杏介は何も言わなかった。
「揚輝荘って?」
市外では滅多に耳にしない名前だろう。冬彦が知らないのも当然だ。
「私のバイト先で、大切な人と過ごす場所です」
詩でも朗読するような言い草だ。綴の今の姿だとなんだか様になる。
「……毒気を抜かれるな」
冬彦はため息交じりに笑う。肩に食い込むほどの重さがあった荷物を「持つ必要はない」とやっと言ってもらえた、そんな安堵があった。
冬彦たちは足早に出口に向かった。正規の手段を踏んでワイルドフラワーガーデンにいるわけではない。長居は不要である。
甘い匂いが鼻をくすぐる。冬彦は一度立ち止まり、手で口をおさえながら体をくの字に曲げた。ボソリと零す。
「驚いた」
「どうしたの?」
「……くしゃみが出たんだ」
「くしゃみ?」
前を行く杏介は紙礫でも当てられたような顔をしている。冬彦は満足げにその言葉をもう一度繰り返した。
「くしゃみだよ。直山先生」
さらに前を行く綴が「漱石っぽいですね」と顔を綻ばせる。冬彦も大きく頷いた。
冬彦は感動すら覚えた。くしゃみなど二度としないと思っていたのだ。死ぬつもりだったのだから。
生まれてこの方、何百、何千回と行ってきた生理反応なのに、恐ろしいまでに初々しく感じられる。
(何かが変わろうとしている)
冬彦は背後を一瞥した。海が冬彦を見ている。色は黒く、波打つ姿は寂しい。
自分のようだと思いかけて、踏みとどまる。今が最初で最後のチャンスなのだ。長い苦悩を断ち切って、終止符を打つことができる。杏介と綴のおかげだった。
冬彦は自分自身を侮蔑した。
「精神的に向上心がないものは馬鹿だ」
そういう未練の切り方が性に合っていた。
帰って早く寝なくては。明日はデートだから。軽くなった体で思った。
8
冬彦はホテルに戻っていった。名古屋港まで杏介たちを連れてきたタクシーを使った。
「では、開館時間の九時半に」と言う綴に首を振る。あろうことか縦にだ。
「さ、私たちも帰りましょう」
最寄り駅まで同乗することを綴は断った。曰く、都会に来たら歩くのが普通だから、らしい。ワイルドフラワーガーデンまでの全力疾走だけでもへとへとなのに、これ以上運動するのか。数日後に筋肉痛になることが運命づけられた杏介からすれば、若さ溢れる発言だった。
「そういえば、いかがでしたか?」
「何がだい?」
県道225号線を連なって歩く。
「『こゝろ』の読書感想文です」
「ああ……」
杏介は胸の内からせり上がったものを口にした。
「え、なんですか?」
脇をトラックが飛ばしていったせいで本人すらよく聞こえない。先を行く綴が振り返った。
(あれ?)
杏介は首を傾げた。
綴の顔が、さっきまでとは違って見えるのだ。どっしり構えていると感じていた瞳は落ち着きなく動き、口元は何かを言いたげに戦慄いている。あくまでかすかに、だが。
(まさかだけど……緊張してる?)
杏介は少しだけ時間を置いてから、「面白かった、かな」と告げた。さっきは違うことを言ったのだけれど、これもまた噓のない所感だった。
「本当ですか!?」
体がわずかに跳ねる。綴が、今まで聞いた中で一番大きな声を出したのだ。十トントラックなんて目じゃない。
「本当の本当に!?」
そこからは一瀉千里である。
「お世辞だったら止めてください。あれ、初めて書いたものですから言いたいこと全然まとまってないですし、なんか格好つけてますし!」
「え、……え?」
呆気にとられた。十六、七歳という年を思えば相応の反応なのだが、綴がやると意外すぎるのだ。「私、文中で〝であります〟とか使ってませんでした? 調子乗るとすぐ書いちゃうんです」と慌てふためく少女に、杏介はついインパクトのあるあだ名のほうで呼びかけてしまった。
「えーっと、スガリさん?」
綴は顔に水をかけられたような反応をする。
しまった、と思ってももう遅い。杏介は読書感想文の中で綴が気に入ったと書いていた、〝黒い光〟を見た。
「ごめん!!」
羞恥で顔が火照る。
綴に負けず劣らずの早口で「教員なのに何やってんだろう、ごめんね、変なあだ名で呼んじゃって」とまくし立てた。長い腕をブンブンやるとちょっと風が起きる。
「これだから野間垣先生にいつも頼りないって言われちゃうんだよ、本当ごめん!」
自分よりパニックになっている者を見ると冷静になる。そんな言葉をなぞるように綴は緊張を解き、杏介の懐に飛び込んだ。自身の長い生命線を見せつけるように手のひらを突き出す。
「大、丈、夫、です!」
呪文が効いたように杏介の暴走が止まった。
「……ちょっと落ち着きましょう、お互い」
「そうだね……」
次の言葉はなかなか出てこない。しばらく歩いたところで綴は小さな声で告白した。
「初めてなんです、人に読んでもらうの」
耳は夜道でも分かるほどに赤くなっている。
「特にこれ……読んでもらおうと一生懸命書いたやつなので……」
「そうなんだ」
杏介は仰天する。少なくともあの自信満々な文章からは読み解けない事実だ。
「……はい」
カメラの前にいきなり連れ出された子どものようだ。綴はもじもじと視線を泳がせる。裏腹に頭はフル回転しているようで、「すごい今さらなんですけど」と口火を切った。
「本の感想を人に見られるのって、よくよく考えると恥ずかしいことですよね。一種のヌードというか」
「ヌードって……」
「私、露出癖があるのかもしれません」
さすがにあの読書感想文を書いた人間なだけある。綴の口から飛び出した表現に、杏介も思わず赤面をした。教師という立場を無視して告白すると、少しだけ想像した。
綴の視線が対岸の夜景にいった隙をついて、杏介は自分の頰を力一杯張った。
「今の音なんです?」
「……さあ?」
杏介はすっ惚けた。
「でも……良かったです」
子どもの丸みを残す綴の頰に、睫毛の影が降りる。
「面白かったって言ってもらえて」
杏介は綴から目が離せなかった。はにかみ気味の表情はこちらまで照れてしまいそうになる。
普段あまり表情を変えない女の子の笑顔。この効果は絶大だ。
「えへへ、書いた甲斐がありました」
もうすぐ橋を渡り終わる。後ろ歩きをしていた綴がまた背を見せかけたとき、杏介はか細い声を出した。
「僕も……ちょっと恥ずかしかった」
学校でも履いている明るい茶色のローファーがぴたりと動かなくなる。
「え?」
あだ名を呼ばれたときと同じ顔だ。杏介は理性の忠告を無視して勝手に喋り始めた自分の心に呆れながら、たどたどしく続けた。
今言わないと、いけない気がしたのだ。幸い、車が来る気配はない。
「本当に良く書けていたんだよ。だからスガ……須賀田さんの頭の中がはっきり見えたと思ったんだ。それに、……勇気づけられた」
綴の読書感想文がなかったら、冬彦の異変に気づかなかったかもしれない。内気な自分のことだ、気づいたところで、自分が変な考えをしているのではないかと尻込みしたはずである。
「赤裸々なのに自信たっぷりな書きっぷりのおかげかな? さっきの言葉じゃないけれど、ちょっといけないことをしている気分に……って! 何言ってるんだろうね」
杏介は乾いた笑い声をあげる。遅ればせながら恥ずかしさがこみ上げてきた。
「忘れて、忘れて! 身近な人の真剣な考えを読むって、貴重な機会だから。先生、舞い上がっちゃったんだよ」
──だが、それが読書感想文というものだ。
物語に揺さぶられた読者の心は、全てが原稿用紙の上に表れる。登場人物と重ね、または反射させ、己を繙いていく過程を、努力を読むということは決して気軽に行えるものではない。
空咳を一度して、杏介は目尻を下げた。
「頭の中を読ませてくれてありがとう。やっぱり須賀田さんって面白いって再認識できた」
綴は先ほどよりもさらにはっきりと口角を上げた。
「スガリでいいですよ。実は気に入っているんです」
ああ、これは一生忘れられない。そんな気持ちにさせてくれる笑顔だった。
なるほど、男子に人気があるわけだ。
(虫さえ食べなければなぁ……)
杏介はしみじみ思った。
問題は柴田駅に着いたあとだった。
「と、いうわけで。これ今日の分です」
「え?」
巾着型のポシェットに手を突っ込んだ綴は、杏介の胸に紙束を押し付けてきた。なぜ持っているのか。聞くに聞けない。恐ろしいことに『こゝろ』の感想文の倍の厚みがある。
「こ、れは……」
杏介は青ざめた。
今となっては遅すぎる告白をしてしまうと、文章を読むのは大の苦手なのだ。
「いや、この量はちょっと……」
「初作の出来で読めたのであれば絶対にいけます。今日か明日の一晩で読めます」
読書感想部部長(仮)・スガリこと須賀田綴は自信満々に断言する。杏介に「僕、今日はもう寝たいし、明日の夕方以降は手芸屋さんにモヘアの布を探しに行きたいんだけど……」と断る暇を与えない。
原稿用紙を顧問の顔に貼り付けるように示し、自分自身も顔をぐっと近づける。杏介の長身のおかげで、二人の唇にはまだ距離があった。
「大丈夫です。私たちきっと相性がいいんですよ。考えの伝え方と受け取り方の」
「それは語弊が……」
杏介の視界の半分は原稿用紙、半分は瞳の中の星をきらめかせる綴だ。
もはや逃げ場はない。
綺麗な文字で綴られた題名もいけなかった。
「〝作者不明『桃太郎』〟……?」
気になってしまった自分が恨めしい。
「力作です」と念を押す綴に、杏介は観念して頷いた。