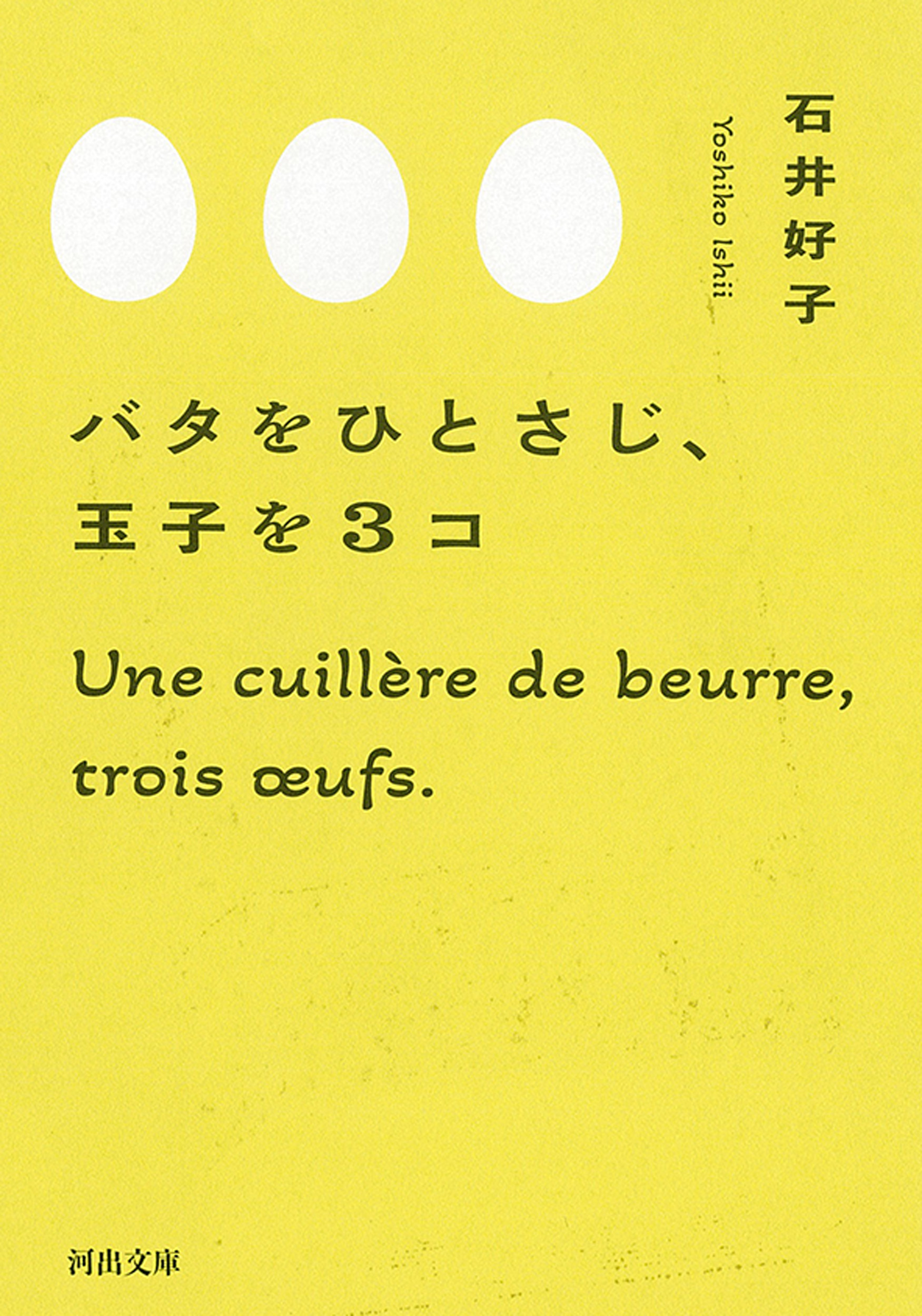単行本 - 日本文学
時価数十億のストラディヴァリウスが消えた!? 『最後のトリック』著者が描く華麗な音楽ミステリ、試し読み公開!
深水 黎一郎
2017.06.09

熱狂。奇想。前代未聞。超満員の音楽ホールが巨大な密室になる――
『ストラディヴァリウスを上手に盗む方法』
深水黎一郎
時価十数億の伝説の名器が、若き女性ヴァイオリニストの凱旋コンサート会場から消えた! 巨大な密室と化した超満員の音楽ホール。犯人の驚くべき手口とは?
「読 者 全 員 が 犯 人」というミステリー界究極のトリックでベストセラーとなった『最後のトリック』の深水黎一郎さんによる華麗な音楽ミステリー集が発売となりました。
★表題作の冒頭を公開します。ぜひご一読ください。
_____________________
1
警視庁捜査一課強行犯捜査第一〇係の主任である海埜(うんの)警部補は、その夜自宅で、いつものように瞬一郎と二人で呑んでいた。
この男は神泉寺家に嫁いだ海埜の妹未知子の忘れ形見で、海埜にとっては唯一の甥に当たる。二人ともいける口なので、時々世界の珍しい酒を一緒に試したりもするのだが、今日は基本に戻って、海埜秘蔵のシングルモルトのスコッチ・ウイスキーをオンザロックで玩味していた。
するとたまたま点けていたテレビに、臨時ニュースのテロップが流れた。
エリザベート王妃国際コンクールヴァイオリン部門で、
日本の武藤麻巳子さん(21)が優勝
瞬一郎は背中をぴくりと動かすと、
「ああ、麻巳子ちゃん優勝したんだ。さっすが」
そう言って、まるで画面と乾杯するかのように、片手に持っていたグラスをちょっと持ち上げると、そのまま口に運んでぐいと空けた。
「何だお前、知り合いなのか」
「知り合いと言うか、同じ先生に師事していました」
「同門ということか?」
「日本風に言えば、そういうことになるんですかね」
さっきよりも、ほんの少しだけ赫(あか)い顔になった気がするが、それは酔いのせいなのか、それとも知り合いの名前を臨時ニュースで見ての興奮か。
神泉寺家は我が国を代表する芸術一家として、日本画家や作曲家、作家に舞台演出家、デザイナーなどを綿々と輩出して来たことで知られている。声楽家を目指していた未知子は、留学先のパリで若き洋画家の卵と出会って恋に落ち、そのまま結婚したのだが、それがこの男の父親の神泉寺瞬介だった。その未知子は帰国して瞬一郎を産んだあと、まだ三〇代の若さでこの世を去ってしまったのだが、瞬介はその喪が明けるとすぐに、自分の絵のモデルだった一回り以上若い女性と再婚し、父子の関係は悪化した。もちろんそれ以前から瞬一郎は、母方の伯父である海埜を慕ってくれてはいたが、特にそれ以降は、ほとんど父親代わりと見做(みな)しているようなフシもある。
芸術一家の末裔(まつえい)としての血のなせる業(わざ)か、この男は小さい頃からさまざまな芸術的才能を発揮したが、未知子が習わせたヴァイオリンもその中に入っていた。そもそも小さい頃に特別な音楽教育を受けたわけではない未知子が声楽家を目指したのは、声楽が音楽の中で〈最も遅く始めても挽回がきく分野〉だからであり、自分に子供ができたら絶対に英才教育を授けてあげたいと、夙(つと)に漏らしていたのだ。その期待違わず瞬一郎は、何度もコンクールのジュニア部門で優勝し、海埜をはじめ周囲の大人たちの多くが、そのままプロのヴァイオリニストになるのだろうと思っていたわけだが、音大付属高校の特待生の誘いを断って普通の高校へと進んだかと思うと、結局日本の大学は受験すらせず、そのまま高校卒業と同時に海外に渡って六年間もボウフラのように彷徨し、その結果として現在の為体(ていたらく)──本人の弁によれば世界を股にかけたフリーター──に至っているのである。子供のいない海埜としては可愛くない筈(はず)はないのだが、その分心配させられっ放しでもある。
「何という先生?」
「オットー先生です」
「ああ……」
合点した。その名前はこの男の話の中に、過去何度か登場したことがある。たとえばどこぞの音楽祭を聴きに行ったところ、オーケストラの団員に季節外れのインフルエンザが蔓延して奏者が足りなくなり、コンサートマスターを務めていたその先生の命令で、そのまま臨時で音楽祭のオーケストラ・ピットの中に入らされた時のことなんかを聞いた憶えがある。まあ師事と言ってもどうせこいつのことだから、フラフラしている合間にタマに顔を出していた程度なのだろうが──。
「教え子が優勝するくらいだから、きっといい先生なんだろうな」
海埜のその言葉は、表面上はその先生を讃えながら、同じ先生に師事しながら片や国際コンクール優勝、片やいまだにフリーターかよという皮肉が込められていたのだが、本人はそれに気付いているのかいないのか、どこ吹く風で答える。
「厳しい先生ですよ。1にスケール2にスケール! 3、4がなくて5にスケール! ハイフェツはドントの24のエチュードだけを、パールマンはセヴシックのスケール集だけを、蜿蜒(えんえん)と練習していた! 二人ともそれ一冊しかやらなかったが、その代わりそれを何千回と繰り返していた! 1にスケール2にスケール! 3、4がなくて5にスケール!」
「はあ」
どうやらその先生の口真似らしいのだが、本物を知らない海埜には、似ているのかどうかの判断はもちろんつかない。
その日はそのまま四方山話(よもやばなし)をして寝てしまったのだが、その数週間後に再び現れた時には、瞬一郎は演奏会のチケットを二枚持っていた。
「この前一緒に呑んでる時に臨時ニュースで見た武藤麻巳子さんが、凱旋コンサートのチケットを送って来てくれましたよ。話の流れからして、いちおう伯父さんを誘うべきかと」
「いちおうは余計だろ」
ぶっきら棒に答えたが、誘ってもらって気分が悪かろう筈はない。いい年頃の若い男が、ペアチケットで伯父なんかを誘って良いのだろうかとは思うが──。
「いつなんだ?」
「来週の水曜日です」
「来週? ずいぶん急だな。コンクールで優勝して、まだ一ヶ月も経ってないだろう?」
「在京のニュージャパンシンフォニーオーケストラの定期演奏会に、ソリストとして急遽出演することになったんですよ」
「オーケストラの定期に? ふうーん」
「首都圏の主要な会場は、予約でもう一年先まで全部埋まっていますからね。一口に凱旋コンサートと言っても、簡単には開けないんですよ。だから今回は元々演奏会の日程が組まれていたニュージャパンシンフォニーオーケストラが、定期の曲目を変更して、彼女の凱旋コンサートをセッティングしたという形ですね。ソロのリサイタルは、また改めてじっくりとやるんでしょう」
「それって、オーケストラ側にメリットはあるのか?」
「大ありですよ。在京オーケストラは何年も前から飽和状態で、残念ながら定期演奏会はどこもなかなか満員にはなりません。その定期が俄然注目の演奏会になってチケットは売り出しわずか十五分で完売ですから。これ以上win-winの関係というのも珍しいでしょう」
「来週の水曜日か……」
海埜は壁掛けのカレンダーをちらりと見たが、それはいわゆる世間的慣習に従っただけであって、大した意味はない。普通の会社員とは違い、カレンダーを見たところで事前にスケジュールがわかるわけではない。
「仕事がヒマな時期なら行かせてもらうが……」
自分で言いながら、言ってるそばから自己撞着(どうちゃく)であることを感じる。刑事にとってヒマな時期など、定年になるまで一回もないことがわかっているからだ。ただ普通に忙しい時期と、ものすごく忙しい時期のどちらかがあるだけである。もし大きな事件が起きて帳場(捜査本部)が立ったら、音楽会のために抜け出すなんてまず不可能だ。
瞬一郎は少し不満そうな表情だ。
「もう少し感激して欲しいなあ。彼女、ネットを中心に人気が沸騰しちゃって、これだってネットオークションで、現在定価の三倍近い値段で取引きされているプラチナ・チケットなんですよ?」
「だが俺は、そういう仕事なんだからしょうがない。お前だってわかっているだろ」
「はいはい」
2
そして翌週の水曜日。
幸い帳場が立つような大事件は起こらず、海埜はコンサートホールのあるJRの蒲田駅前で、無事瞬一郎と落ち合うことができた。もちろんその間、小さな事件は幾つも起こったが、いずれもスピード解決に漕ぎつけたのだ。
「そう言えば曲目を聞いていなかったな」
会場までの道を並んで歩きながら海埜は尋ねた。クラシックのコンサートなんて何年ぶりだろう。
「この前エリザベートの本選で弾いた、ベートーヴェンのヴァイオリン協奏曲です。ヴァイオリンコンクールの本選でベートーヴェンを選ぶのは自殺行為とまで言われているのに、それを敢えてやって優勝したんだから、すごく価値がありますよ」
「それは楽しみだ」
駅から七、八分ほど歩くと、コンサートホールが見えて来た。五年ほど前に杮落(こけらおと)しが行われたまだ新しいホールで、収容人数は一八〇〇人。クラシックのコンサート会場としては大きな部類だ。今日はここが満員になるというのだろうか。
エントランスを潜(くぐ)る。今後の演奏会のチラシの分厚い束を、薄手のビニール袋に入れて配布している男女がいたが、荷物になるので断り、そのまま切符のもぎりを通過した。次に演奏会に行けるのは何年後になるかわからないのに、チラシだけ山ほど貰っても虚しいだけである。見ると瞬一郎も貰っていない。
まだ開場したばかりなので、フォワイエにも人の姿はまばらだ。濃紺のスーツ姿の女性が、つややかに磨かれた板張りの床の上をハイヒールで戛々(かつかつ)と歩きながら、いらっしゃいませと頭を下げた。
瞬一郎は一階の客席の扉を潜ると、どんどん前へと進んで行く。一番前列の通路に立って、無人の舞台の上の椅子の配置を眺めている。
「なるほど。なかなかやり手のステマネがいるようですね」
したり顔で頷く。
「何がなるほどなんだ?」
誰もいないのに──。
「椅子の配置を見ると、ステージマネージャーの力量がわかるんですよ。特に前とぶつかりやすいトロンボーンの前の空間を、どう確保しているかを見るのがポイントです」
それからまた歩き出して、そのままステージに向かって下手(しもて)、すなわち左側の一番前の扉を開けて、脇の廊下に出てしまった。
そこには踊り場のような小空間が広がっていた。右側にはスチール製の防火扉があり、左にはフォワイエに戻るための上向きの階段が伸びている。
「一体どこへ行くんだ?」
「ちょっと楽屋に寄って挨拶して行きましょう」
そう言って右側の防火扉に手をかける。
「誰に?」
「武藤さんですよ。チケットのお礼も言いたいし」
「いや、俺はいいよ。俺は客席で待っているから、お前だけ行って来い」
海埜は慌てて首を横に振った。
「よろしく伝えておいてくれ」
すると瞬一郎は唇をちょっと尖らせた。
「一緒に行きましょうよ。これから確実に世界的ヴァイオリニストになる若い女性と話をする機会なんて、伯父さんの幸薄くて残り少ない人生には、もう二度と訪れないかも知れませんよ」
「確かに滅多にない機会だとは思うが、幸(さち)が薄いとか残り少ないは余計だろ」
海埜は憮然(ぶぜん)とする。
「それに本番前にお邪魔するというのはさすがに……」
「いや、それがさっきメールしたら、来て欲しいという返信がすぐにあったんですよ。元々彼女は、本番前は緊張がほぐれるから、誰かにいて欲しいというタイプなんです」
そう言って携帯端末をポケットから出して見せる。
「お前が携帯を携帯するようになったのは、人類にとっては大きな一歩だな」
海埜がアームストロング船長の名言を意識しながら奇妙なトートロジーを弄(ろう)しているうちに、瞬一郎はもう防火扉を押しはじめていた。
防火扉はゆっくりと開いて、その先に続く薄暗い廊下が現れた。
「ここは?」
「楽屋の廊下ですよ」
「え、もう?」
こんなに簡単に行けるものなのか。海埜も過去に警備等で何度か劇場やコンサート会場に出入りしたし、楽屋に入ったこともあるが、客席に行く時は入口から、楽屋に行く時は楽屋口から、毎回ガードマンに手帳を見せて入っていた。
「案外簡単に行けるものなんですよ。あんまりみんな知っちゃって、関係者以外がどっと押し寄せるようになったらマズイですけどね」
瞬一郎は先に立ってどんどん廊下を歩いて行く。途中でオーケストラの団員らしい黒いロングスカートの女性や、インカムを付けてネル地のシャツにチノパンというラフな恰好の裏方らしい男性とすれ違う。何か言われるかなと思ったが、あべこべに会釈までされてしまい、海埜は何だか申し訳ない気分になった。
やがて武藤様控室という張り紙がされたドアを見つけ、瞬一郎はそれをノックした。
「はい」
涼しげな声がして、小さな磨(す)りガラスの向こう側で影が微妙に動き、やがてドアが内側から開かれた。
ドアの内側に立っていたのは、海埜が想像していたよりもずっと華奢(きゃしゃ)で小柄な女性だった。身長は一五〇センチそこそこ。髪は一度も染めたことのなさそうな漆黒のショートボブだ。先日のテレビの臨時テロップでは確か二十一歳となっていたが、欧米ではまず間違いなくティーンエイジャー扱いされることだろう。ヘアセットや化粧などは済ませてあるようだが、それもごくごく薄い。ラッフルスリーブというのか、幅広の襞飾りが袖についたトップスに下はジーンズ。明らかに普段着で、今どきの若い音楽家はこういう恰好で演奏するのか? と一瞬訝ったが、よく見ると鏡台前のハンガーには、ブルーのステージ用ドレスが掛かっている。どうやら、出番のぎりぎり直前に着替えるらしい。
「優勝おめでとう、麻巳子ちゃん」
「うわあ、嬉しい! 来てくれてありがとう、瞬先輩!」
武藤麻巳子は飛び上がった。低身長にもかかわらず平底の靴を履いているのは、万が一にも足を挫(くじ)いたりしないようにという配慮だろうか。
だが着地してすぐに、細眉を八の字に寄せて複雑な表情を泛(うか)べた。
「あれれ、でも瞬先輩に演奏を聴かれるなんて、よく考えたら一大プレッシャーかも」
「何を言っているんだ。自分でチケットを送って来たくせに」
「うーん、送ったことを今ちょっと後悔してますぅ」
人差し指を目の下に持って行って左右に動かし、泣きマネをする。なかなか愛嬌の方も満点の娘さんのようである。
「それに錚々(そうそう)たる審査員の前で演奏して優勝したんじゃないか。今さら僕に聴かれるくらいが何だと言うんだ」
「先輩が出ていたら優勝できてないかも」
「そんなことはないし、そういうことを言ってはダメだよ。二位以下の全参加者に対して失礼だ」
「すみません……」
瞬一郎が真顔で窘(たし)めると、武藤麻巳子はしょげ返った。いつもこの男の言いたい放題を窘める側の海埜は、その光景を何だか不思議な気持ちで眺めた。
「ところでカデンツァは何を弾くの?」
「ヨアヒムです!」
あっさりと元気を取り戻す。
「ああ、意外と当たり障りのないところを選んだね」
「瞬先輩はベトコンのカデンツァは断然シュニトケ派ですよね。あたしもシュニトケのカデンツァ大好きなんですけど、指揮のマルコリーニさんが嫌いらしいんです。カデンツァのモチーフは、絶対にその曲から取られなければならないという信念の持ち主らしくて……」
「えっ? だけどカデンツァは一〇〇%、ソリストの裁量だろう?」
「そんな気もするんですけど、駆け出しのソリストの分際で、指揮者の意向を無視することなんて、とてもできませんよぉ」
「構わないよ。本番でいきなりシュニトケ弾いちゃえ」
「やっちゃいますか、カデンツァテロ!?」
そう言って小さく舌を出す。話の内容は海埜の理解の外にあるが、どこからどう見ても今どきの若い娘さんであり、街で見かけたら、そんな国際的なコンクールで優勝した演奏家とは、まず思わないことだろう。
それから瞬一郎が海埜を紹介した。海埜が軽く会釈すると、武藤麻巳子はまるで舞台上のレヴェランスのように膝を曲げてお辞儀をしていた。
「そういえば伯父さんが刑事だって、先輩言ってましたね! うわぁあたし、本物の刑事さんに会うのは生まれて初めてかも」
「それはお嬢さん、幸せなことかも知れません。みんなあまり、知り合いになりたがらない人種でして」
「きゃは♡」
それから再び何やら専門的な話になった。
「二次予選の時に強い音が欲しくて、ゴールドブラカットの0・27にしてみたんですけど、何かしっくり来なくて。それで思い切って本選は0・26に戻したんですよ」
「ああ、0・27は全くの別物だね。確かに音は強くなるけど、倍音が乱れがちになるような気がする」
「やっぱりそう思います? じゃあ戻して正解だったかなぁ?」
「間違いなく正解だと思う」
「本選直前に気が付いて良かったぁ。ラッキーでした」
「いやそれは普段から、自分で自分の音をちゃんと聴けている証拠だから自慢して良いよ」
「瞬先輩にそんなこと言われたら、調子に乗っちゃいますよ、あたし」
「本番前はいくら調子に乗っても良いさ。世界で一番上手いのは自分だと思って弾くんだ」
「そーします。と言うか、そーしてます」
「だろうね」
瞬一郎は首を竦(すく)めた。
「そう言えばオットー先生はお元気?」
「相変わらず元気ですよ。1にスケール、2にスケール、3、4がなくて5にスケール! ハイフェツはドントの24のエチュードだけを、パールマンはセヴシックのスケール集だけを、蜿蜒と練習していた! 1にスケール、2にスケール、3、4がなくて5にスケール!」
武藤麻巳子がこの前の瞬一郎と全く同じ口真似をはじめたので、海埜は思わず噴き出しそうになった。よっぽどその台詞が口癖なのだろうが、オットー先生、弟子たちに真似され過ぎである。
だがここで武藤麻巳子が、憶い出したように赤い唇を尖らせた。
「ところで瞬先輩は、本当にヴァイオリニストにはならないんですか?」
すると瞬一郎は再び首を竦めた。
「どうして? ヴァイオリニストとは、ヴァイオリンを弾く人という意味だろう? そういう意味では僕は一生、ヴァイオリニストの端くれではいるつもりだけどね」
「そうじゃなくて、演奏のプロとしての活動はしないんですか?」
「現状それには興味はない」
「えー何で」
「理由はいろいろあるけど、演奏活動をするということは、演奏会に向けての準備期間を含めた一定期間、自分の身体の関係性の網の目を、特定の楽曲に完全に従属させるということに他ならないからね。僕は小さい頃からそれがどうにも苦手で、本当はジュニアのコンクールに出るのも好きじゃなかった。僕はいつもフラットな状態でいたい人間なんだよ」
「んーあたしのような凡人には、何を言っているのかぜんぜん理解できませーん」
武藤麻巳子は首をかしげた。
「演奏活動と自己研鑽は両立しないってこと? 既に押しも押されもせぬ巨匠だったハイフェツが、デビューしたばかりのアイザック・スターンの演奏を聴いて、その後の演奏活動の予定を全てキャンセルして、一からみっちり技倆(ぎりょう)を鍛え直した、みたいな話?」
「いや、それともちょっと違う。僕は常に座標軸のゼロの地点にいたいんだよ」
「んー」
もう一度首をかしげる。
「ん!?」
それまで会話に夢中だった瞬一郎が、テーブル上のヴァイオリン・ケースにようやく目を留めた。実はさっきから海埜は、耳は二人の会話を聞きながら、目の方はそれに釘付けになっていたのだが、ケースのフタが開いていて、中が見えている。ケース内部に敷き詰められた緑色のフェルトに、静かに抱きかかえられるかのように収まっているのは、深い琥珀(こはく)色を湛える一挺(いっちょう)のヴァイオリン。その手前には弓が、こちらはケースから出した状態で置いてある。
「ひょっとして、これが今回貸与されたストラド?」
「そうです。〈エッサイ〉です」
「おーこれが。写真では何度か見たことがあるけど、本物を見るのは初めてだ」
思わずといった感じで一歩近づく。
「先輩、ちょっと弾いてみます?」
瞬一郎は一瞬ぴくり、と背中を震わせた。
「いや、しかし……」
「弾いて下さいよぉ」
瞬一郎は乞われるがまま楽器を取り上げて、顎と鎖骨の間に挟み込んだ。武藤麻巳子が手前にあった弓をすかさず手渡す。
瞬一郎は弓をほぼ水平に大きく引くと、一番左側の一番太い弦を勢い良く弾いた。松脂(まつやに)の白い粉がぱっと飛び散る。
かと思うとそのままのダウンボウイングを続けながら、すぐに隣の二本の弦の上に弓を移動させて重音を奏でた。
最初に弾いた弦の響きがまだ空中に残っているから、結果として海埜の耳には、三重音となって聞こえて来た。
重音の練習?
いや違うな、れっきとした曲だ。何だっけ、これ──?
瞬一郎はそのまま弓の先ぎりぎりまで弾き切ると、早いアップのボウイングで手に持つ箇所に近い部分──確か元弓とか言うんだったか──まで戻し、再度左側の二本の弦の上に乗せて、低い重音を奏ではじめた。
だがまたすぐに弦から弓を浮かせて角度を変えると、今度は右側の細い二本の弦の上に素早く移動した。
そして高い二重音を一気に弾き下ろした。
左側の太い二本の弦はまだ震動しているから、今度は結果的には四重音となって聞こえて来た。ヴァイオリンの弦は四本しかないのだから、これがヴァイオリンが出せる重音の限界ということになるのだろう。
瞬一郎はそのまましばらく三重音や四重音を連続で弾き続けていたが、やがて武藤麻巳子が、赤い唇を尖らせてそれを止めた。
「ちょっと瞬先輩。ワンストロークで、これからステージで演奏しなきゃいけない人よりも、いい音を出さないで下さいよぉ! しかもいきなりバッハの『シャコンヌ』とかぁ!」
「え、あ、ああ……」
瞬一郎は我に返ったような顔で演奏を止めた。
「世界で自分が一番上手いつもりで弾けとか何とか言っといて! こんなの聞かされて思えますか! 瞬先輩って時々空気読みませんよね!」
時々じゃなくていつもだろうと海埜は横で思う。
一方その本人は、愕いた顔で手の中の楽器を眺めている。
「やばいな、これ。さすがは〈エッサイ〉。これまで、バイロイトでオットー先生から貸与されたデル・ジェズが僕の理想の一挺だったけど、これはそれと甲乙つけがたい」
_____________________
……この後、〈エッサイ〉が超満員の音楽ホールから消える!? 果たしてその真相とは?
続きは書籍でお楽しみください!
★刊行を記念して、「クラシック音楽×ミステリー」の名作を深水さんに選んでいただきました。hontoブックツリーにて公開中です。こちらから。