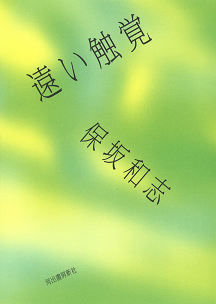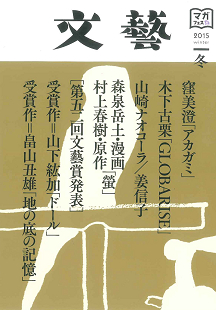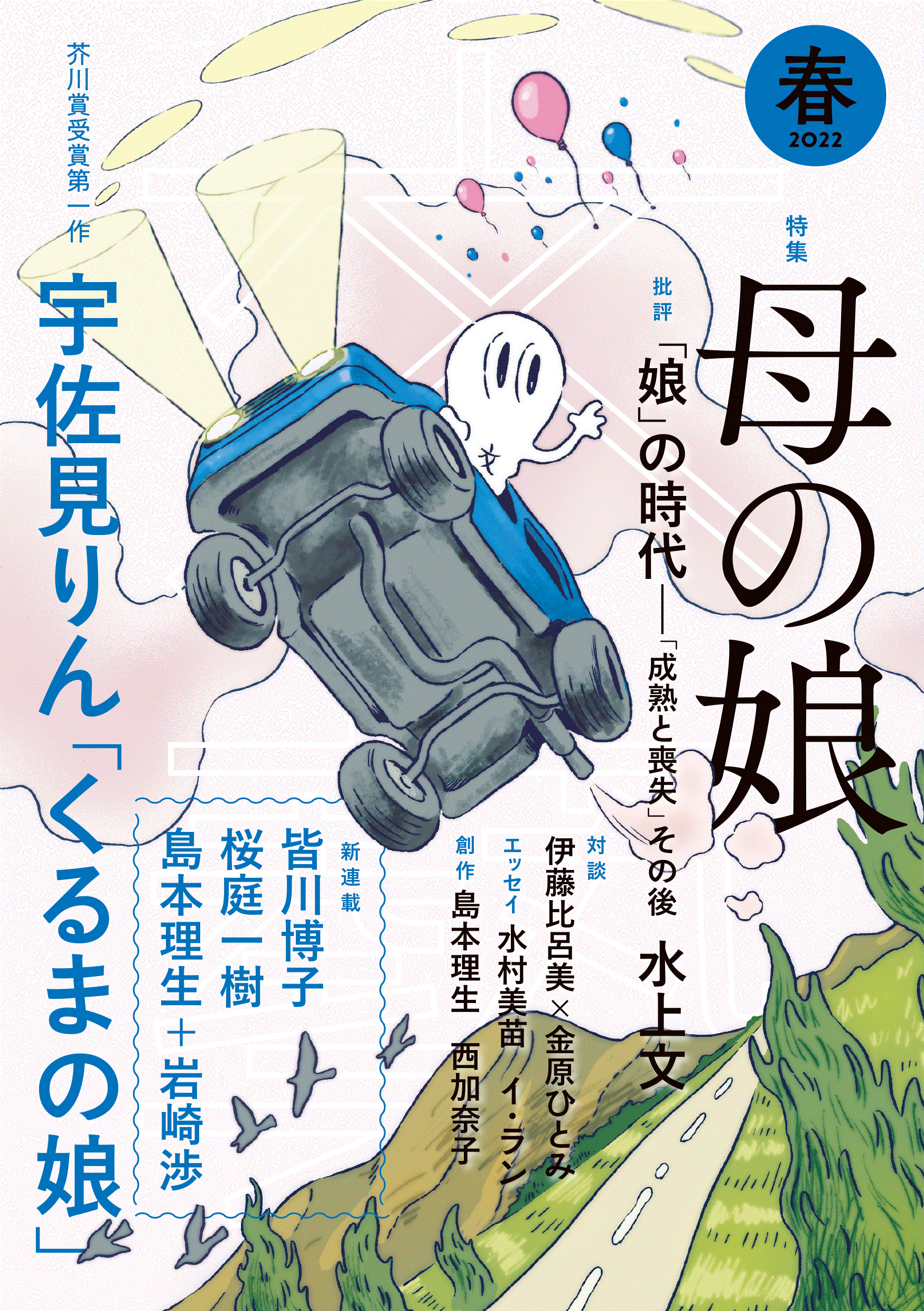単行本 - 文藝
保坂さんの文章は読む者の記憶を呼び覚ます働きがある。『遠い触覚』 保坂和志
【評者】種田陽平
2015.12.15
保坂和志著
【評者】種田陽平
──言葉による長回し──
映画には長回し撮影というものがある。短いカットの積み重ねには、作り手の意図を確実に反映させることができる。しかし、長回し撮影においては、どんなに計算してとりかかっても、撮影時の演技の流れやカメラワーク、タイミングなどで思いもかけぬ方向に展開することもあり、予想以上の結果が生まれることもある。昔、長回しの相米慎二と呼ばれた監督が「溝口(健二)さんやアンゲロプロス(監督)は長回し撮影をどうやってるのかな? ゴダールのなら、おれにもわかるんだが……」と言って、長回しにも二通りあるのだということを話してくれた。保坂さんの文章は読む者の記憶を呼び覚ます働きがある。本書、『遠い触覚』に「記憶は色褪せることなく保持されつづける」とあるとおり、今は故人となった相米監督の、その会話の声の調子まで鮮明に思い出された。本書の主人公とも言えるデイヴィッド・リンチ監督の世界は「悪夢のようだ」とよく語られるが、夢のようなショットはセピアトーンではなく、強烈な色彩で表現される。リンチの赤、青、紫などイメージの反復は 「記憶」に訴えかける。本書に繰り返し登場する『インランド・エンパイア』は未見であった。本書を読み進めながら、読者はこの映画を間違いなく観たくなるはずだが、私も早速DVDを借りてきて『遠い触覚』を読んでは、『インランド』を観るということになった。すると、連鎖反応のように記憶が立ち上がってきた。若い頃、リンチの連続ドラマ『ツイン・ピークス』を観ながら、劇中のドーナツを食べるシーンをまねてむさぼったこと。同じ頃、長崎俊一監督が「友人の保坂が書いた『プレーンソング』を読んでみないか……」と勧めてくれたこと。その数年後、私が美術を手がけた長崎監督の映画の主人公の本棚に、そっと『プレーンソング』を置いたこと。これらあざやかに彩られた記憶は、『遠い触覚』を読むことによってつくりだされた、偽りの記憶かもしれないのだが。『遠い触覚』を読み終え、ほぼ同時に『インランド』を観終えた時、長かった夢から醒めたような感じがした。夏の日中、映画館から外に出た時の、真っ白な世界に包まれた感覚だ。保坂さんの記したリンチやゴダールやフロイトやフィリップ・K・ディック、保坂さんのお父さん、猫のペチャも、皆、保坂さんによる長回し撮影の中に現れる登場人物のようだ。この『遠い触覚』は相米監督の言っていた「溝口ではなくゴダールの長回し」のようなものかもしれないと思った。ゴダールとリンチの撮影、編集についての共通点は、映画のセオリーや計画にとらわれないことだ。しかし、改めて本書の目次を見直すと、そこには、とても自由に語ったとは思えない、緻密に組み立てられた確かな意図があった。文章を書くということは映画撮影とは違い、偶然が入り込むことがないのだろう。最終章のタイトルが「時間は不死である」。
私は時間と記憶を意識しながら『遠い触覚』をもう一度頭から読み直すことにした。