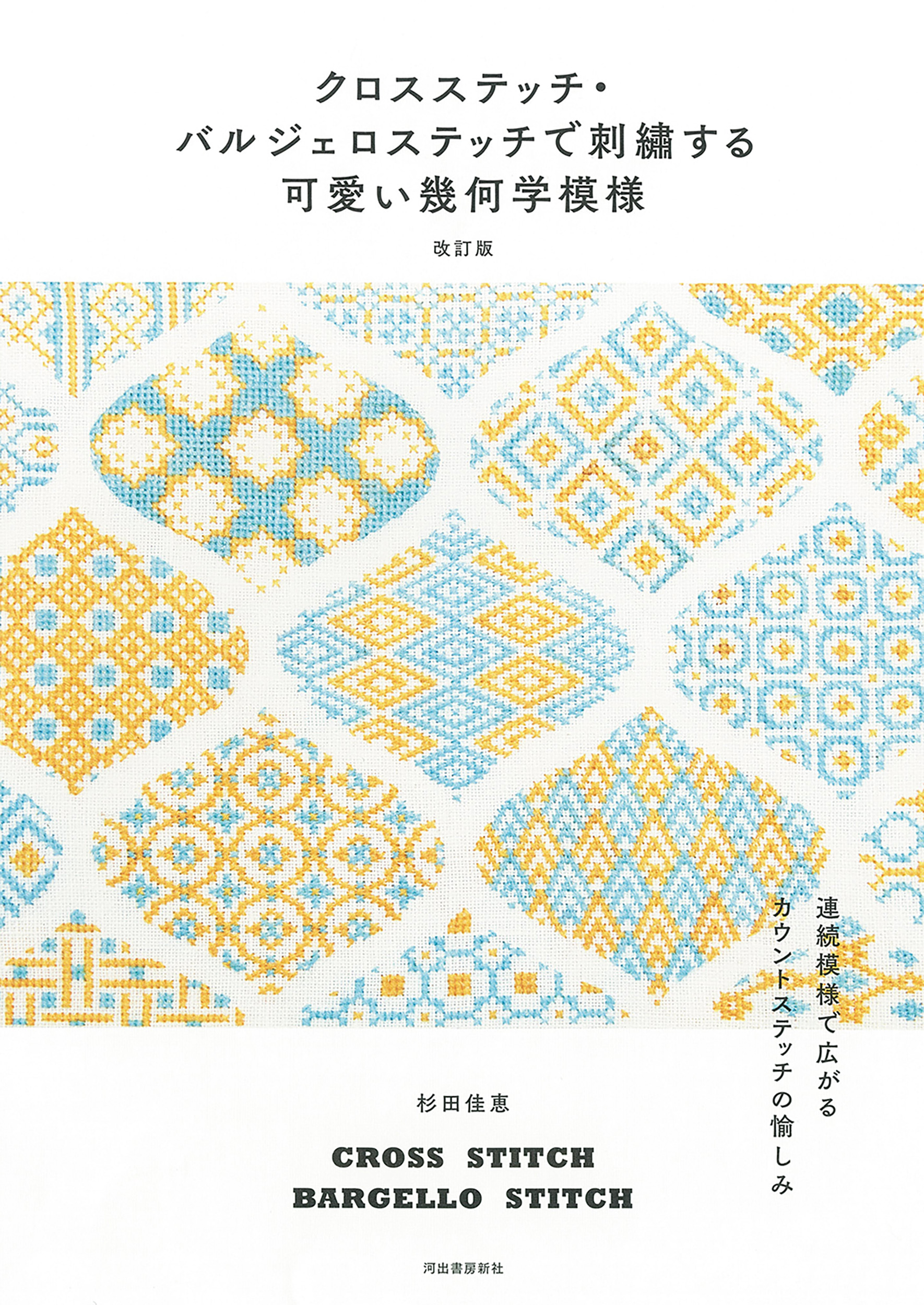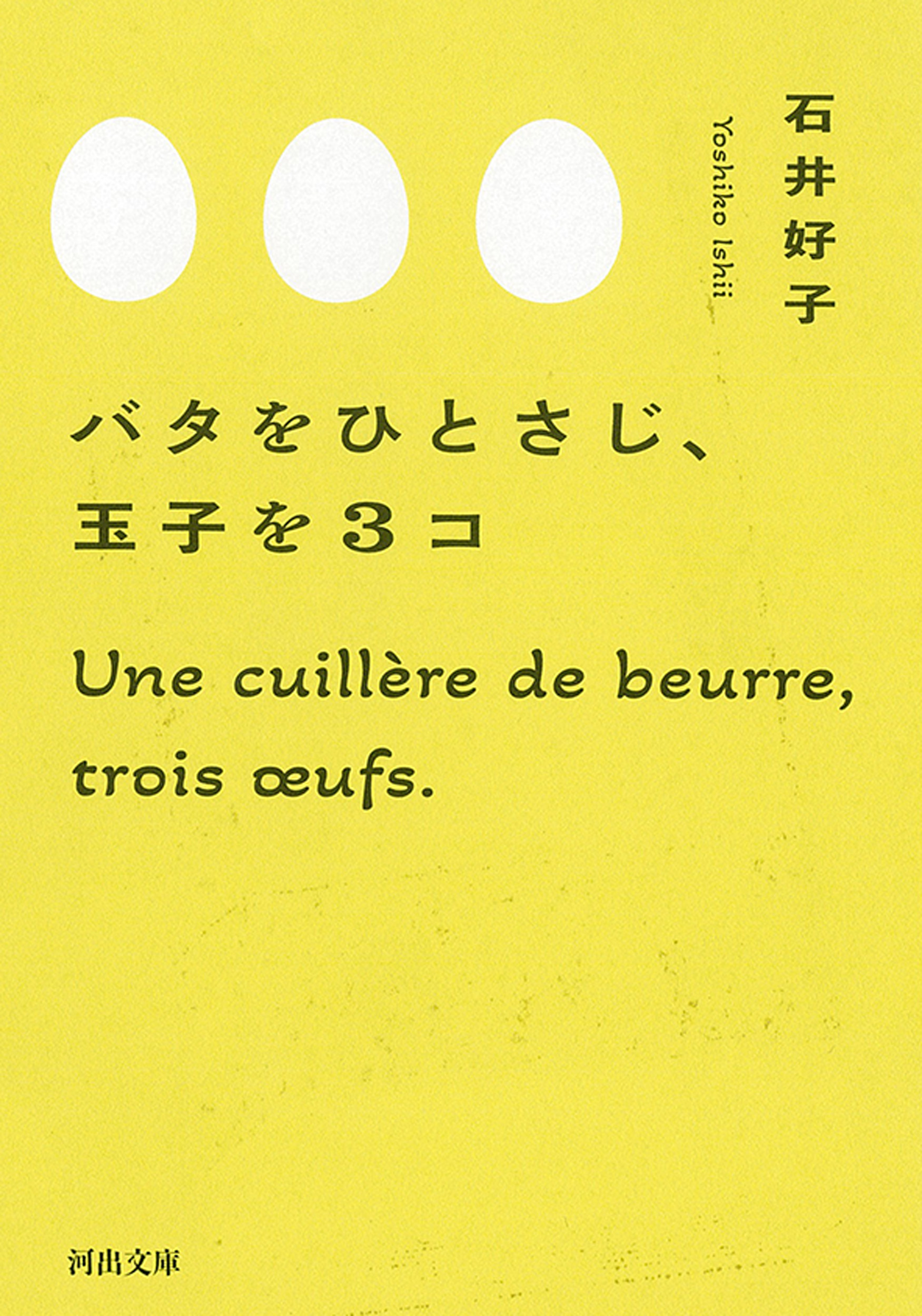単行本 - 日本文学
かつて日本中の涙を誘った傑作小説「もしかしたら有り得たかもしれないもう一つの人生、そのことを考えなかった日は一日もありませんでした」
蓮見圭一
2017.11.08
「もしかしたら有り得たかもしれないもう一つの人生、そのことを考えなかった日は一日もありませんでした」
かつて日本中の涙を誘った傑作小説が、装いも新たに河出文庫としてよみがえりました。人生を揺さぶる最高の物語です。
本日より2日連続で、冒頭部分と中盤の試し読みを公開します。
ぜひご一読ください。
——————————————————
第一回
——————————————————
これは、四条直美という女性が病床で吹き込んだ四巻のテープを起こしたものである。
一九九二年の年明けに脳腫瘍の告知を受け、築地の国立がんセンターに入院した四条直美は、その年の秋に死んだ。四十五歳だった。彼女は翻訳家であり、詩人でもあったので、数日後、社会面の左隅に二十行ばかりの死亡記事が掲載された。いい記事だったけれど、写真があればもっとよかったのにと思う。
テープは直美が危篤に陥る二週間前に、ニューヨークに留学していた一人娘の葉子のもとへ郵送された。当初、直美は自分で吹き込んだテープをもとに、娘に宛てた長い手紙を書くつもりでいたらしい。あとに残された便箋に三枚ほどの走り書きが、そのことを問わず語りに語っている。ニューヨークに届いた四巻のテープは、直美が愛用していたオメガの腕時計とともに、この便箋に包まれていたのである。
葉子は、その書きかけの便箋をとても大事にしている。母親が記した最後の文字を繰り返し目で追った彼女は、いまではその内容を空で話すことができる。けれども、葉子はテープの内容をまとめ上げることはしなかった。誰よりも母親を崇拝していた葉子にとって、それは難しい作業だったのかもしれない。テープの内容は、とうてい父親に聞かせられるようなものではなかったからだ。
四条直美は、確かに品行方正なだけの女性ではなかった。彼女は多くの人に愛されていたけれど、それと同じくらいの数の人たちに憎まれ、恐れられてもいた。とはいえ、表立って誰かを批判したり、攻撃したりするような女性ではなかった。軽蔑するしかない人間に出会っても、彼女はただ、ほんの数秒相手の目を見つめるだけだった。葉子も何度かそんな目で見つめられ、子供心に母親に対して恐れの混じった不思議な感情を抱いたことがあるという。それでも葉子にとって、四条直美が特別の女性だったという事実には少しも変わりはない。
僕が初めて葉子に会ったのは六歳の春だった。僕たちは一年青組のクラスで一緒だったのだ。
学校時代、葉子はずっと首席だった。長い学生生活の間には何人ものライバルが現れたけれども、誰一人、彼女には歯が立たなかった。葉子は何の苦もなく教師の質問に答えたし、母親の影響もあってか、六年生の時にはフィリップ・マーロウの物語を原書で読んでいた。暮らしぶりもIQの数値にふさわしいもので、夏休み明けにはきまって軽井沢の街並や浅間山を描いた絵日記を提出した。葉子の描く浅間山はひどく険しく、そして大きな山だった。
「葉子は俺たちとは血筋が違うんだよ」
四年生の夏、プールからの帰りに同級生の一人がそう言ったのを思い出す。道ばたで買ったアイスクリームを舐めながら、彼はこんなふうに続けた。
「うちのお母さんが言ってたけど、葉子の家はすごいんだってさ。お母さんも頭がいいし、ひいおじいちゃんなんか、ものすごく偉い」
こんな話を聞かされると、家柄や血統といった後ろ盾を持たない子供たちはぼんやりとした不安を感じるものだ。
「偉いって、どれくらい?」
別の同級生が恐るおそる訊ねると、彼は我がことのように得意になって答えた。
「偉すぎて、A級センパンになったくらいだよ」
その場にいた同級生たちが感心したように頷くので、僕も一緒になって頷いた。でも、A級センパンというのがどれほど偉いのか、実のところよく分からなかった。Aである以上、BやCよりは偉いのだろう。ただ単にそう思っただけだ。けど、センパンってのは一体何なんだ? それが疑問だったけれど、他のみんなが納得している以上、安易に訊ねるわけにいかなかった。僕たちは同級生に何かを訊ねるという習慣を持ち合わせていなかった。世田谷の四年生たちは、すでに物を知らないと思われることを何よりも恐れるようになっていたのだと思う。
A級センパンというのは何なのだろう? いましがた聞いたばかりの言葉を忘れないように、僕は心の中で「センパン、センパン」と繰り返した。不思議な響きを持つ言葉だった。家に帰ったら真っ先に母親に訊ねてみるつもりだったし、早く帰りたいと思った。九歳だった僕は、たまらなく葉子の家の秘密を知りたかった。
小学生の頃、僕は毎年、葉子の誕生会に招かれていた。でも僕の母親は、誕生会に行くことをあまり喜ばなかった。母は直美のことを「あの不良女」と呼んでいた。母の言う通り、四条直美は当時の一般的な母親像からは遠く隔たった存在だった。
かなり後になってから知ったのだけれど、母は毎日のように直美を観察していたらしい。母の話によれば、直美はいつも上野毛駅近くの喫茶店で夕方までの時間を過ごし、五時になるとスーパーで買い物をしていたという。
「あの女は三分に一本のペースで煙草を吸っていたよ」
その言葉に母は軽蔑を込めたつもりのようだったけれど、僕はそこにむしろ嫉妬に近い何かを感じ取った。
葉子の誕生日は八月二十日。その日に関する記憶はいまも残っている。夏休みの間に久しぶりに同級生と顔を合わせるのも楽しみだったし、何よりも母親の直美が楽しい人だった。サマードレスを着た直美は同級生たちを盛大にもてなし、食事の時には僕たちの担任教師のことを話題にした。
「あの先生、まだ髪型は変わらないの?」
直美がそう訊ねただけで全員が笑った。確かに変な髪型だった。彼女が教師の髪型を「真っ黒な段々畑」と表現すると、笑いが収まるまでかなりの時間がかかった。
その教師は上野毛駅の近くで車に撥ねられ、入院していたことがあった。
「車にだけは注意しなさい」
僕たちにはいつもそう言っていたくせに、本人は横断歩道を渡りながら「考え事をしていた」らしい。彼が考え事の途中で車に弾き飛ばされた時、事故現場に居合わせたのが直美だったというのは、僕たちの間では有名な話だった。
「うつ伏せに倒れていたから顔は見えなかったけれど、すぐにあなたたちの先生だと分かった。髪型でね」
直美がそう話すと、また全員が笑う。彼女は会話のツボを心得ていた。笑い声が収まると、隣に座っていた子の肩を揺さぶり、こんなふうに続けた。
「先生、大丈夫ですか、しっかりしてくださいって私が声をかけていたら、救急隊員が来て、お知り合いですかって訊くのよ。私、思わず、よく知りませんって答えちゃった」
黒縁眼鏡にショートヘアの直美は、招待客全員の料理を出し終え、いくつかジョークを飛ばすと、あとはリビングのソファーに寝転んで洋書を読み、ひっきりなしに煙草を吸っていた。時折、レコードに合わせて外国の曲を口ずさんでいるのが聞こえてきた。普通の母親とは、やはりどこか違っていた。
若々しく陽気な女性だったけれど、煙草の吸いすぎのせいか、多少声がザラついているのが難点だった。それに、僕たちが帰る夕方近くにはいつもホロ酔い加減だった。見た目には何も変わらないのだけれど、吐く息でそれと分かった。彼女はセブンスターを吸い、『J&B』を飲んでいた。そんな女性が近所の主婦たちに受けのいいはずがなかった。
最後の誕生会となった六年生の夏、直美は僕たちの前でギターの弾き語りをした。
「これまで葉子と仲よくしてくれてありがとう。むかし、流行った曲よ」
そう言って、彼女は流暢な英語で歌い始めた。美しい曲だったし、フォークギターを爪弾くのも上手だった。ラジオで同じ曲が流れているのを聴いて、その時に歌ったのがジョニ・ミッチェルの曲だと知ったのはずいぶん後になってからだ。僕たちが拍手をすると、直美は立ち上がって深々と頭を下げた。この時もきっと少し酒が入っていたのだと思う。
直美自身がデザインしたというモダンな感じのリビングには、昭和天皇の大きな写真が飾られていた。それがひどく不釣り合いだった。
「これ、いいでしょ?」
ある時、僕がその写真を見ているのに気づいた直美は、そう言って悪戯っぽく笑った。それが何だかおかしくて、僕も一緒になって笑った。真面目くさった大人なんかより、不良の方がずっといい――そんなふうに思ったのは、もう十五年も前の夏の午後だ。
僕は四条直美という人が好きだった。葉子の家の近くを通る時、偶然に直美に出くわすことをいつも心のどこかで期待していた。晴れた日にはよく愛車であるベレットを洗車していたし、顔を合わせるたびに声をかけてきた。僕たちはガレージの前で色々な話をした。というか、ほとんど直美が一方的に話し、僕の方は彼女の話術にひたすら圧倒され続けていた。
一度だけ、直美の運転するベレットに乗ったことがある。多摩川べりまでの短いドライブだったけれど、僕にとっては忘れ難い時間だ。どういう経緯から多摩川へなんか行くことになったのか、いまとなっては思い出すことができないけれど、カーラジオから『オールド・ファッションド・ラブソング』が流れていたことを憶えている。あの印象的なイントロが流れると、直美は口笛を吹き、エンジンを空噴かしした。
「大好きな曲よ」
彼女はラジオのボリュームを上げ、一緒になって歌詞を口ずさんだ。曲が早々にフェイドアウトすると、直美はラジオを消し、盛大に舌打ちをした。
「これだから民放って嫌いよ。くだらないお喋りばっかりしてさ」
ひとしきり悪態をつくと、直美は歌詞の内容を説明し、「素敵な曲でしょ」と言った。僕は「はい」と答えながら、結婚するとしたらこんな人がいいな、なんて思っていた。
河川敷に車を停め、僕たちは多摩川べりを散歩した。訊ねられるままに学校のことを話したものの、直美はほとんど上の空だった。彼女はセブンスターに火をつけ、指の間に挟んだマッチ棒を弾き飛ばした。
「この次は一緒に遠くまで行こうか」
川面を眺めながら、直美は唐突にそう言った。遠くって、どこまでですか。そう訊ねると、彼女はこんなことを言った。
「私は西へ向かって走るのが好きなの。この前は名古屋の近くまで行ったわ。本当はもっと遠くまで行きたかったんだけど」
直美が何を考えていたのか、その時の僕には知る由もなかったけれど、いまなら答えることができる。彼女が思い描いていたのは名古屋よりももっと先、伝説に彩られた山々に囲まれた、あのあたりなのだ。
直美が乗っていたベレットは、いまでは僕のマンションの駐車場に停まっている。
丹念に整備されていたから、エンジンは冬でも一発でかかる。ベレットの助手席に葉子を乗せて、僕は週末ごとにスーパーへ買い物に出かける。世の中には古い車が好きだという人間が結構いるもので、駐車場で見知らぬ人に話しかけられることも珍しくない。直美のおかげで、僕はこの界隈ではちょっとした好事家と見なされている。
母親の死後、葉子は大学を中退して帰国し、アメリカ大使館で働いていた。でも、それも半年ほどで辞めてしまい、かなり長い間、渋谷の書店でアルバイトをしていた。ごく近所に住んでいたにもかかわらず、僕たちは道玄坂に近いその大型書店で偶然に再会したのだった。
「母が生きていたら、あなたのことを説明する手間が省けたのにね」
結婚の承諾を得るために葉子の家を訪ねた帰り、彼女は僕にそう言った。
新聞記者である葉子の父親とは、この時が初対面だった。半年もしないうちに孫が生まれると聞かされて、葉子の父親はひどく腹を立てていた。僕にはそのことが気がかりだったけれど、葉子はなぜか楽観していた。それどころか、むしろこの状況を楽しんでいるようにさえ見えた。
「笑っちゃうわ」歩きながら、葉子はくすくすと笑った。
「何がおかしいんだ」
「生まれてくるのは双子の男の子たちなのよ。昨日の検査でそれが分かったの。一度に二人の孫ができるんだから、父はきっと反対している暇もなくなる。威張っていられるのもいまのうちよ。週末には子供たちを父に預けて、遠くまでドライブしましょうよ」
それを聞いて、先ほどまでの気がかりはどこかへ消し飛んでしまった。葉子の中で日々成長し続ける子供に対する恐れも、同時に霧消してしまっていた。この気持ちは双子の父親になることが決まった者にしか分からないかもしれない。他のことは、とりあえずどうでもよくなってしまうのだ。
考えなければならないことはいくつもあり、するべきことも多数あるように思えた。ともあれ、子供たちのために何か食べようということになり、僕たちは二子玉川の『つばめグリル』へ行き、ブイヤベースを注文した。この夜の葉子はいつもよりもずっと口数が多かった。僕の方は新たな状況に慣れるのに、もうしばらく時間がかかりそうだった。
「十年たって変わらないものは何もない。二十年たてば、周りの景色さえも変わってしまう。誰もが年をとり、やがて新しい世代が部屋に飛び込んでくる。時代は否応なく進み、世の中はそのようにして続いていく」
食事が済むと、葉子はそんな意味のことを言った。
「すごいな、いまの台詞」
「実はこれ、母が雑誌に書いていたことなの。世の中はそのようにして続いていく、という部分が私は特に好きなの」
そう言うと、葉子はショルダーバッグからその雑誌を取り出し、テーブルの上に置いた。
コーヒーを飲みながら、僕は記事を読んだ。葉子が口にした一節に続けて、直美はこう書いていた。
「これでおしまいだ、もうどうにもならない。私自身、何度そう考えたかしれません。でも、運命というものは私たちが考えているよりもずっと気まぐれなのです。昨日の怒りや哀しみが、明日には何物にも代え難い喜びに変わっているかもしれないし、事実、この人生はそうしたことの繰り返しなのです」
四条直美はそう信じていた。少なくともそう信じようとし、常に自分にそう言い聞かせていた。
娘に宛てた最後の手紙に、彼女はこう書いている。
「私はこれまでに何千冊もの本を読んできたけれど、それ以上に日々の暮らしから学ぶことの方がずっと多かった。二十代の私は嫌味な自信家だったし、多くの人のことを軽蔑していたけれど、それでもけして自分の知的確信の奴隷にはなれなかった。内心では花見客を馬鹿にしていながら、偶然に桜の花を目にして、その美しさに圧倒されたりしていたのです。ピアニストが毎日休みなく鍵盤を叩くように、私は人生の練習を続けてきたのです」
これが典型的な四条直美である。彼女が残したテープにも、僕はこれとほぼ同じ響きを何度も聞いた。
初めてテープを聞いた夜のことを僕はけして忘れないだろう。その後、繰り返し聞き込んだせいで、いまでは咳払いやノイズが入る箇所までも熟知している。
直美の話には重複が多いし、明らかに混乱している部分もある。登場人物の何人かは、恐らく彼女の中で理想化されている。言いよどむ箇所もあれば、省略されすぎている部分も多い。そうかと思うと唐突にテープが途切れてしまうこともある。やはり彼女には時間がなかったのだ。
このように、肉声で吹き込まれた四巻のテープは、人間の話し言葉の常として不完全なものだというのが真相だが、それにもかかわらず、低い声で語られたこの回顧録のいくつかの部分にはどこかしら圧倒されてしまうところがある。
フローベールは言っている。ペンとは何と重い櫂なのだろう、と。漕いでも漕いでも進まないのだ。最後の手紙に記されていた人生の練習――その結果がどうあれ、人生の最後にこの困難な仕事に立ち向かおうとした四条直美を僕は愛し、そんな彼女をいまも支持する。