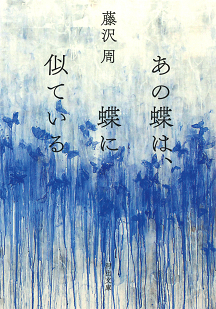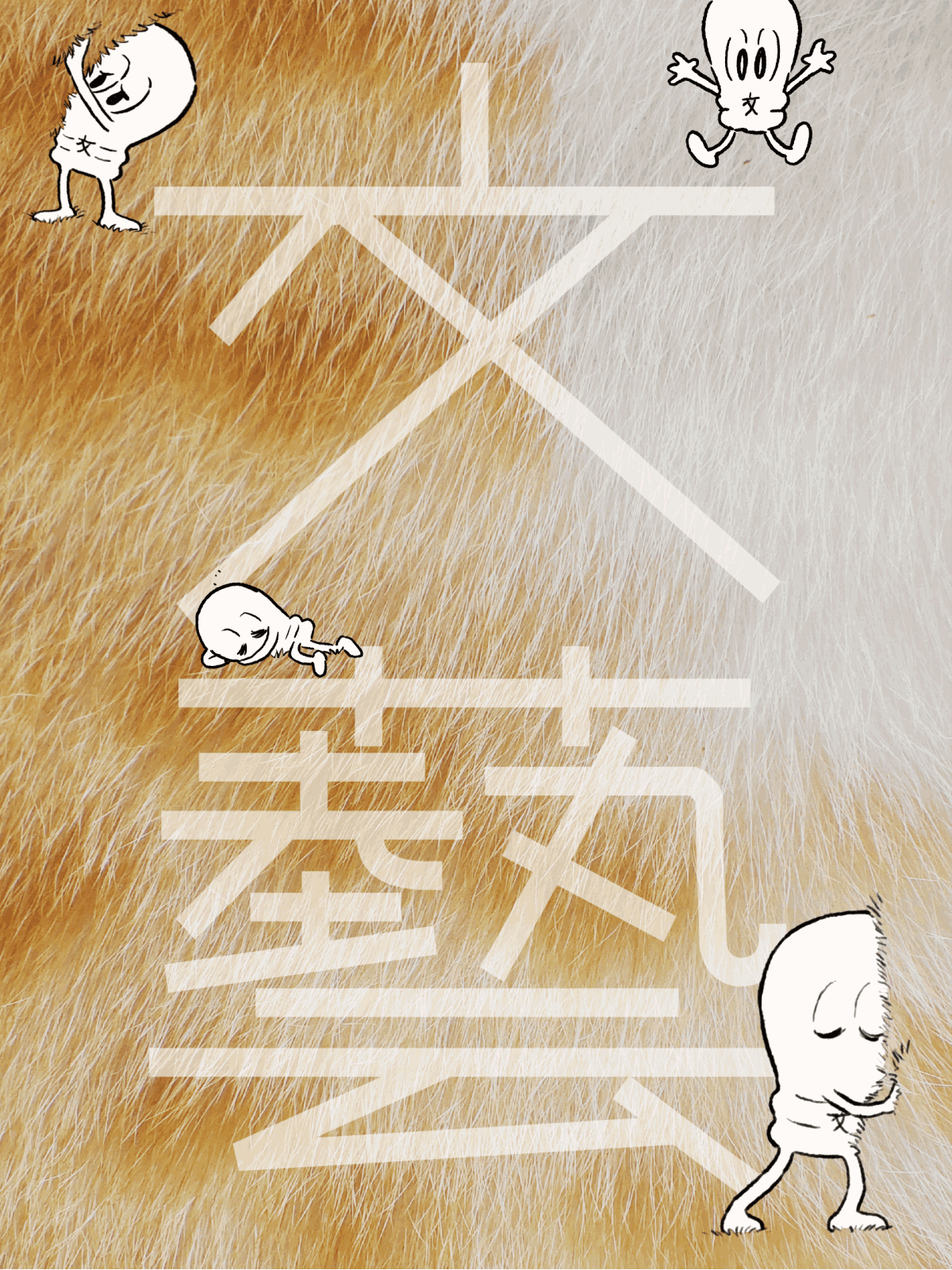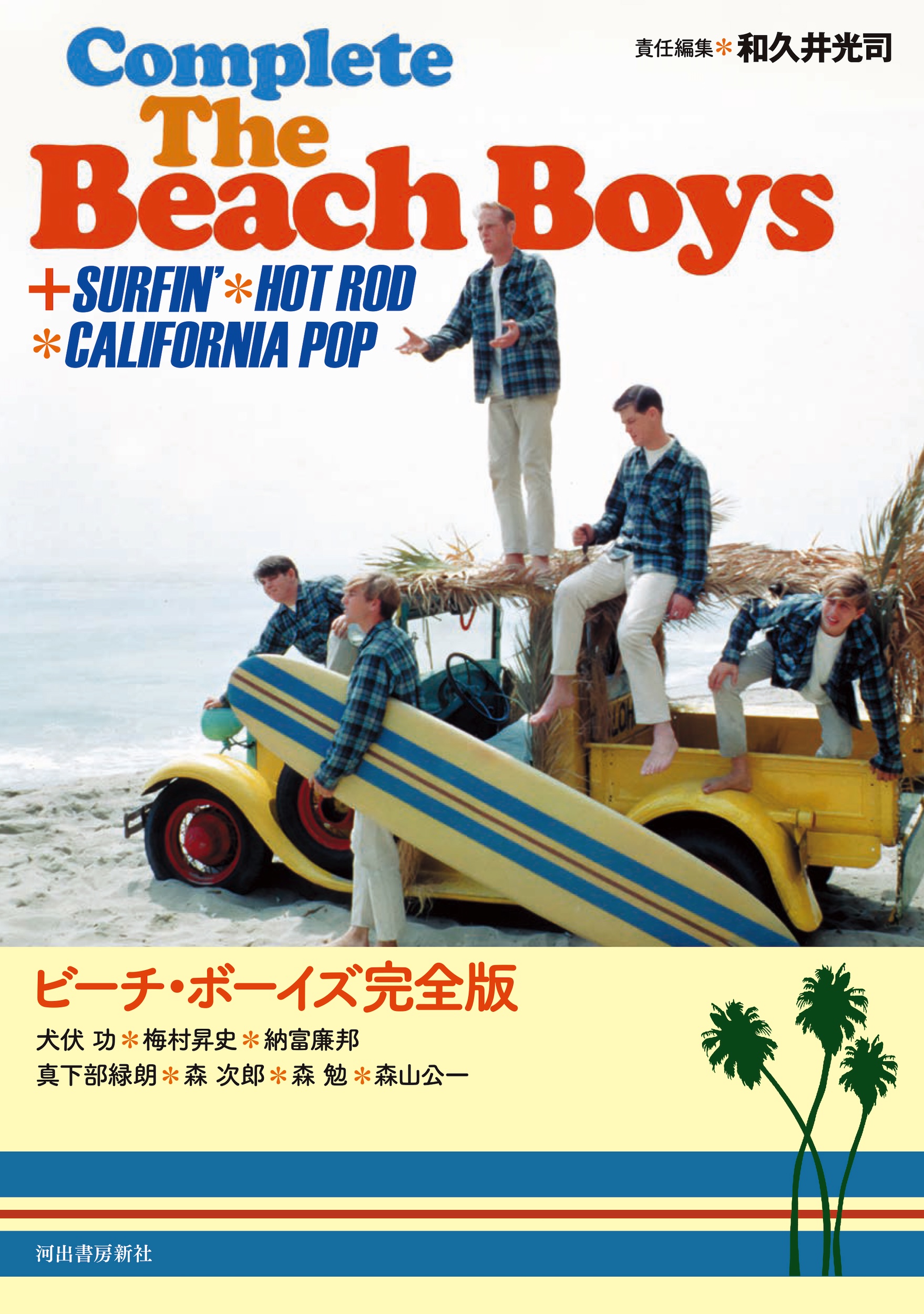単行本 - 日本文学
芥川賞作家・藤沢周が人間・世阿弥を描く感動長編『世阿弥最後の花』発売。本書執筆に寄せてエッセイ公開
藤沢周
2021.06.25

世阿弥は、なぜ72歳で遠く佐渡へと流され、彼の地で何を見つけたのか?
室町の都を幽玄の美で瞠目させた天才が最晩年に到達した至高の舞と、
そこに秘められた謎に迫る著者最高傑作!
* * *
『世阿弥最後の花』執筆に寄せて
まことの花
藤沢周
闇に揺らめく炎に、霊の輪郭が朧に浮かび上がってくる。仄かにあらわれた面は泣いているのか。憂えているのか。佐渡島の正法寺で毎年行われている蠟燭能。主人公であるシテの幽霊の静かな語りを聞きながら、私は人の無意識の底に沈む物語を世界で初めて舞台化した人について、想いを馳せていた。室町時代に、七〇歳を過ぎた老いの身で佐渡に配流となって、その古刹に逗留したという能の大成者・世阿弥元清(一三六三?~一四四三?)についてである。
『風姿花伝』や『花鏡』『拾玉得花』など世阿弥の能芸論は、個人的に親しんでいた禅や武道とも通底していて、昔から事あるごとに繰ってはいたが、晩年のその人を描くという畏れ多い試みなど、考えもしなかった。だが、正法寺の寺宝である世阿弥所有の「雨乞いの面」という鬼神面を、観能後に拝見した時に、声なき者の言葉が聞こえた気がしたのである。
――それは、父観阿弥の形見……。
そして、父親の形見である鬼神面を厳かにかける世阿弥を、そばで見守るように座すもう一人の男の姿も浮かんできた。誰か。老翁を見つめるその眼差しのあり方を追ううちに、伊勢で急死し、逆縁となった世阿弥の息男元雅のものではないか、と思えてくる。その刹那、闇の中を世阿弥が舞い、霊の元雅が添うた。
世阿弥が都から遠い佐渡の地にまで持ってきた雨乞いの面が、観阿弥の形見であるというのは、むろん私の想像である。だが、その直感の感触が一気に「世阿弥最後の花」執筆へと向かわせた。世阿弥の創出した夢幻能は、シテである霊の声を、ワキの僧などが感受して物語が進むが、私の作品は逆に霊である元雅がワキとなって、シテである老いた世阿弥の声を聞くことにもなった。
この作品を書くにあたって能を自らの身体に通したいと、観世梅若流の謡と仕舞を稽古するようになったが、ほんのわずかな動きにさえも森羅万象とつながっているのを体感する。また、全方位と自己とのぎりぎりの均衡そのものが、「在る」ということなのだとも。
晩年の世阿弥が摑んだ到達点とは何か。老いという人生の鄙、佐渡の地という鄙。都で一世を風靡した世阿弥が、配流の地で「まことの花」をいかに咲かすのか。これは現在の私たちの生き方にとっても、大事なことのように思えるのだ。
「文藝」2021年夏号掲載