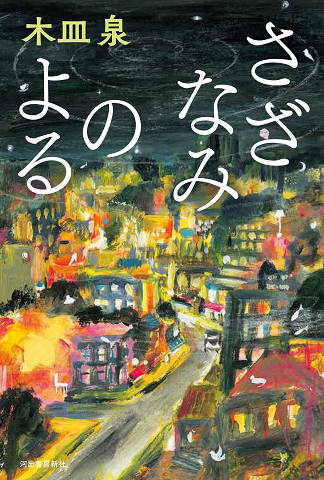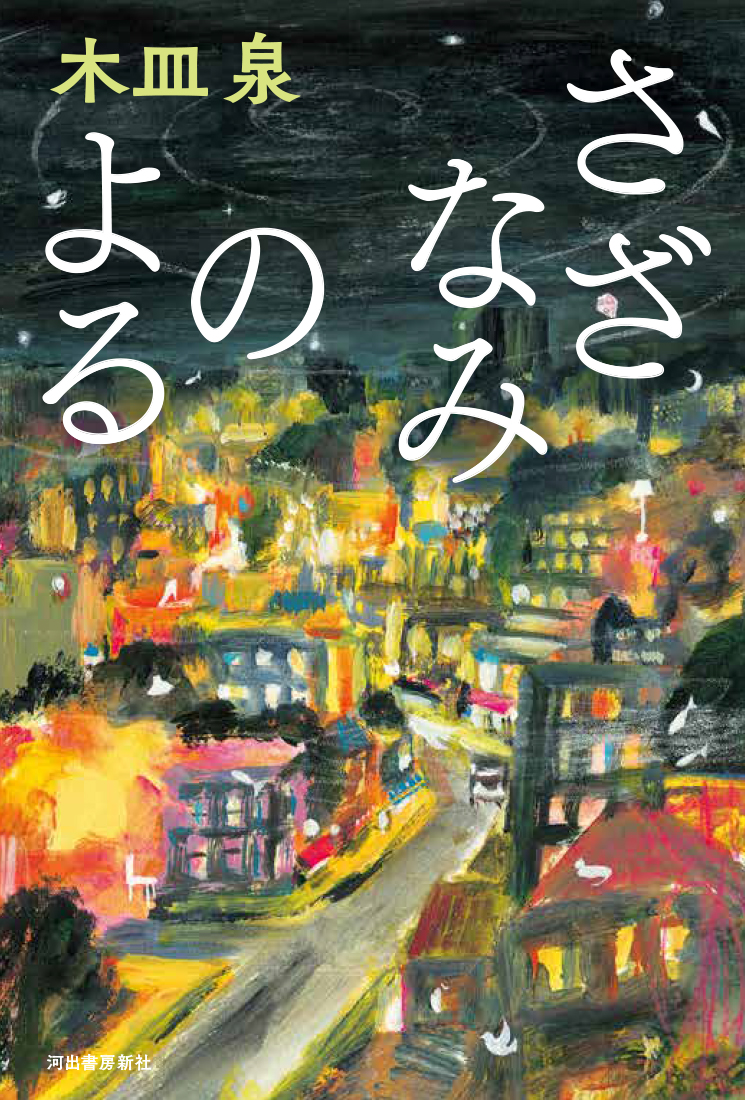
単行本 - 日本文学
文学というよりも、光だ──『さざなみのよる』書評
評者・山崎ナオコーラ
2018.06.11
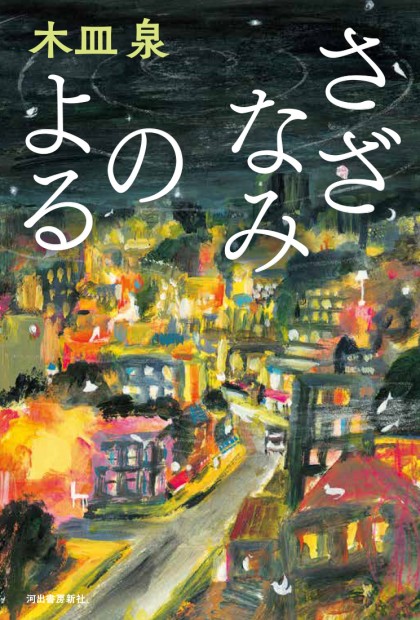 木皿泉『さざなみのよる』書評
木皿泉『さざなみのよる』書評
*********
文学というよりも、光だ
山崎ナオコーラ
文学は死の仕事を常に行ってきた。死とは何か、死をどう受け止めたら良いのか、世界中の作家が考え続けている。古今東西の小説に死が描かれており、死はありふれたテーマだ。
『さざなみのよる』も、死に関する仕事が行われている小説だ。
ただ、この小説は、文学なんて概念が吹っ飛ぶくらいの迫力がある。『さざなみのよる』は、文学というよりも、光だ。
作者の木皿泉さんがこの執筆に大きな気持ちを抱いて臨んだのだろうということが、文章の端々から伝わってくる。ただ、その気持ちというのは、文学的な野心や、仕事の責任感ではなく、祈りのようなものだったのではないか。そうだ、それでいいのだ。小説を書くからといって、いつも暗闇を描いたり、恥や悪に挑んだりする必要はない。小説は、自由だ。祈りながら、光を見つけて、ペンを動かしたっていいのだ。
日常においては、多くの人が死を語りたがらない。死なない方が良い、死が訪れることはもちろん、死を口に出すことも避けた方が良い。死なんてものが世にないフリをして過ごした方が日常を明るく過ごせる、と思い込んでいる。逆に文学では死がよく扱われるが、その際は、秘密を暴くように、暗闇を見つめるように描かれがちだ。だが、『さざなみのよる』の読後に、考えが変わる。死をみつめた方が、かえって日常をうまく送れる。そして、死を明るく書いていい。
前作『昨夜のカレー、明日のパン』でも、ひとりの人間の死を、いろいろな登場人物がそれぞれのやり方で受け止めていく様が描かれていた。『さざなみのよる』も、その形で始まる。まず、死ぬ本人であるナスミが死を受け止め、姉妹や夫などの身近な人たちがそれぞれのやり方で死を感じていく。
出だしを読んだとき、私はちょっとつらくなった。ああ、また死を感じなければならない。ユーモア溢れる筆致とはいえ、悲しみに耐えなければならないし、読むのに力がいる、と思った。それに、末期がんのリアルな描写に、身近な人の死を思い出してしまう読者も多いのではないか。死について考えるのが文学だが、力仕事だし大変だ。だが、読み進めるうちに、これは違うぞ、とわかってきた。死の新しい地平が描かれるぞ、と。
そう、ラストに向かって、どんどん明るくなっていくのだ。なぜ明るくなるのか。それは、死を完全に肯定していくからだ。「死なない方が良い」という基本的な価値観が、どんどん打ち壊されていく。死があるからこそ、世界が成り立っている。「世界とは、死だ」と言っても過言ではない。「ウェルカム、死」という気分になってくる。
ふざけているときにも、笑っているときにも、子どもを産んでいるときにも、死は隣にある。死を忘れたから笑えるのではなく、死を考えたからこそ笑える。日頃から、死について、考えたり喋ったり書いたりして構わないのだ。この先の自分の人生にも必ずある、自分の死や身近な人の死が怖くなくなった。 (「文藝 二〇一八年夏季号」より)