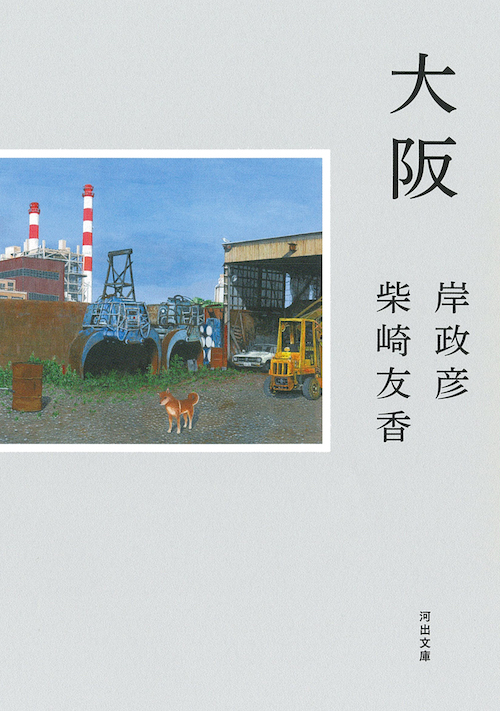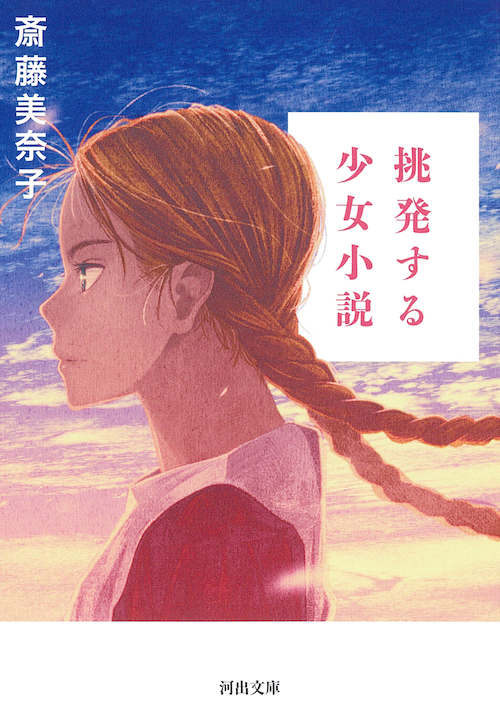単行本 - 日本文学
闇からの一撃──辻原登『不意撃ち』書評
評者・東山彰良
2019.03.25
私の信念のひとつに、「想像しうる悪いことは、現実には起こらない」というのがある。たとえば飛行機に乗るときには、敢えて墜落について想像をたくましくする。そうすれば、私が搭乗した飛行機はぜったいに落ちないというわけだ。根拠はない。しかし、奇妙な確信めいたものはある。だってそうだろう。最悪なことは、私たちが思いもかけないときに、思いもよらない形で襲いかかってくる。それはいつだって、想像力を遥かに超えてくる。そうじゃなければ、「最悪」を名乗る資格はない。
さて、辻原登氏の新刊は五つの短篇を編み込んだ、その名も『不意撃ち』である。「不意撃ち」と言うからには、まったく想像もつかないようなアクシデントが登場人物たちを襲う。そしてその不意撃ちによって物語は思いもよらない方向へと落着していく、もしくは堕ちていく。「渡鹿野(わたかの)」の主人公はデリバリーヘルスのドライバーで、懇意になった風俗嬢を追ってたどり着いたのは、伊勢の海に浮かぶ売春の島だ。「仮面」は東日本大震災をモチーフにしており、ボランティアと称する男と女がある犯罪に手を染める。「いかなる因果にて」は少々特異で、短篇小説でありながら辻原氏自身の回想録のような趣がある。あるささいな事件が呼び水となって、それがいつしか語り手が中学時代に遭遇したある教師による体罰の記憶へとつながっていく。「Delusion」では女性宇宙飛行士が精神科医のもとを訪れる。彼女の身に起こった不思議な幻覚体験が現実世界を侵蝕し、精神科医をも巻き込んでいく。
出色なのは、なんといっても「月も隈(くま)なきは」だろう。平穏無事な人生を歩んで定年退職した「奥本さん」がある日突然、妻子に隠れて独り暮らしを始める。ほかに女がいるわけでも、確たる目的があるわけでもない。趣味が街の散策と将棋の奥本さんがなぜ発作的に家を出たのかと言えば、それはいわば中年の危機的な逃避としか言いようがなく、自分探しのためのささやかで大いなる一歩を踏み出しただけのこと。他の短篇で描かれる不意撃ちには瞬間的なものもあれば、あとからじわりと効いてくる毒薬のようなものもあるが、本編のそれは間違いなく後者だ。この奇妙な独り暮らしの徒然に奥本さんは思索し、それまでの人生を襲ったいくつかの不意撃ち、つまりはよく理解できないけれど彼の心に強烈なインパクトを残した出来事を回顧する。その果てに奥本さんがたどり着く結論はちっぽけで、ありきたりだけど、このうえなくありのままだ。そう、なにものにも制限されない自由など、もはや自由でもなんでもないのだ。
人生は思いもよらないことばかり起こる。ひとつの不意撃ちが長い年月を経て次の不意撃ちと結びつくこともある。不意撃ちに打ち倒された者は少しだけ強くなり、もう少しだけ遠くまで歩ける。そしてまた、次の不意撃ちに打ち倒されるのだ。運がよければ、また立ち上がれる。けっきょくのところ、私たちはそのようにしか前へ進めないのではないだろうか。