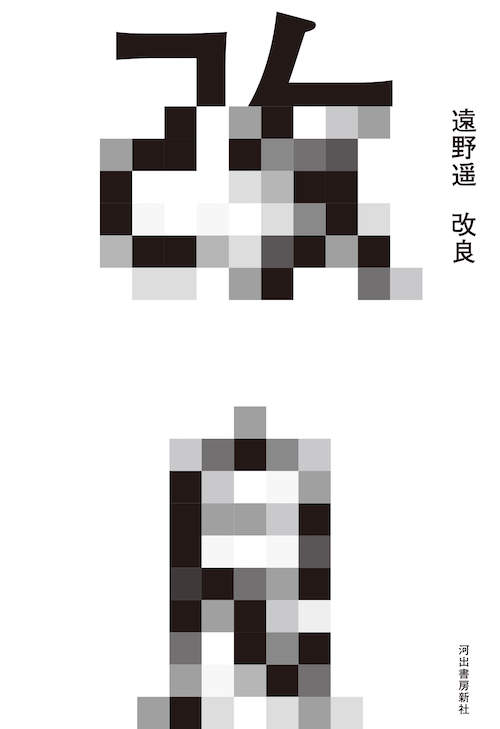単行本 - 日本文学
第56回文藝賞受賞記念対談 磯﨑憲一郎×遠野遥
唯一無二の語り口ーー型にはめる圧力に抵抗する小説、28歳の新たなる才能
遠野遥 磯﨑憲一郎
2019.11.15
第56回文藝賞受賞作『改良』(遠野遥著)が、11月15日に単行本として刊行されました。異性装をモチーフに男女の性差以前の生のあり方を、極限の絶望で描き出した本作。受賞を記念し、選考委員のひとりである磯﨑憲一郎さんと、その創作の背景について語り合いました。
自分自身をも疑う小説
磯﨑 「改良」という作品のなにが他と違って優れているのかというと、作者が常に自分自身や自意識といったものを疑いつづけている、という点です。たとえば、冒頭で語り手の「私」がスイミングスクールに通っていた話が出てきます。そこで、「私は常にスクールをやめたいと思っていた気がするけれど」と書いている。普通は「スクールをやめたいと思っていた」と書くところを、遠野さんは「気がする」をつけてしまうんだよね。つづいてそのスイミングスクールをやめる頃には喘息が治ったという話になるけどそこで、「でもそれは水泳をやっていたからではなく、成長とともに自然と治ったのだと思う」と書いて、常に現実を揺るがせつづけているんです。
遠野 スイミングスクールに通っていたことや、喘息が治ったことは、実際に私もそうなんです。
磯﨑 なるほど。そしてスイミングスクール友だちの「バヤシコ」も、誰がどう考えても本名は「小林」なんだけど、「バヤシコと呼ばれているということはたぶん小林だったのだと思うが、子供はたまに奇想天外なことを考えるから定かではない」と書く。この、すべての可能性を考えなければ気が済まない目線が、明らかに異質なんですよね。遠野さんがこれをどこまで自覚的にやっているのかはわからないんですが。
僕が最初に「これはいい小説だ」と思った表現があって、それは、バヤシコが主人公のズボンを下ろして性器を触り始める場面で、「こんなことはやめさせなければと私は思った。しかし、なぜやめさせなくてはいけないのか、理由はよくわからなかった」というところです。つまり、この主人公は、自分が嫌だと思ったことについてすら、その是否を検証せずにはいられないんです。さらに、「混乱の中で、やめてくれと私の口が言った」と書く。ここで、これは明らかにふつうの小説とは違うと思いました。ふつうは「やめてくれと言った」ですよね。それを、「私の口が言った」と突き放す。明らかにこの作品の作者は、世界との向き合い方に独特の何かを持っていると感じました。
遠野 自覚的というよりも、素直に文章を書くと、自然とこうなるんです。むしろこういう書き方は矯正したいと思っていて、実際に削った部分もあります。でも、ここは読み直してもこの描き方以外に考えられないと思いました。
磯﨑 僕はこの異質さを信じて、「改良」を受賞作に推したんです。これは文体の問題とか小説の書き方のテクニックの問題として捉えられがちなところだけど、そうではない。おそらくどうしようもなく出てきてしまう、思考の癖みたいなものなんですよね。
遠野 思考の癖というのはその通りだと思います。小説に限らず、私は普段からこんな感じです。
磯﨑 自分自身も含めた世界のありようを、疑わずにはいられないんですよね。その思考の癖みたいなものがどうしようもなく出てきてしまっているところが、小説として信頼に足ると思った。「改良」が受賞にふさわしい作品なのはその点です。この小説は、物事を型にはめよう、単純化しようという世の中の圧力に対して、徹底的にゼロに立ち戻って考えているんです。「なんで女子と男子で水着のかたちが違うんだろう」という主人公の言葉についてバヤシコが、「たぶんお前は身体は男で心は女っていう、そういう人なんじゃないか」と言い、「隠さなくても大丈夫だよ。オレ、変な目で見たりしないし。たぶんメチャメチャ理解とかあると思うし」とつづける。こういう、凡庸さの型にはめようとする圧力に抵抗する、その戦いが描かれている。
遠野 戦いを描く意図はありませんでしたが、物事を型にはめたり、無理に説明をつけたりとか、単純化しようとする圧力への嫌悪感はあって、それが自然と出てきたのだと思います。
磯﨑 その、自然と出てきたというのが重要なんです。その後大学生になった主人公が、デリヘル嬢の「カオリ」を家に呼ぶ場面でも、「カオリが少しだけ声を出して笑う。カオリの身体の振動が私に伝わる。人は笑うと振動するのだなと私は思う」と書く、この徹底的に冷徹な観察者の視点。ここはいくらでも感傷的に書こうと思えば書ける場面で、しかしそうすると台無しになる。そうではなく、つづく文では「カオリは私の言ったことがおかしかったというよりは、私が何を言ったとしても、あらかじめ笑おうと決めていたような感じだった」という、この突き放し方。それから、コールセンターのバイト仲間である「つくね」が、ストーカーまがいの電話を受けたと主人公に相談をして、下心を持った主人公が家まで送ると言って、ひとり暮らしのつくねの家へ行く場面がありますね。ここで主人公はつくねにセックスを持ち掛けたくてできないんだけど、その時に「セックスを日常的に行っている人間がこの世に少なからずいることを思い、今更のように愕然とした」と書く。プロで何年もやっている作家でも、こういう場面はつまらなく書いてしまう人が多いんだけど、遠野さんは、自分を外側から見る感じというか、自意識から遠く離れた感じを、終始徹底しているんですよね。
遠野 ありがとうございます。
磯﨑 そうやって、自分からどうしようもなく自然と出てきてしまったものをこそ、大事にしなければいけない。編集者によってはよけいなことを言ってくる人もいるから、批判されても簡単に反省しちゃいけない。作家は、なけなしの自分だけを頼りにしてやっていかなければいけない仕事だし、編集者よりも批評家よりも読者よりも、誰よりも作品を何度も読み返しているのは書き手なんだから、なによりも自分を信じなくちゃいけないんです。だから、外からいろいろ言われても、遠野さんが「自然と出てきた」という、そこを信じてやっていくしかないんですよね。
ありきたりな意味に回収されない
磯﨑 僕は「改良」を読んで、ベケットの『モロイ』を思い出したんです。『モロイ』の冒頭は、「私は母の部屋にいる。いまここに住んでいるのは私なんだ。どうやってここにたどり着いたのか、よくわからない。たぶん救急車か、とにかく車に乗ってきたはずだ。誰かが助けてくれたにちがいない。ひとりではたどり着けなかっただろう」(宇野邦一訳)というものです。自分がいまここにいることの来歴の不確かさというか……。この感じが似ているような気がしました。

遠野 冒頭からすごく面白そうですね。
磯﨑 ベケットはあまり読んだことはないんですね?
遠野 大学生のときに義務感から一度だけ『ゴドーを待ちながら』を読みましたが、それだけです。
磯﨑 きっと遠野さんが読んだら面白いと感じますよ。
遠野 ぜひ読んでみたいです。
磯﨑 主人公が美術館へ行く場面がありますよね。鏡の前に立つと機械の部品が集まってきて、腕が機関銃みたいになる作品が出てくる。そういうところも面白いと思うんですが、現代美術がお好きなんですか?
遠野 そうなんです。学生時代に美術館を舞台にしたホラーゲームを好きになり、それがきっかけでした。
磯﨑 どんな作品が好きなんでしょう?
遠野 美術館へ行っても自分の小説のことばかり考えてしまうので、どの作家が好きというのはあまりないんです。でも、二藤建人さんの「手を合わせる」という作品は特別に印象に残っています。二〇一六年のあいちトリエンナーレで観たんですが、簡単に説明すると、ごくふつうの部屋の中にテーブルがあって、その上に水の入ったポットとお湯の入ったポットが置かれている作品です。鑑賞者は自分で別々のコップにお湯と水を注ぎ、片方の手でお湯の入ったコップを持ち、もう片方の手で冷たい水が入ったコップを持ちます。そうして温度に差がついた両手を、温度が揃うまで合わせているという体験型の作品です。私がこの作品の何に衝撃を受けたのか、うまく説明できませんが、説明したいとも思わないぐらいすごい作品でした。
磯﨑 遠野さんが美術を好きなのはきっと、ありきたりな意味に回収されないものに魅力を感じているということですよね。それはすごく大事なことだし、ご自分がそういうものに魅かれる感覚は、信じた方がいいと思います。
遠野 本を読むよりも、そうしたことの方が大事でしょうか?
磯﨑 本も読んだ方がいいけれど(笑)。僕の場合は音楽だったんです。音楽が与えてくれる高揚感とか、記憶の喚起力とか、小説を書くことでそうした感覚に近づきたいという思いが常にあるんです。すぐれた美術作品や音楽作品に触れたとき、言葉で表現できないような驚きってありますよね。その感覚に対して、いかに言葉を用いて近づいてゆくのか、だと思うんです。だから、小説を書く人は自分の中のそういう部分を大切にした方がいいと思います。
型にはめる圧力との戦い
磯﨑 この作品の主人公は、女性用のウイッグをかぶって、女性用の洋服を着て、家でメイクをしながら、美しくなりたいと思っています。だから多くの人は、これはジェンダーやセクシュアリティの問題を扱った小説だと言うと思うんです。毎年河出から出ているプレスリリースの作品の内容紹介をディスって申し訳ないんだけど、ここでもやっぱり、「希薄な人間関係にすがりながら、美への執着心の果てにもたらされた暴力とは……冷徹な文体で、現代を生きる個人の孤独の淵を描き出す。男であること、そして女であることを決めるのは何か?」と書いてある。この小説って、そういう内容の「新世代のダーク・ロマン」なのかなあ? 僕は、ジェンダーやセクシュアリティや孤独を描いた小説だとは、ぜんぜん思わなかった。むしろこの小説は、そうやって物事を型にはめて単純化しようとする圧力や凡庸さとの戦いの記録なんですよね。それは、先ほど話した子供時代のバヤシコとの場面でそれははっきり書かれていますね。大学生になり女の格好をするようになって、その姿を見せたデリヘル嬢のカオリから「変態さん」と言われて強く拒絶する場面もそうですし、その後ナンパしてきた男にトイレへ引きずりこまれて暴行を受けた時に、「私は、美しくなりたいだけだった。男に好かれたいわけでも、女になろうとしたわけでもなかった」と書いて、つづいて「本当にやるべきことは恐怖や嫌悪の原因を根本から取り去ることで、そして今ならそれは難しくなかった」と書き、反撃を始めるのも、これらはすべて、主人公の存在をありきたりの型にはめようとする圧力との戦いなんですよ。
遠野 「改良」がジェンダーやセクシュアリティや孤独を描いた小説だとは、私も思っていません。でも、どのように読んでもらっても構わないです。私は一枚岩ではないから、そういうものを描きたい気持ちがまったくなかったかといえば、それはわかりません。ただ、圧力や凡庸さとの戦いの記録と言われた方が、どちちらかといえば今の自分にはしっくりきます。

磯﨑 ベケットだって、「母と子の関係を描いた作品」とか「レジスタンス経験を描いた作品」とか、そういったわかりやすい解釈に落とし込もうとされたわけです。ベケットがそれと戦いつづけたように、遠野さんもこれから小説を書きつづけていくのなら、物事を単純化しようとする圧力に常にさらされるから、それに負けちゃいけない。作家を続けていてつくづく思うのは、作家というのは小説の中にしかいない、小説の中でのみ生き続けるということなんですよね。小説家は、小説を書くことによって圧力に抵抗しないといけないんですよ。
この小説は面白いところはたくさんあるんですが、僕が特に面白いと思ったシーンのお話をします。まず、ナンパ男からトイレで暴行を受けながら主人公は、「踏まれた腹はもちろん痛んだが、それ以上に大切な洋服が汚れてしまったことを思った」り、頭を摑まれて「ウイッグが本来あるべき位置から大きくずれるのを感じた」り、ずっとそういうことを気にしている。それも面白いんですが、僕がこの小説はやはりいい小説だなと思ったのは、男から首を絞められて殺されそうになるくらいの危機的状況をはねかえして、男が首から手を話したときに主人公が咳き込むんです。その瞬間、幼少期の喘息の経験を思い出す。そして、「私のことを思ってスイミングスクールに通わせてくれた親への感謝が唐突に溢れ」る、ここなんだよね。これが小説的リアリティだと思うんですよね。
遠野 そこは私も大事だと思っています。私は一度小説を書きあげると、批判的な観点から何十回か読み返して原型がなくなるくらいボコボコに修正しますが、この一文はたぶん最後までこのまま残ると最初から思っていて、実際に残りました。
磯﨑 この一文を出せるということが、この小説の独自性であり、遠野さんの身体性だと思うんですよね。その後の、殴られて鼻が曲がってしまって「もし治らなかったら、そのときは、いっそお金を貯めて整形でもするしかない」「整形をするなら、風俗に金を使うことはできない」というところも、まあ面白いんだけど。でも、これは選評にも書いたんですが、僕はこの作品のネーミングセンスがわからなかった。
遠野 そうですか……。
磯﨑 「バヤシコ」もそうだし、「ヨシヨシ」「つくね」「五里霧中ズ」というのも(笑)。
遠野 「つくね」については、焼き鳥のつくねが好物なので、書くのが楽しくなり、結果的にいいものが書けると考えたんです。ねぎまも好きなので、つくねかねぎまかで最後まで迷いました。でも、何かできるだけポップで親しみやすいものにしようというサービス精神もあったかもしれません。
磯﨑 それはまったくいらないサービス精神だね。タイトルの「改良」も、受賞作の感じじゃないんだよな。でも、そういうところも含めて遠野さんの中の何かなのだと思う。もしそれがあなたのセンスであって、どうひねり出してもそうしたものしか出てこないのだとしたら、きっとそこには何かあるんですよ。
遠野 タイトルを決めるにあたっては、100か200くらい案を書き出して、その中からベストなものを選んだつもりです。
磯﨑 だったらそこには何かあるんですよ。プロの小説家になったら、いろいろなことを言われるけど、それでも最終的に決めるのは自分であって、その場合に、自分の中からどうしようもなく出てきたものに忠実に従うというストイックさが必要なんですよね。
唯一無二の語り口
磯﨑 小説はいつ頃から書き始めたんですか?
遠野 六、七年前からです。
磯﨑 きっかけはあったんですか? 何かを読んで、面白いから自分も書いてみようと思ったとか……。
遠野 過去の私が何を考えていたのか私にはよくわかりませんが、その少し前には、夏目漱石を読んでいたのをなんとなく覚えています。前期三部作の『三四郎』『それから』『門』や後期三部作の『彼岸過迄』『行人』『こころ』を何度も読んでいました。記憶力が悪いので内容はほとんど覚えていないんですが、書き方のほうに注目していた気がします。
書き始めてからも、最初の数ヶ月間は漱石全集を机に置いて、書き方に迷ったときにはよく参照していました。たとえば人物の外見的な特徴をどの程度書き込むべきか迷ったときに、漱石はどの程度書き込んでいるのかな、と参照したりしていました。
磯﨑 漱石を読んで書くようになった、というのも珍しいですね。
遠野 漱石がきっかけかというと、そうではない気がします。今思えば、小説に限らず音楽でも美術でもその他の分野でも、この世には作品をつくっている人間がたくさんいるのだから、自分もいつまでもオーディエンス一辺倒でいてはいけないんじゃないかと思っていた気がします。
私は小説を書く時間と読む時間の割合が九対一くらいで、つまり全然読んでいないんです。自分の小説に行き詰まったら他人の小説を読もうと思っているのですが、ここ二、三年行き詰まっていないので、電車の中とか、待ち合わせに人が現れないときとか、ちょっとした隙間時間にしか読んでいません。でも、これから先も書き続けていくためには、さすがにもう少し読んだ方がいいんじゃないかと感じています。磯﨑さんも、やはりたくさん読んだ方がいいと思いますか?
磯﨑 読んだ方がいいですよ。まだ二十八歳だから、たくさん読んだらいいと思う。まずはベケットを読んで欲しいけど、自分で面白いと思う作家を見つけたら、その人の作品を全部読む、という読み方がいいと思う。小説家は学校の先生じゃないから、たとえば太宰治は一作も読んだことありません、谷崎潤一郎は知りません、といっても全然いいけど、好きな作家のことなら細かいことでも、誰よりも知っている、という方が大事です。遠野さんの作風だったら、カフカは好きかもしれない。
遠野 いまはジム・トンプスンを読んでいます。私の作品がトンプスンに似ていると言った人がいたので、それで気になって最近読み始めました。どこが似ているのかよくわかりませんが、でもとにかく面白いことは面白いので、たぶんトンプスンの作品はこれからも読むと思います。語り手が個性的で面白いので、どんな場面でも退屈せず読めてしまいます。
これからプロとして小説を書いていくうえで、大事なことって何でしょうか?
磯﨑 僕は、小説は語り口がいちばん大事だと思っています。二〇〇七年に僕が文藝賞でデビューした頃よりもはるかに、今強くそれを感じるんですよね。小説を書けば書くほど、そう思うようになってきた。語り口は、絵画でいえばタッチにあたるようなものだと思います。小説を書くときに、その語り口に乗っかれるかどうか、これがほとんどすべてなんじゃないか、テーマとかメッセージなんて、ある意味どうでもいい。文体、と言うとアカデミックで、テクニック的なニュアンスが入ってしまうから、僕は文体とは言わないようにしています。ただ、語り口に導かれて書かれた小説はいまの世の中、分が悪いんです。というのも、昨今は小説が売れないから、意味に回収できる小説の方が、説明しやすくて共感させやすい、つまり出版社が売りやすい。でも、古井由吉さんも金井美恵子さんも、語り口で書いていると思うんですよね。そしてその語り口というのは、長く書きつづけることによってしか生まれない何かなんです。遠野さんの「改良」は、そうした独自の語り口の萌芽が感じられる作品だから、それをご自身で、いかに育てていくかというのが一番大事なんじゃないかと思います。
(二〇一九・九・七)