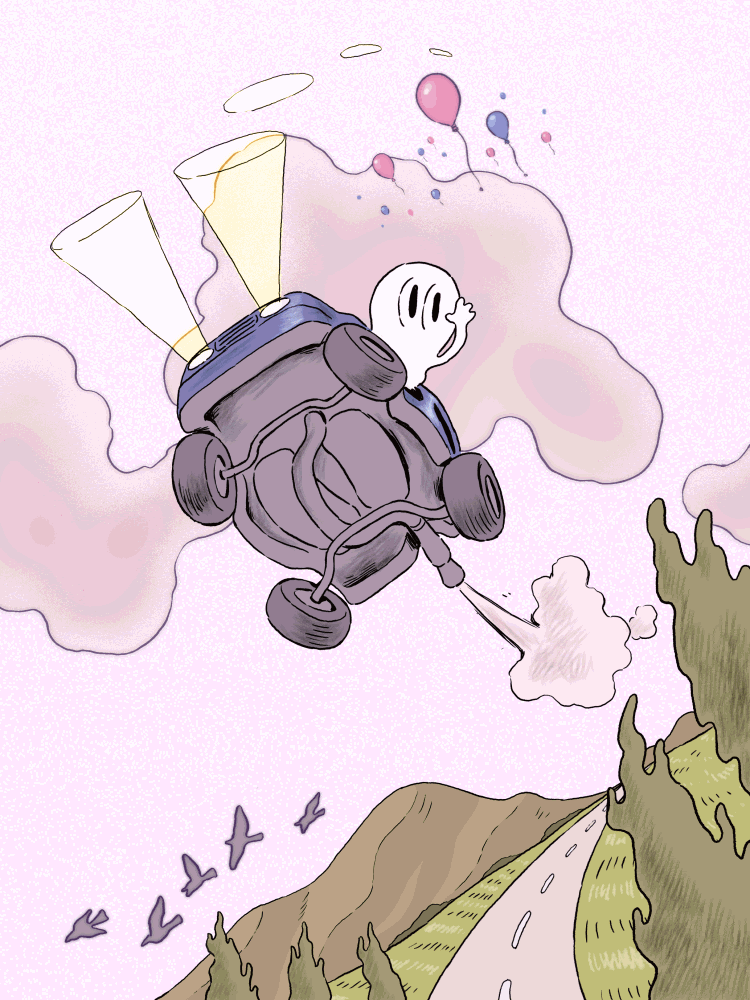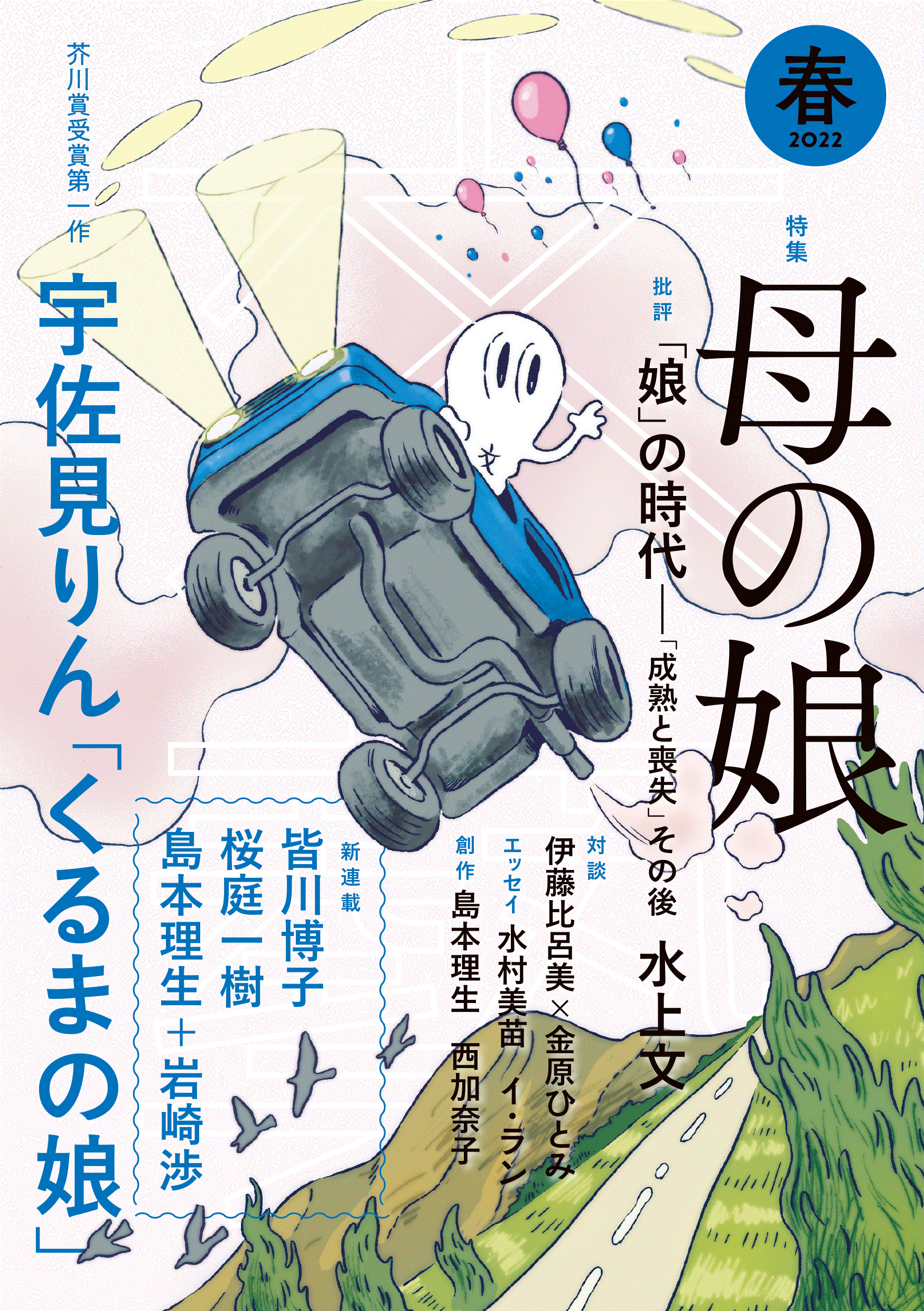
単行本 - 日本文学
作家・新胡桃が震撼した「ほんとうのころし、ころされ」とは? 町屋良平著『ほんのこども』
新胡桃
2022.02.07
MADとは、既存の映像・画像をいち個人が継ぎ接ぎしてつくる作品の事だ。
本書を読み始めてすぐ、数年前にネットで見かけたあやしげなMADを思い出した。四分の一秒毎にすばやく切り替わる映像は様々で、セル画時代のアニメーションから蝶の飛び立つ様子、戦前の政治情勢を記録したものと思われるモノクロフィルムに至るまで、雑多に集められた素材は統一されていない。音楽も、簡素な何小節かを繰り返すギターのみだ。
しかしそこに、圧倒的な強度と、釘付けになるような生っぽさがあった。にこちゃんマークとヒトラーの演説が、ケネディ大統領の笑顔とセーラームーンが、すべて等しい重さで、つめたく層になっていく。喜劇と悲劇もハレとケも、ただ過ぎゆく現実の一瞬だという残酷さが胸を衝いた。虚しい、いやな中毒性があった。
本作は徹底して、私たち読者を平らな地面に立たせない。フィクションのありふれた展開に収まる事も、あべくんや筆者の感情に分かりやすい線を引く事も、もっと言えば物語の枠にある事すら拒んでいるからだ。やがて私たちは、クリアな視界でこの小説を「解釈」するのを諦める。詩歌を楽しむみたいに、言葉、ひらがなの連関や強弱のパンチを食らいながらも、不安定な文のテンションや虐殺の歴史、ストーリーそのものに体重をあずけ始める。
風景や、躯体としての人間がこわれる様が詳細に描かれる時、登場人物は基本、サブリミナル効果のように唐突なタッチで、記号的に感情を表す。あべくんが優しくした女の子や友達のお母さんはえてして「キュン」または「トゥンク」し、「ポワッ」となってしまう。ヤクザの事務所はそれらしく設えてあるし、「家族だけは……」という紋切りの命乞いも存在する。輪郭のパキリとした感情が他人や世間に与えられる分、「かれ」はそれを、フィクショナルだ、と感じる。どうして現実の方がそっちに向かうかな、と思ってしまう。結局、恋人である加賀に初めてプロポーズされた時も、あべくんは「へらーっ」と笑った。
めちゃくちゃ有機なもの(本書での他人)が徹底して無機質なおかしみとして扱われると、じつは怖い。使い古されて画質の荒くなったネットミームや誰かの笑顔、真顔、黒電話、液体、いきもの、国道の線、八〇年代のCMなど、数えきれない世界のあれこれを揃えて分断、切り貼りしたあのMADは、なんの主張も持っていなかった。それぞれの素材が持つ「キュン」も「トゥンク」も「ポワッ」も構成要素に過ぎず、表情はギターの音色で完全に殺されていた。しかし、大量にそれら絵文字みたいな殺害が重なると、新しい、何かしらのリアルがぬるり顔を出す。そんな後味が、二つの作品をそれぞれ、とてもおそろしくさせていた。
「ほんのこども」は人をころしているから怖いのではない。人がころされているから怖いのでもない。無論、虐殺の歴史そのものが怖いのでもない。本当に殺されているのは、その世界の方だからだ。死体となった様々な世界が、不思議に模様を作っているからだ。