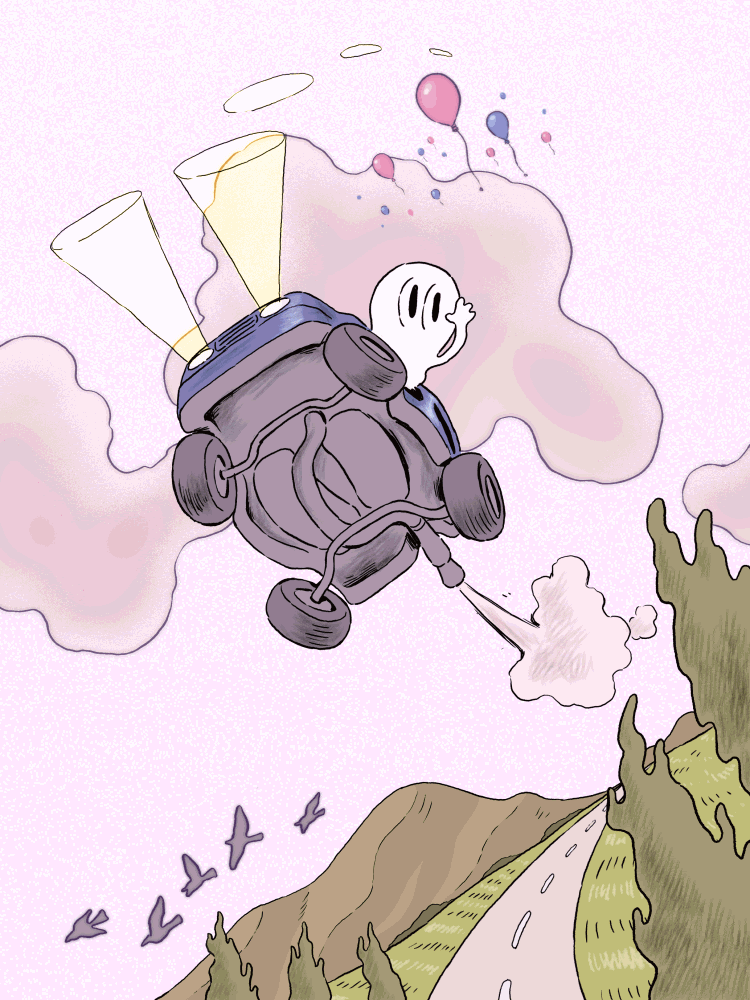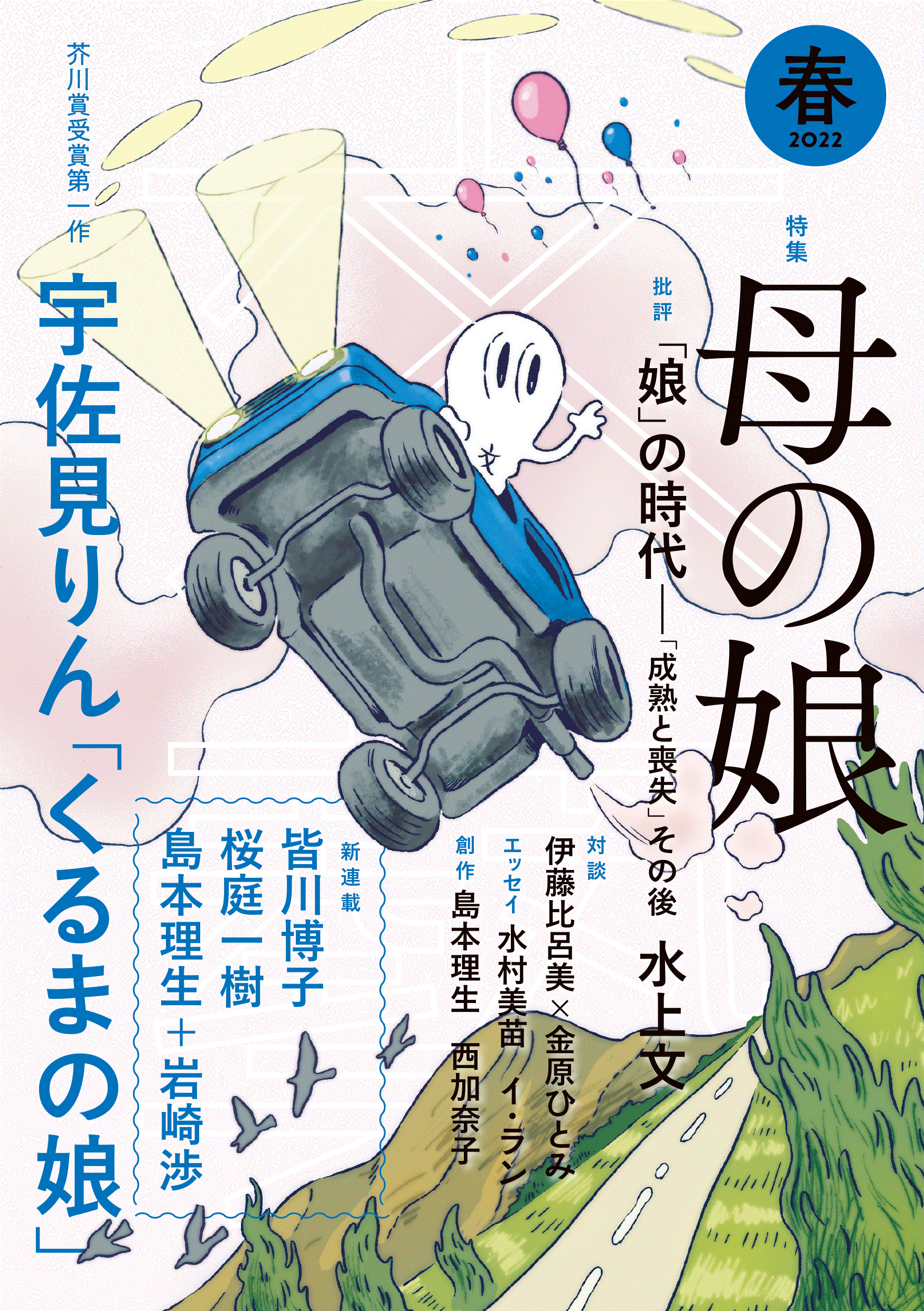
単行本 - 日本文学
作家・円城塔は、『その午後、巨匠たちは、』を読みながらこう考えた。
円城塔
2022.02.15
『草枕』を持ち出すまでもなく、絵画と小説の相性はよい。
どちらも何かを描くのである。片方は文字で、他方は色の広がりで何かをそこに、止まった形であらわすのだが、何が描かれているかについての議論は込み入る。
ごく素朴には、どちらも現実の何かを描くのであり、であるならば、そこには主客というものがある。ところがそこでたとえば、絵が絵を描く、小説が小説を描くということをはじめたならば、どちらがもとの主であったかわからなくなるという事態も生じる。何かを描いていたはずのものが、何ものをも描かないことを目指しはじめたりもする。そういうことを考えていく種類の活動は前衛と呼ばれたりもするのだが、主客ともに苦しめる結果に至ることが目立つ。
本作では、奇妙なねじれが語られている。時代や空間、主観の置き方などが激しく切りかわっていく。それは、とある神社に、モネや北斎、ダリといった絵画の「巨匠」たちが神様として集められるという筋運びから、注釈へと切り替わり、本文へと滑らかに復帰する小説全体の姿にまで及ぶ。まずねじれがあって筋ができたか、筋が必然的にねじれを呼んだか、同時にうまれたのであろうと思わせる自然さがここにはあって、地球という時空上の存在には人が馴染むといった種類の、起源をともにしたものたちの安定感とでも呼ぶべきものがある。
妙なつくりであるのは明らかなのに、あれあれと戸惑いながらも先へ先へと読み手を誘引していく工夫が凝らされており、新幹線の車窓から後ろへ消し飛んでいく景色を眺めているような気持ちともなる。その新幹線はいつのまにやら銀河を進む鉄道に変わっていたりするわけなのだが。
あるいは、布製のボールを手渡され、ふと気になって調べてみると、縫い目がさっぱり見当たらなかったといった種類の当惑にも似る。
「筋を読まなけりゃ何を読むんです。筋のほかに何か読むものがありますか」と『草枕』の登場人物は画家の主人公に向かって問うのだが、本作では筋が小説の姿へと直接接続していくわけで、筋を追いかけていたはずなのにいつの間にやら画を眺めていたということが平気に起こり、さらにはそこに集められているのが画家たちであるときては、愉快としかなりようがない。
と、内容にはほとんど触れないままにこの評は終わろうとしているのだが、だってやっぱりこの文章を追う楽しさは直接手にとって欲しいものであるのだし、筋を説明しなけりゃ何を説明すればよいのかというと、絵を前に筋を求める者はいないのであり、その構築や手つきをを紹介するので構わぬはずで、ここにあるのはさて見事な立ち姿に疑いない。そんなことは一目見ればわかるではないかと言われたならば、そのとおり。