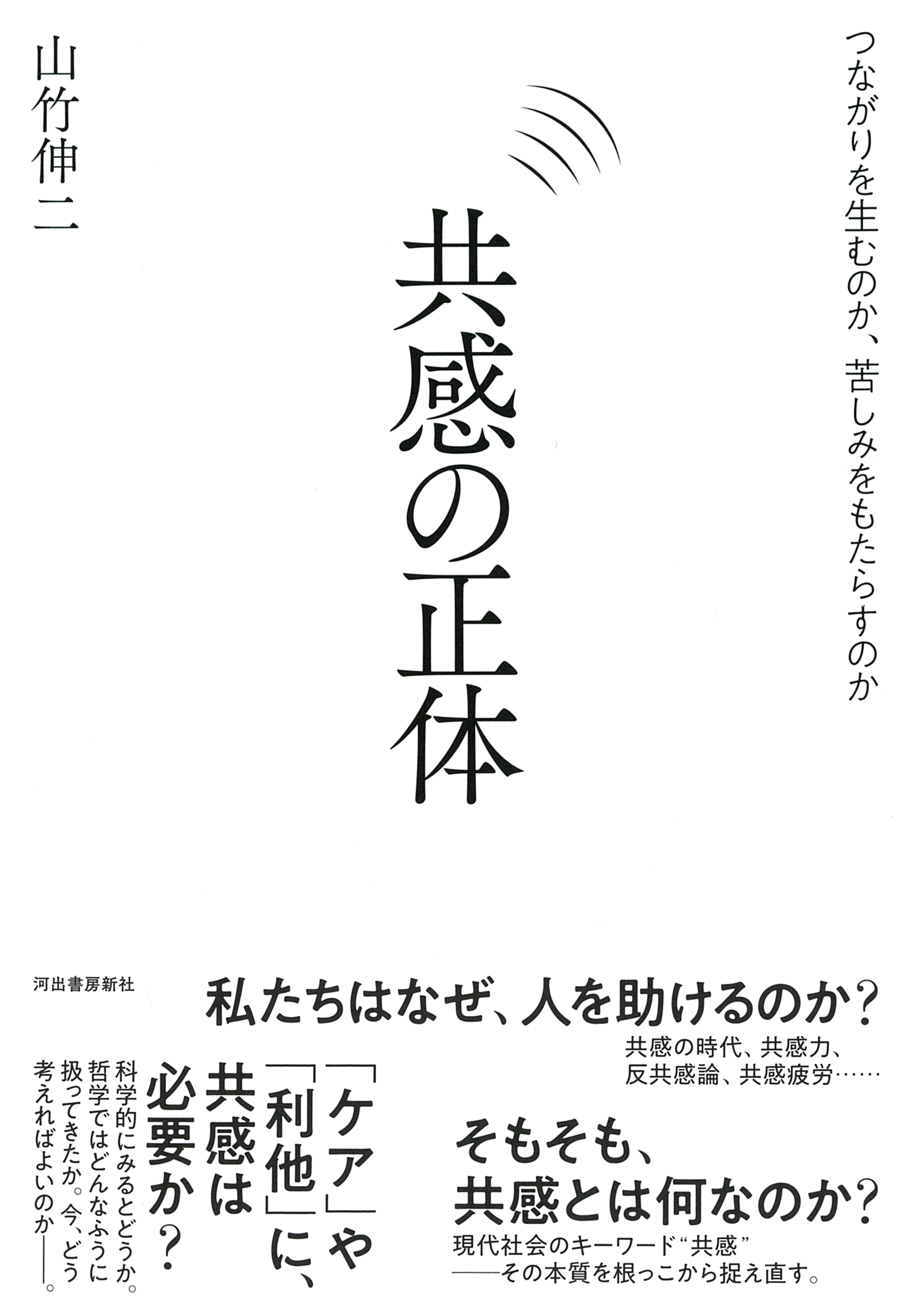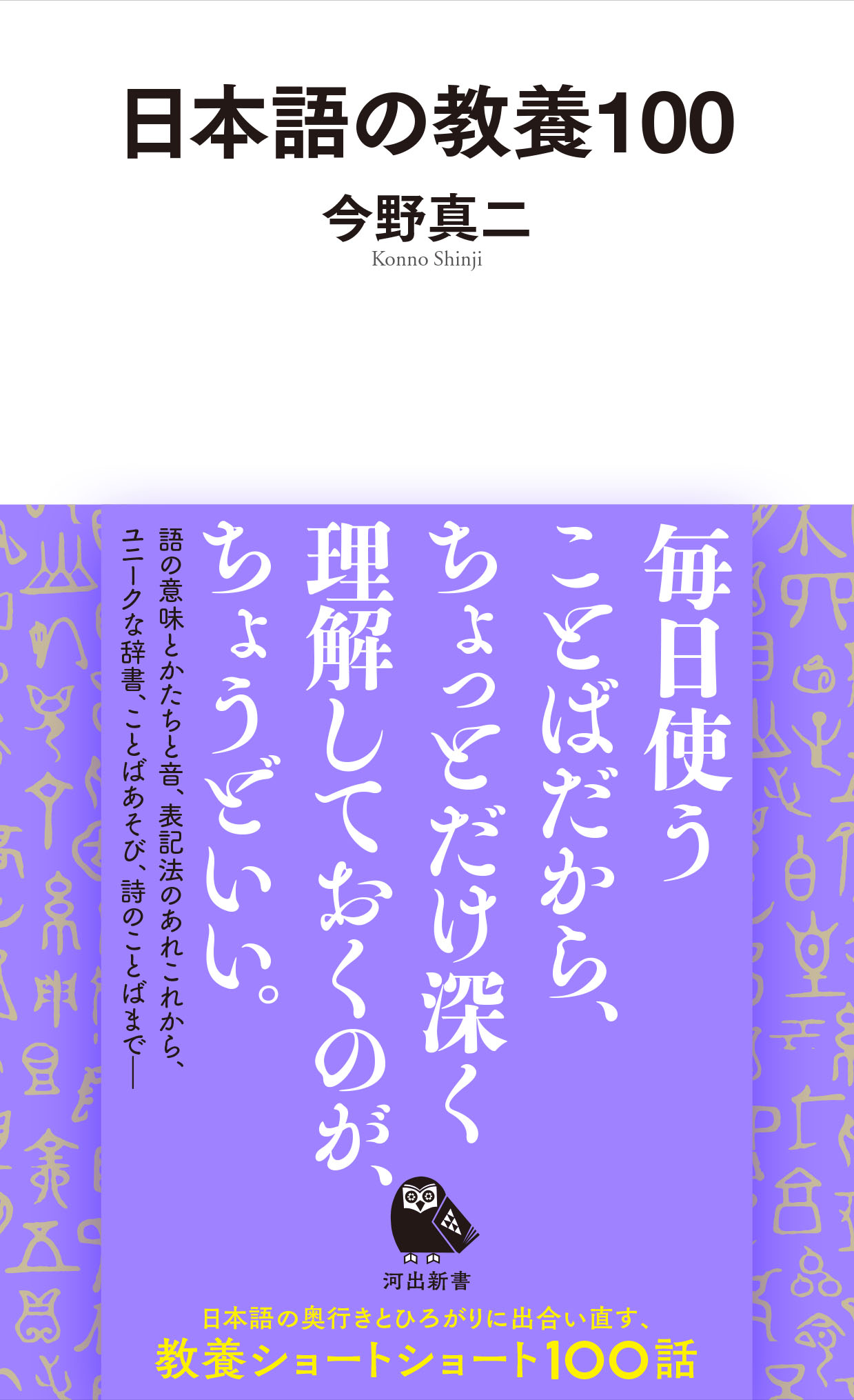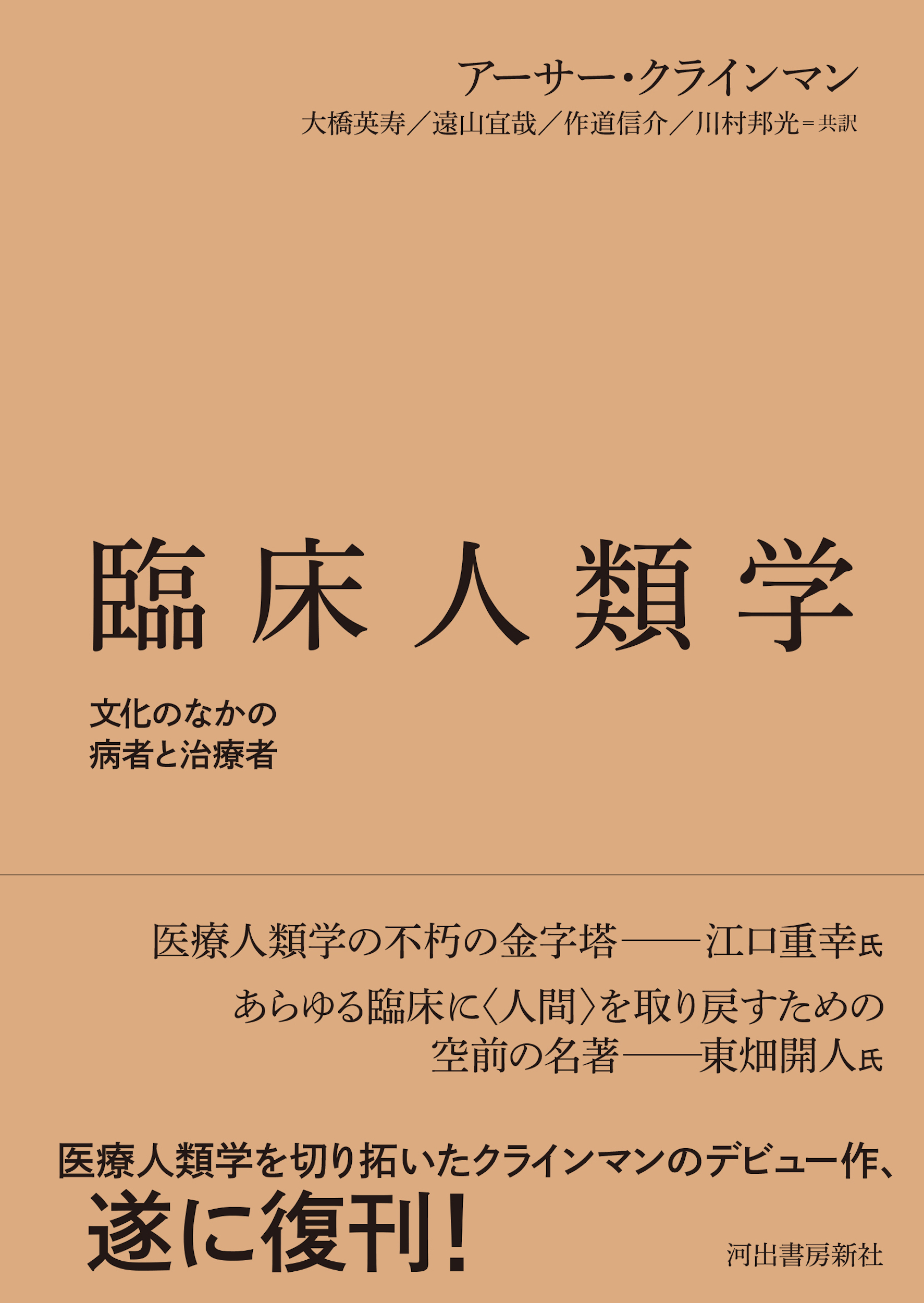単行本 - 人文書
【真山仁 特別寄稿】奇跡は、しなやかな現場主義から生まれた──泉賢一『ミャンマー金融道 ゼロから「信用」をつくった日本人銀行員の3105日』書評
真山仁
2022.03.29
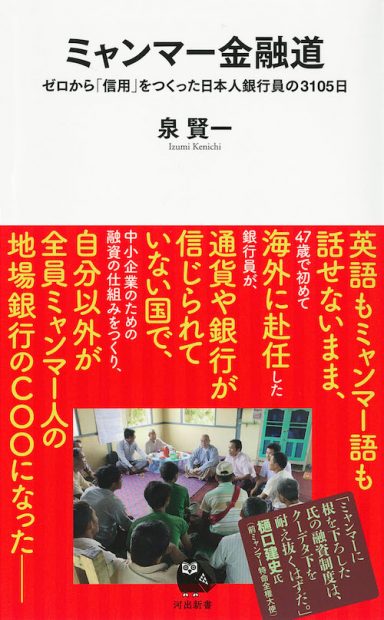
2016年3月、ミャンマーを訪ねた。拙著『プリンス』の取材のためだ。同作は、東南アジアの軍事政権国家で、初めて大統領選挙が行われた中で、日本で政治運動を行ってきた大学生が、騒乱に巻き込まれるという物語だ。
小説の舞台は架空の国家だが、軍事政権から民政化へと舵を切ったミャンマーの状況が参考になると考え、取材を敢行した。
滞在期間は6日間だった。
海外取材の前にはいつも、日本にいる関係者と会い、話を聞くようにしている。現地取材のアドバイスや取材対象者の紹介を得るためだ。
当時、取材候補者の中に、泉賢一氏の名もあった。
しかし、仲介者が泉氏に連絡できなかったのと、私の主眼が経済より政治だったこともあって、会えずじまい。
そんな「すれ違い」だった人物の著書を紹介する機会が巡ってきた時には、奇縁を感じた。
さらに、本書の「はじめに」の中で、泉氏が拙著『ハゲタカ』シリーズの映画化作品を観て、一念発起されたエピソードが記されているのを見つけ、その縁の深さを実感した。
さて、ミャンマーである。
私が今、ミャンマーと聞いてすぐに思い出すのは、「体力を消耗させる痛烈な蒸し暑さ」だ。
元来、暑さに弱いわけではない。夏バテとは無縁だし、2009年に取材で訪れた、アフリカの赤道直下の国、ニジェールでは、その暑さを楽しんだ記憶がある。おそらく気温は、ミャンマーより高かったはずだ。
にもかかわらず、ミャンマーの暑さは、体にこたえた。その原因は強烈な湿度だった。暴力的とも言えるほどの蒸し暑さ。それが、体力を奪っていった。
その気候とは反対に、ミャンマーの人たちは、誰もが誠実で穏やかだった。
蒸し暑さで参っている私に、ヤンゴンの街で会う人は皆、温和な微笑みを返してくる。彼らの笑顔は今でも、脳裏に鮮明に甦る。
そうした穏やかで、のんびりしているお国柄は、旅行者には馴染むが、政治の話をしたり、経済活動をするのは難しさがあるという印象も抱いた。
本書を読んで、その認識を新たにした。
著者の泉氏は、銀行マンとして、単身ミャンマーに残り込む。ミャンマーどころか、東南アジアでの勤務歴は皆無なのにだ。しかも、彼に課されたミッションは、自行のビジネス拡大ではなく、「ミャンマーのために汗をかく」ことだった。
よくこんな無茶な命令を受けたものだ、と感心した。おそらく、それを前向きに引き受けられたからこそ、泉氏はミャンマーで大活躍できたのだろう。そう考えると、彼を指名した上司の洞察力は驚嘆に値する。
「朝令暮改で、何も決まらない」という愚痴を、東南アジアでビジネスをしている人から、頻繁に聞く。だが、ミャンマーの場合、少し事情が違う気がする。
彼らは、てきぱきとルールを決めるのを良しとせず、成り行き任せでもいいから穏やかに流していく方が居心地がよいととらえているのを、私自身が取材を通して感じたからだ。だったら、こちらが引っ張っていけばよいので、仕事がやりやすいのでは、と考える人もいるかもしれない。
いや、整然とした社会に慣れている我々日本人にとって、そういう気質の人と仕事するのは、想像以上に骨が折れるのだ。
本書を読み進めば、まさにそのミャンマー人気質に泉氏は何度も苦しめられている。
しかも、長い年月、厳しい軍事政権下にあったため、通常の経済活動が行える基盤すら存在していなかった。
金融が成り立つには、金融機関の信用創造が前提となる。自分の虎の子のお金を預けても安心だと銀行が信用を得ていて、さらに銀行が、しっかりとした返済能力があると融資先を信じられる環境のことだ。
だが、ミャンマーでは、信用創造が不安定なため、金融が十分に機能しておらず、先進国では当たり前の経済活動ができない。つまり、国民は銀行を信用していないから、預金なんてほとんどしないし、銀行も預金者や融資先を信用していない。その上、最低限の金融ルールを規定する法律もない――。
このないない尽くしの中で泉氏は、国民の命や国家の存亡に関わる、金融ビジネスの基盤を創るというフロンティア役を務めたのだ。
幾多の苦難がありながら、泉氏はなぜ、成果を上げられたのか――。
それが、本書を読む一番の原動力となった。
日本人は、「壁にぶち当たった時に、その人の真価が試される」という言葉が好きだ。つまり、崖っぷちに追い詰められたら底力が出せると考える人が多い。
泉氏もきっとそうだろう。だが、それ以上に、泉氏の個性こそが成功の要因だと思わせる点もある。
その一つは、何事も直接人に会って、相手の思いを聞き、彼も伝える――という現場主義だ。
しかも、いわゆる押しの強い営業マンタイプではなく、まずは輪に溶け込み、信用を得た上で、相手のためになるビジネスを提案することが自然にできる。
郷に入っては郷に従えと言われるように、異文化を持つ双方が信頼関係を築くには、時間が掛かってもこれが最適の方法だ。しかし、言うは易しで、現実には一筋縄ではいかない。
本書の中で、泉氏は「簡単に諦めるわけにはいかない」と何度か書いている。その粘り強さと意志の強さも、大きな武器となったろう。
そして、その地道な活動の中で、泉氏は途上国に於ける支援の要諦を見つける。
それは、「指摘や批判ではなく、一緒に解決でき人を望んでいる」点だ。
ODAをはじめとして、日本は世界中の途上国に様々な支援を提供している。
その中には、理想的なご託宣を並べ、ダメ出しをするだけで、何の責任も取らないコンサルタントや、カネは出してハコモノや道路はつくるが、あとは知らないというような例が、山ほどある。
だが、泉氏は支援先の問題を解決し、一緒に悔しがる人を目指したのだ。
さらに、もう一点、日本(自社)のルールが通用しない時の対処法についても、格闘の中で気づく。
「前例がないのなら、自分でつくる」という柔軟かつ大胆な行動力の賜だ。
現場力の重要性を説くビジネス指南書も多いが、ほとんどは現場に足を運べばそれで足る程度のことしか記されていない。
実際に現場で重要なのは、状況を的確に把握した上で、最適化を創り上げる力なのだ。
知識もモラルもない状況下で、あるべき論をいくら唱えたところで、通用しない。彼らが理解できる範疇で、信頼関係を結び、自らの提案を受け容れてもらわなくてはいけない。そこで発揮されるのが、本当の現場力なのだ。
泉氏は、押しが強いわけでも雄弁でもない。ひたすら愚直に相手の話を聞き、彼らの立場にたって最良の選択を一緒に見つけるという姿勢を貫く。
そうした試行錯誤の中で、成果に至るプロセスは、すべてのビジネスマンにとって貴重なサジェスチョンとなるだろう。
それにしても、泉氏は我慢強い。周囲からも、もっと楽に仕事をすればと言われても、「これが私のポリシー」と言って、スタンスを変えない。だからこそ、彼は政府の要人から地方の人にまで信頼を得られたのだろう。
言葉より、行動こそが、信頼を獲得するために重要であるという行動哲学が、彼の心の拠り所だった。
当初は、銀行マンとして課されたミッションの達成を目指すに過ぎなかった泉氏は、やがて自身の使命を実感するに至る。
全身全霊をかけて、ミャンマーの人たちが、支援漬けの状況から脱出し、自立することをサポートしていく。
その強い思いが、大言壮語には響かない。
地に足のついた説得力を、本書は感じさせてくれるのだ。
だが、彼とミャンマーにとって二つの「不幸」が襲う。新型コロナウイルスの大感染とクーデターだ。
果たして泉氏の夢は実現できるのか。
その答えは、神のみぞ知るかもしれないが、本書を読めば、すでに答えは出ている。
【まやま・じん=小説家】