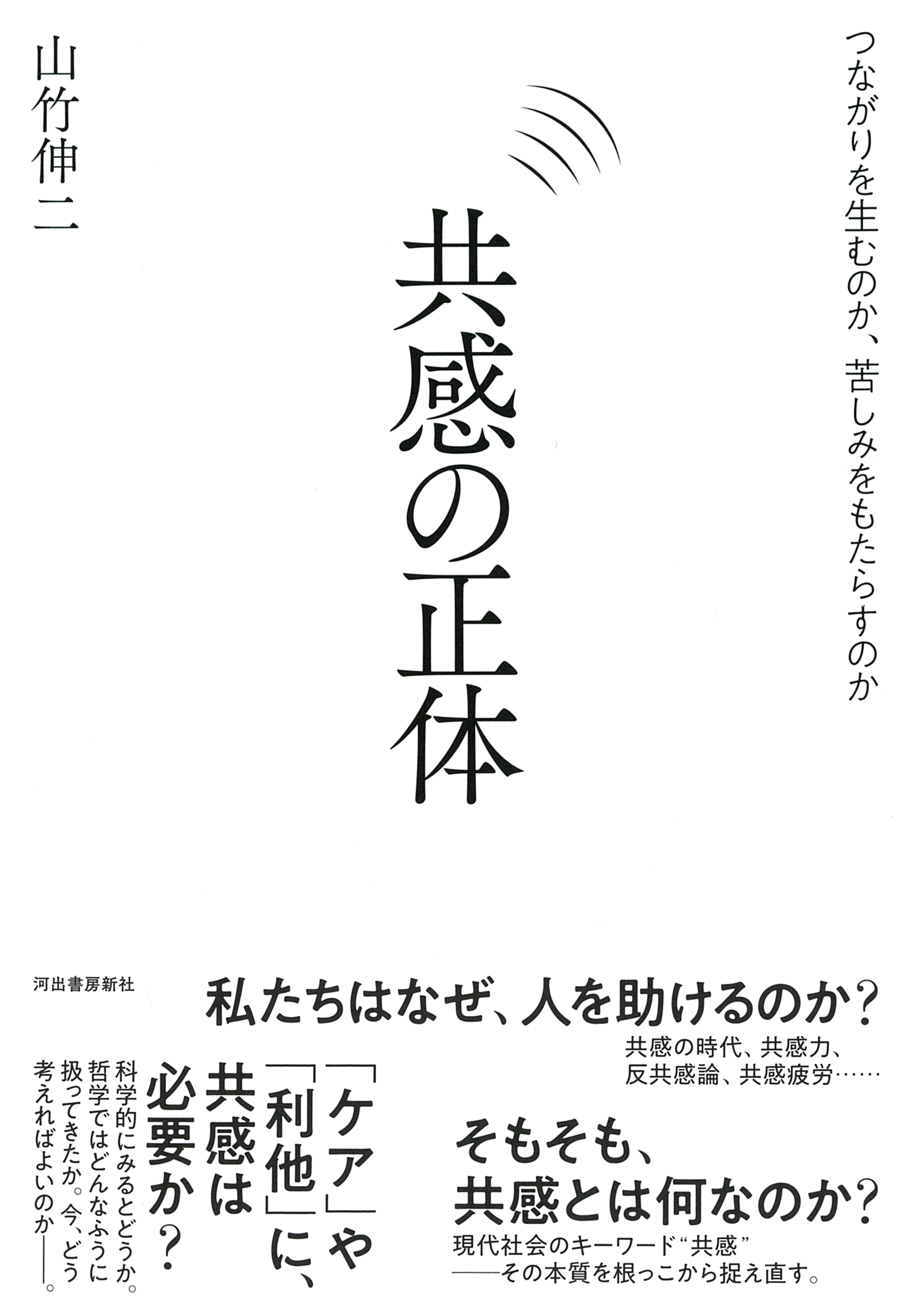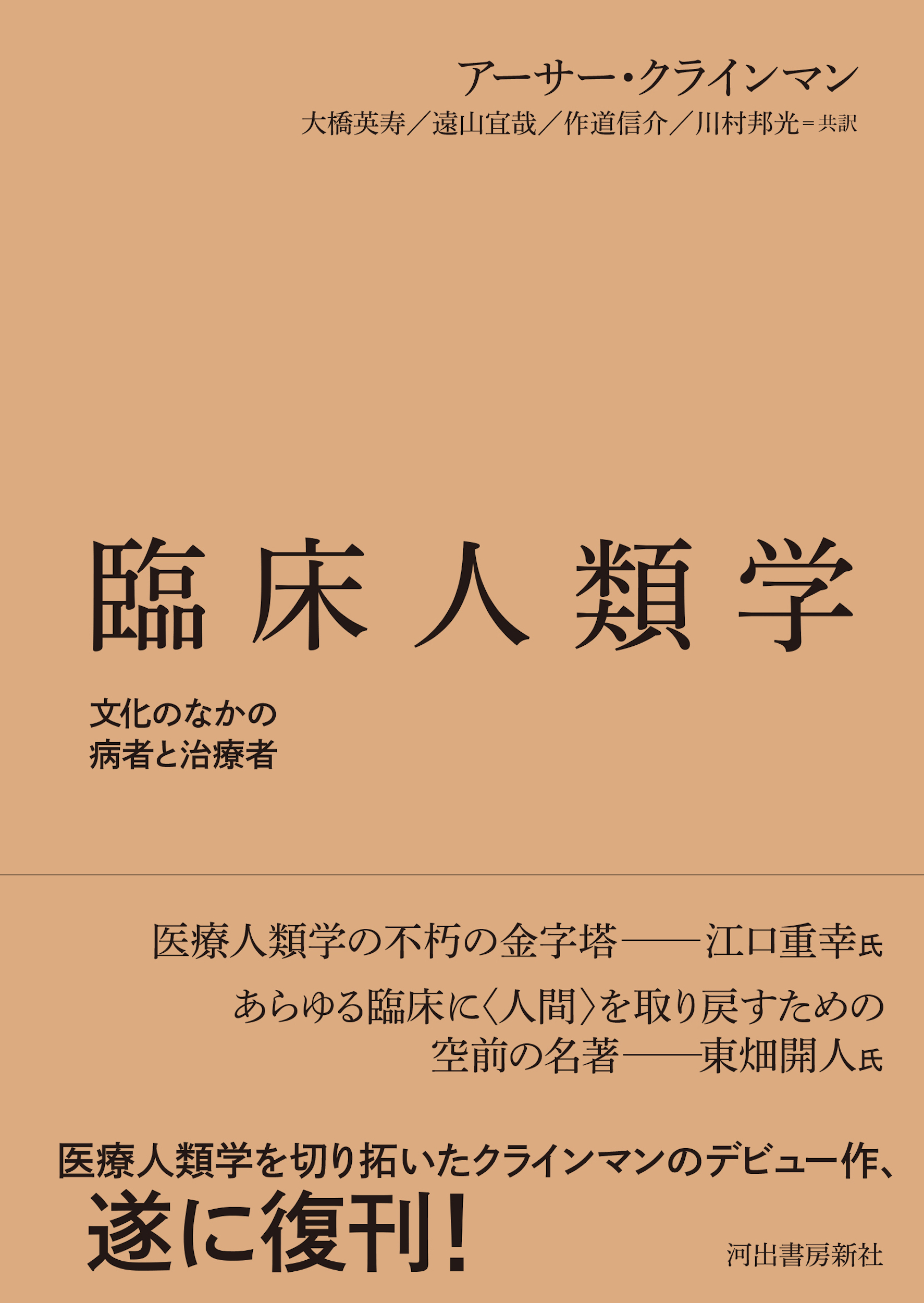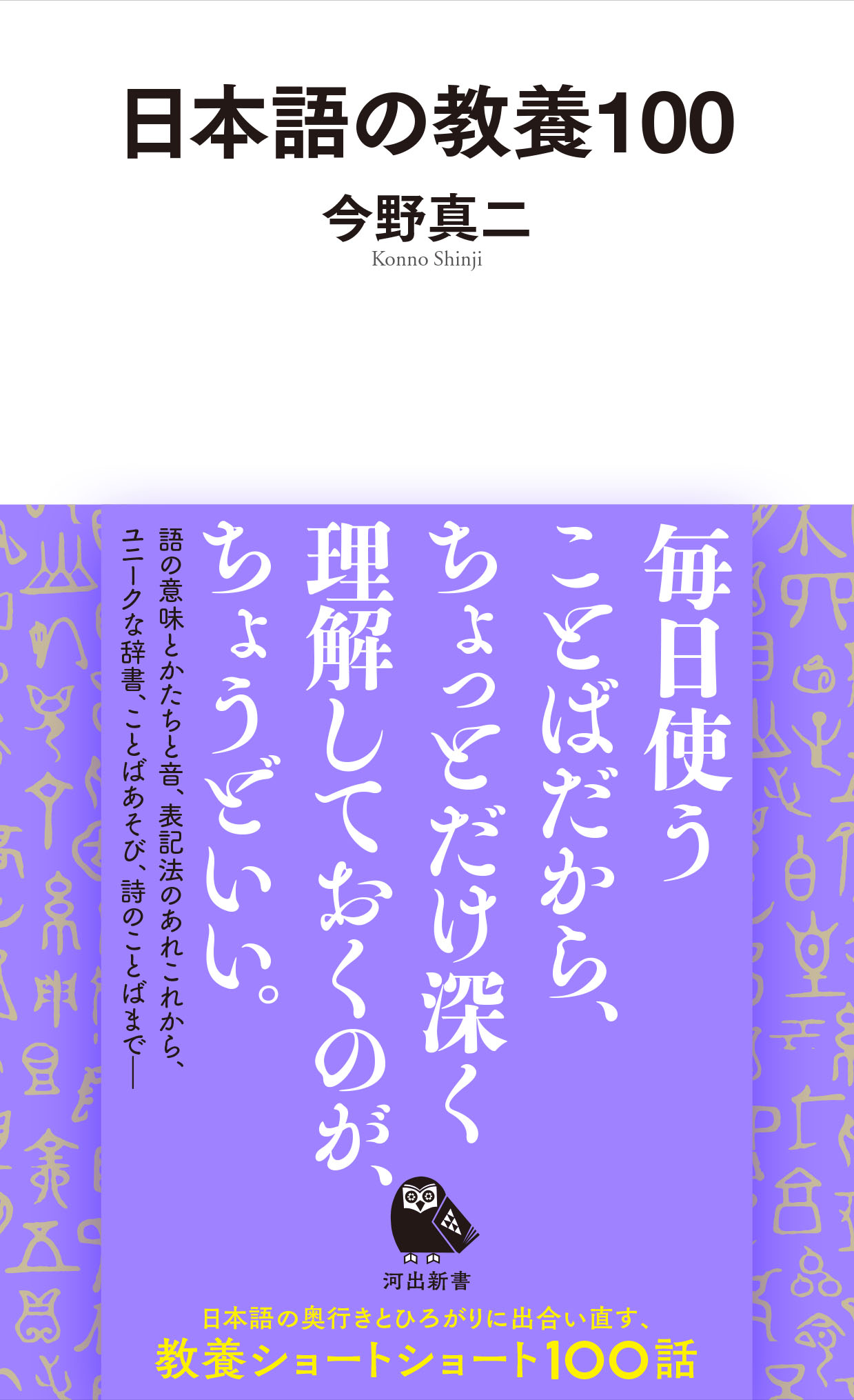
単行本 - 人文書
今野真二『日本語の教養100』(河出新書)刊行記念 往復書簡 「知識の沼――ことばで巨人の肩にのる」第7回 山本貴光→今野真二
山本貴光
2021.09.03
10年以上にわたって多彩な視点から日本語をめぐる著作を発表しつづけてきた今野真二さん。その日本語学のエッセンスを凝縮した一冊とも言える『日本語の教養100』が刊行されました。これを機に、今野日本語学の「年季の入った読者」と自任する山本貴光さんとの往復書簡が実現。日本語についてのみならず、世界をとらえるための知識とことば全般に話題が広がりそうな、ディープかつスリリングな対話をご堪能ください。
第1回はこちら。
第2回はこちら。
第3回はこちら。
第4回はこちら。
第5回はこちら。
第6回はこちら。
* * * * *
今野真二さま
この書簡も3往復をしてみたところで、少しずつリズムというのでしょうか、ことばの行き交う感じ、ペースのようなものが染みこんできたような気がしています。「染みこんで」というのも変なものですけれど、その前に「分かってきたような気がしています」と書いてみて違和を感じたのでした。頭で理解したというよりは、体の感覚に近いと思ってことばを選び直した次第です。
それにしても書簡を流れる時間は、忙しない現代においてますます貴重なゆるやかさを湛えたものだなあと思うことしきりです。一通ごとにそれなりの分量があって(といっても書いていると、これでも短いように感じるのですが)、話すそばから空中に消えてゆく会話とも違い、自分のペースで行きつ戻りつしたり、あるいは何度でも読み返したりすることもできます。いただいた書簡を読むつど頭のなかのあちらこちらが刺激され、思い浮かぶことをまたお伝えしたくなるにつけても書くことがどんどん増えていきます。
また、そのようにして一通を書き、あるいは頂戴して読むたび、それまでの書簡の積み重ねから文脈もさまざまに生じますね。互いのことばが、意識している場合はもちろんのこと、意識しない場合も含めてハイパーリンクのように連環を生み出してゆきます。あっちの話がこっちにつながった、そういえばこんなことも、と連想が連想を呼ぶ楽しさと申しましょうか。
このようなことばの織物のあり方は、往復書簡という形式ならではなかなかあり得ないようにも感じているところです。とは、言えば当たり前のようなことを長々と述べてしまいましたが、ここでのことばや知の交わし方の面白さを噛みしめているのでした。
この点についてはこの往復書簡が最後まで終わったところで、すべての回をそのつもりで見直してみようと思います。どこでどんな「カード」が出されたのか、そこからどんな話題が連想され、また別の「カード」が出されたのか。それをマッピングしてみると、私たちのあいだで交わされていることばが、どこへ注意を向けようとしているのか、なにが論じられたのかということも連載中とは別の視点で見えてくるような気がしています。
*
などということを考えたのは、最近手にした本のせいかもしれません。先日立ち寄った紀伊國屋書店の洋書部で『手紙の共和国――アンソロジー(République des Lettres: Une Anthologie)』(Les Belles Lettres, 2021)という本に出会いました。いま仮に『手紙の共和国』と訳しましたが「文芸の共和国」「学問の共和国」とも訳されます。ここでは往復書簡という文脈でもあるので「手紙の共和国」としてみましょう。
これはルネッサンス期のヨーロッパで生まれ、18世紀の啓蒙期にかけて存在した共同体の一種でした(途中からはアメリカにもつながっています)。政治や宗教においては多数の国や立場に分裂したり対立したりしていた状況にあるものの、学者や文学者たちがそうした違いを超えて、学問や文芸という共通関心のために協力しあう場というわけです。実際にどこまでそうだったかは別として、理念としてはお互いに平等であり、あらゆる問題を自由に検討できるのがこの「手紙の共和国」でした。そこでの有力な手段はことばです。とりわけ遠方にいる者同士がやりとりする場面では、手紙であり雑誌であり書物だったのですね。
「手紙の共和国」は、彼らの共通語だったラテン語で「レースプーブリカ・リテラーリア(Respublica literaria)」といい、仏語ではRépublique des Lettres、英語ではRepublic of Lettersなどと記されます。つまりliteraria / lettres / lettersをなんと訳すかによって先ほど書いたような日本語として表記に違いも出るわけです。litteraは「文字」のことであり、それによって記される「手紙」や「文章」のことであり、そこで表現・伝達される「知識」や「学問」あるいは「文芸」のことでもありました。
私は、学術の歴史のなかでもインターネット以前の世界で人びとがどんなふうに学術に関わる交流をしていたのかに興味があって、以前から気になっているテーマなのです。管見では日本語でこれを主題とした本はまだ少なく、ハンス・ボーツ&フランソワ・ヴァケ『学問の共和国』(池端次郎+田村滋男訳、知泉書館、2015〔原書は1997〕)という本はまとまって読める数少ないものの一つです
ここでちょっと余計なことを言えば、インターネットが一般に普及しはじめた1990年代半ば頃、これからはインターネットによって人びとが互いに直に話しあえる真の民主主義が実現されるといった夢と希望が語られるのをしばしば目にしたのを覚えています。古代ギリシアのポリスにおける直接民主制のような状態が思い浮かべられてもいたのでしょう。
実際はどうなったかといえば、目下私たちが目にしている通りで、ネットのおかげでそんなことでもなければ交わることもなかった人びとが交流できるようになった一方、同時にネットがなければ生じなかったはずの摩擦や争いも毎日のように山ほど起きています。「万人の万人に対する闘争」(©ホッブズ)の野蛮状態などと言ったら言い過ぎですが、小林弘人さんと柳瀬博一さんの共著の書名をお借りして「インターネットが普及したら、ぼくたちが原始人に戻っちゃったわけ」という気分があるのも事実です。
なにを言いたいかというと、「手紙の共和国」のような状態をつくったり維持したりするにも、もちろんなにかしらの条件が必要なのだ、ということでした。では、現在の技術や社会の環境を前提に改めてある種、理想的な知の共和国のようなものがありうるとしたら、それはどのようなものだろうと夢想することがあります。大学をはじめとする各種の研究機関や学会などは、「手紙の共和国」の延長線上で制度化され、それなりに機能してきたしくみではあります。ただ、いつの頃からかもっぱら論文生産数を指標とする競争の場にもなっていて、目的と手段が転倒しているように見えなくもありません。論文という「成果」の捏造事件が後を絶たないのはその象徴です。未知の探究ではなく、影響力の大きいと評価される学術誌への投稿実績が目標になった結果でもありますね。それは学術、知の探求という営みがもともと持っているはずの性質にそぐわない状態であると思います。
こうした現状を見直したり、未来を構想したりする上でも、過去の事例をあれこれ見てみるのは悪くないだろうと思うのです。「手紙の共和国」は16から18世紀のヨーロッパの事例ですが、そのつもりで見てゆくと、時代や場所によって似たような、あるいは別のかたちでの工夫や活動がなされていたはずです。日本のケースも含めて少し時間をかけて検討してみたいなと思っています。
*
さて、先ほど触れた本『手紙の共和国』に戻ります。同書は、そうした「手紙の共和国」について当時の(とは16から18世紀の)人びとが書いたものから、関連するテキストや交わされていた書簡を集め編んだアンソロジーです。
この本に序文を寄せているマルク・フュマロリ(1932-2020)は、コレージュ・ド・フランスで長く教鞭を執っていた文学や美術の歴史の研究者で、彼自身にも同名の本があります。今回私が手にしたアンソロジーのほうの『手紙の共和国』は、このフュマロリ氏が生前構想しながら実現せぬまま2020年に亡くなったことを受けて、3人の友人たちが編んだ本のようでした。本書自体が、いってみれば「手紙(学問)の共和国」の成果でもあるのですね。
こうした本を読んでいると、知識や疑問や発想というものは一人でぽんと思い浮かぶものではなく、誰か同好の士とのやりとりも大事なのだ、ということがいまさらながら痛感されます。以前触れた「巨人の肩に乗る」という話は、いずれかといえば過去の先人たちの仕事(知識や発想)を学んでさらにその先を見るということでした。それに対して書簡のネットワークでは、同じ時代の空気を吸っている人たちとことばを通じてアイデアや疑問や知識をやりとりしたり、同意を得たり疑問を提示しあったりするうちに、自分だけでは思いつかないなにかが脳裡に浮かんでくる状態ですね。そう考えると、私たちは主にことばを媒介として死者と生者とともにものを考えているとも言えそうです。いずれも共同作業ですね。
これは現在の制度化された学問の世界でも活用されているしくみです。ある研究テーマにかんする学会にいわば同好の士が集まって議論や論文を通じて意見や考えを交換しあうなかで研究を進めていくというやり方は、分野を問わず共通している知の技法かもしれません。
そういえば、今野さんが触れてくださった『現代思想』2021年7月号(青土社)の「和算の世界」特集号でも、江戸期の日本における和算が、同好の士の集まりとそのやりとりを通じて営まれていた様子に注意を向けて一文を草してみたのでした。私は物事を一種のエコロジー、そこに関わる要素とそれら要素同士のあいだにある関係の全体として考えてみたくなります。それで「算術者のつくり方」という文章でも、もし江戸の町とそこで活動する人たちの生活をシミュレーションするとしたら、そこにいる算術者(和算家、数学者)は朝起きてから寝るまでなにをしてるだろう、と考えてみました。それにしても、そこで触れた『廣益諸家人名録』の実物を今野さんが入手されるとは、想像もしませんでした!
*
ところで先ほど、本と「出会いました」と書きました。そうとしか言いようのない出来事だと感じます。というのも、その書棚の前にいくまで、そんな本があることを知らず、しかし目にした途端に「あ!」と手にとって、「これこれ!」と読みたくなるわけです。これは何度経験しても面白いことで、これぞ書店の楽しみと申しましょうか。
もう少し具体的に書いてみます。先ほどの『手紙の共和国』を例にすれば、こんな具合でした。紀伊國屋書店の洋書部を訪れる場合、フロアを巡る順路もだいたい決まっているのですが、そこから書くと同書に辿り着く前に数千文字を要しそうなので省略します。フランス語の棚の前からにしましょう。大きく人文書と文芸が並んでいるうちの、哲学などの人文書がある棚を見ます。バディウ(Badiou)、バルト(Barthes)、ベルクソン(Bergson)、デリダ(Derrida)やドゥルーズ(Deleuze)、フーコー(Focault)と著者名のアルファベット順を基本とした配置の前後に、それとは別の分類の本があって、そこにRépublique des Lettresと大きく記した表紙が見えます。「おお、文芸の共和国だ!」と、ちょっと大袈裟に言えば電気が走ったような状態で考えるより前に本を手にする。表紙をよく見ると「アンソロジー」とあって、当時の人たちが書簡を通じて交流していた書簡やらを選んで編んであるのではなかろうかという期待が浮かぶ。ページを後ろのほうから繰ります。フランス語の本は、目次が後ろのほうにあるからというのと、索引があれば見てみたいからでした。細々と記された目次から、ペトラルカ、エラスムス、ピエール・ベール、スピノザとオルデンバーグなど、知っている名前が目に飛び込んできます。わあ、これは間違いない、と今度は本の頭に戻って改めて最初からページを繰る。書簡だけでなく「手紙の共和国」に触れたテキストの抜粋に、概説と出典が示されています。これだこれ、こういうのを読みたかったのですよ! ありがとう、これを仕入れてここに置いてくださった人! と勝手に興奮して小脇に抱えます。そしてその近辺に類書がないだろうかとまた眺めるのでした。
ちょっと描写が長くなりましたが、本と出合うとき何が起きているのかを書いてみると、概ねこんなことが生じているわけです。要約すればこうなりましょうか。
・書店員さんが選書して、ある棚にその本を配置する。
・ある日山本がその書棚の前に立つ。
・その瞬間までそういう本があることを知らなかったにもかかわらず「これだ!」となる。
・本を検討して「読みたい」と感じる。
これが先ほど本と「出会う」と述べたことの内実です。
いま書いた要約に足りないことが一つあります。それは「関心」です。以前から「手紙の共和国」「文芸の共和国」が気になっていたためにその本があちらから意識に飛び込んできたように感じるわけです。つまり、そこに並ぶ全ての本が同じようにではなく、そのつどデコボコして見えます。よく目につくものもあれば、背後に退いて見えるものもある。書棚とそのときの私の関心との組み合わせから「これだ!」が生じるのですね。同じ書棚でも、別の日に訪れたら以前は目にしていたのに気にならなかった本が「これだ!」となるかもしれない。と、文字で書いてみれば、なんだか至極当たり前のことのようでもありますが、この「これだ!」の面白さにはなにかあるように思うのです。また、書店という場所は「これだ!」が生じやすい空間でもあるように感じています。
なぜこんな話をしているのかというと、この往復書簡でテーマにしている知識やそれを入れる器としての本について考えるとき、あるいは前便で触れた記憶のことを考えるとき、本屋の空間やそれに限らない書棚という物理環境は存外重要な気がしていて、そのことを今野さんにも伺ってみたいと思ったからなのでした。こういう話題は、本を集めたり読んだりすることが日常になっている人にとっては茶飯事で、それだけにわざわざ説明したりする機会も少ないかと思うのですが、他のみなさんはどうしているのだろうということがやはり気になります。
*
さて、今回は今野さんからいただいた前便を拝読してから、いろいろなことが思い浮かぶのをいったん脇に置いてみて、改めて往復書簡についていま思うことをまずは述べてみました。書簡を拝読すると、そこで触れておられることの一つひとつに接して思い浮かぶことに順次応答したくなります。それももちろん楽しく意味のあることなのですが、せっかくの機会でもあるからと、ちょっと違う書き方もしてみようと試してみたわけでした。といっても、ここまで書いてきたこともまた、今野さんとのこの一連の書簡のやりとりがなければ、このようなかたちで考えたり書いたりすることのなかったはずの文章だと思います。
以下では、今野さんが書いてくださったことに重ねてもう少しお話ししてみます。
「閉じたテキスト」と「閉じていないテキスト」の区別、つまり印刷された本のように固定されて変化しないものと、ネットで公開されているデジタルテキストのようにいつでも変化しうるものとの違いは、利用する私たちの認知のあり方ともおおいに関係がありますね。コンピュータのソフトウェア(アプリ)なども、現在では時々刻々とアップデートされるのが当たり前になっていて、場合によっては利用者が気づかないうちに変化が起きていたりもします。あるいは変化したことに気づいても、それ以前がどうだったのかを忘れてしまうので、やがて分からなくなったりもしますね。
こうした状況は便利といえば便利なのですが、開発者によって「勝手」に行われる改善のアップデートは、ときとして利用者にとっては改悪であることもあります。つい最近では、私もよく使っているTwitterのボタンの色が従来の設定から替えられるということがありました。その結果、しばらくのあいだ操作ミスを繰り返すことになったのは、従来馴染んでいたルールが勝手に変更された結果でもあります。ソフトウェア開発では、以前と違う状態にするのが改善だと考えられている節もあって、こうした変更が日常茶飯事になっています。でも、つきあわされるほうはなかなかたまったものではありません。私などは、お金を払ってでもよいので、自分が使い勝手がよいと感じているヴァージョンに固定したり、余計だと感じる機能をオフにさせて欲しいと思ったりもします。
同じことがゲームソフト(アプリ)にも言えます。日々自動的にアップデートされるので、いつのどのヴァージョンかによっては、同じタイトルのゲームでも中身が変わっていることがあります。すると、ゲームの構造やつくり方を教える講義などで、あるゲームを例にとりあげると、学生が知っているヴァージョンと違っているために、話が食い違うということも生じます。そうかといって「ここに提示したのは、何月何日のヴァージョン1.320015bです」と言われても、それが一体どういう状態のものかは分からない。こうなると経験を比較することがこれまで以上に難しくなりそうです。結果的には今野さんが本やデジタルテキストについておっしゃっていた「「版」という概念も成り立たなくなります」というのと同じような状況が生じるわけでした。
もっとも各種のアプリの場合、そのときの最新版を使えればいいじゃない、という立場からすれば、これでなんの問題もないわけです。他方で、そうした対象を分析したり検討したりするような場合には、これはたいへん厄介な問題にもなりますね。現在の技術環境や各種メディア上で起きていることを扱う未来の歴史学者は大変そうです。そうでなくても厖大な種類のソフトウェアによって構成されるインターネットやパソコンやスマートフォンも、そのときどきで各ソフトのヴァージョンが違い、場合によってはその違いによって利用者が経験していることにも差が出たりするわけですから。
このように考えると今野さんが実演してみせてくださった『広辞苑』の版違いの比較は、ご指摘のように版ごとの著者の違いなどがあるとはいえ、それぞれの版ごとにいったんは固定されたテキストが存在するので、人間の身にも比較的扱いやすい状態なのだなと思われてきます。といっても、現物を目の前に揃えて比較・観察するという作業は、誰にでも上手にできることではないわけですけれど。
*
(仮称)「ABC殺人事件問題」もたいへん面白いですね。あるある! と膝を打ちながら拝読しました。時間の順序も含めて「ほんとうはつながりがないかもしれない対象であっても、そこにつながりを「みてしまう・感じてしまう」」という人間の性質については、認知科学の領域などでもさまざまな指摘をお見かけします(実験の再現性も含めてそれらの指摘がどこまで妥当なのかについては注意が必要とはいえ)。
私たちはバラバラに得た知覚や情報のあいだに因果関係を見たり、ストーリーをつくって捉えたりすることがあります。あります、というより自覚の有無にかかわらず日々行っていることと言ってもよいかもしれません。そもそも外界で生じている出来事のすべてを見聞きしたり経験できる人は1人もいない。加えて世界は時々刻々と変化しているし、自然にしても社会にしても個人の身に起きていることにしても、人間からすれば複雑過ぎて捉えきれるものではありません。にもかかわらず、誰もが限られた時間と外界からの限られた知覚をもとにそのつど「今日はこういう出来事があった」とか「いま世界はこうなっているようだ」とか「あの人はこんな人だ」といった認識をつくっているわけです。世界について丸ごと知ることはできない。でも、想像や推論によってそれなりに「こういうことだ」と因果関係やストーリーのかたちで理解しています。
最近、『知ってるつもり――無知の科学』(土方奈美訳、早川書房、2018〔原書2017〕)という本の文庫版に解説を書く機会がありました(この書簡が公開される頃には刊行されていると思います)。原題をそのまま訳せば『知識の錯覚――なぜ人は一人で考えられないのか』といいます。著者はスティーブン・スローマンとフィリップ・ファーンバックという認知科学者です。
私たちは、本当は知ってはいないことをなぜか知っていると思い込むことがある。そして場合によっては大失敗につながることがある。それはなぜか、どのようなしくみによるのか、ということを説いた本です。1人の人間の知っていることはたいしたものではない。でも、環境や他の人たちとの集団に蓄積された知識に依存して生きるうえで必要なことをまかなっている。ただ、そのことを人は自覚せず、また必ずしも正しくない推論によって、自分はものを知っていると錯覚して、ときにミスをする。まとめてしまうとそういう次第を教えてくれる本です。
今野さんが書いてくださった、ものごとが生じた順序と、それを観察した人が認識する順序のズレでも似たようなことが作用しているのだろうと思いました。例えば、私はしばしば語源を調べるのですが、ヨーロッパ諸語の場合、大きく見れば古代ギリシア語⇒ラテン語⇒ヨーロッパ諸語という順序が頭にあるため、ある言葉の形成もこの順で生じたと考えてしまいがちです。でも実際には必ずそうであるわけではなくて、これとは異なる順でことばが言語から言語へ移されることもあるわけです。ラテン語からギリシア語に、あるいは英語からラテン語にことばが借用されるというように。
同じようなことは、これもまたお話で触れてくださった『色葉字類抄』についてもありそうです。私などは和書の扱いに不慣れなために、写本の相互関係や来歴をよく弁えないまま読んでしまうことがあります。ご示唆いただいた「取り合わせ本」の事情や書名の漢字の当て方なども、よく見てとれずに意識できずにいることが多いようです。「同じ」本を見ても、そこになにを見てとり読み取ることができるかは、まことにその人が脳裡に蓄えてきた経験や知識次第であるということを痛感します。私が今野さんのご著書を読み始めてすぐに「この人の本は手に入るものを端から読まねば」と感じて実行に移してきたのは、そこにさまざまなかたちで示されている資料の扱い方、見る目を学びたいという動機もあったのではないかと、後知恵ながら思います。というのは、今回『廣益諸家人名録』を検分してゆく今野さんの視線と思考の動きの一端を見せていただいて、改めて舌を巻いたからでもありました。
もうひとつ、情報の連鎖(チェーン)をトレースするというお話についてもあれこれ考えてみたいのですが、長くなってきましたので次便で触れたいと思います。この書簡を終える前に申し添えれば、今野さんと私とは、広義の「メンター・チェーン」であるとは同感であり光栄です。私が今野さんのご著書を通じていわば私淑していたところに、ひょんなことから(とまとめてはいけませんが)交流が始まり、こんなふうに対話を楽しむ機会が巡ってこようとは考えたこともありませんでした。あくまでも私の貧しい経験に照らしてですけれど、こうした出会いは願ったからといって叶うものでもなく、むしろ稀有な出来事に属すると思います。それにしても、有間しのぶさんの『その女ジルバ』はいいですね。と、話は尽きませんがここで筆を擱きます。
2021.09.03
山本貴光