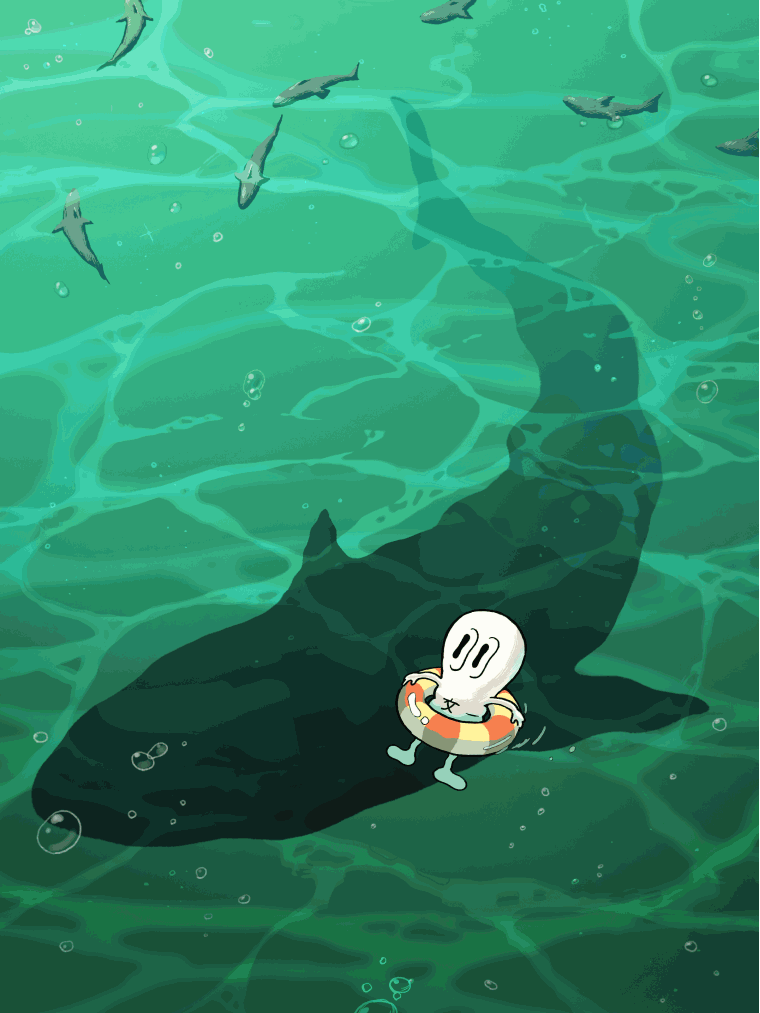単行本 - 日本文学
「文藝」夏季号掲載、でか美ちゃん「名前だけでも覚えてください」試し読み
でか美ちゃん
2022.04.07
私には特別な才能があるはずなのに、いつもいつも“普通”で、名前も普通、あだ名さえつけてもらえない。名前を巡る冒険を描く、著者初の小説。
===↓試し読みはこの↓へ===
名前だけでも覚えてください
でか美ちゃん
田中由美
今ここで立ち上がって、大きい声でも出したら、私、どうなっちゃうんだろう。
「えー、文武両道を掲げるからにはですね、我が校の為に、みんながやるべき事。わかるね?口を開けて待っているだけではいけません。能動的な行動を起こせば、受動的な─」
校長先生がもう7分以上は喋っている。よし。
「話長(なげ)ぇんだよバーカ!」
なんて言えたらどれだけよかっただろうか。そんな勇気私にはない。寒い。とにかく寒い。冬の体育館集合は地獄の合……
「話長ぇんだよバーカ!いっつも口開けてよだれ垂らしてんのはてめぇの方だろうが!」
……地獄の合図だ。
「な、お前、先生に向かってなんだその口のきき方は!」
「うるせぇお前のことジジイとしか思ったことねぇよ!」
妄想よりも口汚い言葉に唖然としていると、東雲(しの のめ)さんが先生に引きずられるようにして退場していった。
「ねぇ由美、東雲さんってさ、やっぱクスリとかやってんのかな?」
「流石(さすが)にそれはないでしょ」
「集会で大声出すってみんな一度は妄想したことあるじゃん。でもさ、本当に実行するのはヤバいって」
「……ねー」
みんな一度は妄想したことあるんだ。みんな?みんなそうなのかな。私だけの特別な妄想じゃなかったんだ。私だけがこんな変なこと考えてるんだと思ってた。実行には移せないよ。それでも、こんなとこで大声出したらどうなるかな?なんて、特別な私の、特別な思考回路じゃなかったんだ。
まただ。またド真ん中。平均点。普通。並。
そもそも田中由美って名前が普通すぎる。私の名前が注目を浴びたのはたまたま英語の教科書に出てきた例文が「Yumi Tanaka」だった時だけ。Yumi TanakaはTomに日本食として寿司を勧め、富士山の美しさを伝えていた。お前まで普通なのかよ。
それに対して東雲さん。いいなぁ東雲さんは。だって初めて見た時まず読めなかったもん。東雲さんは学校に内緒でバイトもしているらしい。東雲さんはそのバイト代でギターを買って、他校の人とバンドを組んだらしい。東雲さんが好きな音楽はヒットチャートには載らないし着うたも買えない。売ってないから。実は私もバンドとか好きなんだ!って、卒業までには話しかけたいけど、あと3ヶ月か。ぐるぐると考えているうちに集会は終わっていた。校長先生が何度も口をハンカチで拭っている。あーあ、気にしちゃってんじゃん。
明日は二十日だから予習を多めにしておかなくては。四十人いるクラスで出席番号すらド真ん中なんて笑える。
田中さん、田中、田中先輩、由美ちゃん、由美。みんなが私を呼ぶ声。どうして特別な名前をくれないんだろう。田中の「か」と由美で「かゆみちゃん」とか、良くない?こっちはもう先に思いついてんのよ。あとは誰かが呼んでくれるだけ。てかもう田中っちとかでも全然いい。あだ名欲しさに中学の時はポケットに常にコンパスを入れてみたりもしたっけ。あれだって、私がギリギリ勇気を出せる奇行だったのにな。それすら「田中さん、コンパス貸して!」以上に言及されることなんてなかったけど。
お父さんがいてお母さんがいてお兄ちゃんがいて犬がいて、年に数回はおじいちゃんとおばあちゃんに会いに行く。
成績は良くもなく悪くもなく、身長も高くなく低くなく、友達は多くもなく少なくもなく、人並みに恋も失恋もした。
「普通」という言葉を使えば簡単だけど、東雲さんの普通と私の普通は違うのだろうけど、私こそが、田中由美こそが、普通だと思う。
でもどうしてか、こんなに普通なのにどこに行っても居心地が悪くて、何をしててもモヤモヤするのだ。こんなにも普通なのに、みんなより何かが劣っている気がしてならない。そしてその代わりに、本当はすごく特別な存在な気がしてならないのだ。
私にしかない特別な何かがきっと。
卒業式に東雲さんは来なかった。ラストチャンスだったのにな。
東雲さんみたいな人がいっぱいいるかもしれないから、卒業後は東京の大学に進学した。1女(イチジョ)として新歓でとにかくチヤホヤされる時期を抜けたら、私はまた普通の人に囲まれた普通の人になっていた。
つまんない。つまらなすぎる。わざわざ東京に出てきてまでのつまらない日々は、地元で感じるそれの数倍辛かった。あまりにも辛くて、晴れでも雨でもない、暑くも寒くもない日に、大学を辞めた。親の反対を押し切ったことなんてこれが初めてだった。
大学に進学しておいて、半年で辞めるなんて、私ってばやるじゃん!やっと自分という容れ物の中に中身が入ってきたような気持ちになれた。本来私はこんなに大胆な人だったんだ。まさかあの田中由美が大学を半年で辞めるなんてね!地元の友達が聞いたらびっくりするだろう。聞かせる気もないのに想像してしまう。東雲さんもびっくりするかもしれない。しないか。
田舎の情報網は速い。親が誰か一人にポツリとこぼせば瞬く間に情報は拡がっていく。それまでは別に誰にも教えなくていいや、と思った。風の噂で「由美が大学を辞めちゃったらしい」と耳に入る方が何となくクールな気もしたからだ。とにかく東京の自由を今私は全身で浴びている。
あぁ、何でもできる気がする、こんな気分になったのは生まれて初めてだった。思いつくがままに憧れのライブハウスに電話をして、バイトの面接を受けた。
「由美ちゃんは真面目で助かるよー。今まで時間守ってるやつなんてうちのバイトには一人もいなかったからね(笑)」
下北沢EVEで働き始めてから3ヶ月、店長の笹(ささ)やんさんに言われた。笹谷だから笹やん。ドレッドヘアーの管理が大変だ、という話を何回もしてくる。
「それって私が、普通ってことですか?」
「ん?普通じゃないんじゃない?ビールサーバーもまめに掃除してくれるしね。こんな真面目な子うちじゃ異端児だよ(笑)。その調子でよろしくね!」
普通な私が、少し日常からズレた場所で働き始めたら普通じゃなくなった。笹やんさんからの異端児という評価は私の求めている姿ではなかったけど、突然常識がひっくり返った日常にはワクワクしていた。でも、私だって遅刻したりバックれたりしたい時はある。
性格的に無理なだけだ。
今日のライブはほんのりとインディーズ界で人気が伸び始めているyomoyayomoya(ヨモヤヨモヤ)、略してヨモヨモの自主企画だ。きっとドリンクもいつもよりは忙しくなる。楽なスミノフをもう少し発注しておくべきだったかな。
ヨモヨモの曲はストレートに響く。存在を知ったのはここに来てからだけど、この3ヶ月でも集客が明らかに伸びてきている。耳の早い音楽ファンにはもう届き始めているのだ。
メッセージ性だけじゃない技術もあるし、グッズのセンスだっていい。きっと地元じゃこの音楽には気付けなかっただろう。でもいつかはあんな田舎にも届くくらいのバンドになる気がする。
「今日は本当に来てくれてありがとう。俺たちは極端なことを言うとスタジオで音鳴らしてるだけで満足なんだよ」
8割くらい埋まったフロアに向かってボーカルの西﨑が語りかけている。熱いMCもファンの心を掴んで離さないのだろう。
「でもさ、こうやって4年やってきて……みんながいい顔で聞いてくれるこの光景を知っちゃったんだわ。正直、今日ソールドしなかったこと超悔しい。でももっと俺たちやれるから、ついてきてく……」
ガゴンガランゴロン!
「……ま、ついてきてくれってこと!それじゃ最後の曲!」
うわー。またやってしまった。いや、やってしまったのは私ではないんだけど。古い業務用製氷機は氷ができた瞬間にでかい音が鳴る。またやってしまったというのは、製氷機のやつがまたやってしまったのだ。私がやってしまったわけではない。めっちゃいい感じの雰囲気だったのに……せめて曲中に頼むよ。一瞬の静寂のあと、私のせいではないのに、ドリンクカウンターに立ってる以上なんとなく私のせいみたいな空気が流れる。
「お疲れ様でした。あのー、何かすみません」
「ほんと勘弁してよ!この前なんてバラード中に鳴らされちゃったからね。あの時よりはマシ」
西﨑は笑って仲間たちの分の酒を奢るとそっと一つだけビールを置いていった。
「もう仕事終わるでしょ。こっちで一緒に飲もうよ。笹やんから真面目すぎて心配って聞いたよ!たまには息抜きしな!」
西﨑さん私ビール苦手なんです、とはよもや言えず、やっとEVEの一員という扱いをしてもらえた感覚だった。
今日もタイムカードを5分前に押す。
「こおりちゃん!あとで表の看板ちょっと拭いといて。鳥のフンついちゃってたわ」
「えー、笹やんさんがやってくださいよー。鳥のうんち嫌だよー」
「俺だって嫌だよ! こおりちゃんも遂に言うようになったか……俺は悲しいよ」
大袈裟に肩を落として笹やんさんは雑巾片手に外に出て行った。 こおりちゃんというのは私のあだ名だ。あの日西﨑がつけてくれた人生初のあだ名。
「半年で大学やめたの!? ウケるね~。笹やんから聞く限りはそんな子に見えないのになー。えーっと……」
「田中です。田中由美」
「ごめんごめん、田中さんだ。覚えづらいからさ、こおりちゃんって呼んでいい?」
「……こおりちゃん?」
「氷鳴らしすぎのこおりちゃんね!」
「え?」
こおりちゃんというあだ名は瞬く間に浸透して、EVEで田中由美として働いていたことを忘れてしまいそうになるほどみんな私をそう呼んだ。笹やんさんや、ヨモヨモのメンバー、他のバンドマンはもちろん、ヨモヨモファンの子にまで呼ばれた時はびっくりした。こおりちゃんさん今日はMCの時鳴らさないでくださいね!って私だって出来るならそうしたいんだよ馬鹿野郎。
明らかに、田中由美であった時よりもみんなに親しまれている実感があった。嬉しい。あだ名ってこんなに嬉しいんだ。
親じゃない、他人がつけてくれた特別な名前。呼びやすくって愛らしい私だけの名前。
続きは2022年4月7日発売 「文藝」夏季号でお楽しみください。