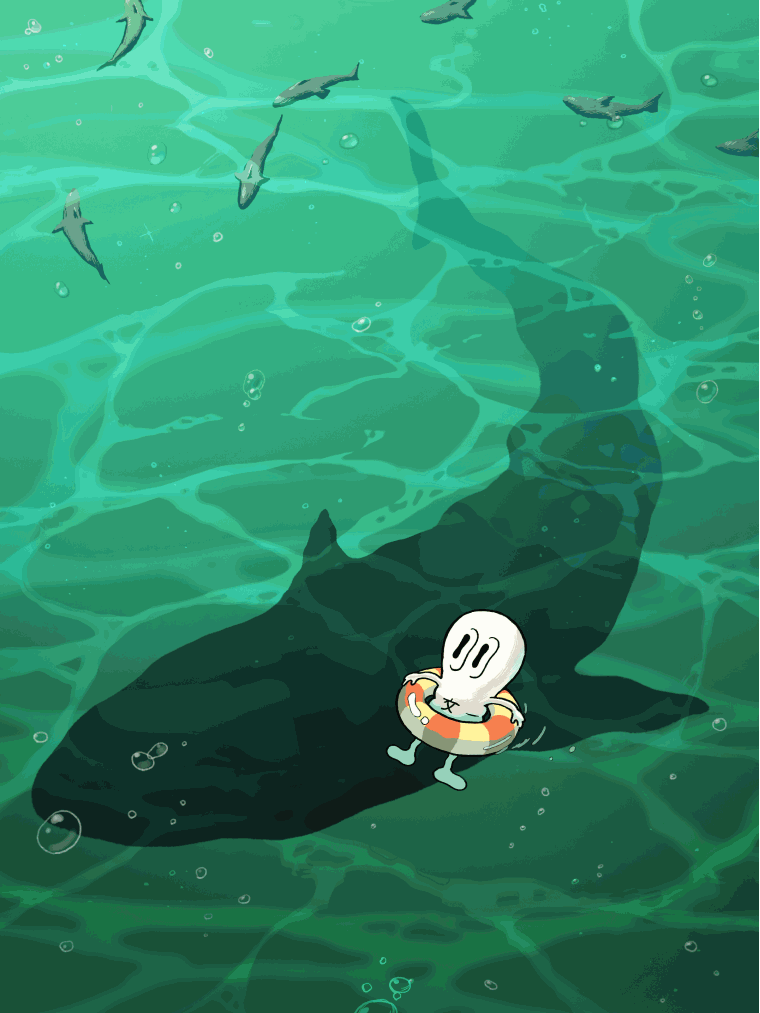単行本 - 日本文学
「文藝」夏季号掲載、文藝賞優秀作受賞第一作の新胡桃「何食わぬきみたちへ」試し読み
新胡桃
2022.04.07
向き合わずにいられて、安全圏で生きられて、いいな――。高校の教室、ひりつく記憶。第57回文藝賞優秀作受賞の著者による第二作。
===↓試し読みはこの↓へ===
何食わぬきみたちへ
新胡桃
伏見の場合
ピピッと小気味よい電子音が鳴った。スイカで改札を出てすぐバスに乗り、しばらく揺られ、住宅街のこぢんまりした停留所で降りる。スニーカー越しにも伝わるアスファルトのむんむんとした熱。首筋を包み焼くような光。だいたいのものが眩しくて、すぐに目を細めた。光の密度が濃い。木々の素朴な匂いと、ところどころの坂道。
草いきれ、という言葉をふと思い出した。夏に帰るのは初めてだったけど、帰省する度に、自分の中で日常だったはずの単語、その匂いや姿が、大きな街に暮らす中で褪せてしまうのを、こうして自覚する事がままある。
「伏見君って、いい匂いするよね」
大学に入ってから何度か言われた言葉だ。
高校生の時は、「いい匂い」と褒められる事もなかった。おれから発せられる匂いはこの地域特有の匂いなのかも知れない。すぐそばを車が通り過ぎる。一歩一歩を確かめるように踏みしめ、歩いた。
ことん
不意に、背後で軽い音がした。
振り向いても、スズメがたどたどしく跳ねている以外、動くものを見つけられない。
ことん
それは明らかにすぐそばで鳴っていた。
ことん
鍋蓋をとじる音のようだ、と思う。そうなると、地面に金属質のモノが転がっているのだろうか。
ごとん
ひときわ大きな音がして思わず顔を伏せると、足元に何か棒状のものが転がってくるのが見えた。ころころ、という乾いた響きではなく、ごろりざらりと重い物質感で、ゆっくりと。錆びて曇った表面が、やがておれのスニーカーにぶつかる。リレーのバトンほどの大きさで、なるほど、古びた鉄パイプだ。さっきの音はこれが落ちた事によるらしい。恐る恐る好奇心で拾うと、まるで人肌の中にあったかのような生々しいぬくみと湿りがあり、慌てて手を放す。片手で持てない重さではなかったのに、やはり、ごとん、と鈍くぬるい音でそれは着地する。
「ん!」
声がして振り返ると、おれの目線より少し高い石垣に、男がいた。いや、男の子、かも知れない。小太りで色の白いそいつは、爪を噛みながら強い眼差しでおれに手を差し出している。あぐらを少し崩した形で座っていて、チノパンにしわが寄っている。
「ぽくぽく!」
しばらく見つめ合った後、そう言われた。とても間の抜けた、おかしな抑揚の声。しかし変声期は確実に終えたであろう低さもあり、なにもかもちぐはぐだ。おれは頭を掻いた。
「ぽ、く、ぽく、くらしゃ」
黙っているおれを見て、男は手を叩きながら、ゆっくりとそう繰り返した。何かを要求されている事は確かなのだが、どうすればいいのか分からない。
「すみません」
そう答えるのが精いっぱいだった。得体のしれない恐怖があった。
数秒経っても返事はない。そいつは爪を噛み続けながら、やや険しい顔でおれをじっと見つめている。胸が毛羽立つような気分になり、おれは足早にそこを離れ、元の方向へ歩き出した。
二、三歩進んだところで、いきなり洪水のような泣き声が響いた。空間全体がふるえてエコーをかけている。おれは狼狽するも、すぐに全速力で駆け出す。明らかに異様だ。
角を曲がると、ちょうど実家に繋がる一本道が現れた。怒鳴るように泣く不愉快な声が、まだ鼓膜の奥をくすぐる。
「ちょっと」
今にも赤い標識を過ぎようとしたその時、背中に大きな衝撃を受けた。おれはそのまま地面に倒れこむような形になり、アスファルトの不潔な熱を頬で受け取らねばならなくなる。
服をはらいながら注意深く起き上がると、おれの前に女の子が回り込んで言った。
「あんたでしょ、ツボイさん泣かせたの」
ツボイサン、とおれは間抜けに繰り返す。どうやらさっきの衝撃は彼女の通学バッグによるものらしく、あの奇怪な男はツボイというらしい。
「早く立って、行こう」
やけに鷹揚な態度を見せる彼女をしぶしぶ追いながら、女子にしては高いその背に視線をあずける。ノッポ、と心の中で呼ぶ事にした。汗がさっきよりも粘度高く、しつこく噴き出してくるような気がする。男の姿が次第に大きくなり、顔を歪めて泣いているのもはっきり見えた。
「どうしたの」
ノッポが落ち着き払ってそう言い、男を見上げると、割れんばかりに響いていた泣き声が数段おとなしくなった。
「何があったの、ツボイさん」
しばらく周囲を見渡して、やがて鉄パイプを見つけるノッポ。かがんで拾うと、彼女のボブヘアは重力に従ってはらはら動いた。おれはその二歩手前から足を動かせず、Tシャツの襟でひたすら汗を拭う。
「あこちゃん、あこちゃん!」
彼女は、あきことかあつことかそういう名前なのだろうか。斜め上から聞こえるその声は、もう随分と弱々しくなっている。
「帰ろうよ。そこ、危ないんだよ」
ノッポの諭すような優しい口調がとんがって響く程には。
ん、としおらしい返事をして、ツボイサンはこちらに背を向ける。彼のすぐそばで、アリが大仰な行列をなしている。ツボイサンは彼らには目もくれず、コッペパンみたいに白くまるい手足を器用に凹凸へあてがい、石垣を下り始めた。うんしょ、よいしょ、と踏ん張っている。アスファルトに着地したあたりで彼はチノパンに手を突っ込み、股を掻いた。ベビーカーを押しながら、痩せた女性が反対側の歩道を歩いてくる。おれはなんとなく焦って、緊張してしまう。女性の表情を横目で窺うと、やっぱりそうだ、おれたちを見て困ったように眉を顰めていた。ツボイサンは何か虫でも捕まえるようにして、手をパクパクと動かす。決まりが悪そうに、口を尖らせながら「ピーマン」「あかと、あおと」と大きく呟くのをやめない。
「おれ、もう行って良い?」
ツボイサンがのっそり両足を着地させるまで、ノッポはおれの目を見ようとしなかった。だから投げた問いもカンペキに無視されてしまって、正直戸惑うというよりも苛立つ。
「もう行って良い?」
女性の姿が見えなくなったあたりで二回目を投げると、ノッポは「ちょっと待って」と言いながらおれの隣に回った。今にも歩き出しそうな様子のツボイサンの正面に立ち、息を吸う。
「はい、ぽくぽく」
鉄パイプを彼に差し出す。
すると、みるみるうちにツボイサンは笑った。「ありがとうは?」ノッポがそう言って彼の肩をつつくと、「ぐふふ」となんだかゴキゲンな声を出す。
横に揺れながら、赤いおでこを鈍く光らせながら、ツボイサンはにっこり笑っていた。意外と綺麗な歯並びをしていて、目尻のしわがたこ焼きみたいなほっぺたに軽く乗っかっている。チャーミング、と言うと言い過ぎてしまうけど、不思議にどきりとするような可愛さがあった。
「ぽく、ぽく、よ!」
威勢よくその言葉を繰り返すツボイサンの表情は総じて赤ちゃんみたいで、おれはそのまるい顔をじっと見てしまう。
「ぽ、く、ぽ、く、よ!」
ぽくぽくを手に入れた事に感激しているというよりは、「ぽくぽく」という言葉、その語感におかしみを感じているようだった。
「ぽくぽ、く、よー!」
ちりちりした髪の毛が、ツボイサンのメトロノームのような動きに合わせて日の光を受けたり、陰ったりしている。その揺れは催眠術のようにおれを捕えた。変な抑揚で繰り返される「ぽ」「く」「ぽ」「く」「よ」の音一つ一つに不安定な中毒性があり、五音終えるごとに胸の中に蒸気が満ちるような、ほかほかした気持ちになる。結局ツボイサンがくるりとそっぽを向いて歩き出すまで、おれはその場から一歩も動けなかった。
何かに、圧倒されていたのだ。
「行かないの?」とノッポが言う。気が済んだみたいにほどけた声で。パチンと膜が弾けるような感覚があって、おれはようやく自分が腹を空かせている事に気付いた。同時に、一体こいつは何者なのか、なぜおれを呼んだのか、ツボイサン、とは誰なのか、といった質問が喉元で渋滞して、しばらくノッポの顔を見ながら足踏みしてしまう。
ノッポの容貌や話し方、身なりは本当によくいる高校生で、ツボイサンのちぐはぐなそれとは異なる。初対面のおれに偉そうな態度を取っている事以外、まったく奇妙じゃない。
女の子特有の丸く小さな膝小僧、そのギリギリまで履かれたハイソックスは濃い緑色だ。
「サンコー生なの?」
この市の第三高校は山の麓に位置している。盆地の端っこに白壁で建つ、よくある地方の公立校なのだが、制服が特徴的すぎる。何某とかいうデザイナーに特注したそれは派手なのかダサいのかよく分からないし、黄色の差し色が入ったスカートも、斬新なようで古いような、要領を得ないスタイルだ。なんと男子のスラックスまで無駄に主張の強いチェック模様で、着崩し辛いったらありゃしない。
おれの母校だ。
「今日学校ないっけ」
二年前の記憶を辿ると、おそらく夏休みはまだ始まっていない。よく見るとノッポは汗もかいておらず、今家を出てきたばかりという風だった。その涼しげな夏服の肩を落として、大げさにため息をつく。
「なにそれ、うちがいつ学校行くとか、一ミリもあんたに関係ないでしょ」
ズル休みを誤魔化す高校生というより、常識のないおれに完全に呆れているみたいなノッポの様子に少し困惑する。初対面でのため口といい、どうしてか態度がデカい。その上無駄に好戦的だ。大きな蠅がおれたちの間をぶしつけに通り過ぎ、その羽音が暑苦しさを増幅させる。
二秒くらい考えたあと、「じゃあ、どうも」と可もなく不可もない挨拶をして、おれはまた歩き出した。道路に大きく落ちる影のコントラストがより激しく、日陰の部分だけ黒いクレヨンでぐりぐり塗ったようだった。思い出せば、くたびれたクレヨンの白と塗装された実線の白もよく似ている。全体がうす汚れて、道具箱や通りの中にそれぞれ馴染んでしまうあの感じが。
続きは2022年4月7日発売 「文藝」夏季号でお楽しみください。