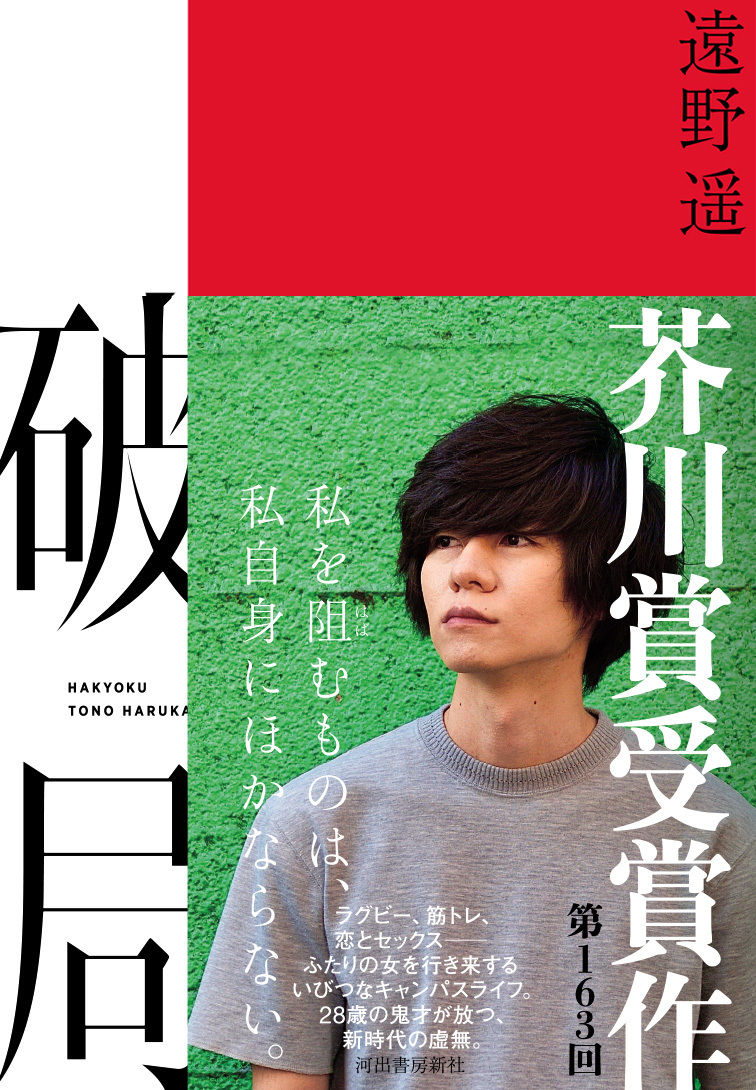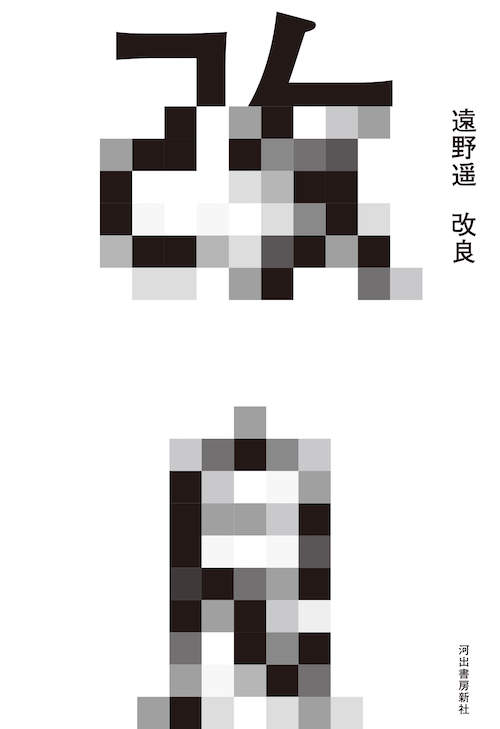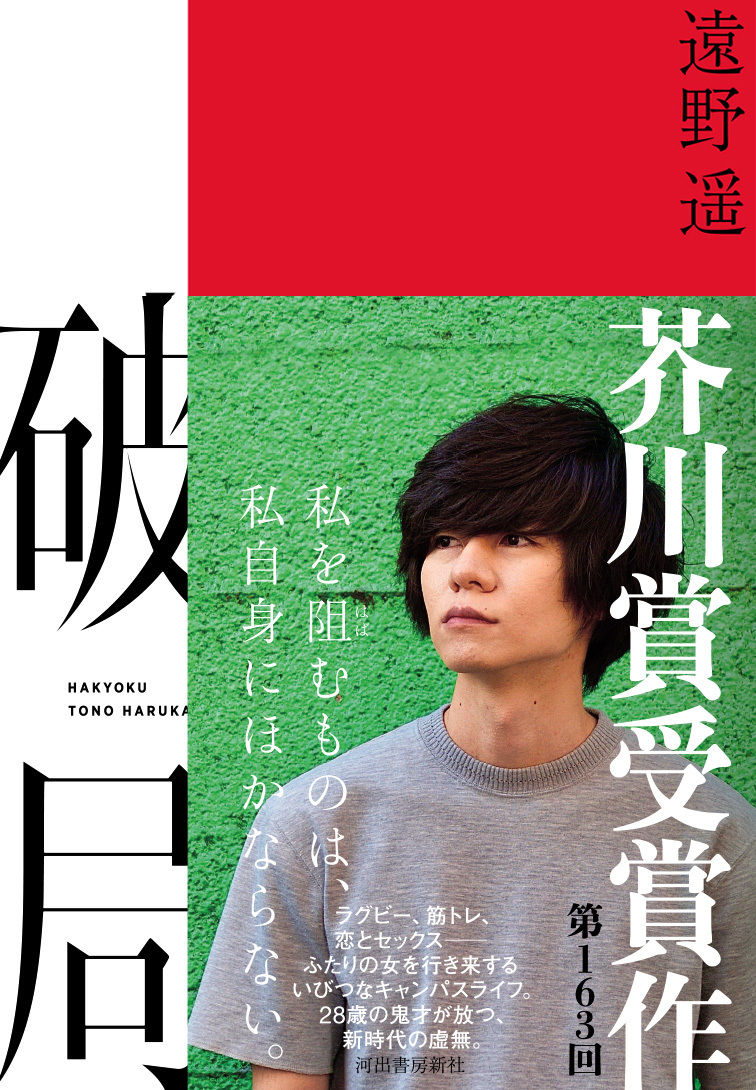
単行本 - 日本文学
今泉力哉が読む、肉食なのに乾いている小説 遠野遥 著『破局』
評者・今泉力哉
2020.09.15
肉食なのに乾いている小説『破局』を読んで笑った――遠野遥 著『破局』
今泉力哉
私は普段小説を読む習慣がないので、一冊の本を読み終えるのに相当な時間がかかる。最初から最後まで一気に読めたことなんてほとんどない。でもいつぶりかに一気に読めたのが、この遠野遥という人が書いて文藝賞を受賞した前作『改良』だった。笑いながら読んだ。『破局』もたくさん笑った。
『破局』は、主人公の陽介があまりうまくいっていない彼女の麻衣子と、新しく出会ってつきあうようになる灯との間で翻弄され、破局を迎えるまでの物語だ。遠野さんは、断定しない思考のそれをすべて書く。疑い続けるのだ。しかし、何というかそれなのにくどくならない。その決めつけなさは、責任の取らなさとも言えるし、繊細さとも言える。でも相手の気持ちがわかっているわけでもない。なんなら鈍感だ。そして、かなり乾いている。例えば、麻衣子と大事な話をしている時に、ふと「穴」だと思ってしまう描写。「口や鼻というのはつまり人間の顔に空いた穴だと気づいたのだ。」え、今?となる。笑ってしまう。他にも灯のつむじがよく見えるシーンで地肌が見えすぎている気がして隠してやりたくなる描写があるのだが、「でも女のつむじに注目したことは今までなかったから、案外これくらいが普通かもしれない。」と考える。また、走る灯を追いかける場面でも、もし追いついたとして、それからどうしたいのか、わからない、と考えてしまったりする。あと、なぜか執拗に男女共用のトイレで便器の蓋をあげっぱなしにすることに怒っている。これは一体なんなのだ。
読みながら、ぺこぱの漫才、トリプルファイヤーの音楽、ホン・サンスの映画『カンウォンドの恋』などを思い浮かべた。ぺこぱ、と思ったのは、その思考において。一旦持ち帰って考えるというか。トリプルファイヤーみを感じたのはその乾き方と笑い、シニカルさについて。今の感じ、って言っていいのかわからないが、またそれってとても失礼な気もするのだが、なぜか今の時代性を感じる。しかし、ただ草食な訳でもなく、なんなら肉食なのだが、乾いている。そこが独特なのだ。
終盤には不条理な何かが訪れ、事故的に強制終了する。『改良』も『破局』も同じような構造でもって終わりを迎える。遠野遥という人は、物語の始め方や終わらせ方についてどう考えているのだろうか。終わりに重きをおいていないのかもしれない。『カンウォンドの恋』を感じたのは、最初に灯の家に行ったとき、ベッドの下に彼女が隠れているあのシーンだ。姿が見える、見えない、そういった不穏についてのシークエンスがどちらにもある。カンウォンドの場合は窓からの身投げだったが。また、金魚やメダカの扱い方もどこか似ている気がした。また新しい小説が出たら読んでみたい。私も誰かに不意に殴られて、遠くなる意識の中で、小鳥のさえずりとかに耳を傾けたい。あと私は便器の蓋をあげっぱなしにする人間だ。
初出「文藝」2020年秋季号