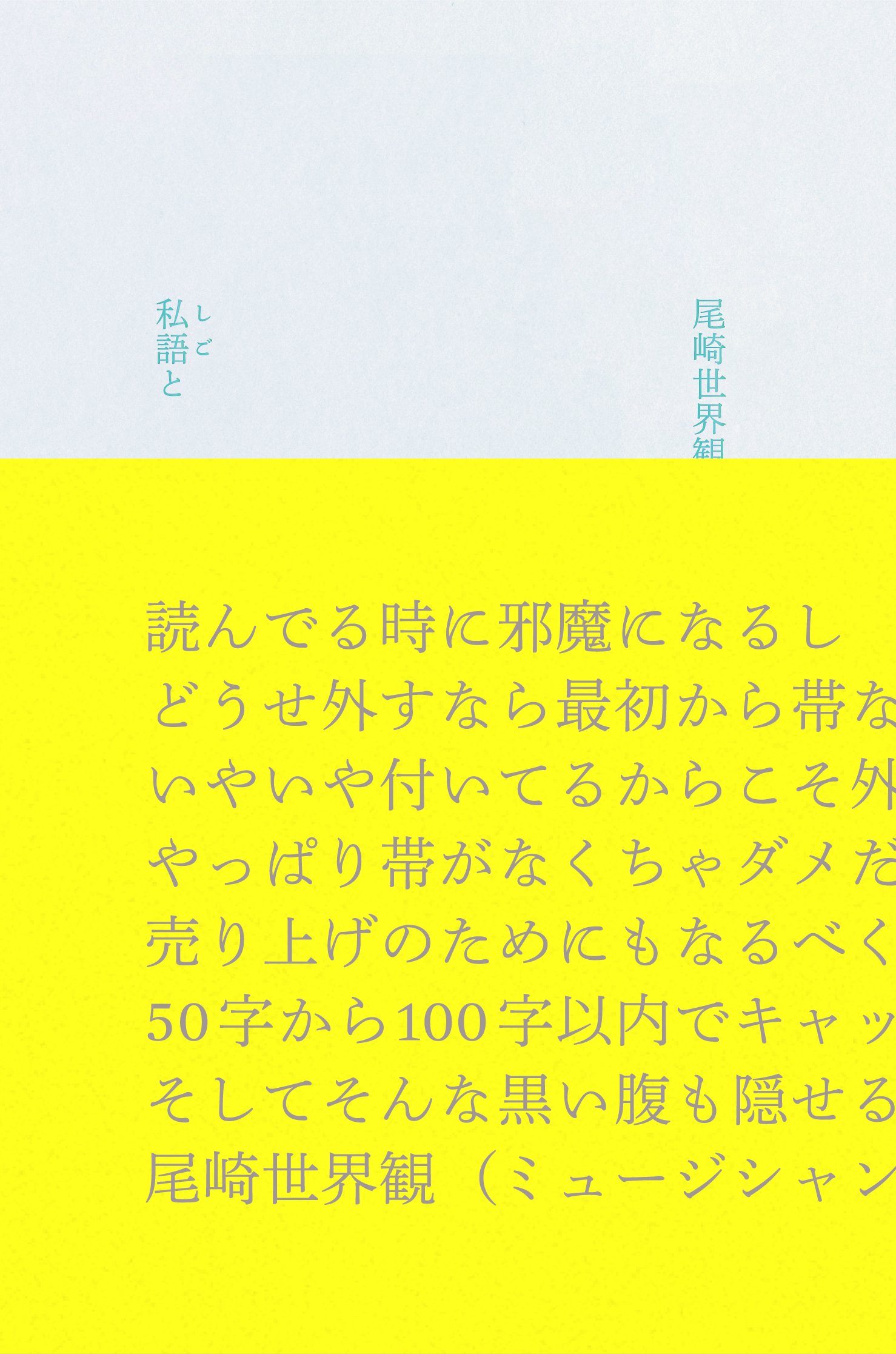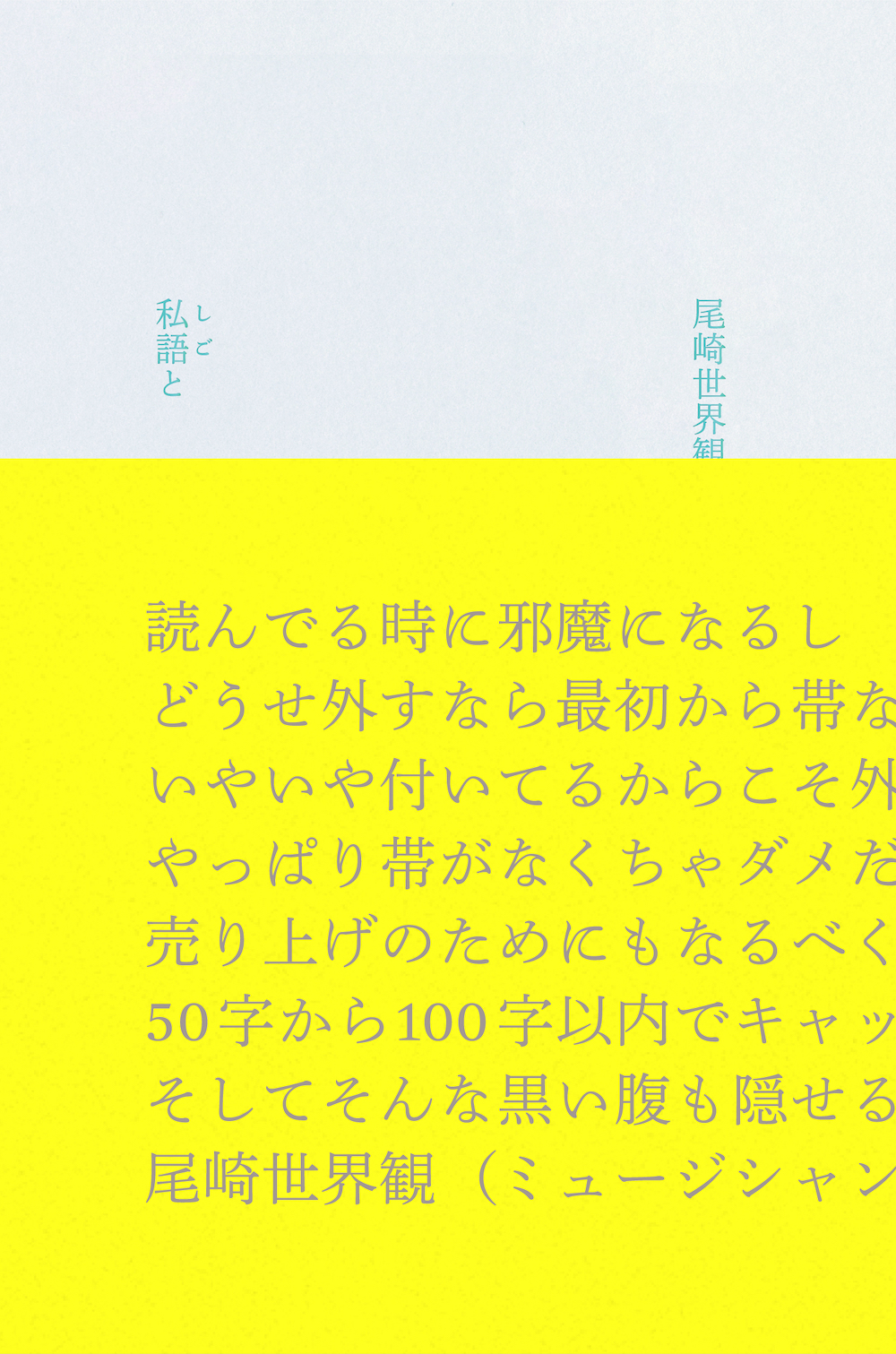
単行本 - 日本文学
無数の『お前』に届く私語 —— 歌人・大森静佳が読む、尾崎世界観初歌詞集『私語と』
大森静佳
2022.05.02
私たちは、言葉があるから苦しむのか。それとも苦しいから言葉にすがるのか。
『私語と』は、クリープハイプの尾崎世界観が20年の歳月をかけて書きつづってきたもののなかから、よりすぐりの75曲をおさめた歌詞集である。言葉によってわかりやすくまとまる前の、胸の疼きのようなものを慎重に、ときに破れかぶれに保存している一冊だと思った。破れかぶれというのは、その試みが、「言葉」からこぼれ落ちてしまう疼きを「言葉」によって書き留めようとする、矛盾をはらんだ闘いだからだ。
歌詞のほとんどは、うまくいかない恋愛を扱っている。一人称の「僕/あたし」は生きることに不器用で、ひねくれていて、やや自虐的な語り手であることが多い。素直に気持ちを伝えることが苦手で、相手とのすれちがいが重なり、やがて別れへ。孤独な部屋で、過去の幸せだった場面をあれこれと振り返る。そのとき尾崎の歌詞において特徴的なのは、「君/あなた」の顔や表情などよりも、そこに「君/あなた」が確かにいたという、気配や余韻のようなものが豊かに書き起こされている点だろう。たとえば、〈一段低い所に置き換えたシャワー〉(「愛の標識」)や〈肩にかけたカバンのねじれた部分〉(「愛す」)などがそうだ。もし「君/あなた」の顔や身体が描写されていれば、それをそのまま思い浮かべて終わりだが、書かれていないせいで、私たちは「シャワー」の位置や「カバンのねじれ」といった細部から「君/あなた」の輪郭そのものを能動的に想像することになる。そこにあるドラマに、こちらが能動的に参加すること。その過程によって、歌詞はより深く私たちの心に沁みとおってゆく。
女性視点と男性視点が途中で入れ替わる「寝癖」にとりわけはっきりと表れているように、恋愛においてはもちろん、人と人はいつも「言葉」のせいですれちがう。自分の本心をそのとおりに伝えることは難しくて、言葉足らずになったり、言い過ぎてしまったり、たとえ本心を伝えたとしてもちょっとした語尾のニュアンスやそのときの表情によっては皮肉やお世辞と思われてしまったり。たとえば家族であれば、ある程度一緒に過ごしてきた時間の蓄積があるけれど、恋人同士の場合は共有されたものが何もないまま突然に「わかりあう」必要に迫られる。そこで、「言葉」のすれちがいが起きる。つまり恋愛関係は、言葉による意思疎通の困難をもっとも痛感する現場でもある。尾崎の歌詞ではしばしば、犬(「マルコ」)、チョコレート(「ミルクリスピー」)など、人間ならざるものが擬人化されて登場することがあるけれど、それらを恋人の暗喩として読むとき、言葉が「つうじない」者同士というニュアンスがいっそう強調されるだろう。
そういう意味でも、この一冊の主題は「言葉」なのだ。「恋愛」ではなく。
あ、無害な言葉を並べて
あ、これくらい意味の無い言葉なら
恥ずかしくなったりしないしな (「あ」)
こうやってエイトビートに乗ってしまう
ありきたりな感情が恥ずかしい (「手」)
簡単なあらすじなんかにまとまってたまるか (「栞」)
そう、意味は恥ずかしい、言葉はそもそも恥ずかしい、と強く共感する。言葉にしたとたん、わかったようなニュアンスが出てしまう。そして実際に、言葉にすると周囲から「わかられて」しまう、簡単に共感されてしまうことがあって、それも恥ずかしい。「社会の窓」や「本当」などの歌詞にも、たやすく理解されることへの抵抗感がつづられているが、そこには、自分の感情はそんなわかりやすいものではないはずだという誇り高さと、いざ言葉にすると「ありきたりな感情」に思えてくる不安が同居している。
言葉というものの嘘くささを痛いくらいに感じていながら、言葉を尽くす。その矛盾した営みのなか、尾崎世界観の独自の文体はさまざまにきらめく。
たとえばひとつめは、韻の踏み方や同音異義語の使い方。〈泣き声〉は〈無き声〉へ変身して、好きな人の泣き声さえ今はもうここに「無い」ということを語るし(「おやすみ泣き声、さよなら歌姫」)、〈痛い〉は〈居たい〉へ変身し、相手の隣にずっと「居たい」思いを吐露する(「百八円の恋」)。いわゆる言葉遊びだが、これによって、「意味」の恥ずかしさから少しだけ逃れることができる。「居たい」というのが単に「痛い」からの駄洒落的な連想で出てきた言葉にすぎない、という衣装を着ることができるから。でもそれが衣装にすぎないこともまた明らかであり、私たちはそうしてようやく、尾崎世界観が抱え持つ「恥ずかしさ」ごと歌詞を受け取ることができるのだ。そういえば、『私語と』というタイトルだってそうだ。これは世界に向けたメッセージなんかではなくて、ただの「私語」なんだよとしたたかにエクスキューズしながら、だけどそれこそが自分の「仕事」であると胸を張っている。
一瞬我に返る 君が居ない部屋に一人だった
今週君は帰る 生まれ育った町へと
一瞬我に返るけど 君と居たあの部屋は二人だったし
今週君は帰る 生まれ育ったあの町へと (「愛の標識」)
ふたつめは、気持ちが固定されず揺らいだり引き裂かれたりしているさまを、ナマなまま動的に書いていることだ。たとえば〈一瞬で消えていく思い出になれたらな/汗ばんだ手のひらからすべり落ちた記憶/本当に見えてるなら あたしには教えてよ/本当に見えてるなら/あたしには隠してよ〉(「手」)のように、すべり落ちてしまった記憶を「教えてよ」と告げた次の瞬間には「隠してよ」と正反対の願いを突きつける。教えてほしい、でも知りたくない。そんなふうに引き裂かれる思いをそのまま流れるように書きとめる。〈「今ならまだやり直せるよ」が風に舞う/嘘だよ ごめんね 新しい街にいっても元気でね〉(「栞」)であれば「やり直せるよ」という気持ちが一度は光って見えたのに、やっぱり「嘘だよ」「ごめんね」と引き返す。こういう感情がある、というふうに固定してしまってから書き始めたとしたら、きっとその歌詞は死んでしまう。言葉や意味の嘘くささに濁ってしまう。尾崎の歌詞はまったくそうではなくて、固定しない不安定な地点から書き始められているのだ。行きつ戻りつする、その気持ちの流れ方がリアルなのだ。
言葉に追いつかれないスピードで
ほんとしょうもないただの音で
あたしは世間じゃなくてお前に
お前だけに用があるんだよ (「しょうもな」)
最後に、私がいちばん好きなフレーズを引く。言葉を用いていながら、「言葉に追いつかれない」もの。「世間」の大きな文脈ではなくて、たったひとりの「お前」だけに伝える音。ひとりの「お前」だけに伝えようとした個人的な言葉、すなわち「私語」が、無数の「お前」に刺さってゆく。それが、尾崎世界観の歌詞の魔力なのだと思う。
あえて音楽のことには触れず、この一冊を純粋に「詩集」として読んでみた。書き下ろしの「帯」「はじめに」「おわりに」はいずれもアクロバティックな内容だが、特に「はじめに」は、「メロディ」から無理やり切断された「言葉」が「干され」「乾かされ」「枯れる」までを描き、「歌詞集」というこの書物そのものへの、おそらく照れ隠し込みの自己批判になっている。しかし、ただひとりの「お前」に向けられた肉声、という意味で、たとえメロディを抜きにしたって、ここにある歌詞は本質的に(詩や散文ではなく)「うた」なのだ。