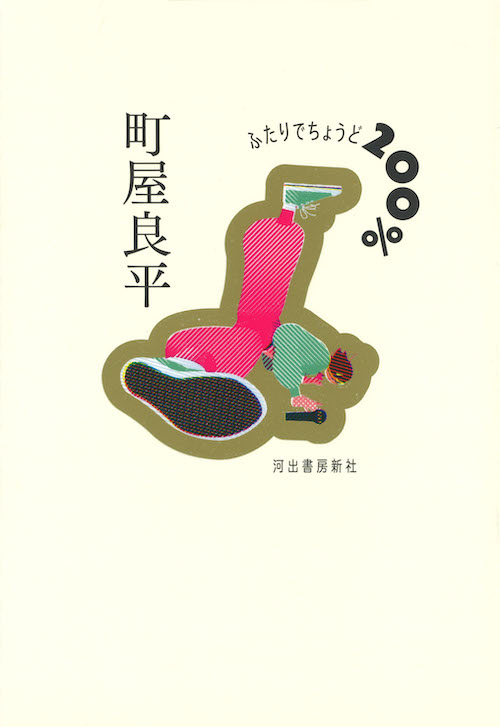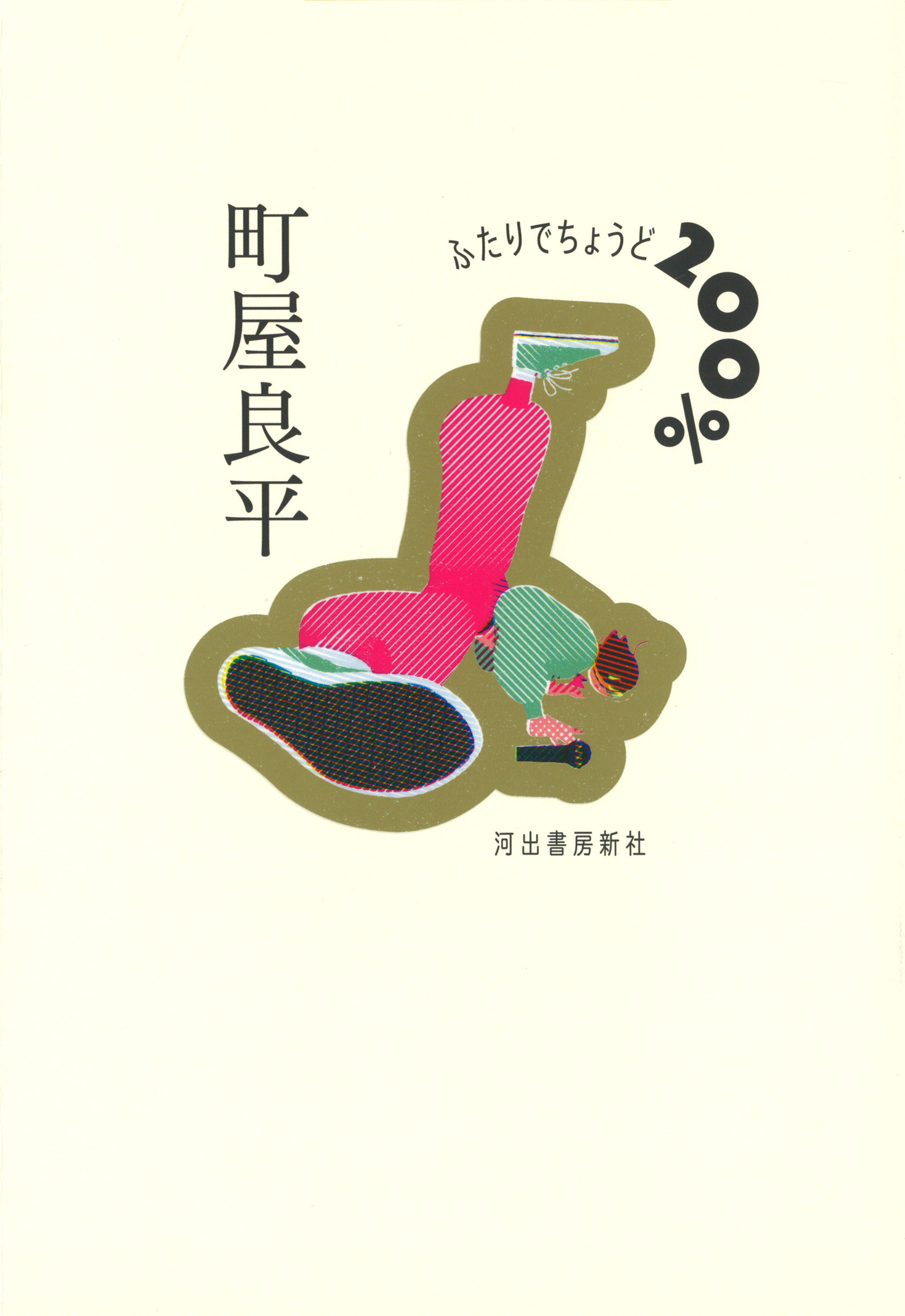
単行本 - 日本文学
「男同士の、とりわけ1対1の関係に宿るなんとも言えない感触」抱きしめ合えない俺たち。芥川賞作家が拓く新らしい男子――町屋良平 著『ふたりでちょうど200%』
評者・清田隆之(桃山商事)
2020.12.04

本書は4つの短編からなる連作小説集だ。すべて鳥井陽太と菅航大というふたりの男性が主人公になっているのだが、バドミントンのダブルス、ブラック企業の同僚、男性アイドルとそのアンチ、有名俳優とゴシップライターと、作品ごとに関係性が異なっている。一方、ふたりは同じ小学校の同級生で、当時の記憶のいくつかを曖昧に共有している点は全作品に共通する。そこから分岐する鳥井と菅のあり得たかもしれない人生が交錯するパラレルワールドのようでもあり、また、何度生まれ変わっても出会ってしまう奇妙な腐れ縁を目の当たりにしているようでもある。そんな不思議な手触りの本作は、私にとって男同士の、とりわけ1対1の関係に宿るなんとも言えない感触について考えさせられる1冊となった。
例えば「カタストロフ」という作品における鳥井と菅は中堅出版社の新人営業マンとして働き、行き詰まった状況の中で数字を追求させられている。忙しさで余裕を失い、日々の記憶もぼんやりしている。彼らにとって週に1度のバドミントンは発散の場であり、試行錯誤しながら連携を高めていく。スポーツはとかく勝ち負けに主眼が置かれがちだが、プレーを通じて互いを発見していく姿は、競争に拠らない新たなホモソーシャルの形を提示しているようで希望がわく。
しかし一方で、ラケットやコートに身体感覚を拡張させていくことに生の実感を見出し、パートナーとの境界すら溶け合わせていきたい鳥井に対し、菅は段々とその密度に恐れをなしていく。ふたりのコミュニケーションには終始「交わりきらなさ」のようなものが残る。感極まってもハイタッチがせいぜいで、互いの身体を抱きしめ合うことができない。「ソーシャル」という作品にもこのような場面があった。
〈ある日のサイゼリアでワインを三本あけながら、「おれはもう、やめる気力すらなくなってしまったんだよお。だから、お前だけでもさっさと転職してくれ」と泣いて、服薬とうつ症状を告白したのだが、菅は「つらいのはみんないっしょだぞ」といった〉
これらを読み、ふいに身近な友人たちの顔が浮かんだ。私にも特別な結びつきを感じている男友達が何人かいる。その関係には依存や支配、嫉妬や憧れなどいろんな感情が入り混じる。傍から見ても仲良しだと言われるが、親友と呼ぶにはなんだか照れくさい。しっくり来る言葉を探すなら「コンビ」が近いだろうか。
コンビとは何かを媒介にしてつながる関係のあり方で、同じ方向を目指すにはいいが、向き合うことはときに苦手だったりする。私もかつて失恋のショックに耐えかねて男友達の前で涙を流したことがあるが、なぜか笑いの空気に変えられてしまった。でも相手の戸惑いも痛いほどわかる。はたして我々は、男同士で抱きしめ合うことができるだろうか。思えば芥川賞受賞作『1R1分34秒』におけるボクサーとトレーナーの関係も極めてコンビ的だったが、胸を打つラストだった。町屋良平の小説にはその先の可能性が描かれている。俺たちだって互いにケアし合えるはずなのだ。
初出「文藝」2020年冬季号