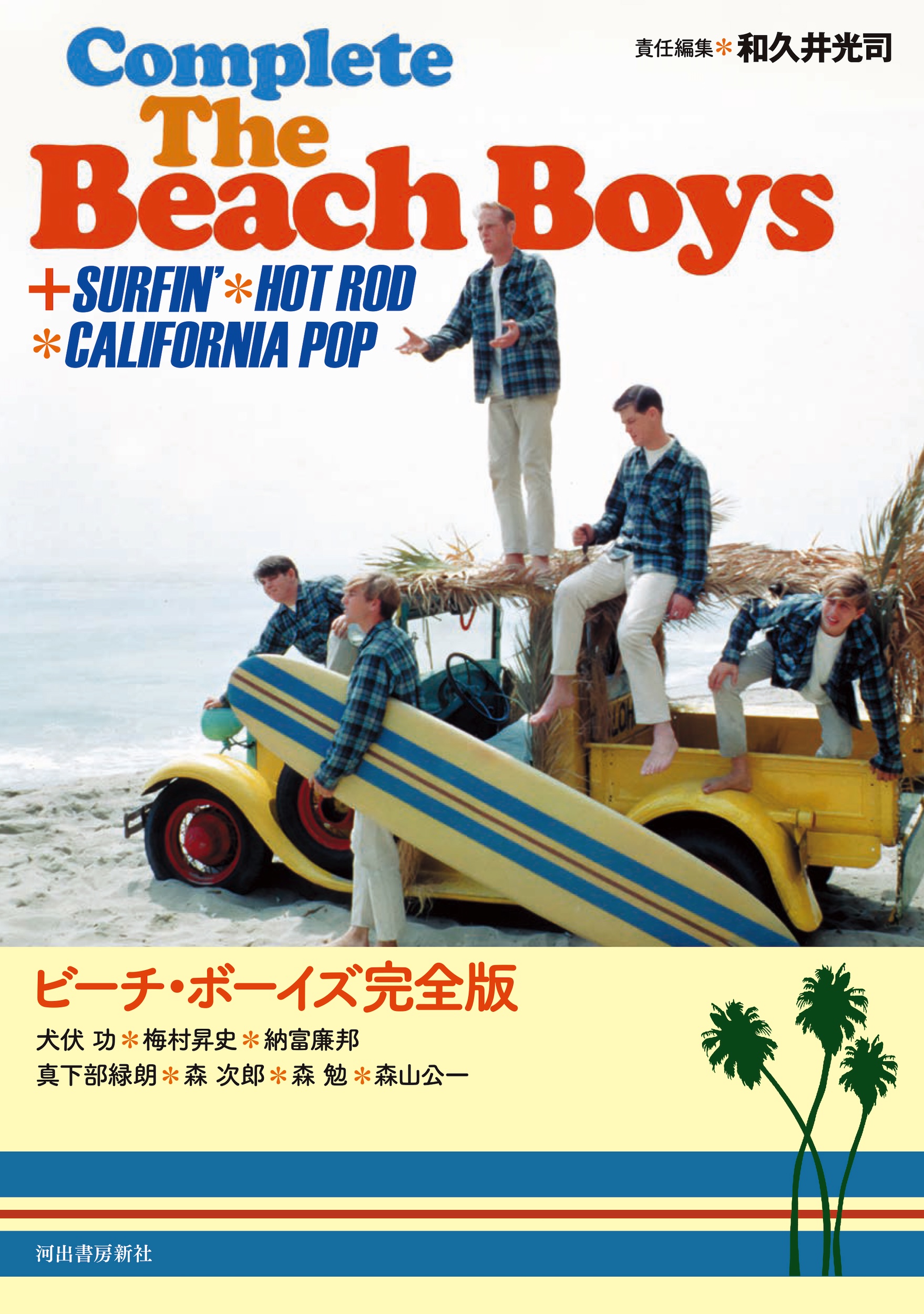単行本 - 日本文学
山田悠介 最新刊『サブスクの子と呼ばれて』10月25日より全国書店にて順次発売!
山田悠介
2022.10.11

鬼才・山田悠介が放つ狂気と感動の最新作!
花火の下で交わした人形に、すべてを込めて――
「ヒト」のサブスクサービスが普及した日本。
児童養護施設で暮らす怜と仄花は、違法な仕事を繰り返しながら、身を寄せ合って生きていた。
ところが、そんな高1の秋に狂気と悲劇が訪れる。
それから10年、気鋭の弁護士として活躍する怜は、変わり果てた仄花を救うことができるのか?
そして、調査の先に見えてきた衝撃の真実とは!?
豪華アーティストが集結した小説オリジナルPVを初公開!
CVは小野賢章さんと石川由依さん。アニメーションはカバーイラストも手掛けたさとまさん。そして本書のための書き下ろしテーマソング「狂えない」を歌うのは、次世代バーチャルシンガーの理芽さん、作詞・作曲・編曲は笹川真生さん。
本書の世界観を、迫真の演技と切なさ溢れる楽曲、そして渾身のアニメーションで凝縮してくださいました。
初回限定特典 朗読劇「花火の下の約束」公開中!
PVキャストの小野賢章さん、石川由依さんによる本編の一部朗読劇「花火の下の約束」を、初回限定で書籍購入者全員にプレゼント!
主人公とヒロイン2人の絆が強まる、物語前半の感動のシーンを、お二人の迫真の演技で朗読化します。本書を読みながら、ぜひ世界観をお楽しみください!
小野賢章さん、石川由依さん、理芽さん、笹川真生さんから本書にコメントを寄せていただきました。
【小野賢章さん】
子どものサブスクが存在する世界。
様々なサブスクリプションがあり、僕も当たり前のように利用してますが、もしも本当に子どものサブスクが存在したら?と考えただけでゾッとしてしまいました。ぜひ本編をお楽しみに!
【石川由依さん】
怜と仄花、二人の運命を想像して、見守るような、祈るような気持ちで、一気に読み進めてしまいました。
近い将来、現実となるかもしれないサブスク社会。私が演じた仄花をリアルに感じていただけると嬉しいです。
【理芽さん】
どうも、理芽です。「サブスクの子と呼ばれて」のPVテーマソングを新曲「狂えない」で担当いたしました。作品に対する愛と願いを声に込めて歌いました。
実はあたし「好きな本は?」と聞かれたら「山田悠介さんの作品!!!」と答えるほど大好きで、小学生の頃から沢山の作品を読んできました。そんな推しである山田さんの作品に今回携わることが出来てとても光栄です。
楽曲を担当するにあたって今回の新作も一足早く読ませていただいたのですが、冒頭からこれは面白い作品だと分かる一作です。
現代に生きるあたしたちだからこそ理解できる、自由さと恐ろしさ。とても考えさせられます。「サブスクの子と呼ばれて」是非ともお楽しみに!
【笹川真生さん】
わたしが学生だった頃、「毎朝、始業前に10分間、本を読みましょう」という、「朝読書」という習慣がありました。
各々が好きな書籍を選んで読むことができたのですが、同級生の多くが山田さんの作品を選んでいたことを記憶しています(わたしもその内のひとりでした)。
あれから時が経ち、いま山田さんの作品に音楽として携わることができ、感慨深いです。
「サブスク」を名に冠した今作ですが、わたし自身、月にいくら支払っているのか把握できない程にサブスクリプションに浸かっています。
ぜひ小説といっしょに、音楽も楽しんで頂けたら幸いです。
著者の山田悠介さんメッセージ!
「サブスクサービスが爆発的に浸透している中、いつかこんな世界が来るかもしれない……」そんなアイデアから生まれた物語です。
主人公の怜や仄花は商品として契約者のもとへと派遣されていきますが、「ヒト」は「モノ」や「サービス」とは違います。結果、悲劇が起きてしまいます。
商品なら返品もできるし、使わなくなったら捨てればいいかもしれません。
でも人はそうはいきません。人との絆は便利さや面白さ、お金では計れません。だからこそ怜たちは苦しむことになります。
この物語を通して、周りにいる大切な人との絆について、見つめ直すきっかけになれば嬉しいです。
最新作『サブスクの子と呼ばれて』ぜひ読んでみてください!
刊行記念!「プロローグ」試し読み!
『サブスクの子と呼ばれて』の刊行を記念して、「プロローグ」を無料公開いたします。
Prologue
目も眩むような光が真上から降り注ぐ。
空には雲一つなく、燦々と輝く太陽があたりを照らしていた。
ちょうど昨日、関東地方での梅雨明けが宣言されたばかりだ。一ヶ月以上どんよりとした厚い雲に覆われていたのが嘘のように、昼下がりの都内は晴れ渡っていた。
「ほら、リョウ。なんでも好きな物を注文しなさい」
大きな窓から外の景色を眺めていた高山怜は、横からの声にふと我に返った。目の前にタブレット端末が差し出されている。
「あ、ごめん。お母さん」
そう言って、怜は差し出されたタブレットを受け取った。
「値段のことは気にしないでね。せっかくの誕生日なんだから」
怜の母はそう言ってにっこりと微笑む。
怜は画面に映し出された豪華な料理の数々に視線を落とした。
怜たちが来ているのは下町にある中華の名店だ。上野公園に面したビルの最上階にあり、目の前の窓からは不忍池が一望できる。池一面には蓮が鮮やかなピンク色の花を咲かせている。真夏の太陽が池に反射して、上からも下からもレストランの窓に射し込んでいた。床こそワインレッドの絨毯が敷かれているが、壁もテーブルクロスもすべてが白い。そのせいで眩しいくらいに店内は明るい。所々に置かれた高そうな調度品や花瓶に活けられた花が、光に包まれて輝いていた。
Tシャツにジーンズというラフな恰好で来た怜は少し気後れしたが、母が常連であるためか店から咎められることはない。丁寧に予約席へ案内されると、適度な冷房で汗が引いてくる。
怜は改めてタブレットを眺めたが、そこに記されていた値段に驚いた。いくら誕生日とはいえ昼からこんな贅沢をしていいものだろうか。
様子を見ていた母が怜からタブレットを取り上げた。
「もう、リョウはホントに優しい子ね。値段気にするなって言っても気を遣うんだから…… もういいわ、お母さんが勝手に注文する」
そう言うと彼女は迷うことなくタブレットに触れていった。
母は今年四十五歳になる。しかし料理を品定めする姿は怜から見ても若々しい。少し茶色に染めた髪は艶やかで、ウェイブして肩に掛かる。肌は白く真っ赤な口紅がよく似合っている。スカイブルーのワンピースが涼しげだ。
前菜、スープ、魚料理、肉料理……
母は口元でつぶやきながら画面をスクロールしていった。
「あ、そうだ。小籠包も食べましょ。ここのウニの小籠包は最高なのよ!」
「お母さん、そんなに食べきれないよ」
「いいのよ。余ったらテイクアウトすればいいんだから。ね、お母さんがそうしたいの」
彼女はそう言ってペロッと舌を出すと、『注文』ボタンを押した。
しばらくすると、怜たちの卓の上にはテーブルクロスが見えなくなるほどの皿が並んだ。フカヒレのスープや北京ダックなど初めて食べる物ばかりである。こんなに豪華な誕生日は今まで経験がない。
蒸籠に入った小籠包がやってくると、店のスタッフが一斉に蓋を開けてくれる。立ち上る湯気と一緒に美味しそうな匂いが漂った。
どの小籠包も熱々で旨い。皮を噛んだ瞬間、熱せられた肉汁が口の中に広がり火傷しそうになる。それを見て母が大きな声で笑った。
「レンゲに取って穴を開けると食べやすいわよ」
言いながら手本を見せてくれる。
「なら最初から教えてよ!」
怜が怒った素振りでそう言うと母は嬉しそうに微笑んだ。
どれも美味しかったが母が言うとおり特にウニの小籠包は絶品だ。食べたとたん、磯の香りが口いっぱいに広がる。どこにも臭味はなく芳醇な海の匂いだった。
夢中で食べ進めたがだんだんとお腹いっぱいになってくる。怜は身長こそとっくに母を越していたがまだ線は細い。それほど大食いではなかった。テーブルを見渡してもまだ半分近くが残っている。
「もう無理」と言うと、母がスタッフを呼んでくれた。テイクアウトしたいから包んでくれと指示を出す。
「それから、ボチボチあれもお願い」
彼女がスタッフの耳元でそっと囁く。
「かしこまりました」
スタッフがそう言って厨房のほうに消える。怜が不思議に思って尋ねようとすると、店の奥にあったグランドピアノから音が響いてくる。それは誕生日に付き物のメロディだった。
スタッフの一人が手にしたお盆を掲げて怜たちの下へ近づいてくる。お盆の上には大きなホールのケーキが載っていた。丁寧に十五本の蝋燭には火が灯っている。後ろに続くスタッフたちが「ハッピーバースデートゥーユー」と手拍子をしながら口ずさんでいた。
「お母さん……」
「十五歳のお誕生日おめでとう。来年はもう高校生なのね。今日は盛大に祝わせてちょうだい」
スタッフたちの歌声が店内に響く。居合わせた客が怜に注目し、母子の姿を温かく見守っている。恥ずかしいのと嬉しいのがゴチャ混ぜになる。それは歌のラストで怜の名前が告げられた瞬間最高潮に達した。
「ハッピーバースデーディア、リョウ君」
歌い終わった瞬間、母が口をすぼめて指でケーキを差す。
怜は頭を掻きながらケーキに向かって盛大に息を吹きかけた。
蝋燭の火が一気に消える。
次の瞬間、店内は大きな拍手に包まれた。
昼の誕生日パーティを終えると怜たちはそのまま上野公園までやってきた。
昔はそのまま動物園に行くことが多かったが、さすがに中学三年になって動物園はない。母の提案もあって隣接する美術館に行くことにした。
怜自身は美術に大して興味はない。ただ嬉しそうに横を歩く母を見ているとせっかくの楽しい雰囲気を壊したくない。夏休みは始まっていたが平日の午後の館内は静かだった。冷房の効いた中は快適である。母は芸術鑑賞、怜は単に涼みながら数時間を過ごした。
そのあと夕暮れが迫るころに歩いてやってきたのは秋葉原の電気街だった。
美術館よりこっちのほうが怜には興味がある。有名な電気街はゲームやアニメのキャラクターで溢れている。どの商品も怜にはキラキラと輝いて見えた。
「今日は特別、何か好きな物買ってあげる」
「え?」
急な申し出に驚く。正直まったく期待していなかった提案だった。さっきのパーティといい、今日はやけに豪華だ。一瞬気持ちが揺れたが、さすがにそんなに甘えられない。
「いや、いいよ。今日は十分楽しかったし」
「子どもが遠慮するんじゃないの。あなた、このゲーム機欲しがってたじゃない」
そう言って母が差し出したスマートフォンには、大人気の携帯ゲーム機が映っていた。
「これがあればいつでも遊べるでしょ」
「でも……」
渋る怜の手を引っ張って、目の前のゲーム専門店に入った。
広いフロアは青白い蛍光灯の光に溢れている。展示されているゲームの数に圧倒されながら目指すフロアまで突き進んだ。
遠慮する怜を尻目に母が店員とどんどん話を進めていく。時折「色は何がいい?」や「携帯用ケースも買っとく?」などと訊かれたが、そのたびに「任せる」と答えた。
店員がいま一番流行っている『トランス・ファイター』という格闘ゲームのソフトを選んでくれる。母は「それもお願い」と言って、店員に薦められるがままに購入していった。
ゲーム店を出るとあたりはもうオレンジ色の光に包まれていた。
陽が長い時期とはいえ時計を見るともうすぐ夕方の六時半になろうとしている。怜の手には買ってもらったゲーム機が大きな紙袋に入れられて提げてある。目の前で渡すのに律儀にプレゼント包装までしてもらったのだ。
あんな豪華な食事をして、芸術鑑賞、そして最後はプレゼントまで。さすがに贅沢だったのではないか。
しかし母はずっと楽しそうだ。今も歩きながら主婦友達の噂話を喋り続けている。
ところが駅前に来ると急に静かになった。様々な路線が入っている秋葉原駅前は家路につくサラリーマンや学生でごった返している。改札前広場までやってくると二人は自然と立ち止まった。この瞬間いつも嫌な空気に包まれる。今日もそうだ。
「リョウ、それじゃあまたね」
「うん、今日はいろいろありがとう。楽しかったよ」
「私も楽しかった…… でも私と一緒のときは今日みたいにいちいち遠慮しちゃダメよ」
母はそう言って少し寂しそうに口を歪める。
「そうだね。次からはそうするよ」
怜はそう言うと、母を残して地下鉄の入口へと向かっていった。
振り向くと母はまだこっちを見て手を振っている。
怜は地下鉄、母はJRを利用するため、いつもここで別れるのだ。
名残惜しそうに手を振り続ける視線を断ち切って、怜は地下へと続く階段を降りていった。
人混みに紛れてエスカレーターに乗りホームにたどり着く。電車が来るのを待っていると、手に提げたゲーム機を思い出した。
いくら誕生日だからってこんな高い物をくれるなんて。慣れてはいたが少しばかりの罪悪感が込み上げてくる。
しかしあそこで断るわけにはいかない。彼女がそうしたくてしているのだ。
仕方ないんだ──
そう自分に言い聞かせる。
駅で別れる自分たちは、傍目からは親子に見えただろうか。離婚によって離れて暮らす実の母と息子に。
電車到着のアナウンスが流れ、怜の髪を風が揺らす。車両がスムーズに滑(すべ)り込んでくる。
そして目の前のドアが開いた瞬間、自分を納得させようとする怜の意に反して、彼女が今日一日で何度も呼んだ名前がふたたび頭の中に響いてきた。
リョウ君──
楽し気なその声を聞くたびに、怜は密かにやるせなさを感じる。それは長い年月を掛けて少しずつ怜の重荷になっていた。
怜の名前は“リョウ”ではない。”レイ”だ。
そして今日は、怜の誕生日でもなんでもない。今日が誕生日なのは六年前に亡くなったリョウなのである。生きていれば十五歳。今の怜と同じ年齢。
今日ずっと一緒に居たのはリョウの実の母親だ。
そして怜にとって彼女は親戚どころか血の繫がりさえまったくない。
一緒のときは『お母さん』と呼ぶ。”母”だと思い込む。そう取り決められているだけ。
リョウが亡くなった翌年から、月に一度一緒に過ごす、赤の他人の契約相手だった──