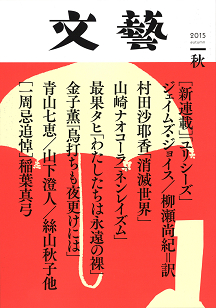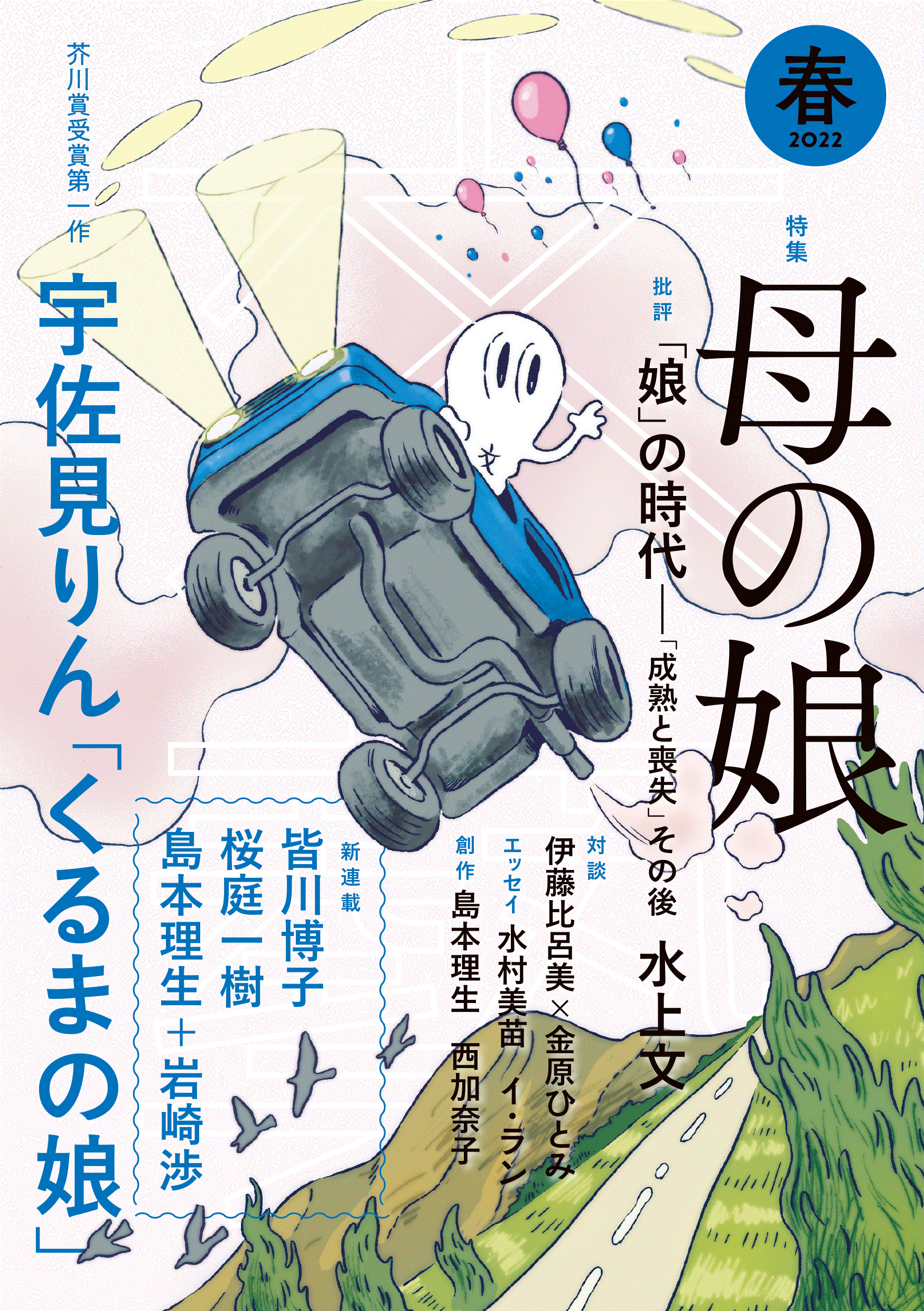単行本 - 文藝
僕はかつてこのような小説を書いてみたかったのだ。『アメリカ大陸のナチ文学』
【評者】中原昌也
2015.10.05
 『アメリカ大陸のナチ文学』
『アメリカ大陸のナチ文学』ロベルト・ボラーニョ著/野谷文昭訳
『アメリカ大陸のナチ文学』
ロベルト・ボラーニョ著
野谷文昭訳
【評者】中原昌也
Text: Nakahara Masaya
架空の事象について、ああでもないこうでもないと考えて過ごすのは、楽しい……ありもしないことについて、できるだけ、もっともらしく心がけて書くのも楽しい。ロベルト・ボラーニョの『アメリカ大陸のナチ文学』は、小説の根源的な面白さである、いい年した大人がデタラメを真剣に捏ねくり廻すという、まともな 人間であれば虚しくてやってられないはずの行為に、正面から向き合っている。
僕は決して文学プロパーではないが、ボルヘスやレムに実在しない本の書評集という体裁の作品があるのを知っている。だが、残念ながら、どれも読んではいない。自慢ではないが、ボラーニョの小説だって『通話』ですら最後まで読んでいない。
だが、「ナチ」というマジックが加わっただけで、どんな文章であっても急にオデッサ・ファイル度が上昇することによって、本書の輝きは増す。とはいえ特に個人的にはヒトラーに心酔した経験はないし、人種差別を肯定する思想もない。大量虐殺の写真にはいつも吐き気がする……けれども常に「ナチ」という言葉や、それにまつわるエピソードや美学が、我々を惹き付けてやまないのは何故だろう。南米に消えたかもしれないハインリッヒ・ミュラーや93歳までシュパンダウ刑務所で生きたルドルフ・ヘス、すでに死んでいたのにセックス・ピストルズと競演させられたマルティン・ボルマンを筆頭にアイヒマンやメンゲレなど、いかがわしい20世紀のフィクションは、ナチの残党を必要とした。小説においてはデイトン『SS-GB』、エリクソン『黒い時計の旅』、ディック『高い城の男』、スピンラッド『鉄の夢』などがワクワクさせてくれた恩を忘れてはいない。だが、ビネの『HHhH (プラハ、1942年)』が出てくるまで、いつの間にか「ナチ」という言葉がドキドキさせてくれる時代ではなくなっていたような気がした。ナチの末裔が、新宿歌舞伎町でボッタクリバーを経営していたとしてもガッカリしないが、ナチの旗を現代の日本で振る薄っぺらなナショナリストには、失笑せざるを得ない。「ナチ」に反応するなんて、ただの「中二病」でしかない……などと、本書をまったく読まないで想像だけで書いてみたが、その後百ページほど読んでみて、いままで書いたことが、的を射ていないのがわかった。「ナチ」はあくまで隠し味。
存在しない人の名前を真剣に考える、というのは、また創作の楽しさのひとつである。ありもしない人間が作者の本……そんな著作が何かの間違いで現実に出現し、古書店や図書館などで入手できて読めたとしても、書いた作家本人は永遠に生きられる筈もなく、どのような作品を書いたとしても、作家本人のそのものの1%でさえも地上には残らない。人間が生きた証などと人は容易く口にするが、その程度で何が世界に刻まれた、というのか。
結局、最後まで読んでみて、僕はかつてこのような小説を書いてみたかったのだなぁと自覚した。読んでからではもう遅い。ぜんぜん違うことをしないと。