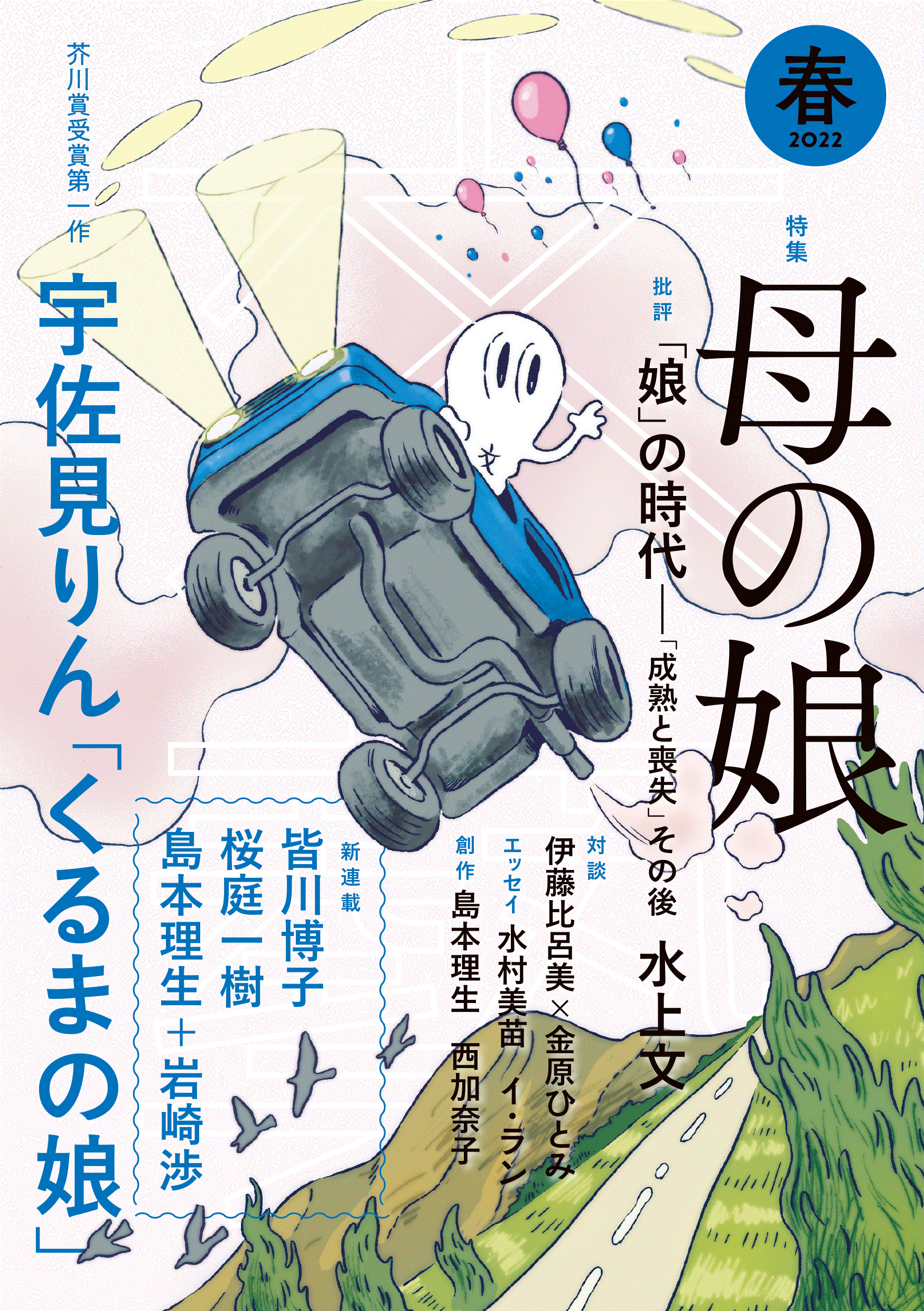単行本 - 文藝
町田康『ギケイキ 千年の流転』書評・古川日出男
【評者】古川日出男
2016.07.26
『ギケイキ 千年の流転』
町田康 著
【評者】古川日出男
「もし源平戦わば」的に
我々はすでに結末を知っている。源義経、という人物を知っていて、その末路を知っている。あらゆる歴史物語は─それこそ大河ドラマなどは─「知っているものを、どう愉しませるか?」との課題を抱える。しかし、ほとんどの“あらゆる歴史物語”において、語られている作中人物はおのれの「その末路」を知らない、ゆえにその課題は課題として生じている。つまり、解決すべきシンプルな課題として、だ。町田康の『ギケイキ』は、二段階、このシンプルさを脱臼させる。
その一、語られているのは源義経だが、これは一人称の語りで、つまり、語っているのも源義経である。
その二、彼は末路を知っている。
それはこのように記される。〈私の父もそうして無惨に死んだ。私もそのようにして死ぬ。つか、死んだ〉
これは、死んだ源義経が、“この現代にいる”という時点から、ふり返って、本人に書かれている。引用文の、私、というのが義経で、彼は語らずに、書いている。
書く、という行為は、(単に口で)語る、というよりも、語られる内容に関して自意識を向ける。その部分も引用する。
〈そのとき私はどう感じたか。相手はどんなだったか。そうしたことは書かない。後で書くかも知れないけどね〉
語る行為以上に、書く行為では“内容”に書き手の注意が向けられるのは、その“内容”が、書いた瞬間から文字として「見えるもの」になるからだ。目に映ってしまうのだから、意識する。自意識が発生する。そして、目に映っている文字に、自意識的な何事かを集中させているのは、語り手=源義経の背後にいる、作者=町田康でもある。というのは─説明を要するのかが微妙にわからないが─ギケイキと読ませるもう一つの書物が日本/日本文学にはあるからで、それは室町時代に成立したと言われている『義経記』だ。その『義経記』に、町田康の視線が注がれ、凝らされて、そこから源義経の語りが“自意識にまみれたもの”として発生しているからだ。よって、義経のエゴも猛烈に炙り出される。
と、ここまで真面目に書いたので、あとは少し飛ばす。町田さんの小説において類を絶するのは「読んでいて爆笑できる」ことで、その手の感情を操作できる小説は、結局、この時代に他に見当たらない。その意味で最高に自由なので、「いや、ほんと、面白いですね」と答えればいいわけで、ただ、この本の帯にも、またカバーを外した本の表1にも表4にも、大きな文字で「平家、マジでいってこます」と書いてあって(担当編集者の作ったコピーらしい。執拗に四カ所に書いてある。営業努力がうかがえる)、評者がただいま『平家物語』の現代語訳を進めていて、こういうのって挑発と受けとめて「受けて立つ」書評を書いたほうがいいんだろうかと悩むところもあって、というか「喧嘩を売られているのかなあ」と思わざるをえず、そこで何かをズバッと言おうと思って、この『ギケイキ』の肝はここまでに書いた批評性(作品の)と哄笑(つまり爆笑)と、速度それから迂回(これは後述)にあるのだと、そう断じる。
批評性のことを掘り下げる。『平家物語』を訳していると、「これは、ちょっと意味不明(わからない)だろう」という箇所が多々見つかる。語釈レベルではない。例えば、まさに源義経だ。彼は、平家との合戦が本格的に始まる時に突如として物語に現われ、大活躍し、兄=頼朝に逐われたらスッと物語から去る。生い立ちが書かれない。末路が書かれない。また弁慶に関してもそうだ。弁慶の活躍などほぼ“無”に等しい(物語的な層では)。
そう思ったのは二〇一〇年代に生きる評者だけではないわけで、七、八〇〇年前の人たちも思った。鎌倉幕府が存続している間は、ちょっと公然とは「思っている」とは言えなかった(し書けなかった)。なにしろ幕府を築いたのが兄=頼朝だから。しかし、これが倒れると、弟=義経って、実際のところはどうだったのか? と誰もが口にしはじめたし、書いちゃえ、と思った。『平家物語』は辟易するほどに鎌倉殿こと源頼朝の賞讃の書だから、鎌倉殿に睨まれた義経のことはスルーしたがった(し事実スルーした)。つまり、この時点で、新たな書物が必要とされた。『義経記』だ。ここにはまさに、義経の幼少期、義経の晩年の悲劇、それから弁慶の活躍、が描かれている。
しかし、『平家物語』からほんの少し時代を下った読者に「わからない」とされた要素が補塡されたとして、それを時代がずっと下った現代の読者が読んだ時、「わからない」はないのかと言えば、ある。さまざまな部分で「これは、ちょっと意味不明(わからない)だろう」との展開、あるいは風俗、あるいは価値観が多々ある。つまり、現代語訳したり翻案したりする表現者の誰もが思うのだろうが、現代からのつっこみを入れたい。しかし、常識的に言えば、入れられない。
が、語り手が、現代にいるのならば、どうか。語り手が、まさに源義経で、源平合戦の時代を八五〇年前と見て、「いやー、あの頃は……」と語れる土俵を用意していたとしたら、どうか。
つっこんでよい、ということになる。見事な構造だ。
これは「わからない」をわからせ、二つの時代(今と過去)を同期させて疾走させる。
それで、その“疾走”のことだ。走り抜ける速度のことだ。『ギケイキ』の義経は、速い。〈思えば私の後年の功績はすべて尋常でない速力に負うところが大きかったがこの時点で既に私は速かった〉と自ら言うほどに、速い。その神速は瞬間移動を可能にし、物語と物語の間の、あるいは挿話内の「隙間」を埋める。古典を語る/語り直すには、この術を見出せるかどうかが肝だ。義経は─と同時に作者の町田さんは─もちろん術を最初から見出した/仕込んだ。
とはいえ速度だけで進めば、じつは、それは古典の「古典性」から遊離する。なぜならば日本の(いわゆる)古典文学には、「ストーリーの前進・増殖よりも、細部への粘着・迂回」が本然としてあるから。この点を無視すると、古典に基づいている意味が九分九厘消える。さて「隙間」を埋めるとどうなるか? 語りはさらに細部に粘着する。迂回する。ここだ。『ギケイキ』は痛快なほど古典と同期している。