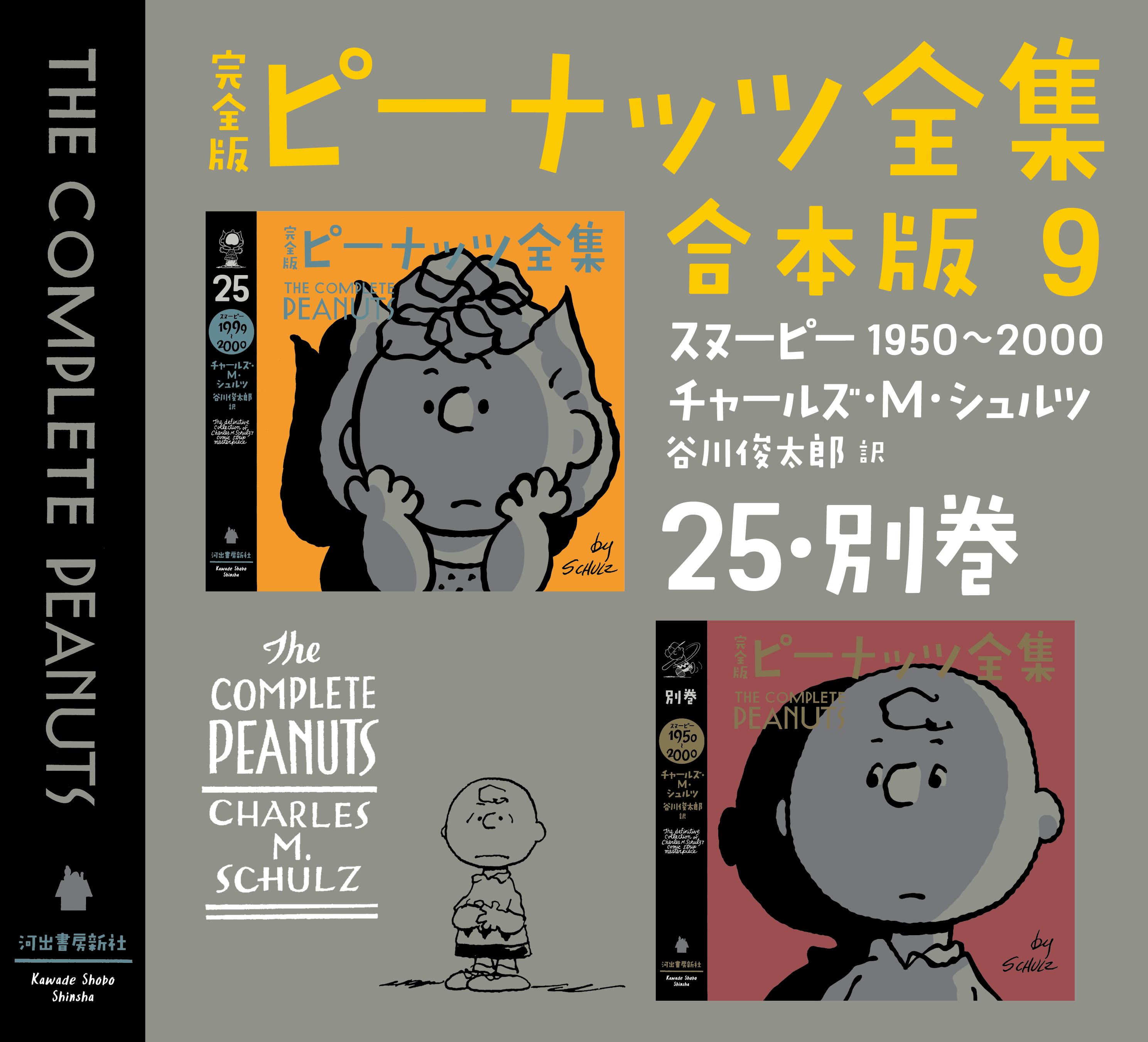単行本 - 外国文学
『青い脂』のモンスター、ソローキン。「氷三部作」完結記念、『氷』試し読み公開
ウラジーミル・ソローキン
2016.08.23
ウラジーミル・ソローキン 著
松下 隆志 訳
21世紀初頭のモスクワで世界の再生を目指すカルト集団が暗躍する。氷のハンマーで覚醒する金髪碧眼の男女たち。20世紀を生き抜いたそのカリスマ的指導者。世界的にも評価の高まる作家の代表作。
氷の大槌が肉機械を生者に変えた。
妄想と暴力で編まれたソ連/ロシアの20世紀が、
カルトの半生としていま鮮やかに蘇る。傑作!
——東浩紀
おソローキン!!
おそロシア!!
ソローキンは氷のハンマーで私の心臓を打った。
——池澤春菜
—————-【試し読み公開】—————-
第一部
兄弟ウラル
23時42分
モスクワ近郊、ムィティシチ、シリカトナヤ通り4、第2棟
〈モスクワ州テレフォントラスト〉の新倉庫。
暗青色のリンカーン・ナビゲーター。屋内に入った。止まった。ヘッドライトが照らした━━コンクリートの床、煉瓦壁、変圧器の箱、地下ケーブルのリール、ディーゼルコンプレッサー、セメント袋、瀝青の樽、壊れた担架、空の牛乳パック三箱、バール、煙草の吸い殻、ネズミの死骸、乾いた糞の塊二つ。
ゴルボヴェツは門に手を掛けた。引いた。鋼の門扉が合わさった。ガキンと。彼は閂を掛けた。ぺっと唾を吐いた。車に向かった。
ウラノフとルトマンが車から降りてきた。トランクのドアを開けた。オフロードカーの床に手錠をはめられた男が二人横たわっている。口を塞がれた状態で。
ゴルボヴェツが近づいてきた。
「どこかに明かりのスイッチがある」ウラノフは巻いた縄を取り出した。
「そんなに見えづらいの?」ルトマンは手袋を引っ張った。
「それほどでもないが」ウラノフは目を細めた。
「おめえさん、肝心なのは音が聞こえるっちゅうことだぞ!」ゴルボヴェツはにっと笑った。
「ここは音響がいい」ウラノフは疲れたように顔を拭った。「やるぞ」
彼らは捕らえた者たちを車から引きずり出した。二本の鋼柱のところへ連れていった。しっかりと縄で縛りつけ、取り囲んで立った。縛られた二人の男を黙って見つめた。
ヘッドライトの光が人々を照らしていた。五人とも金髪碧眼だった。
ウラノフ━━三十歳、長身、狭い肩、痩せた知的な顔、ベージュのレインコート。
ルトマン━━二十一歳、中背、痩躯、平らな胸、しなやか、青白い地味な顔、暗青色のジャケット、黒いレザーパンツ。
ゴルボヴェツ━━五十四歳、顎ひげ、短身、寸胴、筋張った農夫のような腕、鳩胸、粗野な顔、暗黄色の羊革のコート。
縛られた男たち。
一人目━━五十歳近く、肥満、赤ら顔、整った身なり、高価なスーツ。
二人目━━若者、貧相、鉤鼻、にきび面、黒いジーンズ、レザージャケット。
二人の口は半透明の粘着テープで塞がれている。
「こいつからやるぞ」ウラノフは太った男を顎で示した。
ルトマンは車から細長い金属製の箱を取り出した。ウラノフの前のコンクリートの床に置き、金属製の錠を外した。箱は小型冷凍庫だった。
中には氷のハンマーが二本、上下を違えて収められていた。氷の頭部は円筒形で、生皮のバンドで頭部に括りつけられた木の柄は、長く凸凹している。霜が柄を覆っている。
ウラノフは手袋をはめ、ハンマーをつかんだ。縛られた男の方へ一歩踏み出した。ゴルボヴェツは太った男のスーツの胸ボタンを外した。ネクタイを外した。シャツを引っ張った。ボタンが飛び散った。むっちりとした白い胸が露わになり、小さな乳首とチェーン付きの金の十字架が現れた。ゴルボヴェツのざらざらした指が十字架をつかみ、むしり取った。太った男は呻きだした。目配せを始めた。首を回しだした。
「応えよ!」ウラノフは大声を張り上げた。
腕を振り上げ、ハンマーで男の胸の真ん中を打った。
太った男はいっそう激しく呻きだした。
三人は息を殺し、耳を傾けた。
「応えよ!」間を置いてから、ウラノフは再び言った。そしてまた強く打った。太った男は腹の底から唸りだした。三人は息を殺した。耳を澄ました。
「応えよ!」ウラノフはさらに強く打った。
男は唸り、呻いた。体が震えていた。胸に三つの丸い血斑が浮かび上がった。
「わいにやらせとくれ」ゴルボヴェツはハンマーを取り上げた。両手にぺっぺっと唾を吐き、振りかぶった。
「応えろ!」カーンと抜ける音を立て、ハンマーが胸に激突した。氷の細片が飛び散った。
そして再び三人は息を殺した。耳を傾けた。太った男は呻き、痙攣していた。顔が青ざめた。胸は汗に濡れ、赤紫色になった。
「オルサ? オルス?」
ルトマンは自信なさげに自分の唇に触れた。
「そりゃ腹がしゃっくりしとるんじゃ」ゴルボヴェツは首を振った。
「下だ、下」ウラノフは同意の印にうなずいた。「空っぽだ」
「応えろ!」ゴルボヴェツは吠え、打った。男の体がびくっと震えた。ぐったりと縄に垂れ下がった。
彼らは間近に寄り、赤紫色の胸に耳を向けた。注意深く聴いた。
「腹が唸っとる……」ゴルボヴェツは嘆息し、振りかぶった。
「こた、えろ!」
「こた、えろ!」
「こた、えろ!」
「こた、えろ!」
殴った。殴った。殴った。ハンマーから氷の破片が飛んだ。骨にひびが入った。太った男の鼻から血が滴りだした。
「空っぽだ」ウラノフは背筋を伸ばした。
「空っぽね……」ルトマンは唇を噛んだ。
「空っぽじゃあ、くそったれ……」息を切らしながら、ゴルボヴェツはハンマーの柄にもたれ掛かった。「ふう……まったく……中身のない連中はどれだけおるんじゃ……」
「そういう巡り合わせなのよ」ルトマンはため息をついた。
ゴルボヴェツは力任せにハンマーを床に叩きつけた。氷の頭部が割れた。氷が飛び散った。裂けたバンドがぶらぶらしていた。ゴルボヴェツは柄を冷凍庫に放り投げ、もう一本のハンマーをつかんだ。ウラノフに渡した。
ウラノフは柄から霜を拭い取り、太った男の息絶えた体を陰気に睨んだ。重苦しい眼差しを二人目の男に移した。二組の青い目がかち合った。縛られた青年はもがき、唸りだした。
「おろおろしなさんな、坊や」ゴルボヴェツは頬から血飛沫を拭い取った。一方の鼻の穴を押さえた。うつむき、床に向かって洟をかんだ。コートで手を拭いた。「なあ、イレよ、十六人も叩いとるっちゅうのに、また空振りときた! こりゃいったいどこの福引きじゃ? 十六人じゃぞ! それでまた空っぽとは」
「百十六人だろうとやってやるさ」ウラノフは縛られた青年のジャケットのボタンを外した。青年はめそめそ泣きだした。骨ばった膝がガクガク震えていた。
ルトマンはウラノフを手伝った。二人は赤い字で〈WWW.FUCK.RU〉と書かれた青年の黒いTシャツの胸の部分を破いた。Tシャツの下で、大量のそばかすに覆われた白い骨ばった胸が震えていた。
ウラノフはしばし考えを巡らせ、ハンマーをゴルボヴェツに差し出した。
「ロム、あんたがやってくれ。俺はもう長いことツキがない」
「合点だ……」ゴルボヴェツは両手のひらに唾を吐いた。つかんだ。振り上げた。
「応えろ!」
氷の円筒がひゅっと風を切り、虚弱な胸骨にめり込んだ。縛られた青年の体は打たれてびくっと震えた。三人は耳を傾けた。青年の細長い鼻の穴がひくひく震えだし、そこから嗚咽が逬った。ゴルボヴェツはもじゃもじゃ頭を悲しげに振った。ゆっくりとハンマーを後ろに引いた。
「こた、えろ!」
空気を切る音。響き渡る打撃音。飛び散る氷の細片。弱まっていく呻き声。
「何か……何かが……」ルトマンは青ずんだ胸に耳を傾けていた。
「今度は上過ぎる……」ウラノフは否定的に頭を振っていた。
「こりゃなんじゃ……わからん……喉が鳴りよったか?」ゴルボヴェツは赤茶けた顎ひげをかいていた。
「ロム、もう一度頼む、だがもう少し正確にな」ウラノフが命じた。
「これ以上正確にったって……」ゴルボヴェツは振りかぶった。「こ、た、えろ!」
胸骨にひびが入った。氷がぱらぱらと床に舞った。裂けた皮膚の下から血がわずかに噴き出した。青年はぐったりと縄に垂れ下がった。青い目がぐりんと裏返った。黒いまつげがひくひく震えだした。
三人は聞き耳を立てていた。青年の胸の中で弱々しい断続的な唸り声が響いている。
「よし!」ウラノフは身震いした。
「おお、これぞ天の思し召し!」ゴルボヴェツはハンマーを投げ捨てた。
「思った通りだわ!」ルトマンは嬉しそうに笑いだした。指に息を吹きかけた。
三人は若者の胸に顔を近づけた。
「心で語れ! 心で語れ! 心で語れ!」ウラノフは大声を張り上げた。
「語れ、語れ、語れ、坊や!」ゴルボヴェツはつぶやいた。
「心で語れ、心で語れ、心で……」ルトマンは嬉しそうにささやいた。
血塗れの青ずんだ胸の中で奇妙な弱々しい音が現れては消えていった。
「名を名乗れ! 名を名乗れ! 名を名乗れ!」ウラノフは繰り返していた。
「坊や、名を、名を言え、名を!」ゴルボヴェツは青年の亜麻色の髪をなでていた。
「自らの名を、名を名乗れ、名を名乗れ、名を、名を……」ルトマンは薄いピンクの乳首にささやいていた。
彼らはぴたりと動きを止めた。微動だにせず、耳を澄ましていた。
「ウラル」とウラノフは口に出した。
「ウル……ウルァ……ウラル!」ゴルボヴェツは自分の顎ひげを引っ張った。
「ウルルルァァァル……ウラァァァル……」ルトマンは嬉しそうに瞼を閉じた。
彼らは有頂天になってはしゃぎだした。
「早く、早く!」ウラノフは木製の柄が付いた粗雑な造りのナイフを引き抜いた。
縄が切られ、テープが口から外された。青年はコンクリートの床に寝かされた。ルトマンが救急箱を持ってきた。アンモニア水を取り出し、近づけた。ウラノフは痛めつけられた胸に濡れたタオルを置いた。ゴルボヴェツは青年の背中を支え、そっと揺すった。
「さあさあ、坊や、さあさあ、おちびちゃん……」
青年は虚弱な体全体を痙攣させた。厚底のブーツが床でもぞもぞしだした。彼は目を開け、苦しげに息を吸った。放屁した。啜り泣きはじめた。
「よしよし。放くがええ、おちびちゃん、放くがええ……」ゴルボヴェツは彼を床から一気に持ち上げた。がに股の頑丈な脚で支えながら、車へと運んでいった。
ウラノフはハンマーを拾い上げた。床に叩きつけて氷を砕いた。柄を冷凍庫に放り投げた。蓋を閉め、持ち上げた。
青年は後部座席に座らされた。ゴルボヴェツとルトマンがその両脇に座り、支えた。ウラノフは門を開けた。湿った闇に車を出した。降り、門を閉じた。ハンドルを握った。広くなく、あまり平らでない道に車を発進させた。
汚れた雪が残る道の端をヘッドライトが照らしていた。光る文字盤が00時20分を表示している。
「お前の名はユーリーか?」ウラノフはバックミラーに映った青年をちらっと見た。
「ユー……リー……ラーピン……」青年は苦しげに息を吐き出した。
「覚えておけ、お前の真の名はウラルだ。お前の心臓がその名を名乗った。今日という日までお前は生きてはいなかった、ただ存在していただけだ。これからお前は生きる。ほしいものをすべて手に入れる。そして人生の大いなる目的を持つことになる。年齢は?」
「二十歳……」
「この二十年間、お前はずっと眠っていた。ようやく今、目覚めた。俺たち兄弟がお前の心臓を目覚めさせた。俺はイレ」
「わしはロム」ゴルボヴェツは青年の頬をなでていた。
「オハムよ」ルトマンはウィンクした。ラーピンの汗ばんだ額から髪の房を払った。
「これからお前をクリニックに連れていく。そこでお前は手当てを受け、正気に返ることができる」
青年は憔悴しきった目をルトマンに向けた。それから、ひげ面のゴルボヴェツに。
「でも……僕は……いつ僕は……いつ……しなきゃ……」
「質問するな」ウラノフが遮った。「お前はショックを受けた。それに慣れる必要がある」
「おめえさんはまだ弱い」ゴルボヴェツは彼の頭をなでていた。「寝て休むがええ、話はそれからじゃ」
「そしたら何もかもわかるわ。痛い?」ルトマンは濡れたタオルを円い紫斑にそっと当てた。
「い……たい……」青年は嗚咽を漏らした。目を閉じた。
「やっとタオルが役に立ったわ。毎度毎度、叩く前に濡らすの。なのにいつも空っぽ。だからすぐ水を絞らなきゃならないの!」ルトマンは笑いだした。そっとラーピンを抱いた。「ねえ……君が仲間だなんて最高よ。とっても嬉しい……」
オフロードカーが道の窪みでガタガタ揺れだした。青年はわっと叫んだ。
「もちっと丁寧にな……飛ばすでない……」ゴルボヴェツは顎ひげをいじっていた。
「すごく痛い、ウラル?」ルトマンは満足げに新しい名を口にした。
「すごく……ぐぁああ!」若者は呻き、叫んでいた。
「大丈夫、大丈夫。もう揺れない」ウラノフはハンドルを回した。慎重に。車はヤロスラフスコエ街道に出た。曲がり、モスクワへ向かって走りだした。
「君は学生ね」ルトマンは確信をもって述べた。「モスクワ大、ジャーナリズム学部」
青年はもぐもぐと答えた。
「私も学生だったの。教育大の経済」
「こりゃどうも、お若いの……」ゴルボヴェツは微笑んだ。鼻を伸ばした。「漏らしおったな! 怖かったんじゃなあ、おちびちゃん!」
ラーピンからほのかに大便の臭いが漂っていた。
「何もおかしいことはない」ウラノフは道路に向かって目を細めた。
「私だって叩かれたときは、茶色いカッテージチーズを捻り出したものよ」ルトマンは青年の痩せた顔を間近で見つめた。「それに、上手いことお湯も混ぜてやったの、こっそりとね。でも君は……」彼女は彼の股に触れた。「前は乾いてる。君、アルメニア人じゃない?」
青年は首を振った。
「カフカスの血は混ざってる?」彼女はラーピンの鉤鼻に指を這わせた。
彼は再び首を振った。その顔はひどく青ざめ、汗に塗れていた。
「バルト海沿岸地域の血は━━ない? 君の鼻ってきれい」
「しつこいぞ、じゃじゃ馬娘、こやつは今鼻どころでねえんだ」ゴルボヴェツはぶつくさ言った。
「オハム、クリニックに電話しろ」ウラノフが命じた。
ルトマンは携帯電話を取り出し、番号を押した。
「私たちよ。兄弟が一人いるの。二十歳。ええ。ええ。どのくらいかかるかって? ええと……」
「二十五分」ウラノフが教えた。
「三十分以内に。ええ」
彼女は携帯を仕舞った。
ラーピンは彼女の肩に頭を預けた。目を閉じた。気を失った。
クリニックに到着した。
ノヴォルジニェツキー横丁7。
守衛所で止まった。ウラノフは通行証を見せ、三階建ての建物に乗りつけた。ガラス扉の向こうに青い白衣を着た逞しい看護員が二人立っていた。
ウラノフは車のドアを開けた。看護員たちがストレッチャーを押しながら駆け寄ってきた。ラーピンを車から運び出した。彼は気がつき、力なく叫んだ。ストレッチャーに寝かされ、バンドで括りつけられた。クリニックの扉から運び込まれた。
ルトマンとゴルボヴェツは車の傍らに残った。ウラノフはストレッチャーの後についていった。
診察室で一人の男が彼らを待っていた。医者━━小太り、猫背、白髪交じりの濃い髪、金縁眼鏡、几帳面に刈り込まれた顎ひげ、青い白衣。
彼は壁際に立ち、煙草を吸っていた。灰皿を手にしながら。
看護員たちが彼のもとへストレッチャーを運んできた。
「いつも通りかね?」医者は訊ねた。
「ああ」ウラノフは彼の顎ひげを見た。
「複雑な怪我か?」
「どうも、胸の骨にひびが入ったみたいだ」
「どのくらい経つ?」医者はラーピンの胸からタオルを外した。
「だいたい……四十分ほど前」
女が駆け込んできた。助手━━中背、栗色の髪、頬骨の出た真面目そうな顔。
「失礼します、セミョーン・イリイチ」
「では……」医者は吸いさしの煙草の火をもみ消し、灰皿を窓台に置いた。ラーピンの上に屈み込んだ。すみれ色に腫れ上がった胸骨に触れた。「まずは歌にあるように、〈私たちのカクテルは霧の中で輝く〉といこう。次にレントゲン。それから私のところへ」
彼は急に振り返ると、扉の方へ歩きだした。
「俺は必要か?」ウラノフは訊ねた。
「必要ない。明朝来たまえ」医者は出ていった。
助手は注射器の封を切った。針を取りつけた。アンプルを二つ折り、その中身を注射器で吸った。
ウラノフはラーピンの頬をなでた。青年は目を開けた。頭をもたげた。辺りを見回し、咳き込んだ。ストレッチャーから降りようとしてもがいた。
看護員たちが彼に飛びかかった。
「やめろぉぉぉ! やめろぉぉぉ! やめろぉぉぉ‼」彼は掠れた声で叫びだした。
彼はストレッチャーに押さえつけられた。服を脱がされた。出したての大便が臭った。ウラノフは息を吐き出した。
ラーピンは掠れた声で泣き叫んでいた。