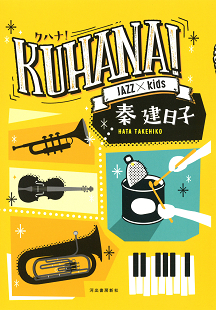単行本 - 日本文学
秦建日子『And so this is Xmas』試し読み 第1回
秦建日子
2016.11.17
篠原涼子さん主演でドラマ・映画が大ヒットした「アンフェア」シリーズの原作者であり、最近ではドラマ「そして、誰もいなくなった」などの脚本も手掛ける秦建日子さんの最新小説『And so this is Xmas』が間もなく発売になります。
本日より4回に分けて試し読みを公開しますので、ぜひお読みください。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
秦建日子『And so this is Xmas』試し読み 第1回
プロローグ
記録として、今日、私の身に起きた出来事を記します。
今日とは、二〇一六年の十二月二十二日のことです。木曜日です。
今日も私は、いつもと変わらない朝を迎えました。いつもと同じ午前七時三十分に起き、リビングのカーテンを開けて陽の光を部屋に入れ、洗面所で顔を洗い歯を磨きました。それからキッチンでホットコーヒーとトーストを用意し、テレビの情報番組を眺めながら朝食を摂りました。
「もうすぐクリスマスですね。大事な人へのプレゼント、きちんと考えてますか?」
そんなことをアナウンサーが言うので、
(そうだ、今日は夫のためにクリスマスプレゼントを買いに行こう)
と思い立ちました。
それが、最初の間違いでした。
JRの山手線に乗り、恵比寿駅に向かいました。買い物の場所はどこでもよかったのですが、新宿や渋谷は人が多過ぎるし百貨店も大き過ぎて疲れるので、そこよりはこぢんまりした恵比寿三越くらいが、ひとりで買い物に行くにはちょうどいいかなと思いました。そこで私は、暖かそうなグレーのカシミアのマフラーを買いました。調べていただければ、私のこのメモが本当だとわかると思います。店員さんは、背が高く黒縁のメガネをかけた若い男性でした。
その後、せっかく恵比寿まで来たのだから、お茶くらいしていこうと思い立ちました。三越を出ると、目の前の広場の中に、カフェコーナーが併設されているパン屋さんがあるのが目に入りました。そこで、その店に入り、たまごサンドとホットコーヒーを買いました。これも調べていただけたら本当のことだとわかるはずです。カフェコーナーはかなり混んでいたけれど、ガラス窓の向こうに見えた外のベンチには誰も座っていませんでした。窮屈な店内よりも、日向ぼっこのつもりであのベンチで食べて帰ろう。私はそう思いました。今日は天気が良く、肌寒さはほとんど感じなかったからです。
その選択も、間違いでした。
ベンチに腰を掛け、持っていた巾着バッグを隣に置き、買ったばかりのたまごサンドを食べました。ガーデンプレイスの中央には、バカラの巨大なツリーが飾られていて、その周りで若いカップルやベビーカーを押している親子連れが笑顔で写真を撮っていました。それがなんだか微笑ましくて、自分もこのサンドイッチを食べ終わったら、あのツリーの前で写真を一枚撮ってから帰ろう、そんなことを考えていたら、私の目の前に、誰かがすっと立ちました。
男の人でした。
他のベンチも全部空いているのに、なぜか私の前にその男の人は立ちました。
私は、不審に思いつつ、隣に置いていたバッグを膝に乗せ直しました。
彼は座りませんでした。その代わりに、
「おばさん。落ち着いて聞いてくださいね」
と言いました。
「実はね、このベンチの下に爆弾があるんですよ」
「?」
私は、その言葉の意味がすぐには理解できませんでした。
「実はね、このベンチの下に爆弾があるんですよ」
やけに穏やかな言い方で、それがとても気持ち悪く感じました。とにかくこの男から離れなければ。そう思って立ち上がろうとしたら、突然両肩を強い力で押さえられました。
「だめですよ。あなたが立ったら、爆発してしまいます」
「は? あなた、何なんですか?」
意味がわからず、その男に強い口調で尋ねました。
男は黒いニット帽を深く被っていて、表情はあまりわかりませんでした。黒いダウンジャケットにジーンズ。確か、濃紺のスニーカーを履いていたと思いますが、靴までは自信がありません。
男は、口に人差し指を立て「しーっ」と言いました。それから、
「あなたが座っているベンチの下に、僕は爆弾を仕掛けました。三十キロ以上の負荷がかかると爆発待機状態になり、それが三十キロ未満のレベルに戻ると爆発するんです」
「……あなた、何を言っているの?」
「あなたが今どういう状況下にあるか、きちんと説明しているんです」
「説明って……」
「あなたはこのベンチに座ってしまった。このまま立ち上がれば爆発に巻き込まれて死んでしまいます」
「バカなことを言わないで!」
「すみません。でも事実なので。まだ死にたくはないのなら、これから僕の言うことを聞いて、その通りに行動してください」
「!」
「死」という言葉を出された瞬間、体がすくみました。悪質な冗談に違いない……理性ではそう思っていても、もう体が動かないのです。
「このままここに座っていてください。あと少ししたら、人が来ます。『ニュース・ドクター』という番組のスタッフです。知っていますか? KXテレビで月曜から金曜までやっている人気情報番組です。そこのスタッフが来ます。何人来るかは知らないけれど」
「……」
「彼らが来たら、まず彼らの一人をあなたの横に座らせましょう。そうすればあなたは立ち上がることができる。そして、今僕がしたのと同じ説明を彼らにしてあげてください。その人たちが、あっさり爆発で死んでしまわないように」
「……」
「ここまでは、ご理解いただけましたか?」
「……」
男はやけに丁寧な口調で訊いてきました。私は、恐怖で声が出ませんでした。それで、とにかく二度、首を縦に振りました。男はそれを見ると、満足げに口元に笑みを浮かべました。そして、
「全ての説明が終わったら、あなたから彼らに、僕の言葉を伝言してください」
そして、男は私の耳元に顔を近づけ、そっと囁きました。
「これは、戦争です」
第一章
1
六本木。夜。
高層ファッションビルの二十四階。店内をぐるりと囲む巨大な強化ガラスの窓から、東京タワーや汐留の再開発地区をフィーチャーした夜景が一面に広がっているのが見える。
ビストロ「KIRAKU」。
その日、朝比奈仁は、店のキッチンでガーリックライスを炒めていた。
と、グランシェフが隣に来て、彼にそっと耳打ちをした。
「ホールが全然回ってないんだ。こいつは俺がやっとくから、おまえ、今だけレジを頼む」
「わかりました」
今日、クリーニングから返ってきたばかりの真っ白なエプロンで両手を拭く。それからキッチンを出て、ホールを横切ると店の出入口前にあるレジカウンターへと向かった。
レジの前には、既に、客が待っていた。
大柄で、筋肉質な、西洋人だった。
Tシャツの上からでも明確にわかるほど隆起した大胸筋。日焼けした丸太のような腕。腹筋はさすがに見えないが、きっとシックスパックに割れているだろう。髪は薄茶色で短くカットされていて、意識して鍛えられたであろう太い首に、マットシルバーのネックレスがかけられている。
軍人だな……
一目でそうわかった。
「たいへんお待たせいたしました」
仁は、レジに入り、伝票を見る。
「二万八千円になります」
が、男は動かなかった。財布を出しもせず、ただ、仁の前に立っている。
「?」
仁は、顔を上げて男を見た。男はじっと仁を見ていた。当然、目が合った。目が合った瞬間に、仁は全てを理解した。バレている。相手は既に自分の秘密に気がついている。
「今日は、とてもLuckyな夜だ。TOKYOで、こんな出会いがあるなんて」
男は、流暢な日本語で言った。そして、
「あんた。それで隠しているつもりなら甘いぜ。俺にはすぐにわかったよ」
と言って、ニヤリと笑った。
仁は動けずにいた。何も言わず、ただ混乱していた。と男は、レジ横のスペースに置かれていた店のカードを一枚取り、カウンターに転がっていた安いボールペンで電話番号を書きつけた。そしてそれを、仁のエプロンのポケットに乱暴に突っ込んだ。
「店が終わったら電話をくれよナ」
「……」
「くれなかったら、俺はまたこの店に来る。でも、おまえはそれは困るんだろう?」
☆
銀座。夜。
その日、印南綾乃は、中央通りにある、とある多国籍料理店でIT関係の男たちとの合コンに参加していた。合コンという形の飲み会はあまり得意ではなかったが、友人の高梨真奈美に強引に連れて来られ、五対五の長方形のテーブルの一番端の席に座らされていた。男性のうち、一人だけ大きく遅刻していて、そのせいで綾乃の前の席はずっと空席だった。綾乃は手酌でビールを飲み、料理を遠慮なくつまみ、お腹いっぱいになったら先に帰ろうと思っていた。男たちの話は退屈だったし、積極的に彼氏をほしいとも思っていなかった。彼氏なしのクリスマスでも、それはそれでいいじゃないか。
合コン開始から一時間。そろそろ帰るタイミングかと椅子の下の鞄に手を伸ばした時、大遅刻の五人目の男が来た。ガリガリのひょろっとした体。真っ白な肌に鋭い目。他の男性は全員スーツなのに対し、彼はヨレヨレの白のロングTシャツに、油ジミが付いたままのデニム、そして砂埃がやけに目立つスニーカーといういでたちだった。
「遅くなりました。須永です」
須永基樹。この男が本日の合コンの目玉商品だからね、と真奈美はここに来る前に何度も言っていた。先月に発売された週刊誌「have ones’ day」の表紙になった男だ。この週刊誌の表紙になるのは、各界を代表する若き有名人。そのくらいは、綾乃も知っている。須永基樹は、綾乃と同じ三十歳。スマホのアプリ開発の会社を自ら経営し、個人資産は十億円を軽く超えているという噂だ。
須永は、ストンと、綾乃の前の席に座った。
他に見るべきものもないので、綾乃は須永を観察していた。金持ちには見えないが、頭は良さそうに見えた。整った可愛い顔をしているが、性格は冷たそうだ。根拠はないけれど。
幹事役の男子が、須永が週刊誌の表紙になったのを自分のことのように自慢し始めた。
「すげえよな。雑誌の表紙とか、俺には百年頑張っても無理!」
両手を振り、大げさに言った。
「いいことばかりじゃないよ」
須永はつまらなそうな顔で答えた。
「そう? 有名になるって気持ちいいだろ?」
「そうでもない。まず、よくわからないメールが大量に届く。理不尽に褒められたり、理不尽にけなされたりする。どっちにしろ意味がわからない。あと、話した記憶もない同級生とかから連絡が来る。どこそこのパーティで会ったとか、顔も覚えてないようなやつからも連絡が来る。でも、そういうことがストレスだと言うと、なぜか俺の方が変わり者みたいに言われることが多いんだ。あるいは贅沢病だよ、とかね」
なるほど。そういうものなのか。
「で、そういう目に遭うと、俺はスティーヴン・キングが言った言葉を思い出してアンガーマネジメントに努めてきた。『ウンコ投げ競争の優勝者は、手が一番汚れていない人間だ』。他人に悪意を投げつけるより、そんな無意味なことで手を汚さないのが人間の品格のはずだってね。だから俺は、最近ではそういうストレスをポジティブな思考に転換するきっかけにしようと考えることにした。例えば、俺が正常で向こうが異常なのか、それとも向こうが正常で俺が異常なのか。そこのところを数式でロジカルに計算する方法がないだろうかって」
「は? なんだそれ」
「数式にできればいろいろ応用が可能で世の中の役にも立つと思うんだ。例えば、たまたま、今、同じマンションに挙動不審なやつが住んでるんだけど……」
「挙動不審?」
「そう。でも、何がどう不審なのかって、そういうのは説明が難しいじゃないか。第六感ってやつだからね。管理会社に何か言うにしても警察に何か言うにしても、具体的な説明ができないと困る。でも数式でロジカルに計算できるなら、そういうストレスもなくなる。彼は数値27だから正常とか、彼は数値65だからやや危険とかね」
それからしばらく、須永は、数学的な話を淡々と続けた。綾乃には、その内容の大半はわからなかったが、須永という男がかなりユニークな人間であることは理解できた。そこで合コンから先に抜けるのはやめ、とりあえず一次会の終わりまでは彼の話を聞いていようと考え直した。
十分くらい経っただろうか。須永のスマホがメールの着信を告げた。彼は不機嫌そうにちらっと画面を確認すると、
「……悪い。急用」
と会話を切った。須永は席を立った。そして、店にはもう戻ってこなかった。
☆
赤坂。昼。
赤坂の駅から歩いて二分。四十階建てのKXテレビの本社ビル。その豪奢なビルの三十一階の一番奥に、来栖公太がバイトとして働いている情報番組『ニュース・ドクター』のスタッフルームはある。ステンレスのグレーのデスクが向かい合わせに六つ。それぞれのデスクの上には書類や取材資料などが山積みになっていて、デスクの向かい側の相手の顔を見ることはほぼできない。大学四年生の来栖公太は、ここで半年前から、弁当の手配、車の運転、スタッフルームの掃除、お茶出し、現場取材のアシスタント、インサートするテロップ原稿の下書きなどなど、雑用係として忙しく働いていた。目標は、ここで局員の誰かに気に入られ「KXの契約社員にならないか」と声を掛けられること。既に、正規の就職活動は全敗が確定しているので、公太は精神的にかなり追い詰められていた。
その日、公太はスタッフルームの隅で、視聴者から番組に寄せられた声をせっせとファイルにまとめていた。昨日放送した「東京はテロの標的になるのか⁉」という特集。人気若手議員の不倫会見が延期になり、急遽差し替えられた穴埋め企画だ。
司会者が何度も訊く。
「日本って安全なんですか? 安心していていいんでしょうか?」
ゲストの政治家が何度も言う。
「危機管理には万全を期しています」「他国と比較した場合、日本は極めて安全だとデータが実証しています」
目新しい情報は何もない。今の首相になってから、日本人の立ち位置は明確になった。
テロ組織から見た場合、日本人は敵。いつでもテロや誘拐の標的。
ただ、日本という国は紛争地域から遠く離れているので、国内にいる限りは多分安全。
すると、「バイト! ちょっと来い!」という声がいきなり飛んできた。番組の総合演出家で、プロデューサーも兼務している正社員の木田康夫が、遠くから中指を天井に向けて突き立て、その中指だけでおいでおいでをしている。
(相変わらず下品な人だな)
公太はファイルを閉じて、木田のもとに走った。木田の脇には、二年先輩のAD・高沢雅也が既に待機していた。
「ついさっきな、恵比寿ガーデンプレイスに爆弾を仕掛けたという電話がうちの番組あてに入った」
「は? 爆弾?」
木田は、不機嫌そうな顔で言った。
「どうせイタズラに決まってるが、ここんとこネタ枯れだからな。おまえら下っ端二人で一応カメラ持って行ってこい。イタズラならイタズラで、憤慨する関係者の顔でも撮ってこい」
「わ、わかりました」
高沢が困惑した顔で答えた。公太もきっと同じような顔をしていたと思う。ガセなら(確実にガセだと思うが)それはもう完全に不毛な無駄足だし、万が一(というような確率すらないと思うが、もし万が一)ホンモノのタレコミなら、自分の命が危険だ。どちらにしてもロクな命令ではない。
公太と高沢は、千代田線で赤坂駅から明治神宮前駅に出て、そこからJR山手線で恵比寿駅に来た。東口を出て、スカイウォークを使って恵比寿ガーデンプレイスの入口へ。
「その電話、何だっけ。ベスポジで撮影したければ、パン屋前のベンチに来い……だっけ?」
高沢が不機嫌そうに確認してくる。
「はい。三つあるやつの真ん中です」
公太は早足で移動する高沢の背中に向かって言った。
「くだらんイタズラだな」
高沢はそう吐き捨てるように言った。
「まあ、そうですよね」
「どっかから望遠で俺たちを隠し撮りするのかもな。『ニュース・ドクター』の馬鹿スタッフ発見とかタイトル付けられて、そのうちYouTubeあたりで晒されるのかもな」
「それは嫌っすね」
公太と高沢は、そんな会話をしつつ、ガーデンプレイスの敷地に入った。平日の中途半端な時間ではあったが、センター広場はそれなりに混雑していた。右側にはビヤホール。左側にはカフェコーナー併設のベーカリー。そのベーカリーの周囲に、木製のベンチがいくつか置かれている。
「あれか?」
高沢が立ち止まり、ベンチを指差す。
「ええ、そうです」
ベンチには先客がいた。三越の紙袋と黒い巾着型のバッグを膝に乗せた四十歳前後に見える女性だ。公太は、デニムのポケットからスマホを取り出し時計を見た。十五時〇五分。爆破予告の時間まであと二十五分。
「どうせイタズラなのにな」
高沢はまたそう愚痴ると、女のいるベンチの隣のベンチに向かった。
「真ん中でなくたって別にいいだろ。あ、帰りにさ、ラーメン食って帰ろうぜ。恵比寿の駅前に美味いラーメン屋があるんだよ。ギトギト脂っこいやつ」
「いいっすね!」
高沢の誘いに公太は嬉しそうに返事をした。本当は腹は減っていないし、ラーメンはあっさり系が好きだ。が、もちろん、そのことは口に出さない。なぜなら、高沢は公太と違ってKXテレビの社員であり、長い目で見たら、絶対に彼から可愛がられている方が得だからだ。
二人は左端のベンチに座ろうと、先客の女の前を通過した。
その時だった。先客の女が突然話しかけてきた。
「このベンチに座ってください」
「え?」
「カメラを持っているってことは、『ニュース・ドクター』のスタッフの方ですよね? なら、このベンチに座ってください」
「……」
公太と高沢は顔を見合わせた。イタズラはイタズラでも、ちょっと事前の予想とは違う展開だった。公太は改めて女を見た。小柄な女だ。黒いロングコート、黒いショートブーツ。肩まで伸びた髪には毛先にかけてふんわりとパーマがかかっている。この周辺に住むちょっとしたセレブなマダムだろうか。彼女の声は、微かに震えていた。
高沢が、女の隣にドカッと座った。
「おばさん。あんたがうちに電話してきた人?」
ぞんざいな口調で言う。が、女は高沢が座った途端、跳ね飛ぶように立ち上がり、ベンチから数メートルの距離を取った。
「?」
高沢も、公太も、彼女の青ざめた表情を見て混乱した。
「私の言うことをきちんと聞いてほしいの」
女は囁くような声で、まず高沢に言った。
「あなたはもう、絶対にそこから立たないで。絶対に」
「はあ?」
「爆弾は、そのベンチの真裏に貼り付けられているの。三十キロ以上の重さでスイッチが入り、三十キロを下回ると爆発するの」
「!」
高沢は、ギョッとした顔になった。腰を浮かそうとしたが、女の言葉の切迫した雰囲気に気圧されて、そのまま立たなかった。
女は次に公太に向き直り、
「あなた、手を出して」
と言った。
「俺?」
「そう。あなた」
怪しい女に突然手を出せと言われ、公太は躊躇した。と、女は、
「早く‼」
とびっくりするような大声を出した。通行人たちが何人かこちらを見たのが視界の端に見えた。次の瞬間、女は公太に詰め寄ると強引に彼の右腕を掴んだ。ダウンジャケットの袖を素早く十センチほどまくり上げ、手錠のようにガチャンと公太の手首に黒いスポーツ時計をはめた。
「?」
公太は、時計を見る。表示は、時間のみのシンプルなデジタル時計だ。
「何ですか、これ……」
公太は、時計と女を交互に見た。女は、自分の右腕を公太に見せた。同じ、黒のデジタル時計が見えた。
「……時計も爆弾らしいの」
女は、また囁くような声に戻った。
「は?」
「時計も爆弾なの。ベンチの裏と、この時計。どちらも爆弾なの。時計も無理やり外すと爆発すると言われてる」
「言われてるって、誰からですか!」
「そんなの知らないです! 知らない人です!」
女の目に、微かに涙が見えた気がした。公太と高沢は、もう何も言えなくなっていた。
「その人は、あなたたちが来たらこう言えと言っていました」
「……」
「きちんとカメラを回すこと。テレビ局に電話をして、その映像を『ニュース・ドクター』できちんと流すように言うこと」
「……」
と、その時、携帯の着信音が鳴った。それだけで公太の心臓は痛いほど暴れた。念のため、デニムのポケットのスマホを触る。バイブが震えてはいない。自分への着信ではない。女にだった。女は、手に持っていた紙袋の中からスマホを取り出し、耳にあてた。
「はい……はい……はい、わかりました」
携帯の向こうの声は、公太には聞こえなかった。携帯を切ると、女は公太に言った。
「あなたは、私と一緒に行かなければなりません」
「え?」
「拒絶すれば、遠隔操作でその時計を爆破するそうです。体の半分がなくなります」
「!」
女は、公太のダウンジャケットを掴んだ。
「行きましょう」
「……」
拒絶もできないまま、公太は女と一緒に歩き始めた。
「おい、俺を放置する気か!」
背後で高沢が叫んでいる。
「おいっ! 公太!」
公太は、ベンチの方を振り返ると、
「よくわからないけど、従うしかないでしょうが!」
と怒鳴った。そして、
「高沢さんは、カメラ、回してください」
と付け加えた。
2
恵比寿三越の二階。「関係者以外立入禁止」と書かれたドアの奥に、六畳ほどの小さな警備室がある。その日、警備室には前田孝雄が一人で駐在していた。定年後の再就職としては、なかなかいい選択だったと思っている。窓からは、ガーデンプレイスのきらびやかな景色が見えて気分がいいし、仕事はかなり暇だ。見回りの時以外は、大好きな時代小説を持ち込んで読む。たまに万引きの現行犯で警備室直通の電話がかかってくるが、万引きは金額にかかわらずすぐに警察に通報する決まりになっているので、大した労力を使わない。
壁に掛けられた白い電波時計を見る。十五時二十六分。巡回まで四分。一時間に一度、この義務だけを果たせば、それで仕事は終わったも同然だ。前田は読みさしの小説を閉じ、小さな手鏡を見ながら「安楽綜合警備保障」のエンブレムが付いた緑の制帽を被り直した。そして、いつものように白髪まじりのもみ上げを丁寧に整える。
と、突然、警備室のドアが開いた。入ってきたのは、ダウンジャケットにジーンズ、そして茶色に髪を染めた若い男だった。
「どうされましたか?」
できるだけ丁寧な口調でそう尋ねた。
「あの……」
若い男は、不自然なほど落ち着かない様子だった。
「何かご用ですか?」
「あの……なんというか……」
そして、突然「ああ」と呻き、茶色の頭を掻きむしった。それを見て前田は、この男は少し頭がおかしいのではないかと思った。
すると、若い男の後ろから、背の低い四十代前半の女が顔を出した。男の後ろにすっぽりと隠れていたせいで最初は見えなかったのだ。その女は囁くように、
「でも、ありえない話じゃないと思うんです。今の私たちの状況から見ても」
と言って、手首にはめた黒い腕時計を前田に見せた。
まったく意味不明な二人だった。
「お客様、ここは警備室ですので、何かご不明な点がございましたら、どうぞ一階のインフォメーションの女性にお尋ねいただけませんか?」
前田はそう丁寧に言った。
「いや、そういうことじゃなくて……爆弾のことを言いに来たんです」
女が言った。
「は?」
「あと三分で、恵比寿ガーデンプレイスの中で爆弾が爆発するらしいんです!」
「は?」
「いえ、あと二分三十秒です。いえ、二十五秒です」
「は?」
「犯人は、館内放送を流せと言っています。今すぐ逃げろって」
「……」
前田は、目の前の男と女を凝視した。そして、
「これ以上、そんな話をするのなら、私は警察に電話をしますよ。そうしたら、あなたたち二人は威力業務妨害で逮捕されると思いますよ」
と告げた。
「つまらない冗談はやめて、さっさとここから出て行きなさい」
が、男も女も動かなかった。
「あなたが館内放送をするまで、私たちはここを動けないんです」
女が言った。
「あと一分と十五秒しかない!」
男が泣くような声で言った。
「ベンチよ! ベンチの裏に爆弾があるの!」
女が言った。
「あなたも窓から見てみてください! パン屋の前のベンチに男が座ってるでしょう!」
「あと一分!」
男が叫んだ。
前田は、目の前の男女に不気味な恐怖を感じ、窓際に後ずさった。ちらりと外を見る。ベーカリー前のベンチには確かに若い男が一人座っており、手元にカメラを抱えている。距離が遠いので表情までは見えないが、体が緊張で硬直しているように見えた。
爆弾?
いや、まさか。そんな、東京のど真ん中で、爆弾だなんて。
「早く館内放送を流して! お客さんを避難させるのよ!」
女が言った。
「もうダメだ。あと三十秒しかない!」
男が叫んだ。
「あと、二十秒! ちくしょう! 高沢さんが死んだらあんたのせいだからな!」
男は前田に向かって吠えた。壁の時計を見る。十五時二十九分四十五秒。彼らの言うことが真実なら、あと十五秒で爆発が起きる……
女は黙った。男は頭を抱えてしゃがみこんだ。
前田はもう一度、外を見た。
「!!!」
時計が十五時半になるのとまったく同時に、その爆発は起きた。
爆発したのは、カメラの男が座るベンチではなく、そのベンチの近くにあった青いプラスチックのゴミ箱だった。ゴミ箱は激しく回転しながら、二階にいる前田の目線より高く舞い上がった。
(つづきはこちら)