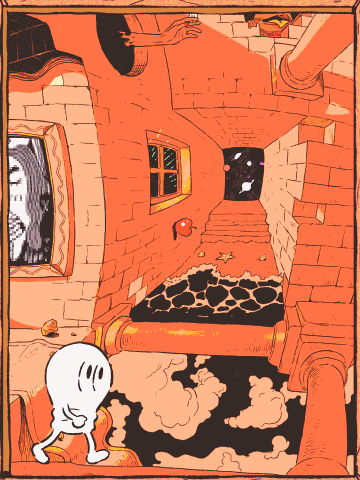単行本 - 日本文学
37年ぶりに同窓会で再会し惹かれあう、かつての恋人たち。文藝賞作家が還暦の恋を描く長編『あなたがはいというから』。
評者・北村浩子
2021.02.06
「物語」を問い続けること――谷川直子著『あなたがはいというから』
北村浩子
一流ホテルや劇場に足を運ぶ日常をFacebookに投稿し、フラワーショップから定期的に届く花で広い部屋を飾る。父の病院を継いでくれた婿養子の夫は優秀な脳外科医、ひとり息子の優斗はレジデント。何不自由なく優雅に暮らす還暦間近の柊瞳子は、大学時代のプチ同窓会にエルメスのケリーバッグを持ち、フォクシーのスーツを着て出かける。会場には元恋人で作家の和久井亮がいた。
エキセントリックな妻との波瀾万丈の生活を綴った、五十歳を過ぎての自伝的デビュー作が話題になったものの、二作目は売れずくすぶっている亮。彼と連絡を取るようになった瞳子は、自分の人生の空疎さに気付いてしまう。〈家事や社交を楽しんでいるふりをしてきた〉〈何かを消費することでしか社会とつながっていない〉〈物語なら、自分はよくあるタイプの登場人物だ〉と。
同窓会での再会が熟年女性の心を揺らす。それこそ「よくある」話を予感させる出だしから、ストーリーは劇画的要素をたっぷり盛り込んで進んでいく。息子の優斗は実は内密に「買った」子供で、彼の交際相手は血のつながった妹で、優斗の産みの親はどうやら夫の愛人で、その愛人に「宣戦布告」され、亮の妻に関係を疑われて罵声を浴びせられる。パリでの密会、ある人物の不治の病。積み重ねられるアイテムはどれも見事に「お話感」にあふれている。
メロドラマのような筋立ては、もちろん意図的なものだ。これは瞳子が「なぜ、そのような『物語』が自分の人生にやって来たのか」を問い続ける小説なのだ。問いを際立たせるために、著者はくっきりと分かりやすい「通俗」を注ぎ込んだ。瞳子を「ブランド物を苦もなく買える院長夫人」という記号的人物にしたのもそのためだ。
人の現実に訪れる出来事とフィクション。全く違うのに「物語」という言葉は両方を表現できる。瞳子の思考はその二つの間を行き来する。亮の愛読書であるカミュの『ペスト』を繰り返し読む瞳子は、熱病の蔓延する街で闘う『ペスト』の登場人物のふるまいの中に今の自分への答えがあるのではと〈目を皿のようにして〉文章を追うが、自分をとりまく人々の内面を探る手がかりを見出すことができない。失望する一方で、〈人が人を求めるように、人は物語を、物語の中の人に出会うことを求め続ける〉〈物語があるからこそ人は、他人も生きているのだということを思い出せる〉とも思う。そう、瞳子はふりかかってくる自分自身の「物語」に対峙しながら、普遍的な「物語」の周りをぐるぐると回り続けるのだ。
冒頭に置かれているのは、亮でも瞳子でもない初老の男女がオランジュリー美術館で出会い、詩の話をしながらパリの街角を歩いている場面。この男女の「物語」が、ラストで瞳子を救う。謎かけのようなその救いは、書きあぐねていた亮が果たした「作家の役目」そのものであることが、哀しく、美しい。
初出=「文藝」2021年春季号