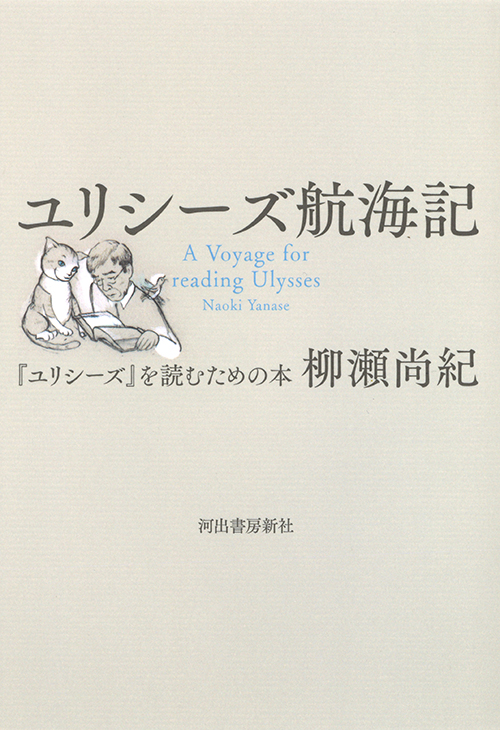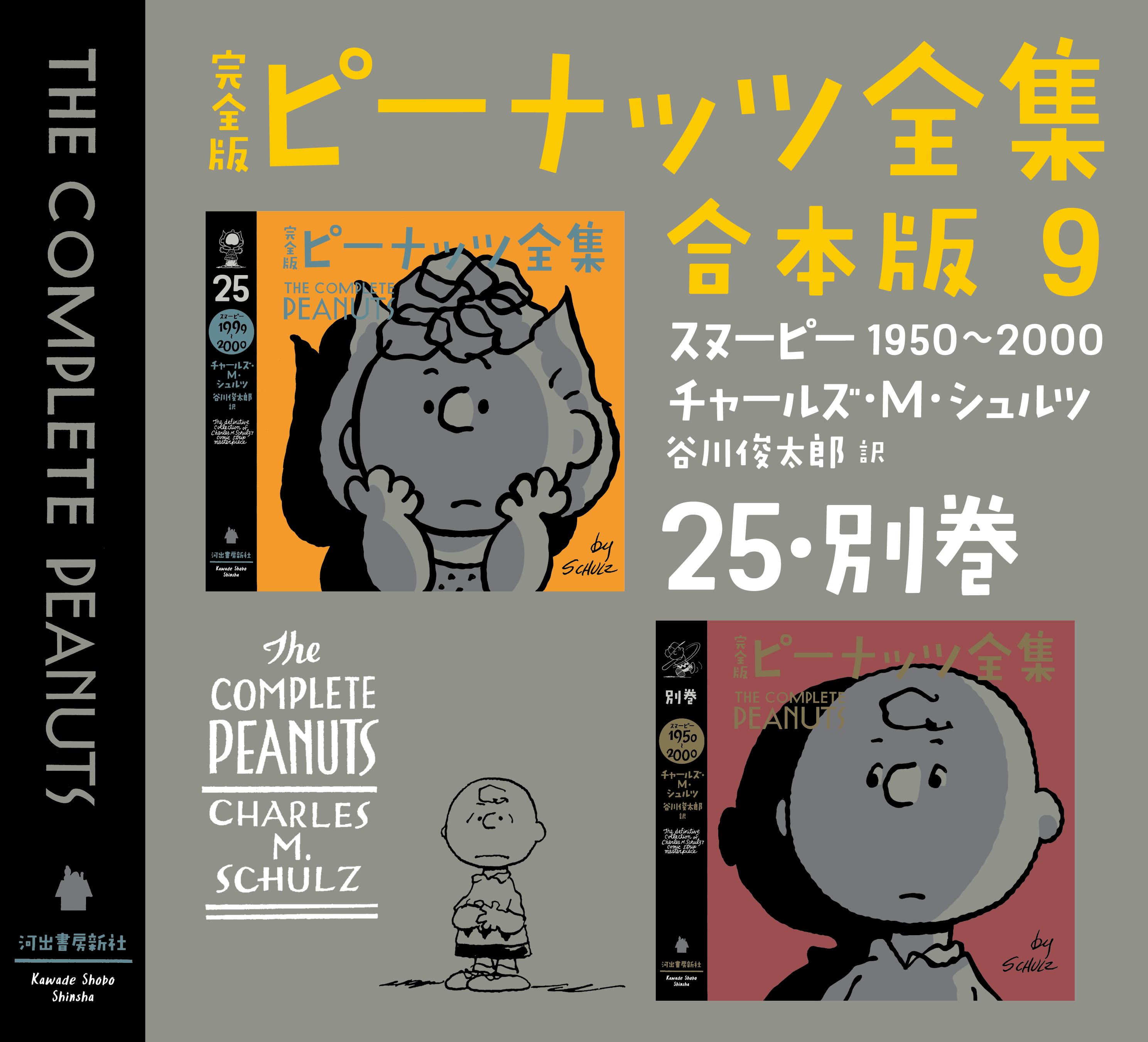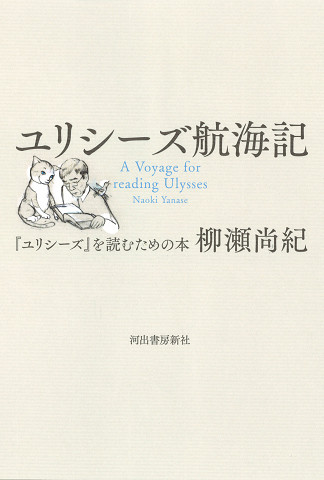
単行本 - 外国文学
天才翻訳家が遺した、『ユリシーズ航海記』(柳瀬尚紀)刊行記念 第4回 四方田犬彦によるエッセイ公開
四方田犬彦
2017.06.16
昨年7月、ジェイムズ・ジョイスやルイス・キャロルの翻訳で知られる英文学者で翻訳家の柳瀬尚紀さんが逝去されました。1993年、翻訳不可能と言われていた『フィネガンズ・ウェイク』を個人で初めて完訳して話題を集め、亡くなる直前まで、ジョイスの最高傑作『ユリシーズ』の完訳を目指して翻訳中でした。
そんな天才翻訳家が遺した『ユリシーズ』に関する文章と、『ユリシーズ1-12』に収録していない試訳を集成した『ユリシーズ航海記 『ユリシーズ』を読むための本』(柳瀬尚紀)が本日刊行となりました。第12章の発犬伝をはじめ、ジョイスが仕掛けた謎を精緻に読み解き、正解の翻訳を追求した航跡を一冊に集めた、まさに航海記です。
本書の刊行を記念し、「文藝2017年春季号」に掲載された特集「追悼 柳瀬尚紀」から、柳瀬さんの追悼文と、柳瀬訳の魅力に迫るエッセイを毎日連続で公開いたします。
柴田元幸をして「名訳者と言える人は何人もいるが、化け物と呼べるのは柳瀬尚紀だけだ。」と言わしめる柳瀬尚紀ワールド。
まだ未体験の方もこれを機にぜひ、豊穣なる言葉の世界に溺れてみてください。
(8日連続更新予定)
********************************************
四方田犬彦
In his Penisula War 柳瀬尚紀の訳業
1977年も終わろうとするころ、わたしは友人たちと語り合って、映画批評をめぐる同人誌『シネマグラ』を創刊した。わたしはそのとき、初めてグラウチョ・マルクスについて書いた。
刷り上がったばかりの同人誌とは新しい名刺だ。どこに送ろうか、誰に読んでもらおうかと、仲間どうしで相談となる。わたしたちはまず畏敬していた松本俊夫に送った。それから巖谷國士と川本三郎にも。松本俊夫はただちに「きみたちに会いたい」といい、定期購読料を払い込んできた。巖谷國士は、「あなたはいったい何者ですか?」と、葉書に書いてきた。川本三郎は「読者のお便り」コーナーに投書してきた。
だがわたしには、映画関係者とは別に、自分のマルクス論を読んでもらいたい人物がいた。柳瀬尚紀である。そこで「『シリヴィーとブルーノ』の翻訳者に敬意をこめて」と添え書きして、雑誌を送った。しばらくして返事が来た。
「いい仲間をもって羨ましいですね。ぼくはしばらくin his Penisula warです。」
Peninsula なら「半島」である。ガリポリ半島から朝鮮半島まで、20世紀には世界中のいたるところの半島で戦争が起きている。だがPenisulaとは何だろう? ペニスの戦い? それとも鉛筆の戦い? 半島とペニス、鉛筆は、いずれも先端が尖っていることで似ているのだが、ひょっとして語源をともにしているのだろうか。
しばらくしてわたしは、この言葉がジョイスの『フィネガンズ・ウェイク』にあることを発見した。彼の孤立した、独りぼっちの戦い。彼の孤独に屹立したペニスの戦い。わたしがマルクスの言語遊戯と格闘していたとき、柳瀬尚紀はジョイスの独りぼっちの言語戦争の奥地に深く踏み込み、銃弾飛び交うなかで懸命にメモをとっていたのである。
それから14年の歳月が流れ、his Peninsula warはついに終わりを遂げた。『フィネガンズ・ウェイク』は美しい表紙絵に飾られて、二巻本として刊行された。そうか、ついに……訳者から美本を送られたわたしは、ジョイスの表現の中で以前から気になっていたところを、訳者がどのように訳出したのかが気になった。そこで該当頁を探し出すところから、この大部の書物の内側へそっと侵入していった。
『フィネガンズ・ウェイク』ではまず開幕してしばらくのところに、fadographという単語が出現する。いかにもテクノロジーとメディアの発展に気を配り、その形而上学的側面を見据えようとしたジョイスにふさわしい表現である。この造語はfade(色褪せる)とphotograph(写真)の結合からなり、そこには時間の移ろいのなかで色褪せ、やがては消滅してしまうであろう写真という意味合いが込められている。ベンヤミンが複製時代の芸術を扱ったエッセイのなかで「アウラ」の消滅を論じ、中原中也が「茶色い戦争ありました」と書きつけた時期に、さりげなくこうした言葉を考案してしまうのだから、ジョイスは油断ができない。柳瀬尚紀はこれを「惜日の写真」と訳した。
When they were yung and easily freudenedはどうだろうか。この一行には、いずれ雲霞のように押し掛けてくるだろう、精神分析学的な解釈者や註釈者をあらかじめ牽制しておきたいという原作者の意図が窺われる。若いころはみんな、フロイトにチョロリと騙され、嬉しそうにしていたものだけど……くらいの意味である。もちろんこの表現の背後には、誰もが知っているように、ユングとフロイトの友情と離反の物語が隠されているのだが。柳瀬訳では「若さを弓具に扶労厭わず嬉々として」となっている。
ジョイスの言語の本質である多層性、遊戯性、オノマトペ性を日本語に移植するにあたって、柳瀬はそこに日本語表記における独自の修辞法を衝突させた。いわずと知れたルビである。ルビは難解な漢字の発音を説明するばかりか、その漢字表記に批評的な解釈を施すこともできる。またさらにこのシステムを援用すれば、思いも寄らぬルビが付加することで、漢字表記の周辺において意味論的な衝突を組織することすら可能である。柳瀬はこうしたルビの両義的な機能を十二分に活用し、ジョイスの言語遊戯に拮抗させようと企てた。分析心理学の創始者に「弓具」の二字を与え、労苦の映像に結合させ、返す刀でフロイトの原義である悦びを「嬉々として」という表現で掬いあげている。この綱渡り芸人のような剽軽な身振りは、ビュトールの語を借りていうならば、まさに「猿丹蛮狗」saltimbanqueにふさわしい。
もうひとつ例を挙げよう。『フィネガンズ・ウェイク』のなかでもとりわけ美しい音楽的響きをもった一行、Tell me, tell me, tell me, elm ! はどうだろうか。第一部の終わりに出現し、楡の樹を媒介として死と再生の教義が説かれる一節である。柳瀬訳では「話して、話しておくれ、話しておくれよ、暮の楡よ! 暮れる夜よ!」となっている。音読してみると、kureという音が幾重にも響きあい、反復される語を少しずつ変化させていくことがわかる。
これは畏怖すべき訳業だ。わたしはそう思った。だが一人の英文学者が生涯の半ばにおいて、かかる高峰の登攀に成功してしまったとしたら、その後に何をすればよいのか。英語が読めるという理由だけでソンタグの小説を翻訳したり、十年一日のように、教壇に立ってワーズワースの詩を朗読したりするわけにはいかないだろう。
わたしはただちに柳瀬尚紀に会った。場所は新宿駅の駅ビルの喫茶店。彼は憔悴しきっていて、注がれたビールに口をつけるのがやっとといった感じだった。そして、何か後悔をするような口調で、ぼくはもう普通の英語の本が読めなくなったんですよといった。わたしが啞然としていると、別れしなに止めの一撃を加えてきた。寺山さんと吉増さん、それに四方田さんの名前を、翻訳のなかにこっそり縫い込めておきました。全巻を読まないと発見できない仕組みになっています。みごとに発見できたら、教えてくださいね。
モノを書く人間の墓とは、つまるところその人物が遺した書物のなかにある。柳瀬尚紀の墓は柳瀬尚紀の遺した翻訳書のなかにある。この大仕事の後も、わたしの彼への畏怖の念は変わらなかった。それは彼が未刊のうちに遺した『ガリヴァー旅行記』の翻訳にまで至っている。
そうそう、思い出した。梨花女子大学の羅英均教授が来日された折、柳瀬さんに会っていただいたことがあった。羅教授は『若き芸術家の肖像』を韓国語に翻訳し、『日帝時代、わが家は』(みすず書房)を著した人物である。あのときほど愉しかったことはなかったと、彼女は後になってわたしに語った。何しろ初めて会ったというのに話が弾んで、ジョイスのことで十時間くらい、ずっと話してたのよ。
この出会いは柳瀬さんの方でも印象深いことだったようだ。彼が晩年まで継続して思考していた日本語の問題に、それは微妙に影を落としているはずである。
ところで二人は何語で話したのだろうか? ひょっとしてフィネガン語?
(明日は高山宏さんの予定です)