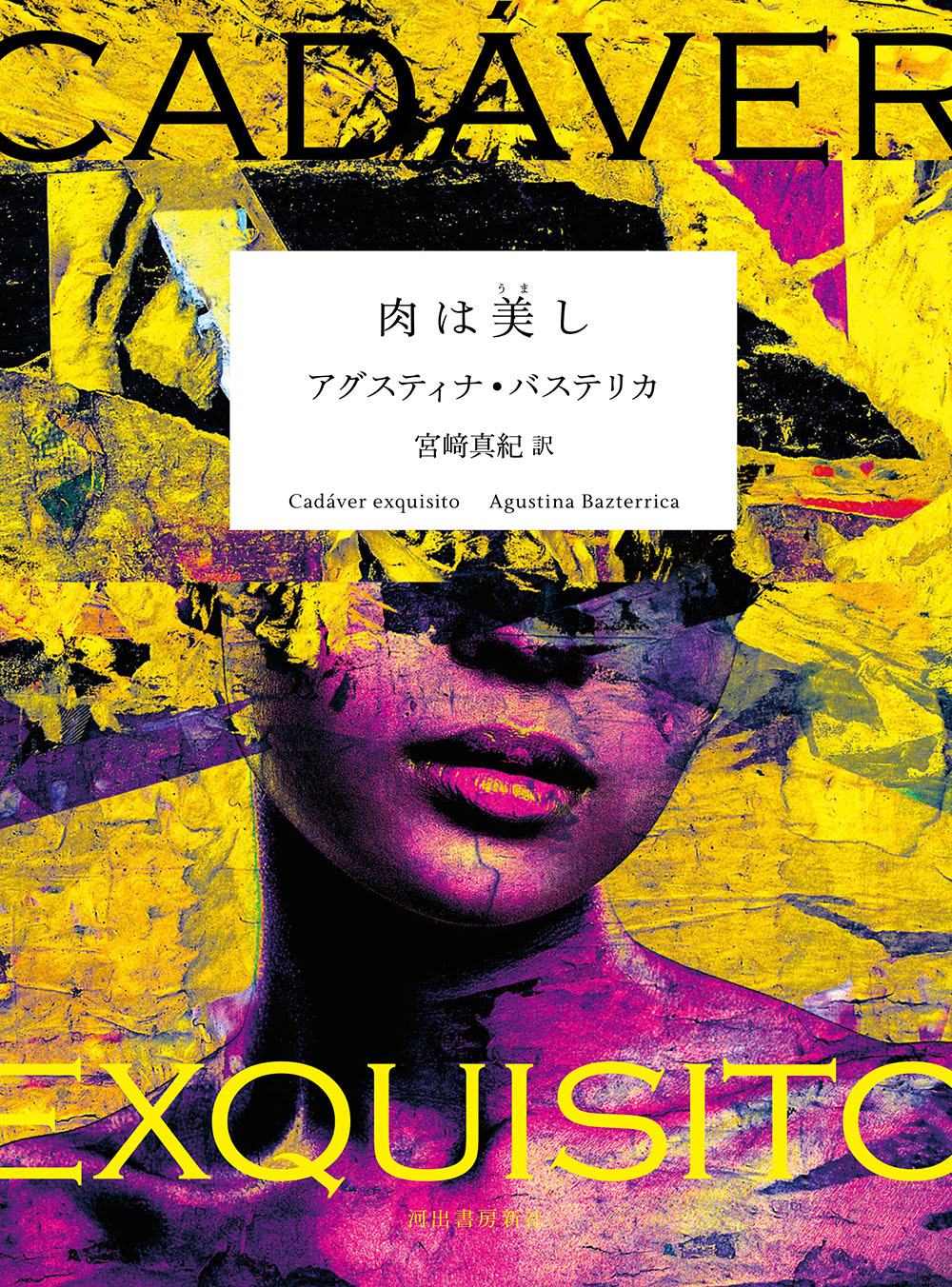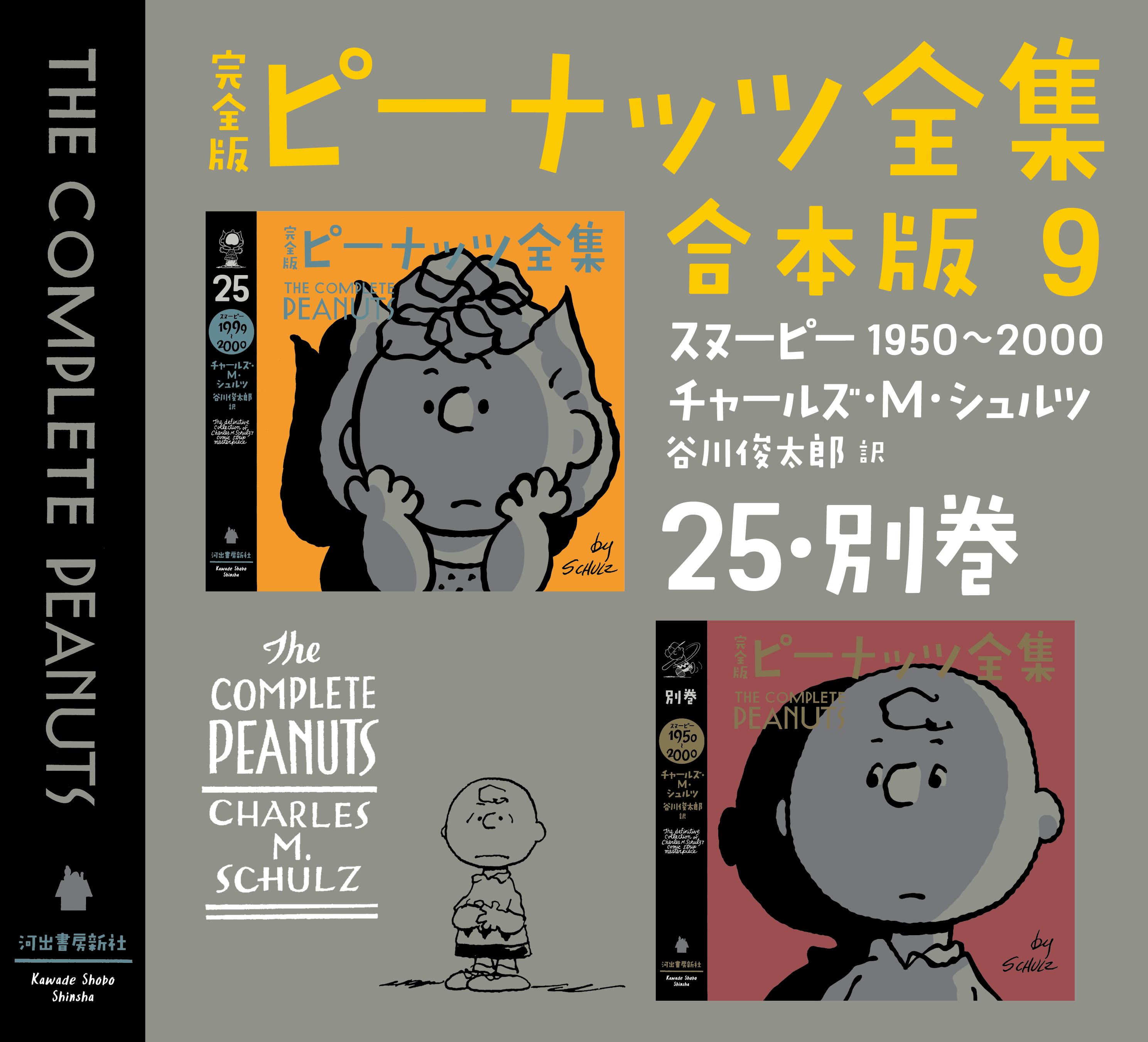単行本 - 外国文学
タヴァレスが作り出した暗黒の「王国」では、闇の向こうに垣間見える柔らかな灯はない──ゴンサロ・M・タヴァレス『エルサレム』訳者あとがき
木下眞穂
2021.05.31
『エルサレム』
ゴンサロ・M・タヴァレス 著 木下眞穂 訳
46上製 本体2,950円(税別) 272ページ
*
五月二十九日、夜明け前。
死病を患うミリアは痛みのあまり通りへ飛び出した。
時を同じくして、自殺しようと窓から身を乗り出すミリアの元恋人、
娼婦を求めさまよう精神科医の元夫、父親を探す少年と、獲物を探す元兵士。
彼らの暗い運命は、誉れ高きゲオルグ・ローゼンベルク精神病院の記憶につながっていく……。
世界約50カ国で翻訳される現代ポルトガル最重要作家による、
狂気と怒りと愚かさを残酷に描ききる圧倒的代表作。
*
────────────────────────
五月二十九日、いちばん暗いと言われる夜明け前に主人公ミリアとその他の登場人物はそれぞれの痛みを抱えながら通りをさまよっている。死病を患うミリアは、教会の扉を叩くが中に入れてもらえない。ミリアの元恋人エルンストは自殺しようとしたところに彼女から電話を受けて家を飛び出す。一時は「時の人」ともてはやされたものの、今は世間から忘れ去られているミリアの前夫、テオドールは一夜限りの相手を求め、テオドールの十二歳の息子、カース(実はミリアとエルンストの子)は家にいない父を捜して、外へ出る。そして、帰還兵のヒンネルクは銃を懐にしのばせて獲物を探している。
精神科医のテオドールは、患者として診察にきたミリアに一目ぼれして周囲の反対を押し切って結婚し、医者として働く傍ら、歴史に残る虐殺事件をつぶさに調べ「歴史の健康状態」を示すグラフの作成に没頭していた。一方で、同じく精神科医であり、のちにミリアが入院しエルンストと知り合ったゲオルグ・ローゼンベルク精神病院の院長でもあるゴンペルツは、倫理と狂気には相関関係があると信じて患者たちを厳しく統制する。患者たちは病院の外の世界を懐かしみ夢想するが、昔の自分のままでいてはそこには帰れない。これまでの自分をすべて忘れ去らないと「治癒」とはみなされないのだ。
「エルサレムよ、もしも、わたしがあなたを忘れるなら、わたしの右手はなえるがよい」とは、旧約聖書の詩編の一節で、迫害を受けて異郷に拡散したユダヤ人たちが心の拠り所であるエルサレムを謳っている。この「エルサレム」を「ゲオルグ・ローゼンベルク」に替えた句に、ミリアも、エルンストも、退院してもなおつきまとわれる。登場人物それぞれの危うい過去と現在が断片的に描かれ、次第に運命の五月二十九日に近づいていく……。
本書『エルサレム(原題Jerusalém)』は二〇〇五年にポルトガルで出版され、レール賞、ジョゼ・サラマーゴ文学賞、ポルトガル・テレコム文学賞(現オセアノス賞)とポルトガル語圏の重要な文学賞を次々に受賞し、作者、ゴンサロ・M・タヴァレスの名を一気に世に知らしめた作品である。
一九七〇年生まれのゴンサロ・M・タヴァレスが作家デビューしたのは二〇〇一年。それから二十年、たゆまず精力的に作品を発表しつづけている。「書いていないと精神のバランスが崩れてくる」そうで、まだまだこれからも作品を生み出していくだろう。では、そのタヴァレスがどういう作家かというと、彼自身が一つの宇宙の創り手のようで、ここで充分な紹介ができるか少々心もとないほどである。
タヴァレスは、自分の作品を「ノート」と呼び、それらは多岐にわたるテーマで分類されている。「王国」、「町」、「都市」、「百科事典」、「唄」、「研究」等々、「ノート」が一作しかないテーマもあれば、「町」のように十作もあるものもある。「王国」と「町」はすでに完結し、近年では、史実と童話などに人類の科学的発展を絡み合わせた奇天烈な「神話」が二作、出版されている。「町」もユニークで、十作すべてのタイトルに、カルヴィーノ、ブレヒト、ヴァレリーなどの著名な文化人の名前がついている(うちの一作「ヴァルザー氏と森」は現代企画室より二〇一九年に出版された『ポルトガル短篇小説傑作選 よみがえるルーススの声』に近藤紀子氏の訳で収録されている)。また、大航海時代のポルトガルの栄光を謳いポルトガル文学史上最高の叙事詩とされる、十六世紀の詩人ルイス・デ・カモンイスの『ウズ・ルジアダス』(池上岑夫訳、白水社、二〇〇〇年)を基盤にした「叙事詩」の『インドへの旅(A Viagem à Índia)』(二〇一〇年)は各方面から絶賛を受けた。ゴンサロ・M・タヴァレスの作品は五十か国以上で翻訳、出版されており、本作をはじめとするさまざまな著作についての考察や論文が国内外で無数に執筆され、名実ともに二十一世紀のポルトガル文学を担う作家の一人である。
タヴァレスは作家デビューする前の二十代から三十代にかけて大量の作品を執筆したと言う(三十歳になるまで発表はしないと決めていた)。最初に手書きでノートに書きつけたそれらの作品は、その後、長い時間寝かせてから推敲に入る。推敲の時にはすでに作品から距離があるので、作家自身が客観的な視点を持つ最初の読者になる。『エルサレム』は彼の最初の長篇群である「王国」四部作の第三作にあたる。出版と同じく『ある男、クラウス・クルンプ(Um Homem : Klaus Klump)』(二〇〇三年)、『ヨーゼフ・ヴァルザーの機械(A Máquina de Joseph Walser)』(二〇〇四年)、『エルサレム』、『技巧の時代に祈りを学ぶということ(Aprender a Rezar na Era da Técinca)』(二〇〇七年)の順で執筆したのだが、正確にいつのことだったかは記憶にないそうだ。二十世紀の終わりだったか、二十一世紀の初めだったか。ただ、世紀の移り変わりの頃だったということは覚えているし、『エルサレム』を書き終わったときには疲労困憊していたと言う。
痛みと死の恐怖に苛まれるミリアが冒頭で教会に入れてもらっていたら『エルサレム』は生まれなかった。ほかの人物たちも、危険な夜の通りに出ていくことはなく、それぞれが出会うこともなかったとタヴァレスは断言する。悪のメカニズムの解析を試みたという「王国」の四作品は、そのメカニズムを構築する部品なのだ。四つの物語はそれぞれ独立していながらも、ともに東欧あるいは中欧を想起させる町を舞台にし、戦争がある。この「王国」では、戦争と平時、悪と善、支配と服従、強者と弱者の境界はぼやけてにじみ、互いを侵食しあっている。この戦争では何を争っているのか、どの作品を読んでもわからない。人間と物体との境も同じくどこか曖昧だ。人と人との交わりにおける情愛や悲哀の描写は平易なのに、人と物体の関係性の描き方は濃密で温度が高い。第二作の主人公、ヨーゼフ・ヴァルザーは機械の部品に執着し、本作のヒンネルクは銃の匂いで興奮し、ミリアは男を触るがごとき手つきで物体に触れる。四作の登場人物も数人が繋がっており、たとえば、通りすがりにミリアとエルンストに手を貸すヒンネルクは、同じように夜の通りでヨーゼフ・ヴァルザーにも忌むべき所業に手を貸している。
「王国」に蔓延する暴力は、正体が明確ではないからこそ苛烈で、読む者の記憶にしつこく残る、それがタヴァレスの狙いなのだ。忘れないことだ、と彼は言う。われわれの前に立ちはだかり、後をつけてくる暴力のことを忘れないことだ、と。タヴァレスが作り出した暗黒の「王国」では、闇の向こうに垣間見える柔らかな灯はない。その代わり、一語一語が時おり光を放っては、どこに視線を向けるべきかを教えてくれる。
自身の名を冠した文学賞を本作に授与する式でのスピーチでサラマーゴが放った「ゴンサロ・M・タヴァレスはたった三十五歳でこんなにすごい本を書くなんて、ずるいじゃないか。叩いてやりたくなる」という賛辞は非常に有名になった。だが、その際にこのノーベル文学賞作家はこうも評している。「タヴァレスが創造したこの世界は、われわれとは無関係のように見えるが、実は百年後の人類の脅威である」と。受賞から十五年、サラマーゴが世を去って十年が過ぎたが、この言葉はすでに現実味を帯びてきてはいまいか。作品が発表された当時は二十世紀が終わって間もないころで、ヨーロッパを覆った全体主義とその結果として行なわれた無数の戦争や虐殺の記憶を想起して読む人が多かったかもしれない。それを未来への警鐘と予告したサラマーゴの慧眼であるが、たとえば、作中作の『ヨーロッパ02』は「過去の恐怖時代」を映していると、現代のわれわれは言い切れるだろうか。
ところで、サラマーゴはまた別の機会に、タヴァレスはノーベル文学賞を獲得するだろうとも予言している。「その時、自分はすでにこの世にいないだろうから、彼の肩を抱いて祝えないのがいかにも残念だ」と。さて、サラマーゴのこの言葉が現実となるかどうか、楽しみに見守っていきたい。
本作はCaminho 社から二〇一〇年に発刊された“Jerusalém”第九版を底本として翻訳した。作中に引用される聖書の言葉は新共同訳から引いたが、「シラの書」のみフェデリコ・バルバロの『聖書』(講談社)を参照した。ハンナ・アーレントの文章の引用もあるということで、作者にも問い合わせたのだが、出典を明確にすることはできなかったことをお断りしておく。また、このあとがきを書くにあたり、タヴァレスへのインタビュー記事(Público 二〇一二年八月四日)を参照した。
私が本作を読んだのは十年ほど前になる。一読して衝撃を受け、日本に紹介をしたいという思いを抱きつつも、この作品が持つ強大なエネルギーに自分の力量が追いつくのかという迷いと恐れがあり、一歩を踏み出せずにいた。それが、二年ほど前に河出書房新社の編集者、町田真穂さんにおそるおそる本書の話をしたことから訳出への道が開けた。翻訳作業中、つねに温かな励ましを下さった町田さんと、本書の出版を引き受けて下さった河出書房新社のみなさんに心から御礼を申し上げたい。本書の舞台となる場所は特定されていないが、作中の地名、人名の読み方については、訳者の判断でドイツ語を基準とすることにし、ドイツ語翻訳者の井口富美子さんにご助力いただいた。また、清水ユミさんは、私がポルトガル語の解釈で迷子になると快く救いの手を差し伸べて光を当てて下さった。お二人に御礼申し上げるとともに、さまざまな形で支えてくれた友人たちと家族にも感謝したい。
作者のゴンサロ・M・タヴァレスには、彼が二〇一八年に来日した際に幸運にも会うことができた。そのときにサインしてもらった本作の原書には「いつかこの本が日本語になりますように」という一言が添えてある。本書の邦訳出版の可能性を探るようにと私の背中を最初に押してくれたのはタヴァレスその人だった。今、こうして彼の希望を叶えることができたのは幸せであるが、一方で、本書はタヴァレスという広漠たる宇宙のほんの一端にすぎないのだと、もう一度、念を押しておきたい。日本の読者がさらに暗黒の「王国」をさまよい、謎多き宇宙に分け入っていかれるよう、タヴァレスの作品の邦訳が進むことを祈る。
二〇二一年早春
木下眞穂