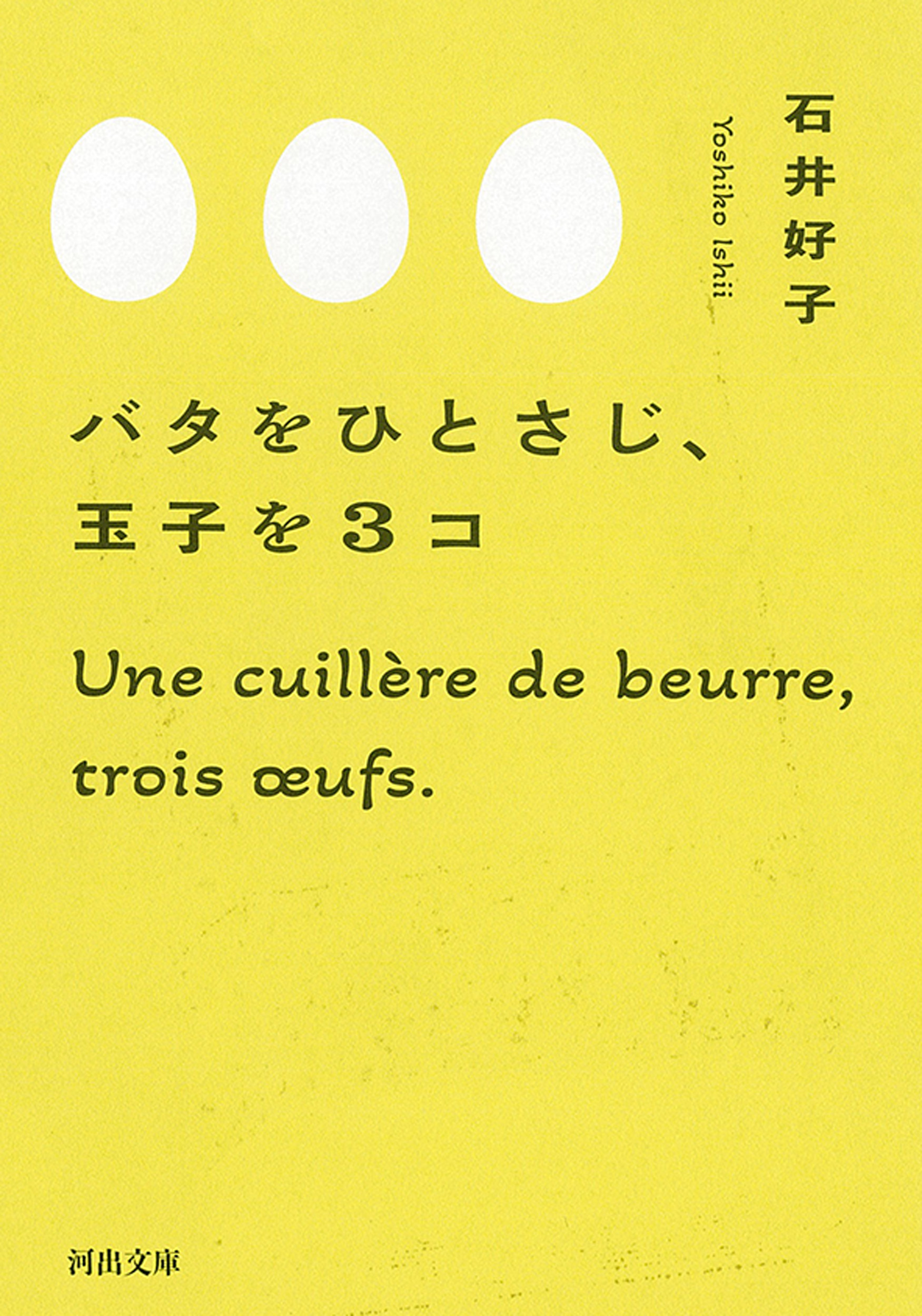単行本 - 日本文学
対立も断罪もしない新しい夫婦のありかたとは? 島本理生が読む「作家の夫と書かれる妻」──彩瀬まる著『森があふれる』書評
評者・島本理生
2019.08.20
不思議だったことがある。
たとえば道に迷ったとき、問題に突き当たったとき、目の前の相手の気持ちが分からないとき、頑ななまでに相談することを避ける男の人が多いのはなぜだろう、と。
『森があふれる』の中で、「最後まで弱いままで愛される少年漫画の主人公なんていないんだ」という台詞を読み、あの奇妙な拒絶の本音を垣間見た気がした。
編集者の瀬木口は、担当作家の埜渡の自宅で、偶然、妻の琉生が草木の種を食べて発芽してしまう場面に遭遇する。琉生は夫の浮気を疑っており、実際、埜渡はカルチャースクールの生徒と関係を持って小説にしている。また埜渡には妻の琉生をモデルにした小説で成功した過去がある。
その成功は、埜渡にある種の麻痺をもたらしている。創作を現実の女性に依存することに慣れ切った彼は瀬木口に告げる。「下手な作りものより、今の琉生の方がずっと面白くて」と。そのくせ「ああなったのも、俺への当てつけなんだよ」とも言う。一方的な主張には呆れると同時に、そんな夫と別れずに植物化した琉生に対しても疑問を覚える。
琉生は、埜渡にも浮気相手にも攻撃的な感情を向けない。まるで自分の声に、彼女自身さえも気付いていないみたいだ。広がり続ける森へと形を変えさせたものは、私は怒りや憤りではなく、むしろ善良さだと思う。
「外に出たい」という琉生に、瀬木口は「自分から、どこにでも行ける、なんでも出来る人の体を手放したくせに」と考えるが、それは誤りだ。埜渡は愛人の夕湖に「木綿子」という字を当て、琉生を「涙」に変えた。私はこの行為になにより無自覚な身勝手さを覚えた。
全く違う名にはせずに響きを残したまま別の字を当てることは、ありのままを受け入れる気はなく、でもあなたがいいから自分に都合良く変質しろと言っているようなものである。琉生はずっと前から、琉生、ではなかったし、どこへも行けなかったのだ。
そんな琉生の善良さや曖昧さに関して、ハッとさせられる場面がある。
女性編集者の白崎が、琉生に対する様々なことに「女だから」疑問を持たなかったと気付く瞬間だ。女性らしさを強いるのは、なにも男性だけではないのだ。
埜渡の新作を読んだ編集長の棚橋はこう指摘する。
「埜渡さんにはもっと自分を疑って、苦しんでもらった方がいい気がするんだけども」と。
最初、この『森があふれる』という小説は、男性の無自覚を鋭く描き出す物語だと思っていた。だけど作者はその刃を自分にも向け返す。棚橋が言ったことを守るように。
この物語がどこへ向かったのかを言葉にするのは難しい。なぜなら作者自身がそれを決めつけぬように慎重に繊細に言葉を尽くしているからだ。
フェミニズムが叫ばれながら、それによって対立したり断罪し合うことが加速する時代に、そのどちらでもない第三の光を懸命に模索する姿勢が美しい一冊だった。