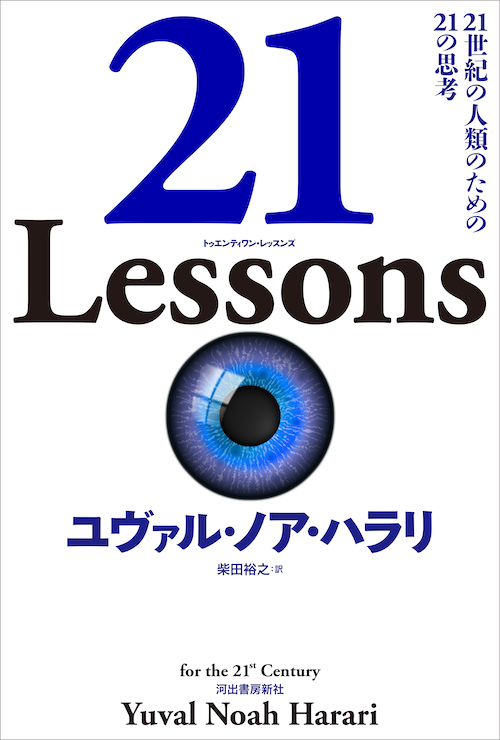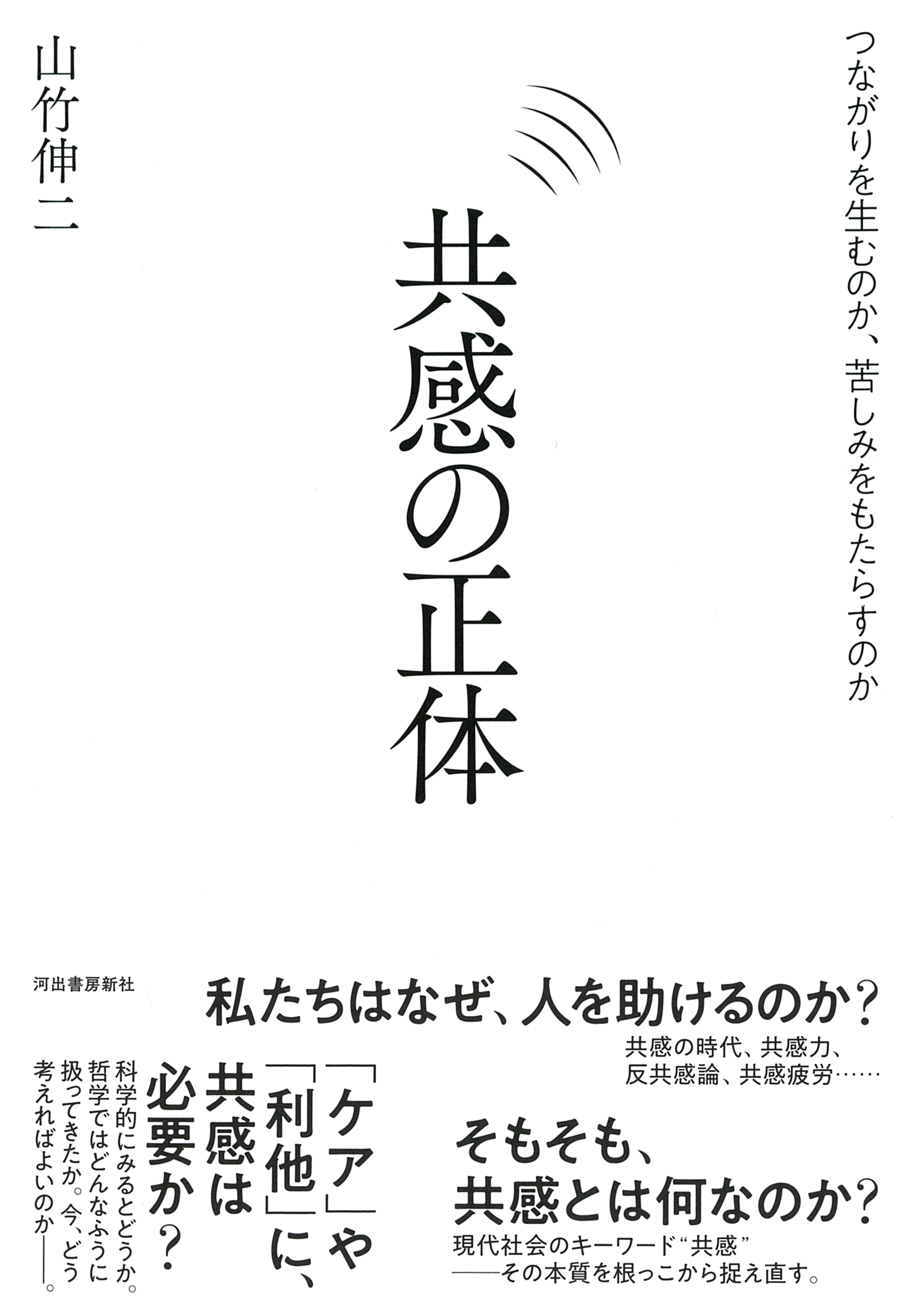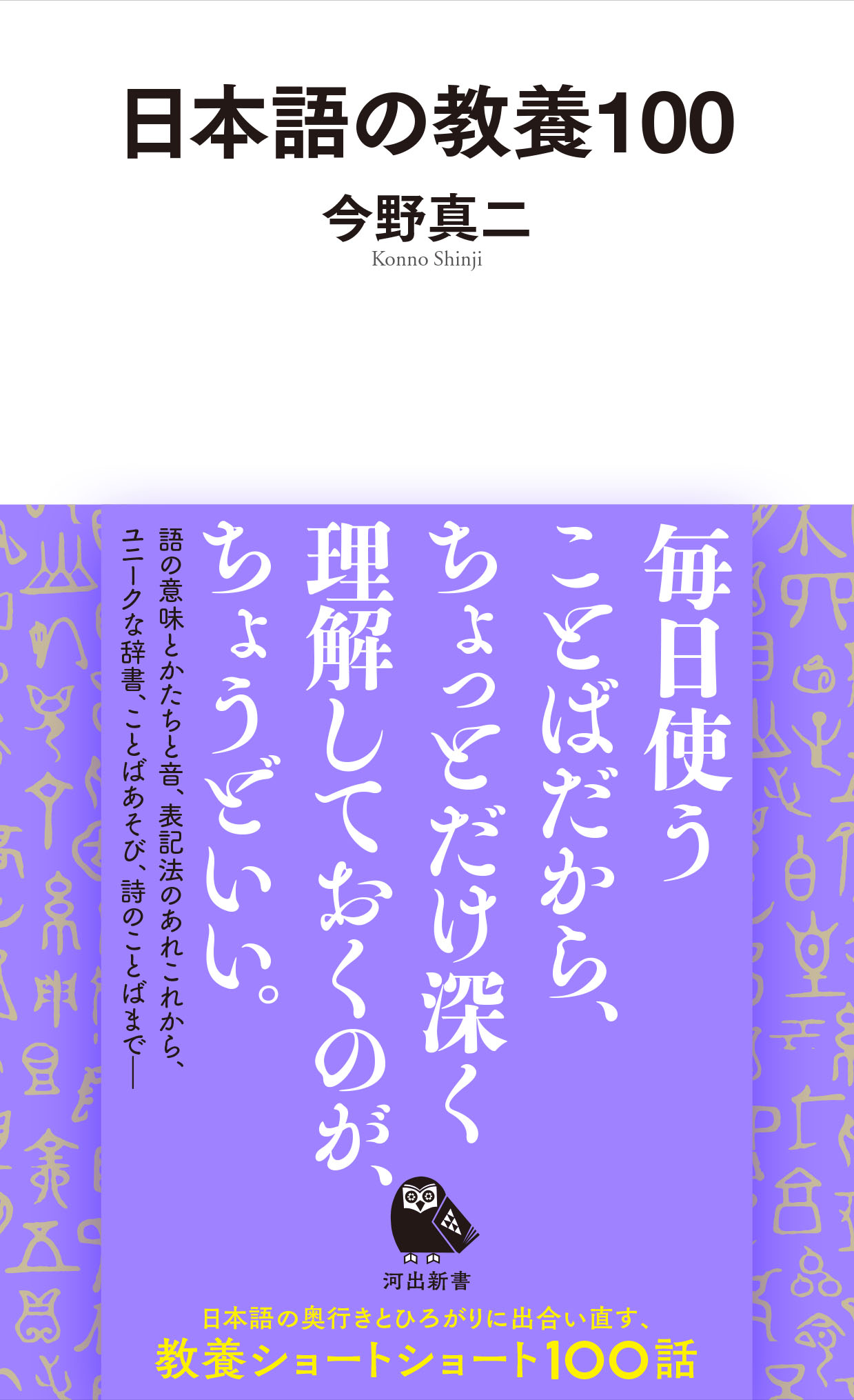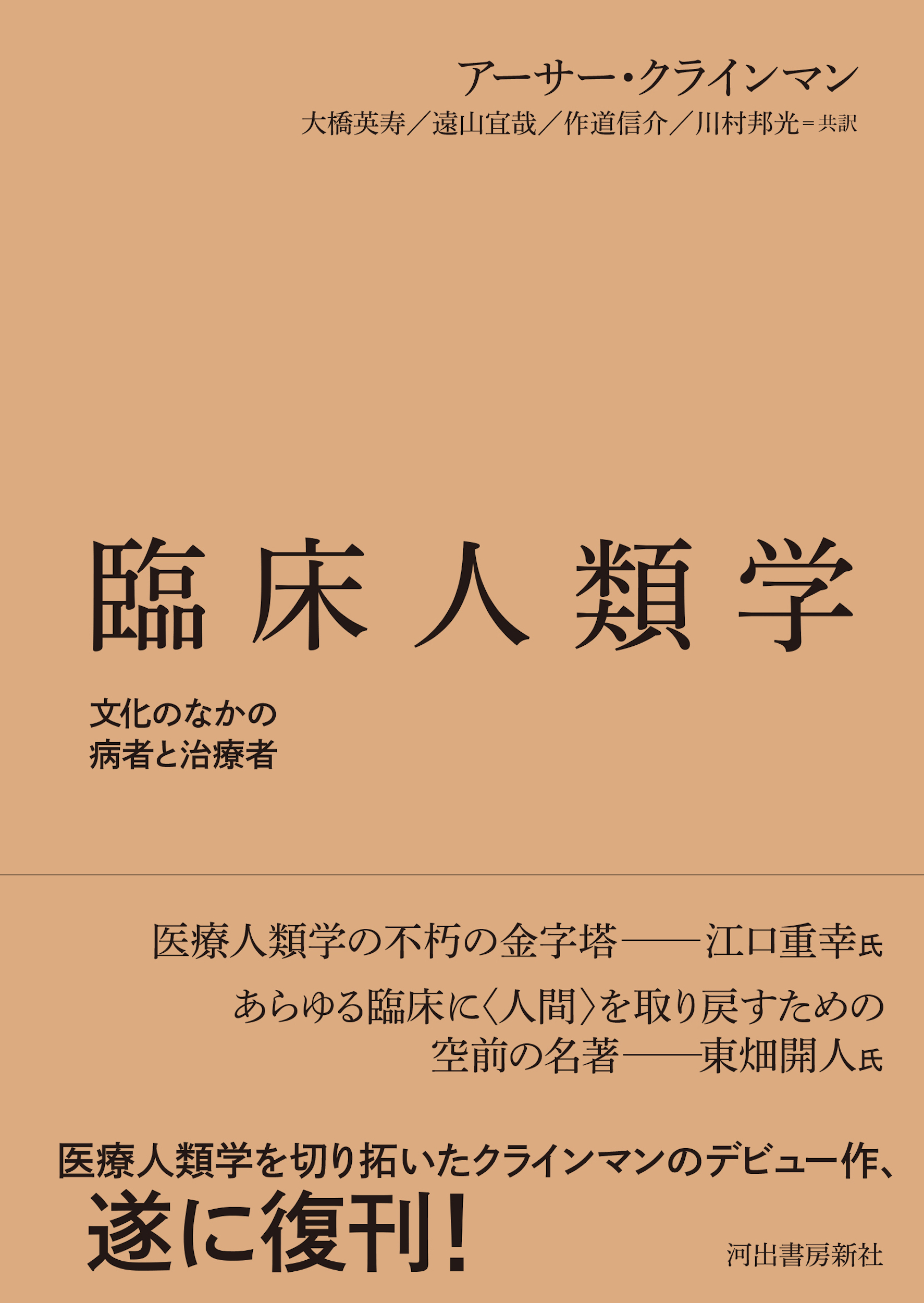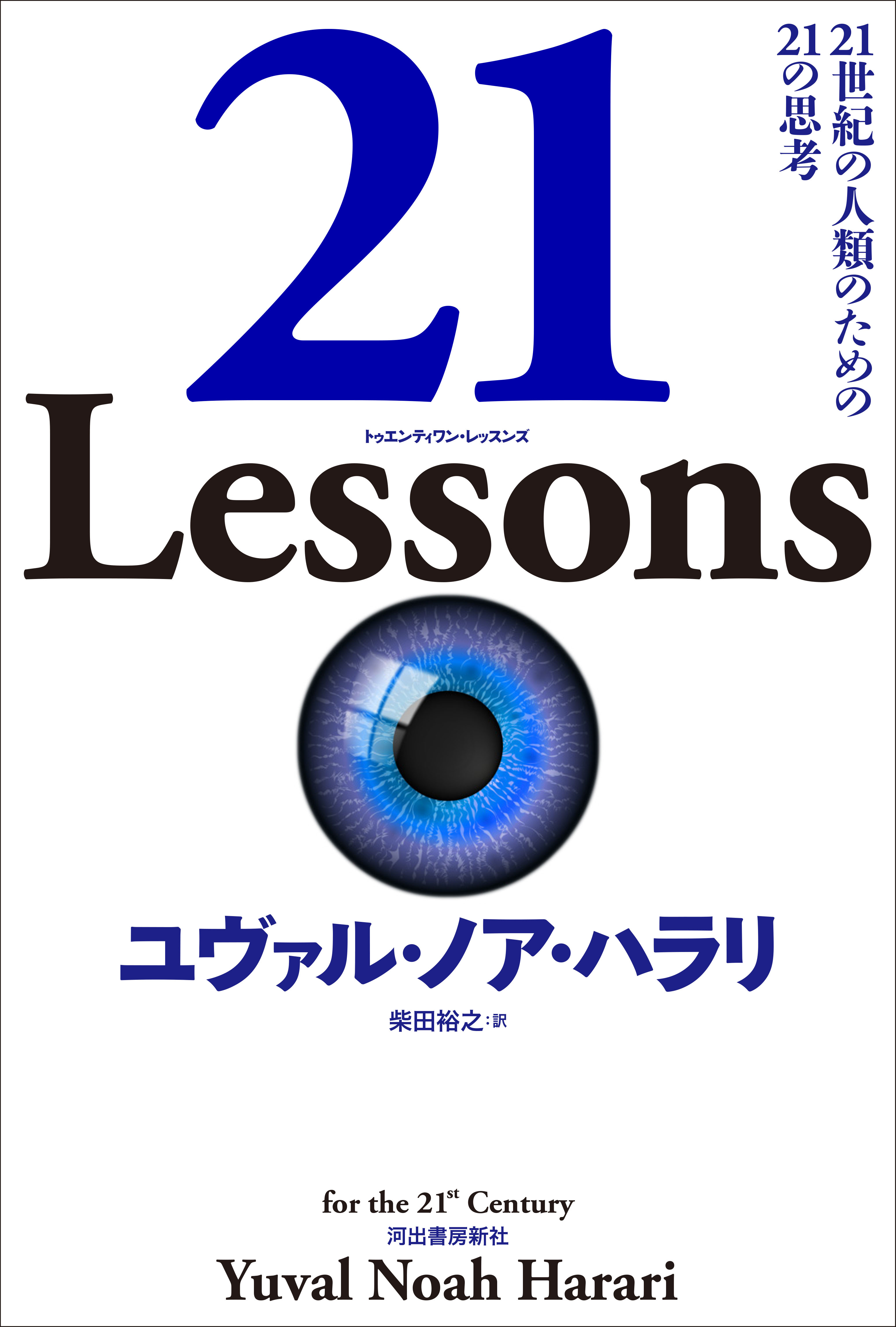
単行本 - 人文書
【ユヴァル・ノア・ハラリを読む】「物語」に背を向けるハラリ――『21 Lessons』の読みどころ
斎藤哲也(ライター・編集者)
2019.12.20
ユヴァル・ノア・ハラリの新著『21 Lessons――21世紀の人類のための21の考察』には、彼のデビュー作である『サピエンス全史』に寄せられた感想に関する興味深いエピソードが記されている。
『サピエンス全史』はもともと、彼の住むイスラエルの一般市民向けにヘブライ語で書かれた本だった。刊行後、多くのイスラエル人読者から寄せられた質問は、次のようなものだったという。
〈人類の歴史を綴ったこの本で、なぜ私(引用者注:ハラリのこと)はほとんどユダヤ教に触れなかったのか? なぜ私はキリスト教とイスラム教と仏教について詳しく書いているのに、ユダヤ教とユダヤ民族にはほんの数語しか費やさなかったのか? 人類史に対するユダヤ教とユダヤ民族の計り知れない貢献を、私はわざと無視しているのか? 何か悪意のある政治目的が動機なのか?〉(『21 Lessons』241頁)
これは『21 Lessons』の「謙虚さ――あなたは世界の中心ではない」という題された章の一節だ。
章題が示すように、同章は、自文化や自民族を過大評価する態度を強く戒める内容となっている。なぜか。そういった夜郎自大な自文化語り、自民族語りは端的に間違っているし、他者に対して偏狭な態度を生み出してしまうからだ。その例として、ハラリはユダヤ教を取り上げる。そして、ユダヤ教正統派を筆頭とした多くのユダヤ人の認識とは異なり、人類史というスケールでは、ユダヤ教がじつにささやかな役割しか果たさなかったことを具体的に綴っていく。
と要約すると、「ふーん」と読み流されそうだが、その語り口はかなり辛辣だ。他人事ながら「ハラリさん、そこまで言って大丈夫?」と心配になってしまう。
*
『21 Lessons』は、雇用、自由、平等、ナショナリズム、移民、ポスト・トゥルースなど、現代の人類が直面している課題を中心に、21のテーマに関する小論から構成されている。『サピエンス全史』が過去の人類、『ホモ・デウス』が未来の人類を考察しているとすれば、『21 Lessons』は「今、ここ」に焦点を当てた教養読本という趣きが強い。
さらに、前二作と異なる本書の特徴として、いま紹介したようなハラリ自身のエピソードが随所で披露されている点が挙げられる。いや、エピソードだけにとどまらない。現在のグローバルな危機や課題を省察することから始まる本書は、中盤以降、ハラリ自身の世界観が少しずつ開陳されていくような構成になっている。その意味で、三部作のなかで最もハラリ自身を語っている本としても楽しめる。
だが、人類の危機とハラリの世界観とがどうつながっていくのか。そのキーワードを一つ拾うならば「物語」となるだろう。
ITとバイオテクノロジーという「双子の革命」がもたらす自由・平等の危機、気候変動や生態系の危機、世界各地を席巻するナショナリズムの高揚など、人類は待ったなしの対応が迫られる多くの課題に直面している。
これらの危機や課題の諸相を明晰に整理し、多彩な具体例を織りまぜながら平易に伝える手さばきも本書の読みどころの一つだが、解決の展望は決して明るいものではない。それは〈私たちの昔ながらの物語はみな崩れかけ、その代わりとなる新しい物語は、今のところ一つも現れていない〉からだ。
すでに前二作を読んだ方はご承知のように、近代がつくりあげた「自由主義の物語」は、計り知れない成功を収めてきた。そこに民主主義や資本主義、国民国家といった物語を加えてもいいだろう。だが、これらの物語では、人類の危機を乗り越えられそうにない。というよりも、これらの危機は、ほかならぬ近代の物語を推し進めた結果、生まれたものであり、自由主義の物語はみずから首を締めているようなありさまなのだ。
では、どうすればいいのか。ここでハラリは意外な方向へ舵を切る。すなわち、サピエンスが自家薬籠中のものとしてきた「物語」や「虚構」にメスを入れるのだ。
*
本書に収められている21章のなかで、最も多くのページ数が割かれているのは「意味――人生は物語ではない」と題された第20章だ。そしてそれに続く最終章のテーマは「瞑想――ひたすら観察せよ」である。
この二つの章からは、ハラリの思想的バックボーンの核が垣間見える。「瞑想」という言葉からもわかるように、それは仏教だ。
その片鱗は『サピエンス全史』からもうかがい知ることができる。同書下巻の第19章「文明は人類を幸福にしたのか」では、幸福を探求してきた宗教や哲学のなかでも、仏教を特に重視して次のように述べている。
〈仏教はおそらく、人間の奉じる他のどんな信条と比べても、幸福の問題を重要視していると考えられる。二五〇〇年にわたって、仏教は幸福の本質と根源について、体系的に研究してきた。科学界で仏教哲学とその瞑想の実践の双方に関心が高まっている理由もそこにある〉(『サピエンス全史』下巻、237頁)
この一節に続けて、ハラリはかなり詳細に、仏教について肯定的な解説を加えているが、こうした直接的な言及だけでなく、『サピエンス全史』以来の屋台骨である「虚構」「物語」といった概念とも仏教は相性がいい。
というのも、仏教では物語や虚構こそ苦しみの原因と考えるからだ。『サピエンス全史』は、一見、言語を使って虚構を想像する力を手に入れたサピエンスが、地球の支配者に君臨するまでの成功ヒストリーとして読める。だがハラリは、サピエンスの物語を手放しで褒め称えたりはしない。だからこそ先の幸福を論じた章で、〈私たちは以前より幸せになっただろうか?〉と問いを投げかけるのだ。
『21 Lessons』に話を戻そう。こちらでもハラリは、ブッダの教えを解説しながら、意味や物語が苦しみの原因であることを伝えている。そして次のように言うのだ。〈人類が直面している大きな疑問は、「人生の意味とは何か?」ではなく、「どうやって苦しみから逃れるか?」だ〉と。
*
もちろん、虚構や物語のパワーを誰よりも熟知しているハラリだから、80億人総解脱なんて夢想を抱いているわけじゃない。それどころか、〈真実が君臨し、神話が無視される社会をあなたが夢見ているのなら、ホモ・サピエンスにはまったく期待が持てない〉と、物語に対して真実がいかに無力かを繰り返し力説している。
ここには、ハラリのジレンマがよくあらわれている。
一方では、人類規模の危機に対して、グローバルな連帯や協力が要請されている。そのためには、古い物語には使い物にならないので、どうにかして新しい物語を紡ぐことが要請されている。他方で虚構や物語は、個という単位でも集団という単位でも、苦しみの原因となる厄介な代物だ。
このジレンマから抜け出すさしあたっての出発点が、「どうやって苦しみから逃れるか?」という仏教的な問いなのだろう。
しかし私見では、意味や物語から距離を取ることは、別種のジレンマを抱え込むことになる。というのも、『ホモ・デウス』で描き出したようなアルゴリズムの支配もまた、意味や物語をデータに還元することへと向かうからだ。つまり、物語に囚われるなというハラリ=仏教的な啓蒙は、自己や自我を幻想と捉える点で、生命を生化学アルゴリズムに還元するデータ主義に接近してしまうのである。
こうした批判を織り込んでのことかどうかはわからないが、ハラリはその陥穽を、かなりアクロバティックな語り口で抜け出そうとしている。それがどのような理路なのか、そしてそれは成功しているのか。ぜひ本書を直接読んで考えてみてもらいたい。
関連ページ
■『21 Lessons for the 21st Century』オフィシャルHP(英語版)
【ユヴァル・ノア・ハラリを読む】
■未来の選択肢を増やす歴史のレッスン――まだ読んでいない人のためのユヴァル・ノア・ハラリ入門■混沌とした現代を理解するための壮大な仕掛け ――人類進化学者が考えるハラリ三部作の価値