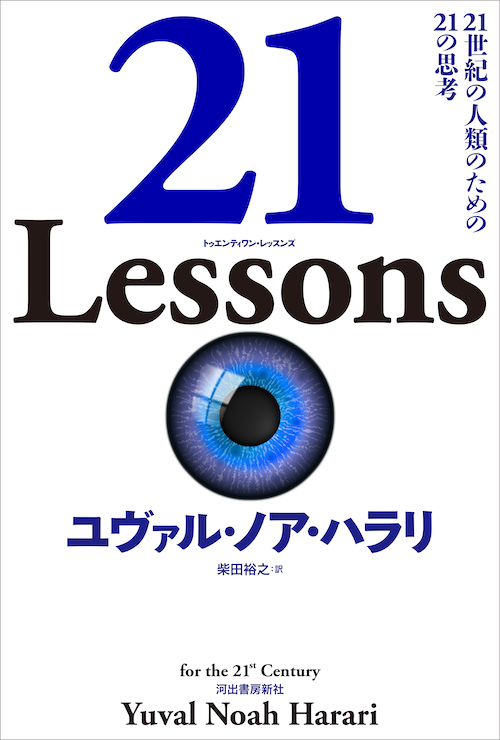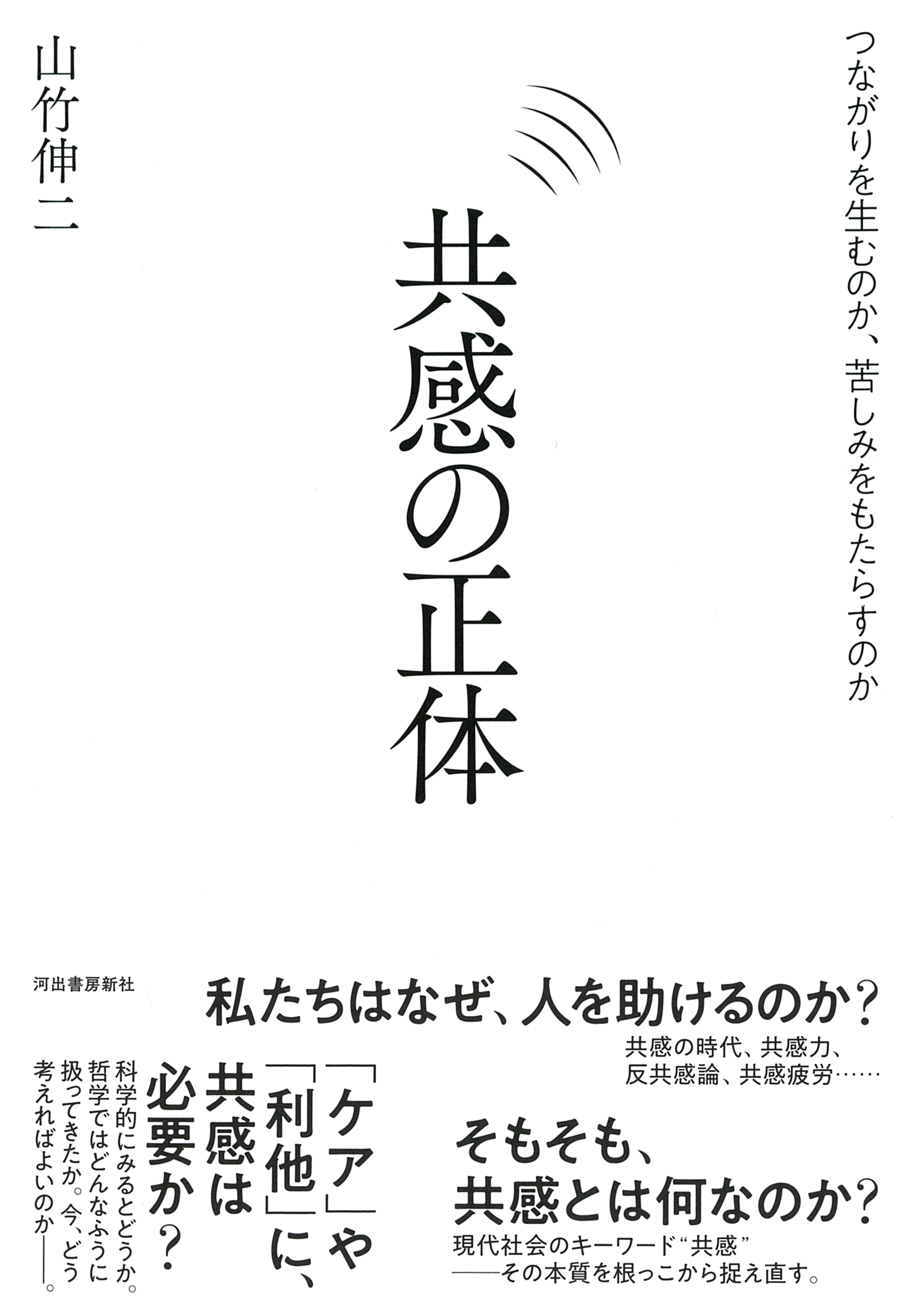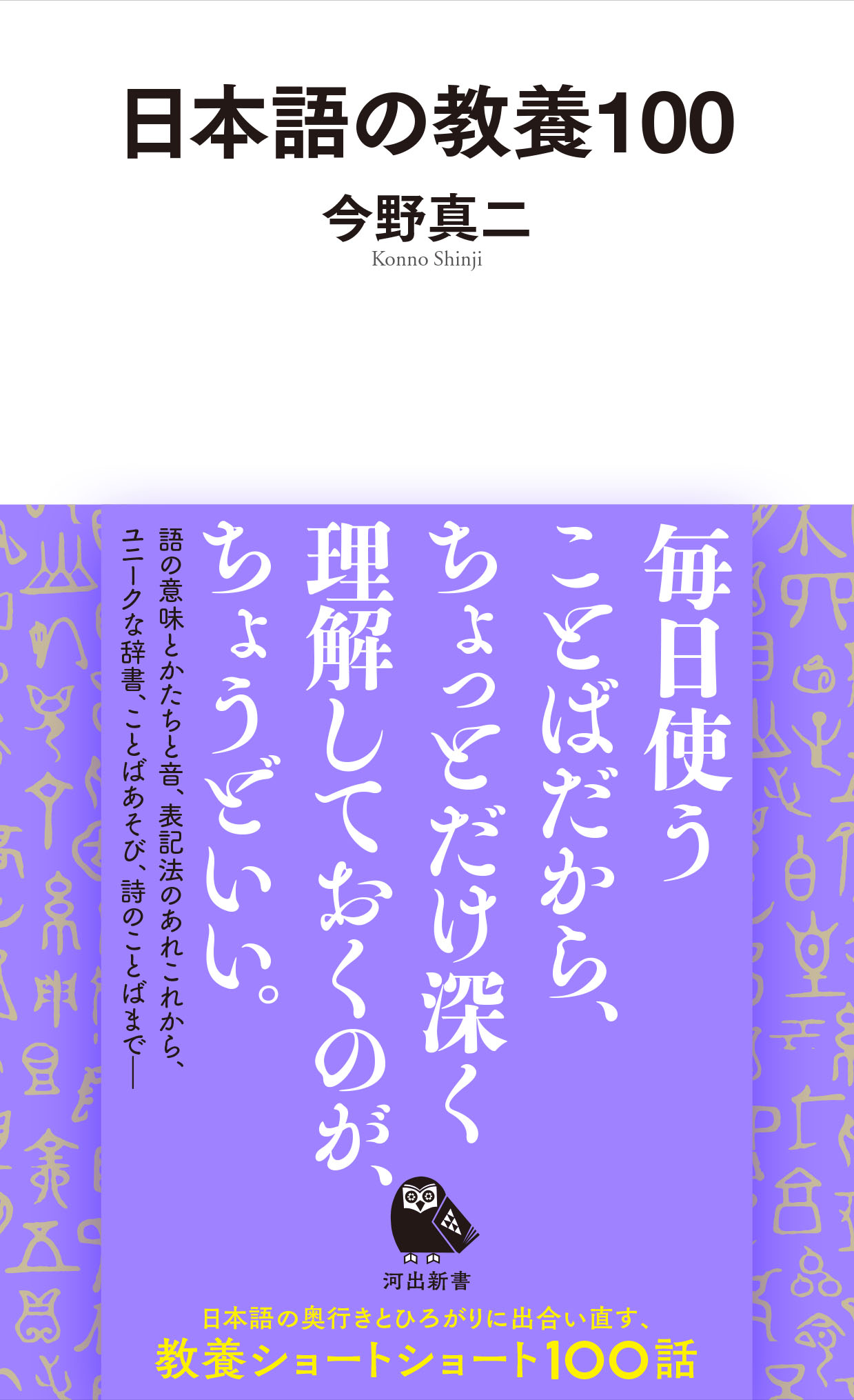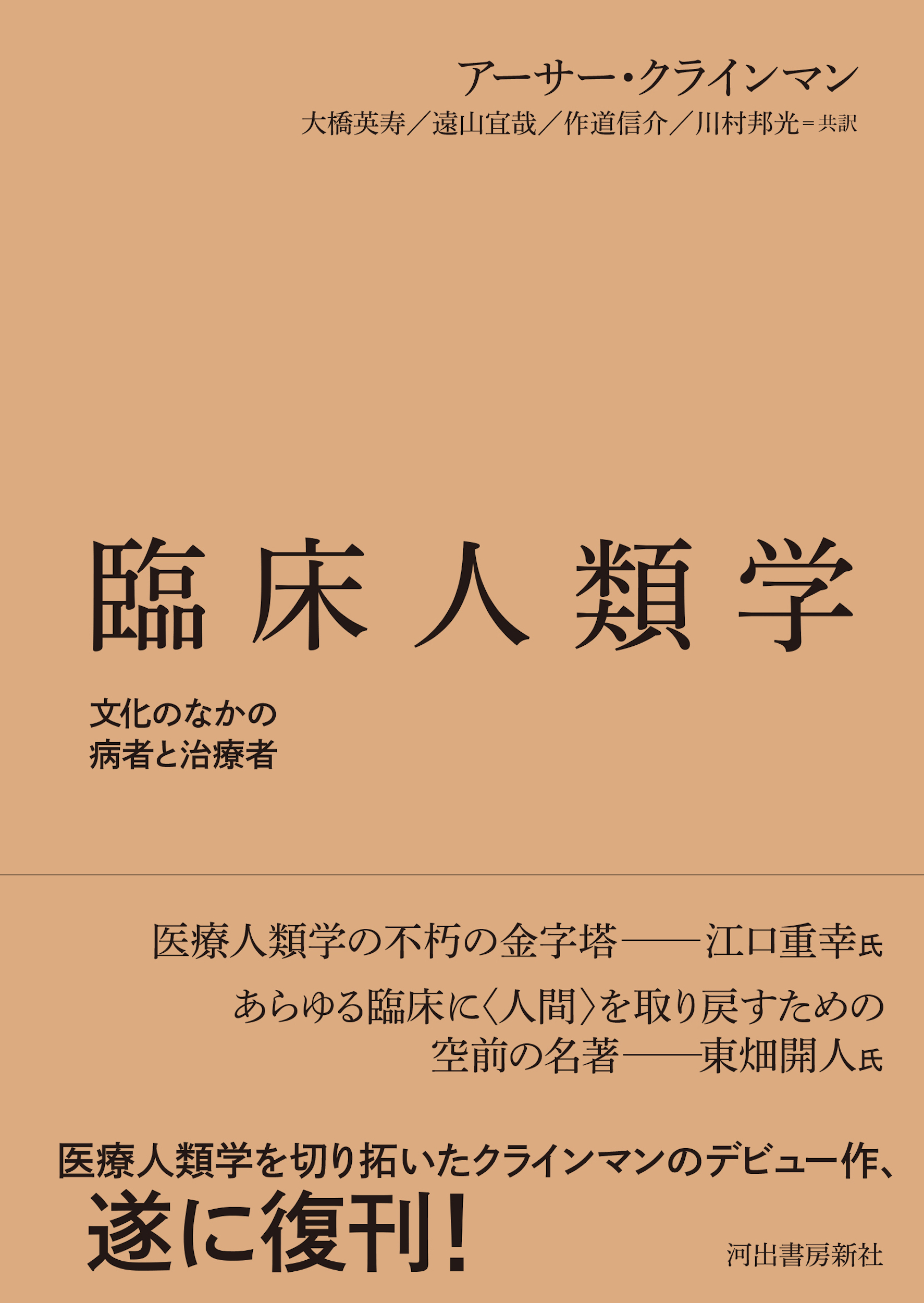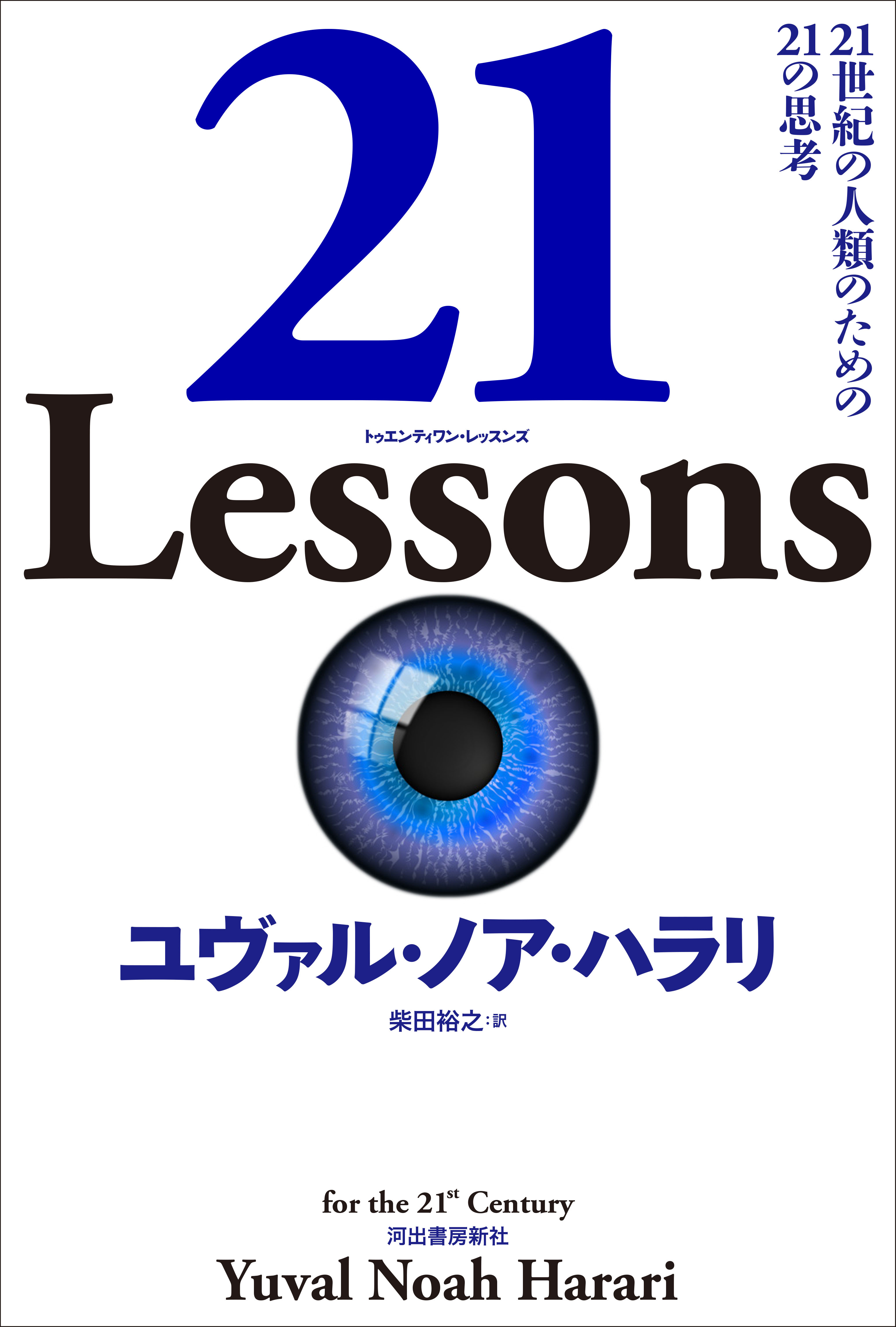
単行本 - 人文書
【ユヴァル・ノア・ハラリを読む】 ハラリの「虚構」概念をめぐって ―─ヘーゲルとガブリエルを参照しつつ
瀧澤弘和(中央大学経済学部教授)
2020.01.14
ハラリの著作を貫く基本コンセプトとは
ハラリは『サピエンス全史』,『ホモ・デウス』,『21 Lessons』を通じて,人類が辿ってきた過去,未来,そして現在を描いている.実は,ハラリがこれらの著作において挙げている個々の「事実」はそれ自体としては,よく知られているものであることが多い.それにもかかわらず,全体として大きな含意をもったストーリーが展開されているということは特筆すべきことであり,このことこそがハラリ独自の天才的洞察のなせる技だと言える.では,このような壮大なロジックの展開を可能にしているものは何なのだろうか.私が思うに,その鍵は,ハラリが彼の著作を貫いて使用しているコンセプトのダイナミシティにある.
ハラリが使用する概念のなかで,わたし自身がもっとも重要だと考えているのは,「共同主観的現実」という概念である.「想像上の秩序」という言葉もほぼ同じような文脈で用いられている.これらの概念について,『サピエンス全史』では,上巻146ページ以降に,『ホモ・デウス』では上巻180ページ以降に説明されているので,この部分をどのように理解するかが読解のうえで重要である.
「共同主観的現実」は「客観的現実」とも「主観的現実」とも異なる第三の現実のことで,簡単に言い換えれば,人間が集団的に産み出してきた世界のことである.ハラリは,人間の大規模協力を支え,今日に至る文明構築を可能としてきたのは,人間が共同主観的現実を構築する能力を持つからであると主張する.ここまでは,現代の社会科学研究者のほとんどが大いに同感することだろう.わたし自身も,人間のもっとも重要な特性の一つとして「制度をつくる」ことのできる能力をあげ,人間が自然界から相対的に独立した制度的世界を作り出すことをたびたび強調してきた.
しかし,「大いに同感」と思いつつハラリの議論を読み進めていくうちに,この当初ポジティブに見えた概念が次第に「虚構」という言葉で形容されるようになり,われわれの持つ信念の虚構性が暴露されていくような方向へと話が急展開する.この結果,われわれはハラリ独特のニヒリズムへと引き入れられていくように感じるのだ.共同主観的現実を構築する能力を持った人間は,やがてその能力を駆使して,自分自身をもアップグレードしてしまう世界へと足を踏み込んでいるとハラリは警告する.
『21 Lessons』における虚構
上述のような概念の自己展開がなぜ可能なのか.これが,わたしがハラリの『サピエンス全史』と『ホモ・デウス』を読んだときに抱いた疑問だった.近著『21 Lessons』では,少しヒントが与えられている.虚構ということで彼が何を意味しているのかがより詳細に論じられているからである.
そこでの説明によれば,人間は物語を創作し,そのなかの一定の役割を担うことに自分の生の意味を見出す動物である.これは先に述べた共同主観性のことであるように思われる.物語を創作できる人間の能力こそが大規模協力行動や文明構築を可能にしてきた秘密である.しかし,人間が作り上げてきた物語は,ほとんど例外なく不完全なもので,究極的な根拠を欠いていて,矛盾に満ちたものであった.それでも人間にとっては,自分の生の意義を見出すには十分なものだとハラリは透徹する.しかし,こうした出来の悪い物語に自己投影することが,人間を不幸にしてしまうのである.たとえば,殉教者のことを考えてみるとよい.
ハラリは,人間の生にも,はたまた世界一般にも意味がないと考えている.だから,こうした物語は虚構なのだ.このことをハラリは,『21 Lessons』において,彼が解釈する仏教の教え――「人生には何の意味もなく,人々はどんな意味も生み出す必要はない」(p.390)――に訴えて力説しており,最終章では,珍しく彼自身の個人的知的遍歴にも触れつつ,人間の心と世界を真実そのままに観察するための手法として瞑想を勧めてもいる.
このようなことを考えると,結局,ハラリの議論に対して好意的になれるかどうかを決める鍵は,一方でポジティブに評価されながら,他方でネガティブに評価されている人間の共同主観的現実──ハラリが他方で虚構と呼ぶもの──をどのように評価するかであるように思う.『ホモ・デウス』における恐ろしい警告の論調や『21 Lessons』におけるリベラル・デモクラシーの物語の崩壊を逆手にとった議論は,共同主観的現実の虚構性を強調することに依存しているからである.
自然主義的な傾き?
もう一度『ホモ・デウス』でハラリが虚構性を論じる地点に戻ろう.そこにおけるハラリは,自覚的にか,無自覚的にか,最終的に自然主義的で技術決定論的な思考に陥ってしまっているように思われる.ここを出発点にして,再度ハラリの考え方を検討しよう.
自然主義とは,ラフに言うならば,物的自然を唯一の実在とし,精神現象をも含めて,自然科学的な方法で説明できるという考え方である.振り返ってみれば,『サピエンス全史』においても,通常の人間の歴史の扱いとは異なり,歴史それ自体を可能とするような独特な一つの生物種として,ヒトを「距離をおいた視点から」考察する視点で貫かれていることに気づくはずである.
ハラリの自然主義的な議論の仕方は,『ホモ・デウス』のなかで,近代のヒューマニズムにとってもっとも基礎的な概念であると彼が見なす「意志の自由」について一章を割き,人間に意志の自由がないことは数々の心理学の実験室で証明済みであるかのように述べるところに見られる.そしてハラリは,このことをヒューマニズムからデータイズムへの移行を必然化するストーリー展開のなかに位置づけているように思われる.しかし,それは妥当な議論の仕方なのだろうか.ここに一つの分岐点があるのではないだろうか.
わたしにとって,「意志の自由」という概念は,ハラリがそうしているように,自然科学的な手法によって「事実」として確立されるようなものではない.それは,われわれが近代社会のなかで,相互に行為主体者としての自律性を承認しあうところに成立した共同主観的現実である.もちろん,このように言うことは,自然科学的手法によって得られた研究結果が間違っているということを意味しない.ハラリの指摘を受けるまでもなく,われわれが「意志の自由」と考えていることが幻想にすぎないことは,たとえばリベットの『マインド・タイム』などによって知られていることなのだ.
では何が問題なのか.先に述べたように,ハラリは「共同主観的現実」という言葉から,よりネガティブな「虚構」という言葉へと移行していく.しかし,ハラリがいかに述べようとも,虚構という言葉はあきらかに非実在性を主張する言葉である.つまり,人間が創出してきた世界を,ハラリがネガティブに虚構と見なす転換をしてしまうところに問題があるのではないか.
対極にあるガブリエルの議論
ハラリの思考方法と対極にあるのが,近年日本でよく知られるようになった哲学者マルクス・ガブリエルの主張である.彼は『なぜ世界は存在しないのか』,『「私」は脳ではない』等の著作において,20世紀の世界を席巻してきた自然主義的な物の見方の一面性を批判し,人間が創りあげてきた世界の実在性を主張しようとしている.自然科学的観点での実在性だけでなく,われわれが創り出してきた「意味の場(Sinnfeld)」をも認め,存在するとは意味の場に現れることだと定義することで,人間が作り上げてきた物事の実在性を認めるのである.これは,人間が歴史のなかで精神世界を作り上げてきたプロセスを重視するヘーゲルの立場にも通底するものである(ただし,彼はヘーゲルを批判するために,全体を包含するような「世界」は存在しないことを上掲書において証明しようとしているのだが,それ自体は,現在の文脈ではあまり関連性がないと思われる).
ここで若干,ドイツ観念論の問題意識を引き継ぎ,その大きな問いに回答しようとしたヘーゲルの考え方に触れよう.ガブリエルもその系統にあると考えられるからだ.ラフに言うならば,自然のなかに置かれながら,自然を貫く因果法則を把握し,かつそこから自立した道徳的世界を展開して生きている人間存在を,自然との関係でどのように考えたらいいのかというのが,ドイツ観念論の問題意識であった.
ヘーゲルは,世界を「精神」が自己展開するものとして捉えたということが知られているが,その「精神」を,われわれが慣らされてしまっている精神と物質の二分法で理解してしまっては,大きく間違えることになる.ヘーゲルの精神とは,わかりやすく言うならば,人間が作り上げた意味の世界であり,それは人間が創出した人工物(物的人工物や制度などの文化的人工物も含む)をも包含する概念である.このような意味での精神は,物質的なものを基盤とするのだが,それに依拠しつつも,決してそれに還元されない独自性を持っている.この点で,精神は物質的なものとの間にある種の「連続性」を持ちながら,自律性を有しているのである(実は,『サピエンス全史』の147ページ以降の記述は,この意味での精神の概念の記述にかなり近く,もしかしたらハラリはヘーゲルを読んでいるのではないかと思わせるものである).精神の持つ物質的世界からの自律性は,たとえば「貨幣」とか「結婚」といった制度の例を考えてみると,わかりやすいだろう.
ガブリエルに戻ろう.彼によれば,人間は,自分自身に対する概念化を歴史的に展開するようなタイプの心的動物である.そして,われわれが作り上げる制度のどれをとってみても,そこにはわれわれの自己概念化が浸透しており,そこからわれわれの価値観や行為のあり方のすべてが影響を受けている.このような意味での,「意志の自由」の実在性を認めるならば,それは単純に自然科学的知見によって否定されるものではない.もちろん,われわれが自分自身を単なる動物として自己概念化するならば,そこにはそれに基づいた一連の制度を創出する世界が待ち受けているとも言えるのだが・・・.
技術決定論的傾向
先にわたしはハラリの議論を特徴づけるのに,自然主義と並んで技術決定論という言葉を使用した.もちろん,ハラリの議論はなかなか手強いので,容易に批判の観点が見出せるようなものではない.ここでは,彼が『ホモ・デウス』第9章「知能と意識との大いなる分離」で論じた点に注目したい.
ハラリは,進化由来の生物が持つ「意識」については,現代の先端科学でも十分解明されていないことを認める.しかし,現代科学は生物のアルゴリズムとしての側面である知能については十分に解明してきたと言う.そのうえで,「知能と意識では,どちらの方が本当に重要なのか」という問いを投げかけ,「少なくとも軍と企業にとっては答えは単純明快で,知能は必要だが意識はオプションにすぎない」と言う.このことからハラリは,人間が不要とされていく可能性について論じていく.
技術と人間の関係については,今もっともさらなる展開が望まれている論点である.現代の哲学では,人間が人間として自律的であるという描像は捨て,人間が技術を含む環境世界と密接な相互作用のなかに置かれているという人間観を彫琢しつつある.人間は物的・制度的・文化的人工物を創り出すとともに,それに強く拘束される存在なので,かつてのヒューマニズムが想定したような自律的な存在ではないのである.このことは,ハラリのストーリー展開をサポートするのだろうか.
ここでも,わたしはヘーゲル的な視点が重要であると思っている.人間は技術的世界との関係に置かれ,それに強く拘束されはするものの,その拘束性のなかで,自分自身の主体性を構成することのできる生き物なのである.このことは,先に言及したガブリエルの「自己概念化」というアイディアにも含まれていると考えられる.
その際に重要なのは,ヘーゲルが使用しているような意味での「意識」である.ヘーゲル的な観点からは,人間が対象を知覚したり,認識したりするとき,人間は自分と対象とのこの関係自体を,より高次の認識の対象としていく.このプロセスは繰り返されて,さらに高次なものへと展開していく.こうして人間は制度を創るなどして,人間的な世界を豊富化する運動にかかわっているのだが,そのプロセスこそ「自由」の発現であり,そこで作用しているのが意識なのである.だとすれば,このような意味で意識を持つ人間と人工物とがどのような関係を社会的に構築していくのかは,単純に技術の発展動向で決められるものではないだろう.
高度な知能をもったロボットがわたしたちの身の回りに配置されていくとき,人間とロボットたちはどのような関係を結ぶことになるのだろうか.その際に問題になるのは,われわれが社会として,その人工物に対して,われわれと同じような属性を帰属させていくことになるのかどうなのかということを含む,自己概念化の問題である.家庭のなかで役に立つロボットに対して,われわれは家族の一員としての感情を抱くようになるのかもしれないし,そうでないのかもしれない.人工物ではないが,すでにわれわれはペットに対して,人間と同様の感情をしばしば帰属させていることにも注意が必要である.こう考えると,現在の急速な技術的発展のなかで最も重要な問題として浮上してくるのは,人工知能のような,人間以外のものに対して行為者性を定義していく動きである可能性も否定できないだろう.
新しいヒューマニズムへの刺激として
ハラリの議論はわれわれを震撼させる.しかし,その結論を技術決定論的にそのまま受け取るのではなく,警告として受け取るべきだろう.実際,『21 Lessons』の最終部分において,ハラリは「アルゴリズムが私たちに代わって私たちの心を決めるようになる前に,自分の心を理解しておかなくてはいけない」(p.408),「あと数年あるいは数十年は,私たちにはまだ選択の余地が残されている.努力をすれば,私たちは自分が本当は何者なのかを,依然としてじっくり吟味することができる」(p.409)と述べて,強い警告を発しているのである.
これまでにも,人類は,きわめて強力な知的アプローチが登場すると,それによって自然観・人間観・世界観を一元的に理解しようとする傾向を持ってきた.しかし,そのような機会には,つねに対抗するアイディアが産み出されてきたことも歴史的事実である.デカルトに対してはジャンバッティスタ・ヴィーコが,1950年代後半の人工知能ブームに対してはチャールズ・テイラーが,それまでは表現することが不可能だった人間の側面を掘り下げて,新たなヒューマニズムを展開してきた.現在においても,そのようなヒューマニズムの系譜が受けつがれるに違いない.たとえば,先述したガブリエルの議論は,リベラル・デモクラシーが大きな挑戦を受け,AIを始めとする急速な技術革新が社会を激変される可能性が取り沙汰される時代に,新しいヒューマニズムを構築しようとする試みと見なすことができるだろう.
このような観点から見ると,ハラリの議論は,われわれがいまだかつて人類が経験したことのない大きな転換期に立たされていることを明らかにすることで,われわれの自己概念化を促す意義を持つものと言うことができよう.
関連ページ
■『21 Lessons for the 21st Century』オフィシャルHP(英語版)
【ユヴァル・ノア・ハラリを読む】
■【ユヴァル・ノア・ハラリを読む】「物語」に背を向けるハラリ――『21 Lessons』の読みどころ
■未来の選択肢を増やす歴史のレッスン――まだ読んでいない人のためのユヴァル・ノア・ハラリ入門