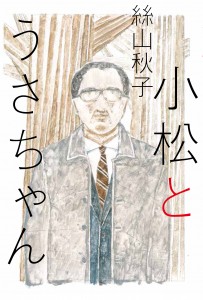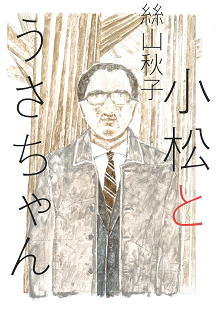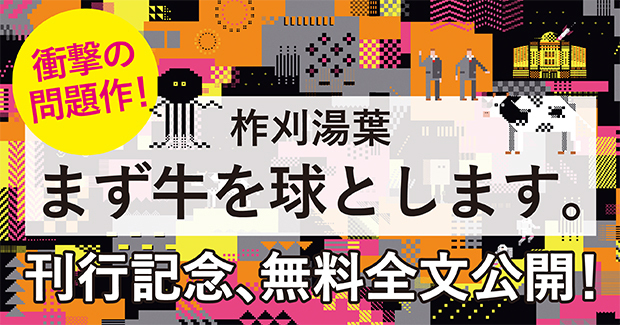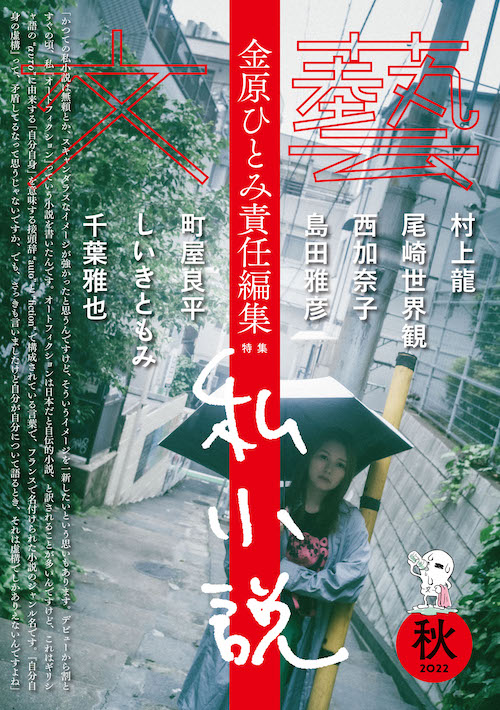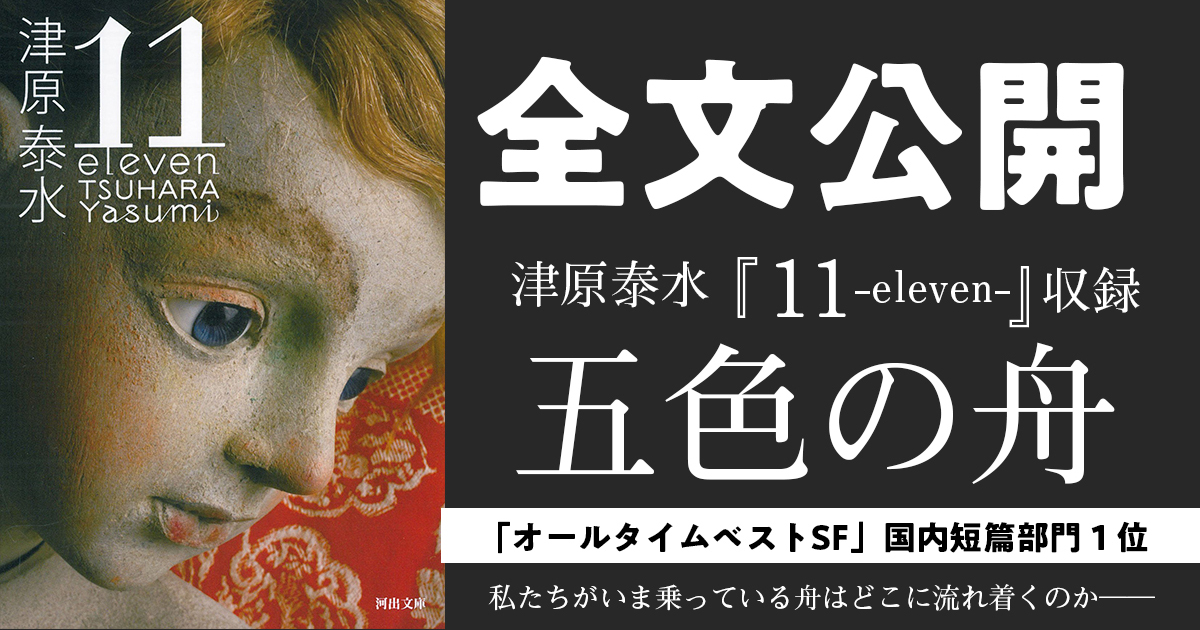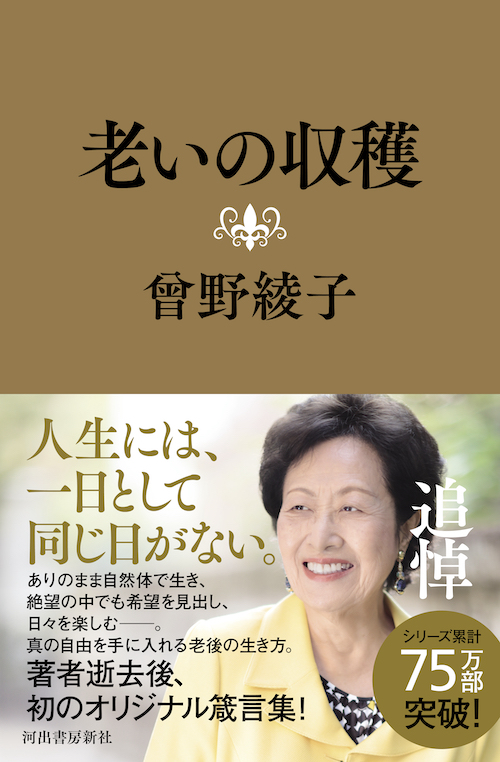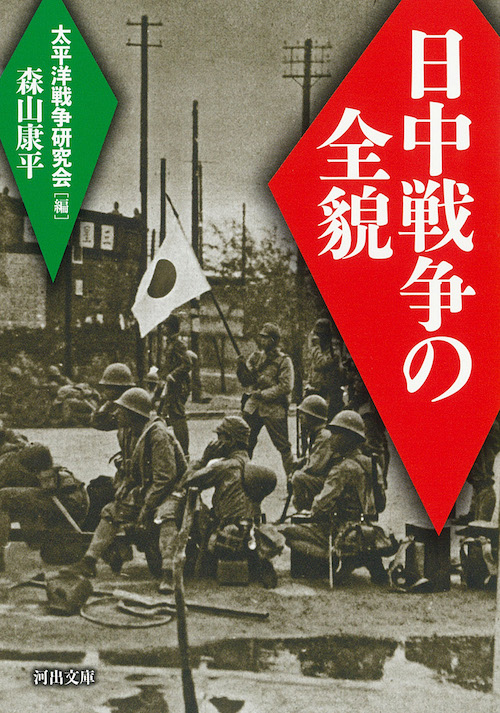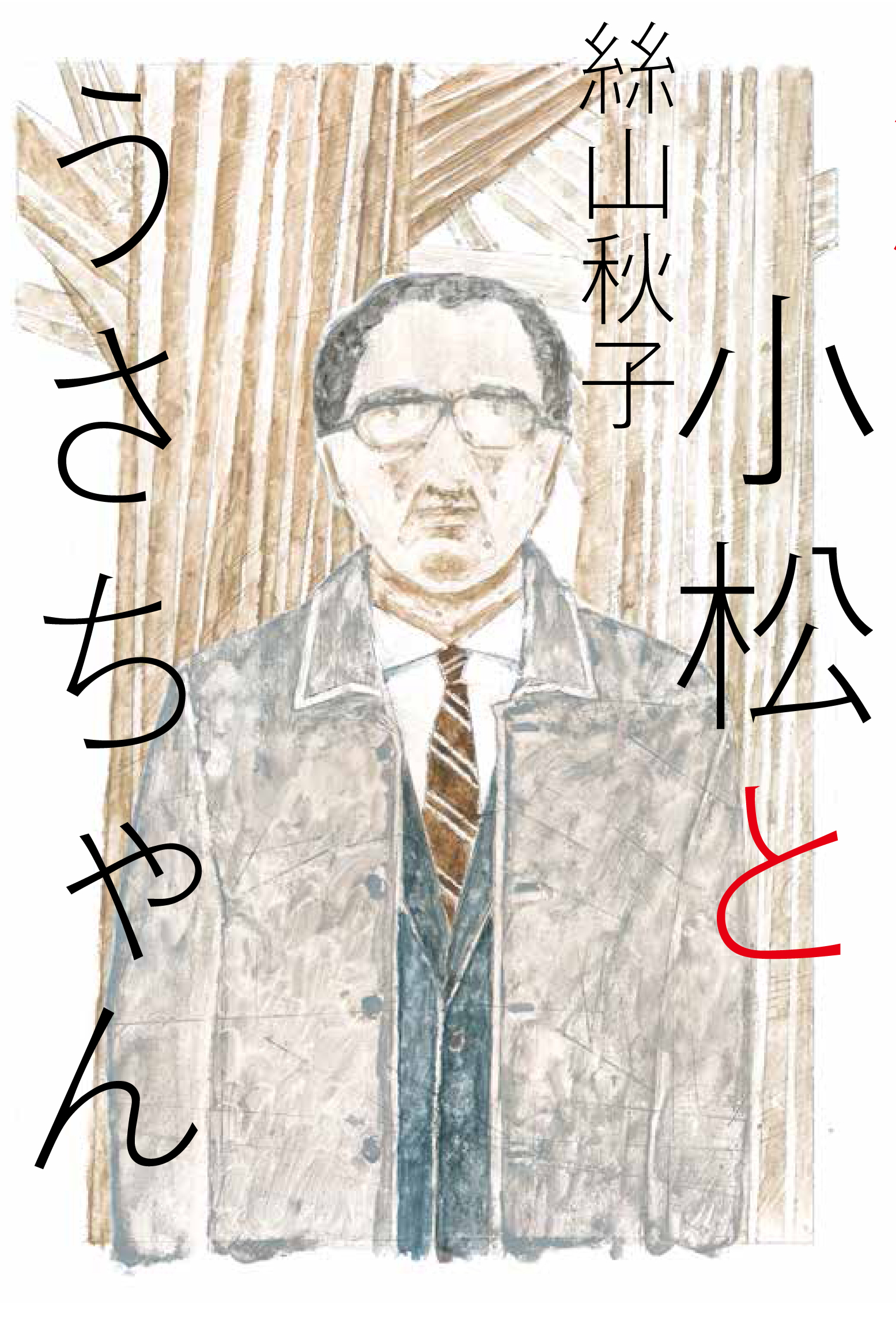
単行本 - 日本文学
虚構のなかの現実を生きる『小松とうさちゃん』
【評者】内山節
2016.02.19
『小松とうさちゃん』
絲山秋子
【評者】内山節
虚構のなかの現実を生きる
今しがた、私は駅の券売機で切符を買っていた。新幹線の切符なのだが、以前とはタッチパネルのつくられ方が変わっていて、画面が私に問いかけてくるようになっていた。その問いに答えていくと切符が買えるのである。
券売機と会話をしているような不思議な感覚だった。本当は私が機械の操作をしているはずなのである。
ふと会話とは何だろうと思った。昔なら音声を交錯させるのが会話だ。しかし、いまではメールやスマホのショートメールや、SNSでも会話をしている。相手の問いや情報提供に対して対応しているのだから、これが会話でないはずはない。とすると券売機からの問いに答えていた私は会話をしていたのか。
この本を読んでいるときもそうだ。私は読みながら問いかけている。たとえば「小松とうさちゃん」はこれからどんな行動に出るのか。その問いに予想どおりの答えが返ってくることもあるし、裏切られることもある。そして私はほっとしたり、その答えに戸惑ったりする。ここでも私は会話をしている。
とすると、虚構の会話と現実の会話に区別はあるのだろうか。あるのかもしれない。ないのかもしれない。そんなことを考える必要もないかのごとく展開しているのが私たちの日々だ。
この小説が扱っているのはそういう世界なのだろうと思う。現実と虚構。その区別を必要としない世界。
とするとそれは、能の世界と似ている。世阿弥が描いた世界は、現実と幻との境界のない世界だ。そこにこそ真実の私たちの生きる世界がある、と。
だがこの本は世阿弥の世界とは違う。世阿弥の謡曲には、結びあう世界への信頼があった。自然と生者と死者の共同体が、当然視されていた時代の作品だったといってもよい。ところがこの作品が描いているのは現代なのだ。共同体など存在しない。それは個人がいるだけの世界だ。その個人が虚構と現実の区別のない世界を生きている。個人が他者と交錯するとき、ふと現実があらわれ、しかしその奥には虚構の深淵が存在している。あるいは虚構の奥に現実が垣間見られる。
それが私たちの生きている世界だとするなら、私たちが交わしている会話も虚構であり、現実なのである。会話の多い小説だ。テンポのいい会話が、こんな世界をみせている。ストーリーのなかに自我の展開を描こうとした近代小説などとは全く違う世界。いま私たちはどんな世界を生きているのか。読み終えてからそんなことを考えはじめる作品である。