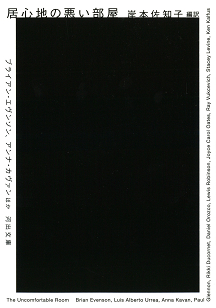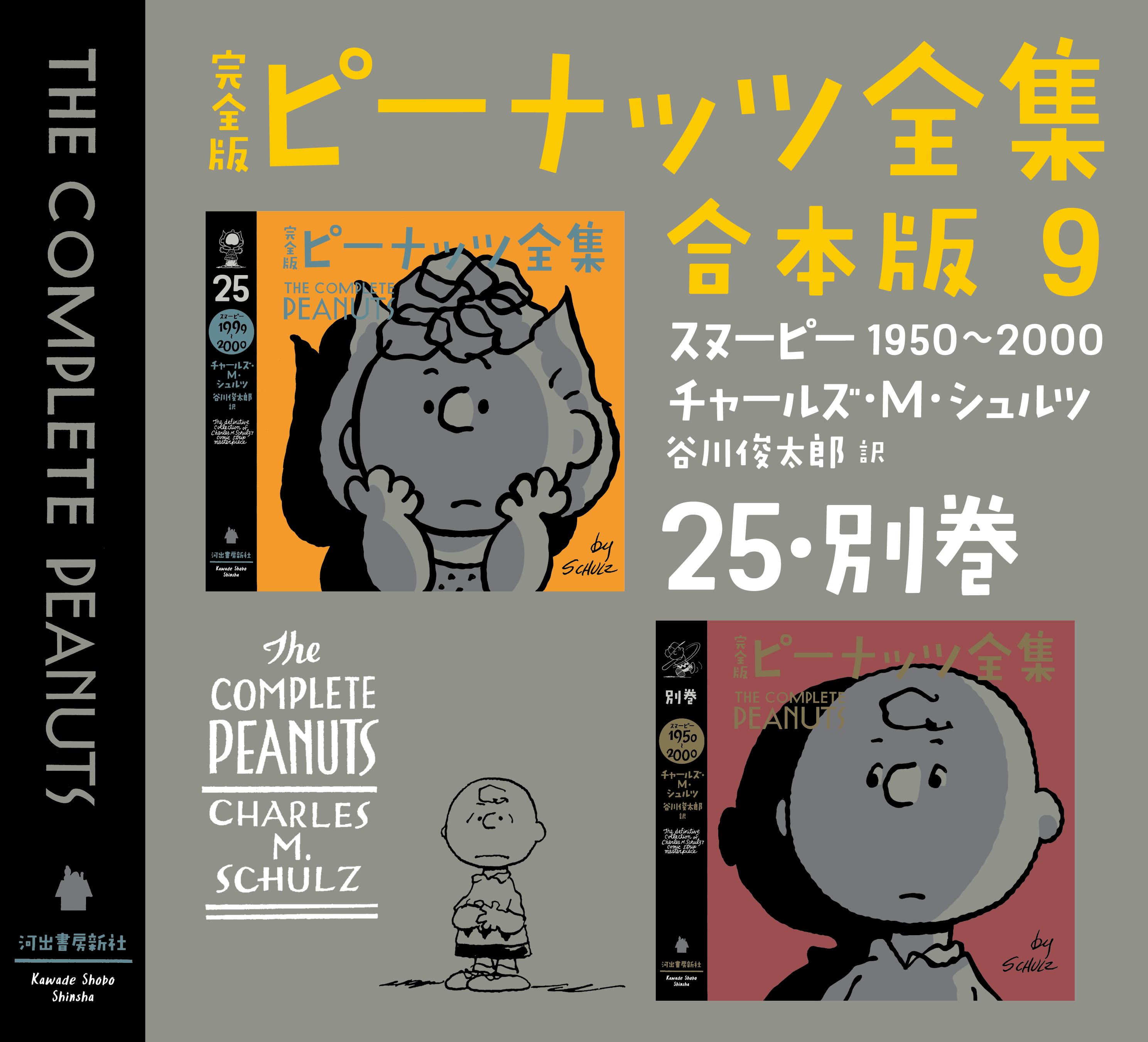単行本 - 外国文学
開かれすぎの心。『コドモノセカイ』岸本佐知子
【編訳】岸本佐知子
2016.03.17
『コドモノセカイ』
【編訳】岸本佐知子
【評者】津村記久子
開かれすぎの心
子供でいることほど心もとないことはなかった。かといって大人になれば無事になるとも思えなかった。だからわたしは心もとないなりに、恐ろしいほど今を生きていた。ほとんど毎秒が綱渡りと言っていいほどの。
編訳者が子供にまつわる12編を選んだ本書を読んでいると、子供当事者であった時の不安が寒々とこみ上げるのを感じる。けれども、裏腹の万能感と、異常なまでに満たされきった世界の見え方もまた、よみがえってくるのである。もう、冒頭にぶつけられる「まじない」のめちゃくちゃな世界観からして、覚えがありすぎてうあああと頭を抱えたくなる。ああそうだった。そうだったさ。自分の周囲が宇宙人にとってかわられているという主人公の妄想は、たとえ同種のものでなくても同じ濃度で記憶の奥に刻みつけられている。子供の頃は、大人になることなどいっさい信じられなかったけれども、自分の認識の歪みは完全に信じられていた。今考えると、自らの想像力が作り出したその細部は、大人の自分がふんわり捉えている現実の細部の何倍もリアリティがあったように思える。「追跡」や「薬の用法」といった小説にもまた、自分の認識しているものがすべてだというあの頃の、悪夢のようなディテールがある。それは悪夢のように明晰だからこそ、徹底的に豊かだ。小説を読みながら、自分の見えているものは貧しくなった、本当に貧しくなった、としきりに悔いた。「ブタを割る」や「靴」にも、豊かな思い込みがある。主人公の思い入れによって、ブタの貯金箱ペサフザンに、ドイツ製のアディダスのスニーカーに命が与えられる。子供の頃わたしたちは、見ようと思えば本当に何でも見ることができたのだ。
ものの見え方だけではなく、実際に悪夢の中を生きているかのような、「弟」や「最終果実」といった小説には、子供たちが子供ならではの残酷さを発揮する。腰から生えた弟を疎ましく思う姉というシュールな存在が語りだしたかと思うと、気まぐれに米粒を食べさせてもらった姉の付属物でしかないような小さな弟が、まだ生きていることの興奮で腰の上で跳ねまわる。そこには、読んでるわたしが跳ねまわりたいわというほどの不気味で根源的な興奮がある。「最終果実」の、広場に座り込む怪物の来し方と、その幼なじみの「木だったら木らしくさ、実でもつけてみせろよ」という横暴な呪いの顚末も、まさしく子供の悪夢の飛躍を思わせる。悪夢だけではなく、ゆかしい夢に満ちた物語もある。「七人の司書の館」の、女の子を育てる七人のそれぞれに独自な女性の司書たちのことを、わたしはずっと読んでいたかった。とちゅう、あまりにも読んでいて幸福なので、読み終わることが寂しくなって泣いた。
ああ子供の頃に戻りたい。あのめちゃくちゃな目の見え方と解釈の頃に戻りたい。なにもかも、なにがなんだかよくわからなかった。でも確かにそのことに心は開かれていたのだ。心の閉じ方を知らなかったあの頃に戻りたい。そういう願望をなみなみと満たしてくれる作品集である。
—————————————————
『コドモノセカイ』 【編訳】岸本佐知子
とても孤独で、暗くきらめく、幼いときだけ見えていた、決して忘れられない小さな世界たち。
名翻訳者が「子供」をテーマに選りすぐった、誰も読んだことのない全12篇。
《目次》
「まじない」リッキー・デュコーネイ
「王様ネズミ」カレン・ジョイ・ファウラー
「子供」アリ・スミス
「ブタを割る」エトガル・ケレット
「ポノたち」ピーター・マインキー
「弟」ステイシー・レヴィーン
「最終果実」レイ・ヴクサヴィッチ
「トンネル」ベン・ルーリー
「追跡」ジョイス・キャロル・オーツ
「靴」エトガル・ケレット
「薬の用法」ジョー・メノ
「七人の司書の館」エレン・クレイジャズ
「ここに出てくる子供たちのほとんどは、孤独だったり、弱かったり、ひねくれていたり、
卑怯だったり、とにかくただもう変だったりする。
話の最後に輝きを与えられもしなければ、成長もしない。
ただ、どの子供も、どの話も、読んでいてひりひりするほど『あの頃』のリアルさを (すくなくとも私にとっては)感じさせてくれる」
——岸本佐知子(「訳者あとがき」より)