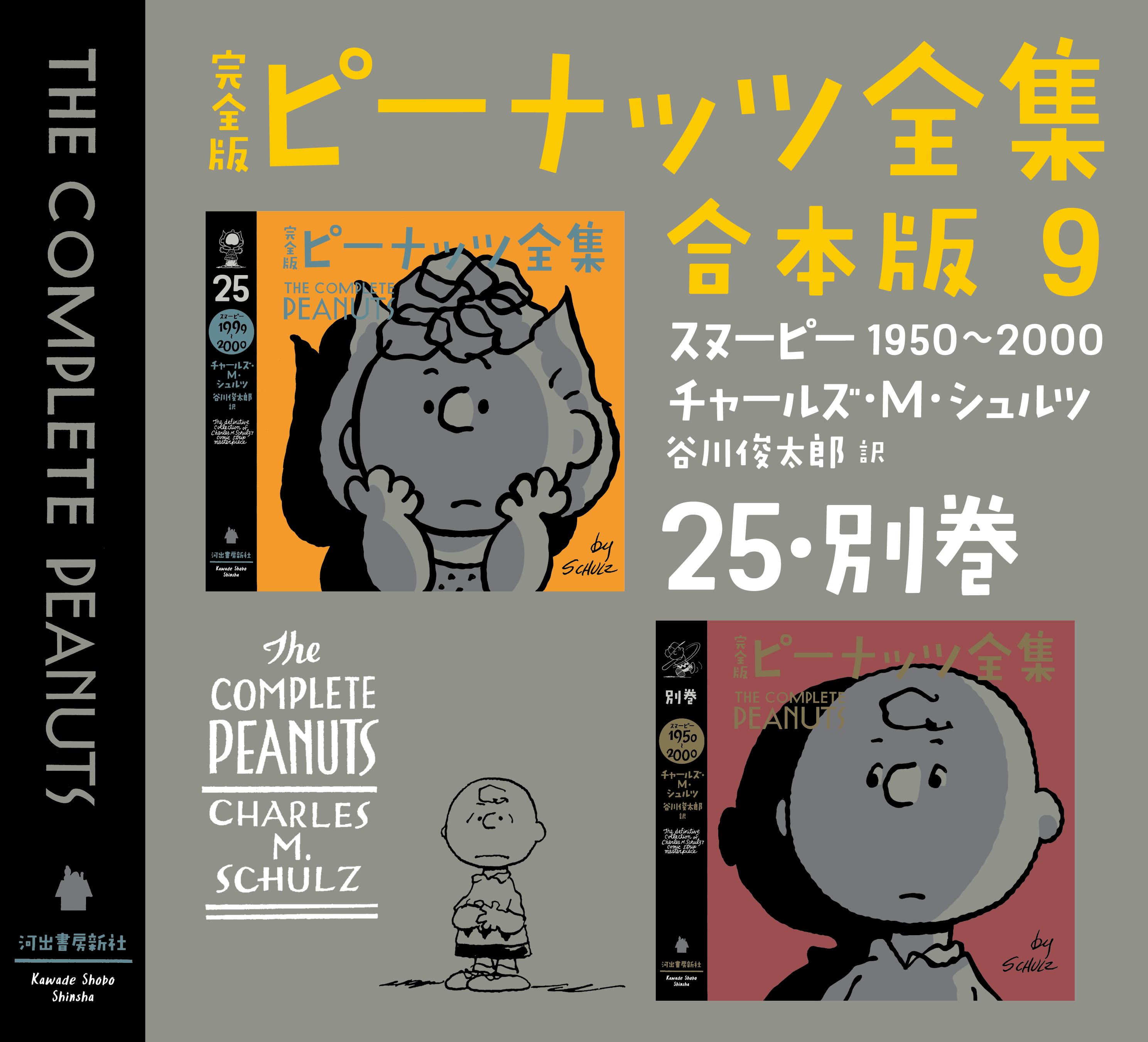単行本 - 外国文学
失われた魂の楽園探しの小説。『氷』ウラジーミル・ソローキン
ウラジーミル・ソローキン
2016.08.25
ウラジーミル・ソローキン 著
松下 隆志 訳
訳者あとがき
———————-
ウラジーミル・ソローキンВладимир Сорокин(一九五五〜)は現代ロシアのポストモダン文学を代表する作家である。コンセプチュアルな実験性と過激な性や暴力の描写から、一九九〇年代まではカルト的な作家と見なされていたが、二〇〇〇年代以降は英訳が本格的に出版されはじめたこともあり、徐々に世界的評価が高まっている。受賞こそしなかったものの、二〇一三年度の国際ブッカー賞へのノミネートは、まさにそうした評価の高まりを反映する出来事であった。
さらに、数年のブランクを経て発表された最新長編『テルリア』(二〇一三)は、民族問題や宗教紛争などの激化により混沌の度合いを増す近未来のロシアやヨーロッパを、五十もの断片的エピソードから多角的に描いた意欲作であるが、その後ウクライナ情勢が急変したこともあり、ロシア国内では「予言的な書」としてセンセーションを巻き起こしている(二〇一四年九月には早くもサンクトペテルブルグのアレクサンドリンスキー劇場で『テルリア』の舞台化が実現した)。
また、最近では実に三十五年ぶり(!)に絵筆をとり(ソローキンはコンセプチュアル・アーティストとしての顔も持っている)、『新人類学』と題された連作絵画の制作に取りかかるなど、芸術家としての創作意欲は衰えることを知らないようだ。
「失われた魂の楽園探しの小説」
このように読者層を拡大しつつある近年のソローキンだが、まさにそのターニングポイントとなった画期的作品が、今回訳出した長編『氷』《Лёд》(二〇〇二)である。世界を創造した「原初の光」という独自の神話に基づく壮大な物語は、他のソローキン作品の中でも異彩を放っている。
作品発表の事前に行われたインタビューで、作者は新作について「私にとって形式ではなく内容が前面に出た最初の小説」と述べ、『氷』がそれまでの作品とは質的に異なることを強調した。そして、作品の主題について以下のように語っている。
こう言ってもいいでしょう︱『氷』は現代の主知主義に対する幻滅への反応である、と。文明は破壊を行う。人々はどうも自己を見失ってしまっている。食べ物から愛に至るまで、あらゆる点で外的なテクノロジーの型に嵌められた存在と化している。根源的なもの、直接的なものへの郷愁が感じられるのです。我々は間接性という蜘蛛の巣の中で生きています。私は自分の祖父を思い出します。今日、心で語ることのできる人はたいへん少ない。そして、失われた楽園への郷愁もあります。楽園とは直接性です。『氷』は全体主義の小説ではなく、失われた魂の楽園探しの小説なのです。
こうした「告白」を作家の偽らざる本心と取るか、はたまた戦略的なポーズと取るかは読者の自由だが、『氷』がソローキンの創作を新たな段階へ引き上げたことは確かである。従来のソローキンが身体・言語両面に及ぶありとあらゆる暴力表現を縦横無尽に駆使しながら、小説の徹底した脱意味化を行っていたとすれば、『氷』の衝撃は、それとは逆に、無意味で不条理に見える暴力の背後から思いがけず物語=意味が立ち現れてくるところにある。それもただの物語ではなく、「神話」というもっとも強力な物語が。
言葉を現代アートのオブジェのように扱うアーティストから自身の物語を紡ぐ作家への「転向」は、いかにして生じたのか。一つには、しばしば弱点として指摘されてきた「反復的手法」からの脱却という作家の個人的な事情が考えられるが、その他に、いわゆる「新しい誠実さ」“New Sincerity” と呼ばれる比較的新しい文化潮流を参照項として挙げることができるだろう。
「新しい誠実さ」は、ポストモダニズムのアイロニーやシニシズムの克服を志向する芸術作品を形容する用語として、文学・映画・音楽など広範な領域で世界的に用いられている。ロシアの文脈では、ソローキンと結びつきがある現代詩人ドミトリー・プリゴフや批評家のミハイル・エプシテインなどが、コンセプチュアリズムに対抗する概念として用いたことがある。ただし、「新しい誠実さ」は単なる直接性への回帰ではない。対象にコミットしつつ、同時に自身のコミットに対してアイロニカルでいる、というアンビバレントな性質のものであり、自らの振る舞いに対してきわめて自覚的であるという点で、ポストモダニズムの延長に位置づけられる。
実際、ソローキン自身も直接性への郷愁を「告白」する一方で、別のインタビューでは作品に対する作者の役割を過大評価すべきではないと述べており、自身の「物語」に対する態度は単純なものではない。
ともあれ、結果としてソローキンは二〇〇〇年代の前半をほぼ丸ごと自らの神話世界の構築に捧げることになり、『氷』は続けて発表された『ブロの道』、『23000』という二つの長編と合わせ、革命期から現代に至る二十世紀のソ連・ロシアを丸ごと描く一大叙事詩へと発展した。「長編の死」を宣言した作者の筆からこのようなトルストイばりの巨大な長編が生まれるとはなんとも皮肉な話ではあるが、以下ではひとまず、本書『氷』の概要を見ていくことにしたい。
多彩なスタイルで書かれた長編
『氷』は四部構成で、各部が異なるスタイルで書かれている。
ミステリー風の筋立ての第一部は、現代のモスクワが舞台となっている。金髪碧眼の人間のみから構成される「兄弟団」と自称する謎の組織がモスクワで暗躍しており、彼らは密かに人々を拉致しては、氷でできた特殊なハンマーを用い、「心臓で語れ」と叫びながら拉致した人々の胸を殴打する。通常の人間はそれで絶命する(あるいは重傷を負う)が、一部の人間の心臓はハンマーの衝撃によって文字通り語りだし、「真の名」を告げる。
第一部で氷のハンマーの餌食となるのは、大学生の青年ラーピン、娼婦のニコラーエワ、ビジネスマンのボレンボイム。三人は職業も年齢もバラバラで、一見すると何の繋がりもなさそうだが、いずれも金髪碧眼という共通点を持っている。それぞれ異なる場所で兄弟団のメンバーに拉致され、氷のハンマーで殴打される。その結果、彼らの心臓は「ウラル」、「ディアル」、「モホ」という「真の名」を告げる。その後、三人は兄弟団の施設で傷の治療を受けるなどして日常に戻るが、奇妙な夢を見たり、原因不明の号泣の発作に襲われたりするようになり、徐々に心身に変調をきたしていく。
ピリオドで極端に短く区切られたセンテンス、まるで戯曲のト書きのように羅列される登場人物の特徴や場面状況など、第一部は最大限に装飾を取り払ったミニマルで無機質な文体で書かれており、主人公たちが流す「心臓の涙」と鮮やかなコントラストをなしている。また、数々のブランド名とともに、ポストソ連ロシアの代表的な若者雑誌『OM』や、現在もロシアで活動を続けるロックバンド「レニングラード」、あるいは国外の映画俳優やゲームキャラなど、現代ロシアを象徴するような国内外のサブカルチャーの産物が豊富に引用されているのも特徴的である。
続く第二部では、兄弟団の現指導者であるフラム(ワルワーラ・サムシコワ)により、半世紀以上にわたる自伝的物語が展開される。外面描写に徹していた第一部とは対照的に、ここでは心臓の覚醒の過程が感覚に重点を置いた一人称の文体で描かれており、語り手の内面の変化に伴って文体自体も徐々に変化していく。
物語の始まりは一九四一年まで遡る。独ソ戦が始まり、十二歳になったばかりのワルワーラが住む小村にドイツ軍がやって来る。彼らは二年間村に駐留し、最後には村を焼き払った上、労働力として子どもたちを連れ去る。列車ではるばるドイツへ運ばれたワルワーラは他の子どもたちとともに収容所へ送られるが、そこで密かに仲間探しを行っていた兄弟団のメンバーによって氷のハンマーで打たれ、「フラム」として覚醒する。彼女は兄弟団に加わり、最初の覚醒者であるブロから「原初の光」による創世神話を聞かされる。二十三の「心臓の言葉」をすべて習得した彼女は祖国へ帰還し、秘密警察の要職に就く仲間たちの助けを借りながら、次々にロシアの仲間を見つけ出していく。
ちなみに、第二部に登場する国家保安省の中将レフ・ヴロジミルスキー(心臓の名は「ハー」)は実在の人物で、小説でも史実通りベリヤの失脚がきっかけで銃殺される。ヴロジミルスキー亡き後も、兄弟団は密かに権力の中枢に侵入しつつ自分たちの勢力を拡大し、やがては資本主義ロシアの経済界を裏から牛耳るような巨大組織に発展していくが、そのプロセスも基本的には史実と矛盾しておらず、第二部にはいわゆる「陰謀小説」としての側面もある。
一方、第三部は前二部とは趣が異なり、兄弟団が資金集めのために開発した、氷のハンマーの効果を疑似体験できる健康増進システム〈アイス〉の取扱説明書と、その最初のモニターたちの感想文から構成されている。感想文の書き手は老若男女様々で、職業も映画監督から失業者、学生、詩人までと幅広い。このように、ある一つの対象を様々な視点や文体によって描くキュビズム的手法は、初期の『ノルマ』から最新作『テルリア』に至るまで、ソローキンがしばしば好んで用いる手法であり、ここではそれがセルフパロディ的な効果を生んでいる。
結末のごく短い第四部はエピローグ的な内容で、文体は再び第一部と同じミニマルなものに戻っている。幼い男の子が家の中で見つけた健康増進システム〈アイス〉のケースの中にある氷の数はすでに残り一つになっており、兄弟団の目的が成就の一歩手前まで迫っていることが暗示される。
翻訳について
作者の指定により、底本には『ブロの道』、『氷』、『23000』の三長編が収録された『氷三部作』«Ледяная трилогия»(二〇〇九、AST社)を用いた。二〇〇二年にアド・マルギネム社から出版された『氷』からの大きな変更点として、第一部に「痕跡」という章が新たに書き加えられている。
また、邦訳では各長編を個別に出版するに当たり、物語の時系列順ではなく、執筆順(『氷』→『ブロの道』→『23000』)に刊行することにした。完結編の『23000』は別として、『ブロの道』も『氷』も独立した作品としての強度を持っており、ソローキンの創作の新たな段階を告げる壮大な物語の入り口としては、やはり最初に書かれ、かつスタイルの多様性という面でも鮮烈な印象を与える『氷』が適当と判断したためである。
『氷三部作』全体のキーワードである「心臓」という訳語についても述べておく。ロシア語のсердцеは英語のheartに相当するが、日本語では基本的に「心臓」と「心」は区別されるため、文脈に応じて訳し分けられるのが一般的である。しかし本作では、「心で語る」とは、文字通り「心臓で語る」ことを意味している。こうしたメタファーの現実化はソローキンの得意とする手法であり、兄弟団のメンバーにとって「心臓」と「心」の間の区別はほとんど消滅している。よって本書では、сердцеを兄弟団の文脈では基本的に「心臓」と訳し、それ以外の文脈では場合に応じて「心臓」、「心」、「心臓(こころ)」と訳し分けを行った。
最後に、ソローキンが『氷』のアイディアを思いついたときのエピソードを紹介しておこう。意外なことに、それは日本滞在中の二〇〇〇年の出来事だった。
「ある日の夜、大学のパーティーを終えて吉祥寺の自宅へ帰る途中、暗い路地を歩いていると、前方でいきなり扉が開き、バーテンがバケツの氷を地面に捨てました。私がその上を歩くと、氷は足元で何やら謎めいた音を立てて砕けました。言っておかねばなりませんが、それは七月末の猛暑の時期でした。そしてその数日後、私は氷のハンマーのアイディアを思いついたのです」
猛暑の東京で冷たい『氷』の物語が生まれたというのは、何やら逆説めいているが、考えてみれば、ソローキンの創作は常にそうした逆説に満ちている。兄弟団の物語はまだまだ続くが、まずは氷のハンマーの衝撃に思う存分心臓を揺さぶられてほしい。
——————————
『氷』試し読み公開中!