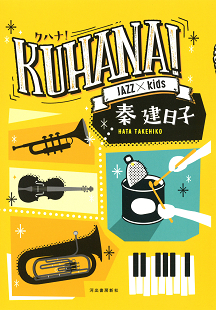単行本 - 日本文学
秦建日子『And so this is Xmas』試し読み 第4回
秦建日子
2016.11.22
篠原涼子さん主演でドラマ・映画が大ヒットした「アンフェア」シリーズの原作者であり、最近ではドラマ「そして、誰もいなくなった」などの脚本も手掛ける秦建日子さんの最新小説『And so this is Xmas』が間もなく発売になります。
試し読み第4回を公開しました。
(第1回はこちら)(第2回はこちら)(第3回はこちら)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
秦建日子『And so this is Xmas』試し読み 第4回
4
須永基樹と合コンで初めて会ってから、ちょうど一か月後の十二月二十二日。時刻は十三時四十五分。印南綾乃は、ランチタイムをとうに過ぎた空席だらけの社員食堂の一番奥の席にいた。肩まで伸びきった髪を、手首から外したシュシュでさっと結ぶ。レインボー飲料という食品メーカーの社屋の一階にあるこの社員食堂は、九時から二十時まで営業しており、好きな時間にそこそこ美味な料理を格安で食べることができるのがありがたかった。
綾乃は、木の大きな丼を左手で押さえ、右手のスプーンで中のものをぐちゃぐちゃにかき混ぜ始める。納豆、オクラ、山芋、まぐろのぶつ切り。それぞれが色よく配置され、更に具の真ん中には卵の黄身が落としてある。この「ネバネバ丼」はもともと、夏季限定のメニューだったが、女子社員からの多数のリクエストで、通年のメニューに切り替わった。綾乃も、強くそれをリクエストした社員の一人だ。
「綾乃さぁ。ちょっと前まで嫌いじゃなかったっけ。ネバネバ丼」
「真奈美、知らないの? 失恋すると、女は好きな食べ物が変わるのよ」
綾乃は、ぐちゃぐちゃに混ぜ合わせた丼の中身をスプーンですくい、わざと大きく開いた口の中に入れて見せた。
「聞いたことないわ、そんなの」
真奈美はド派手なネイルアートを施した手で箸を割り、木のトレーに載った二百九十円の盛りそばを食べ始める。
「私には、真奈美のそのネイルアートの方がわかんない」
「何でよ! 見て、これ。ほら。サンタクロースとトナカイ♪ クリスマス仕様なんだよん♡」
真奈美は箸を置き、自慢気に綾乃にネイルアートを見せつける。右手の親指の爪には小さな3Dのサンタクロース。そして、右手の小指の爪には、更に小さな3Dのトナカイ。
「可愛いでしょ?」
「……パソコン打つ時、邪魔じゃない?」
「バーカ。これも一つの営業です!」
真奈美の言うこともわからなくもない。真奈美は、外食事業部の所属だ。飛び込みで入ったレストランの店長が真奈美のネイルアートを見て「すごいね、それ!」と興味を持ち、店内の飲料をライバル社からレインボー飲料に替えてくれたという武勇伝を聞いたことがある。
「これで一万円だよ? 安いよね〜」
真奈美は、自慢のネイルアートをうっとりと眺める。綾乃は、そんな真奈美を羨ましく思う。真奈美がこだわるのは、ネイルアートだけではない。髪も化粧も体型にも女子力に抜かりはない。少し茶髪の長い髪は触りたくなるようなサラサラ感。毎日営業で数万歩歩くせいか、入社した時から三十歳になる今まで、ずっと惚れ惚れするようなカモシカのような足。百七十センチの長身で、黒のパンツスーツがよく似合う。それでいて、合コンの時には器用にふわふわ女子にも変身できる。
一方の綾乃はというと、実はもう半年も美容院に行っていない。顔にBBクリームを塗るだけなので、朝の支度は十分で終わる。今着ているベージュのニットとデニムのスキニーパンツの組み合わせは、今週既に三回目だ。冬はどうせコートを羽織るのだから、中の服なんて何だっていい。女子力はゼロに近い。そういう自覚はある。このままではいけない。そういう自覚もある。
ちらりと携帯を見る。
「今ので十三回目」
真奈美がすかさず言った。
「え?」
「綾乃がそこに座ってから、チラチラとスマホをチェックした回数」
「……」
真奈美はいつも観察眼が鋭い。
「待ってるんでしょ? 連絡」
「別に、待ってるってほどじゃないわよ」
綾乃はスプーンを持ち上げ、否定するように小さく左右に振った。
「でも、気になってる」
「別に、気になるってほどでもないわ」
「でも、ようやく、新しい恋を悪くないかなと思い始めてる」
「……」
「でしょ?」
「やめてよ、もう」
綾乃は、半年前の誕生日のことを思い出した。世の中的には「ついに大台」とか言われてしまう、三十歳の誕生日だ。綾乃には、二十歳の時から付き合っていた卓哉という恋人がいた。その卓哉から、きっと誕生日にプロポーズをされると思っていた。なぜなら、誕生日の数週間前から、卓哉が妙にそわそわし始めたからだ。しかし、綾乃の予想は完璧に外れた。よりによって三十歳の誕生日に、卓哉は別れ話を切り出してきた。
新しい女がいるのだと。
その女は実はもう妊娠しているのだと。
そして、綾乃と別れて二週間後に二人は籍を入れ、二か月後にはその泥棒女は赤ちゃんを産んだらしい。
私の二十代はなんだったのだ。男はもう懲り懲りだ。綾乃は三か月ほど泣き暮らし、ついに泣くことにも飽きてしまった。
ちなみに、その卓哉という男は、とても束縛癖のある男で、一日に何度もLINEでメールを送ってきては、綾乃がすぐに既読にしないと言って怒るような男だった。卓哉のせいで、綾乃は常に携帯の通知画面を意識する癖がついてしまっていた。卓哉が綾乃に残したものは、心の傷と、そのくだらない癖くらいである。
「私は、悪くないと思ったよ?」
「は?」
「須永さん」
「え」
「合コンの時、須永さんのこと気になってたでしょ? だから、チラチラ携帯気にしてるんでしょ? でもね。待つだけじゃダメ。もう一度会ってみたいなーって思うなら、勇気を出して自分から連絡しなくっちゃ!」
真奈美の言葉は力強い。綾乃は、申し訳なさそうな声で返事をした。
「そういうことじゃないんだよね」
「え? でも、須永さんからの連絡を待ってるんでしょ?」
「ううん、違うよ。ていうか、彼からはもう連絡こないと思うし」
「え? もうって何? ちょっと話が見えないんだけど」
「んー」
「何が、んー?」
「実はさ、もう会ったの」
「は?」
真奈美は、もともと大きな目を、更に更に大きく見開いて驚いた。
「もう会った⁉」
「うん」
「いつ⁉」
「……昨日」
「昨日!!! 私、聞いてないよ?」
「急な話だったの。だから、ご飯の後、話そうと思ってたの」
本当に、急な話だったのだ。昨日の仕事帰り、電車に乗っている時に突然須永からLINEで連絡があったのだ。LINEのIDは、合コンの後、男性幹事が勝手にグループLINEを作ったので、お互い訊いたわけではないのに連絡先を知ることができていた。
「今から焼き鳥食べない?」
たった一言だけのLINEだった。合コンの時は彼はあっという間に帰ってしまったので、綾乃はもう少し須永と話をしたいと思っていた。なので、突然の連絡にはびっくりしたが、同時に少し嬉しかった。いつまでも卓哉のことを引きずっているばかりではなく、新しい恋愛を始めたいという気持ちも正直あった。
「焼き鳥は大好きです」
と短く返す。そして、あっという間に、「三十分後に東横線の祐天寺という駅で待ち合わせ」に決まったのだった。
綾乃が着いた時、既に須永は改札の外で待っていた。青いTシャツにデニム。綾乃と目が合うと、軽く手を挙げ、口元を少し緩めた。微笑み、のように見えなくもなかった。それが綾乃には意外だった。
「汚いところだけど」
そう須永は言った。なので、古くて小汚い焼き鳥屋を綾乃は想像したが、須永が連れて行ったのは、祐天寺の駅から歩いて三分ほどの場所に立つ須永のマンションだった。
か、彼の部屋? 焼き鳥屋ではなくて彼の部屋?
綾乃はびっくりして入るのを躊躇ったが、須永の方は、非常識なことをしているという自覚が微塵もないようで、振り返りもせずに、築四十年以上は経っていそうな古くて薄汚れたマンションの中に入っていった。それで綾乃も抗議のタイミングを失ってしまい、彼と一緒にそのマンションに入ることになった。
「どうぞ」
須永が綾乃を室内に招き入れる。
「お邪魔します」
小さな玄関には、須永のサンダルしかなかった。高年収で雑誌の表紙に抜擢される若き起業家でありスタープログラマーの住む部屋とは思えなかった。当惑しながら靴を脱いだ。
玄関を入ると、左手に二畳ほどのキッチンがあった。
「今、用意するから中で適当に座ってて」
「あ。はい」
前方にあるリビングに続く扉を開けた。二十畳ほどのリビング。ベージュの三人掛けのソファーと黒いガラステーブルが、真ん中に置いてある。他には何もない。壁の右側は全面クローゼット。お洒落な気もするし、殺風景なだけという気もする。真奈美がこの部屋を見たらなんというだろうかと少し考えた。
「ごめん、開けて」
扉の向こうから須永の声がした。鞄を床に置き、閉めたドアを再び開ける。彼は右手に新品の焼き鳥焼き器を持っていた。そして、左手にはシルバーのトレー。その上には、串を綺麗に刺してあとは焼くだけという状態のものが三十本ほど並んでいる。須永は、ガラステーブルの上にその両方を置き、
「よし。やろう」
と嬉しそうに言った。
「これ、マイ焼き鳥器?」
「そう。昨日届いた」
「へえ」
須永はソファーに座ると、焼き鳥器の使用説明書をぱらぱらと復習するように見た。
「錦糸町に美味い焼き鳥屋があってね。で、もしかしたらあの味は家でも作れるんじゃないかと思ったらどうしてもやってみたくなって」
「へえ」
そういうところは、普通の男子とあまり変わらないのだなと綾乃は思った。とことん変人というわけではなく、とっつきやすい部分もあるようだ。少し親近感が持てて良かった。須永は一度キッチンに戻ると、次は半ダースの缶ビールと、封が開いていないたくさんの調味料を持ってきた。
「さて、焼きますか」
綾乃は、どこに座っていいかわからず、
「何をすればいい?」
と立ったまま須永に訊いた。
「君の仕事は、座って、そして食べること」
そう言って、須永はソファーの席を右にずれた。同じソファーに座れという意味のようだ。それが嫌なら床に座るしかない。そこで、綾乃は多少緊張しながら須永の隣に座った。
それから何時間も、須永は微妙に調味料の加減を変えながら、鳥を焼き続けた。綾乃はそれを、ただずっと眺めていた。
正直、会話はあまり弾まなかった。例えば、
「この部屋、南向き?」
と綾乃が訊く。
「ううん。北」
「へえ。北なんだ」
「日当たりの悪い場所に住むことが多かったから、慣れてるんだ。ていうか、むしろ薄暗い方が心地良いんだ」
「へえ。そうなんだ」
だいたいこのくらいで会話は途切れる。そして、綾乃は焼き鳥をかじりながら、次の会話のネタを一生懸命考える。
「そういえばこの部屋ってテレビないね?」
「ネットで十分情報とれるし、それにアプリ開発って、あんまり世の中のニュースと関係ないから」
「ふうん」
この会話も即座に終わってしまった。ちなみに、須永が開発して最初にヒットしたのは、シンプルな日記アプリだという。使用者は普通に日記を書くだけ。あとはアプリが自動でその他の情報を保管してくれる。カメラフォルダから、その日撮った写真や動画を紐付け。Wi‐Fi機能のあるスマート体重計と連動して、体重・体脂肪・脈拍などの健康管理。スマートウォッチと連動して運動の記録。GPSと連動して、その日の行動ルートも自動で記録されるらしい。綾乃はそれらを、合コンの後、Wikiで調べていた。確かに、日々、テレビから情報を収集する必要はなさそうだ。綾乃はビールを飲みつつ、また次の会話のネタを一生懸命考える。ふと、マガジンラックの中の雑誌が目についた。須永が表紙の雑誌である。
「表紙……ご両親喜んだでしょ?」
綾乃は訊いた。
「……ま、それなりに」
「そういえば、実家ってどこなの?」
「茨城の田舎の方」
「そうなんだ」
また会話が終わってしまいそうだ。そこで綾乃はもう少し粘った。
「須永さんのご両親ってどういう人なの? 須永さんみたいな天才を育てるって、ある意味親もすごいってことだよね? もしかしてスパルタだったとか?」
「全然違う。そもそも俺は天才じゃないし。学校嫌いで、学歴、高卒だし」
「え? そうなの?」
てっきり、東大とか一橋だとかを出ているのだと思っていた。
「お父さんとか、大学ぐらい行け!とか言わなかったの?」
「……」
不意に須永の顔が曇った。
「?」
「あんまり、父親の話はしたくないんだ」
「え」
「耳、悪いの? あんまり、父親の話はしたくないんだ」
怒鳴りこそしなかったが、綾乃が萎縮するのに十分なトゲトゲしさで須永は言った。
「そうなんだ。ごめん」
慌てて綾乃は謝ったが、それに対する須永の返事は、
「ところで、終電は大丈夫?」
だった。
終電の時間は、途中、こっそりと調べていた。まだ一時間以上は余裕がある。でも、それを言うより先に、
「そろそろ帰った方がいいかもね。もうこんな時間だし。お腹、いっぱいになったよね? じゃ、また連絡するから」
と次々に須永から言葉を被せられた。
「うん。わかった」
そのまま立ち上がり、綾乃は須永の部屋を出たのだった。
「もう連絡こないと思うよ」
そう綾乃は真奈美に言った。
「なんで?」
「なんとなく……地雷を踏んだから?」
そう自虐的に肩をすくめて見せた。
「でも、また連絡するって言われたんでしょう?」
「まあ、そうだけど……」
確かに「また連絡する」という須永の言葉を聞いたは聞いた。
「また、ってのがあるんだから、こっちから連絡してもいいんじゃないの?」
真奈美は、綾乃の目を覗き込むようにして言った。
「受け身ばっかじゃ都合のいい女になっちゃうよ。こっちからも攻めようぜ」
そういうものだろうか。
冷静に考えれば、須永というのは変わっているだけでなく、かなり自分に対して失礼な男である。どういう気持ちで誘ったのか。それも、店ではなく、いきなり家に。それでいて、ロマンティックなムードは一切なく、挙げ句の果てには追い出されるような仕打ちまで受けた。なのに、どうして自分はこんなに須永のことを考えているのだろう。そんなことをうじうじと考えながら、綾乃は食事を済ませ、そして、真奈美と別れて二階にある総務部に戻った。なんとなく、すっきりとしない、遅番の昼休みだった。
自分のデスクに座る。老朽化したビルの白壁は、タバコのヤニで黄ばんでいる。全フロアを禁煙にする決断が遅過ぎたのだ。大して広くないフロアには、デスクと黒い椅子が窮屈に並べられた五つの島がある。奥から社長秘書関係。法務関係。その他三つの島はざっくりと言えば雑務、雑用だ。綾乃はその雑務、雑用の島に属している。
十七時頃だったか。総務部長の戸田武が「恵比寿で爆発だってよ!」と興奮しながら外出先から帰ってきた。どこかでガス漏れでもあったのだろうか。それとも、ガススタンドか何かで事故でもあったのだろうか。が、その話題に乗る前に、ポケットに入っていたスマホがブルッと振動した。
そっとスマホを取り出し、通知画面を見た。
「!」
それは、須永からのLINEだった。
「また、ご飯食べましょう」
たったの一文である。
マジか。なんだ、これは。昨日のことは、この男の中ではどう消化されているのだ。こんなLINE、どう返事をしていいのかまったくわからない。仕方がないので、そのまま真奈美に転送し、仕事に戻った。
それから、定時まで、努めて須永のことは考えないように仕事をした。年末というのは雑用のピークの時期なのでやらなければいけないことが多く、集中するには都合がよかった。そして、気だるい定時のチャイムが聞こえてからも三十分くらい働き、キリのいいところでパソコンの電源を落とした。と、背後から、
「で、なんて返事をしたの?」
という声がした。振り向くと、真奈美が腰に両手を当てて、見下ろすように立っていた。
「……」
「まさか、まだ返信してないの?」
「……」
「しょうがないなあ、もう。じゃ、これ使いなさい。取引先からもらったの」
そう言って、真奈美が一枚の紙を差し出してきた。それは、最近渋谷で人気のイタリアン「リストランテ・ナカヤマ」のクーポン券だった。スパークリングワインがフルボトルで一本付くコースのディナー。期限は二十五日のクリスマスまで。格安クーポンサイトのチケットだ。
「こんなの貰えないよ。真奈美が彼と行けばいいじゃない」
「もう断られた」
「え?」
「クリスマスは家族サービスなんだって」
そう言って、真奈美は綾乃の隣のデスクに座り、両手で頬杖をついた。真奈美の不倫はもう四年になる。相手は二十歳も年上の男で、今まで一度も「いつか妻とは別れる」と言ったことがないのだという。男なんて選び放題のはずの真奈美が、もう四年もそういう男と付き合っていることに、綾乃はいつも男女関係の難しさを感じる。
「だからさ。これ、無駄にするのもったいないから、綾乃と須永さんで行って来なよ!」
そう真奈美は不機嫌そうに言った。
「いいよ」
「いいから」
「いいってば!」
「いいから!」
何度かチケットを互いに押し合ったが、結局、真奈美の押しの方が強かった。それで綾乃は、ありがたくそのクーポンを受け取ることになった。真奈美はその場でリストランテ・ナカヤマに空席確認の電話をかける。人気のレストランなので、普通はそんな近々の空きがあるとは思えない。格安クーポンサイトで販売している商品は、期限切れで使うことができなかった客を見込んだ上で商品価格を安く設定している。予約がとれないというのも計算済みのはずだ。ましてや、今日の明日とか明後日となると、まず、期待はできないと綾乃は思っていた。ところが、ところが。真奈美が電話をしつつ、綾乃にOKサインを笑顔で送ってきた。なんと、今日起きた恵比寿ガーデンプレイス爆弾事件の影響で、明日の十九時にキャンセルが出たという。真奈美は即、綾乃の名前で予約を入れた。
「空いてるし! 予約できたし! これはもう運命だね」
「何の運命よ」
「もち、あんたと須永さん」
「待ってよ。今日の明日だよ? 誘っても彼の方が無理かもしれないよ」
「そんなものは誘ってみないとわからないでしょ。さ、とりあえず誘ってみな」
「んー」
「早く!」
と、ろくに仕事もしないくせにいつもなぜかだらだらと会社に居残る戸田が、二人の会話に割り込んできた。
「おいっ。渋谷はやばいぞ。YouTubeで犯人からの犯行声明が配信されてるの知らないのか? 明日の十八時半に、渋谷ハチ公前で爆破予告だぞ!」
「は? 何ですか、それ」
真奈美が訊き返す。
「場所も時間もわかってるなら、そんなの警察か自衛隊がさっさと爆弾撤去しておしまいじゃないですか。その犯人、バカですか?」
確かにその通りだ。というか、恵比寿の爆弾がただの音と光だけの空砲だったことから、犯人は単なる愉快犯という説がネットでは圧倒的に多かった。夕方、お茶休憩を十分ほど取った時、綾乃もそのくらいは検索していたのだ。
「では、今日はこれで失礼します」
真奈美と二人、オフィスを出た。そして、ビルの外に出てすぐに、須永にLINE電話をかけた。昨日の焼き鳥のお礼に、コスパのいいイタリアンはどう? とても人気の店らしいんだけど。が、須永の返事は素っ気なかった。
「ごめん。大事な接待があって、明日の夜は東京駅近くの店で会食なんだ。じゃ、また」
ある意味、予想通りである。多分、本当にそうなのだろう。
「で、どうしよっか」
綾乃は真奈美を見た。
「女二人で行く? 男に断られた者同士」
「だね。明日は二人でやけ食いだ!」
そう、真奈美が苦笑いをしながら言った。
5
二〇一六年の十二月二十二日。
恵比寿ガーデンプレイスで爆弾事件があったその日の十六時半。
須永基樹は、パトカーやらテレビ局の名前の入った大型車でごった返す事件現場から離れ、とある喫茶店を目指して歩いていた。大通りから細道に入り、そこから三百メートルほど住宅密集地に入って行くと、古いビルとビルの間に窮屈そうに建つ一軒家に行き着く。二階は、店主の住居で一階がコーヒーとナポリタンしか出さない喫茶店。ここまで、須永がオフィスとして自宅とは別に持っている恵比寿のマンションから、歩いて十分ほどだ。
薄汚れたガラス窓から店内を覗くと、一番奥の四人掛けの席に、グレーのスーツを着た四十代後半の男が既に座っていて、店自慢のナポリタンを食べているのが見えた。背筋を伸ばしたまま、フォークに丁寧にパスタをからめ、口に運ぶ際は、左手を添える。行儀のいい食べ方だった。
建て付けの悪い木の重いドアを開けると、コーヒーの香ばしい匂いが鼻腔に広がる。男は、須永の姿に気づくと、ナプキンを手に取り、丁寧に口を拭きながら軽く会釈をした。入口脇のレジに立っていた七十代の白髪頭の店主にハウスブレンドを注文し、そのまま奥の席へと向かう。店内に客は、須永とその男の二人だけだ。この店は、だいたいいつも客がいない。そこを須永はとても気に入っていた。
「すみません。とても美味しそうなナポリタンだったもので」
言いながら、男は、ケチャップが少しだけ残った白い皿をゆっくりとテーブルの脇に押しやる。
「かまいません」
言いながら、男の前の席に須永は座った。
「大丈夫でしたか?」
「大丈夫……とは?」
「久しぶりにあんなに沢山のパトカーを見ました。なかなか派手な事件だったみたいですね」
「ああ。そうですね」
確かに、ガーデンプレイスの広場やその周辺は、今も警官とパトカーとマスコミと野次馬とで埋め尽くされている。
「私の前を歩いていた方が、職務質問をされていました。今日三回目だと嘆かれていました。おかしいですよね。私は、一度もされていないのに」
「怪しい人物ではないと、そう警官が判断したのでしょう」
須永がそう言うと、男はアイロンがきっちりとかかった青いハンカチで口を拭いながらクツクツと小さく笑った。
「さすが、日本の警察は見る目がありますね」
これはもちろん嫌味だろう。須永は本題に入ることにした。
「早速ですが……結果を教えていただけますか?」
「これはこれは、失礼しました」
男は、自分の右横の椅子の上に置いてあった黒いビジネスバッグを手に取り、ファスナーを開けて中からA4サイズのベージュの封筒を取り出した。それを、すっと向きを反転させ、須永の目の前に置く。
「まだ百パーセントの達成率ではないのですが」
須永は、封筒を開け、中に入っていた一枚の紙を取り出した。
「……」
男の言う通りだった。確かに期待していた内容ではない。
「今回、ちょっと時間が足りませんでした」
男は、素直に頭を下げた。
「いえ。ありがとうございました。残金は今日のうちに振り込みしておきますよ」
確かに、完全な回答にはなっていなかった。しかし、どのみち最後は自分で確かめるしかないのだ。そういう意味では、これでも十分に役に立つ。そうも思った。
「ありがとうございます。もし、きちんと住所まで押さえてくれということでしたら、改めてぜひお願いいたします。その時は、必要経費だけのご請求にして、うちの儲けはなしでいいんで」
「わかりました。その時はまたよろしくお願いいたします」
須永が頭を下げる。男は爽やかに微笑むと、さっと立ち上がり、店を出て行った。入れ替わりに、頼んでいたハウスブレンドが出てきた。須永は一人で、そのコーヒーを飲んだ。今日は彼の好みより、酸味も苦味もどちらも強過ぎる気がした。
携帯を確認する。
仕事用としてネットに公開している会社名義のメールも、全て彼個人の携帯に転送される設定になっている。新たなメールは何も来ていなかった。
喫茶店を出て、また自分の会社に戻る。一歩足を踏み出すごとに、気持ちがささくれていくのが自覚できた。たまにはプールにでも行って、気分転換に泳ごうかと考える。仕事場の近くに、二十五メートルが三レーンある小さな屋内温水プールがある。そこで無心に一キロくらい泳ぐのだ。それとも、誰か、まったく利害関係がない人間と、飯でも食うか。昨日、一緒に焼き鳥を食べたOLのことを思い出した。彼女には何の落ち度もないのに、後味の悪い会にしてしまったなと、須永は少し反省をした。それで、「また、ご飯食べましょう」とLINEでメッセージを送った。そしてその後、一時間ほど泳いだ。
須永のオフィスのある二十四階建てのマンションは、恵比寿ガーデンプレイスのすぐ脇にある。スペイン風の中庭に小さな噴水があり、その先にエントランスがある。木目調で統一された共用部分には、革の茶色のアンティークの椅子と、黒みがかった丸い机が、それぞれ三セット置かれている。左手にはカウンターがあり、髪をアップにし、黒いスーツに白いシャツを着た三十代後半の女性コンシェルジュが常駐している。いつも「須永様、おかえりなさいませ」とわざとらしいほどの笑顔で迎えてくれる。
が、今日は普段と雰囲気が違っていた。
見知らぬ男性二人と、少し困惑した表情で小声で何か話していたが、須永が帰ってきたのに気がつくと、慌てて、
「須永様、おかえりなさいませ」
と笑顔なしで言い、手元のボタンを押して、奥のエレベーターホールへのドアを開けた。須永は軽く会釈をして、彼らの横を通り過ぎ、二基あるうちの手前のエレベーターに乗り込んだ。
と、二人の男のうち、年配の方が、
「あ、ちょっとすみません」
と声をかけてきた。そして、二人して小走りに同じエレベーターに乗り込んできた。
「お名前、教えていただいていいですか? あと部屋番号も」
「は?」
「おっと、失礼。私たち、こういうものです」
男が手帳を取り出した。警察手帳だった。
「警察、ですか?」
「はい。今日のガーデンプレイスの事件の件で聞き込みをしてまして。私、渋谷署の世田と言います」
隣に立っていた若い男も警察手帳を出した。
「同じく泉です」
「……」
「で、お名前、教えていただいていいですか? あと部屋番号も」
温和な声と話し方だったが、世田という男からは拒否はさせないという意思が感じられた。なので、須永は素直に答えた。
「須永と言います。このマンションの一四〇二号室がオフィスなんです。免許証とか確認しますか?」
須永は免許証を財布から取り出して、彼らに見せた。
若い方の警察官が恐縮そうに頭を下げた。
「ご協力感謝いたします。拝見いたします」
その横で、年配の方が「14」のボタンを押した。ドアが閉まり、エレベーターは上昇を始めた。須永は、少し胸騒ぎを覚えたが、言葉は出さなかった。
「……ええと、須永基樹さん。三十歳。本籍は、茨城県。現住所は、祐天寺……お住まいは、このマンションではなく祐天寺ですか?」
若い方が訊いてくる。
「ええ。ここはオフィスとして持ってるんです。駅が近くて便利なので」
「須永さん、社長さんってことですか? 若いのにすごいですね」
若い方が、免許証を須永に返しながら言う。
「小さな会社ですよ」
「いやいや、こんな立派なマンションにオフィスが構えられるなんてすごいですよ。ところで、何の会社なんですか?」
「アプリを作ってます。iPhoneやAndroidの携帯にインストールして使うアプリです」
「へええ。すごいなあ」
若い方が、とにかく「すごい」を連発した。エレベーターは十四階に到着した。出る。男たちも当然のように出る。若い方が、
「あ! もしかして、須永さんて、雑誌に出てませんでしたか?」
と大きな声を出した。
「ええ。まあ」
「やっぱり! すごい!」
と、その時、須永の携帯が鳴った。
「ちょっと、失礼……電話に出てもいいですか」
画面を確認する。印南綾乃の文字がディスプレイに表示されていた。電話に出てみると、明日、一緒に食事をしないか、という誘いだった。昨日の焼き鳥のお礼。コスパのいいイタリアン。とても人気の店らしい。
「ごめん。大事な接待があって、明日の夜は東京駅近くの店で会食なんだ。じゃ、また」
そう言って、手短に電話を切った。
「で、聞き込みは始めなくていいんですか?」
「そうでした。そうでした。今日のあの爆弾騒ぎの時、須永さんはどちらにいらっしゃいました?」
「オフィスにいました」
「お一人で?」
「はい。一人で」
「爆発は目撃されました?」
「いえ、仕事に集中していたので」
「音も?」
「はい。窓は閉めていましたし、音楽もかけていたので気がつきませんでした」
「そうですか」
年配の方が、右の顎の下あたりを薬指で小さく掻いた。
「ところで、ここ最近、怪しい人を見かけた記憶はありませんか?」
「怪しい人?」
「はい。漠然とした質問で恐縮なのですが。どんな些細なことでも結構です」
「ないですね。全然ないです」
「そうですか。ご協力ありがとうございます。では、我々はこれで」
男たちはそう言うと、エレベーターの「▼」ボタンを押した。須永は彼らに軽く頭を下げ、一四〇二号室のドアを開けて中に入った。
「ただいま」
声に出して言ったが、オフィスからはもちろん返事はない。電気を点ける。四つ向かい合わせに白いデスクが置かれている。ワーキングスペースはいつもすっきりと片付けられ、パソコンとキーボードしか置かれていない。今日は、席にも誰も座っていない。須永の会社では、出勤して仕事をしても在宅で仕事をしてもどちらでもいいことになっている。社員は全員プロジェクトごとの契約制で、人数は時期ごとに変動する。今は、二十代の女性社員と三十代の男性社員が一人ずつ。今日はどちらも出勤していない。須永は部屋を横切り、更に奥右側のドアを開けた。
八畳の広さの須永の部屋。つまり、社長室。窓に背を向ける形で、長く大きな黒いデスクが一つ置いてある。そのデスクの上には、パソコンとモニターとキーボード。他には何もない。椅子に腰を掛け、キーボードのエンターキーを叩く。〇・二秒でパソコンがスリープ状態から復帰する。
デスクトップ画面に、音声ファイルが一つ置かれている。実は、須永は今日の夕方からずっと、この音声ファイルを繰り返し再生しては聴き直しているのだ。
録音時刻は十五時四十二分。
すぐ隣の恵比寿ガーデンプレイスの広場で、爆発事件があった直後である。
くぐもって不明瞭な男の声。だが、俺にはわかる。これは、あいつの声だ。
須永の脳裏で、ずっとそうもう一人の自分が喚いている。
これはあいつだぞ。あいつに決まっている。これは絶対にあいつからだ。
と、インターフォンが鳴った。
来客の予定はない。宅配か何かだろうか。椅子から立ち上がり、壁に付いているモニターカメラの映像を見た。玄関の外にいたのは、さっきのあの警察官たちだった。
……番組の途中ですが、臨時ニュースをお伝えします。
本日、恵比寿ガーデンプレイスの広場において爆弾騒ぎがありましたが、その件について、磯山首相が声明を発表いたしました。
首相官邸前から秋元アナウンサーがお送りします。秋元です。本日、磯山首相は、首席秘書官を通じて下記のコメントを発表いたしました。読みます。
「日本国は、テロには屈しません。日本国は、テロリストといかなる交渉もいたしません。日本国は、テロリストの非道な犯罪に対して、断固、不退転の決意で戦うのみです」ということは、犯人が要求している、テレビの生放送番組での対話については、これを拒否するということですね?
はい。そういう結論になるかと思います。繰り返します。本日、磯山首相は、首席秘書官を通じて下記のコメントを発表いたしました。「日本国は、テロには屈しません。日本国は、テロリストといかなる交渉もいたしません。日本国は、テロリストの非道な犯罪に対して、断固、不退転の決意で戦うのみです」