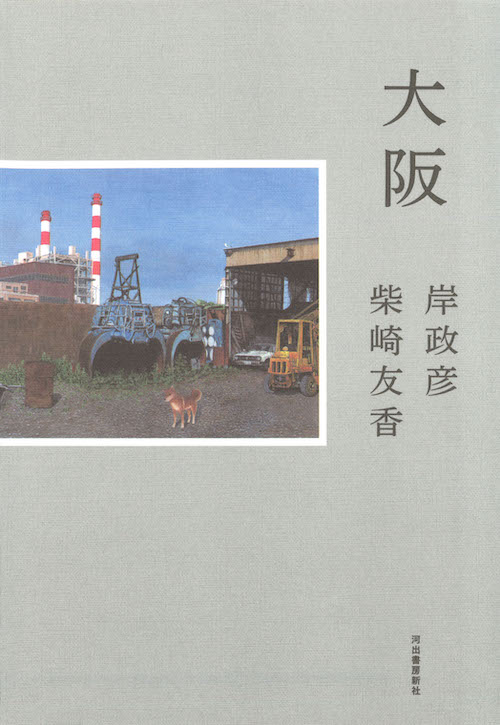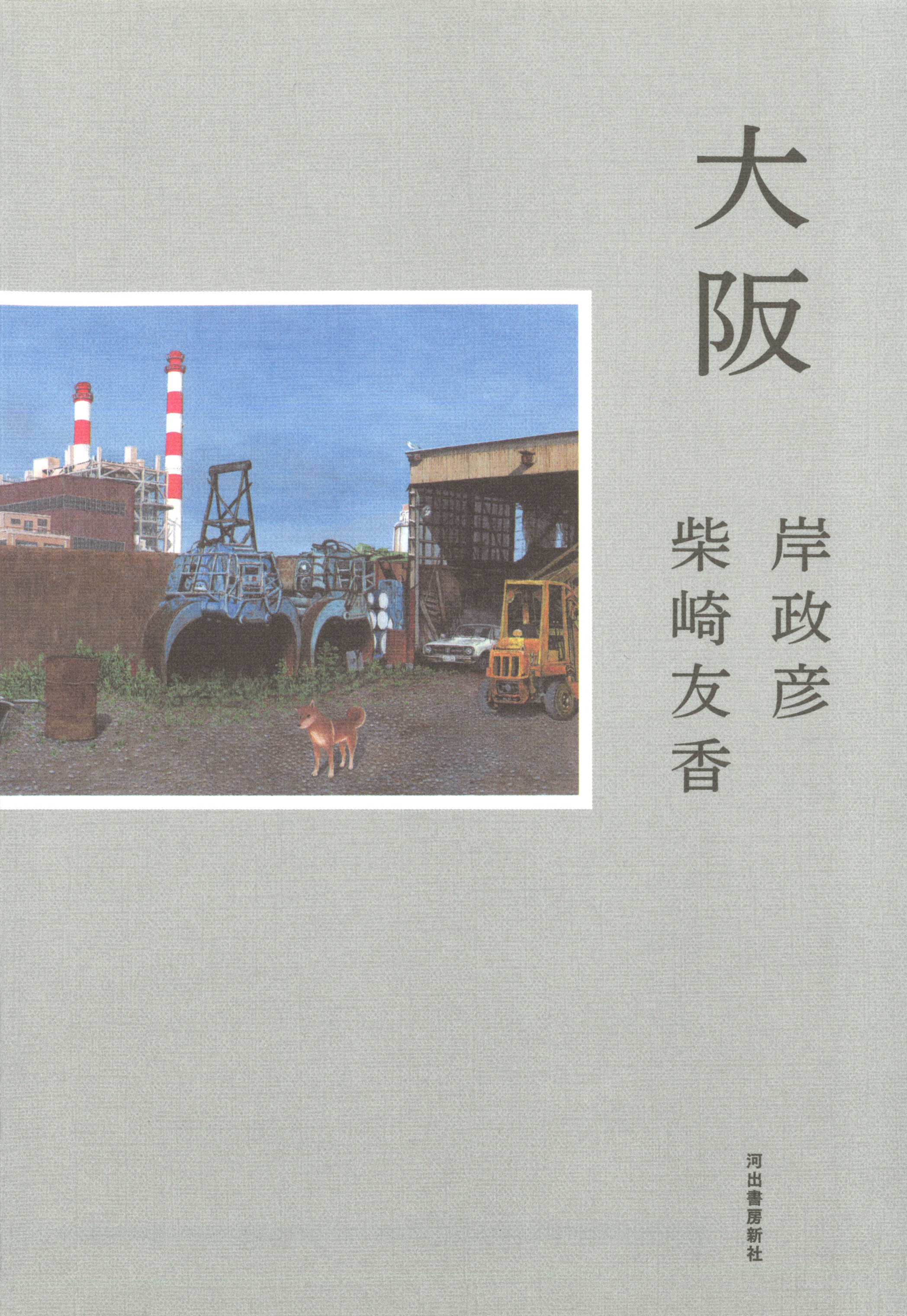
単行本 - 日本文学
岸政彦・柴崎友香の初共著エッセイ『大阪』より「おわりに」を特別公開
柴崎友香
2021.02.22
「文藝」連載時より反響を読んだ、岸政彦さんと柴崎友香さんによる初共著エッセイ『大阪』。大学生のときに大阪に住みはじめて現在に至る岸さんと、20代後半で生まれ育った大阪を出て東京に住み始めた柴崎さん。おふたりの「大阪」への交差する視点は、世間一般で言われがちな「コテコテ」「たこ焼き」「アクが強い」といった「大阪」イメージとは異なる、誰もが知っているけれど知らなかった、大阪の街と、そこに生きる人々が描き出されています。
誰もが持つ、住んでいる/暮らしたことがある土地への思い出。
街のどこか、あのとき、あの場所ですれ違っていたかもしれない、あの人。
『大阪』は、私たちが生きてきた土地と出会った人々への捨てられない想いを、やわらかく浮かび上がらせてくれるようです。おかげさまで好評につき重版となりました。
おわりに
柴崎友香
二〇二〇年十月の最終月曜日、わたしは大阪にいた。
新型コロナウイルスの影響で、二月にナンバーガールのライブを観に来てから、八か月半ぶりの大阪。そんなに長く大阪を離れていたのも、東京から出なかったのも、初めてだった。
大丸心斎橋店のウェブサイトの、いくつか店を回って商品を紹介するという広告記事の仕事で、大阪に行くのはずっと躊躇していたが、依頼をもらったころは新型コロナウイルスの感染者数も落ち着いていたし、大丸やし、ということで、受けることにしたのだった。
二〇一九年に建替えの終わった本館のオープニングイベントに招いてもらって以来だが、そのときはゆっくり見ることができなかったので、あちこち回れるのはうれしかった。平日ということもあり、心斎橋筋商店街も人通りはかなり少なく、お昼時のレストランフロアも静かだった。
近江八幡の会社でヴォーリズとも縁があって、元の建物の照明器具を引き継いでつかっている和菓子の「たねや」や、二十年以上愛用している「ディーゼル」などをまわった。いつだったか、ディーゼルジャパンの本社が大阪だと知ったときは、あー、このなにか余分なものを絶対付け加えないと気が済まないデザインは、大阪の人が好きそうやもんなあと納得した。
取材が終わってから、ディーゼルとたねやで買い物をし、天ぷら(練りもののほう)の大寅でうめやきを買い、大丸を出て、心斎橋筋商店街をひたすら南へ下った。毎日のように歩いていたころからある店もあるが、三分の二くらいは入れ替わっていて、この角はなんやったかなあ、と思いながら歩いた。幅が広くなった戎橋から見えるグリコの看板は、いつの間にかネオンではなくのっぺりとした板状のものになっていた。道頓堀でも千日前でも街頭ビジョンでは「YES!都構想」のCMが延々と流れていた。十二月に閉店する生地の「とらや」の写真を撮り、高島屋の前まで出てなんば南海通りへ入り、昔と変わらず筆書きの新刊案内が掲げてある波屋書房を通り過ぎ、堺筋のほうへ向かえば、今は飲食店がにぎやかに増えて「ウラナンバ」と呼ばれるようになったあたりに、美容学校へ通っていたときに曲がる目印だった地味で愛想のない家具屋がそこだけ時間が止まったみたいに変わらずにあった。
通常料金からだいぶ安くで泊まれたホテルは、昭和の初期に松坂屋大阪店として作られ長らく高島屋別館の事務所として使われてきた近代建築だ。今年、外資系の滞在型ホテルとしてリノベーションされたばかりで、キッチン付きの部屋は快適だったし、一階のアーケードやエレベーターホールも昔のまま残されていた。難波の中心から離れているので油断してるうちに周囲の飲食店は閉まってしまい、コンビニで肉うどんを買ってきて食べ、本を読んで早々に寝た。
朝、チェックアウトして黒門市場を十年以上ぶりに歩くと、角でおっちゃんたちが、ウーバーイーツどないでっかて言われてまんねん、と立ち話をしていた。「どないでっか」「まんねん」も、商業用大阪弁というか、日常会話では使わないのに大阪で商売をするとあっというまにその言葉を友人も仕事中は言うようになったのを思い出す。
雲一つない青空で、数年ぶりに乗った近鉄奈良線の生駒へ上る車両からは大阪の街が一望できた。この風景は死ぬほど好きだ。
奈良に着いて、奈良公園の広大な公園と鹿を見ると、東京も大阪も人間のあれやこれやがしんどいし、奈良に住もかな、木ぃと鹿に囲まれときたい、という気持ちが湧いてきた。
極力移動しないように生活していた中で大阪での仕事を受けたのは、奈良市写真美術館の「妹尾豊孝展」を観に行くためでもあった。卒論の資料を探しにいった大阪市立中央図書館の「大阪の本」の棚で出会って以来、わたしは「大阪環状線 海まわり」というその写真集を繰り返し眺めてきた。そこに写し取られた大阪環状線の西側、福島区、此花区、港区、大正区の光景は、まさに自分の見てきた場所だった。自分の家があり、通った高校があり、友達の家がある。妹尾さんの写真は、そこに写っている一人一人にも、建物や看板にも、その前後が見える。この前にあったこと、このあとに起きること、それが連なった人の暮らし、人の暮らす街。写真の下のプレートには、その場面を説明するひと言と、地名だけが書かれていた。
展示室に入ったときはわたし一人だったが、しばらくして七十歳くらいの夫婦が入ってきた。これはどこかしら? 地名を見ても土地勘がないからわからないわね。話し方やたとえている地名から、おそらく東京から来た人なのだろうと思った。
わたしは、展示室の真ん中に座って、大正区の写真をじっと眺めていた。夫婦が、そこに立った。
「どんな街なのかしらね」
「この子、このあと川に落ちたんだってさ」
そこ、わたしの街なんです。わたしが生まれ育った街なんです。そのやたらと植え込みの木が伸びてるのはたぶん保育園の前の道をちょっと行ったとこで、柱がタイル張りの戦前からあるアパートって書いてあるのは十五年ぐらい前までは半分朽ちてたけどまだあって、その運河の船で遊んでる子らはもしかしたら友達の弟かも。
よほど話しかけようかと何度も声に出しかけたが、結局はわたしは黙って座っていた。
その風景は、一九九〇年前後だが、木造の長屋や小さな商店の造形からもっと昔に見える。「バブルの喧噪から取り残された」とか「人情が残る」とか、そんなふうに安易に紹介されてしまうかもしれない。
違う。そんなわかったようなフレーズでは絶対にとらえられないもの、伝わらないことがここにはある。一人一人の生きている時間が、暮らしてきた場所が、確かにある。
それを、わたしは書きたい。
東京に長くいると、入ってくる大阪のことは「情報」になっていく。大阪に実際に帰って、街を歩いて、人が話していて、その中にいると、大阪やなと思う。難しいことも山積みだけれども、この街で人の暮らしは続いていく。
今は大阪市民でない、大阪に住んでいないわたしが、大阪の今についてなにをどう言うべきなのか逡巡し続けている。ただ、大阪がいろんな人にとって暮らしやすい街、生きていける街であってほしいと願っている。いろんな人が暮らすためのだいじなところを「無駄」と切り捨てないでほしいと思う。
「大阪」のことを書くのでなければ、共著という形でなければ、ここに書いたことは書くことがなかったかもしれない。大阪にやってきた岸さんがいて、岸さんが見た大阪のことが書かれて、それを読んでわたしが思い出すこともあって、また書いて……。わたしが神楽坂でのイベントで岸さんに初めて会ったときには、東京に移って十年が経っていた。わたしと岸さんは大阪で出会わなかったけれど、同じ時期に大阪にいて、どこかですれ違ったり、もしかしたら同じ映画館や店にいたかもしれない。岸さんがよく散歩してるあたりは、そこにもここにも友達の家がある。地名を聞くたび、何組の誰々さんのとこや、と思う。何度もすれ違ったかもしれなくて、でも知らずに過ごしていて、それぞれが自分の暮らしを生きていて、そんな人の軌跡がいっぱい重なり合っている。それが街だし、わたしと岸さんはそんな大阪を共有していた。
だから、「自分の話を書きたかった」というのではなかった。四十年以上見続けてきた大阪を書くのに、たまたまその街で生まれた一人の人間をサンプルにして眺めてみようと思った。そのために使えるところだけ書いたから、それは端的に言うと暴力的なことかもしれないと思う。物事も人も、とても複雑でとらえきれないものなのに、ある一面を言葉で書く。ここに書いた「大阪」は、ほんの一部分のさらに断面でしかないのだ。『その街の今は』や『ビリジアン』や『わたしがいなかった街で』など、身近な大阪の風景を書いてきて、フィクションにしてもそうでない文章にしても、書くということは常に多かれ少なかれ力を持つことで、この仕事を始めて二十年が過ぎたけれど、書けば書くほど、おそれる気持ちは大きくなる。
それでも、なにかしら毎回書いたのは、誰かから見た断片を、道を歩いて考えてきたことを、積み重ねることでしか街の全体はわからないし、東京で暮らしていて大阪のことは全然知られていないと思うことが度々あるからだ。連載中に読んだ大阪に縁のある人が、メンバメイコボルスミ11やナンバブックセンターや「シネマ大好き!」などもう今はなくて、昭和や平成を振り返る的な特集で取り上げられるほぼ形骸化した定番のものごととちがってほとんど語られることもない大阪のあれこれに、自身の記憶や経験を重ねて感想を伝えてくれたことも大きかった。
そういうふうに、自分の書いたものが誰かにとってのひとつの場所みたいになるならそれでいいなと、このところ小説を書いていて、考えている。
自発的に旅行ができないわたしが、この数年間は仕事のおかげで十以上の国や街に行くことができた。東京も八戸もニューヨークもダブリンも台北もソウルもアラン島もモスクワも、どこも同じように好きだ。どこへ行っても、人の暮らしがあるところは好きだ。道端でほんの数秒だけ隣合った人の存在を感じるのが好きだ。誰もいないベンチや階段にも、人間の感じが残っているのが好きだ。どうにかその日その日を生きている人たちが、歩く道、住む部屋、食べに行く店、立ち寄る本屋、待っているバス停、無数のそれらが集積して、その隙間に自分もいてもいい気がする、そんな場所が好きだ。そこで生きている人のことを考えるのが好きだ。
生まれた土地がその人に合っているとは限らないし、何歳になっても別の国や街に行ってみたらそここそが最良の場所になるかもしれない。たまたま生まれて育って、自分で選んだわけではないけれど、大阪で暮らしていなければ今のわたしではなかったし、これからどこに行っても、どこで出会った人にも、ここがわたしの街です、と言うだろう。
二年近くにわたって書き継いできた「大阪」がこうして一冊の本になりました。この本にこれ以上ないくらいすばらしい装画は、小川雅章さんの絵です。最初、岸さんからこの方の絵がものすごくいいとSNSのアカウントを教えてもらい、どの絵もあまりにわたしにとっての大阪が描かれていて、子供のころにさまよっていた場所そのもので、そしてこの風景をこんなふうに描くことができるなんて、と衝撃でした。夢中で遡って見ていたら、見覚えのあるご夫婦の姿がありました。まさか絵を書かれたのが、何度も通って今でも食べたくて仕方ない担担麵の楽天食堂のご主人だったとは! アメリカ村の大好きな場所としてこの連載の中でも書いていました。絵を使わせていただけて、無上の喜びです。
その絵を素敵な装幀に仕上げてくださった名久井直子さん。「東京の友達」である名久井さんには東京のいいところをたくさん教えてもらったし、わたしの小説もエッセイも美しい形にして読者のもとへ届けてもらって、とても信頼しています。
そして、この連載を提案してくれた「文藝」編集長の坂上陽子さん。関西の同世代である坂上さんとも、原稿のやりとりをしながら大阪のいろんな場所やできごとを話し、どこかですれ違っていたかもと思うことが多々ありました。
いくつもの出会いと歩いた場所が、この本を支えてくれています。この本に関わってくださった方、この本を手に取ってくださった方に、心から感謝します。