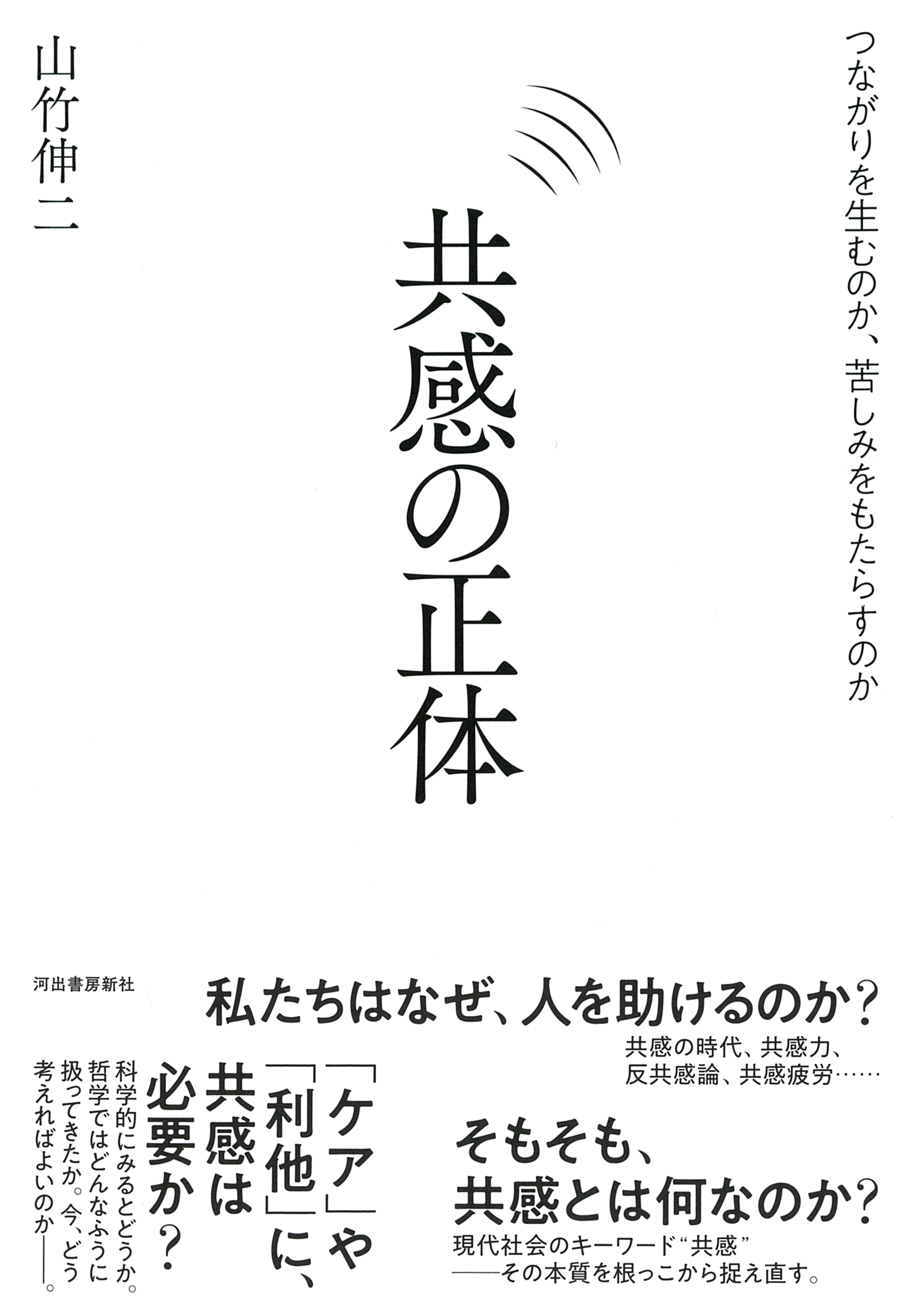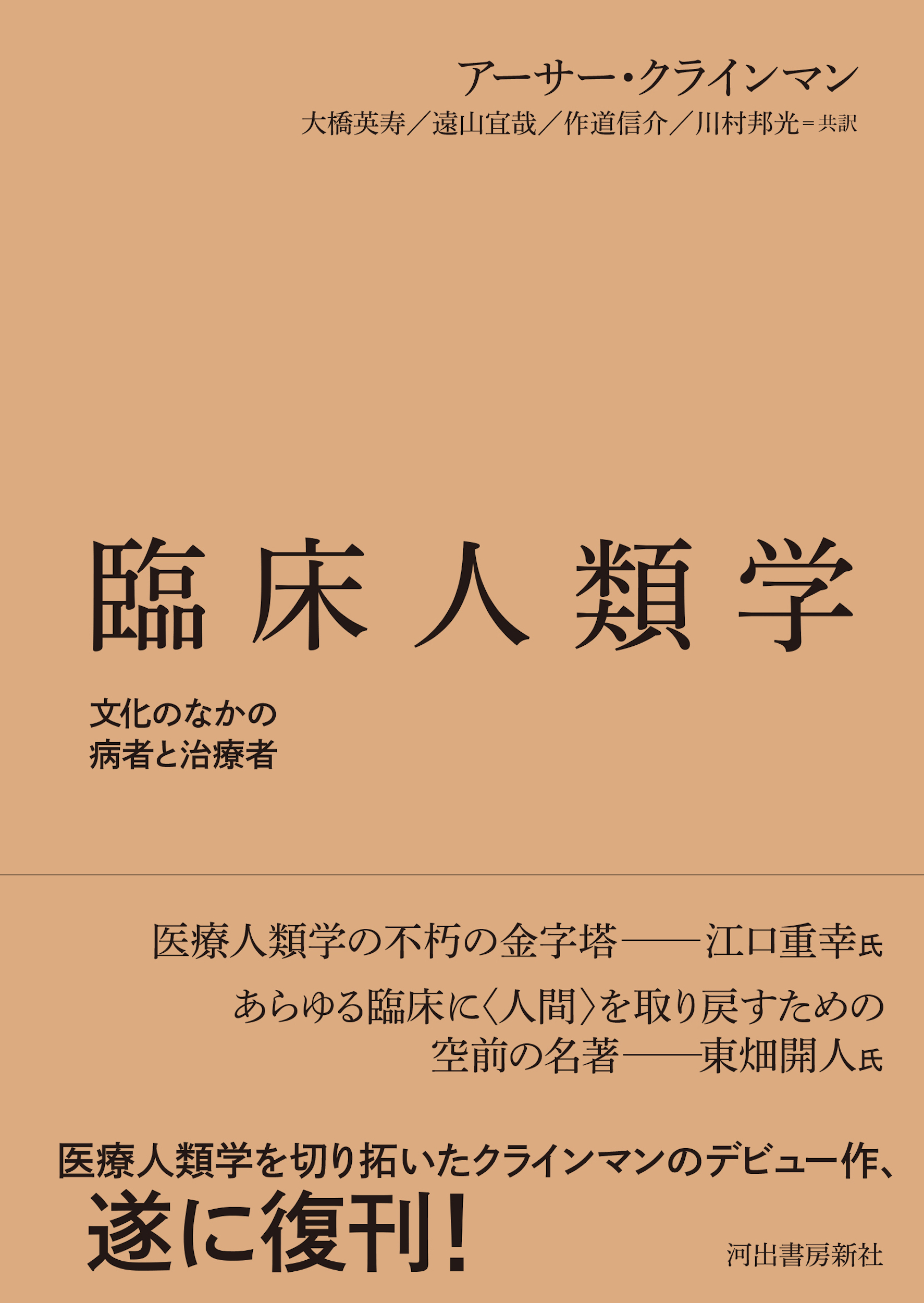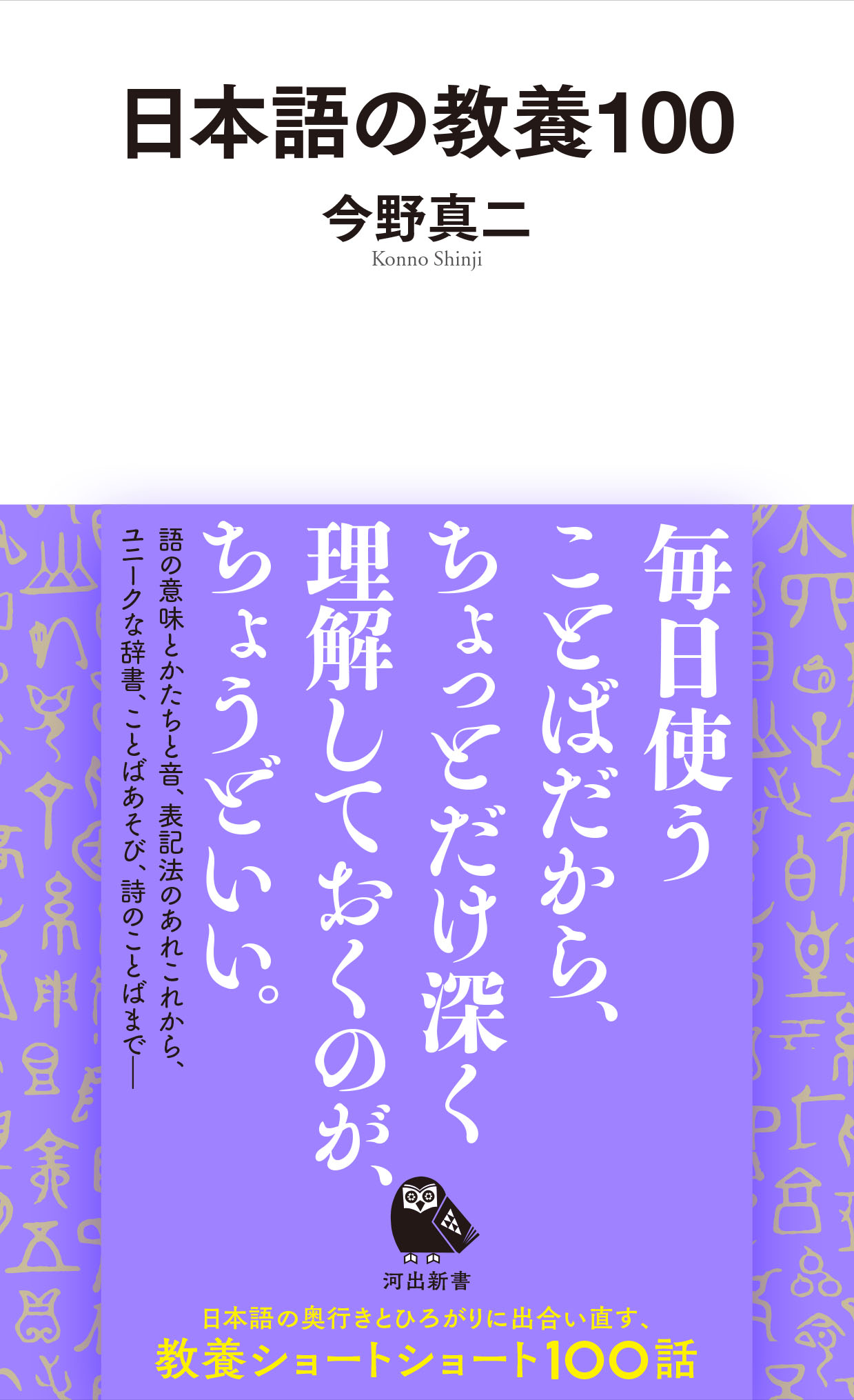
単行本 - 人文書
今野真二『日本語の教養100』(河出新書)刊行記念 往復書簡 「知識の沼――ことばで巨人の肩にのる」第4回 今野真二→山本貴光
今野真二
2021.06.01
10年以上にわたって多彩な視点から日本語をめぐる著作を発表しつづけてきた今野真二さん。その日本語学のエッセンスを凝縮した一冊とも言える『日本語の教養100』が刊行されました。これを機に、今野日本語学の「年季の入った読者」と自任する山本貴光さんとの往復書簡が実現。日本語についてのみならず、世界をとらえるための知識とことば全般に話題が広がりそうな、ディープかつスリリングな対話をご堪能ください。
第1回はこちら。
第2回はこちら。
第3回はこちら。
* * * * *
山本貴光さま
今野の勤務している大学は、まずは「対面授業」でスタートしましたが、今はまた「遠隔授業」になっています。山本さんの「オンライン講義」のこと、興味深く拝読しました。
さて、前便で「taking seriously©リチャード・ローティ」という表示について質問させていただいたのですが、「そうだったのですね!」と思いました。先例を重んじる、とてもすばらしい考え方だと思います。
議論をする場合、意見を交換する場合に、今野が大事だと思っているのは、「枠組み」です。どういう「枠組み」の中で議論や意見交換をするか、ということによって交換するべき「情報」が変わってきます。「枠組み」が大きくていろいろな「分野」を覆うものであれば、その大きさにふさわしい「情報」を交換しなければならないし、「枠組み」が小さく具体的であれば、それにふさわしい具体性をもった「情報」の交換が求められます。
「枠組み」と重なり合いもあると思いますが、どのような「用語」で説明をするか、ということも大事だと思います。学術研究の場でいえば「用語」は「学術用語(academic terms)」ということになるでしょう。「学術用語」は一つ一つ(ある程度)きちんと定義されています。その定義を前提にし、共有しながら議論、意見交換が行なわれるわけです。
「taking seriously©リチャード・ローティ」の「taking seriously」は「用語」というよりは「表現」といったほうがいいのかもしれません。しかし、この表示方式は、この「表現」のしかたは重要だ、と吉川さんと山本さんが感じ、「その表現の考案者に対する敬意」を示す表示形式であり、そこには「定義」と先人への敬意ということについてのはっきりとした意識が感じられ、かぎりなく「(学術)用語」にちかいものだと思います。しかもちょっとおしゃれ(お茶目?)な感じがするところがとてもいいですね。
何を表現するにしても、どのように表現するかを考える必要があり、表現に使う語は(中には初めて作られた複合語もあるかもしれませんが、多くの場合は)どの語も誰かがかつて使った語であるはずです。だからこそ、先人の使った「用語」に丁寧に接するということは大事なことだと今野も考えています。このことについては、山本さんも「知識を伝える手段として使っている言葉からして、自分でつくったものではありません」と述べていらっしゃいますね。
*
今野は現在の勤務先に着任する前に、4年間、高知大学に勤めていました。大学から自転車で10分程の距離の官舎にいたので、通勤時間もほとんどなく、いろいろなことをする時間が充分にありました。その時間を使って、毎日亀井孝の論文集と、吉川幸次郎の全集を読み、「抜き書き」を作っていました。
亀井孝は「ペダントリーのために」(『一橋論叢』第69巻第5号、1973)という論文(『亀井孝論文集6 言語 諸言語 倭族語』吉川弘文館、1992、所収)の冒頭ちかくで、「およそわたくしはわたくしなりに、ことばのことをそもそも職とするものとしてのそのペダントリーから、まず学問はことばであると考えている。これにちなんで、もって学問にわたることどもを表現の目的とする文章のその形骸、ここにまさにわたくしのばあいはおおいにこだわりたいのである」と述べています。「学問」といわれると、少し身構えてしまいますが、言語で何かを表現するにあたって、重要なのが「まずことばである」という主張と読み替えることができそうです。
『広辞苑』第7版(2018)は見出し「けいがい」を「①からだ。肉体。むくろ。生命や精神のないからだ。建物などのさらされた骨組」「②中身が失われて外形だけ残っているもの」と2つに分けて説明しています。「ケイガイカ(形骸化)」の語義は「当初の意義や内容が失われ、形ばかりのものになること」(『広辞苑』)ですので、「ケイガイ(形骸)」という語も、どちらかといえば、②の語義が思い浮かぶかもしれません。
『広辞苑』の①の説明も、「生命や精神のない」あるいは「さらされた」という表現が、現代風にいえばネガティヴな傾きをもっているように感じられますが、もともとは「からだ。肉体」という語義をもっているわけです。亀井孝は、文・文章を「からだ=形骸」と「生命・精神=内容」と分けてとらえ、まずはその「からだ=形骸」に「おおいにこだわりたい」と述べていると思われます。この文・文章のとらえかたは、今野の考えている「器」と「情報」というとらえかたと重なります。というよりも、今野はこの亀井孝のとらえかたを採り入れて現在のとらえかたに至ったというべきなのかもしれません。そうであれば、今野が何かの折に、「文章の形骸」という表現を使うにあたっては「文章の形骸 ©亀井孝」と表示することになります。
現在日本で出版されている最大規模の漢和辞典である『大漢和辞典』(大修館書店)を調べると「形骸」は「からだ。肉体。形体。又、外貌」と説明されています。使用例として『荘子』があげられています。『大漢和辞典』には同じ『荘子』に「形骸之外」「形骸之内」という表現が使われていることも示されており、前者は「肉体の外面。心徳を内とするに対して肉体・形貌を外といふ」、後者は「人の肉体の内。心・精神・道徳をいふ」と説明されています。
荘子は、中国の戦国時代の思想家で、著書とされる『荘子』は西晋の郭象(252-312)がまとめたと考えられています。つまり、中国の戦国時代(紀元前5世紀 – 紀元前221年)には「肉体」と「心・精神」とを分けてとらえる「みかた」があったことになります。そして、「形骸」はその「肉体」のことだったということになりそうです。
長々と何を言っているのだろうと思われるかもしれません。今野は碩学、亀井孝が「文章のその形骸」と表現したのはなぜか、と思うからです。そして調べてみると、今野が思っている「ケイガイ(形骸)」の語義と、亀井孝が思っている語義とが違うのではないかというところにたどりついた、ということです。亀井孝は『荘子』に「ケイガイ(形骸)」という語が上記のような語義で使われていることを知っていたから、その線で、この語を使ったわけです。もしかすると、今野のように「あれ?」と思う人が、論文を発表した1973年当時にもいたかもしれません。それをも予想して、あえて「ケイガイ(形骸)」という語を使ったと予想するのは考えすぎでしょうか。何しろ論文のタイトルは「ペダントリーのために」です。
*
脱線ついでにいえば、『広辞苑』第7版の「けいがい」の語義①はすでに語義②にいわば「浸食」されているようにみえます。『広辞苑』の語釈を批判しているのではありません。辞書も人間が作るものである以上、(結果的には)作っている人の「内省」をもとに作られることになります。作っている人の「心的辞書」を反映したものになることはむしろ当然といっていいでしょう。それだからこそ、「辞書をよむ」ことがおもしろいわけです。ちょっと『広辞苑』を調べてみました。『広辞苑』の「前身」と位置付けることができる『辞苑』も加えてみます。
『辞苑』(1935)からだ。身体。
初版(1955)からだ。身体。むくろ。
第2版(1969)①からだ。むくろ。②中身が失われて外形だけ残っているもの。
第3版(1983)①からだ。むくろ。生命や精神のないからだ。②中身が失われて外形だけ残っているもの。
第4版(1991)[荘子徳充符]①からだ。肉体。むくろ。生命や精神のないからだ。建物などのさらされた骨組。②中身が失われて外形だけ残っているもの。
第5版(1998)[荘子徳充符]①からだ。肉体。むくろ。生命や精神のないからだ。建物などのさらされた骨組。②中身が失われて外形だけ残っているもの。
第6版(2008)[荘子徳充符]①からだ。肉体。むくろ。生命や精神のないからだ。建物などのさらされた骨組。②中身が失われて外形だけ残っているもの。
第7版(2018) [荘子徳充符]①からだ。肉体。むくろ。生命や精神のないからだ。建物などのさらされた骨組。②中身が失われて外形だけ残っているもの。
第4版から第7版までは語釈が同じであることがわかります。一方、②の語義が加わったのは、1969年の第2版からです。となると、1973年の時点では、先に述べたように、②の語義で「ケイガイ(形骸)」という語を理解していた人はいそうです。第4版からはこの語が『荘子』で使われていることが積極的に示されているようにみえます。そこで、『荘子』にもどってみれば、この語がどのように使われているかを確認することができます。こういうことは大事なことですが、もしかすると、せっかくの出典の表示が「形骸化」してしまっているのかもしれません。
*
さて、脱線を続けてきました。索引の話に入りたいと思います。
山本さんと吉川さんとの「印象に残っていた『ニーチェ全集』の索引」は是非とも見ておかなければ、と思い購入しました。やはり「事項索引」が「!」です。「三脚台」って何だろうと502ページを見てみるとか、いささかふとどきではありますが、そういう「拾い読みの手引き」にもなりそうです。
「索引」は誰かが作るものだということはわかっていましたが、すでに付けられている「索引に物足りなさを感じたら、自分で追加してもよい」というくだりは「なるほど」です。「索引をつくるのは、本をどう読むかということにつなが」るということもまったく同感です。索引は、何がこの本のキーワードか、ということとも重なり合いがあるはずです。
「巨人の肩の上」という表現についての追跡、興味深く拝読しました。その中に、「ローレンス・スターンの脱線小説『トリストラム・シャンディの生活と意見』の主人公の名前にあやかった形容詞」というくだりがありました。
実は、必要があって、サミュエル・リチャードソンの「パミラ」を読んでみようと思った時に、筑摩書房から出版されている『世界文学大系33』(1966)を入手したのですが、この33には海老池俊治訳の「パミラ」とともにスターンの「紳士トリストラム・シャンディの生涯と意見」が朱牟田夏雄訳で収められていたのです。
「主人公のないこの『物語』には、普通の意味での筋の展開がない。そればかりでなく、数人の人物の交渉から生じる種々な事件が、相関連するかのように、また、せぬかのように、語り続けられる間に、時折、前後と何の関係もないように見える不可解な談義や挿話が挿まれる」(海老池俊治『第十八世紀英国小説研究』研究社、1950)と評される「トリストラム・シャンディ」は「物語」に対していえば「非物語」といってもよいかもしれません。1969年にはやはり朱牟田夏雄訳で、『トリストラム・シャンデイ』(上中下3巻)が岩波文庫として出版されていますし、1987年には綱島窈(ふかし)訳『トリストラム・シヤンディ氏の生活と意見』(八潮出版社)が出版されています。こうなると、朱牟田訳と綱島訳とを比べてみたくもなるのですが、それはまた機会があったらということにしましょう。昭和16(1941)年に河出書房から出版された、伊藤整『得能五郎の生活と意見』のタイトルは「トリストラム・シャンディ」から採ったことが指摘されています(どこが? という声が聞こえてきそうですが)。
*
現代においては、学術的な論文や著書までもが、「物語」を意識して(直線的に)書かれる「傾向」があります。そういういわば人為的に「仕立てられた物語」ははたして「物語」といえるのかどうか、とも思います。
山本さんはたくさんの書物を丁寧に読んでいらっしゃると拝察します。今野は必要に応じていろいろな本を読みはしますが、中には読み切らないままになっている本も少なくありません。その点、お恥ずかしい限りと言わなければなりません。
さて、「トリストラム・シャンディ」という書名を見た時に、「バートルビー」という語が思い浮かびました。たしかこのあたりに、と思ったあたりを探してみると、ジョルジョ・アガンベンの『バートルビー 偶然性について』(月曜社、2005)をみつけました。本の帯には「〈する〉ことも〈しない〉こともできる潜勢力とは何か。西洋哲学史におけるその概念的系譜に分け入り、メルヴィルの小説「バートルビー」(1853年)に忽然と現れた奇妙な主人公を、潜勢力によるあらゆる可能性の〈全的回復者〉として読み解く」とあります。
この本は2010年の4月5日に読み始めて5月22日にちゃんと読み終わっていることが巻末に貼ってある付箋でわかります。何かもう1冊あったはずだと思ってみると、アガンベンの本のそばにエンリーケ・ビラ=マタス、木村榮一訳『バートルビーと仲間たち』(新潮社、2008)がありました。こちらはまだ読んでいません。「訳者解説」をみてみると、「1924年、マルセル・デュシャンを中心にロレンス・スターンの小説『トリストラム・シャンディ』から名前をとった〈秘密結社シャンディ〉という団体が誕生する」(218ページ)と記されていました。
また「トリストラム・シャンディ」です。こんなことは、山本さんはご承知のことだろうと思いますが、今野にとっては、「!」です。こういう経験は少なくないのです。何かを起点として、調べていくと、またもとに戻ってくる。あるいは、いろいろなことが一瞬にしてつながるというような「感覚」です。こうしてみると、山本さんが「トリストラム・シャンディ」の名前をあげたのは「脱線しようぜ」(すみません。山本さんはこんなことばづかいをしないですね)というお誘いだったのではないか、そしてそれに今野はうかうかと乗った、と思わないでもありません。しかし「楽しい大風呂敷」を標榜するこの往復書簡においては、それもよしとしませんか。
*
さて、索引の話に戻りましょう。山本さんが「電子テキストの索引を自分なりに設計するとしたら」という「条件」を①~⑥まで示してくださっています。
❶ 本の構成要素を提示する。
❷ 眺めて楽しく発見を促す。
❸ 検索語を五十音順などで探しやすく配置する。
❹ ❸に加えて、検索語同士の関係を表示できる。
❺ 索引と対応する本文を並べて閲覧できる。
❻ 利用者が検索語を追加したり、書き込んだりできる。
「ほとんどの条件は、難なく実現できるもの」とおっしゃり、ただし❹の「検索語同士の関係を表示できる」は「ちょっと性質が違うかもしれません」と述べておられます。『ロジェ類語辞典』が具体的に採りあげられています。
「類語」はもちろん類義の語ということですから、語義によってグループ化をする必要があります。語の語義を何らかのグループに分け、そこに語を収めるというやりかたです。昭和39(1964)年に国立国語研究所が、現代日本語の本格的な類義語集(thesaurus)として出版した『分類語彙表』は「類義」や語のカテゴリーを考えるにあたって長く使われてきました。2004年には増補改訂版が出版されています。
現在出版されている「国語辞書」の多くは「50音順」に見出しを配列しています。明治期までであれば「いろは順」ですが、こうした配列は、見出しとなっている語の語形=発音がはっきりしていて、かつそれが辞書の作り手と使い手との間で共有されていることが前提になります。そもそも、見出しとなっている語の語形がわからなかったり、発音がはっきりしていない場合には、「50音順」や「いろは順」といった(どちらかといえば)発音寄りの配列を採ることができません。
見出しとなっている語の語形=発音がはっきりしていないということなんかあるのだろうか、と思われるかもしれませんが、辞書が見出しを仮名で示すようになったのは、江戸時代からといってよいでしょう。それまでは漢字でした。
『図説 日本語の歴史』(河出書房新社、2015)でも採りあげていますが、12世紀半ば頃にできた『色葉字類抄』という名前の辞書があります。この辞書は見出し語を「いろは分類」した上で、その内部を「天象・地儀・植物・動物・人倫・人体・人事・飲食・雑物・光彩・方角・員数・辞字・重点・畳字・諸社・諸寺・国郡・官職・姓氏・名字」のように「意義分類」しています。今ここでは一つ一つの「意義分類」がどのようなカテゴリーであるかについての説明は省きますが、「植物」や「動物」はわかりやすいですね。
さて、この辞書の「に」の「畳字」のところに「睚眦 ニラム」という項目があります(この場合の「畳字」とは漢字2字の熟語ぐらいに考えておけばいいと思います)。また「か」の「畳字」のところには「睚眦 カイサイ」という項目があります。この時期には、濁音音節に100パーセント濁点を附していたわけではないので、この語の発音は「ガイサイ」だと思われますが、「カイサイ」と記されています。この「睚眦」には「ニラム」という振仮名が施されています。改めていうまでもありませんが、「に」のところの「睚眦」は「ニラム」という和語と対応する漢字列としてそこに置かれ、「か」のところの「睚眦」は「ガイサイ」という漢語と対応する漢字列としてそこに置かれているわけです。
つまり、この時期には、漢字列「睚眦」が和語「ニラム」にも漢語「ガイサイ」にも対応していた、ということです。こういう状況であると、ある漢字列がどんな語を文字化したものか、ということはその漢字列だけではわからないことになります。「わからない」というと「不便だな」ということになりそうですが、「複数の語と対応する」と考えれば、「便利だ」ということになるかもしれません。
さて、『色葉字類抄』は「いろは分類+意義分類」という配列形式を採っています。こういう辞書を使って、自身が探している語にたどりつくためには、まず探している語の発音によって、「いろは分類」のどこを探せばよいかを考え、次には自身が探している語が、『色葉字類抄』の「意義分類」のどこにありそうか、の見当をつける必要があります。
またまた「めんどくさい」となりそうですが、クイズだと思えばいいかもしれません。この語はどのカテゴリーに分類されているだろう、というクイズです。それは、『色葉字類抄』の編纂者のカテゴリーを探ることでもあります。過去の人の「脳内辞書」「心的辞書」を覗くような、そんなおもしろさがあります。
山本さんは最後に「三才」についてふれています。中国には1609年に出版された『三才図会』(全106巻)という、中国では類書と呼ばれる百科事典的な辞書があります。この『三才図会』のいわば日本版が寺島良安が編纂して正徳2(1712)年に出版した『和漢三才図会』です。これらの辞書については、山本さんが『「百学連環」を読む』(三省堂、2016)の64-66ページでふれていらっしゃいますね。また、「類書」については『文体の科学』(新潮社、2014)の「類書――ことばで造る宇宙模型」の節で、『和名類聚抄』や『古事類苑』についてふれていらっしゃいます。
ちょっと長くなったかもしれません。『三才図会』や『和漢三才図会』、『訓蒙図彙』などについてはまた機会をみて、お話できればと思います。「索引」と「総索引」の違いについても話題にしたかったのですが、これも機会を改めたいと思います。
2021.06.01
今野真二