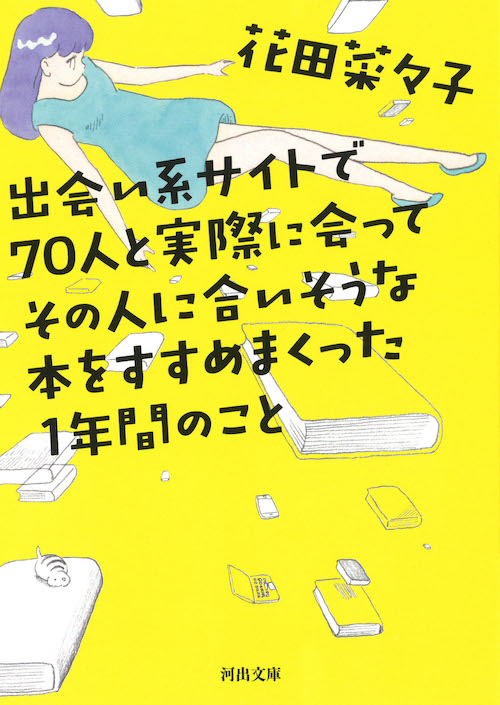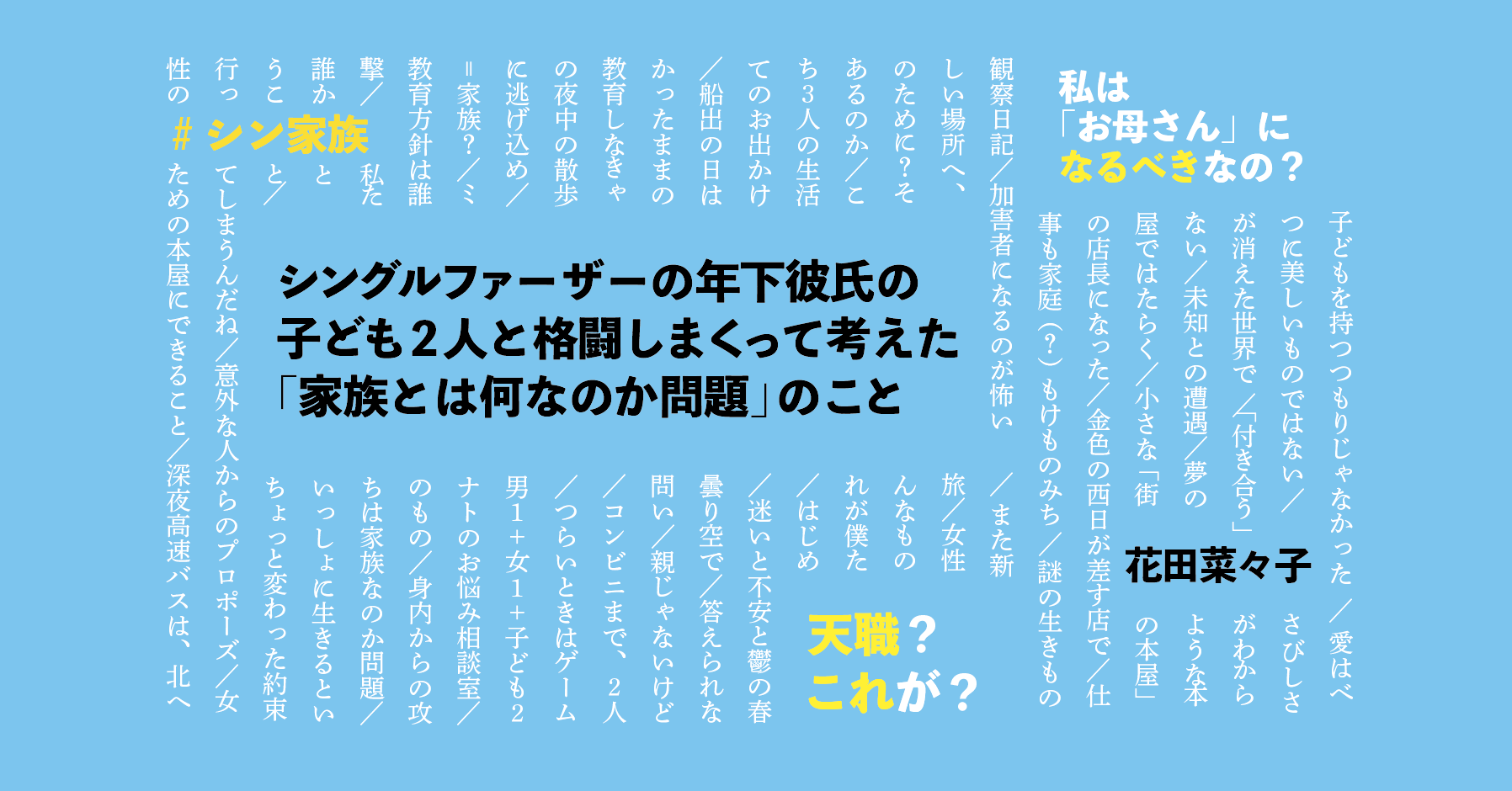
単行本 - 日本文学
【試し読み】第4章『シングルファーザーの年下彼氏の 子ども2人と格闘しまくって考えた 「家族とは何なのか問題」のこと』 - 2ページ目
花田菜々子
2020.03.11
答えられなかったままの問い
4人で家で昼ごはんを食べていたときのこと。ミナトが唐突に話しだした。
「パパー。ホシノがさ、親の財布から金、盗んでるんだよ」
ホシノとは、ミナトのクラスメイトであり、よく遊んでいる友達のひとりのようだ。
「それでさ、デュエマトレカを買いまくってる」
「えっ、そうなの? なんでミナトは知ってんの?」
「ホシノが自分で言ってるから」
こういう話を聞くこと自体がはじめてで、どう対応していいものかまったくわからなかった。会話に参加していいのかさえ。というわけであえて核心にふれないような質問をする。
「いくらくらい盗んでるんだろう」
「さあ……でもけっこうたくさん。10万円とか?」
「えっ……けっこうな額だよ。それ、親が気づかないことあるかな?」
「どうなんだろうなあ。普通なら気づくと思うけど。でもホシノくんちはけっこう金持ちなんだろ?」
「うん、たぶん」
「気づいてて黙認してるのかな?」
「言ったほうがいいのかな」
「誰に? ホシノくんのお母さんに?」
「わかんないけど」
こんな問題のことを、考えたことがなさすぎて言ったほうがいいよ、とも、言わなくていいんじゃない、とも、言えなかった。でも、いいとか悪いとか言い切れない、どうしたらいいかわからない問題にいま直面していて、こうして意見を求めているのだということだけはわかった。でもいい言葉が見つからなかった。
「うーん、でも、言うとしても、親が出ていくっていうのは違うような……。いや、親が言ったほうがいいのかな? トンはホシノくんのお母さんと仲いいの?」
「いやあ、挨拶する程度だなあ、顔はわかるけど」
なんとなくもやもやした空気の中、別の話題になってその話は終わった。
なんて言ってあげるのが正解だったんだろう。会話が終わってからも、せっかく投げてもらったボールをキャッチし損ねてしまった気がしてもやもやした。
「それはいけないことだから親と先生に言おう」でも「ミナトがはっきりとホシノくんにやめろって言うべきだよ」でも「その家の問題だから放っておけば? そのうちバレるよ」でもなく、私が言いたかった言葉があるとしたら……。
多分それは「ミナトはどうしたいの? どう思うの?」ということだった。
友達の行動をやめさせたいのか、心を痛めているのか、それともお金を盗んでもバレない環境をうらやましく思っているのか、バレて怒られればいいのにと思うのか。感情はわかりやすいひとつの答えじゃないと思うけど、気持ちを聞いてあげればよかったんだなあと思った。
だけどそれって親という保護者の立場だとしたら、11歳を大人として扱いすぎなのだろうか。個を尊重するような私の考え方は子育てには向いてないのかもしれない。
「それは絶対にいけないことだよ。もうこれ以上ホシノくんがそんなことをしないように、私からホシノくんのお母さんに電話で教えておくよ。それに、ミナトが言ってた、ってホシノくんには言わないようにってこともきちんとお願いしておくから」
っていう言葉こそがミナトが欲しかった答えで、正しい親の姿なのかもしれないと思う。だけど私はその言葉を多分ずっと言えない気がする。
今度同じ状況が来たら、ミナトに「ミナトはどうしたいの?」ってちゃんと聞こうと思う。でもあのときに言えなかったことはもう取り戻せない。子どもへの接し方は、その場の瞬発力が大事だ。後から思いついてももう遅い。こういうときのために、普段から、たくさんたくさん「こう言われたら、こう答える」というパターンを考えておかなくちゃいけないのかもしれない。
そういえば、南海キャンディーズの山ちゃん(山里亮太さん)も著書の『天才はあきらめた』という本の中で「いろんなつっこみができるのは、才能じゃなくてひたすら努力しているから。こう言われたらこう返す、とパターンを何百通りも予想して前もって考えている」と言っていて心を打たれた。まずは山ちゃんの100分の1くらいでも努力するようにがんばるしかないか。
親じゃないけど教育しなきゃ
子どもたちに与えられるものはなるべく与えてあげたいと思うのだけど(せっかく知り合った縁だ)、何が正しいことか、何を教えるべきなのか、私には教育がわからない。たとえば子どもたちは挨拶をしない。お礼を言わない。ジュースを冷蔵庫から取ってあげてもありがとうとは言わない。特にミナトは意識して言わないようにしているのを感じる。
私は挨拶やお礼は言うことができたほうが「この子たちのために、いい」んじゃないかと考える。「取ってもらったら、その人にお礼言わなきゃだめだよ」って言うのは簡単なんだけど、そんなの教育すべきかなあって悩んでしまう。言いたくないなら言わなくてもいいんじゃないかなあと思ってしまうのだ。
「いや、将来この子たちが苦労することになるから、言えるようにさせなきゃ」って思ったりもするのだけど、私は誰かからそんなことを頼まれたり望まれたりしていただろうか? と我にかえってしまう。
子どもを不幸にして、ズタズタに傷つける親のほとんどが「こうしたほうが子どものためになる」と思って自分の考える「良さ」を押し付けることから始まっているような気がする。たとえばたくさん勉強させること。こんなゲームばかりしてたらだめ、もっとこういう本を読みなさい、と言うこと。心配になることはたくさんあるけど、子どもを思い通りにしようとしたらキリがない。自分の理想通りにする子育ても楽しいのだろうけど、私は怖くてできない。
通りすがりのわけわからん大人にできることは、まあ、とにかくほめることだ。「ほめ」は間違いないだろう。「これができないと大人になったとき困るよ」は、出すぎた真似な感じがする。
通りすがりの人間でさえ、こうして、教育とは何かを考えざるを得ない局面に立たされるのである。教育方針はなるべくトンに任せたい。私が口出しするのはかえって混乱を招きかねない。とも思うのだが、あれ、やば、これってほとんど育児に参加しない、土日に子どもと遊んで育児した気になってるお父さんとほぼ同じ語り口になってるじゃん。たしかにこの程度の関与で育児は語れてしまうし、これくらいの関与レベルで「子どもはかわいい」って、私も心から言えるし。「子どものことは妻に任せてるんです」って、そんな態度でいいのかな。もちろんそれはそれぞれの家が決めることだけど。あと私がトンに任せるのは当たり前だし。なに横並びになろうとしてるんだ、って自分を諌める。
ん? 諌めていいところだっけ? もう自分の立ち位置がわからない。
育てるってなんだろう。すごく難しい。育てるほうが、育ててないより偉いのかな。
しかし、それでも「教育」に無理やり立ち向かわされるときがある。
マルちゃんはとにかく中指を立てるファックサインが最近好きで、それを家の中でやっている分には無視していたのだが、その動きが超気に入っているらしいマルちゃんは、ついに外に出ても、道端に座り込んで寝ている(?)人を見つけた途端、その人に向かって中指を立て、超高速で腕を上下に動かし始めたのである。
「ちょ、ちょ、ちょっとやめて」
思わずマルちゃんを羽交い締めにして止めた。マルちゃんはきょとんとしている。
「なんで?」
「うーん……」
難問だ。なんでだろうなあ。
「日本ではまあそこまででもないけど、外国だとシャレにならないんだよその動き。ほんとうにすごく怒らせたり嫌な気持ちにさせるかもしれないの。だから同じクラスの友達とお互い楽しくやってるだけならまあいいけど、知らない人は、外国の人かもしれないし絶対だめ」
「ふーん……あっそ」
この説明も不十分すぎてどうかと思ったが、案の定マルちゃんもまったくどうでもよさそうな返事だった。まあ、こんな説明で響きはしないだろうなあ、と思ったし、でもこの先もこういうことたくさんあるだろうなあ、と思うと辟易する。でも、そのときだってまた、こんなふうに言わざるをえないだろう。
他の全ての大人の人たち、教育ってどうやってやっているのだろう。みんなはゼロ歳のときからやっているからマリオの1面から始めてるみたいなもので、操作方法も慣れたものかもしれないけど、こっちは突然6面くらいからのスタートで、ルールも操作方法もまるでわからない。
ところが別の日、マルちゃんが、
「あのさあ、外国の人にこれやったらどうなる?」
とファックサインを出しながら家で不意に聞いてきた。覚えてたんだ、この前言ったこと。それで自分でもう1回考えてるんだ。
すごいじゃん! え! これが教育!
そっか、こうやって聞いてくれるのか。だったら親も言おう、って思うかもなあ。知らなかった。そうなのか。
「んー? すごい怒る。それかすごい嫌な気持ちになる。馬鹿にされたって思って悲しくなるか、怖い人だったら殴りかかってくるかも。あ、あと日本の人でも嫌な気持ちにはなる」
人にファックサインなんか出したことないから知らないけど。多分。
「そっかー、そうなのかー」
マルちゃんは自分の立てた中指を見つめながら不思議そうな顔をしていた。
コンビニまで、2人の夜中の散歩
彼らと過ごす日々の解像度は上がり、ミナトとの関係とマルちゃんとの関係に差がつくようになっていた。マルちゃんは私に明らかになついてきて、それまでにはなかった言動で私に好意を示すようになっていた。
金曜日、家に帰る頃になるとマルちゃんからLINEが来る(ミナトもマルちゃんもスマホは持っていないが、家のWi-Fiでふだんゲームに使っているタブレットからLINEを使えるのだ)。
「花田さん今日は来ないの? 泊まらないの? 泊まりに来てよー」
マルちゃんの強引な誘いに、「じゃあそうしようかな」と答えることもたびたびあった。
家に行くと、
「ああ、マルちゃんが誘ってくれたの? そりゃグッジョブだね」
と、トンはそのことを知らなかったようで、私はまるで部室に遊びに行くような感覚だ。
「だってさ、花田さんが来ると遊べるしさ、早く寝なさいってあんまり言われなくなるしさ」
なつかれるとやはりかわいさは倍増する。
「それにさ、花田さんが来てから、パパは明るくなったよね」
「えっ、そう? 俺は変わらないよ」
「変わるよ! 前はネクラだった」
たしかに、子どもから見たらそんな変化もあるのかもしれないなあと思う。
対してミナトは基本的にパパだけにべったりで、「6年生ってこんなに子どもっぽいものだったかなあ」と思うこともあるくらい、しょっちゅう座っているトンの膝の上に乗ったり、寝ているトンの上に乗ったりしている。
私に対しては、おちゃらけたり、いっしょにゲームをして盛り上がったりもしてくれるときもあれば、どこかで一線を引いているような、「絶対に服従しないからな」という意志を感じることもときどきあった。ましてや異性の自分に「なつく」という姿はまったく見せなかった。
「マルちゃんはともかく、ミナトは内心では私にあんまり家に来てほしくないと思ってるんじゃないかなあ」
前述のとおり、聞いても無駄なのかもしれないが半分はひとりごとでトンに言う。
「いや、ミナトのあれは、最近俺にもなんだよ。なんだか急に始まっちゃってさ。話しかけても返事しないとか、『知らない』『わかんない』『べつに』みたいな感じばっかりだったりしてさ」とのことで、それは私に対してのものだけではないらしかった。ちょっと安堵。とはいえさびしくもある。
もともとマルちゃんは人に話しかけることが得意で、むしろ際どい質問をぶつけてきて私たちがどんな反応をするか見たがるところがある。家に遊びに来た友達に「パパの彼女でございまーす」と私を紹介して部屋にいる全員を凍りつかせたり、クーラーの修理に来た人がいる前でわざと「パパって童貞? 童貞でしょ?」と聞いてみたり。いろいろ問題も多いが、人なつっこくてコミュニケーションしやすいのだ。対して、ミナトは基本的には常にちょっと離れた場所で傍観者の立ち位置をとって、こちらの様子を伺っている。
そうして、離れたいのかな? 距離を置きたいと思っているのかな? とこちらも特にかまわずに様子を見ていると、ときどきは、
「なんか4人みんなでできる新しいゲームないかなあ」と皆に聞こえるように言っていたり、「花田さん、今度また天ぷら作って! 芋ととり天多めで」と言ってきたりして、つかめないけど、揺らいでいる気分を含めて、自分でちょうどいい距離を調節してくれているのかもしれない。
それでもミナトを除いた3人でばかりコミュニケーションが深まってしまっていいのだろうかという迷いもある。たとえば休みの前の日の夜遅くにコンビニに行くのは、3人の恒例行事と化してしまっていた。でも無理やり連れて行くというのも変だし。
そうなると、ミナトのことをじゃまと思っているわけではないよ、という意思表示はどうしたらいいのかというのが次の問題だ。
手っ取り早くできるのは、食事のときにミナトの好物を優先して作ることだ。とりあえず何にでもチーズを入れるか、クリーム系のものを作るか、サーモンの刺身を用意すればいいので簡単ではある。
しかし「昼ごはんどうする?」ときいて、
ミナト 「カルボナーラ」
マルちゃん「たこ焼き!」
トン 「そうねえ、うどんとか」
とアンケートを取ったあげく、じゃあたまにはカルボナーラでも作るか、などと露骨なことばかりやっていると、
「ミナトの言ったやつばっかり! ずるいよ!」となってしまう。
はっ、もしかして……。どこの家でもお母さんがやたらと長男の機嫌を伺ったり長男ばっかりひいきしているように見える現象の正体はこれか……?
普通の家の「家族あるある」を、試食スプーンでひとくちずつ味見するように、この1年間でひととおり駆け抜けている気がする。
ある日、動画を見たりゲームをしたりそれぞれが好きなことをしている時間、私は本を読んでいた。トンがベランダにタバコを吸いに行って、ミナトがお風呂に入りに行って、2人になったタイミングで、押入れのおもちゃを引っ掻き回していたマルちゃんが、
「花田さん! これ何?」
と神社でもらうような木札を振り回しながら聞いてきた。
「ん……お札じゃない?」
私はちらっと見ただけで本に視線を戻しながら答えた。
「みなさん! これが伝説のダイナマイトちんぽです!」
とそれをまた股間に当てながら遊んでいるので、
「ええっ!! これが伝説の…!?」
と雑にリアクションしたあとは放置して本を読んでいたら、それを面白くなく思ったマルちゃんが「ちんぽ! ちんぽ! しこしこー」と言いながら近づいてきた。人の顔のそばで股間に立てた木札をこする動作をしてきたので、さすがに教育として(顔射などをよしとするパーソナリティーを育成しないために……ここはあえてキレておいたほうがいいのではないかと悩んだあげくに、
「うるさいよ」
と言って手と木札を強めに払いのけた。すると思いのほか強く手が当たり、木札がかなりの飛距離で飛んでいった。マルちゃんはあからさまにびくっとなって様子を伺っている。
やば……と思いつつも、いや、しかしここはあえて怒る作戦だったし、と思いとりあえず、
「顔の近くでそれやるのやめてくれる? ムカつくから」
となるべく無表情で言い放つと、
「は……い」
とマルちゃんは明らかにしょぼんとした様子で離れていった。これでいいのか? これで合ってるのか? この、そもそもの前提から間違ってそうなこの性教育の行方は……。
もうどこから直していいかわからない。佐々木正美先生に「子どもが木札をちんぽに見立てて顔に近づけてきた場合にはどう対処するのがいいでしょうか」と聞いたら何と答えてくれるのだろうか。答えて……くれるのだろうか。
しばらくして、気まずさを紛らわせるためにマルちゃんをコンビニに誘う。
「なんかコーヒー牛乳飲みたいな。マルちゃんもなんか食べたくない?」
「セブン? 行く行くー! つぶグミ買って!」
2人で夜中のコンビニに散歩に出かけた。マルちゃんはほんとうに夜の散歩が好きだ。3人で行くことが多いとはいえ、気がつけば2人だけでも普通に行けるようになっていた。
「さっきさあ……怒ってた?」
「うん。でもごめんね」
「ちょっと怖かった」
「そうだよね。なんか思いのほかお札が遠くに飛んでいっちゃったんだよね。ごめん、びっくりさせちゃった」
「よかった……もう今は怒ってない?」
「うん、怒ってないよ」
あまりにもくだらなすぎる事の発端と驚かせてしまったのにすぐに謝れなかった自分への恥ずかしさと、下ネタばっかり言ってるマルちゃんの裏にひそんでいる繊細さと、すべてが夜の空にやさしく溶けて広がっていった。
こんなふうに2人っきりで歩きながら話していると、距離はぐっと近づくように思えてうれしかった。
つらいときはゲームに逃げ込め
出会い系サイトで出会った人たちのことを書いた本、『出会い系サイトで70人と実際に会ってその人に合いそうな本をすすめまくった1年間のこと』が発売されると、予想外に一気に世間から注目されることになった。TVにも出た。店のオープンについての取材も多かったが、本の分の取材も増えて、さらにめまぐるしい日々が始まった。本の評判はとてもよかった。多くの人が、ただセンセーショナルなネタとしての話題性でなく、自分の人生の問題に引きつけて、本を真剣に読んでくれたのがSNSや読書サイトのはしばしから伝わった。店にもたくさんの人が「本読みました、面白かったです」と言いに来てくれた。すごいことだ。そしてみんな「よかったら私にも1冊……」とリクエストしてくれるので、1年どころか、月に70人くらいに本をおすすめする生活が始まった。まるで会いに行ける書店員。いや、それ普通の書店員か。
書いてあること自体はもう5年前のこととはいえ、自分をさらけ出して書いた本だから、まるで自分を丸ごと受け入れてもらったようで、それはとんでもないうれしさだった。大きい反響が信じられなくて、受け止めきれなかった。知らない人から、尊敬してます、とか、憧れです、と言われるのは、さすがに居心地が悪かった。言葉に嘘はなく、ありがたいことだと思うし、本に書いたことに嘘はないのだけど、聖人君子なわけじゃないし、都合の悪いことは書いてないから、超いい人みたいに見えてしまっているようだ。そう書いた自分が悪いのだけど。
それでも取材があれば何度でも同じ話を熱を込めて話すようにし、東京だけでなく関西でもイベントを開催してもらったりした。新しい執筆依頼や選書の企画の話も次々にいただいた。まだぜんぜん落ち着く気配のない新しい本屋の仕事をしながら、さらに新しい執筆の仕事をしてびゅんびゅん飛ばしているとどうなるかというと、たいがいの人が予想するとおり、鬱になるか身体を壊すかの2択である。
家に帰ると電源が切れたように布団に倒れ込むようになり、そのうち、本がまったく読めなくなった。面白そうな本が次から次へと出ているのに、読みたいという気持ちが湧いてこない。無理やり買ってカバンに入れておいても全然開く気になれない。あんなに楽しみにしていた新刊なのに。こうして「もっとがんばらなくては、期待に応えなくては、もっと店をよくしなくては」というプレッシャーに押しつぶされ(いいことずくめなのに)私はだめになってしまうのか。 休日の休みの日は力をふりしぼってトンの家に行き子どもたちと遊ぶが、平日の休みは朝から夜まで何もせずに布団にもぐっている。できるのはツイッターを見ることくらいだ。
ちょうどその頃、子どもたちのあいだに「荒野行動」の大ブームが起きた。
「ひさしぶりに焼肉にでも行こうよ!」
食べることは嫌いでも、子どもたちが例外的によろこぶ唯一のメニューが焼肉だった。2人の気を引こうと思ってそうみんなに提案すると、
「むり。今日みんなと荒野行く約束してるから」とミナトがそっけなく言う。
「荒野? どこの荒野に?」
「いや、ゲームゲーム。なんか最近子どもたちのあいだですっごい流行ってんのよ。もう帰ってきてから寝るまでずっとだよ。ごはんもゲームが終わったタイミングだし、もう完全に荒野行動中心の生活」
「オンラインで対戦するの?」
「それが、なんかみんなで音声チャットみたいなものでしゃべりながら5人グループとかで戦うみたいなんだけど。いろんな家庭の生活音がまる聞こえ。まさか他の家に中継されると思ってないみたいで。ゲームやってる子がずっと怒られてたりとか」
「花田さんもやろうよ」
マルちゃんがスマホを奪い取って勝手にダウンロードを始める。
「できるかなあ」
「いいから」
私はアクションゲーム的なものはまったくセンスがないので、マルちゃんの指導のもとおどおどとプレイヤーを動かしてみるが、すべてのアクションがぎこちなく、ゲームになる気がしない。
「よし行こう!」
「え、待って、まだデビューは」
こちらの怖気付きなど気にもせず、勝手にチームをマッチングされ、ミナトとマルちゃんと3人の部隊で飛び立たされる。
「え、どうやって降りるの? わ、どうしよう、変なとこ押しちゃった! やばい! やばい! えっ、待って、川に落ちたんだけど!」
私の慌てっぷりを見て2人は大ウケしている。
「このマップのこの印のとこ来て」
「マップ? 来て、ってどうすれば! こわいよー! 敵来たらどうしよう」
フィールド上の草むらに隠れてもたもたしてたら車で迎えに来てくれた。なんてかっこいいんだ。ヴァーチャルの世界はすごいな。
「頼りになる! ありがと〜」
その後敵とぶつかり、2人が銃を乱射するはるか後方でもぞもぞしていたら一瞬で撃ち抜かれて自分だけ死んだ。
「どんだけ弱いんだよ!」
いやほんとこういうの無理なんだって。と思ったが、もしかしてこれをマスターすれば仲間に入れてもらえるようになって、もっと仲良くなれるかも?
気分は打越正行の『ヤンキーと地元』だ。まず研究対象者の居住する世界に溶け込むことで、彼らに警戒心を無くさせてから彼らを調査するのだ。
というわけで、家で死んでいる時間を練習にあてることにした。ゲームの中とはいえビビりすぎて、「敵が来た!」と思うとすぐに隠れてしまい、闘争心が1ミリもない。ただただ殺され続けて殺され飽きた頃に「もしかして自分からも撃てば生き残る可能性があるのでは?」ということにやっと目覚めた。
そしておそらく同じくらいの初心者と出会い頭にぶつかり、お互いド下手に撃ち合って初めて一人を撃破して、うれしくて2人にLINEで報告する。
「ついに1キルしたよ!」
「すごいじゃん」
「おめ」
しかし鬱ムーブとバトルゲームの相性のよさは半端なかった。私は練習を重ね、次第にオンライン上の他プレイヤーと遊べるくらいの技術を身につけ、平日の昼間にひとりでプレイするのに飽きると、オンライン上の知らない人とチームを組んでボイスチャットで話しながらゲームするまでの荒野廃人になってしまった。変な人がいるときもあるけど、だいたい知らない人と平日の昼からゲームしようと考えるような人たちだから基本的には礼儀正しくてやさしい。ときどきいっしょになるなじみの人、みたいな存在ができたり、何時間も同じ4人でプレイする中でそれぞれの人生の話をちょっと聞いたりもして、ゲームの中の人間とのやりとりもまた楽しくて味わい深いのだった。現実世界から転げ落ちても、どこにもまた違う世界が広がっている。知らないことがいっぱいだ。「出会い系」のことを書いたのはインパクトがあったみたいだけど、またここでももう普通のことになってるじゃん、知らない人と仲良くすること。
こうやって仕組みを知って、しかもずぶずぶに入り込んでしまえば、子どもが知らない人とオンライン上でゲームで遊んでいるということを聞いてもそんなに頭ごなしに心配したりしなくなる。まあ、自分がずぶずぶになる必要はまったくなかったが……。
本を読む気力はあいかわらず起きなかったが、例外的に山本さほの『岡崎に捧ぐ』だけが異様に面白く感じられて心に刺さって、何度も読み返していた。自分が通常運転のときに出会ってもきっと名作として受け止めたと思うのだけど、ゲームのことを多く描いてることもあって、そのときの自分は一層共感したし、かわいい2人が小学校時代からゲームにハマり、長い時を超えてまだ友情を復活させていく物語に深く入り込んでいった。なぜかそんなふうに特定の状況下でやたらと効く本ってある。
さらに今までは子どもたちがYouTubeのゲーム動画を見ているのをうるさいなあと思っていたが、マイナーな実況配信者でいい感じの人を見つけ、その人のライブ配信にも足繁く(?)通うようになった。その人は他のYouTuberと違って、テンション高く声を張り上げたりすることがなかったので、見ていてとても居心地がよかったのだ。いつも配信には50人くらいしか来ていないけど、それくらいの規模だとすぐにおなじみのメンバー感が出て、その人たちとも文字チャットでコミュニケーションするようになった。
私はいったいどこに向かっているんだろう、と思ったが、でもやっぱり新しい世界は楽しかった。本や本屋の世界から離れたいときにこのコミュニティーがあることは、自分を失わずに済む避難所のようだった。
週末にマルちゃんとゲームするたびにこちらのレベルは上がっており、
「え、これ、なんでこんなにレベル上がってんの? どういうこと?」と詰められた。
「いや、これにはいろいろ事情があって! でも、ほら、キルレ(キルレベル)はマルちゃんより低いから! ね!」
なぜか焦って謎の言い訳をする。
そしてゲームをやり尽くして飽きた頃には、また本を読みたくなっていた。
まるで短い旅だったみたいだ。でもとてもいい思い出だ。知らない世界の人たちと、ちょっとだけ交流できたこと。
星野源が、自らのエッセイ『蘇える変態』の中で、自身が病気で倒れて、活動ができない日々の中で「星野源」のアカウントで発信することがつらく、一般人のフリをしてツイッターに紛れ込んだ話を書いていた。無名の自分でも誰かに話しかけたり挨拶をして関わっていくことで、やりとりをしてもらえるのだと知り、癒しになったという。
知らない人との何でもないやりとりが、自信につながるというのはこういうことだと思った。
試し読み プロローグはこちら
試し読み 第1章はこちら
試し読み 第2章はこちら
試し読み 第3章はこちら
予約受付中!!!花田菜々子
シングルファーザーの年下彼氏の 子ども2人と格闘しまくって考えた 「家族とは何なのか問題」のこと」
1400円(税別)
46判/224ページ
2020年3月下旬発売予定